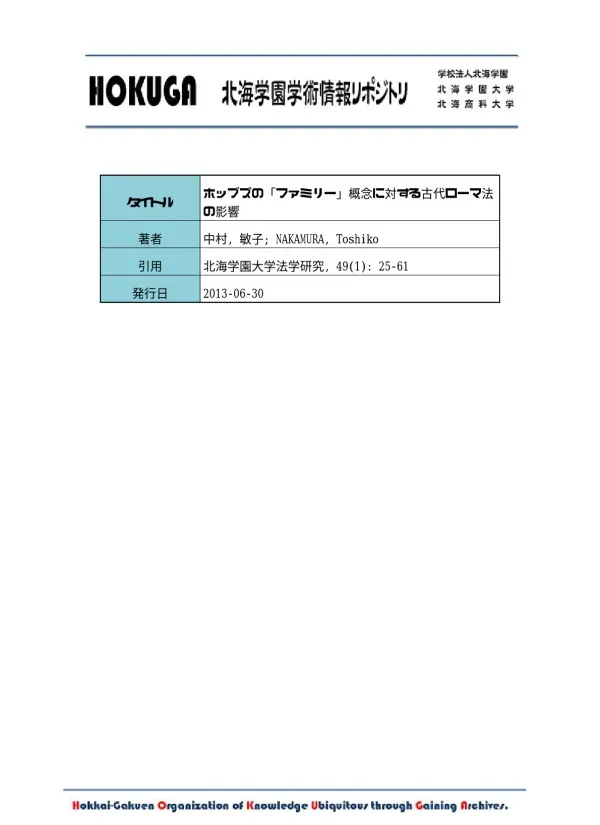
ホッブズと古代ローマ法:家父長制と国家
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.41 MB |
| 専攻 | 法学、歴史学、政治学 |
| 文書タイプ | 論文 |
概要
I.ホッブズの思想とローマ法における家父権 家族構造と継承
本稿は、トーマス・ホッブズの思想、特に『リヴァイアサン』における国家権力論と、古代ローマ法における家父権(Patriarchy)構造との関連性を考察しています。特に、ローマ法上のファミリア(Familia)という家族制度が、ホッブズの継承や権力に関する考え方にどう影響を与えたかを分析しています。ファミリアは家父が絶対的な権力を持ち、その成員の生死や財産を支配する閉鎖的な共同体であり、この構造がホッブズの国家観に投影されている点を明らかにしています。また、ローマ法における婚姻や養子縁組といった制度も、家父権の維持と継承という観点から分析され、ホッブズの思想との共通点を探っています。さらに、母権(Maternal Power)との対比を通して、ホッブズの父権的な国家観の特質を浮き彫りにしています。
1. ローマ法におけるファミリアと家父権
この節では、古代ローマ法における『ファミリア』(Familia) の概念が、ホッブズの思想に与えた影響を検討しています。ファミリアは、家父、その妻、生物学的な繋がりを持つ子供たちから構成される人間集団とされ、家父はファミリアに属する全ての財産を所有し、単独で処分する権利を持っていました。奴隷も家父の所有物とみなされていた点が指摘されています。新生児は必ずしもファミリアの一員として迎え入れられ、養育されるわけではなく、家父にはその義務はなかったとされています。また、家子(家父の子)は権利主体であるものの、家父権力の下ではその権利主体性が隠蔽されている状態にあったと分析されています。このように、ローマ法におけるファミリアは家父権が絶対的な権力を握る構造を有しており、この構造がホッブズの権力思想に深く関わっていることが示唆されています。特に、家父の生殺与奪権は、家父権の強大さを象徴的に示すものとして捉えられています。
2. ローマ法における婚姻と家族の継承
ローマの婚姻は、単なる当事者の合意によって成立し、必ずしも法的関係を伴うものではなかったとされています。ファミリアは男系集団であるため、婚姻によって男性が女性のファミリアに帰属を変えることはありませんでしたが、既に自らの生家からの家父権を脱して自権者となっていた女性が、手権婚によって夫の家父権に従うようになると解説されています。手権婚による妻は、自らの生家の家父権力よりも弱い権力である手権に従うことになりますが、法的権利は必ずしも失われるわけではなかったとされています。婚姻の主な目的は、夫婦が共に暮らし、男性の正統な子供を得ることでした。家父や後見人の同意は、かなり以前の時代から不要とされていたとされています。離婚も同様に事実上の過程であり、相続人が自権者の地位を失うことのない法的行為として、遺言という形式が生じたことが説明されています。嫡子を持たない家父は、養子縁組によって後継者を確保することができました。これは、家父個人の系統の継続や自身の祀りの確保という個人的な目的と、ファミリアの存続という集団的な目的の両方に合致するものでした。ファミリアの目的の一つは、そこに属する人間の生存を保障することであり、この点を踏まえると、ホッブズの思想とローマ法の関連性がより明確になるだろうとされています。
3. ホッブズ思想とローマ法における権力構造の比較
この節では、ホッブズの論じた支配の三形態が、ローマ法において人間の法的状態に変化をもたらす三種類の基準に基づいている可能性が示唆されています。 ホッブズの議論における重要な点は、女性の持つ母権が父権へと転換される過程が、婚姻関係における男性の支配権と、それを国家が父権的な法によって固定化することによって実現すると解釈されている点です。 また、奇形児のファミリアへの帰属承認についても、家父権力の行使における問題点として言及されています。ホッブズは、初期の段階から生命の継承の問題を考えていたと推測させる記述も分析されており、ローマ法における家父権構造と、ホッブズが『リヴァイアサン』において展開した国家権力の問題との関連性が深く考察されています。 特に、ローマ法上の家父が、相続という観点から、自らを誰かに引き継がせる権利、すなわち継承させる権利を持っていたことが強調されています。 しかし、実際の継承方法については、君主の遺言が最優先されるという記述もあります。
II.ローマ法における婚姻と家族の法的構造
古代ローマ法における婚姻は、現代の概念とは異なり、単なる当事者の合意に基づくものであり、必ずしも法的関係を伴うものではありませんでした。特に、手権婚(coemptio)においては、女性の家父権からの脱却と夫の家父権への服従という法的変化が分析されています。子供は必ずしもファミリアの構成員として迎え入れられるわけではなく、家父の裁量に委ねられていました。継承に関しては、家父が嫡子を持たない場合の養子縁組が重要な手段であり、ファミリアの存続と家系の継続が重視されていたことが示されています。
1. ローマ法における婚姻の性質と成立要件
この部分では、古代ローマ法における婚姻の性質と成立要件について論じています。現代の私たちから見ると、古代ローマ法上のファミリアは非常に奇妙なものに見えますが、ローマの婚姻は、単に当事者が婚姻するという意思を持ち、合意することで成立したとされています。これは、現代の婚姻制度とは異なり、法的関係を伴わないものであった点を強調しています。ファミリアが男系集団であったため、婚姻によって男性が女性のファミリアに帰属を変えることはなく、婚姻は夫婦が共に暮らし、男性の正統な子供を得ることを主な目的としていたと解説されています。家父や後見人の同意は、かなり以前の時代から必要ないとされていたとされており、離婚も婚姻と同様に事実上の過程であったと記述されています。 この記述から、ローマにおける婚姻は、現代の法的婚姻制度とは異なる、より個人的・事実上の合意に基づくものであったことがわかります。
2. 手権婚と女性の法的権利
既に自らの生家の家父権から脱し、自権者となっていた女性が、手権婚によって夫の家父権に従うようになる場合が解説されています。手権婚によって妻となった女性は、自らの生家の家父権力よりも弱い権力である手権に従うことになりますが、その法的権利が完全に消失したわけではなかったことが重要な点として指摘されています。この点は、ローマ法における女性の法的権利の複雑さを示しており、家父権の絶対的な支配力の下でも、女性が一定の権利を保持していた可能性を示唆しています。この手権婚の制度は、女性が家父権の支配からある程度自由になる可能性と、同時に夫の家父権に従属する関係を同時に示すものであり、ローマ社会における女性の地位を考える上で重要な要素となります。 現代の婚姻制度とは大きく異なるこの制度は、ローマ法における家父権と女性の権利関係の微妙なバランスを理解する上で重要な手がかりとなります。
3. 子どもの帰属とファミリアの継承
この部分では、ローマ法における子どもの帰属とファミリアの継承について論じています。婚姻の目的が夫婦が共に暮らし、男性の正統な子供を得ることだったことから、子どもの帰属とファミリアの継承の問題が深く関わっていたことが分かります。生まれた子供を全てファミリアのメンバーとして養育することは家父にとっての義務ではなく、ファミリアは共同体維持のために存在したため、構成員を理由もなく殺害することは行われなかったと考えられると解説されています。相続人の自権者の地位を失わせないための法的行為として遺言という形式が生まれたことも説明されており、ファミリアの家父が嫡子を持たない場合、養子縁組によって後継者を確保することができたとされています。これは、家父個人の系統の継続や自身の祀りの確保という個人的な目的と、ファミリアの存続という集団的な目的の両方に合致するものでした。ファミリアの構造は、この目的が達成されることを明確に意図したものであったと結論付けられています。このことから、ローマ法における家族制度は、家父権と継承という要素が強く結びついていたことが分かります。
III.ホッブズとローマ法 支配の三形態と権力構造
本稿では、ホッブズが論じた支配の三形態と、ローマ法における個人の法的状態の変化を引き起こす三つの基準との関連性を検討しています。ホッブズの思想が、ローマ法における家父権の強大さを反映している可能性を示唆し、特に生殺与奪権、婚姻、継承といった側面から分析することで、ホッブズの国家権力論におけるローマ法の影響を明らかにしています。また、ホッブズが初期の段階から継承の問題に関心を抱いていた可能性を示唆する記述も分析されています。
1. ホッブズの支配の三形態とローマ法の基準との関連性
この節では、ホッブズが論じた支配の三形態と、ローマ法において人間の法的状態に変化をもたらす三種類の基準との関連性を検討しています。 文章は、ホッブズの支配の三形態が、ローマ法における個人の法的状態に影響を与える基準と対応している可能性を示唆しています。 この関連性を明らかにすることで、ホッブズの政治思想にローマ法がどのように影響を与えたのかを解き明かそうとしています。 具体的には、ローマ法における家父権の強大さ、婚姻制度、相続制度といった要素が、ホッブズの国家観や権力構造の形成に深く関わっている可能性が示唆されています。 この分析を通じて、ホッブズの思想におけるローマ法の影響の大きさを理解することができます。
2. ローマ法における家父権とホッブズ思想の比較検討
この部分は、ローマ法における家父権の構造と、ホッブズの政治哲学における権力構造を比較検討しています。 ローマ法における家父は、ファミリアの全ての成員と財産に対する絶対的な権力を持ち、その権力は「生殺与奪権」という言葉で表現されるほど強大であったと説明されています。 この家父権の強大さは、ホッブズの国家における主権者の絶対的な権力と共通点があると指摘されています。 また、家父が子どものファミリアへの受け入れに関して許諾権を持っていたという事実は、受け入れた子どもの養育責任を負うことの表れと解釈できることも説明されています。 こうしたローマ法における家父権の特質が、ホッブズの権力思想に影響を与えた可能性を詳細に分析しています。
3. 婚姻 継承制度とホッブズ思想の関連性
この節では、ローマ法における婚姻と継承の制度が、ホッブズの思想にどのように影響を与えたのかを分析しています。 ローマ法における婚姻は、現代とは異なり、当事者の合意によって成立し、必ずしも法的関係を伴うものではなかったとされています。 この点に関して、ホッブズが婚姻を国家法の範囲外の自然状態におけるものとして議論した可能性が示唆されています。 また、ファミリアにおける継承の問題は、家父権の枠組みを超えて、国家権力の問題としてホッブズによって議論されたと考えられています。 特に、家父が持つ「継承させる権利」と、実際の継承方法(例えば君主の遺言)との関係性が、ホッブズの国家権力論を考える上で重要であることが指摘されています。 これらの分析を通じて、ホッブズの思想がローマ法の制度や概念にどのように触発され、構築されているのかを理解することができます。
IV.ホッブズ リヴァイアサン における生命と継承の概念
ホッブズがどのようにキリスト教の「永遠の生命」という概念を、権力による生命の永続性の保障へと置き換えたのかが、リヴァイアサンにおける国家権力の議論を通して考察されています。特に、継承の問題は、家父権の枠組みを超えて国家権力のレベルで検討されており、ホッブズの思想における生命と権力の複雑な関係性が示されています。
1. ホッブズにおける永遠の生命と権力による生命の永続性
この節では、ホッブズがキリスト教の教義における「永遠の生命」という概念を、権力による生命の永続性の保障へとどのように置き換えたのかを検証しています。 これは、『リヴァイアサン』におけるホッブズの議論の中心的なテーマであり、彼の政治哲学を理解する上で極めて重要です。 ホッブズは、宗教的な永遠の生命ではなく、世俗的な権力による秩序と安全保障を通して、個人の生命の継続と社会の安定を確保しようとしたと考えられます。 この置き換えの過程を分析することで、ホッブズがいかに世俗的な権力と個人の生存を結びつけ、自身の政治哲学を構築したのかを明らかにしようとしています。
2. リヴァイアサンにおける国家権力と生命の継承
この部分は、『リヴァイアサン』において国家権力の問題として展開されている生命の継承の問題について論じています。 ホッブズは、国家権力の維持と安定のために、生命の継承という問題をどのように扱ったのかが分析されています。 これは、単に個人の生命の継続だけでなく、国家や社会全体の存続という観点からも検討されていると考えられます。 ホッブズが初期の段階から生命の継承について考えていた可能性を示唆する記述も分析されており、彼の思想形成におけるこの問題の重要性を示しています。 この分析を通じて、ホッブズの国家観と生命観が密接に関連していることが明らかになります。
3. 継承の権利と国家権力
この節では、「継承」という概念を、個人の権利と国家権力の両面から考察しています。 具体的には、誰かに自分を引き継がせる権利、すなわち「継承させる権利」という概念が論じられています。 これは、ローマ法上の家父が持っていた権力と関連づけて考察されており、ホッブズの国家権力論においても同様の概念が重要な役割を果たしている可能性が示唆されています。 しかし、実際の継承方法については、君主の遺言が優先されるなど、複雑な側面があることも指摘されています。 この分析を通して、ホッブズがどのように個人の権利と国家権力を結びつけ、自身の政治思想を構築したのかを理解することができます。
