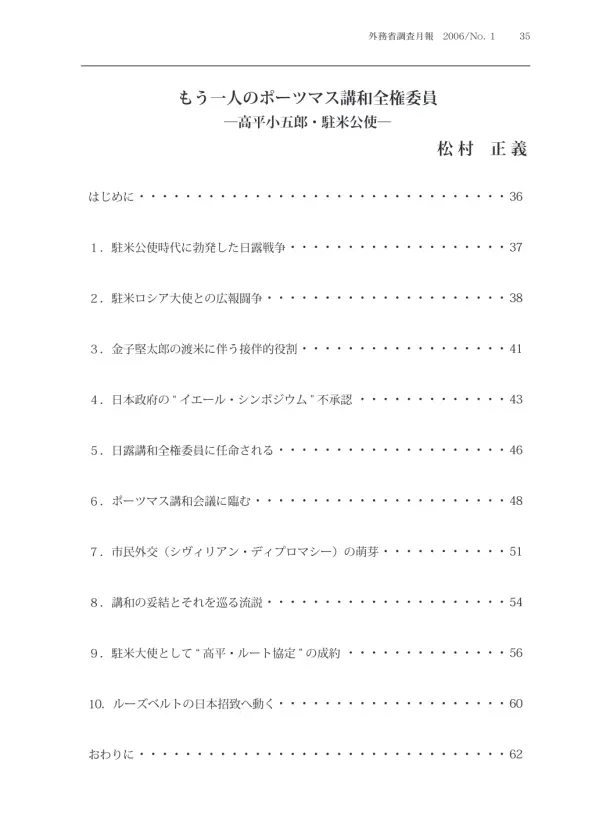
ポーツマス講和:高平小五郎の貢献
文書情報
| 著者 | 松村正義 |
| 専攻 | 外交史 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 532.78 KB |
概要
I.日露戦争と 高平小五郎 の役割 ポーツマス講和会議 への道
日露戦争終結に向けたポーツマス講和会議において、高平小五郎駐米公使は重要な役割を果たしました。日米関係の緊密化に尽力し、特に開戦前後の米国の世論操作に注力。ロシア側の反日宣伝に対抗するため、英国大使ジュランドとも連携し、米国政府への働きかけを行いました。小村寿太郎外務大臣との連携も密接で、米国の世論動向に関する報告は、小村から高く評価されました。高平は、雑誌『World's Work』への寄稿などを通じて、日本の正当性を訴える広報外交(パブリック・ディプロマシー)にも尽力しました。
1. 高平小五郎の駐米公使就任と日露戦争開戦
1900年6月、高平小五郎は駐米公使として着任。それから約4年後、日露戦争が勃発します。明治政府は、大国ロシアに勝利するため限定戦争戦略を採用。同時に、露独仏三国干渉の教訓を活かし、親日的な国際世論形成に注力しました。これは当時「外国新聞操縦」と呼ばれた広報外交であり、外務大臣小村寿太郎は、1904年2月6日、栗野慎一郎駐露公使を通じてロシア政府に国交断絶を通告、2月8日には高平への訓令が下されました。この時点から、高平の役割は、米国における世論誘導、特にロシア側の反日宣伝への対抗に重点が置かれるようになります。高平は、英国大使ジュランドからも情報収集を行いながら、米国民の日本への同情を維持することに尽力しました。これは、日本海軍の旅順港と仁川港への奇襲攻撃、特にヴリャーク号の自爆に関するロシア側の非難キャンペーンへの対応が重要な課題となっていたためです。ロシアは、カッシーニ駐米大使の令嬢を募金活動の先頭に立てるなど、巧妙な世論工作を展開しました。
2. 米国世論操作と広報外交 World s Work への寄稿
高平は、小村外務大臣との緊密な連携のもと、米国における世論動向を綿密に監視し、定期的に報告を行いました。その報告内容は、小村から高く評価され、米国の世論が政府の方針を左右する可能性があるため、その動向の把握が非常に重要であると認識されていました。高平は、小村から送られた英文電報を現地向けに修正するなど、対外広報活動にも積極的に関わりました。さらに、1904年4月号の雑誌『World's Work』に「What Japan Is Fighting For」という論説を掲載し、日本が周辺国の独立や領土保全を侵害する意図はないことを主張しました。これは、ロシア側の黄禍論への反論であり、米国民の懸念払拭を目的とした広報外交(パブリック・ディプロマシー) の一環でした。高平は、日露開戦前、ロシア大使が米国政府のロシアへの同情を示唆する報告を母国に送ったが、開戦後の米国世論が日本への圧倒的な支持に変わったことを指摘。ロシア大使が形式的な対応を余儀なくされたことを報告し、小村の信頼を得ました。
3. 高平小五郎と小村寿太郎の信頼関係と外交戦略
高平の報告は、小村外務大臣によって非常に高く評価されました。小村は高平からの報告を受け取るとすぐに、米国の世論動向を注視し、必要に応じて日本政府に報告するよう改めて指示を出しました。このことから、小村は高平を深く信頼し、彼の役割を非常に重要視していたことがわかります。高平と小村は緊密に協力し、日露戦争における日本の立場を米国に理解させ、親日的な世論を形成するために、様々な広報活動や外交努力を行いました。彼らは、日本が戦争を始めた理由を明確に説明し、誤解を解くことに努めました。これは、戦争の目的や日本の外交政策に対する米国民の懸念を払拭する上で非常に重要でした。また、高平は金子堅太郎の渡米についても小村からの連絡を受け、その活動に協力しました。これらの行動は、日露戦争における日本の勝利に貢献しただけでなく、日米関係強化にも大きく寄与しました。
II. 金子堅太郎 と 高平小五郎 協調から対立へ
同じく米国に派遣された金子堅太郎との関係は、良好なスタートから次第に悪化しました。金子のイエール大学教授陣への講和条件に関する意見聴取は、小村外務大臣から訓令違反と厳しく批判され、高平もその報告をヘイ国務長官に伝えています。この出来事をきっかけに、両者の間には確執が生じ、ポーツマス講和会議後には、金子による高平への誹謗中傷が流布される事態にまで発展しました。両者の対立は、戦後の排日移民問題への対応にも影響を与えた可能性を示唆しています。
1. 金子堅太郎の米国派遣と高平小五郎との連携
日露戦争勃発後、日本政府は、国際世論の動向を把握するため、金子堅太郎を米国に派遣しました。1904年2月23日、小村外務大臣は高平小五郎駐米公使に金子の渡米を通知。高平は4月5日、金子の渡米を承認し、ジョン・ヘイ国務長官との面会に際し、「開明諸国、特に貴国と英国の輿情を討察することは、戦争終結の利益に関し必須」と内密に説明しました。これは、日露戦争が欧州の大国との戦いであることを踏まえ、主要国の世論を動かす重要性を認識していたためです。高平は、公然の事務は自身が代表するものの、地方の人心も洞察し、誤解がないよう金子を特派したと説明しました。この時点では、高平と金子は協力関係にあったことがうかがえます。金子は、戦争終結後の講和条件に関して、イエール大学の教授らに意見を求めるなど、積極的な活動を行いました。これは、金子が自身の判断で進めたものであり、高平との事前協議が十分であったかどうかは不明です。
2. イエール シンポジウムと小村外務大臣の訓令違反認定
金子は、イエール大学の教授らに日本の対露講和条件に関する意見を求める「イエール・シンポジウム」を開催。しかし、1904年10月時点では、その意見書は東京に送られず、金子が保管していました。金子は、1905年2月、旅順陥落、奉天の危機迫る状況を踏まえ、意見書を小村外務大臣に報告。同時に、ルーズベルト大統領にも内報しました。ところが、小村は2月13日、高平公使を通じて金子に厳しく譴責する電報を送ります。講和問題に関して、時期尚早に部外者に諮問することは、日本側の弱みを露呈させる危険性があると判断したためです。ルーズベルトへの意見書提示についても、強い遺憾を示しました。この出来事は、高平と金子の関係悪化の大きな要因となりました。小村は、高平に日本政府が対露講和のイニシアチブを取っていない旨をヘイ国務長官に伝えるよう指示しました。この出来事は、高平と金子の間の協力関係が崩れ始めたことを示しています。
3. ポーツマス講和会議と金子による高平への誹謗中傷
ポーツマス講和会議が妥結した8月29日、ニューヨークの金子の元にAP通信社のストーン社長が訪れ、講和における日本の譲歩は小村の本意ではなく、金子とルーズベルト、伊藤博文の陰謀によるものだと主張する風説を伝えました。小村はすぐに金子に返電し、高平は関与していないと否定。金子も虚偽だと主張し、各紙が事実無根と報じました。しかし、この流言は、既に高平と金子の間で感情的な溝ができていたことを示唆します。 これは、以前のイエール・シンポジウムに関する件に加え、金子の高平への悪感情が増幅した結果だと考えられます。この事件は、金子と高平の間の不和、そして金子と外務省との間の意見の相違が、戦後の排日移民問題への対応にも影響を与えた可能性を示唆しています。金子の発言は、彼自身のアウトスポークンな性格が影響している可能性がありますが、小村から渡米前に与えられた「高平との表裏一致の行動」という訓令は、この時点で完全に破綻していました。
III. ポーツマス講和会議 小村寿太郎 と 高平小五郎 の活躍と市民外交の萌芽
ポーツマス講和会議では、小村と高平は日本全権委員として参加。小村が中心となって交渉を進める一方、高平はロシア側との直接交渉にはあまり関与せず、主に小村をサポートする役割に徹しました。しかし、会議が難航するにつれて、ポーツマスの市民らから講和成立を願う声が強まり、市民外交(シヴィリアン・ディプロマシー)の萌芽が見られました。市民による歓迎会や集会が開催され、日露両全権委員も参加しました。重要な登場人物として、ロシア全権委員のセルゲイ・ウィッテとロマン・ローゼンが挙げられます。最終的に、ロシアによるサハリン南部割譲という妥協点で講和は成立しました。
1. ポーツマス講和会議の開催と日本側全権委員
1905年8月10日から約1ヶ月間、ニューハンプシャー州ポーツマス海軍工廠で日露講和会議が開かれました。小村寿太郎とセルゲイ・ウィッテがそれぞれ日露の首席全権委員を務めましたが、高平小五郎は次席全権委員として参加しました。会議の主役は小村とウィッテでしたが、高平は比較的目立たない存在だったとされています。 ローゼンは回顧録を残しましたが、高平は何も残さなかったことが、彼のその後における研究の難しさに繋がっています。小村は高平を信頼しており、高平の米国における活動は、小村の外交戦略において重要な役割を果たしていました。日本側全権委員の随員として、佐藤愛麿、山座円次郎、安達峯一郎、本多熊太郎、小西孝太郎の5名が任命されました。さらに、外務省顧問のH.W.デニソン、落合謙太郎、陸軍武官の立花小一郎大佐、海軍武官の竹下勇少佐などが参加しました。会議開催地であるポーツマスは、当時人口1万余人の避暑地であり、海軍工廠として安全と機密保持に適した場所でした。会議開催地決定には、日露米三国の思惑が複雑に絡み合っていました。
2. 講和交渉の進展と難航 小村 ウィッテ間の激しい攻防
会議は8月10日に正式に開始されましたが、日本側の要求条件がすぐに新聞に漏洩し、ロシア側の厳しい回答によって、すぐに難航が予想されました。交渉は主に小村とウィッテによって行われ、ウィッテは米国の新聞を巧みに利用して親露的な世論形成を進め、交渉を有利に進めていきました。高平は、小村と時折言葉を交わす程度で、ロシア側と直接発言することはほとんどありませんでした。これは、当時の日本人の態度を反映しているのかもしれません。賠償金と領土割譲の問題で交渉は難航し、ルーズベルト大統領の積極的な介入もありましたが、容易には進展しませんでした。会議の難航は、ポーツマスの市民にも影響を与え、講和成立を望む声が強まりました。これは、市民外交(シヴィリアン・ディプロマシー)の萌芽と言えるでしょう。市民らは、歓迎会や集会を開催し、日露両国の全権委員や関係者を招いて、講和成立と平和の尊さを訴えました。ロシア全権委員はローゼンとウィッテでした。
3. 講和成立と市民外交の萌芽 ポーツマス市民の働きかけ
交渉は難航しましたが、日本政府がロシア皇帝の樺太南部譲歩という秘密情報を掴んだことで、講和は成立へと向かいました。最終会議は1日延期され、高平はウィッテと会談し延期に合意しました。講和条約調印後、高平らはポーツマス近郊のグリーン・エイカーのバハイ教センターで開かれた集会に参加し、日本の戦争目的達成と講和成立を誇りました。この出来事は、市民が政府代表に働きかけ、講和を促す市民外交の萌芽を示しています。ポーツマスの市民は、講和会議の開催を喜び、講和成立を強く望んでいました。彼らは、日露両国の全権委員や関係者を招いた歓迎会や集会を企画し、講和の成立と平和の尊さを熱心に訴えました。高平は、マンチェスター市の工場見学や地方政治家との会食などにも参加しており、当時の満州における米綿製品輸出の盛況なども背景にあったと考えられます。講和成立後も、高平は小村とともにポーツマスを離れ、ボストン、ニューヨークへと移動しました。
IV.戦後の 日米関係 と 高平 ルート協定
日露戦争勝利後、高平は駐米大使に昇格。しかし、日米関係は、満州の門戸開放問題や日本人移民排斥問題などを巡って悪化の兆しを見せ始めます。この状況下で、高平は1908年にエリュー・ルート国務長官と高平・ルート協定を締結し、アジア太平洋地域における日米間の現状維持を確認しました。この協定は、日米関係における重要な外交成果の一つです。 高平はルーズベルト大統領との親密な関係を維持し、退任後の来日招聘にも尽力しますが、実現には至りませんでした。
1. 日露戦争後の日米関係の変化と高平小五郎の再任
日露戦争後、日本は国際的に一等国の地位を認められるようになりました。1905年12月には在英公使館が大使館に昇格し、翌年には在米公使館も大使館に昇格しました。高平小五郎は1907年2月にイタリアへ赴任した後、1908年1月、二代目の駐米大使としてワシントンに戻りました。しかし、この時点の日米関係は、戦争前とは大きく変化していました。 ヘイ国務長官は既に亡くなり、ルート国務長官が後任となっていました。満州における門戸開放と機会均等の原則をめぐり、日米間の摩擦が生じていました。満州市場では、米国の綿製品が日本の製品に取って代わられつつあり、日本の経済的進出は米国に懸念を与えていました。日本は満州での鉄道経営や貿易による利益追求だけでなく、増大する国内労働力の海外への進出も模索しており、これが米国による日本の中国大陸支配への懸念につながっていました。これらの問題に加え、米国ではカリフォルニア州を中心に日本人移民への排斥運動が激化していました。
2. 高平 ルート協定の締結と日米関係の現状維持
高平は、変化する日米関係の潮流の中で、日米間の現状維持を図ろうと努力しました。ポーツマス講和会議直前の1905年7月には、桂・タフト覚書が締結され、米国が日本の韓国保護権を認め、日本がフィリピンに領土的野心を持たないことを確認していました。しかし、日露戦争での日本の勝利は、欧米人に黄禍論を想起させ、戦後の日米関係悪化の一因となりました。1908年11月30日、高平はルート国務長官と高平・ルート協定を締結しました。この協定は、アジア太平洋地域における日米勢力の現状維持を確認するものでした。これは、独米清協商案への動きを押し切る形での合意でした。 高平は、ルーズベルト大統領の離任後における日本への招聘にも尽力しました。これは、ルーズベルト大統領が日露戦争において日本に好意的な立場を取り、日本の勝利に貢献したことに対する感謝の気持ちからでした。しかし、日本の政府からは、ルーズベルト大統領への訪日招聘や勲章授与といった動きは見られませんでした。
3. ルーズベルト大統領の日本招致への働きかけと結果
高平は、日露戦争中に日本の勝利に大きく貢献したセオドア・ルーズベルト大統領を、明治天皇の名において日本に招きたいと強く望んでいました。彼は、ルーズベルト大統領の退任を機に、その功績に対する謝意を表すため、明治天皇からの親書による招致を小村外務大臣に提案しました。小村は、天皇からの直接の招致は前例のない異例のことであるとしながらも、ルーズベルト大統領が適当な時期に日本を訪問することを希望しており、高平にその勧誘を行うよう指示しました。高平は1909年2月下旬と3月上旬にルーズベルト大統領と面会し、日本の熱意を伝えました。しかし、ルーズベルト大統領の反応は消極的なものでした。 結局、ルーズベルト大統領の訪日は実現しませんでした。 高平は、ルーズベルトを敬愛し、まるで慈父のように見ていたと推測されます。 一方で、金子堅太郎はルーズベルトを親友と見ていたと推測されます。 このルーズベルト招致への高平の尽力は、日米関係における高平の深い思い入れを示しています。
