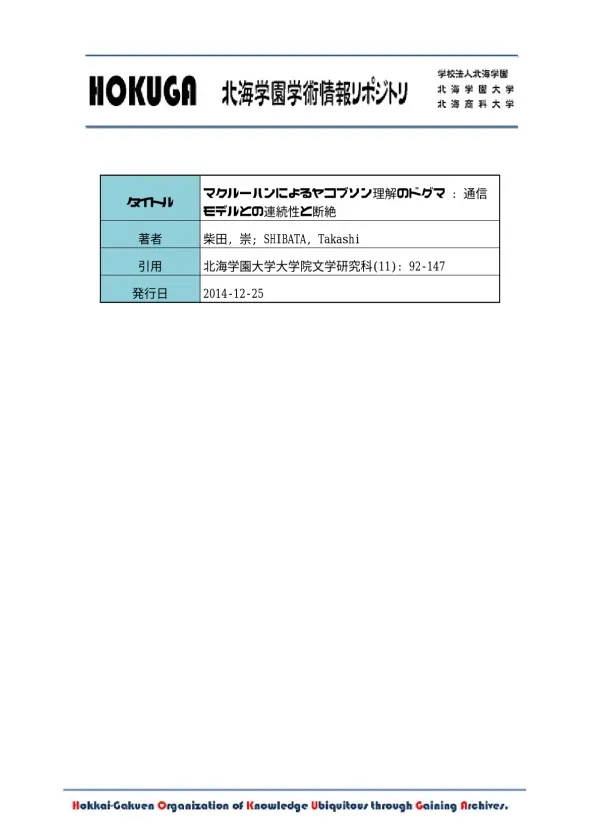
マクルーハン:ヤコブソン理解のドグマ
文書情報
| 著者 | 柴田 崇 |
| 専攻 | メディア論, コミュニケーション論 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.30 MB |
概要
I. マクルーハン の難解さと メディア生態学 コミュニケーションモデル への批判
本稿は、マーシャル・マクルーハンの著作の難解さの原因を探りつつ、彼のメディア生態学における主要な主張を、既存のコミュニケーションモデルとの比較を通して解説する。特に、シャノン=ウィーバーモデルやヤコブソンの言語モデルとの差異に焦点を当て、マクルーハンが左脳的・線形的な従来のモデルを批判し、右脳的・共鳴的なモデルを提唱した点を明らかにする。彼の理論は、記号論(特にパースの記号論)の概念を基盤としつつ、メディア環境が人間の認識に与える潜在的な影響を強調している。 図と地の概念を用いた議論や、構造主義への批判も重要な要素となる。
1. マクルーハンの著作の難解さ
マクルーハンの著作は、その難解さゆえに理解が困難であると指摘されている。その原因として、まず、文学的な素養に基づいたマクルーハンの博覧強記が挙げられる。アフォリズムを多用し、論理的な読解を妨げる書き方は、理解を阻む一因となっている。本稿では、マクルーハンの戦略に逆らって論理的な読解を試み、彼の思想全体を貫く不変の構造や理論を抽出しようとする。このアプローチによって、マクルーハン自身が自身の理論の発展過程を常に意識していたわけではないことも明らかになる。例えば、「外化(externalization)」という概念は、理論構築において重要な役割を果たしているが、マクルーハンはこれを同時代の思想を参照し、正しく引用した結果として理解していたに過ぎず、概念の系譜を遡って源流を特定しようとする自覚的な作業は行っていなかったと考えられる。彼の著作は、既存の思想の系譜をまとめ、未来に向けて保存するアーカイブとしての性質を持つが、それは二種類のアーカイブが存在するという意味ではなく、現在用いられている概念を精査し、保存する作業が、過去から現在、未来へと続く思想の糸のノード(結び目)を自然と形成するという事実を示している。マクルーハンの博覧強記に裏打ちされた著作は、良くも悪くも、そのようなノードとして申し分ない存在と言える。
2. シャノン ウィーバーモデルへの批判
マクルーハンは、シャノン=ウィーバーらの通信モデルを批判的視点から出発点として自身の理論を構築した。この通信モデルは、情報伝達を線形的なプロセスとして捉え、送受信者間のコード共有を前提としている。マクルーハンは、このモデルがコミュニケーションを情報伝達という機械的なプロセスに還元し、使用者の感受性や文脈を無視している点を指摘する。特に、アリストテレスやノースロップ・フライへの批判を経て、彼は西洋の科学的コミュニケーションモデルを総括的に批判する。これらのモデルは、動力因のパターンに従い、線形、論理的、継起的であり、左脳特有の「地」を欠いた図式に基づいているため、電子文化における同時並行性、非連続性、共鳴といった特性を捉えられないと主張する。電子時代においては、右脳的なコミュニケーションモデルが必要であり、それは左脳志向の伝統の残滓を払拭し、あらゆる「地」から切り離された抽象的なモデルではない、という結論に至る。
3. マクルーハンのメディア環境論と歴史的視点
マクルーハンは、メディア環境が人間の認識や文化に与える影響を重視する。音声言語が視覚的コードであるアルファベットに置き換えられたことで、西洋文明は視覚的なものへと変化し、吟遊詩人は衰退し哲人が台頭したと主張する。これは、新しい技術が古い技術を「内容」とし、自らが「形式」となるという、技術史におけるコードの変遷を示唆する。活版印刷の発明によって究極の視覚文化が形成されたが、電信の発明によってその状況は一変する。マルコーニによる無線電信の発明以降、図と地の関係は、視覚的な構成要素ではなく、両者の間の共鳴する隔たりによって規定される触覚的な関係へと変化したと主張する。この触覚的な関係を理解することで、視覚と聴覚を同一地平で比較し、線形的な歴史観を乗り越えることができる。マクルーハンは、この歴史的変化を基に、図と地の反転を意識的に作り出す内発的モデルの構築を試みたとされる。
4. ヤコブソンの言語モデルとの比較
マクルーハンのヤコブソン批判は、視覚的な発想にとらわれた西洋人が「図と地」の概念を誤解しているという指摘から始まる。ヤコブソンは、ソシュールを例に、視覚的なものと聴覚的なものを排他的に捉え、一方の考察のみで満足する傾向があると批判する。これは、視覚的なものと聴覚的なものを同時並存させ、両者の間隙における共鳴を捉えようとするマクルーハンの姿勢とは対照的である。マクルーハンの後期の著作では、ヤコブソンを「構造主義者」と見なし、構造主義的な発想を第二パラダイムのバイアスとして扱っている。しかし、彼のヤコブソン批判は、必ずしもヤコブソンの著作を直接的に参照したものではなく、文献表にもヤコブソンの著作は記載されていない点が指摘される。 コミュニケーションモデルにおいて、送受信者が同じコードを共有するという前提は、コンテクストの重要性を軽視しているという批判がされている。
II.ヤコブソン批判と 記号論 の統合 パース と シルヴァスティン
マクルーハンは、ヤコブソンを含む多くの言語学者を、視覚的な発想に囚われた「構造主義者」と捉え批判する。彼の批判は、ヤコブソンの言語モデルがコンテクストを十分に考慮していない点、つまり、コードの共有に依存しすぎている点にある。対照的に、マクルーハンは、パースの記号論(類像・指標・象徴の三分類)と、それを継承したシルヴァスティンらの言語人類学の成果を取り入れ、より包括的なコミュニケーションモデルを提示しようとした。シカゴ大学のシルヴァスティンと彼の弟子である小山亘の研究が、ヤコブソンのモデルを拡張した「出来事モデル」として紹介されている。
1. マクルーハンのヤコブソン批判 視覚的発想の限界
マクルーハンは、ヤコブソンを含む多くの言語学者を、視覚的な発想から抜け出せず、「図と地」の概念を誤解していると批判する。特に、ソシュールの通時態と共時態の説明における、視覚的要素と聴覚的要素の排他的な捉え方を問題視する。ヤコブソンを含む構造主義者たちは、視覚的なものと聴覚的なものを同時並存させ、その間隙での共鳴を捉えようとするマクルーハンの視点を欠いているとされる。マクルーハンは、彼らのアプローチが従来の視覚的発想を引きずっており、電子文化におけるコミュニケーションの本質を捉えきれていないと主張する。この批判は、単なる学問的な論争にとどまらず、西洋文明におけるコミュニケーションモデル全般に対する批判へと発展していく。マクルーハンの主張は、電子メディアが右脳的な特性を持つという認識に基づいており、西洋文化が認識の様式を左脳から右脳に移行させる過程にあるという前提が置かれている。そのため、左脳志向の伝統の残滓を払拭した新しいコミュニケーションモデルの必要性を説いている。
2. パースの記号論の導入 包括的なコミュニケーション理解へ
マクルーハンの批判をより深く理解するために、パースの記号論が重要な役割を果たす。ヤコブソンは、既に1950年代にパースの記号論の重要性に気づき、その後の研究に大きな影響を与えたとされる。パースの記号論、特に類像、指標、象徴の三分類は、ヤコブソンの言語理論、ひいてはマクルーハンのメディア理論を理解する上で不可欠な概念となる。ソシュールの文法論における連辞と範疇列も、指標性と類像性で説明できるほど、パースの記号論は包括的な体系を持つ。シルヴァスティンは、形式と機能のどちらか一方に偏った現代文法論のやり方を批判し、形式(象徴)と機能(指標)の相関関係を理論化するこそが文法論の責務だと主張する。 このシルヴァスティンの主張は、ヤコブソン、そしてパースの記号論によって支えられている。 マクルーハンの「構造主義」批判も、パースの記号論を用いて整理することが可能であり、ソシュール、チョムスキー、レヴィ=ストロースなどがその範囲に含まれると解釈できる。
3. シルヴァスティンと出来事モデル 言語人類学からのアプローチ
シカゴ大学のシルヴァスティンと彼の弟子である小山亘は、ヤコブソンの言語モデルを拡張した「出来事モデル」を提案している。このモデルは、コミュニケーションを「メッセージ」のやり取りではなく、「出来事」を中心に概念化する。 「出来事」には、言語的なメッセージだけでなく、笑い、音楽、身振りなど、様々な非言語的な要素が含まれる。これらの出来事は、コンテクストを示すことで、社会文化的意味づけが可能な「テクスト化された出来事」として浮かび上がるとされる。 通信モデルでは、送受信者が同じコードを共有していることが前提とされているが、小山は、この点が通信モデルと言語モデルの大きな違いであると指摘する。 さらに、小山は、ヤコブソンの「メタ言語的機能」を「メタ意味論的機能」と「メタ語用論的機能」に細分化することで、言語使用におけるコンテクストの重要性を強調する。 これは、静的なラングのコードだけでなく、パロール、すなわち言語使用の文脈も考慮する必要があることを示している。
III.メディア環境と テクスト化 グーテンベルクの銀河系 から 地球村 へ
マクルーハンのメディア生態学は、グーテンベルクの発明以降の西洋文明史を、メディア環境の変化による認識のパラダイムシフトとして捉える。印刷術による視覚文化の台頭、そして電信・電子メディアによる新たなパラダイムの出現を、図と地の反転という概念を用いて説明する。この歴史的視点を通して、マクルーハンは、メディアが「メッセージ」そのものであるという主張を展開する。 彼の著作は、**『メディアの理解』や『グーテンベルクの銀河系』**など、メディア研究の古典として広く知られている。
1. グーテンベルク銀河系から地球村へ メディア環境の変遷と認識
マクルーハンは、グーテンベルクによる活版印刷の発明を契機に西洋文明が視覚中心の文化へと移行したと主張する。『グーテンベルクの銀河系』で展開されるこの視点は、メディア環境の変化が人間の認識や文化に根本的な影響を与えるという彼のメディア生態学の中核をなす。アルファベットという視覚的コードは、音声言語を断片化し、視覚的傾向を助長する。これにより、吟遊詩人は文化の中心から追われ、哲人が台頭するという文化的変容が生じた。マクルーハンは、新しい技術(形式)が古い技術(内容)を包含するというコードの概念を提示し、この概念をアルファベットの発明だけでなく、他の技術革新にも適用する。西洋文明は、活版印刷によって完全に視覚的なものになったが、その後電信の発明によってこの完全な適応状態が破壊された。この歴史的視点を通して、メディアが人間の認識をどのように形作るか、そしてその影響がいかに潜在的かつ不可視であるかを説き明かす。
2. 図と地のパラダイムシフト 触覚的なコミュニケーション
マクルーハンは、「図と地」の概念を用いてメディア環境の変化を説明する。従来の心理学では、図と地は共に視覚的な構成要素と捉えられていたが、マクルーハンは、図と地の間にある共鳴する隔たりが、イコン的あるいは触覚的な関係を形成すると主張する。つまり、図と地の間には連続性や連結関係はなく、変形(transforming)という界面(interface)が存在する。この考え方は、彼とPowersによる共著(McLuhan & Powers 1989: 22-23)にも見られる。マクルーハンは、図と地の反転する関係を「共鳴的関係」と呼び、それを触覚的なものと定義づける。この触覚的な側面の導入によって、視覚と聴覚を同一地平で比較可能となり、線形的な歴史観を否定する。彼の文化コード論は、この触覚的な側面を理解することで初めて完全に理解できる。この触覚的な関係性は、外発的な認識メカニズムの理解から、図と地の反転を意識的に作り出す内発的モデルへと発展していく。
3. メディアのメッセージとテクスト化戦略
マクルーハンのメディア研究の主題は、「メディアのメッセージ」、つまりメディア環境からの影響の理解にある。この影響は潜在的で、直接的な検証が難しい。人間は、メディア環境に常に影響を受けているにもかかわらず、新旧のパラダイムが転換する時期を除いて、その存在に気づかないことが多い。マクルーハンの研究の特徴は、メディア環境が自ずと図化した様子を解き明かす点にある。彼は、先行するテーゼをコンテクストとして、際限のないテクスト化を行う戦略を用いる。これは、単なる言葉遊びではなく、類像性への強い執着を示している。マクルーハンは、通信モデルとは異なる、全く新しいコミュニケーションモデルを構想した。その意図は、詩的言語の探究へと収斂するものであり、廣松渉の哲学やバルトの仕事など、同時代の思想との関連性も指摘できる。
IV.コミュニケーションの再定義 出来事モデル と メタ言語的機能
従来のコミュニケーションモデルが情報の伝達に焦点を当てるのに対し、マクルーハンは、メディア環境による人間の認識や行動への影響を重視する。ヤコブソンの言語モデルを批判しつつ、シルヴァスティンらの出来事モデルを取り込み、コミュニケーションを単なる情報の伝達ではなく、コンテクストに依存した複雑な「出来事」として捉え直す。特に、ヤコブソンのメタ言語的機能を、メタ意味論的機能とメタ語用論的機能に細分化することで、コンテクストの重要性を強調する。
1. コミュニケーションモデルの限界 情報の伝達から出来事へ
従来のコミュニケーションモデル、特にシャノン=ウィーバーモデルは、情報を導管を通して運ぶような線形的な情報伝達に焦点を当てている。このモデルでは、送受信者が同一のコードを共有し、メッセージはコミュニケーションに先立って既に存在するものとして扱われる。小山は、このモデルではコミュニケーションの成功が同一コードの共有に依存し、メッセージはコンテクストを必要としない「脱コンテクスト化」された意味しか持たないと指摘する。つまり、コミュニケーションは相互行為というよりも、単なる情報の伝達に還元されている。 対照的に、マクルーハンは、メディア環境が人間の認識や行動に与える潜在的な影響を重視する。そのため、従来のモデルでは不十分であり、新たなコミュニケーションモデルが必要となる。
2. ヤコブソンの言語モデルとメタ言語的機能の再解釈
ヤコブソンは、言語によるコミュニケーションを構成する六つの要因(メッセージ、送り手、受け手、接触回路、コード、言及指示対象)と、それぞれの機能(詩的機能、表出的機能、動能的機能、交話的機能、メタ言語的機能、言及指示的機能)をモデル化している。このモデルにおけるコンテクストは、文脈的意味と指示言及対象(referent)の双方を含む概念である。小山は、ヤコブソンのメタ言語的機能について、メタ意味論的機能とメタ語用論的機能という二つの下位範疇を指摘する。前者は、語彙や言い回しの脱コンテクスト化された意味を尋ねるメッセージで、静的なラングのコードが想定される。後者は、コンテクストへの依存が強く、教師の表情や声調といった状況が解釈に大きく影響する。メタ言語的機能は、文法研究の理論的枠組みと密接に関連しており、言語モデルの中心的位置を占める。
3. 出来事モデルによるコミュニケーションの再定義 テクスト化とコンテクスト
シルヴァスティンらは、経験的な研究に基づき、コミュニケーションの出来事の構成要因として七つの要因(参加者、接触回路とその使用様式、コード、環境、メッセージの形態とジャンル、メッセージの内容、出来事そのもの)を同定する。この「出来事モデル」の登場により、コミュニケーションを「メッセージ」ではなく「出来事」を中心に概念化することが可能になった。「出来事」には言語的なメッセージだけでなく、笑い、楽器の音、顔つき、動作なども含まれる。これらの出来事は、コンテクストを指し示すことで、「テクスト化された(社会文化的な意味づけが可能な)出来事」として浮かび上がり、コミュニケーションの理解を深める。 このモデルは、ヤコブソンの言語モデルを拡張し、社会、文化、歴史を記述・分析できる基礎理論を提供する。
