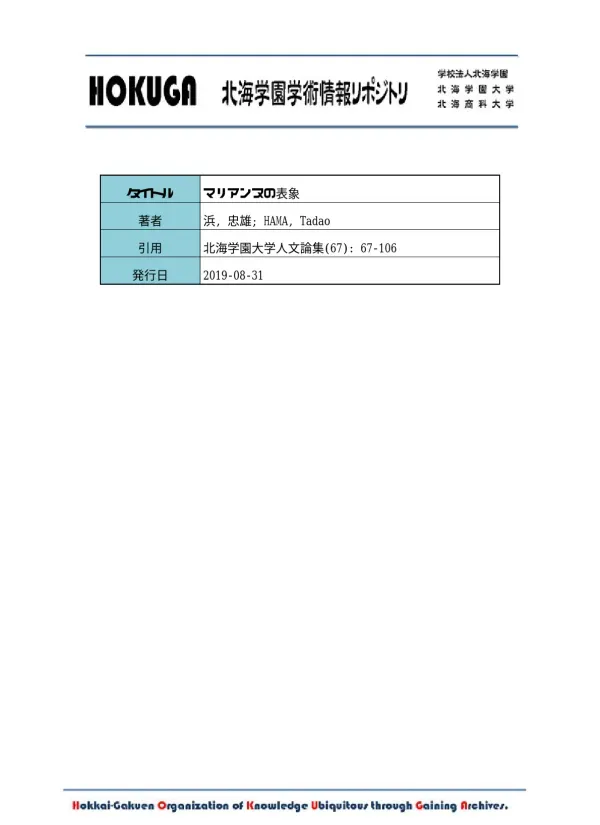
マリアンヌ像の変遷:図像による歴史解読
文書情報
| 著者 | 浜 忠 雄 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 人文科学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.69 MB |
概要
I.マリアンヌ像の誕生とフランス革命
本稿は、フランス革命期から20世紀初頭までのマリアンヌ像の変遷を考察します。革命以前は国王の肖像が国の象徴でしたが、バスティーユ襲撃(1789年7月14日)、人権宣言採択などを経て共和政が成立すると、抽象的な共和国を具象化する象徴としてマリアンヌが登場しました。初期のマリアンヌ像は、グロやヴァランといった画家によって描かれ、新古典主義的な画風で表現されました。これらの作品では、自由、平等、友愛といった革命の理念が反映されています。重要な人物として、マリアンヌ像の制作に携わったグロとヴァラン、そして人権宣言の男女平等を訴えたオランプ・ドゥ・グージュが挙げられます。
1. 革命前と共和政成立 マリアンヌ誕生の背景
フランス革命以前、国家の象徴はブルボン王家の紋章や国王の肖像でした。しかし、1789年のバスティーユ襲撃、同年8月の人権宣言採択、1791年のルイ16世のヴァレンヌ逃亡未遂事件といった出来事を経て、王権は1792年8月10日に停止され、同年9月21日に王政廃止と共和政が宣言されました。この共和政樹立に伴い、抽象的な概念である『共和国』を具象的に表現する新しい象徴の必要性が生じ、これがマリアンヌ像誕生の直接的な背景となります。 従来の王権を表す象徴から、新しい共和国の理念を具現化する象徴への転換が、マリアンヌ像の出現に繋がったのです。この過程は、フランス革命の激動期における政治的・社会的な変化を如実に反映しています。 新たな象徴としてマリアンヌが選ばれた理由、その背景には、革命の理念である自由・平等・友愛を体現する人物像として、マリアンヌという名が選択されたという歴史的経緯が存在するのです。
2. 初期のマリアンヌ像 グロとヴァランの作品
共和政を象徴するマリアンヌ像の初期の作品は、グロとヴァランによって描かれました。両者ともジャック=ルイ・ダヴィッドを師としており、新古典主義的な画風を受け継いでいます。彼らの作品は過度の装飾を避け、形式的な美と写実性を重視した格調高い人物像となっています。グロはナポレオンを題材とした作品で有名ですが、ヴァランは日本では比較的無名です。 グロとヴァランの作品に見られる共通点は、新古典主義的な美意識に基づいた写実的な描写と、革命の理念を反映した象徴的な表現です。例えば、マリアンヌが人権宣言を手にしている姿は、共和政の理念を視覚的に表現していると考えられます。これらの初期のマリアンヌ像は、後のマリアンヌ像の表現に大きな影響を与えただけでなく、フランス革命期における芸術表現のあり方の一端を示す重要な資料となっています。アンシァン・レジーム末期から革命期にかけて活躍した多くの女性画家の中でも、グロとヴァランの才能は際立っていました。
3. マリアンヌという名の由来と象徴性 クリスティアン ロの研究
マリアンヌという名前の由来について、クリスティアン・ロの研究が注目されます。それによると、マリアンヌという名前が革命の精神(自由・平等・友愛)を象徴する名称として使われ始めたのは、1792年10月頃のことだとされています。サン=キュロットであるギヨーム・ラヴァブルが作曲したシャンソン「マリアンノの快復」がその始まりで、オック語で書かれた歌詞には、病と貧困に苦しむマリアンヌが、共和政成立によって回復する様子が描かれています。このシャンソンは、マリアンヌという名前が持つ、革命と共和政への希望、そして民衆の回復への願いといった意味合いを鮮やかに示しています。 このシャンソンは、マリアンヌという名前の持つ意味と、その名前がどのようにして共和政の象徴となったのかを理解する上で、極めて重要な資料と言えるでしょう。 マリアンヌの名は、聖母マリアとその母アンナの名にも通じることから、当時広く崇敬されていた宗教的要素と共和政の理念が重なり合った複雑な背景を持つと言えるでしょう。
4. マリアンヌ像と女性の権利 オランプ ドゥ グージュ
マリアンヌ像は「自由」や「共和国」を象徴する女性像として描かれますが、当時、女性は政治的主体としてはみなされていませんでした。人権宣言は当初女性への適用を想定しておらず、女性の人権は否定されていたのです。にもかかわらず、なぜ女性像が共和国の象徴として用いられたのかは複雑な問題です。オランプ・ドゥ・グージュは、人権宣言が男性中心であることを指摘し、1791年頃に「女性の権利宣言」を起草して男女平等を訴えました。しかし、その主張は無視され、グージュ自身も1793年に処刑されました。 グージュの主張は、革命における女性の役割と、女性の人権が否定されていたという矛盾を浮き彫りにしています。グージュは、女性の人権だけでなく、非嫡出子や奴隷の人権も主張した革新的な思想家でした。彼女の活動と主張は、後のフェミニズム運動にも大きな影響を与え、現代においても重要な意味を持ち続けているのです。彼女と彼女の宣言は、長らくフランス人の記憶から消されていたという事実も重要な意味を持ちます。
II.マリアンヌと黒人奴隷制廃止
1794年の黒人奴隷制廃止は、マリアンヌ像において重要な意味を持ちます。多くの絵画が、フランス共和国による奴隷制廃止を、マリアンヌが上から見下ろす構図で表現しています。これは、フランスが自由の担い手であり、黒人奴隷は恩恵を受けるという、優越的な視点からの表現です。しかし、この廃止は短命に終わり、ナポレオンによって1802年に復活しました。1848年の最終的な廃止は、サルダ=ガリガによる布告を伝える絵画によって表現され、自由と平等が強調されています。この節では、1794年と1848年の奴隷制廃止を描いた絵画が重要な資料となります。
1. 1794年の黒人奴隷制廃止とマリアンヌ像
1794年、フランス革命政府は植民地における黒人奴隷制廃止を決定しました。これはイギリス、スペインなど、奴隷制を維持していたヨーロッパ諸国に先駆けた画期的な出来事でした。この歴史的出来事を描いた絵画が複数紹介されており、それらには共通してマリアンヌ像が登場します。多くの絵画において、マリアンヌは高所から奴隷解放の場面を見下ろす構図で描かれており、フランスが自由の担い手であり、黒人奴隷は恩恵を受けるという、優越的な視点が明確に示されています。マリアンヌはフリジア帽をかぶり、「自由の木」や解放された黒人を象徴する要素と共に描かれ、フランス共和国の象徴としての役割が強調されています。これらの絵画は、フランス革命期の黒人奴隷制廃止という歴史的事実と、マリアンヌ像がどのようにその歴史的文脈の中で用いられたのかを示す貴重な視覚資料となっています。
2. 奴隷制廃止の短命とナポレオン
しかし、1794年の奴隷制廃止は長くは続きませんでした。ナポレオンは1802年に奴隷制を復活させ、奴隷貿易も再開しました。この決定は、フランス革命の理念と、ナポレオンの政策との間の深刻な矛盾を浮き彫りにしています。 短期間のうちに奴隷制が復活されたことは、革命の理想と現実との間のギャップ、そして植民地におけるフランスの政策の複雑さを示す重要な歴史的事実です。この期間、マリアンヌ像はどのように表現され、どのような役割を果たしていたのか、という点についても、更なる研究が必要となるでしょう。ナポレオンによる奴隷制の復活は、フランス革命の理想が完全に実現しなかったことを示す象徴的な出来事と言えるでしょう。
3. 1848年の奴隷制廃止とマリアンヌ像 サルダ ガリガの布告
フランスが黒人奴隷制を最終的に廃止したのは、第二共和政の1848年でした。レユニオン島における奴隷制廃止を描いた絵画には、サルダ=ガリガ総督が解放布告を読み上げる場面が描かれています。この絵画においても、マリアンヌ像は重要な役割を果たしており、サルダ=ガリガの布告と共に、自由と平等が強調されています。サルダ=ガリガの布告文には、「友人たちよ。共和国の法令が実施される。あなたたちはみな自由で法の前で平等である」といった言葉が含まれており、共和国の理念が直接的に表現されています。 この絵画は、1794年の廃止宣言と同様に、フランス共和国の象徴であるマリアンヌが、自由の担い手として描かれている点で共通しています。しかし、同時に、フランスの優位性を示唆する構図も、この絵画には含まれています。1848年の奴隷制廃止は、革命の理想の実現に向けた新たな一歩でありながら、その過程における矛盾も示唆する複雑な出来事と言えるでしょう。
4. マリアンヌ像と 上から目線 解放者と被解放者の関係
1794年と1848年の奴隷制廃止を描いた絵画には共通点があります。それは、「解放する者=フランス人、解放される者=黒人奴隷」という、フランスの優位性を示す「上から目線」の構図です。マリアンヌは「自由の女神」であると同時に、「共和国の女神」として描かれ、フランスが奴隷解放の恩恵を与える存在として表現されています。 この表現は、フランス革命が掲げた自由と平等という理念と、現実の植民地支配における力関係との間の矛盾を浮き彫りにしています。マリアンヌ像を通して、フランス革命期の奴隷制廃止が、単なる人道主義的な行為ではなく、フランスの国家権力や植民地支配と深く結びついていた複雑な歴史的背景を理解する上で、これらの絵画は重要な視点を提供しています。この「上から目線」という表現は、後のフランス植民地主義の歴史を理解する上で重要な示唆を与えます。
III.マリアンヌ像の変遷と象徴性の多様性
革命期には、共和国の象徴としてマリアンヌ像が用いられる一方、ジャコバン独裁期にはヘラクレス像に取って代わられる動きもありました。その後、マリアンヌ像は再び登場し、19世紀には、自由だけでなく、人民の勇気や力を象徴するライオンと組み合わせられるようになります。オノレ・ドーミエによる「共和国」は、母性と豊饒さを象徴するマリアンヌ像として注目されますが、同時に、現実の共和政から女性が排除されていたという矛盾も示唆しています。 また、マリアンヌ像は、20世紀初頭には植民地主義と結びつき、「帝国の女神」としての側面も持つようになりました。フランスの植民地拡大を伝える新聞の表紙絵などに見られるように、マリアンヌの象徴性は時代とともに変化していきました。
1. ジャコバン独裁期における共和国の象徴 ヘラクレス像
ジャコバン独裁期に入ると、共和国の象徴として男性像を用いる動きが出てきました。選ばれたのはギリシア神話のヘラクレスで、国内外の反革命勢力に抗して共和国を守る英雄のイメージが、当時の人々の共感を呼んだようです。 オーギュスタン・デュプレによるヘラクレスのデッサンが紹介されており、中央には古代ギリシアのヘラクレス像がモデルとして用いられています。絵には「République Française, Une et Indivisible」(単一にして不可分なるフランス共和国)の略字が記されており、共和国の統一と不可分性を強調する意図が見て取れます。一方、ポール・アンドレ・バッセの絵画「共和国の表象」では女性は登場せず、共和国の統一と不可分性が強調されています。この時代の変化は、共和国の象徴表現において、女性像から男性像への移行を示す重要な転換点であり、その背景には、ジャコバン派の政治的立場や、当時の社会情勢が大きく影響していると考えられます。 この転換は、マリアンヌ像の変遷において、一時的な中断期とも捉えることができます。
2. 女性像と男性像の間 両性具有的な男性像
女性像から男性像への変化は、一足飛びに起きたわけではなく、その中間段階として両性具有的な男性像が登場しました。アンヌ=ルイ・ジロデ=トリオゾンによる「エンデュミオンの眠り」や、ダヴィッドによる「ジョゼフ・バラの死」といった作品がその例として挙げられています。これらの作品では、優美で女性と見紛うような男性像が描かれており、女性像と男性像の橋渡し的な役割を果たしていると考えられます。これらの作品は、共和国の象徴表現における性の曖昧性、そしてその背後にある複雑な社会・政治的状況を反映していると考えられます。 両性具有的な男性像の登場は、共和国の象徴表現における柔軟性と、時代背景における変化への対応を示唆する興味深い現象です。これらの作品は、マリアンヌ像という女性像が必ずしも共和国の唯一の表現ではなかったことを示す重要な事例と言えます。
3. 1830年以降のマリアンヌ像 ライオンと人民主権
1830年以降のマリアンヌ像は、それまでのものとは異なる特徴を見せています。いくつかの作品では、マリアンヌ像と共にライオンが描かれており、ライオンは「人民の勇気・力」の象徴として解釈されています。 コルニュの作品では、マリアンヌが立像で描かれ、寛衣の赤色が強調されているほか、台座に置かれた肘掛け椅子の脚部にライオンが彫られています。 さらに、マリアンヌが右手で「Souveraineté du peuple」(人民主権)と書かれたものを掲げている作品もあり、人民主権の概念が強調されています。これらのライオンが登場するマリアンヌ像は、共和国の象徴としてのマリアンヌ像に、新たに人民の力と主権という要素が加わったことを示しています。 これらの変化は、1830年以降のフランスにおける政治状況や社会状況の変化を反映していると考えられ、マリアンヌ像の多様な意味合いを理解する上で重要な資料となります。
4. ドーミエの 共和国 とマリアンヌ像の多様な解釈 母性と幻想
オノレ・ドーミエによる「共和国」は、子どもに授乳する逞しく豊饒な女性として描かれています。この作品は、共和政を多産な母として、国民に共和主義という「乳」を与える存在として表現しています。しかし、この作品は同時に、現実の共和政から女性が徹底的に排除されていたという矛盾も示唆しています。鈴木という研究者の指摘を引用し、この作品は現実の女性とは無関係に、男性の幻想を投影したものであり、挑戦的な性格を持たないものだったと分析しています。 ドーミエの作品は、マリアンヌ像が多様な解釈を許容する象徴であることを示しており、その多様な解釈の背後には、時代背景や作者の意識などが複雑に絡み合っていることを示唆しています。 この作品は、マリアンヌ像の表象と、現実の社会における女性の地位との間の乖離を浮き彫りにしています。
IV.マリアンヌ像と女性の表象
マリアンヌ像は女性の身体を用いて自由や共和国を表現していますが、これは女性が政治的主体ではなかったからこそ、という逆説的な側面があります。 オランプ・ドゥ・グージュの「女性の権利宣言」は、フランス革命における女性の権利と地位、そしてジェンダー問題を象徴する重要な文献です。 また、女性の裸体画の歴史において、マリアンヌ像の表象は、男性の視点から女性がどのように描かれてきたかという問題を提起します。マネの「オランピア」や、ドーミエの作品などは、この点を考察する上で重要な資料となります。現代の視点から、マリアンヌ像における女性の表象と、女性の権利・地位との関係性を再考することが重要です。
1. マリアンヌ像と女性の政治的現実 矛盾する象徴性
マリアンヌ像は「自由」や「共和国」を象徴する女性像として描かれますが、この点には大きな矛盾が潜んでいます。なぜなら、フランス革命期において女性は政治的主体として認識されておらず、人権宣言も当初は女性への適用を想定していなかったからです。 アギュロンやリン・ハントといった研究者も、この点を指摘しており、女性像が用いられたのは、女性が政治的影響力を持たなかったがゆえに、自由の理想を表現するために選ばれたという逆説的な側面があると説明しています。 革命期にはマリー・アントワネット、オランプ・ドゥ・グージュ、ロラン夫人といった女性が処刑され、女性の結社や政治活動は厳しく制限されました。マリアンヌ像は、こうした現実を踏まえると、理想と現実の間に存在する矛盾を象徴していると言えるでしょう。この節では、フランス革命における女性の権利と地位、そしてマリアンヌ像の象徴性の複雑さを分析します。
2. オランプ ドゥ グージュと女性の権利宣言 無視された声
オランプ・ドゥ・グージュは、人権宣言が男性中心であることを鋭く批判し、1791年頃に「女性の権利宣言」を起草しました。この宣言では、女性の政治参加や教育の権利、そして男女平等な人権を訴えています。しかし、彼女の主張は革命政府によって無視され、グージュ自身も1793年に反革命分子として処刑されました。グージュは女性の人権だけでなく、非嫡出子や修道士、黒人奴隷の人権をも主張しており、社会的・政治的・宗教的ヒエラルキーと差別システム全体への批判者でした。彼女の「女性の権利宣言」は、フランス革命におけるジェンダー問題、そして女性の権利の歴史を考える上で非常に重要な文献です。 グージュとその宣言が、フランス革命200周年頃までフランス人の記憶から消されていたという事実は、革命後の女性の社会的地位の低さを示す象徴的な事例です。
3. 女性の裸体画とマリアンヌ像 男性の視点と女性の客体化
マリアンヌ像の身体表現、特に裸体画の歴史を考察することで、女性の表象とジェンダー問題への新たな視点を獲得できます。近代西洋絵画において女性の裸体画が圧倒的に多いのは、美術の注文主、作者、批評家、鑑賞者の多くが男性であったためです。 西洋美術史における女性の裸体画には、「デコールム(decorum)」という作法が存在し、ヨーロッパの生身の女性の裸体は描かれてはいけませんでした。しかし、神話や聖書、非ヨーロッパ世界の女性などを題材とすることで、女性の裸体が数多く描かれてきました。19世紀後半にマネの「オランピア」が発表されると大きな批判を浴びましたが、これは、描かれた女性がごくありふれたフランス人女性であったこと、そして絵画の手法にも問題があったためです。 鈴木という研究者の指摘に基づき、マリアンヌ像は「創り手としての男性対素材としての女性」の関係性を示し、さらに「観る側としての男性対観られる側としての女性」という視点を加えることで、マリアンヌ像における女性の客体化を分析します。シルヴィア・スレイといった現代のアーティストの意見も参照し、女性の裸体表現における問題点と、より人間性の尊重された表現の必要性を考察します。
4. ドーミエの 共和国 と母性の象徴 現実と理想の乖離
オノレ・ドーミエの「共和国」は、子どもに授乳する逞しい女性像です。この作品は、共和政を慈愛に満ちた母性と豊饒さの象徴として表現しています。しかし、この作品もまた、現実の共和政から女性が排除されていたという矛盾を内包しています。「共和国」は、現実の女性とは無関係に、男性の幻想を投影した作品であり、現実への挑戦的な性格は持ち合わせていないと分析できます。 ラファエロの「子椅子の聖母」やブシェの「昼食」といった伝統的な母性像と比較することで、ドーミエの作品が持つ独自性を浮き彫りにし、母性という概念の多様な解釈可能性を検討します。 この節では、マリアンヌ像における母性というテーマを、現実の女性の状況と比較検討することで、理想と現実の乖離を改めて示し、マリアンヌ像の複雑な意味合いを深く考察します。
