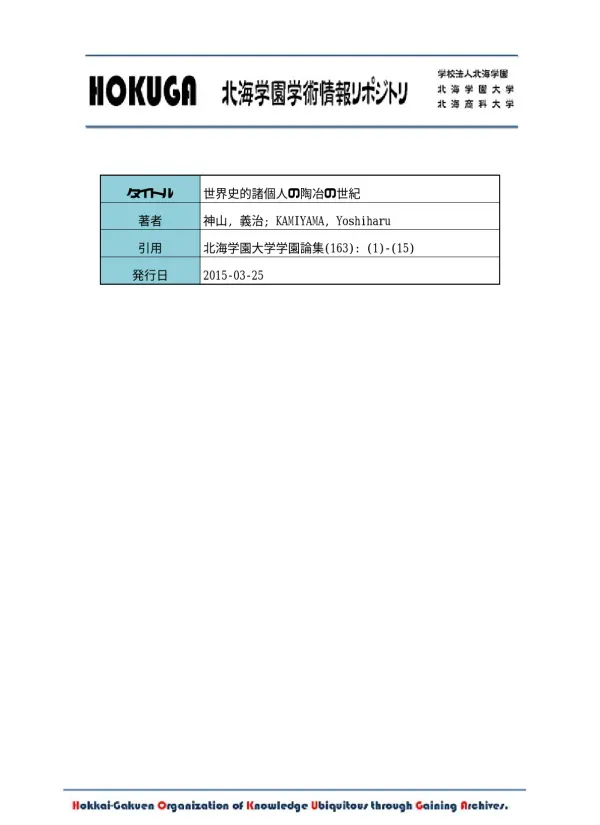
マルクスの資本論:資本主義の必然性と克服
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.05 MB |
| 専攻 | 哲学 |
| 文書タイプ | 論文 |
概要
I.マルクスの資本主義批判 労働と私的所有の矛盾
この文章は、マルクスの理論に基づき、資本主義における労働の疎外と私的所有の矛盾を分析しています。特に、資本主義が歴史における一時的な通過点であり、労働する諸個人の普遍的な団結によって克服されるべきものであると主張しています。資本主義のグローバリゼーションは、この矛盾を世界規模で拡大させ、同時に労働者の社会化と民主主義の発展を促進する力ともなると分析されています。資本論で述べられる生産手段の集中と社会化された労働の組織化が、この転換の鍵となります。
1. 資本主義の必然性と通過点としての役割
この節では、資本主義が労働による社会形成において必然的な役割を果たしているというマルクスの見解が示されています。具体的には、資本主義は自己を否定しながら世界史における特殊な通過点として実現していく過程にあると記述されています。この記述は、資本主義の現在の運動自体から導き出された結論であり、先行する全ての生産様式からの資本の区別を明確にしています。同時に、資本は単なる通過点として位置付けられているという点も強調されています。これは、資本主義が最終的な社会形態ではなく、より高度な社会への移行段階であることを示唆しています。さらに、個々人のこの連関への独立性と、その連関の形成が同時に自己からの移行の条件を含むほどの高みに発展している点が指摘されています。これは、人間の精神的能力が、まず自己に対立する独立した力として宗教的に形づくられる必要があるという点と比較されています。個別の生産過程が世界市場を通じて世界的な過程の諸器官へと転換していく過程も示唆され、個人の生命過程が世界的なものになっていることが強調されています。資本主義の自己超越は、資本の生み出す成果の主体的な形態と客体的な形態の統一として実現する、という展望が提示されています。
2. 自由な労働者と私的所有の矛盾
この節は、自由な労働者の存在が資本主義システムにおいて二重の意味を持つことを論じています。自由な労働者は、資本主義の継続的な生産と永続化に寄与する一方で、私的所有という制度の矛盾を露呈させます。蓄積による拡大の契機として存在する私的所有は、実は承認されざる権利という承認において、自由な私的所有とは正反対の内容を不可避的に露呈するという点に焦点が当てられています。ブルジョア経済学者による既存の経済関係の弁護とは対照的に、この節では、資本主義の下での生産の発展が、労働する諸個人の社会的な生産の対立的な形態における発展であり、その対立的な形態を脱して諸個人の自由な発展の真の基礎へと転換していく過程が論じられています。私的所有の下で対立的に成長した社会的な労働、貧困を蓄積する資本の飽くなき拡大欲求、そしてそれらが労働者をものごとを考え、連帯する諸個人へと社会化していく過程が描かれています。グローバリゼーションの力として対立的に形成されているのは、万国の労働する諸個人が奪還すべき普遍的な力であると結論付けています。
3. 資本主義の自己矛盾と労働者の役割
この節では、資本主義の自己矛盾と労働者の役割について、より詳細な分析がなされています。資本主義システムが自己否定的に自己を媒介しているメカニズムが検討され、商品システムとしての資本主義の把握の要諦が提示されています。私的所有が、蓄積における拡大の契機として、自由な私的所有とは正反対の内容を露呈するという点が改めて強調されます。民主主義の発展と資本の生産発展は、労働する諸個人の社会生産の対立的な形態における発展であり、最終的には諸個人の自由な発展の真の基礎に転換するとされています。この転換は、人類史における真理、変革の根拠として総括されています。労働する諸個人が、敵対的な全体の力として現れ、人間の自然的・社会的諸力を自己のもとに包含しようとする闘いは、労働する市民の人権の発展として現れると述べられています。資本のグローバリゼーションは、資本の内面的矛盾の展開であり、万国の労働する諸個人が奪還すべき普遍的な力として描かれています。ブルジョワ時代の成果である世界市場と近代的生産力を我が物とし、世界的な民主主義を担う労働する諸個人を資本主義が必然化することで、資本主義自身を解消しつつある通過点であるという結論が提示されています。
II.資本主義の自己否定と自己超越
資本主義システムは、その内在的な矛盾によって自ら否定し、超越していく過程にあると論じています。自由な労働者の存在は、資本の蓄積を促す一方で、私的所有の限界と矛盾を明らかにしています。ブルジョア経済学者による弁護とは対照的に、労働する諸個人の社会的な生産の対立的な形態が、最終的に諸個人の自由な発展の基盤へと転換すると主張します。この転換は、人類史における真理であり、変革の根拠となります。
1. 資本主義の自己否定的なメカニズム
この節では、自己再生する資本主義全体がいかにして自己否定的に自己を媒介しているのかが論じられています。資本主義は商品システムとして捉えられ、その本質的な矛盾が自己否定と自己超越のプロセスを駆り立てる原動力として提示されています。特に、自由な労働者の存在が、資本主義の継続的な生産と永続化をもたらす一方で、私的所有という制度の矛盾を不可避的に露呈させるという点に注目が集まっています。蓄積による拡大の契機として機能する私的所有は、皮肉にも自由な私的所有とは正反対の内容を明らかにし、資本主義システムの内在的な矛盾を浮き彫りにしています。ブルジョア経済学者による資本主義体制の弁護とは対照的に、この矛盾こそが資本主義の自己否定的な側面を露呈させる重要な要素として位置づけられています。この自己否定的なプロセスこそが、資本主義の終焉へと繋がる可能性を示唆しています。そして、この矛盾の解決、すなわち資本主義の超越は、労働する諸個人の社会的な生産における対立的な形態の発展、そしてその対立的形態からの脱却によって実現すると考えられています。
2. 私的所有の矛盾と社会変革
この節では、私的所有が資本主義システムにおける根本的な矛盾の源泉として扱われています。蓄積を通じて拡大していく流れの契機として機能する私的所有は、その承認の裏側に自由な私的所有とは正反対の矛盾を隠している、と指摘されています。この矛盾は、ブルジョア経済学者によって既存の経済関係を弁護するための隠れ蓑として利用されている以上に、資本主義システムの不安定性を示す重要な指標となっています。資本主義の下での生産の発展は、労働する諸個人の社会的な生産における対立的な形態の発展として理解されています。この対立的な形態は、最終的には諸個人の自由な発展の真の基礎へと転換すると考えられています。この転換は、人類史における真理であり、社会変革の根拠として提示されています。私的所有の下で対立的に成長した社会的な労働、貧困を蓄積する資本の飽くなき拡大欲求は、労働者をものごとを考え、連帯する諸個人へと社会化していく力として作用します。この社会化のプロセスこそが、資本主義の自己否定と自己超越のプロセスを加速させる重要な要素として捉えられています。
3. 資本主義の自己超越と民主主義
この節は、資本主義の自己超越が、労働する諸個人の普遍的な団結と民主主義の発展を通じて実現すると論じています。資本のグローバリゼーションは、資本主義システムの内面的矛盾の展開であり、同時に万国の労働する諸個人によって奪還されるべき普遍的な力でもあります。この力は、ブルジョア時代の成果である世界市場と近代的な生産力を基盤として、世界的な民主主義を担う労働する諸個人を必然的に創出します。しかし、資本主義は、その自己超越の過程において、超国籍企業の社会的責任や、資本主義システムの限界(例えば、環境問題)といった新たな課題をもたらすことも指摘されています。 労働する諸個人の自由な結合による社会の転換、これは資本主義が自らを生み出した結果であり、資本主義が自らを生み出した矛盾を解消していく過程を示しています。この過程において、企業における自由な諸個人としての社会的承認の実現、そして資本主義というシステムの限界を超えた新たな社会の構築が、根本的な課題として提示されています。 真のグローバルな課題は、民主主義の徹底、社会生産過程の協同的な管理、そして労働する諸個人の普遍性を発動させることだと主張しています。
III.グローバル化と労働者の団結
グローバリゼーションは、資本の拡大欲求によるものであり、同時に世界規模での労働者の普遍的な力の形成を促します。資本主義は、世界市場と近代的な生産力を生み出し、世界的な民主主義を担う労働する諸個人を必然的に創り出します。しかし、超国籍企業の社会的責任や、資本の無政府的な運動の限界も問題視されています。地球環境問題は、人間と自然の関係を超えた、システム全体の矛盾として捉えられています。
1. グローバリゼーションと資本の拡大欲求
この節では、グローバリゼーションが資本の飽くなき拡大欲求によって推進されていると分析しています。貧困を蓄積する資本の拡大欲求は、労働者をものごとを考え、連帯する諸個人へと社会化させる力として作用すると論じています。この過程において、グローバリゼーションは資本主義システムの内面的矛盾の展開でありながらも、同時に万国の労働者が奪還すべき普遍的な力を形成する場ともなると示唆しています。ブルジョア時代の成果である世界市場と近代的な生産力は、この普遍的な力の基盤として位置づけられています。世界的な民主主義を担う労働者階級を資本主義自身が必然的に生み出しているという皮肉な状況も指摘されており、資本主義は自己を解消しつつある通過点であるという見解が示されています。 このグローバリゼーションによって生み出される世界市場と近代的な生産力は、労働する諸個人が共同で利用し、より良い社会を築くための基盤になりうる可能性も示唆されています。
2. 労働者の普遍的団結の重要性
グローバル化が進む現代において、労働する諸個人の普遍的な団結の重要性がますます高まっていると主張しています。これは、現在の排外主義の横行と対照的に、グローバルな課題に対処するための重要な方策として提示されています。この普遍的な団結こそが、資本主義の矛盾を克服し、真の自由な社会を築くための力になると考えられています。 資本主義が創り出すグローバリゼーションは、資本の内面的な矛盾の展開であり、個人の犠牲の上に成り立つ敵対的な形態からの脱却、個々人の進歩への転換を促す力でもあります。この転換は、世界市場と近代的生産力を我が物とし、社会の主人公である諸個人の協同の土台の上に、真に諸個人が自由に結ばれる世界への転換という根源的な課題へとつながっています。超国籍企業の社会的責任や、自由な諸個人としての社会的承認の実現も、この新たな社会を構築する上で重要な課題として挙げられています。
3. グローバルな課題と資本主義の限界
この節では、グローバル化に伴い顕在化する様々な課題、特に資本主義システムの限界が論じられています。資本主義がもたらすグローバリゼーションは、そのシステムの内部矛盾の顕在化であり、その矛盾こそが世界規模での労働者の団結を促進する力になると考えられています。しかし、資本主義システムがその無政府的な運動によって発展をゆだねる現状では、そのシステムの有限性が問われています。いわゆる地球環境問題は、人間一般とその外部の自然の関係を超えた、システム全体の矛盾として捉えられています。より高度な社会の形成のためには、これまでの奴隷制や農奴制よりも有利な方法と条件のもとで労働を強要するのではなく、民主主義の徹底と社会生産過程の協同的な管理が必要不可欠です。労働する諸個人の普遍性が、その全体的な疎外において資本の力として発動する転倒を止揚することが、真にグローバルな課題だと主張されています。 資本主義の全体性を前提とした諸機関の孤立的な変更は必ず失敗する、という点も強調されており、システム全体の変革の必要性が示唆されています。
IV.マルクスの未来社会像と課題
マルクスの未来社会像は、疎外された労働というシステムの矛盾に基づいています。それは、理想論ではなく、労働する諸個人の協同に基づく社会への転換を意味します。大谷禎之介や山本孝則といった研究者も引用され、マルクスの経済学・哲学草稿の労働論が現代資本主義社会の分析に重要な拠り所となります。資本主義の諸機関の孤立的な変化は失敗に終わり、全体的な転換が不可欠であると結論づけています。
1. マルクスの未来社会像 疎外された労働からの解放
この節では、マルクスの未来社会像が、疎外された労働という資本主義システムの根本的な矛盾に基づいていると説明されています。マルクスの未来社会観は、対象に外在的な理想論ではなく、疎外された労働というシステムの発生点における本質的な矛盾に立脚した、現実的な展望であると強調されています。大谷禎之介のマルクスのアソシエーション論に触れながら、マルクスの未来社会像が、単なる空想ではなく、資本主義の内部矛盾から必然的に導き出される結論であることが示唆されています。マルクスの人類史把握は、矛盾としての現在を中心とし、本源的統一としての過去と媒介的統一としての未来という三段階論に基づいており、この三段階論が労働という概念と密接に関連していることが述べられています。資本主義的生産の主要な事実として、マルクスが資本論第三部第十五章で挙げている生産手段の集積と社会化された労働の組織化は、この未来社会への移行過程における重要な要素として捉えられています。これは、対立的な形態で私的所有と私的労働を廃棄するプロセスを示唆しています。
2. 未来社会への移行 労働者の団結と課題
この節では、未来社会への移行における労働者の役割と課題が論じられています。グローバル化の進展に伴い、労働する諸個人の普遍的な団結の重要性がますます高まっていると指摘されており、これは現在の排外主義の横行とは対照的なものです。マルクスの経済学・哲学草稿の労働論を、資本主義批判の拠り所として引用し、山本孝則の現代資本主義社会の対立軸としての環境問題への言及もなされています。 未来社会は、人間そのものを原理とするシステムへの巨大変換を必然化するものとして描かれており、対象世界を人間が自己に有機化する運動が、搾取を伴う生産のための生産から解放されることを示唆しています。 しかし、この移行は容易ではなく、資本主義の全体性を前提とした諸機関の孤立的な変更は必ず失敗するとされています。真のグローバルな課題として、民主主義の徹底、社会生産過程の協同的な管理、そして労働する諸個人の普遍性を発動させることが挙げられています。これは、労働する諸個人の全体的な疎外において資本の力として発動する転倒を止揚することを意味しています。
3. 未来社会の実現可能性と新たな課題
この節では、未来社会の実現可能性と、その実現に際して生じる新たな課題が検討されています。マルクスの未来社会像は、原生的ゲマインシャフトの自然の楽園への回帰ではなく、世界史的な人間としての、全体的に発展した個人のための前進であると位置付けられています。資本主義システムの矛盾を克服し、真に諸個人が自由に結ばれる世界への転換が、根源的な課題として提示されています。 この未来社会の実現には、超国籍企業の社会的責任を問うこと、そして企業という現実的な社会的労働組織において、自由な諸個人としての社会的承認を実現することが不可欠です。資本によって成立した現実としての公共空間や、物象、そして資本主義の無政府的な運動に発展をゆだねるシステムの有限性なども、考慮すべき重要な要素として挙げられています。 これらの課題を克服することで、人間そのものを原理とするシステムへの巨大変換が実現すると考えられています。
