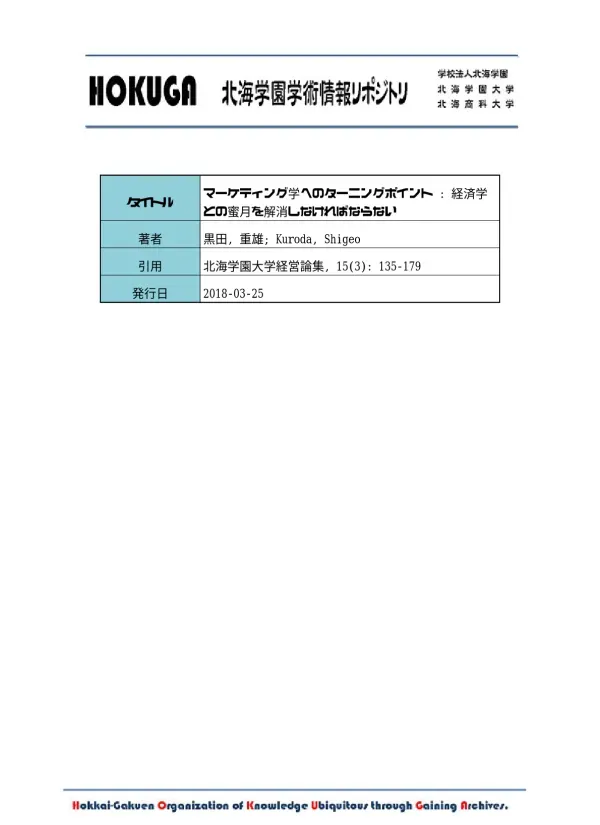
マーケティング学の転換点:経済学との決別
文書情報
| 著者 | 黒田 重雄 |
| 専攻 | マーケティング学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.43 MB |
概要
I.マーケティングと経済学 その本質と課題
本稿は、マーケティングと経済学の関連性、特に日本経済とアメリカ経済における違いを、新古典派経済学などの理論を踏まえながら考察しています。消費者行動や組織行動の違い、CSR(企業の社会的責任)やCSV(共有価値の創出)といった概念も取り上げ、市場経済における公正取引の重要性も指摘しています。特に、アダム・スミスの『国富論』やフィリップ・コトラーのマーケティング理論への言及が頻繁に見られます。日本のグループ行動重視とアメリカの個人主義的な傾向の違い、そして、経済人(ホモ・エコノミクス)モデルの限界が議論の中心となっています。
1. マーケティングの本質と消費者行動
文書の冒頭では、消費者の購買行動を促すには、消費者の感情(エモーション)に訴える「良さ」を追求し、消費者自身も気づいていなかったニーズを創造する必要があると主張されています。これは、経済の拡大再生産にはマーケティングが不可欠だという強い自信に基づいています。単に客観的な商品の優位性を示すだけでは不十分であり、主観的な価値、つまり消費者の感情に響く訴求が重要であると強調されています。 顧客が商品の良さを理解できない限り、購買意欲は生まれないという点が、マーケティングの出発点として示されています。 このマーケティングの展開は、単なる商品販売を超え、新たなニーズの創造へと進展してきた歴史が示唆されています。
2. マーケティングと経済学の接点 40年の考察
著者は、40年以上にわたってマーケティングと経済学の関係性を研究してきた経験から、両者の関係性の重要性を改めて強調しています。当初はマーケティングと経済学の関係について論文を執筆していましたが、近年になって改めてその関係性を深く考えるようになったと述べています。そのきっかけは、世界的に有名なマーケティング研究者であるフィリップ・コトラーの存在であり、コトラーとの対談を通じて、改めてマーケティングと経済学の関係性を深く考察するに至った経緯が示されています。マーケティングが経済学の一部であり、経済理論の質を高めるものであるという強い信念が述べられています。
3. 経済学における市場概念と限界 商人の不在
主流派経済学では市場概念が重視されていますが、その市場概念の限界が指摘されています。具体的には、アダム・スミスの『国富論』では商人システムが中心的に記述されているにもかかわらず、主流派経済学では商人が存在していない、という問題点が挙げられています。これは、経済学における抽象化の過程で、歴史的にも現実的にも重要な要素が多くの場合無視されてしまっているためであると分析されています。また、主流派経済学が個人行動に焦点を当て、組織行動を無視している点も批判されています。経済現象を理解する上で、人間の心理や感情といった要素を考慮することが重要であるという主張が、新古典派経済学への批判を通して示されています。特に、アダム・スミスが『国富論』で繰り返し強調していた、論理的整合性のみを基準とした経済制度は、多様な人間の性向と矛盾するという点を、著者は重要視しています。
4. マーケティングの学問としての体系化可能性
マーケティングを学問として体系化できるかどうかが問われています。著者は長年大学でマーケティング関連科目を担当してきた経験から、マーケティングが学問として確立されることを望んでいると述べています。しかしながら、現状では、マーケティング研究は未だ説得力のある体系性を持ち得ていないと指摘し、その理由として、実務重視の傾向や、ケーススタディ中心の教育方法が挙げられます。 マーケティング理論は、マーケティング活動の成果を予測する試みがなされる場合のみ成立するとし、マーケティング科学の進歩は予測の検証を通して行われると説明しています。 この予測可能性を重視する視点は、マーケティングを科学として捉える上で重要な要素となっています。しかしながら、その体系化には、独自の概念、定義、体系化、方法論などが一体化された明確な枠組みが必要であると指摘しています。
5. 日本とアメリカの経済システムとマーケティング 相違点
日本とアメリカの経済システムの違いが、マーケティングの文脈において議論されています。具体的には、日本のグループ行動重視、ものづくりへの強み、人的資本の重視と、アメリカの個人行動中心、市場重視のシステムの対比です。 アメリカ社会におけるアングロサクソン(AS)プロテスタント(WASP)の要素や、カルヴィニズムの影響などが、アメリカの経済システムや文化を理解する上で重要な要素として挙げられています。日本の伝統的な社会構造や文化と、アメリカの開拓精神や個人主義的な文化との対比が、それぞれの経済システムとマーケティング戦略の違いを理解する鍵であると示唆されています。アメリカにおける寄付文化の事例や、日本とアメリカの競争観念の違いなども、両国の文化的差異を浮き彫りにする例として挙げられています。
II.日本とアメリカの経済システムの違い
日本とアメリカ経済システムの比較では、日本のグループ行動重視、ものづくりへの強み、人的資本の重視といった特徴が、アメリカの個人行動中心、市場重視のシステムと対比されています。この違いは、歴史的、文化的背景、特に宗教の影響(例えば、アメリカのカルヴィニズム)に由来すると分析されています。アメリカの土地の広大さと人口の少なさ、日本の土地の狭小さと人口の多さが、それぞれ異なる経済システムを生み出した要因として挙げられています。
1. 日本経済の特徴 グループ行動と人的資本
本文では、日本の経済システムは欧米とは異なる特徴を持つと指摘しています。具体的には、個人ではなくグループ行動に依存する傾向が強く、「ものづくり」に比較優位性があり、人的資本が重視される点が挙げられています。これらの特徴が、どのような社会文化的条件の下で成立したのかを、宗教の変化とその経済行動へのインパクトという視点から分析する必要があると示唆されています。日本経済の特質は、単に経済的な要因だけでなく、社会構造や文化、そして宗教といった多様な要因が複雑に絡み合っていることを示しています。この分析は、日本経済の独自性を理解する上で重要な視点を提供しています。
2. アメリカ経済の特徴 個人主義と市場メカニズム
対照的に、アメリカ経済は、個人行動を重視する傾向が強いとされています。広大な国土と比較的少ない人口という地理的条件が、個人主義的な文化と市場メカニズムの発達を促したと考えられます。アメリカ企業の成長、統合、多角化は市場の変化によって推進されており、市場への適応が組織構造や経営戦略に大きく影響を与えていることが示唆されています。集権的職能別組織から事業部制への移行といった企業構造の変化は、市場のダイナミズムに対応する戦略として理解できます。 また、アメリカ社会におけるアングロサクソン・プロテスタント(WASP)という白人エリート層の存在や、カルヴィニズムの影響も、アメリカ経済の特色を理解する上で重要な要素として言及されています。
3. 日米経済システムの違い 社会構造と国民感情
日本とアメリカはどちらも混合経済体制を採用していますが、国民感情や社会の底流には大きな違いがあると指摘されています。日本はグループ行動を重視する傾向があり、欧米、特にアメリカは個人を単位とした社会構造を持つと対比されています。この違いは、例えば、罪を犯した若者の責任の取り方や、大学における教授の選抜基準などに顕著に表れると例示されています。著者は、自身の欧米での生活経験から、日米の社会構造と国民感情に違いがあることを実感していると述べています。 この違いは、マーケティング戦略やビジネスにおける倫理観にも影響を与えていると考えることができます。グローバル企業は、それぞれの国の社会構造や国民感情を理解した上で、適切な戦略を展開する必要があることを示唆しています。
4. 地理的条件と経済システムの相違
日本の土地の狭小さと人口の多さ、そして長年にわたる文化の発展は、新たな開発と古い慣習の共存という特異な状況を生み出しています。この状況は、アメリカのような広大な土地と少ない人口を持つ国とは大きく異なる点であり、アメリカ的なマーケティングの考え方をそのまま日本に適用することができない理由として挙げられています。アメリカでは無人地帯に新しい経営形態や組織を設立していくことが容易にできるのに対し、日本においては、既存の組織や慣習との調整が不可欠である点を指摘しています。 これは、日本におけるマーケティング戦略を考える上で重要な制約条件となっています。
III.マーケティングの体系化と学問としての位置づけ
本稿は、マーケティングを学問として体系化できるかという問いに焦点を当てています。マーケティング理論の現状と課題を分析し、予測可能性とマーケティング科学の進歩を結びつけて議論を進めています。大学におけるマーケティング関連科目の現状や、実務重視の傾向、ケーススタディ中心の教育方法なども批判的に検討されています。また、フィリップ・コトラーのマーケティング研究への評価も多角的に考察されています。
1. マーケティングの学問としての位置づけ 体系化の可能性と課題
この文章では、マーケティングを学問(discipline)として体系化できるかどうかが主要なテーマとして扱われています。著者は長年、大学や大学院でマーケティング関連科目を担当してきた経験から、マーケティングが学問として確立されることを望んでいると述べています。しかし、現状のマーケティング研究は、未だ説得力のある体系性を持ち得ていないと指摘しています。 マーケティング理論は、マーケティング活動の成果を予測する試みがなされる場合のみ成立するとし、マーケティング科学の進歩は予測の検証を通して行われると説明しています。この予測可能性を重視する視点は、マーケティングを科学として捉える上で重要な要素となっています。しかし、現状では、そのような体系的な研究は不十分であるという問題意識が示されています。そのため、独自の概念、定義、体系化、方法論などを統合した明確な枠組みが必要であると結論づけています。
2. マーケティング教育の現状と課題 実務重視とケーススタディ
大学や大学院におけるマーケティング教育の現状についても批判的な視点が示されています。講義する側には理論性よりも実務性が重んじられるというプレッシャーがあり、ケーススタディ中心の教育が主流となっています。学生には、ケースごとに成功するための結論を述べる事が求められ、教える側には正解がなくても良いとされる傾向があるとのことです。これはアメリカのビジネススクールのスタイルを踏襲したものではありますが、いくら過去のケーススタディをこなしても、新しい時代や環境に対応できるわけではないという反省が示されています。 この現状は、マーケティングの体系化を阻害する要因の一つとして考えられます。より体系的で理論的な教育が求められていると示唆されています。
3. フィリップ コトラーのマーケティング研究への評価
世界的に有名なマーケティング研究者であるフィリップ・コトラーの研究についても言及されています。コトラーの研究は多様な評価を受けており、「マネジメントの一環である」「マーケティング戦略論の大家に過ぎない」といった意見がある一方、マーケティングを体系化する可能性への期待もあったと述べられています。著者は、コトラーの著書を読む限り、マーケティングを自立的な学問に高めることに関心はないのではないかという見方を示しつつも、彼の学問遍歴から体系化への期待も抱いていたと述べています。このコトラーへの評価は、マーケティングの学問としての体系化というテーマと密接に関連しています。コトラー自身はマーケティングを経済学の一部と捉えているという点も重要な要素です。
4. 商業研究の変遷とマーケティングの学問化への展望
かつて商業研究は「商業なるものの形態」に焦点を当てていましたが、現在は「取引企業」といった本質的な形態をとらえる努力が行われていると述べられています。商学を中心とした学問体系を構築し、大学学部を設立しようとする動きもあると説明されています。 この歴史的背景を踏まえると、マーケティングの学問としての体系化は、商業研究の進化の次の段階として捉えることができます。 マーケティングが学問として確立されるためには、学問としての厳密性、独自の概念や方法論の構築、そして予測可能性に基づく体系的な研究が不可欠であるという結論が示唆されています。
IV.経済学における商人の役割と市場概念
主流派経済学における市場概念の限界が指摘されています。特に、商人の存在の欠如や組織行動の無視が、経済学の現状の課題として挙げられています。アダム・スミスの『国富論』において商人が中心的な役割を果たしていたことと対比することで、現代経済学における盲点を浮き彫りにしています。公正な取引過程や競争のルール、公正な価格の形成といった観点が重要視されています。
1. 主流派経済学における商人の不在と市場概念の限界
本文では、主流派経済学における大きな問題点として、社会を動かす原動力であるはずの「商人」が存在していない点を指摘しています。これは、塩沢らによって以前から指摘されていた問題です。アダム・スミスの『国富論』が商人を中心とした商システムの記述で満ちていることと対比することで、現代経済学における商人の役割の軽視が批判されています。主流派経済学は、市場概念を重視し、需要と供給のバランスによって価格が決まるメカニズムを分析の中心に据えているため、商人の複雑な活動や組織行動を十分に捉えきれていないと批判されています。 この市場中心の経済学は、歴史的にも現実的にも重要な要素を無視しているため、将来予測やイノベーションの方向性について語る可能性を狭めていると主張されています。
2. アダム スミスと経済学の原点 道徳感情論と国富論
アダム・スミスは、『道徳感情論』で人間性の社会的本質を明らかにしようとしており、その思想は『国富論』にも反映されています。『国富論』において、アダム・スミスは、論理的整合性のみを基準とした経済制度は、多様で個性的な人間のもつ基本的性向と矛盾することを繰り返し強調しています。 このことは、現代経済学が、人間の複雑な心理や感情を無視し、単純化された「経済人」(ホモ・エコノミクス) モデルに依存していることを批判する上で重要な根拠となっています。 アダム・スミスは重商主義を批判し、レッセフェールを支持しましたが、需要の法則を説明する際に個人の効用を中心に据え、商人を無視して一般人を理論化の対象とした点も、現代経済学の限界を理解する上で重要な視点となっています。
3. 新古典派経済学とホモ エコノミクス その限界
新古典派経済学は、経済人(ホモ・エコノミクス)を想定しており、効用を最大化する合理的な行動をとると仮定しています。しかし、このモデルは、人間の複雑な心理や感情、そして組織行動といった要素を無視しているため、現実の経済現象を十分に説明できないと批判されています。 例えば、新古典派経済学では、握り寿司を選ぶ際に、経済人は常にトロやタイを選ぶと仮定しますが、これは現実の人間の行動とは必ずしも一致しません。人間の多様な選好や、状況に合わせた柔軟な意思決定を考慮していない点が、このモデルの限界です。 この経済人モデルは、アメリカ人の消費行動と一致すると説明されていますが、それは、アメリカ社会の特殊な状況を反映したものであり、普遍的なモデルではないと解釈できます。
4. 市場における公正性と競争 取引過程の重要性
本文では、市場メカニズムを分析する上で、「取引過程の公正性」に着目する重要性が強調されています。公正な取引過程から形成された価格が公正な価格であり、市場は競争の上に成り立つとされています。しかし、競争はルールなしでは行えないため、それぞれの市場に設定されたルールを完全に守って行われた取引が競争上公正であると定義されています。さらに、競争上公正な取引を通じて形成され、競争上公正な収引によって利用可能な利潤機会を残さない状態が競争上公正な均衡であると定義されています。 この定義では、競争上公正な価格と効率性価格は必ずしも一致しないという重要な点も示されています。 これは、市場の効率性だけでなく、公正性も考慮する必要があることを示唆しています。
V.CSRと企業の社会的責任
企業の社会的責任(CSR)について、日本企業における不祥事や、CSR活動の現状、マイケル・ポーターの提唱するCSV(共有価値の創出)といった概念が議論されています。CSRの目的、企業とステークホルダーの関係、倫理的な経営といった問題が取り上げられ、特に、ステークホルダーとの良好なコミュニケーションの重要性が強調されています。石田梅岩の思想なども参考に、CSRの本質的な問いが提起されています。
1. CSRの定義と現状 企業の社会的責任の高まり
企業の活動領域拡大に伴い、社会への影響力が強まる中、企業の社会的責任(CSR)への関心が国内外で高まっています。企業側も環境問題への対応やCSR担当部門の設置など、CSR活動を積極的に推進する動きが広がっています。しかし、CSRの定義は曖昧で、各企業のCSR報告書に記載されている内容が、その企業にとってのCSRと言える程度です。 この文章では、CSRの定義や現状を説明するだけでなく、その本質的な問いを提起しています。 単にCSR活動を行う方法論ではなく、「なぜCSRに取り組むのか」という問いの重要性を強調しています。多くの日本企業の不祥事が、組織を守るために起こっている現状を踏まえ、現状維持的な姿勢ではなく、倫理的な経営への転換が求められていると示唆しています。
2. CSRとCSV 持続可能な競争優位性へのアプローチ
従来のCSRは、企業が社会に対して社会的価値を提供するという一方通行的な考え方でしたが、持続可能なCSRを実現するには、社会と企業との間で価値が共有され、社会だけでなく企業も利益を得る必要があるとされています。 この考え方は、マイケル・ポーター氏(ハーバード大学教授)が提唱するCSV(共有価値の創出:Creating Shared Value)という概念に近いです。CSVは、企業が持続可能な競争上のポジションを築くための新たなアプローチとして提示されています。CSRには様々な捉え方や側面がありますが、この文章では、日本企業と社会の新たな関係のあり方を模索するという視点が示されています。 企業は、社会から必要とされる存在でありたいという思いから、自社の社会における存在意義を位置づける姿勢を持つべきであると主張されています。
3. 倫理的な経営とCSR 石田梅岩の思想からの考察
倫理的な経営とは何かという問いに対して、経営学者の日野健太氏(2006)の「石田梅岩とCSR」という論説が紹介されています。石田梅岩の精神から、ひたむきに実直にビジネスに取り組み、それが人の心を磨くようなビジネスをすることが、倫理的な経営であると解釈されています。 これは、CSR活動の方法論ではなく、「なぜCSRに取り組むのか」という本質的な問いに答える必要があります。企業人にとってCSRは単なる世渡り術ではなく、ステークホルダーとの関係性や独自の哲学を反映したものとすべきであると強調されています。多くの日本企業の不祥事が所属組織を守るために起こっていることを指摘し、現状維持的な姿勢を批判しています。
