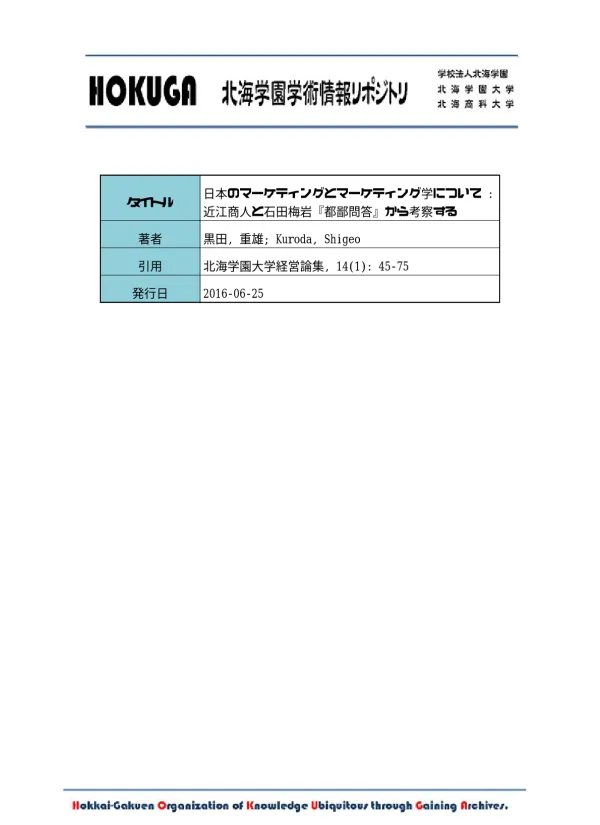
マーケティング学入門:近江商人から考察
文書情報
| 著者 | 黒田 重雄 |
| 専攻 | マーケティング学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 701.64 KB |
概要
I.日本のマーケティング 後進国論と倫理経営
本稿は、2014年のワールドマーケティングサミットを踏まえ、日本のマーケティングにおける課題と方向性を考察する。コトラー教授の厳しい日本企業評や、マーケティング後進国論が議論された点を指摘。大学におけるマーケティング教育についても、現実問題解決に役立つ実践的知識と、原理原則に基づく体系的理解の両立が求められると論じている。さらに、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)の提唱する倫理経営の重要性、JAL再建における稲盛和夫氏の「正しいこととは何か」への問いかけ、ドラッカーのマーケテイング定義(仕事の創造とイノベーション)も紹介。経済学、社会学、法学等の多角的視点からの理論構築が必要性を強調している。
1. マーケティングサミットと日本企業への批判
2014年のワールドマーケティングサミットにおける議論が紹介されている。朝日新聞編集委員である多賀谷克彦氏がサミットの感想を新聞コラムに寄稿したことが記されている。コラムでは、フィリップ・コトラー教授による日本企業への厳しい評価が取り上げられ、日本がマーケティング後進国であるかどうかの議論が展開されたとされている。この議論は、日本のマーケティングの実態と課題を浮き彫りにしている。特に、コトラー教授の具体的な批判内容や、サミット参加者による反論、意見の相違などは、日本のマーケティングの現状を理解する上で重要なポイントとなる。この部分の記述からは、日本のマーケティングが国際的な水準に達していないという認識が、少なくともサミット参加者の一部にはあったことが伺える。
2. 大学におけるマーケティング教育の課題
サミットでの議論を受けて、日本の大学におけるマーケティング教育の在り方が問われている。企業からの要望として、現実の問題解決に役立つ実践的な知識の提供が求められる一方で、原理原則に基づいた体系的な理解の必要性も指摘されている。現状のマーケティング教育がこれらの要請を十分に満たせていないという批判がなされている。具体的には、企業が求める実践的なスキルと、学問としての体系的な理解、この両方をバランスよく提供する教育方法の模索が課題となっている。この問題は、大学におけるマーケティング教育のカリキュラム設計や授業内容、教授法の見直しを迫る重要な論点である。また、企業と大学間の連携強化も必要不可欠となるだろう。
3. 倫理経営の重要性とJAL再建の事例
2014年に出版されたハーバード・ビジネス・スクールの教授3人による書籍が引用され、多国籍企業を中心に、戦略一辺倒の経営から道徳を重視した倫理経営への転換が求められていることが示されている。これは、企業の社会的責任(CSR)の高まりや、倫理的な経営の重要性の認識の高まりを反映している。同時に、JALの再建に成功した稲盛和夫氏の事例が紹介されている。稲盛氏は、アメリカのコンサルタント会社を全て断り、独自の経営手法でJALの再建に取り組んだ。その手法は、社員一人ひとりに「正しいこととは何か」「人は何を望んでいるか」を問い続けることであった。この事例は、倫理経営の具体的な実践例として示唆に富むものである。稲盛氏の経営哲学、そしてその成果は、現代企業の経営戦略を考える上で重要な示唆を与える。
4. ドラッカーのマーケティング定義と理論構築の必要性
ピーター・ドラッカーのマーケティングに関する考え方が紹介されている。ドラッカーは、マーケティングを「自己の仕事を決めて実行し、絶えず新しくする(イノベーションする)こと」と定義している。これは、マーケティングを単なる販売活動ではなく、事業全体を創造し、継続的に発展させるための活動と捉えていることを示している。さらに、この文章では、経済学、社会学、法学などの多様な学問分野からの視点を取り入れ、問題解決型ではなく大陸型理論の構築が必要だと主張している。これは、コトラーの経済学的なアプローチとは異なる、より包括的なマーケティング理論の必要性を示唆している。特に、独自の概念に基づく体系化や、各種理論の比較分析を行うための分析方法の選定が重要視されている。
II.近江商人と日本の経済発展
日本の経済発展における近江商人の役割を分析。未知の市場へ果敢に挑戦し、市場調査と売り込みを両立させた彼らの活動は、日本の流通機構の形成に大きく貢献した。三方よしの理念や、徹底した顧客重視、独自の流通網構築といった近江商人の経営哲学は、現代のマーケティングにおいても学ぶべき点が多い。具体的には、京都、江戸、大阪に店舗網を展開した三井越後屋の事例が紹介されている。彼らの高い士気と、地域情報への精通、全国各地への出店戦略が、日本の経済発展を支えたと主張されている。
1. 近江商人の積極的な市場開拓
近江商人は、日本国内においても全く未知の地域へ積極的に進出し、商売を行っていたことが強調されている。行商を通じて、需要と供給の状況、地域情報を迅速に把握し、販路を開拓、全国各地に出店・支店を設立していった。これは、現代のマーケティングにおける市場調査や販路拡大戦略の先駆けと言える活動である。彼らが独自に築き上げた流通網や、情報収集能力、そしてリスクを負ってでも新たな市場に飛び込む大胆さは、日本の経済発展に大きく貢献したと評価されている。特に、情報収集能力の高さは、現代の高度な情報社会においても重要視されるべき点である。
2. 三井越後屋と日本の流通機構
18世紀前半の三井越後屋は、京都、江戸、大阪に計9店舗を展開し、京都で仕入れ・加工を行い、江戸・大阪で販売する高度な流通システムを構築していた。これは、生産地と消費地を繋ぐ効率的な流通網の原型であり、日本の流通機構の特性(長い流通経路、帳合法など)の形成に大きな影響を与えたと考えられる。越後屋は、3地域で1020人の従業員を雇用しており、手代、子供、下男といった階層構造と、詳細な職階制度が存在した。この組織構造は、近江商人の組織運営能力の高さを示す重要な証拠である。17歳で入社した者は約10年で平手代の筆頭となり、その後さらに30年かけて元〆に昇進するなど、明確なキャリアパスが設けられていたことがわかる。
3. 近江商人の経営哲学 三方よし
近江商人の行動規範は、「他国へ行商するも、全て我事のみと思わず、其国一切の人を大切にし、私利を貪ること勿れ、神仏のことは常に忘れる様なすべからず」と簡潔に要約されている。この規範は、近江商人研究者である小倉栄一郎氏によって「三方よし」(売り手よし、買い手よし、世間よし)という表現でまとめられている。この「三方よし」は、近江商人の倫理的な経営姿勢を示す重要なキーワードである。近江商人の成功は、単なる経済活動の成果だけでなく、顧客、地域社会との良好な関係構築によって支えられたことを示唆している。現代企業にとっても、この「三方よし」の精神は、持続可能な経営を実現する上で重要な指針となるだろう。
III.中世日本の職人制度と経済
中世日本の職人制度と経済活動の関連性を考察。鎌倉時代から室町時代にかけて、職人集団である「座」の形成とその役割、西国と東国における職人制度の違いなどが分析されている。職能と結びついた権利「職」の重要性、給田による生活保障、そして南北朝時代以降の職人・商人の職業区分明確化、細分化などが論じられている。信長・秀吉時代の楽市楽座政策が、経済発展に与えた影響についても触れられている。
1. 中世における 職人 概念の多様性
現代では「職人」といえば手工業者を指すのが一般的だが、中世日本ではその意味合いが異なっていた。鎌倉時代から室町時代にかけて、「職人」は在庁官人や下級荘官なども含む広範な意味で使われていた。手工業者や芸能民なども「職人」と呼ばれたのは、彼らが職能と結びついた利益の源泉となる権利「職」を有していたためである。中世前期には、手工業者の仕事が少なく、職能だけでは生活できないため、雇う側が給田を提供することで生活を保障していた。これは、技能を持つ者と、彼らを雇用する者との関係を示しており、単なる雇用関係を超えた、一種のパトロンシップ的な関係が見て取れる。
2. 西国と東国における職人制度の違い
中世前期の西国と東国では、職人制度に大きな違いがあった。西国には職人を抱える権門が多く、職人も畿内を中心に集中していたため、「座」と呼ばれる職人組織も発達した。西国の「座」は、加入年数を序列の基盤とし、職業の独占をはかっていたが、内部的には平等な権利が保障されていたケースが多い。一方、東国では主従制的な関係が強く、西国のような平等な「座」は発達しなかった。さらに、西国では職人に対する差別意識が強かったのに対し、東国ではそれが弱かった。このように、西国と東国では、職人と武士との関係性にも違いが見られた。地域性によって、職人の地位や役割、社会構造が大きく異なっていたことがわかる。
3. 南北朝時代以降の職人制度の変化と経済活動
鎌倉時代の職人は、身分としては確立していたものの、職業の細分化は進んでいなかった。鋳物師が自身の製品だけでなく布や絹、穀物なども交易し、生計を給田にも依存していたことが例として挙げられている。多くの職人が各地を遍歴しながら活動していた。しかし、南北朝時代以降になると、商人、職人、芸能人といった職業上の区分が明確になり、職業の細分化が進んだ。これは、経済活動の高度化と社会分業の進展を示す重要な変化である。室町時代には、職人の作ったものの物々交換や商人による遠距離交易が活発化し、宋や元からの唐人、朝鮮からの高麗人が交易に参加していた。信長・秀吉による楽市楽座政策によって、この流れはさらに加速したとされている。
IV.現代の消費者問題と企業対応
近年増加する消費者被害の問題点を提起。製品の性能・安全問題、不要品輸出による環境問題(ガーナへの電機製品輸出・投棄)、オレオレ詐欺などの高齢者向け詐欺、SNS関連の相談増加などを例に挙げ、企業の消費者対応の重要性を強調。新製品開発への取り組みの必要性、悪徳企業への批判を展開している。国民生活センターへの相談増加も問題視されている。
1. 増加する消費者被害と消費者問題の定義
近年、製品の性能や安全に問題があり、消費者が健康被害を受けたり、不必要な商品を購入させられたりする消費者被害が増加している現状が指摘されている。 商品やサービスが生産者から消費者へ供給され、消費される過程で発生するあらゆるトラブルを「消費者問題」と定義している。これは、単なる製品不良にとどまらず、消費者の権利や安全を守る上で、企業の責任が問われる重要な問題であることを示唆している。この問題の深刻さを示す具体的な事例として、不要になった電化製品がアフリカのガーナに違法に輸出され、環境汚染を引き起こしているという問題も挙げられている。また、高齢者に対するオレオレ詐欺や、若者に対するSNS関連のトラブルも増加傾向にあるとされている。
2. 企業の責任と新製品開発の重要性
消費者問題への対応として、企業は新製品開発に積極的に取り組むべきであると主張されている。単に既存製品の陳腐化で市場に対応しようとする企業は、悪徳企業に過ぎないと批判的に論じている。これは、市場の変化や消費者のニーズを的確に捉え、それに対応する製品やサービスを提供する企業姿勢の重要性を強調している。高齢者に対するオレオレ詐欺や、若者に対するSNS関連のトラブル増加といった、新たな消費者問題への対応策についても検討が必要となるだろう。国民生活センターへの相談件数の増加は、消費者問題の深刻さを示す指標であり、企業はこれらの問題を真剣に受け止め、対策を講じる必要があると示唆している。
V.石田梅岩と 都鄙問答 商人の道徳と経済
江戸時代中期の思想家、石田梅岩の『都鄙問答』を分析。士農工商の意義を論じ、商人の利益追求の正当性を強調しつつ、道徳と経済の調和を説いている。倹約と正直を重視する一方で、流通サービスへの報酬としての商業利潤を肯定。その思想は、現代の倫理経営やCSRにも通じる部分があると指摘されている。ただし、彼の主張は、当時一般的な仏教的思考法に儒教・神道の要素が加えられたもので、革新的なものではないとする見解も示されている。
1. 石田梅岩と 都鄙問答 の概要
江戸時代中期、石門心学の創始者として知られる石田梅岩が著した『都鄙問答』(1739年)が紹介されている。この書物において、梅岩は商人の存在意義を力説し、「商人皆農工となれば財宝を通ずる者なくして万民の難儀と成らん」と述べている。さらに、「売利を得るは商人の道なり、元銀に売を道という事を聞かず」と、商業利潤を明確に肯定している。ただし、その利益追求は「正直」を基盤とすべきと強調し、道徳的な側面も重視している点が注目される。この記述からは、梅岩が当時の社会における商人の役割を肯定的に捉え、その経済活動を倫理的に正当化しようとしていたことが読み取れる。
2. 都鄙問答 における商人の道徳と経済の調和
『都鄙問答』では、封建社会の儒教倫理に沿って、士農工商それぞれの社会的意義が論じられている。梅岩は、経済と道徳の一致を説き、商人にも流通における役割の価値を見出し、利益追求の正当性を強調している。同時に、社会的に認められる利益概念にも言及している点が重要である。これは、単なる経済活動ではなく、社会貢献という側面も考慮した上で、商人の活動を肯定的に評価しようとしていることを示している。当時の社会構造の中で、商人の地位向上や社会的地位の確立を目指していた可能性も示唆されている。 この思想は、現代のCSR(企業の社会的責任)や倫理経営に通じるものがあると解釈できる。
3. 梅岩の思想と当時の社会状況 および現代への示唆
梅岩が一般的に学者として認められていない理由として、当時の学問状況が挙げられている。忠孝を重んじる朱子学や国学が主流だった当時、独学の梅岩は自身の主張を既存の学問用語を用いて表現せざるを得なかった。これは、梅岩の思想が、当時の社会状況や学問体系の中でどのように位置付けられていたかを示している。 また、彼の主張は、倹約と正直という消極的な職業規範を守り、家業としての商売の組織防衛を強調した側面も持ち合わせている。一方で、社会秩序を人間の内面から理解するという仏教的な思考法に基づいていると指摘されている。彼の思想が、現代の倫理経営や、社会における経済活動の在り方を考える上で、様々な示唆を与えてくれることがわかる。
VI.日本の経済と仏教の影響
日本の経済発展の基盤を、個人主義と求道主義の融合に求める分析が紹介されている。鎌倉新仏教における易行化が、知の活用方法としての求道主義をもたらし、それが日本人の経済行動の特質を形成したという仮説が提示されている。天台本覚思想や法然の教えが、職人のものづくりへの熱意に影響を与えたと論じている。山崎正和の「柔らかい個人主義」の概念も関連付けている。
1. 日本の経済力と個人主義 求道主義
日本の経済力の基盤は、自己実現・自己表現を目指す個人主義にあるとされている。しかし、これは西洋的な個人主義とは異なり、他者との競争による排除ではなく、共通の目標や価値観を共有する集団の中で、自己実現と自己表現を追求する「柔らかい個人主義」であると説明されている。個人が他者から独立した行動を重視するのではなく、同じ道を志す仲間との協調性を重んじる点が強調されている。この集団主義的な側面は、日本の経済活動における独特の協調性や、競争と協調のバランス感覚を理解する上で重要な要素となる。この集団的な側面は、企業文化や組織運営にも反映されていると考えられる。
2. 仏教の求道主義と日本の経済行動
日本の経済行動の特質の基礎を、仏教における求道主義がなしたという仮説が提示されている。具体的には、鎌倉新仏教における修行の易行化が、仏教の修行に代わる知の活用方法として求道主義をもたらし、それが日本人の経済行動の特質の基礎をなしたと主張されている。天台本覚思想や法然の教えが、難しい修行を必要としないとしたことが、日本の職人がものづくりに没頭することで求道を行うようになった要因の一つとして挙げられている。また、山崎正和のいう「柔らかい個人主義」も、この文脈で理解されるべきであるとされている。これは、日本の経済発展に、仏教思想が潜在的に大きな影響を与えてきた可能性を示唆している。
VII.マーケティング教育の現状と課題
アメリカのマーケティング教育の現状を批判的に検討。ケーススタディ中心の教育方法の問題点を指摘し、実践的知識と体系的理解のバランス、そして変化する時代への対応力の必要性を主張している。過去の事例のみに頼る教育の限界、新しい時代や環境への対応ができないという点を批判している。
1. 戦後日本のマーケティング教育 アメリカ中心の現状
第二次世界大戦後、ドラッカーを筆頭とする第一次経営学ブームが起こり、マーケティングも盛んに導入された。しかし、昭和30年代以降の日本のマーケティング教育は、コトラーを始めとするアメリカ流のマーケティング理論の受容中心であり、翻訳・研究・講義が中心であったと指摘されている。 これは、アメリカ中心の視点からのみマーケティングを理解している現状を示しており、日本の独自の状況や文化を考慮したマーケティング理論の構築が不足していることを示唆している。特に、ケーススタディ中心の教育方法が批判されており、考えるプロセスよりも、性急な結論を求める傾向があるとされている。これは、アメリカ式ビジネススクールの講義スタイルをそのまま踏襲した結果であると分析されている。
2. ケーススタディ中心の教育方法の問題点
アメリカ式ビジネススクールの講義スタイルであるケーススタディ中心の教育方法の問題点が指摘されている。ケーススタディでは、学生はそれぞれのケースに対して、どうすれば成功するかという結論を述べることを求められるため、考えるプロセスそのものよりも、結果や結論を重視する傾向にある。教える側も、正解を提示するよりも、学生の思考プロセスを重視する傾向にある。しかしながら、いくら過去のケーススタディをこなしても、企業が直面する新しい時代や環境に対応できるわけではないという反省や批判の声も上がっている。これは、変化の激しい現代社会において、柔軟な思考力と問題解決能力を養うための教育方法を見直す必要性を示唆している。
3. 理想的なマーケティング教育の方向性
企業からの要望に応えるためには、現実問題の解決に役立つ実践的な知識の提供が重要となる。しかし、同時に、原理原則に基づいた体系的な理解も不可欠であるとされている。現状のマーケティング教育はこの両方のバランスがとれておらず、改善が必要とされている。具体的な改善策としては、経済学、社会学、法学など、多様な学問分野の視点を取り入れた体系的な理論構築が重要とされている。また、問題解決型のアプローチだけでなく、独自の概念に基づいた理論形成を行う必要性も指摘されている。これは、日本の社会・経済状況に特化した独自のマーケティング理論を構築する必要性を示唆している。
