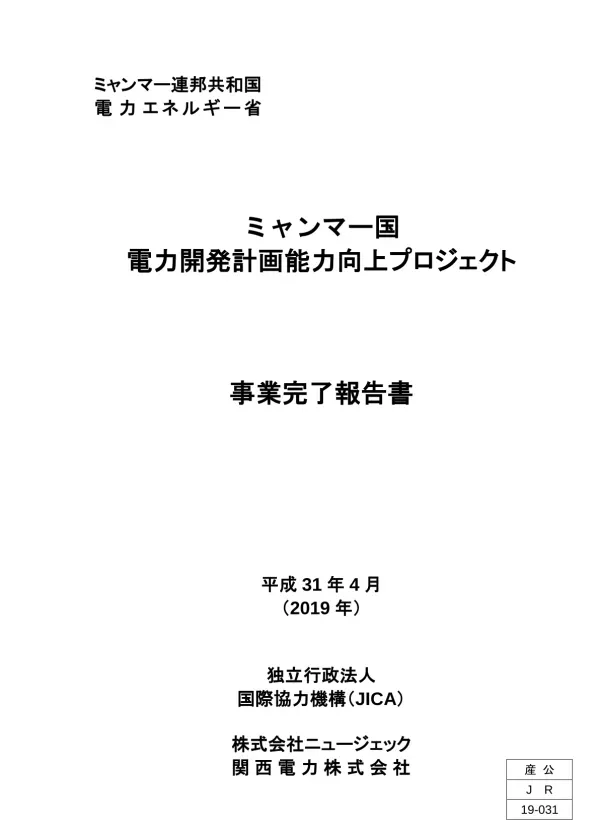
ミャンマー電力開発計画:事業完了報告書
文書情報
| 著者 | 独立行政法人国際協力機構 (JICA) |
| 会社 | 株式会社ニュージェック関西電力株式会社 |
| 文書タイプ | 事業完了報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.94 MB |
概要
I.ミャンマー電力セクター開発計画における技術協力プロジェクト
本報告書は、JICAによるミャンマー電力エネルギー省(MOEE)への技術協力プロジェクト「ミャンマー電力セクター計画策定能力強化」の成果をまとめたものです。プロジェクトの主要目標は、MOEEの電力開発計画策定・運用能力の向上、特に国家エネルギーマスタープラン(NEMP)の立案・更新・活用能力の強化です。このNEMPは、ミャンマーの持続可能な開発計画(MSDP)に沿った、環境・社会配慮を考慮した長期的な電力開発計画です。プロジェクトでは、電力需要予測、電源開発計画、電力系統計画、経済財務分析、環境社会配慮、データ管理といった分野において、カウンターパート職員への技術移転と能力開発を実施しました。特に再生可能エネルギーの導入や、老朽化した水力発電所の改修といった短期対策も検討されています。
1. プロジェクトの背景と目的
2013年、ミャンマー政府は急増する電力需要に対応するため、国家エネルギー管理委員会(NEMC)を設立し、国家エネルギー政策を策定しました。この政策では、長期電源開発計画(NEMP)の策定と定期的な見直し、電力エネルギー省(MOEE)職員の能力強化が謳われています。2013年の最大電力需要は約2,000MWに達し、乾季の需給バランスは既存水力発電所の老朽化とガス燃料生産量の減少により不安定な状況にありました。年率10%以上の電力需要増加が見込まれる中、ミャンマー政府は電力セクターを国家開発の最重点分野と位置づけ、停電解消と電力需給バランス改善を目指しています。こうした状況を踏まえ、MOEEの自律的な長期計画立案・更新を支援するため、2016年3月に協議議事録(R/D)が締結され、本技術協力プロジェクトが開始されました。プロジェクトの目的は、MOEE職員のNEMP立案・更新・活用能力の強化、ひいてはミャンマーの電力セクターの持続可能な発展に貢献することにあります。電力需要の増加、電化率の低さ(2013年時点で約33.4%)、そしてエネルギー安全保障の強化が、このプロジェクトの重要な背景となっています。
2. プロジェクト成果 NEMP関連組織体制整備と制度化の試み
プロジェクトの成果の一つとして、NEMPの立案・更新・活用に関するMOEEの組織体制整備が挙げられます。2017年8月には、NEMPの定期的な更新のための制度的枠組みを提案するRegulation(案)が策定され、第6回、第7回ワークショップ(WS)で関係者への説明が行われ、理解が深まりました。しかし、このRegulation(案)の電力エネルギー省内での承認手続き、閣議了解、そして法制化は、未だ実現していません。これは、プロジェクトの成功にとって重要な課題となっています。また、NEMP策定の実施体制としては、延べ35名のカウンターパート(C/P)が配置され、計画通りの活動が実施されました。データベースの構築と管理体制の整備も進められ、2019年1月には必要なデータが全て収められたデータベースと、その運用マニュアルが完成しました。これらの成果は、NEMPの継続的な更新と活用に不可欠な基盤となります。 しかし、法整備の遅れが、プロジェクトの長期的な持続可能性に影響を与えている点が懸念材料です。
3. プロジェクト成果 技術移転と能力向上
プロジェクトでは、NEMP策定に必要な知識・技術の移転を2年間かけて実施しました。2019年1月には、第12次派遣により技術移転は完了しました。プロジェクトマネジャーをリーダーとするNEMP・WG(ワーキンググループ)が設立され、NEMPの取りまとめ作業を行い、その成果は第10回WSで発表されました。各WG(電力需要予測、電源開発計画、経済財務分析、環境社会配慮、データ管理)において、ベースライン調査と比較したモニタリング調査を実施した結果、カウンターパート職員の能力は大きく向上しました。特に2年目には、プロジェクトリストの作成やWASP(電力系統計画ソフト)の入力・分析を独自で行うなど、自立的な活動が確認されています。 経済財務分析WGでは、エクセルを使った演習や自主的な復習を通して、高い学習意欲と能力向上が見られました。一方、環境社会配慮WGは、他のWGと比較して基礎知識・経験の少ないメンバーが多く、能力向上に課題が残っています。全体として、技術移転目標を達成したカウンターパートも多く、能力向上の成果は明確に示されています。
4. プロジェクトの持続可能性と課題
プロジェクトの上位目標達成の見通しは、カウンターパートの約半数が困難または不明と回答しており、NEMPの法制化方針が不明確なことが原因と分析されています。ミャンマー政府は、国内の地域紛争・民族紛争といった不安定要因を考慮し、NEMPの公表と法制化に消極的な姿勢を示しています。しかし、MOEE職員はNEMPの継続的な立案・更新に積極的な姿勢を示しており、技術・知識の維持と活用は期待できます。プロジェクトの持続可能性を高めるためには、NEMPの早期公表、Regulationの法制化、データベースの継続的な更新、そしてMOEE内部の意思決定システムの改善(上意下達システムからの脱却)が不可欠です。 さらに、省庁間の連携強化のため、NEMCのような委員会の設置も提案されています。日本からの技術支援、特に経済産業省(METI)によるエネルギー政策の説明や、J-Power磯子火力発電所等の視察研修が、ミャンマー側の能力向上に大きく貢献しました。
II.NEMP立案 更新における組織体制と制度整備
プロジェクトでは、NEMPの立案・更新を制度的に支えるための**規則(案)**を策定し、MOEE関係者への説明と理解促進を行いました。しかし、この規則の法制化にはMOEE内部の承認手続き、閣議了解が必要であり、現状では遅れています。そのため、NEMPの公表と法制化は、民間投資促進と電力セクターの透明性向上に繋がる重要な課題として残されています。 延べ35名のカウンターパート(C/P)がプロジェクトに関与し、データベースの構築と管理体制の整備も進められました。
1. NEMP関連規則の策定と課題
本プロジェクトでは、NEMP(国家エネルギーマスタープラン)の立案・更新・活用を円滑に進めるための組織体制整備を目的として、2017年8月にRegulation(案)を策定しました。このRegulation(案)は、NEMPを定期的に更新するための制度的枠組みを提案するもので、第9次、第10次派遣において開催されたワークショップ(WS)でワーキンググループ(WG)メンバーに説明され、その内容と必要性についての理解が深まりました。日本側は計画通りに活動を実施しましたが、ミャンマー側は、Regulation(案)の電力エネルギー省内での承認手続きや閣議了解、さらには法制化といった、制度化に向けた具体的な行動は取っていません。このRegulation(案)の法制化は、NEMPの継続的な更新と効果的な活用に不可欠であり、今後の大きな課題となっています。法制化が遅れることで、NEMPの公表も遅れ、国民への政策理解促進や民間投資誘致にも影響を及ぼす可能性があります。 そのため、ミャンマー政府の承認を得てNEMPを早期に公表することが、電力セクターの政策明確化と民間投資促進に繋がると考えられます。
2. NEMPに必要な情報 データの収集 管理体制の整備
NEMPの策定・更新には、必要な情報・データの収集・管理体制の整備が不可欠です。本プロジェクトでは、各WGにおいてNEMPの見直しに必要なデータの収集を行い、データベースとして整備を進めました。2019年1月には、電力需要予測、電源開発計画、電力系統計画、経済財務分析、環境社会配慮、データ管理といった、NEMP策定に必要な全ての分野のデータベース構築が完了し、同時にデータベースの管理・運用マニュアルも整備されました。このデータベースは、NEMPの立案・更新・活用に不可欠な情報源となるだけでなく、様々な電力セクター開発事業の検討にも役立つ貴重な資産となります。2019年1月に行われた第10回WSでは、データ管理レポートが発表され、組織体制への助言も行われました。 しかし、データベースの継続的な更新と正確なデータ管理は、NEMPの有効性を維持するために不可欠であり、今後の継続的な取り組みが求められます。
3. 組織体制と意思決定システムにおける課題
プロジェクト期間中、延べ35名のカウンターパート(C/P)が配置され、NEMP策定のための体制は整えられました。しかしながら、電力エネルギー省の組織体制と意思決定システムには課題が見られます。具体的には、上意下達型の意思決定システムが、職員レベルでの検討や分析に基づく計画の議論を阻害している可能性があります。これは、プロジェクトで確認された職員のNEMP立案・更新への積極的な姿勢と、実際に行動に移せない現状とのギャップを生み出している要因の一つと考えられます。 より質の高いNEMPを策定し、持続可能な電力開発計画を実現するためには、MOEE内部の組織活性化と意思決定プロセスの改善が不可欠です。ボトムアップ型の仕組みを取り入れるなど、職員の意見を反映しやすい組織風土の醸成が求められます。また、定期的なNEMPの立案・更新には、Regulationの法制化による制度的なプロセス確立が重要であり、早急な対応が求められます。
III.技術移転と能力向上
2年間の技術移転活動を通じて、カウンターパート職員の技術・知識は大きく向上しました。特に、電力需要予測WG、電源開発計画WG、経済財務分析WG、環境社会配慮WGにおいて、WASPやPSSEといったソフトウェアの活用を含め、実務能力の向上が確認されています。しかし、MOEE内部の上意下達型の意思決定システムが、職員の積極性を阻害する要因となっています。そのため、ボトムアップ型の仕組み導入も検討課題となっています。
1. 技術移転の内容と実施期間
本プロジェクトでは、ミャンマー電力エネルギー省(MOEE)職員に対し、NEMP(国家エネルギーマスタープラン)の立案・更新・活用に必要な技術と知識の移転を2年間かけて実施しました。技術移転は、電力需要予測、電源開発計画、電力系統計画、経済財務分析、環境社会配慮、データ管理の6つのワーキンググループ(WG)でそれぞれ行われ、2019年1月の第12次派遣をもって終了しました。技術移転は、講義や演習、そして日本人専門家との協働作業を通して行われ、各分野に必要な基礎知識、技術、シミュレーション解析手法などが習得されました。特に2年目には、ミャンマー側のカウンターパート(C/P)が専門家の支援を受けつつ、独力でNEMPの立案作業を実施することで、実践的な能力向上を目指しました。この段階的なアプローチは、着実に必要な技術や知識を習得させる上で有効であることが示されました。 また、技術移転効果の見える化を図るため、各分野の技術移転終了時点においてワークショップ(WS)を開催し、WGメンバーによる成果発表を実施しました。これは、技術移転の進捗状況を明確に示し、関係者間の理解を深める上で有効な手法でした。
2. 各WGにおける技術移転効果のモニタリング
プロジェクトでは、各WGにおける技術移転効果をモニタリングするために、アンケート調査やインタビュー調査を実施しました。モニタリング調査の結果は、ベースライン調査(2016年11月)と比較することで、2年間の技術移転効果を定量的に評価することを可能にしました。 電力需要WGでは、ベースライン時の平均能力レベル1.9から3.7程度にまで向上し、特に2年目にはプロジェクトリストの作成やWASP(電力系統計画ソフト)の入力・分析を独力で実施できるようになったことで能力向上が確認されました。電源開発計画WGも同様に能力向上が見られ、経済財務分析WGでは、高い学習意欲と能力向上を示す結果が得られました。一方、環境社会配慮WGは、他のWGと比較して初期レベルが低かったものの、リーダー・サブリーダーを中心に能力向上に努めました。これらの結果から、2年間の技術移転活動が、カウンターパート職員の能力向上に大きく貢献したことが明らかになりました。 ただし、各WGの進捗状況は異なっており、個々の能力向上レベルのばらつきも存在します。
3. 技術移転方法とスケジュール管理に関する教訓
技術移転を2つの段階に分けて実施したことは、着実に必要な技術や知識を習得させる上で非常に有効でした。しかし、プロジェクト期間が限られている中で、カウンターパートの作業進捗状況に影響を受けやすく、スケジュール管理が難しいという課題も浮き彫りになりました。時間制限を課すことでスケジュールを管理しましたが、理想的には、カウンターパートの業務進捗状況を考慮し、余裕のある行程を配分することが望ましいと考えられます。 また、異なる組織の職員が集まり協働で作業を行うWGの構成は、情報交換の少ない組織間の相互理解促進に役立ちました。さらに、技術移転終了時点でWSを開催し、WGメンバーによる成果発表を行う手法は、技術移転効果の見える化を図る上で有効でした。 今後の技術移転においては、カウンターパートの作業進捗状況を綿密に把握し、柔軟なスケジュール管理と継続的な支援体制の構築が重要となります。
IV.プロジェクトの持続可能性
プロジェクトの持続可能性は中程度と評価されています。これは、MOEE幹部のNEMP公表への消極的な姿勢と、法制化の遅れに起因します。国内情勢の不安定さも、長期的な電力開発計画策定の障害となっています。一方で、カウンターパート職員はNEMPの継続的な立案・更新に積極的な姿勢を示しており、技術・知識の維持と活用が期待されます。将来的には、NEMCのような省庁横断的な委員会設置も検討すべきです。日本の経済産業省(METI)やJ-Power等の視察研修も実施され、日本のエネルギー政策や技術に関する知識習得に貢献しました。
1. プロジェクト成果の評価と持続可能性
プロジェクトの成果は、大きく分けて3つの成果(NEMP関連組織体制整備、情報・データ収集管理体制整備、職員の技術能力向上)に分類されます。これらの成果は、プロジェクト目標である「電力エネルギー省の電力開発計画策定・運用能力向上」の達成に大きく貢献しました。特に、2年目にはミャンマー側のカウンターパートが独自にNEMP更新作業を実施し、NEMP策定のためのワーキンググループ(WG)が更新版を発表するなど、自立的な活動が確認され、能力向上が図られました。しかしながら、プロジェクトの上位目標達成の見通しについては、半数のカウンターパートが困難または不明と回答しており、その原因として電力エネルギー省のNEMP立案・更新作業に関する法令化方針の不明確さが挙げられています。 電力エネルギー省幹部は、国内の地域紛争や民族紛争などの不安定要因から、長期的な電力開発計画が利害対立を生む可能性を懸念しており、NEMPの立案・公表・法制化に消極的な姿勢を示しています。このため、プロジェクトの持続可能性は中程度と評価されています。
2. MOEE職員のNEMPに対する姿勢と持続可能性
電力エネルギー省の職員は、本プロジェクトを通じた技術協力によってNEMP立案・更新能力を向上させ、十分な実務能力を有するようになりました。さらに、NEMPの継続的な立案・更新に対して非常に積極的な姿勢を示しており、この点はプロジェクトの持続可能性に繋がる高いポテンシャルを示しています。 しかし、この積極的な姿勢は、上意下達型の組織意思決定システムの中では十分に活かされていない可能性があります。職員レベルの検討や分析に基づく計画が組織内で議論されにくい現状は、職員の積極性を阻害する要因となっていると考えられます。そのため、将来的な持続可能性を高めるためには、組織内部の意思決定システムの改善、具体的にはボトムアップ型の仕組みの導入などを検討する必要があります。 また、NEMPの継続的な立案・更新には、関連規則の法制化が不可欠であり、早期実現が求められます。
3. NEMP継続のための助言と今後のモニタリング
ミャンマー側への助言として、NEMPの立案・更新・活用を継続すべき理由が示されています。NEMPは、国家の持続的発展を目指すミャンマー持続可能な開発計画(MSDP)に沿ったエネルギー政策を推進する上で不可欠であり、安定した電力供給が国民の長期的な利益に繋がるためです。 また、電力エネルギー省は、NEMPを可能な限り早期に政府の承認を得て公表すべきです。NEMPの公表は、電力セクターにおける優先政策の明確化、国民への政策理解促進、そして国内外からの投資誘致につながると考えられます。さらに、再生可能エネルギーや省エネルギーの推進を含め、エネルギー電力政策の計画実施のためには、省庁間を俯瞰できるNEMCのような委員会を設置することも提案されています。 プロジェクト終了後も、電力エネルギー省はNEMPの立案・更新・活用を継続し、作成されたマニュアルを活用しながら、必要に応じて更新を行う必要があります。 そして、JICAミャンマー事務所への年度末報告を通じて、プロジェクトの成果と課題が継続的にモニタリングされます。
V.教訓と今後の課題
技術移転の段階的実施は有効でしたが、カウンターパートの業務進捗状況に影響を受けやすいため、スケジュール管理の難しさも浮き彫りになりました。より質の高いNEMP策定のためには、MOEE幹部と職員が共通の目標とスケジュールで活動することが重要であり、そのためには組織体制の改善が不可欠です。NEMPの早期公表は、国民への政策理解促進、民間投資誘致、そして電力セクターの持続的な発展に貢献します。
1. 技術移転方法に関する教訓
本プロジェクトでは、技術移転を2つの段階に分けて実施しました。1年目は専門家チームが中心となり、同時にカウンターパート(C/P)への技術移転を行いました。2年目は、C/Pが専門家の支援を受けつつ、独力でNEMP立案作業を実施しました。この段階的なアプローチは、C/Pが着実に必要な技術や知識を習得する上で非常に有効でした。しかし、プロジェクト期間が限られているため、C/Pの作業進捗状況の影響を受けやすく、スケジュール管理が困難になるという課題も浮き彫りになりました。時間制限を設けることでスケジュール管理は可能でしたが、理想的には、C/Pの業務進捗状況を考慮し、余裕のある行程を組むことが望ましいです。 異なる組織の職員が集まるWGの構成は、情報交換の少ない組織間の相互理解促進に役立ち、各分野の技術移転終了時点でのWS開催と成果発表は、技術移転効果の見える化に有効でした。 これらの経験から、今後の技術移転では、柔軟なスケジュール管理と継続的な支援体制の構築が重要であることが示唆されます。
2. 組織体制と意思決定システムの課題と改善策
より質の高いNEMP策定のためには、電力エネルギー省幹部とスタッフが共通の目標とスケジュールを持って活動することが必要です。しかし、電力エネルギー省内の業務は上意下達システムであり、職員レベルでの検討・分析に基づく計画が組織内で議論されにくい体制となっています。これは、職員の積極性を十分に活かせていない要因の一つです。そのため、場合によっては、下達上意(ボトムアップ)の仕組みも導入すべきです。これは組織の活性化に寄与し、ひいては一般職員の能力向上にも繋がると考えられます。 また、NEMPの公表は、電力エネルギー省の優先政策を明確化し、民間投資を促進する効果が期待できます。しかし、NEMP公表には、地域紛争やステークホルダー間の利害対立といったリスクも伴います。これらのリスクを最小限に抑えるため、問題となる可能性のあるプロジェクト名を伏せるなどの工夫も必要です。 今後の課題として、組織体制の改善と意思決定プロセスの透明性向上、そしてNEMPの早期公表と法制化が挙げられます。
3. 今後のNEMP立案 更新に向けた提言
NEMPを定期的に立案・更新するためには、Regulationの法制化が制度的プロセスの確立という点で不可欠です。電力エネルギー省職員の能力向上、技術の維持のためにも、NEMPの立案・更新・活用を継続することが重要です。 データベースの更新は、NEMPの立案・更新・活用に不可欠なだけでなく、様々な電力セクター開発事業の検討にも役立ちます。 NEMPは、国家の持続的発展を目指すMSDPに沿ったエネルギー政策を推進する上で不可欠であり、安定した電力供給はミャンマー国民の長期的な利益に繋がります。 再生可能エネルギーや省エネルギーの推進を含め、エネルギー電力政策を効果的に推進するためには、省庁間を俯瞰できるNEMCのような委員会を設置することも有効な手段と考えられます。 これらの教訓と課題を踏まえ、将来的なNEMPの質を高め、ミャンマーの電力セクターを持続的に発展させるための取り組みが求められます。
