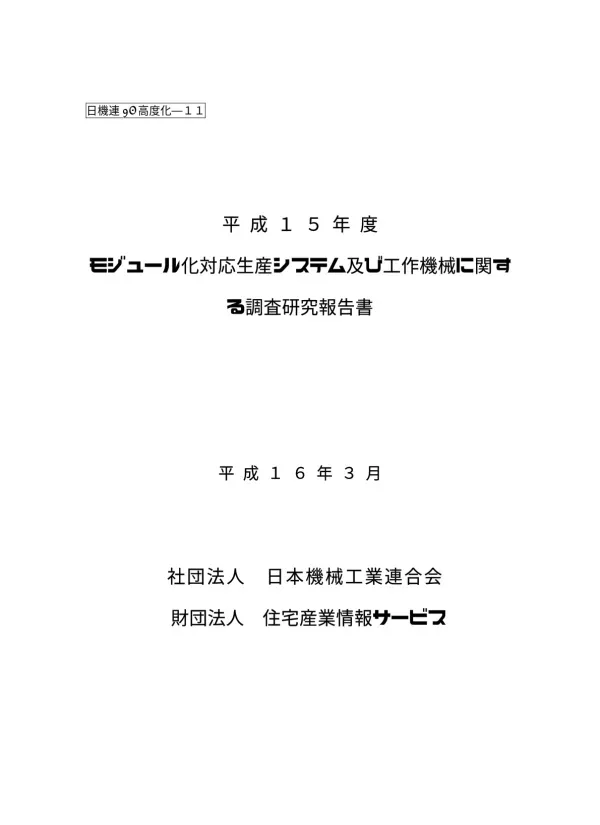
モジュール化生産システムと工作機械
文書情報
| 著者 | 財団法人住宅産業情報サービス |
| 専攻 | 機械工学 |
| 出版年 | 2003 |
| 会社 | 社団法人日本機械工業連合会 |
| 文書タイプ | 調査研究報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.59 MB |
概要
I.日本の住宅産業におけるモジュール化対応生産システムの現状と課題
本調査報告書は、日本の機械工業におけるモジュール化対応生産システムと高度な工作機械の開発に関する研究成果である。特に、住宅産業に着目し、既存の生産システムにおける非効率性を解決するための技術開発を目的としている。現状、日本の住宅建設は多様な工法や部材規格が存在し、標準化、共通化が遅れているため、コスト削減や高品質化が困難な状況にある。特に、大手ハウスメーカーは多様な商品に対応するために膨大な数の部品を保有し、維持管理コストが課題となっている。そのため、モジュール化による部品の共通化、生産工程の効率化が急務である。
1. 日本の住宅産業におけるモジュール化の遅れと課題
日本の住宅産業は、自動車産業等と比較してモジュール化対応生産システムの導入が遅れている現状にある。これは、多様な工法(木質軸組み工法、2×4工法など)や製品規格、さらにメートルモジュールと尺モジュールの寸法基準の違いといった、業界特有の複雑な要因が絡み合っているためである。ハウスメーカー各社は、消費者の多様なニーズに対応するため、多種多様な住宅を生産しているが、その結果、部品点数やバリエーションが膨大になり、保守・アフターフォローのための設計図書、生産設備、治工具、保守用部品在庫等の維持管理コストが大幅に増加している。 特に、住宅は巨大な生産物であり、大量生産に向いていないこと、高価で大型の生産機械の導入が困難であることも、モジュール化を阻む要因となっている。これらの課題を解決するためには、業界全体の標準化・共通化を進め、生産システムの効率化、コスト削減、高品質化を実現することが不可欠である。
2. 住宅生産におけるコスト高騰と非効率性の問題点
近年の新築住宅着工数の減少により、ハウスメーカー各社は販売競争が激化しており、コスト削減の圧力にさらされている。 既存の生産システムでは、多様な部品の調達、複雑な生産工程、膨大な在庫管理などがコスト高騰と非効率性の大きな原因となっている。 特に、大手ハウスメーカーは、数十万棟以上の竣工済み住宅を抱えており、長期的な保守サービス提供のため、膨大な数の部品を維持管理する必要があり、これは大きなコスト負担となっている。 さらに、環境問題、エネルギー問題、高齢化社会といった社会課題への対応も迫られており、新しい機能を備えた部材・部品の開発と、それらを用いた新商品開発が頻繁に行われている。これらの状況が、さらに部品点数の増加とコスト高騰を招いている。 これらの問題を解決するには、モジュール化による部品の共通化、生産工程の合理化、在庫管理の効率化が不可欠である。
3. モジュール化対応生産システム導入の阻害要因
住宅分野におけるモジュール化対応生産システムの導入を阻む要因として、以下の点が挙げられる。まず、ハウスメーカー、ビルダー、工務店など、各社の工法や製品規格が大きく異なるため、共通化が困難である。 住宅は、自動車などとは異なり、巨大で複雑な構造を有しており、大量生産に適した製品とは言い難い。 また、住宅生産に必要な機械設備は、高価で大型であるため、導入コストが非常に高く、中小企業にとっては大きな負担となる。さらに、住宅の主要部位である躯体は、各社のオリジナリティが強く反映されているため、共通化が難しいという課題もある。これらの要因により、モジュール化を前提とした生産システムの構築が遅れている現状がある。しかし、日本の住宅業界全体を視野に入れ、新たなビジネスモデルを構築することを目指すことで、モジュール化の可能性は高まるだろう。
II.住宅部材のモジュール化に向けた取り組み
本研究では、住宅の主要部位である構造材(基礎、柱、壁)のモジュール化を検討し、ハイドロフォーミング加工技術などの高度な工作機械を活用した効率的な生産システムの構築を目指す。 既存の木質軸組み工法や2x4工法といった工法の違い、メートルモジュールと尺モジュールの寸法基準の違いなども考慮し、ハウスメーカー間のOEM生産や部品の共通化による協業の可能性を探る。サッシの標準化事例(社団法人日本サッシ協会)を参考に、住宅部材の標準化・モジュール化のステップ(仕様の層別・標準化、部位・ユニットの標準化、モジュール化)を踏まえた具体的な方策を検討する。 経済産業省や日本自転車振興会、社団法人日本機械工業連合会の協力を得て、この課題に取り組んだ。
1. 住宅部材のモジュール化の現状と課題
日本の住宅産業においては、住宅部材のモジュール化が遅れている。その原因として、ハウスメーカー各社における工法や製品規格の多様性が挙げられる。例えば、木質軸組み工法や2×4工法など、複数の工法が存在し、それぞれの工法で使用する部材や寸法が異なるため、共通化が困難になっている。さらに、住宅の寸法基準として、メートルモジュールと尺モジュールが併用されていることも、標準化を複雑にしている要因の一つである。 ハウスメーカー自身で部材を内製している場合や、建材メーカーから汎用品を調達する場合、個別仕様の特注品を開発購買する場合など、調達方法も多様である。そのため、部材の共通化を進めるためには、これらの相違点を克服し、標準化・共通化を図っていく必要がある。社団法人日本サッシ協会によるサッシの標準化事例は、こうした標準化の取り組みの一例と言えるが、他の部材についても同様の取り組みが求められる。
2. 部材共通化 標準化に向けたアプローチ
工業製品の標準化・モジュール化は、一般的に①仕様の層別・標準化、②部位、ユニットの標準化、③モジュール化というステップで進められる。しかし、住宅部材の場合、複数の企業が関与するため、各社の独自の仕組みや仕様の違いを考慮する必要がある。 住宅の主要部位である躯体は、各社とも企画・開発・設計・製造を一貫して行っているため、共通化は部分的なものにならざるを得ない。しかし、検討範囲を工業化住宅業界内に限定せず、日本の住宅業界全体へと広げ、新たなビジネスモデルの構築を目指すことで、共通化・標準化の可能性は高まる。 IBMのSystem/360シリーズやIBM PC/ATの事例に見られるように、モジュール化は、企業間分業を促進し、競争力を高める効果がある。IT業界の発展もモジュール化の活用によるところが大きく、SCM(サプライチェーンマネジメント)などの技術進歩も、他社との連携を容易にしている。
3. 住宅部材共通化とOEMビジネスの可能性
住宅部材の共通化・標準化を進めることで、ハウスメーカー各社間のOEMビジネスの可能性も高まる。電子機器業界を参考に、住宅部材の共通化・標準化と新たなビジネスモデルの可能性について検討する。 現状、ハウスメーカー各社は、新製品の企画・開発、販売、展示場運営など、多様な機能を有し、量産効果を追求した事業構造をとっている。しかし、部材の共通化・標準化を進めることで、生産効率の向上、コスト削減、高品質化を実現できる可能性がある。 その結果、ハウスメーカー間での部品の共通化や生産委託が促進され、新たなビジネスモデルが構築されることが期待される。 この研究では、躯体とその他の部位(外装・内装・設備)を接続するアタッチメントの標準化・モジュール化が、ハウスメーカーが主体的に取り組める課題であるという結論に至った。
III.新しい生産機械の概念設計と要素技術
現状の住宅生産における生産設備や工程(例:鉄骨ユニット工法)を調査し、モジュール化に対応した新しい生産機械の概念設計と要素技術を検討した。自動化された組立ライン、高精度な溶接技術、省資源・省エネルギー技術などを活用し、複雑な形状の構造材を効率的に生産できる工作機械の開発を目指す。具体的には、ハイドロフォーミング加工技術を応用することで、部品点数の削減とコスト低減、高強度化を図る可能性を探る。
1. 現状の住宅生産設備と工程の調査
モジュール化対応生産システム構築のため、まずは現状のハウスメーカーにおける生産設備と生産工程の調査を行った。特に、工業化が進んでいる鉄骨ユニット工法の組立工場を視察し、その生産工程を詳細に分析した。鉄骨ユニット工法では、約30工程を経てユニット構造体が組み立てられ、断熱材の組み込みなども組立ライン上で行われる流れ作業となっている。屋根、床、壁などのフレームを6面体に組み合わせる工程では、鉄骨の切断から溶接まで工作ロボットによる自動化が進んでおり、1mm単位の精度で、1個のユニットを約3分で組み立てている。この調査結果を基に、モジュール化に対応した新たな組立機械、金型、溶接機械などの高度化・複合化を図るための検討を進めた。自動車業界の事例なども参考に、効率的な生産システムの構築を目指した。
2. モジュール化に対応した新しい生産機械の概念設計
現状の生産設備と工程の調査結果を踏まえ、モジュール化に対応した新しい生産設備、生産機械の概念設計と要素技術の抽出を行った。 具体的には、鉄骨ユニット工法のような高度な自動化ラインを参考に、住宅構造材の生産工程における効率化を目指した。 複雑な形状の構造材を効率よく生産するために、鍛造技術やコンピュータ技術を組み合わせた高度な工作機械の開発が必要となる。数回の工程で切断、プレス、鍛造、ドリル締付け、接合などの複雑な加工を同時に行える機械の開発が目標である。 また、建築現場での施工体制についても検討し、工場での生産比率を高めることで、工期短縮、品質向上、そして天候や騒音への影響軽減を目指す。鉄骨ユニット工法では、全工程の約80%を工場で行うことで、現場での工期を在来工法と比較して約1/3に短縮しているという成功例を参考に、生産機械の設計を進めた。
3. ハイドロフォーミング加工技術の応用可能性
複雑な形状の住宅部材を効率的に生産する技術として、ハイドロフォーミング加工技術の応用可能性についても検討を行った。現在、鉄骨系の工業化住宅では、多くの部材が溶接やボルト締めによって結合されているが、ハイドロフォーミング加工技術を用いることで、複雑な形状の部材を一度に製作できる。この技術は、パイプ状の閉断面構造物に内側から水圧を加えることで加工を行うものであり、従来の板プレス加工と比較して、コストダウンと高強度化が期待できる。自動車産業での活用事例を参考に、住宅部材への応用可能性を検討し、部品点数の削減によるコスト削減効果や、強度向上による住宅性能の向上効果などを分析した。 資源の最大限利用、リサイクル・リユースの容易化、製造工程における排出物削減、エネルギーの有効活用、安全・安心な社会構築への貢献といった、環境面や社会的な側面も考慮しながら技術選定を行った。
IV.ハウスメーカー間の協業と今後の展望
本研究では、ハウスメーカー間の競合から協業への転換を促し、モジュール化による新たなビジネスモデルの構築を目指す。具体的には、躯体とその他の部位を接続するアタッチメントの標準化・モジュール化を推進することで、各社が主体的に取り組める課題を設定する。 社会資本整備審議会の提言(街なか居住、マルチハビテーションなど)も踏まえ、日本の住宅業界全体の活性化に貢献する方策を検討する。 将来的な課題として、住宅の性能表示制度(住宅の品質確保の促進等に関する法律)との整合性も考慮する必要がある。
1. ハウスメーカー間の協業の可能性
本研究では、ハウスメーカー間の競合関係から協業関係への転換を促進し、モジュール化による新たなビジネスモデルの構築を目指す。 これまでハウスメーカーは、それぞれの独自性を重視し、競合関係にあったが、部材の共通化や標準化を進めることで、共同生産やOEM生産といった協業体制を構築できる可能性がある。 具体的には、躯体とその他の部位(外装、内装、設備)を接続するアタッチメントの標準化・モジュール化を推進することで、各社が主体的に取り組める課題を設定し、協業を促進する。 この取り組みは、個々のハウスメーカーの競争力を高めるだけでなく、日本の住宅業界全体の活性化にも繋がる可能性がある。 社会資本整備審議会の提言にある「街なか居住」や「マルチハビテーション」といった多様な居住ニーズに対応するためにも、業界全体の連携が必要不可欠となる。
2. 新たなビジネスモデルの構築に向けた取り組み
住宅部材の共通化・標準化による新たなビジネスモデルの構築に向けて、実現可能性の高いプロジェクトを選定し、実証実験を行う。 具体的には、ハウスメーカー各社間のOEMビジネスの可能性を検討し、効率的な生産システムの構築を目指す。 このためには、各社の工法や製品規格の違いを克服し、標準化・共通化を進める必要がある。 また、住宅の性能表示制度(住宅の品質確保の促進等に関する法律)との整合性を考慮し、法規制を遵守した上で、新たなビジネスモデルを構築する必要がある。 IT業界におけるモジュール化の成功事例(IBMのSystem/360シリーズやPC/AT互換機など)を参考に、住宅業界における企業間分業の促進やサプライチェーンマネジメント(SCM)の活用などを検討する。 これにより、コスト削減、品質向上、リードタイム短縮などの効果が期待される。
3. 今後の課題と展望
今後の課題としては、ハウスメーカー各社間の合意形成と、標準化・共通化に向けた具体的な取り組みの推進が挙げられる。 各社が独自性を維持しながら、共通化を進めるためのバランスのとれた戦略を立案する必要がある。 また、住宅の性能表示制度などの法規制への対応も重要となる。 モジュール化を進めることで、住宅生産の効率化、コスト削減、品質向上、そして多様な消費者のニーズへの対応が可能となる。 さらに、環境問題や高齢化社会への対応といった社会的な課題にも貢献できる可能性がある。 本研究で得られた成果を基に、関係各社と連携し、日本の住宅産業におけるモジュール化対応生産システムの普及促進に貢献していく。
