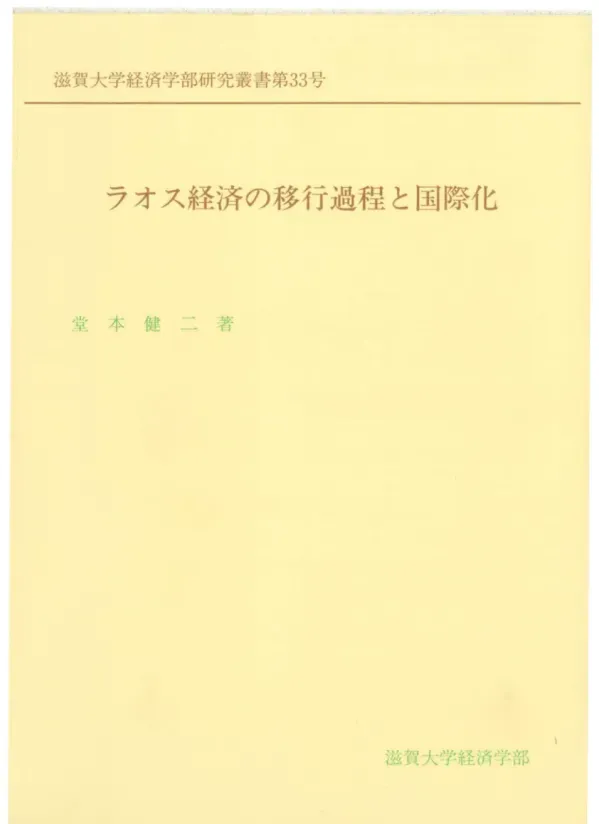
ラオス経済移行:国際化と課題
文書情報
| 著者 | 田原(タハラ) |
| instructor | 村上敦(ムラカミ アツシ) 先生 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 経済学 |
| 場所 | 彦根 |
| 文書タイプ | 研究叢書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.97 MB |
概要
I.インドシナ3国の経済改革と開発課題 特にラオスに焦点を当てて
1980年代後半以降、ベトナム、ラオス、カンボジアは社会主義計画経済から資本主義的市場経済への経済移行を推進しました。旧ソ連からの援助減とASEAN諸国の経済発展が外的要因となり、経済自由化、貿易自由化、外国直接投資導入が積極的に進められました。しかし、マクロ経済の安定化、インフラ整備、人材育成など多くの課題が残されています。特にラオスは内陸国という地理的制約を抱え、援助吸収能力の向上、財政金融の安定化が喫緊の課題です。このレポートでは、ラオスの経済移行過程、経済改革の現状と課題、国際協力の重要性について分析します。特に、AFTA参加による潜在的利益と、その実現に向けた課題、森林保全、電力開発の問題点、そして人材育成の必要性を論じます。
1. インドシナ3国の経済改革 計画経済から市場経済への移行
1980年代半ば以降、ベトナム、ラオス、カンボジアのインドシナ3カ国は、旧西側諸国や国際機関の支援を受け、社会主義的計画経済から資本主義的市場経済への大規模な経済改革に着手しました。これは、財・要素価格の自由化、規制緩和、国営企業の合理化、民間企業育成といった多岐にわたる政策措置を伴いました。同時に、貿易自由化と外国民間投資の導入も積極的に推進されました。これらの改革の成果はマクロ経済面を中心に徐々に現れ始め、ベトナムは1995年、ラオスは1997年にASEANに加盟するなど、国際社会への参画も進みました。特にカンボジアは内戦の影響で遅れをとっていましたが、パリ和平協定後の国際社会の支援を受けて経済復興の道を歩み始めました。ラオスにおいても、70年代末の農業集団化の失敗と国営企業経営の行き詰まりを背景に、経済自由化政策が導入されました。しかし、カンボジアの経済状況は他の2カ国と比べて不安定であり、GDP成長率や物価上昇率の変動が大きくなっています。財政収支や経常収支の赤字は援助流入によって抑えられているものの、財政金融機構の構築は依然として今後の課題となっています。
2. 経済移行を促した外的要因と内在的課題
インドシナ3カ国の経済移行を加速させた外的要因として、80年代後半の旧ソ連からの援助の急速な縮小と、85年プラザ合意以降の通貨調整による日本やNIEsからの東南アジアへの直接投資の急増が挙げられます。これらの変化により、インドシナ諸国は開発資金と技術の不足に直面し、旧東側諸国からの経済支援に頼ることができなくなりました。そのため、貿易・投資・公的援助のチャンネルを旧東側から旧西側へ急速に転換せざるを得ない状況に置かれ、ASEAN諸国、特にタイやマレーシアの急速な経済成長を目の当たりにしたインドシナ3カ国は、経済改革を加速化せざるを得ませんでした。しかし、低開発経済であるインドシナ諸国にとって、経済移行は単なる財政金融政策の見直しだけでは済まず、農業生産性向上やインフラ整備といった生産基盤の抜本的な強化が不可欠でした。94年時点での一人当たり所得はベトナム約200ドル、ラオス約320ドル、カンボジア約270ドルと低く、AFTA参加による自由貿易の利益を享受するためには、制度・組織、そして人材のASEAN化が急務であり、そのギャップは依然として大きいため、多大な調整コストが予想されました。政府部門の人材育成と組織改革、適切なマクロ経済運営が、当面の重要な課題として挙げられています。
3. 国際協力のあり方 連携型援助の重要性と課題
インドシナ3カ国への援助においては、特に農村開発や社会開発分野では、各国の自然条件や文化条件を考慮し、日本を含む先進国がタイやマレーシアなどの周辺国やNIEsと連携した三角支援を進めることが望ましいとされています。東南アジア諸国の産業構造が互いに補完的で、自然条件や文化条件も多様なため、日本単独での効果的な援助は難しいからです。この連携型援助の基本構想は、1993年1月の宮沢元首相のバンコク演説で表明されています。しかし、タイの援助実施能力強化を支援する場合など、タイ側が主導権を握ろうとする傾向があり、援助の効率化という点で課題も存在します。インドシナ3カ国の開発戦略と国際協力は、国際経済環境の変化への積極的な対応と、各国固有の伝統や習慣との摩擦軽減に焦点を当てるべきです。インフラ整備支援は、ラオスをランドブリッジ化することで東南アジア全体の開発水準向上に貢献するものと期待されていますが、財政基盤の強化なくしてはインフラの建設・維持管理は困難です。特にラオスでは、経常支出規模が資本支出規模に比べて相対的に小さく、経常費用負担能力の低さが援助吸収能力の限界となっています。そのため、援助案件のローカルコスト負担には、特別な注意が必要です。
II.ラオスの経済移行 現状と課題
ラオスは70年代末の農業集団化失敗を機に、経済自由化を開始。日本を中心とした外国企業誘致による西太平洋経済圏への参入を目標に、経済改革を推進してきました。しかし、インフラ整備(道路、通信、電力)の遅れ、非貨幣経済・未組織経済の存在、そして人材不足が成長のボトルネックとなっています。国営企業の民営化も課題であり、その進捗状況はベトナムや中国と比較して、雇用問題の悪化は比較的少ないものの、法制度の整備が遅れていることが問題視されています。経常収支赤字は、外国直接投資の流入に依存しており、その安定的な確保が重要です。また、急激な市場経済化に伴う森林面積減少も深刻な問題であり、木材輸出と焼き畑農業が主な原因となっています。
1. ラオス経済移行の本格化 社会主義革命後の転換
1975年の社会主義革命後、ラオスは中央集権的な経済開発を進めていましたが、70年代末には農業集団化の失敗により司令経済運営方式の破綻の兆候が見え始めました。80年代半ば以降本格化した経済の自由化・開放化政策において、ラオス政府は日本を中心とした外国企業の積極的誘致による西太平洋経済圏への参入を重視しました。これは、それまでの東側諸国との経済関係から西側諸国へのシフトを意味するものでした。70年代以降、日本企業を中心とした外国民間投資による工業化が東南アジア諸国の経済発展に大きく貢献した事実を踏まえ、ラオス政府は円高局面での日本企業の進出ラッシュとそれに続く輸出工業化・経済発展を自国経済活性化のモデルと位置付けていました。しかし、この戦略は、市場経済の構築という未成熟な段階における、経済政策の単純な「調整」や「振り子」的アプローチでは不十分であるという問題点を孕んでいました。例えば、道路や通信設備が整備されない状況では、価格自由化の効果は限定的であり、国営企業の民営化も、民間セクターの発達がなければ、外国資本の導入を含め困難を極めます。市場原理に基づく経済開発には、多様な市場形成と経済活動の担い手が不可欠であり、構造調整における市場の歪み是正や政策調整は、新たな生産技術の導入など、多面的な取り組みが求められます。
2. ラオス経済改革の経緯 初期条件と現状
ラオスはインドシナ半島中央部の内陸国で、国土面積は日本の本州とほぼ同じですが、人口密度は低く、経済の集積度も低いのが現状です。全国的な道路網の整備が遅れているため、地域固有の条件を活かした国際貿易や流通サービス、関連軽工業が中心となっています。総人口は1998年時点で約497万人と小さく、内陸国という地理的ハンディに加え、非耐久消費財の国際競争力の高さや、タイ、中国、ベトナムといった周辺国の豊富な未熟練労働力も、ラオスの短期間での工業化を困難にしています。ラオスでは、非効率的な国営・公営企業が政府部門の財政赤字問題を深刻化させているとして、資産売却や賃貸による民営化が進められました。世界銀行の資料によると、80年代末の600件から97年2月末には90件に減少しましたが、民営化に必要な法律や実施規定の未整備、資産評価方法や財務報告様式の不統一などが問題となっています。産業構造は、農業1%、製造業10.5%、サービス業20.7%となっており、外国投資流入が目立つ衣料縫製業(タイからの投資が中心)や電力産業(米国からの投資が中心)は、欧米の輸入規制回避やGSP獲得を狙った生産拠点移転といった側面も持ち合わせています。これらの労働集約型工業が、他の東南アジア諸国のように長期的な所得水準向上や雇用吸収に大きく貢献するとは考えにくいと指摘されています。ラオスは、周辺国と比べて労働人口規模が小さく、国際競争力の強化・維持も容易ではありません。
3. ラオス経済の脆弱性 経常収支とマクロ経済運営
ラオス経済の現状は、経常収支赤字が政府開発援助を大きく上回り、外国資本(直接投資を含む)がそれを補うという構造になっています。IMFの予測でも、2004年まで経常収支赤字の一部を外国民間投資が補うとされています。年間8~9千万ドル規模の無償援助に加え、約2億ドルの外国資金流入が国際収支安定の条件となっています。今後、経済規模の拡大に伴い、外国民間資本と借款への依存度が増すことが予想されますが、マクロ経済の脆弱性を考慮すると、短期資本よりも直接民間投資などの長期資本の導入が重要です。短期資金の安易な導入は、マクロ経済運営を圧迫し、債務負担能力を低下させる可能性があります。木材や電力といった主力分野の輸出の好調と経常収支の安定的な推移は、マクロ経済運営に不可欠です。国内貯蓄動員が進んでいない状況で、財政支出を伴うインフラ整備の推進と輸出の伸び悩みが重なると、経常収支の悪化、激しいインフレ、そして国外への資金逃避が起こり、マクロ経済運営は厳しい局面に陥る可能性があります。GMS計画の実施においても、ラオスのマクロ経済構造の脆弱性を十分に考慮する必要があります。タイ通貨危機の影響により、ラオス・キップの対ドルレートは97年8月と比べて約100%下落し、外貨準備高も深刻な影響を受けました。ラオス経済の将来にとって、経常収支の安定的な推移は不可欠であり、外国投資の安定的な流入を確保するための政策が求められます。
4. ラオスの森林問題 経済発展と環境保全のジレンマ
ラオスにおける森林面積減少の主な原因は、木材輸出と焼き畑農業の拡大です。木材輸出は重要な外貨獲得源であり、木材伐採・販売からのロイヤリティは政府の重要な税収となっています。専門家の意見では、現状では商業目的の伐採が最大の原因とはいえないものの、政府が経済開発資金を木材輸出に依存している限り、森林伐採の抑制は困難です。森林保全を強化するには、他の税収基盤を確立するか、環境保全を制約条件とした最適な経済成長率を実現する必要があります。さらに深刻な問題は、急速な人口増加と平地水稲栽培の生産性伸び悩みによって、中腹地での焼き畑農業が拡大していることです。1992~2000年のラオスの年平均人口増加率は2.9%と、低所得国グループの平均(1.7%)を大きく上回っており、一部の県では6~7%に達しています。平地の食糧生産性は1haあたり2~3トンと低く、灌漑整備や技術普及サービスの不足が原因となっています。ラオス農林省は、森林減少への対応策として、森林資源の再生、木材加工の高付加価値化、焼き畑農民の営農転換などを盛り込んだ部門開発計画を策定していますが、これらの取り組みは始まったばかりであり、効果を評価するには時間がかかります。ラオスの森林資源減少は、急激な市場経済化・国際経済化の中で発生しており、このジレンマを軽減するには、大規模な外国資金・技術の導入、人材確保、そして経常費用の捻出が不可欠です。ラオス側の援助吸収能力が向上しなければ、森林環境問題はさらに深刻化する可能性があります。
III.ラオスのASEAN加盟とAFTA参加
ラオスは1997年7月にASEANに正式加盟。AFTA参加による貿易と投資の潜在的利益は大きいものの、制度・組織・人材の整備が遅れており、調整コストの負担が予想されます。特に、インフラ整備、特に道路網の整備(メコン橋など)が、貿易自由化の恩恵を享受する上で重要です。タイとの経済関係は密接であり、タイはラオス経済の後背地として位置づけられています。しかし、電力開発においては、タイの価格交渉力が強く、ラオス側の開発スケジュールに影響を与えています。電力開発は、ラオスの経済発展とASEANにおける役割強化にとって重要ですが、制度的枠組みの整備、そしてタイとの関係構築が課題です。
1. AFTA参加の意義 潜在的利益と課題
ラオスがAFTAに参加することによる潜在的な経済的利益は、国際貿易と直接投資の拡大です。ただし、国際的なインフラサービスが十分に整備されていない現状では、自由貿易の利益は限定的です。しかし、国際道路網の整備が進めば状況は変わります。既にビエンチャンとタイのノンカイ市を結ぶメコン橋(オーストラリアの無償援助)が完成し、パクセ市にも第2のメコン橋(日本政府の無償援助)が建設中です。さらに、ベトナムとタイを結ぶ複数のルート、そして中国雲南省からカンボジアに至る南北ルートの整備が進むことで、ラオスは国際物流の拠点としての潜在能力を発揮すると期待されます。1997年7月のASEAN正式加盟前後から、周辺国、特にタイとの経済交流が活発化しました。タイは、国内の地域格差是正策として東部・東北部の開発を推進しており、カンボジアとともにラオスを自国経済の後背地と位置づけています。歴史的な確執があるにもかかわらず、貿易や民間直接投資を通じてラオスとの経済関係を強固にしています。韓国、台湾、マレーシア、シンガポールなどの企業もラオスへの進出を加速させています。しかし、ラオスの経済関連制度や組織の整備が遅れていることが、AFTAへのコミットメントを当初の予想よりも遅らせている要因となっています。ラオスは経済地理的に不利な位置にあるものの、国際・地域的な自由貿易制度の枠組みが確立されれば、物流拠点としての可能性を秘めています。効果的な国際インフラ整備のためには、ラオス主導による全国総合開発計画の策定が急務であり、域内の国際分業の変化を考慮した計画が必要です。
2. ラオスの電力開発 現状 制度的枠組み 問題点
ラオスはインドシナ半島のエネルギー供給拠点としての役割が期待されていますが、その実現は容易ではありません。ラオス工業省によると、電力開発有望地は約60カ所あり、1997年までに25カ所の開発が許可されています。政府は中期電力開発戦略の策定、外国援助を活用した案件可能性調査、輸出向け大型案件だけでなく国内供給を目的とした中小規模案件の実施、そして外国民間企業主導案件の精査などを目指しています。しかし、これらの25件の開発案件は、工業省ではなく外国投資管理委員会によって短期間で許可された経緯があり、これはラオス政府が経済の対外開放と規制緩和を急いだ時期と一致しています。多くの案件が許可されたにもかかわらず、建設がほとんど進んでいないという現状は、ラオス政府の制度的・組織的な脆弱性を露呈しています。このことは、ラオスが将来電力供給拠点となりうる可能性があるにもかかわらず、開発スケジュールを遅らせ、潜在的な外国企業のリスクを高めることにもつながっています。電力開発における問題点として、まず援助側の提案内容が現場の実情に合致せず、事前評価や各実施機関の意見が十分に反映されない点が挙げられます。次に、タイとの関係が重要です。タイはラオスの重要な貿易相手、電力輸出先であり、外国投資のパートナーでもあります。タイは、通貨危機後の経済危機にもかかわらず、将来的な工業化による電力輸入需要の増加が見込まれるため、ラオスに対して強い価格交渉力を維持すると予想されます。
IV.国際協力の課題 援助吸収能力の強化
ラオス経済の持続的成長のためには、政府部門の強化が不可欠です。援助吸収能力の向上を図るためには、開発計画と政策の調整機能強化、そして人材育成が重要な課題です。ADB、世界銀行、IMF、UNDPなどの国際機関、そして日本などの二国間援助がラオス経済を支えています。しかし、援助の効率性を高め、インフレや債務累積を防ぐために、コスト節約的な「草の根無償援助」や、タイなど周辺国との連携による三角支援が有効です。特に、人材育成においては、タイとの連携が期待されていますが、ラオスの人口規模を考慮したコストパフォーマンスの検証が重要です。 また、人材育成は、高度な技術導入を成功させる上で不可欠であり、インフラ整備、金融市場整備、制度・組織・政策の整備と相まって、投資の効率性向上に繋がります。
1. ラオス政府の援助吸収能力 政府部門強化の必要性
ラオス経済の持続的な成長のためには、政府部門の強化が不可欠です。具体的には、内陸山岳小国としての不利な国際輸送コストの軽減、非貨幣経済・未組織経済の近代化への統合、多様な民族の生活水準向上と国民経済の一体化、そして周辺諸国との国際経済関係の深化といった構造的な問題に取り組む必要があります。脆弱な直接生産部門を開発するためには、農業用灌漑設備、道路、通信、電力などのインフラ整備に加え、制度・組織・人材の強化も必要不可欠です。80年代後半以降、ラオス経済は比較的安定した推移を見せていますが、これらの構造的な課題を解決しなければ、持続的な成長は難しいでしょう。政府は、これらの課題に対応できる能力を強化するために、具体的で総合的な開発戦略を策定する必要があります。国際協力を受け入れる際にも、政府自身の機能強化を念頭に置いた戦略的なアプローチが重要です。そうでなければ、援助案件関連支出の増加、財政赤字の拡大、ひいては長期的な経済発展阻害につながるリスクがあります。ラオスではインフラ投資プロジェクトが多く、部門的・空間的な調整不足のまま、国際協力によって実施されている現状があります。そのため、国民経済の発展と国土整備の長期的な方向性を見据えた、投資案件間の連携を維持し、投資資金の効果的な配分を目的とする枠組みの構築と実行が不可欠です。援助側も、この枠組みを踏まえた案件提案を行うことで、ラオスのニーズに合った国際協力を実現できる可能性が高まります。さらに、計画立案・提示だけでなく、国際協力の窓口となり、援助案件の適合性評価と実施状況のモニタリングを行う強力な援助調整機関の設置が重要となります。
2. 援助吸収能力向上のための課題 債務管理と人材育成
ラオスの援助吸収能力向上のためには、債務管理と人材育成の両面からのアプローチが必要です。96年春以前は、無償援助は国家計画協力委員会、有償援助は省庁が窓口となっていましたが、援助案件の実施段階では大蔵省が資金管理と実施担当省庁への指導を担っていました。国家計画協力委員会は、省レベル組織だったため、案件や政策調整における主導権を握るには不十分でした。現在、ラオス政府は年間200万ドルの借款受け入れ限度額を設定し、その70%程度が流入していると推定されます。マクロ経済的に見ると、この規模は過剰ではないと判断されますが、援助調整能力や援助吸収能力の限界に近づいているという指摘もあります。そのため、ラオス側の状況をよく見極めながら援助の拡大を検討する必要があるという意見も存在します。人材育成の面では、ASEAN諸国と比較してラオスの経済開発は遅れており、タイやベトナムとの競争において不利な立場にあります。ラオスの人口規模と労働人口規模を考慮すると、労働集約型製造業が基幹産業になりにくいことは明白です。タイからの投資は衣料品分野では伸び悩みを見せており、電力開発や観光産業へのシフトが見られます。ラオス政府は人材育成を急いでいますが、ASEAN諸国と比較すると、中堅管理者層の絶対的な不足が大きな制約となっています。また、経済自由化による消費財の増加に伴い、修理・補修サービスの需要が高まっていますが、多くはタイ人企業に依存している現状があります。ラオス人企業家の自立が、付加価値創出の鍵となります。
3. 人材育成政策と国際協力 ソフト支援と連携型援助の推進
ラオス政府は、マクロ経済の安定化と外国投資流入を背景に、各分野における人材育成を急いでいます。現状では、人材育成は民間企業が主体となって行われていますが、政府は労働者間の格差是正にも関心を示しています。2000年までに全国7カ所の職業訓練センター設立を計画していますが、進捗は遅れています。ビエンチャンの国立高等職業訓練センターは、高度熟練人材育成を担っていますが、英語教育の不足、学習内容の陳腐化、民間企業への就職率の低さなどが問題となっています。国際協力の面では、ラオスには経常収支赤字を相殺できる規模の援助が流入しており、ADB、世界銀行、IMF、UNDPなどの国際機関、そして日本、ドイツ、スウェーデンなどが主要な援助国となっています。援助は農業開発、森林保全、運輸・通信などに重点が置かれています。しかし、ラオスの援助吸収能力は限られており、国際協力の急激な拡大はインフレや債務累積を招く可能性があります。そのため、政策対話に基づいた援助計画が必要不可欠です。日本の国際協力においては、財政不均衡に配慮したコスト節約的な草の根無償援助と、住民参加型のソフト支援型援助が重要です。また、周辺国との連携型援助も有効です。特に人材育成においては、タイとの連携が期待されており、ウボンラチャタニが技術協力の中核都市となる可能性があります。しかし、ラオスの人口規模を考えると、職業訓練センターや大学の設置計画のコストパフォーマンスを慎重に検討する必要があります。
V.東北タイ経済と周辺地域との関係
1980年代後半以降、タイは農工間格差、都市農村格差の是正のため、東北タイ開発を推進してきました。通貨危機以前は、ラオスを含むインドシナ諸国との貿易増加などによって経済は活況を呈していました。ミャンマーと中国雲南省は、インドシナ3国と比較して、経済関係の比重は小さいものの、華僑華人系企業による外国投資が経済発展の鍵を握っています。ラオスはタイ、中国、ベトナムとの経済関係強化を目指しており、その過程で国際経済関係をより深化させる必要に迫られています。
1. 東北タイ経済の動向 農工間格差と地域開発
80年代後半、タイは国内市場の深化を経済開発の重要な柱と位置づけました。これは、70年代からの急速な工業化に伴う農工間格差と都市農村格差の問題に対応するためです。東北タイの開発は、タイの長期的な自律的経済発展にとって極めて重要な課題であり、現在では中央政府との連携の下、地場資本による持続的成長が模索されています。従来、タピオカ、トウモロコシ、大豆の生産と関連産業に依存してきた東北タイ経済は、90年代初めから通貨危機までの間、世界輸出市場の安定、中央政府の規制緩和政策による民間主導の建設投資、オートバイ、繊維・衣料、食品加工業などの農業関連産業への設備投資拡大、そしてラオスを含むインドシナ諸国との貿易増大によって、かつてない活況を呈していました。これらの要因により、東北タイは持続可能な成長軌道を探る段階に到達していると言えるでしょう。 しかし、この発展は世界市場と中央政府の政策に大きく依存しており、将来的な持続可能性については更なる検証が必要でしょう。
2. ミャンマーと中国雲南省の経済状況とインドシナ諸国との関係
人口4400万人(首都220万人)のミャンマーにおいては、シンガポールや雲南省との経済関係に比べ、ラオスを含むインドシナ諸国との経済関係の比重は小さいです。ミャンマー経済発展の鍵を握るのは、タイだけでなくシンガポール、香港、台湾からの華僑華人系企業による外国投資活動です。ミャンマー政府がADBや関係国による「成長の4角地帯構想」や辺境貿易拡大に関心を示すのは、主に国境地帯に住む少数民族の生活安定化政策と関連していると考えられます。一方、人口3900万人の中国雲南省にとっても、インドシナ3カ国との経済交流は小規模です。主要な貿易相手はミャンマーであり、シンガポール、香港、台湾、タイなどの華僑華人系企業がミャンマーを経由して貿易を行っています。雲南省の経済発展は、中国東沿岸部諸都市との貿易や相互投資に大きく依存しており、現状ではインドシナ3カ国は比較的低い位置づけです。しかし、華僑華人系企業がベトナム経済においても重要な役割を果たす可能性を考慮すると、タイだけでなくベトナムや雲南省からの華僑華人系企業の進出によって、地域内の中華系金融ネットワークが活発化する可能性は大きいです。この地域は近代産業の勃興に大きな可能性を秘めていると言えるでしょう。
