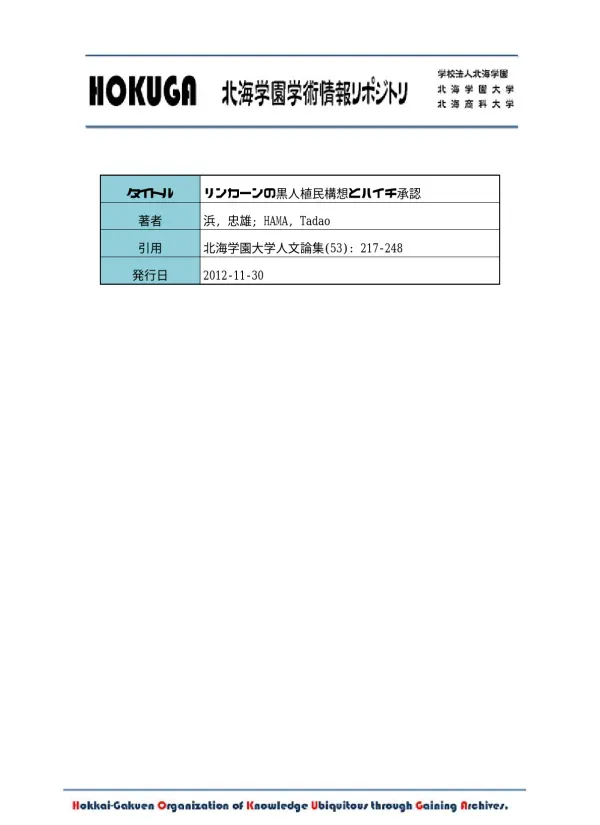
リンカーンと黒人植民:ハイチ承認の背景
文書情報
| 著者 | 浜 忠雄 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 歴史学 (推定) |
| 場所 | 札幌市 (推定) |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.95 MB |
概要
I.リンカーンの黒人植民計画とハイチ承認 南北戦争期のアメリカ人種問題
本稿は、南北戦争期のアメリカにおけるエイブラハム・リンカーン大統領の黒人植民計画と、ハイチ承認の決定について分析しています。リンカーンは、奴隷解放と同時に黒人をアメリカ国外に移住させることを目指しました。その計画は、人種混交への恐怖と、南北戦争後の社会不安を解消するための現実的な政策として捉えられます。当初、リベリアやチリキ地方が候補地として検討されましたが、様々な困難や周辺諸国の反対により、最終的にハイチが注目されました。しかし、ヴァッシュ島への植民は失敗に終わり、リンカーンは死の直前までこの計画に固執していました。一方、1862年、リンカーンはハイチの独立を承認しました。これは、人道的な配慮ではなく、黒人植民計画のための外交的布石として行われた政治的な決断でした。フレデリック・ダグラスのような著名な奴隷解放主義者も植民計画に関与しており、その賛否両論も合わせて考察されています。 アメリカとハイチの関係、そして黒人植民計画の背景には、複雑なアメリカ人種問題の歴史が深く関わっていることを示しています。
1. リンカーンの黒人植民計画 構想の背景と変遷
この節では、リンカーンの黒人植民計画の背景と、その構想の変遷が詳細に分析されています。まず、1852年のヘンリー・クレイ追悼演説における最初の言及から始まり、アフリカへの黒人送還という考え方が、道徳的な側面とアメリカの利益という観点から論じられている点が注目されます。しかし、1854年のペオリア演説では消極的な姿勢を示しますが、1857年のスプリングフィールド演説では再び積極的な姿勢に転じ、人種混交(amalgamation)への強い嫌悪感を背景に、人種分離を目的とした黒人植民の必要性を強調しています。 この計画の根底には、白人社会における人種混交への強い忌避感と、南北戦争後の社会不安への懸念が強く反映されていることがわかります。 当時のアメリカ社会に根強く存在した人種差別意識、特に異人種間結婚禁止法の歴史的背景なども踏まえながら、リンカーンの黒人植民計画が単なる博愛主義的な発想ではなく、複雑な政治的、社会的な思惑に基づいていたことが示唆されています。 また、共和党を誹謗中傷する目的ででっち上げられた、共和党が人種混交を党是としているという偽の文書についても言及され、当時のアメリカ社会における人種問題の複雑さが浮き彫りにされています。 リンカーンは、1858年のオタワ演説でもリベリアへの黒人送還を提案していますが、実現には困難が伴うことを認めています。
2. 黒人植民計画の実行 チリキ計画とヴァッシュ島計画の失敗
この節では、リンカーンの黒人植民計画の実行過程、特にチリキ計画とヴァッシュ島計画の失敗が詳細に分析されています。1862年4月、連邦議会はコロンビア地区の解放奴隷の移住のために10万ドルの予算を承認しますが、植民地候補地については様々な意見が飛び交いました。リベリアは気候や費用、ハイチは文化水準やカトリックであることなどが問題視され、最終的にチリキ地方(現在のパナマ)が候補地として浮上しました。しかし、中米諸国の反対により、この計画は断念されます。 その後、ハイチ南西部のヴァッシュ島が新たな候補地として浮上し、バーナード・コックとの間で植民契約が締結されますが、スワード国務長官の反対により頓挫します。 1863年4月には、453人の黒人がヴァッシュ島へ出発しますが、天然痘の流行や、住居やインフラの不足、マラリアの発生により、計画は惨敗に終わります。 このヴァッシュ島計画の失敗は、ハイチ政府の承認を得ていなかったことや、コックの不誠実な行動などが要因として挙げられています。 さらに、チリキ計画、ヴァッシュ島計画における失敗は、アメリカ政府の傲慢さと、周辺諸国の意向を無視した行動が原因の一端であったという指摘がなされています。 これらの失敗は、黒人植民計画が単なる理想論ではなく、現実的な制約や外交的課題に直面していたことを明確に示しています。
3. ハイチ承認 黒人植民計画とアメリカの戦略的思惑
本節では、1862年6月5日にリンカーンが行ったハイチとリベリアの独立承認の決定が、黒人植民計画と密接に関連していることが論じられています。長らく「交易はするが承認はしない」という立場を貫いていたアメリカが、突然ハイチの独立を承認した背景には、黒人植民計画のための外交的布石という戦略的思惑があったと推測されています。 チャールズ・サムナー上院議員の働きかけや、アメリカとハイチ間の貿易の重要性も強調されていますが、本質的にはリンカーンによる実利的な政治的決断であったと分析されています。 リンカーンの1861年12月3日の年次教書には、ハイチとリベリアの承認に言及した上で、「植民計画の遂行には領土の獲得が必要」と述べられており、ルイジアナ購入の先例も示されています。 このハイチ承認は、反レイシズムや反植民地主義的な視点に基づいたものではなく、黒人植民計画を進めるための手段としてハイチが利用された側面が強調されています。 また、合衆国議会におけるハイチ承認に関する議論の詳細や、その過程で関与した主要人物(チャールズ・サムナー、ウィラード・ソールスベリーなど)の言動についても言及されています。 この節は、アメリカのハイチ政策が単なる善隣外交ではなく、複雑な国内事情と密接に関連していることを明らかにしています。
4. アメリカにおける人種問題と黒人植民論 様々な視点からの考察
この節では、アメリカにおける人種問題と、黒人植民論をめぐる様々な視点からの考察が提示されています。黒人植民計画の失敗後、アメリカは黒人問題を国内で解決せざるを得なくなりますが、黒人植民論は完全に消滅したわけではありません。 ウィリアム・P・ピケットの著書『黒人問題―エイブラハム・リンカーンの解決』が、ハイチやリベリアへの黒人植民を提唱した例として挙げられています。この著書は、リンカーンの黒人植民構想を完成させるべきだと主張しており、現代まで影響を与え続けていることが示唆されています。 さらに、ハリエット・ビーチャー・ストウの『アンクル・トムズ・ケビン』が、黒人賛歌と同時に黒人植民(黒人排斥)を推奨する二重構造を持っていたという分析が紹介されています。 ストウは黒人の道徳的・宗教的優位性を強調しながらも、アメリカ社会からの黒人の排除という側面も描き出しており、その思想はフレデリック・ダグラスのような黒人解放主義者から強い反発を招いたことが述べられています。 この節は、黒人植民論が、人種差別主義的な思想と複雑に絡み合いながら、アメリカ社会に影響を与え続けてきたことを明らかにしています。
5. フレデリック ダグラスの黒人植民観 リンカーンとの対比
この節では、奴隷解放運動家フレデリック・ダグラスの黒人植民観が、リンカーンのそれとの対比を通して論じられています。ダグラスにとってハイチ移住は、南北戦争直前の絶望的な状況下における「次善の策」であり、ハイチの歴史や黒人共和国としての意義よりも、アメリカへの地理的な近さが重視されていました。 ハイチは一時的な避難所として位置づけられており、リンカーンの黒人植民計画のような、黒人をアメリカから排除しようとする発想とは異なる視点が示されています。 ダグラスは、アメリカとハイチ間の通商関係の重要性を認めつつも、ハイチの自主性を尊重する立場をとっており、晩年の彼の「ハイチ賛歌」もこの文脈において理解されるべきだと指摘されています。 また、ダグラスが在ハイチ総領事として両国の架け橋となった経験も紹介され、彼のアメリカとハイチの関係への深い関与が示されています。 この節は、黒人植民論をめぐる異なる立場を明らかにし、人種問題に対する多様な視点の存在を強調しています。
II.リンカーンの黒人植民計画 構想から挫折まで
リンカーンの黒人植民計画は、奴隷解放と表裏一体のものでした。1850年代から構想が始まり、1862年にはコロンビア地区の解放奴隷の移住に国費を充てることが決定されました。チリキ開発会社(Ambrose W. Thompson)とのチリキ植民契約、そしてヴァッシュ島への植民計画などが実行されましたが、いずれも失敗に終わりました。これらの失敗は、周辺諸国の反対や現地状況の悪さ、そしてハイチ政府の承認不足など、様々な要因が絡み合っています。 リンカーンは、黒人のアメリカからの移住(deportation)が白人と黒人の双方にとって最善であると考えており、この考えが計画の根底にありました。計画の失敗は、アメリカが黒人問題を国内で解決せざるを得ないという現実を突きつけました。重要な人物として、ジェームズ・ミッチェル(アメリカ植民協会)、バーナード・コック(ヴァッシュ島)、そしてジェームズ・R・ドゥーリトル(上院議員)などが挙げられます。
1. リンカーンの黒人植民構想 初期の発想と人種混交への懸念
この節では、リンカーンの黒人植民計画の初期段階における構想と、その背景にある人種混交への強い懸念が詳細に分析されています。1852年のヘンリー・クレイ追悼演説が、リンカーンが黒人植民問題に初めて言及した機会として紹介されています。この演説において、リンカーンはアフリカへの黒人送還を道徳的に正しいと主張していますが、それは同時に、アメリカ社会における黒人の存在がもたらす問題、特に人種混交への懸念を反映していると考えられます。 続く1854年と1857年の演説では、計画の実現可能性やその方法論について、リンカーンの考え方の変化が見て取れます。当初消極的な姿勢を示したリンカーンは、後年には人種混交を防ぐための最善策として黒人植民を主張するようになり、人種分離への強い意志が明確に示されています。 この節では、単なるアフリカへの黒人送還という視点にとどまらず、人種混交(amalgamation)への嫌悪感、南北戦争後の社会不安への対処といった、当時のアメリカ社会における複雑な政治的、社会的背景を踏まえた上で、リンカーンの黒人植民計画の真意が探られています。 また、この時代背景を説明する上で、異人種間結婚禁止法の歴史や、人種混交に関する誤った情報を流布した民主党系の新聞記事なども取り上げられており、当時のアメリカ社会における人種問題の複雑さが浮き彫りにされています。
2. チリキ計画の提案と挫折 中米諸国の反対とスワード国務長官の役割
この節では、リンカーン政権下における黒人植民計画の実行過程、特にチリキ計画の提案と挫折が中心的に論じられています。1862年4月、連邦議会はコロンビア地区の解放奴隷の移住費用として10万ドルを拠出することを決定しますが、具体的な植民地候補地については様々な意見が対立しました。 その中で、リベリアやハイチは気候や文化などの問題点から不適切と判断され、最終的にチリキ地方(現在のパナマ)が候補地として浮上します。 しかし、チリキ地方の開発権を持つ実業家アンブローズ・W・トンプソンとの契約締結後、周辺の中米諸国からの強い反対に直面します。 この反対を受け、中南米諸国との良好な関係を重視するウィリアム・ヘンリー・スワード国務長官の説得により、リンカーンはチリキ計画を断念せざるを得ませんでした。 このチリキ計画の挫折は、リンカーンの黒人植民計画が、単に国内の黒人問題解決策という枠を超えて、国際的な外交問題、特に中南米諸国との関係に大きく影響されることを示しています。 また、この計画の失敗が、後のハイチへの植民計画への展開にも影響を与えたことが、この節の重要な論点の一つとなっています。
3. ヴァッシュ島計画の失敗 コックとの契約とハイチ政府の拒否
この節では、チリキ計画の失敗後、ハイチのヴァッシュ島への黒人移住計画(ヴァッシュ島計画)の経緯とその失敗が分析されています。チリキ計画の挫折後、リンカーンはイギリス、デンマーク、オランダなどに黒人移住の可能性を探りますが、満足のいく回答を得られません。 その中で、ハイチのヴァッシュ島の租借権を持つ実業家バーナード・コックからの提案を受け、リンカーンは5000人の黒人を移住させる契約を結びます。しかし、コックの誠実性に疑問を抱いたスワード国務長官が契約を承認せず、計画は頓挫します。 その後、規模を縮小した上で、500人の黒人がヴァッシュ島へ移住する計画が実行されますが、これも失敗に終わります。 この計画の失敗は、天然痘の流行や、ヴァッシュ島の劣悪な環境、そして何よりもハイチ政府の事前の承諾を得ていなかったことが原因として挙げられています。 このヴァッシュ島計画の失敗は、1863年1月1日の奴隷解放宣言の前日に契約が締結されたという事実と関連づけられ、リンカーンが奴隷解放と黒人植民をセットで考えていたことを示唆する重要なエピソードとして取り上げられています。 この計画の失敗は、リンカーンの黒人植民構想における重大な欠陥と、計画実行における重大なミスを露呈する結果となりました。
4. リンカーンの黒人植民への執着と最後の構想の挫折 国内解決への転換
この節では、ヴァッシュ島計画の失敗後も、リンカーンが黒人植民計画に固執していたこと、そしてその最後の構想が挫折した経緯が論じられています。 マグネスとペイジの共著『奴隷解放後の植民』で新たに発見された史料に基づき、リンカーンが奴隷解放宣言の数週間後、イギリス領ホンジュラスやギアナへの植民をイギリス政府に打診していたことが明らかになります。 しかし、この最後の黒人植民構想も内閣の承認を得られず、南北戦争終結前に挫折しました。 この結果、アメリカは黒人問題を国内で解決せざるを得ない状況に追い込まれます。 リンカーンが黒人植民に固執した理由は、南北戦争後の社会的和合と、黒人に対する劣等意識の2点だと分析されています。ギデオン・ウェルズ海軍長官の証言も引用され、リンカーンが政治的には奴隷制廃止主義者ではなかったという見解も提示されています。 また、リンカーンの黒人植民構想が、世論掌握のためのプロパガンダという側面もあった可能性も示唆されていますが、同時に、大規模移住の先例を挙げ、リンカーンの植民への執着が一時的なものではなかったとする反論も提示されています。 この節は、リンカーンの黒人植民計画が、奴隷解放という政策と不可分であった一方で、現実の困難や制約に直面し、最終的には挫折した過程を明確に示しています。
III.ハイチ承認 黒人植民計画のための外交的布石
1862年6月5日、リンカーンはハイチとリベリアの独立を承認しました。これは、アメリカが長年維持してきた「交易はするが承認はしない」という姿勢からの転換でした。この決定は、ハイチ革命への共感に基づいたものではなく、黒人植民計画を成功させるための戦略的な外交的措置でした。チャールズ・サムナー(上院外交委員会委員長)が議案提出に大きく貢献し、ベンジャミン・F・ホィッデンが初代ハイチ総領事に任命されました。この承認は、国内の奴隷制廃止運動の高まりも背景にありますが、本質的にはリンカーンの実利的な政治的決断であったと解釈できます。 アメリカのハイチ承認は、黒人共和国への共感ではなく、黒人問題を「解決」するための手段としてハイチを利用したことを示しています。
1. ハイチ承認の決定と背景 長年の 交易すれども承認せず からの転換
この節では、1862年6月5日にリンカーン大統領がハイチとリベリアの独立を承認したという事実と、その背景にあるアメリカ合衆国の長年の政策転換が分析されています。それまでアメリカ合衆国は、ハイチを独立国家として承認せず、交易のみを行なうという姿勢を長年維持していました。しかし、この決定は、それまでのアメリカの対ハイチ政策を大きく転換させるものとなりました。 ヨーロッパ諸国(フランス、イギリス、オランダ、スペイン、デンマークなど)は既にハイチの独立を承認していたにも関わらず、アメリカ合衆国は独自の立場を貫いていました。このアメリカ合衆国の姿勢は、ハイチ革命を成功させた黒人国家との公式な外交関係を避ける、アメリカ国内の黒人奴隷制維持という思惑に起因していました。 しかし、リンカーン政権下でこの政策が転換された背景には、黒人植民計画の実施という新たな政治的目標が存在していたと推測されています。 この節では、ハイチ承認という決定が、アメリカ合衆国の単なる外交政策ではなく、国内の人種問題と深く関わった政策転換であったという点を強調しています。 アメリカとハイチ間の貿易高がイギリスやフランスを大きく上回っていたという事実も、この承認決定に影響を与えた要因として示唆されています。
2. 議会における承認議論 サムナー議員とソールスベリー議員の対立
この節では、1862年の合衆国議会におけるハイチ承認に関する議論の過程が、主要な登場人物の言動を通して詳細に分析されています。マサチューセッツ州選出の共和党上院議員チャールズ・サムナーは、リンカーン大統領の意向を汲んで、ハイチとリベリア両国への外交代表派遣を大統領に認める議案を提出しました。 サムナーは、長年事実上の独立国であったハイチの承認を遅らせてきた合衆国の従来の政策を批判し、アメリカとハイチ間の貿易の重要性を強調することで、議案の支持を訴えました。 一方、メリーランド州選出の民主党上院議員ウィラード・ソールスベリーは、この議案に強く反対し、アフリカ系アメリカ人の合衆国上院への進出を嫌悪感を込めて批判しています。 このサムナーとソールスベリーの対立は、当時のアメリカ社会における人種問題をめぐる複雑な政治的思惑を反映しています。 最終的には、上院で賛成32対反対7、下院で賛成86対反対37という圧倒的な多数で議案は可決され、リンカーン大統領の署名により発効しました。 この節では、ハイチ承認という決定が、単に人道的な配慮や国際的な情勢の変化によるものではなく、当時のアメリカ合衆国の複雑な政治状況と人種問題が絡み合った結果であったことを示しています。 ベンジャミン・F・ホィッデンが初代総領事に任命され、1871年にはサムナーの功績を称えるメダルがハイチ政府から授与されたことも紹介されています。
3. ハイチ承認の真意 黒人植民計画のための外交的布石としての解釈
この節では、リンカーン大統領によるハイチ承認の真意が、黒人植民計画との関連性から分析されています。 著者は、リンカーンがハイチとリベリアの承認を、黒人植民事業のための外交上の布石として意図していたと推測しています。 この推測を裏付ける決定的な史料は提示されていませんが、1861年12月3日のリンカーンの年次教書において、ハイチとリベリアの主権と独立を認める一方で、「植民計画の遂行には領土の獲得が必要」と述べ、約60年前のルイジアナ購入を例に挙げています。 また、教書には「colonization」という言葉が3回も登場しており、植民計画への強い関心がうかがえます。 このハイチ承認は、ハイチ革命の理念への共感に基づくものではなく、あくまで黒人植民計画という現実的な政治的目標達成のための手段として捉えられています。 ジェームズ・D・ロケットの指摘のように、1862年春のハイチとリベリアの承認は、植民先を探す動機からだったと解釈できます。 この節は、ハイチ承認という出来事を、単なる外交上の出来事としてではなく、リンカーンの黒人植民計画という大きな文脈の中で捉えることの重要性を強調しています。
IV.アンクル トムズ ケビンと黒人植民論
ハリエット・ビーチャー・ストウの小説『アンクル・トムズ・ケビン』は、奴隷制廃止運動の象徴的な作品ですが、同時に黒人植民(黒人排斥)を推奨する側面も持っていました。小説は黒人の道徳的・宗教的な優越性を強調しつつも、アメリカ社会からの排除を暗に示唆しています。この小説は、アメリカ植民協会の宣伝にも利用され、黒人植民という考え方が広く浸透する一因となりました。 ストウの植民論と人種偏見については、清水氏や野口啓子氏の研究が重要です。フレデリック・ダグラスはストウの植民論に強く反発したことが知られています。
1. アンクル トムズ ケビン と黒人植民 二重構造のメッセージ
この節では、ハリエット・ビーチャー・ストウの小説『アンクル・トムズ・ケビン』が、奴隷制廃止運動の象徴的作品であると同時に、黒人植民(黒人排斥)という側面も内包していたという点が分析されています。 一見、奴隷制反対の強力なメッセージが込められた作品と見なされますが、清水氏の分析によると、作品は黒人への賛歌と黒人植民の推奨という二重構造を持っていました。 小説の末尾で、主人公の一人がアフリカへの移住を決意するシーンが取り上げられ、その手紙を通して、アメリカ社会における人種問題に対するストウの複雑な考え方が読み解かれています。 具体的には、アメリカ社会を「人種のるつぼ」と捉えながらも黒人だけを排除しようとする差別的な発想、黒人植民によってアフリカを文明化するという発想、そして黒人資質と白人資質の対照的な描写などが指摘されています。 さらに、アフリカ大陸に対するストウの描写が、従来の「暗黒大陸」といった負のイメージではなく、豊かな資源に恵まれた魅力的な土地として描かれている点が強調されています。 これらの分析を通して、ストウが奴隷制廃止を訴えながらも、黒人との共存という考え方には至らなかったという点が示唆されています。 この分析は、アメリカ史研究における常識とは異なる視点から、ストウの作品を多角的に理解することを促しています。
2. ストウの植民論と人種偏見 野口啓子氏の分析とダグラスの反論
この節では、野口啓子氏の論文が引用され、ストウの植民論と人種偏見について、より詳細な分析が加えられています。野口氏は、『アンクル・トムズ・ケビン』と『スレイヴ・ナラティヴ』におけるストウの描写を分析し、ストウが黒人を排除した白人社会を描いていると結論付けています。 この分析は、清水氏の分析と同様、ストウの作品が黒人植民という思想を内包していたという結論に達しています。しかし、野口氏の分析は、清水氏よりもさらに踏み込んで、アメリカ生まれの黒人を「異邦人」化するストウの未来像に対して、フレデリック・ダグラスが激しく反発したという点を指摘しています。 ダグラスの反論を受け、ストウ自身が植民という設定を後悔し、ダグラスにその思いを伝えたという事実も紹介されています。 このダグラスの反論とストウの反応は、黒人植民論が当時のアメリカ社会において、決して単一的なものではなく、黒人自身から強い反発を招く可能性もあったことを示しています。 この節は、ストウの作品における黒人植民論の表現方法とその影響、そして黒人社会からの反応という多角的な視点から、当時のアメリカ社会における人種問題の複雑性を浮き彫りにしています。
V.フレデリック ダグラスの黒人植民観
著名な奴隷解放主義者であるフレデリック・ダグラスの黒人植民観は、リンカーンのそれとは対照的でした。ダグラスにとってハイチ移住は、アメリカに残ることに対する「次善の策」であり、ハイチの歴史や黒人共和国としての特性よりも、地理的な近さが重視されました。晩年のダグラスはハイチを称賛する発言を残していますが、それはアメリカとハイチ間の通商関係の重要性とハイチの自主性を尊重する文脈の中でなされたものです。 ダグラスは在ハイチ総領事としてアメリカとハイチ間の橋渡し役を務めました。 彼のハイチ観は、リンカーンのそれとは異なり、アメリカ国内での黒人の権利向上を目指したものでした。
1. ダグラスのハイチ観 リンカーンの黒人植民計画に対する批判的視点
この節では、著名な黒人奴隷解放運動家フレデリック・ダグラスのハイチ観、そしてそれがリンカーンの黒人植民計画に対する批判的視点としてどのように位置づけられるかが論じられています。 ダグラスは、奴隷制度からの解放後、アメリカに残留することの困難さを認識しており、ハイチ移住を「次善の策」として捉えていたことが指摘されています。 しかし、彼のハイチへの関心は、ハイチの歴史や黒人共和国としての特殊性に基づくものではなく、アメリカへの地理的近さという現実的な理由によるものでした。 ダグラスは、ハイチをアメリカへの帰還が可能な「一時的な避難所」とみなしていたと解釈できます。 この点は、リンカーンの黒人植民計画が、黒人をアメリカから完全に排除しようとする計画であったことと対照的です。 ダグラスが在ハイチ総領事として務めた経験、そして1893年のハイチ展示館への献呈演説における彼の発言も紹介されており、アメリカとハイチの貿易関係の重要性を認めつつも、ハイチの自主性を尊重する姿勢が強調されています。 この節では、ダグラスのハイチ観を通して、リンカーンら白人主導の黒人植民計画とは異なる、黒人自身によるアメリカ社会における居場所の模索という重要な視点を提示しています。
2. ダグラスの生涯とハイチ 総領事としての役割とハイチ賛歌の背景
この節では、ダグラスの生涯におけるハイチとの関わり、特に在ハイチ総領事としての役割と、晩年に見られる「ハイチ賛歌」の背景が分析されています。 ダグラスは、ハイチ総領事の任命を「生涯最高の名誉」としながらも、アメリカ合衆国の代弁者として働くことのジレンマに直面していたと自伝に記しています。 このジレンマは、彼自身の奴隷解放運動家としての立場と、アメリカ合衆国政府の政策との間の葛藤を象徴的に示しています。 彼の1893年のハイチ展示館への献呈演説では、アメリカとハイチ間の通商関係の重要性を指摘しつつも、ハイチの自主性を尊重する姿勢が明確に示されています。 この演説における「ハイチ賛歌」は、彼の個人的なハイチへの好意というよりも、アメリカとハイチの関係をより良好なものにするための、政治的、外交的な文脈の中で理解されるべきだと指摘されています。 また、アメリカが1891年にハイチの港湾の譲渡を打診した事実に触れられ、ダグラスがアメリカとハイチの橋渡し役として活動したことが強調されています。 この節は、ダグラスの複雑な立場と、彼がハイチに対して抱いていた多様な感情を浮き彫りにすることで、単なる「ハイチ賛歌」を超えた、より深い歴史的文脈での理解を促しています。
