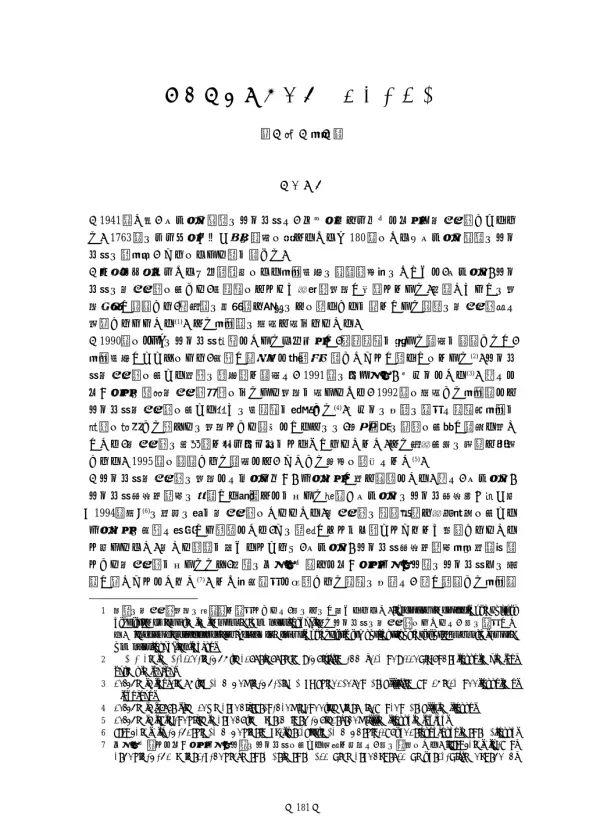
ヴォルガ・ドイツ人強制移住:メカニズムと目的
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 537.69 KB |
| 著者 | 半谷史郎 |
| 文書タイプ | 論文 |
概要
I.これまでの研究と本稿の目的
これまで、ヴォルガ・ドイツ人強制移住に関する研究は、キチヒンやブガイらの初期研究に見られるように不正確な記述や犠牲者数への偏りがありました。ゲルマンの『ヴォルガのドイツ自治区』は詳細な記述で高く評価されますが、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国に限定的な視点がありました。本稿では、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国、サラトフ州、スターリングラード州の3地域を対象に、NKVDによる強制移移住のメカニズムと目的を、既存史料の分析を通して解明することを試みます。特に、ミロワ監修『ドイツ人の強制移住』などの一次史料を精査することで、ゲルマンの研究を補完・発展させます。
1. 既存研究の検証 キチヒン ブガイ ゲルマン
1990年代初頭、KGBのドイツ人担当だったキチヒンは内部文書に基づく論考を発表しましたが、後の史料公開によりその記述の不正確さと信用性の低さが明らかになりました。ドイツ人強制移住に関する本格的な研究としては、1991年のニコライ・ブガイの研究が挙げられます。ブガイはスターリン時代の民族強制移住全般を研究し、1992年には関連する多くの公文書を含む史料集を刊行しました。彼の研究は文書館史料を丹念に調査した点で評価できますが、犠牲者数の特定に偏り、強制移住のメカニズムを十分に解明できていないという欠点がありました。1995年の論考でもこの傾向は変わっていません。
一方、アルカジー・ゲルマンの研究はヴォルガ・ドイツ人強制移住研究において最も重要な位置を占めます。彼の著作『ヴォルガのドイツ自治区』第2巻(1994年刊)は、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国の設立から消滅までを網羅し、最後の章で強制移住を詳細に分析しています。準備過程から実施状況まで綿密な記述がなされており、ほぼ網羅的な検討と言えるでしょう。しかし、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国に焦点を当てているため、近隣のサラトフ州やスターリングラード州のドイツ人への視点は相対的に弱いと指摘できます。なお、ゲルマンの著作で引用された文書の一部は、彼自身が編集した史料集にも収録されています。
2. 本稿の研究目的とアプローチ
本稿では、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国、サラトフ州、スターリングラード州という3地域を包括的に捉え、ヴォルガ・ドイツ人全体の強制移住メカニズムと目的の解明を試みます。理想的には独自の史料調査を行うべきですが、現段階では既刊史料の分析に絞ります。ミロワ監修の『ドイツ人の強制移住』をはじめ、多くの一次史料が既に公開されており、それらを精査することで、ゲルマンらの先行研究を補完し、新たな解釈を示すことを目指します。特にミロワ監修の史料集は、強制移住の全体像を把握するのに十分な量の史料を含んでおり、本稿の分析に重要な役割を果たします。その他にも、カザフスタンでのドイツ人受入れ状況に関する史料集なども参照することで、より多角的な視点からの分析が期待できます。これらの一次史料を精査することにより、ゲルマンの研究成果を基本的に尊重しつつ、いくつかの点において新たな解釈を提示できると考えます。
II.強制移住の決定と準備
従来、ヴォルガ・ドイツ人強制移住は1941年8月28日付ソ連最高会議幹部会令によるものとされてきましたが、ソ連崩壊後の史料公開により、8月26日付ソ連人民委員会議および党中央委員会決定の存在が明らかになりました。この決定は移住先、関係機関の役割分担、具体的な手順などを詳細に規定しており、幹部会令は後付けの正当化であったことが示唆されます。スターリン政権下の民族政策の一環として、ドイツ人住民を潜在的なスパイとみなした安全保障上の懸念が、強制移住の背景にあったと考えられます。サラトフ州とヴォルガ・ドイツ人自治共和国のドイツ人住民数に関する報告書(作成日不明)は、移住計画策定に重要なデータとして用いられたと推測されます。
1. 強制移住決定の再検討 8月26日決定と28日幹部会令
従来、ヴォルガ・ドイツ人の強制移住は1941年8月28日付のソ連最高会議幹部会令によるものと認識されてきました。しかし、ソ連崩壊後の史料公開によって、その前に8月26日付のソ連人民委員会議および党中央委員会決定が存在していたことが判明しました。この決定は、ドイツ人の移住先、関係政府機関の役割分担、移住作戦の具体的な手順などを詳細に規定しています。これに対し、8月28日付の幹部会令は「数千人から数万人の破壊分子とスパイ」という嫌疑をドイツ人に押し付け、強制移住に合法性を装わせるための表向きの理由説明に過ぎなかった可能性が高いと推測されます。実際、ソ連内務人民委員部(NKVD)作成の移住計画や実行指令は、8月26日付の決定に基づいて作成されており、これが強制移住の真の命令であったことを示唆しています。 この8月26日付の決定は、軍当局からの情報に基づき、ヴォルガ地区のドイツ人住民の中に多数の破壊分子やスパイが存在し、ドイツからの合図で爆弾テロを起こす計画があると断定。これをソ連当局に報告しなかったことを、ドイツ人住民が敵を匿っていると解釈し、流血の惨事を防ぐためとして、ノヴォシビルスク州、オムスク州、アルタイ地方、カザフ共和国などへの移住を決定しています。
2. 強制移住計画の準備 住民数調査と財産処理
強制移住の実施に先立ち、徹底的な準備が行われました。その重要な要素として、ドイツ人住民数に関する調査があります。NKVD作戦グループは、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国、サラトフ州、スターリングラード州において、コルホーズ、農村、都市をくまなく調査し、世帯ごとにドイツ人の人数を集計しました。妻がドイツ人で夫が非ドイツ人の場合などは移住対象から除外されましたが、希望すれば家族と行動を共にすることができました。この際、家長が家族全員の移住に責任を負うよう厳しく警告され、逃亡した場合には家長が刑事責任を問われるとされていました。 また、住民の財産処理も重要な準備作業でした。都市住民は信頼できる人物を通して家財道具を売却し、その代金を新しい居住地に送金することが認められました。一方、農民の農耕器具、家畜、家屋などは、ソビエト機関、農業人民委員部、乳肉産業人民委員部などの代表から成る特別委員会に引き渡され、評価額を記した受領書が発行されました。受領書に記載された財産は、移住先で同等のものが提供されることが約束されました。しかし、刈り入れ前の畑の収穫物は放置せざるを得ないなど、多くの困難を伴いました。さらに、治安維持のため住民同士の話し合いなどが禁止され、反ソ分子の逮捕も事前に指示されていました。
3. 準備段階における重要なデータ 住民数報告書
強制移住計画の立案・実行にあたり、重要な役割を果たしたのが、サラトフ州とヴォルガ・ドイツ人自治共和国のドイツ人住民数に関する報告書です。この報告書は、地元の国民経済集計局のデータに基づき、1941年6月1日現在のドイツ人住民数を地区別に詳細にまとめたものでした。この報告書の数値は、1939年の国勢調査と比較して増加しており、一桁まで正確に記録されている点も注目に値します。「ヴォルガ・ドイツ人自治共和国、スターリングラード州およびサラトフ州からのドイツ人住民の移住計画」はこの報告書の数値を引用しており、強制移住の準備段階において、この報告書が重要なデータとして利用されていたことが明らかです。 キチヒン中佐の証言によれば、モロトフとベリヤが1941年7月にエンゲリス市を視察し、ヴォルガ・ドイツ人の危機を指摘したとされています。この視察が強制移住計画の正式決定に繋がった可能性も示唆されていますが、現時点ではこれを裏付ける文書は見つかっておらず、ゲルマンもその信憑性に疑問を呈しています。エンゲリス市は、強制移住において重要な出発地点の一つでした。
III.強制移住の実態
9月3日、ヴォルガ・ドイツ人の強制移住が開始されました。NKVD作戦グループは、迅速な人数調査を行い、コルホーズや都市のドイツ人住民を、シベリアやカザフスタンへ移送しました。移送には列車が使用され、その運行状況を示す「運行表」は、計画性の高さと周到な準備を示しています。列車の運行状況は厳しく管理され、列車長、車両長といった責任者による監視体制が敷かれましたが、食料不足や衛生状態の悪化といった問題も発生しました。多くの犠牲者も出ており、子供たちの死亡例が多かったと報告されています。エンゲリス市は主要な出発地のひとつでした。
1. 強制移住の開始とNKVDの役割
1941年9月3日、ヴォルガ・ドイツ人の強制移住が開始されました。この作戦の中心的な役割を担ったのは、ソ連内務人民委員部(NKVD)です。NKVD作戦グループは、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国、サラトフ州、スターリングラード州の3地域において、ドイツ人住民の徹底的な戸別調査を実施しました。コルホーズ、農村、都市部を対象に、家族構成を詳細に記録する集計カードを作成し、移住対象者の選別を行いました。妻がドイツ人で夫が非ドイツ人の家族は除外されましたが、希望する家族構成員は一緒に移住を許されました。 この人数調査は、わずか1週間足らずという極めて短期間で行われ、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国37万4225人、サラトフ州4万3101人、スターリングラード州2万3945人、合計44万1271人の移住対象者が特定されました。この迅速な調査と集計は、強制移住計画の綿密な準備と、NKVDの効率的な作戦遂行能力を示すものです。 移送手段の確保は困難を極め、多くの場合、ドイツ人男性が徒歩で駅まで移動する事態も発生しました。船舶も利用され、指定の駅まで運ばれたケースもあります。 ヴォルガ川沿いのポクロフスク、クラスヌィ・クト、グメリンカ、パラソフカなどの駅周辺住民は、わずか数日の猶予しかありませんでした。
2. 強制移住の輸送と監視体制
強制移住では、主に貨物列車が使用されました。ゲルマンの記述によると、列車への荷物搬入は9月1日から開始されました。列車には、ドイツ人移住者だけでなく、NKVDの兵士も同乗しており、厳格な監視体制が敷かれていました。 列車長は、命令に従わない者に対して営倉車両への収容権限を有し、1日1回の人数確認と、NKVD特別入植部への運行状況報告が義務付けられていました。安全確保と秩序維持のため、各車両にドイツ人から車両長を選出し、車両内の秩序管理、列車長の指示の遂行、人数確認を担わせました。さらに、複数の車両をまとめてグループを編成し、その行動監視のために兵士の責任者を配置するなど、多層的な監視体制が構築されていました。 しかしながら、この厳格な監視体制にも関わらず、列車内での状況は決して良好ではありませんでした。車両に寝床がない、隔離車両が連結されない、食料配給の乱れ、お湯の不足などが頻発していました。中には、食料の代わりに金銭を渡す列車長もいましたが、移送途上で何かを購入することは困難だったと証言されています。 食料も水も与えられないという劣悪な状況もあったようです。
3. 強制移住の実態 証言と統計データ
強制移住の実態は、ドイツ人移住者の証言からも明らかになります。あるドイツ人の証言では、家畜運搬用の貨車に80人がひしめき合い、板で作った寝床を巡って争奪戦が繰り広げられた様子が伝えられています。食料は兵士の貨車からパンを貰ったり、大きな駅でスープが配給されたりしましたが、量は非常に少なく、自炊する者も多かったようです。 移送中の困難さは、様々な証言から見て取れます。衛生状態の悪さによる胃腸病の蔓延、多くの子供の犠牲、移送中の出産、停車中の列車発車による乗り遅れ、家族の離散、逃亡の試みと逮捕、そして厳しい処罰など、過酷な状況が繰り返されていました。 ゲルマンは、ヴォルガ・ドイツ人自治共和国からの移送列車で少なくとも129人(大半が子供)の死亡を確認し、サラトフ州とスターリングラード州からの列車でも死亡者や乗り遅れ、病気による下車者が多数いたと報告しています。カザフ共和国ジャンブール州の報告書にも、移送途中の死亡者、出生、合流、自殺、乗り遅れなどが記録されており、強制移住の過酷さが改めて浮き彫りになります。 「ドイツ人強制移住列車運行表」は、移住者数、移送先、出発駅、到着駅、日付などを記録した重要な資料であり、その緻密な記録は、強制移住計画の綿密さを裏付けるものです。特に、エンゲリス市は重要な出発駅でした。
IV.移住先の状況と強制移住の目的
アルタイ地方を例に、移住先での受入状況を見てみます。アルタイ地方では、党地方委員会と地方ソビエト執行委員会が合同会議を開き、「アルタイ地方における受入・移送計画」を承認しました。NKVDを主体とした作戦トロイカが設置され、ドイツ人の受入・移送作業を指揮しました。しかし、住居確保や輸送手段の不足といった問題が発生し、多くの混乱を招きました。移住先のドイツ人は、農業労働力として歓迎されましたが、やがて労働軍に動員され、強制労働を強いられることになります。 カザフスタン、シベリアへの移送経路は、南回りルートと北回りルートの両方があり、その効率性や安全性に違いがあったと考えられます。 ヴォルガ・ドイツ人の共同体は完全に破壊され、言語や文化、家族のつながりが失われました。
1. 移住先での混乱と生活状況 アルタイ地方の事例
強制移住されたドイツ人たちは、シベリアやカザフスタン各地で様々な困難に直面しました。アルタイ地方を例に見てみると、「8月26日決定」を受け、9月3日に党地方委員会と地方ソビエト執行委員会の合同会議が開かれ、「アルタイ地方における受入・移送計画」が承認されました。 しかし、実際には計画通りにはいきませんでした。迎えの輸送手段や宿泊場所が不足し、多くのドイツ人たちが降車駅で何日も放置されたり、連絡の不備から目的地が分からずたらい回しされたりしました。住居の確保も困難で、住宅の新築は後回しとなり、古くなった建物の修理も遅れ、多くのドイツ人たちは地元住民の家へ間借りせざるを得ませんでした。クラスノヤルスク地方では、1941年初めにドイツ人1万7307世帯のうち9296世帯が地元住民に間借りしていたという記録が残っています。 アルタイ地方では、9万5000人のドイツ人を58の地区に移送する計画でしたが、実際には計画より少ない地区に、鉄道から遠く離れた僻地にも多くのドイツ人が送られました。降車駅から先は、荷馬車を利用したものの、徒歩で目的地へ向かうことも多くありました。オビ川を利用した水路輸送も行われていました。
2. 移住後の労働力としてのドイツ人
シベリアやカザフスタンでは、ドイツ人移住者は主に農業労働力として受け入れられました。カザフ共和国ジャンブル州では、ドイツ人たちは駅から100キロ以上離れた遠隔地やビート収穫の労働力不足の場所に優先的に送られました。到着後わずか数日でビート収穫などの農作業に駆り出されたケースも少なくありませんでした。北カザフスタン州では脱穀や牛の飼育といったコルホーズの作業に従事し、専門技術を持つ者はその技術を生かした仕事に就きました。アルタイ地方アレイスカヤ駅で降ろされたあるドイツ人女性は、専門家の奪い合いの様子を「奴隷市場」のようだったと回想しています。 しかし、当初は農業労働力として歓迎されたドイツ人ですが、戦況の悪化に伴い、労働力不足を解消するための政策の一環として、計画的に利用されるようになりました。1942年1月10日付の国家国防委員会決定では、17歳から50歳のドイツ人男性12万人を「労働部隊」として動員することが決定され、NKVD管轄の森林伐採、工場建設、鉄道建設などに配置されました。動員拒否は「最高の刑事処分」に問われ、事実上の強制徴用でした。 その後、動員対象は年齢や性別も拡大され、1942年10月には15歳から55歳の男性と16歳から45歳の女性(妊婦と3歳未満の子を持つ女性を除く)が動員対象となり、石炭や石油産業に投入されました。
3. 強制移住の目的とヴォルガ ドイツ人共同体の破壊
文書からは、強制移住の目的は、ドイツ人が「破壊分子とスパイ」であったという事実ではなく、むしろ有事の際の安全保障という国家・体制側の論理に求めるべきであると示唆されています。ナチス・ドイツの侵略開始により、ヨーロッパ各地のドイツ人が潜在的なスパイ、「第五列」として警戒されるようになったのと同様に、ソ連政府もヴォルガ地方のドイツ人を危険視したと考えられます。「大テロル」時代の「疑わしき者は罰する」という姿勢が、潜在的な危険性を理由にヴォルガ・ドイツ人を移住させる決定に繋がったと推測されます。 ヴォルガ地方で育まれたドイツ人共同体は、強制移住によって完全に破壊されました。ヴォルガ地方ではドイツ人が固まって居住し、ドイツ語が日常語でしたが、移住先はロシア人やカザフ人など、非ドイツ語話者が多い環境でした。数世帯単位に細分化され、強制移住の過程や労働軍への動員で家族が離散するケースも頻発し、移住先での生活は過酷を極めました。 この強制移住はヴォルガ・ドイツ人に限らず、ウクライナやカフカスなどソ連各地のドイツ人にも及んでおり、ロシアにおけるドイツ人の歴史に大きな転換をもたらしました。 強制移住によって、ドイツ語教育の機会や家庭でのドイツ語環境が失われたことで、ロシア語への同化が加速しました。
V.強制移住の背景と他の民族強制移住との比較
ヴォルガ・ドイツ人強制移住は、単なるドイツ人への弾圧ではなく、スターリン体制下の安全保障上の懸念が背景にあります。ナチス・ドイツの侵攻という有事において、戦線付近に住むドイツ人を潜在的なスパイ(第五列)とみなした政府の判断が、強制移住の主要因でした。1937年の極東朝鮮人強制移住、1941年秋~冬の極東からの移住など、過去の民族強制移住と比較することで、その共通点と相違点を分析しました。特に、作戦トロイカや特別入植制度といったシステムの共通性は注目に値します。 強制移住によって、ヴォルガ・ドイツ人の文化と共同体は完全に破壊されました。 移住後のドイツ人たちは、農業労働力として利用され、後に労働軍に動員されました。これにより、ドイツ語の母語話者率は低下し、同化が進みました。
1. 強制移住の背景 安全保障上の懸念とスターリン体制
ヴォルガ・ドイツ人強制移住の背景には、ドイツ人が「破壊分子とスパイ」であるという「事実」ではなく、むしろソ連政府による安全保障上の懸念がありました。ナチス・ドイツのヨーロッパ侵略開始に伴い、ヨーロッパ各地に散在するドイツ人が潜在的なスパイ、「第五列」として警戒されるようになり、ソ連においても同様の懸念が強まりました。スターリン体制下では、「大テロル」に見られるように、潜在的な可能性だけでも十分に嫌疑の対象となり、国境地帯に居住するヴォルガ・ドイツ人を危険視したと推測されます。このため、国境地帯の安全保障を確保する目的で、強制移住が行われたと考えられます。 1937年の極東朝鮮人強制移住なども、国境地帯の安全保障を目的とした民族強制移住の例として挙げられます。キチヒン中佐の証言によれば、モロトフとベリヤが1941年7月にエンゲリス市を視察し、ヴォルガ地方におけるドイツ人スパイの暗躍に関する情報を確かめたとされています。もしこの証言が事実であれば、ソ連当局は7月の段階でドイツ人対策の必要性を認識しており、この視察が強制移住計画の決定に繋がった可能性があります。しかし、この証言を裏付ける文書は現時点で見つかっておらず、その信憑性については疑問が残ります。
2. 他の民族強制移住との比較 共通点と相違点
ヴォルガ・ドイツ人強制移住は、ソ連における他の民族強制移住と比較することで、その背景や特徴をより深く理解することができます。例えば、1941年10月25日までに、17万1781人が124本の列車で極東からウズベク共和国とカザフ共和国へ移住させられました。この極東からの移住とヴォルガ・ドイツ人強制移住の間には、移送列車の編成、財産に対する引換証の発行、党・執行委員会・NKVDから構成される地区トロイカの存在など、多くの共通点が見られます。しかし、移住作戦の期間は、極東からの移住の方がドイツ人強制移住より長く、経験の「蓄積途上」であったことがうかがえます。 また、第二次大戦勃発直後にソ連に併合されたモルドヴァ、ベラルーシ、西ウクライナ、バルト諸国からの強制移住(1941年5~6月)でも、ヴォルガ・ドイツ人強制移住と同様の列車運行記録が作成されていました。さらに、ドイツ人や極東朝鮮人の強制移住作戦で重要な役割を果たした「トロイカ」は、1930年代後半の「大テロル」で死刑や長期刑判決を下した組織と関連がある可能性も示唆され、強制移住後の「特別入植」も元来は富農撲滅政策で用いられていた制度です。これらのことから、ヴォルガ・ドイツ人強制移住は過去の政策や経験と無関係ではなく、それらが継続的に利用されていることが分かります。
3. 強制移住後の土地利用と経済的影響
ヴォルガ・ドイツ人が移住した後、その土地は戦線から疎開してきた人々が入植する計画でした。「8月26日決定」では、疎開農民のためにドイツ人が残した建物、家畜、土地を利用すると記されており、8月27日付のヴォルガ・ドイツ人自治共和国決定でも、1万7250人をドイツ人移住後の村落へ送り込むことが定められていました。 しかし、ナチス・ドイツの侵攻のスピードが速かったため、計画通りには進みませんでした。農民の疎開は9月5日から15日に行われる予定でしたが、農民自身も移住に難色を示したため、入植は遅れました。当局は緊急措置として近隣地区からロシア人農民3万人を動員しましたが、十分ではありませんでした。サラトフ州党委員会の会議では、旧ドイツ人村での収穫の遅れ、収穫物の盗難や腐敗、家畜の死亡などが報告され、大きな経済的損害が発生しました。 ヴォルガ・ドイツ人の強制移住によって、地域の産業は破壊され、穀物数万トンもの損失など、多大な経済的損害が発生したと結論付けることができます。
