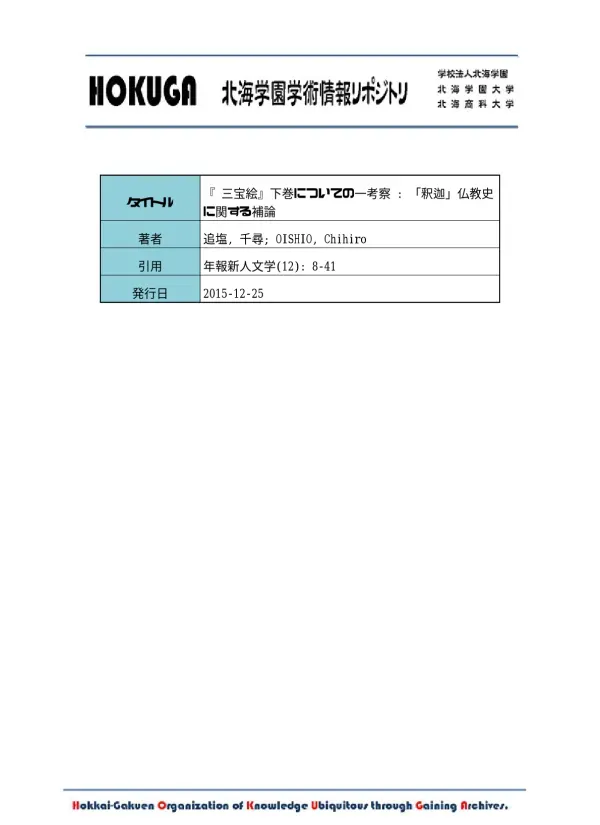
三宝絵と釈迦仏教:下巻仏事の考察
文書情報
| 著者 | 筆者 |
| 学校 | 大学名(本文からは特定できません) |
| 専攻 | 仏教学、日本史、または関連分野 |
| 出版年 | 本文からは特定できません |
| 場所 | 出版場所(本文からは特定できません) |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.07 MB |
概要
I. 源為憲 作 三宝絵 における 釈迦 と 仏事 の考察
本稿は、源為憲が制作した『三宝絵』の下巻に焦点を当て、描かれた釈迦仏教の展開と様々な仏事の意義を考察する。特に、釈迦の描かれ方、および涅槃会などの主要な仏事の記述に注目し、当時の貴族社会における仏教理解や信仰の実態を解明することを目的とする。寛平縁起などの史料も参照しながら、『三宝絵』が示す釈迦像と、仏事への参加を促す姿勢、そして尊子内親王への配慮といった点について分析する。
1. 三宝絵 の全体構想と研究目的
本稿は、源為憲作『三宝絵』の下巻を対象とし、その特質に関する考察を深めることを目的とする。先行研究では紙数の制約などから十分な検討がなされなかった点を踏まえ、釈迦仏教の展開や前稿で提示された構想の妥当性を検証する。特に、阿弥陀仏や浄土が中心的に語られていない点について、藤村安芸子氏の説(尊子内親王への配慮)を参考にしながら、三宝絵全体の構成における下巻の位置づけを再検討する。下巻は仏事の解説が目的だが、それらの法会への参加を促す意図も読み取れる。三国仏法史の体裁を取りつつも日本仏教に重点が置かれている点、インドや中国に関する記述が不十分である点なども分析対象となる。本稿は、三宝絵全体の構想検討という点では不十分であり、日本仏教の展開を完全に読み解くまでには至らないものの、釈迦に関する記述や仏事の解説を通して、当時の仏教観の一端を明らかにすることを目指す。
2. 三宝絵 における釈迦像の考察
『三宝絵』において、釈迦は中巻の序や下巻の随所で経典などを介して間接的に登場する。興味深いのは、インド編では直接語られず、日本編で大きく語られている点である。これは、釈迦の教えが日本において息づいていることを強調していると言える。釈迦の入滅後も永遠不滅であり、常に人々の心の中にあるという考え方が、上巻の序文にある「永く隠レ給ヒニキト不可云ズ。仏ハ常ニ我ガ心ニ伊坐ス。」という記述に端的に示されている。また、仏像は仏の仮の姿(垂迹)であるという認識が、上巻序文の「権リニ丈六ヲ示シ」という記述や、藤村氏の指摘する中巻最終話(法華八講)における記述から推察できる。 寛平縁起に拠ったと思われる記述からも、為憲の仏像観の一端がうかがえる。仏像の霊験については、大安寺以外では長谷観音の霊験くらいしか語られていない点が注目される。
3. 下巻に描かれた仏事の分析 種類と意義
『三宝絵』下巻には、修正月、比叡懺法、温室、布薩、修二月、西院阿難悔過、山階寺涅槃会、石塔、法華寺華厳会、薬師寺万灯会、比叡舎利会、灌仏、比叡受戒、施米など、三十一種類の仏事が記述されている。これらの仏事の解説を通して、当時の仏教実践の姿が明らかになる。涅槃会は、釈迦の死を悲嘆するのではなく、一切衆生に仏性があることを説く機会として捉えられており、「一切衆生悉有仏性」という表現に象徴される本覚論的な思想が垣間見える。舎利会についても、比叡山への参詣が難しい女性のために、唐招提寺や花山寺への参加を勧めている記述が見られる。また、志賀伝法会や比叡坂本勧学会など、特定寺院だけでなく広範囲に及ぶ仏事も描かれている。これらの仏事を通して、当時の仏教の広がりや人々の信仰の様子を知ることができる。
4. 仏事における僧侶の役割と功徳の受容
『三宝絵』では、仏事への参加を通じて得られる功徳は、僧侶の読経や説法といった「声(音)」の功徳だけでなく、僧侶から参加者への施し(法施)も重要な要素となっている。修正月、温室、施米などでは物質的な布施、文殊会などでは三帰五戒を授ける宗教的な法施が行われていた。布薩は僧侶による懺悔の行為で一般には開放されていなかったが、六月三十日だけは一般の人々が参加できた。参加者は仏事を通して感覚的・審美的な体験を得ており、教義の深い理解は必ずしも重視されていない点が特徴的である。勧学会は、比叡山僧と大学学生が対等に交流する場であり、互いに施し合う関係ではない点が特異である。人々の仏事への参加が促されており、僧への布施と僧からの法施を通して功徳を得る仕組みが示されている。
5. 三宝絵 が示す当時の仏教理解と為憲の視点
『三宝絵』は、当時の文人貴族の共通した仏教理解を反映しているが、同時に為憲自身の主体的選択も加わっている。尊子内親王への配慮、和漢の法会の融合、公私の仏事の区別といった三つの視点から分析できる。公的な仏事が多い点は、為憲の文人貴族としての立場や関心が反映していると考えられる。先行する儀式関係書との比較を通して、『三宝絵』が当時の仏教理解を示すだけでなく、為憲独自の視点を反映している点が明らかになる。像法末における教と行の意味、末法克服の可能性を示唆しているという解釈も提示されている。下巻で語られる僧侶の役割の重要性についても、改めて注目すべきである。
II. 三宝絵 における釈迦の描かれ方
『三宝絵』では、釈迦は直接的にはインド編では描かれておらず、むしろ日本編で強調されている。これは、釈迦の教えが日本において息づいていることを示唆していると考えられる。また、釈迦の入滅後も永遠不滅であり、人々の心に常に存在するという考え方が、上巻序文や涅槃会の記述を通じて示されている。仏像についても、仮の姿(垂迹)としての解釈が示唆されている。
1. 三宝絵 における釈迦の位置づけ 日本編での強調
『三宝絵』では釈迦は、インド編においては直接的に描かれず、むしろ日本編において大きく取り上げられている。これは、釈迦の教えが日本において深く根付いていることを強調する表現方法と言える。在世中の釈迦とその弟子らは、下巻の仏事の記述の中で、経典からの引用を中心に間接的に登場する。中巻の序では釈迦一代の教法が五時教・四処十六会として説明されている。このように、釈迦は直接的な描写よりも、経典の引用や仏事の記述を通して、その存在感を示していると言える。この手法は、当時の日本における仏教受容の特殊な形態を反映している可能性を示唆している。
2. 釈迦の永遠性と仏像観 上巻序文と仏像の解釈
『三宝絵』の上巻序文には、「永く隠レ給ヒニキト不可云ズ。仏ハ常ニ我ガ心ニ伊坐ス。」という記述があり、釈迦は命に限りはあったものの、永遠不滅であり、常に人々の心の中に存在すると解釈できる。この考え方は、涅槃会などの仏事の記述にも反映されている。また、上巻序文の「権リニ丈六ヲ示シ」という記述や、藤村氏が指摘する中巻最終話(法華八講)の記述から、仏像は仏の仮の姿(垂迹)であるという認識が示唆されている。 寛平縁起とほぼ同文である記述からも、為憲が依拠した仏像観がうかがえる。ただし、『三宝絵』において仏像の霊験などが語られるのは、大安寺以外では長谷菩薩戒での長谷観音の霊験くらいであり、仏像そのものの霊験については詳細な言及は少ない。
3. 釈迦の死と涅槃会の意義 仏性常住の思想
『三宝絵』では、釈迦の死は避けられない事実として記述されているものの、涅槃会の記述においては、釈迦の死を悲嘆するのではなく、一切衆生に仏性があることを説く機会として捉えている。涅槃経を引用し、「一切衆生ニハミナ仏ノタネア リ。皆マサニ仏ニナルベシ」と仏性常住の理を説き、涅槃会への参加と涅槃経の聴聞を勧めている。この記述には、「一切衆生悉有仏性」という成句に象徴される本覚論ともいうべき思想が見出せる。釈迦の死は、その教えの永遠性を強調する上で、むしろ希薄化される方向へと導かれていると言える。
III. 三宝絵 に描かれた主要な仏事
下巻では、修正会、温室、布薩、比叡山の舎利会、涅槃会、灌仏会、長谷菩薩戒、文殊会、盂蘭盆など、様々な仏事が詳細に描かれている。これらの仏事は、単なる説明にとどまらず、人々の参加を促す記述が見られる。特に、女性が参加できない比叡山の舎利会の代わりに、唐招提寺や花山寺での参加を勧めている点などが注目される。これらの仏事を通して、当時の貴族社会における仏教実践の姿が読み取れる。
1. 主要仏事の概要と特徴 多様な仏事の記述と人々への訴え
『三宝絵』下巻には、修正会、比叡懺法、温室、布薩、修二月、西院阿難悔過、山階寺涅槃会、石塔、法華寺華厳会、薬師寺万灯会、比叡舎利会、灌仏、比叡受戒、施米など、多数の仏事が詳細に記述されている。これらの仏事には、特定寺院で行われるものと、諸寺・諸国で行われるものがあり、地域的な広がりも示唆されている。特徴的なのは、単なる仏事の説明にとどまらず、人々の参加を促す記述が多い点である。例えば、比叡山の舎利会に参加できない女性のために、唐招提寺や花山寺での参加を勧める記述が見られる。また、志賀伝法会では、人々の参加を明確に促している。これらの記述から、『三宝絵』が当時の仏教実践の姿を伝え、人々の信仰生活に深く関与しようとした意図が読み取れる。
2. 涅槃会と仏性常住の思想 釈迦の死を超えた意義
涅槃会は、釈迦の死を悲嘆するのではなく、一切衆生に仏性があることを説く機会として捉えられている。涅槃経の記述を引用し、「一切衆生ニハミナ仏ノタネア リ。皆マサニ仏ニナルベシ」と説き、涅槃会への参加と涅槃経の聴聞を勧めている。この記述からは、「一切衆生悉有仏性」という成句に象徴される本覚論的な思想を読み取ることができる。釈迦の死は、その教えの永遠性を強調する上で、むしろ希薄化され、仏性常住の理がより強く強調されていると言える。涅槃経の功徳を説き、涅槃会への参加を勧めることで、人々に仏性常住の理を啓蒙しようとする姿勢が見て取れる。
3. 舎利会と比叡山 女性への配慮と寺院の代替案
比叡山の舎利会は女性が参加できないため、『三宝絵』では、女性への配慮として唐招提寺や花山寺(元慶寺)での舎利会への参加を勧めている点が注目される。これは、特定の寺院の仏事だけでなく、同様の仏事を営む他の寺院も紹介することで、より多くの人が仏事に参加できるよう配慮していることを示している。他の仏事においても、比叡灌頂では東寺・法性寺、比叡霜月会(大師供)では天台の寺々などが紹介されており、様々な事情で特定の寺院に参詣できない場合の代替案を示していると考えられる。このように、『三宝絵』は特定の寺院に限定せず、仏教の広がりを反映した記述となっている。
4. その他の主要仏事 地域的広がりと参加者の多様性
『三宝絵』下巻には、修正会、温室、布薩、灌仏、長谷寺菩薩戒、施米、文殊会、盂蘭盆、比叡霜月会、仏名会など、多くの仏事が記述されている。これらの仏事の中には、「諸寺」「諸国」といった記述があり、地域的に広く浸透していたことがわかる。また、参加者も老若男女と多様である。特に長谷菩薩戒は一般の人々が広く受戒できたと考えられる。一方、布薩は僧侶による懺悔の行為で、一般の人々は参加できなかった。しかし、六月三十日だけは一般に開放されていた。比叡坂本勧学会は、比叡山僧と大学学生による会合であり、特定寺院を会場としていたわけではない。このように、多様な仏事の記述を通して、当時の仏教の広がりと人々の信仰の様子を示している。
IV.仏事と功徳 僧侶の役割
『三宝絵』における仏事への参加は、感覚的・審美的な体験として捉えられており、教義の理解よりも、僧侶による読経や儀式そのものの効果(功徳)が重視されている。僧侶は読経や説法を通して功徳をもたらし、参加者への法施を行う役割を担う。施米や文殊会などでは、物質的な布施と宗教的な法施が結びついている様子がわかる。また、勧学会のような僧侶と俗人が共に参加する会合も存在し、多様な仏教実践の形態が示されている。
1. 仏事参加と功徳 感覚的 審美的な受容
『三宝絵』では、仏事への参加は、教義の深い理解よりも、感覚的・審美的な体験として捉えられている。参加者が仏事から受ける功徳は、僧侶による読経や説法の「音」から得られるものだけでなく、僧侶から参加者への施し(法施)も重要な要素である。 涅槃会では、僧侶の説法の理解よりも、読経や経文・偈の賛嘆する「音」自体が重視されている。文殊会では、僧侶が三帰五戒を授けるなど、物質的な布施に加え宗教的な法施も行われていた。 長谷菩薩戒や布薩なども、僧侶による行為を通して参加者に功徳がもたらされる例と言える。このように、仏事の功徳は、教義理解よりも、感覚的な体験や儀式そのものへの参加を通して得られるものとして描かれている。
2. 僧侶の役割 読経 説法と法施
仏事において僧侶は中心的な役割を担っており、その行為を通して参加者に功徳がもたらされる。山階寺涅槃会、志賀伝法会、高雄法華会、灌仏、文殊会などでは、僧侶による読経や説法の「声(音)」の功徳が強調されている。涅槃会では本覚論的な思想も説かれているが、参加者にとって重要なのは僧侶の説法の理解ではなく、読経や経文を礼拝し、その音を聴くことである。 文殊会は僧侶から貧民への物質的施しを中核とする一方、「マヅ三帰五戒ヲサヅケ、薬師文殊ヲトナヘ」る宗教的施し(法施)も伴う。この法施は、諸の施の中で最も重要なものとされている。僧侶は、読経・説法を通じて功徳をもたらすだけでなく、法施によって人々と結縁する役割を担っている。
3. 布施と法施 僧侶と民衆の交流
僧侶と民衆の交流において、布施は重要な要素である。修正会、温室、施米などは僧への布施の例である。一方、僧侶は法施を行うことで民衆と結縁する。布薩は僧侶による懺悔の行為で一般には開放されていなかったが、六月三十日だけは一般に開放され、おみくじを引くなどして功徳を得ることができた。文殊会では、僧侶が三帰五戒を授け、薬師文殊をとなえるなど、宗教的な法施を通して功徳を分かち合う様子が描かれている。 志賀伝法会では、大智度論を引用し、僧侶だけでなく、布施を行う人々にも功徳があることが強調されている。このように、布施と法施の相互作用を通して、僧侶と民衆が結縁し、功徳が共有される仕組みが示されている。
4. 勧学会 僧侶と俗人の対等な交流
勧学会は、比叡山僧と大学学生による会合であり、寺院は定まっていない。参加する僧俗は対等であり、互いに施す・施されるという関係ではない。得られる功徳は、僧侶の偈頌や俗人の詩作といった、それぞれの参加者の貢献によるものである。これは、他の仏事とは異なり、僧侶と俗人が対等な立場で交流し、それぞれの能力や才能を活かしながら功徳を得る、独特の形態と言える。この勧学会は、当時の仏教界における僧俗間の交流や、仏教信仰の多様なあり方を示す重要な事例である。
V. 三宝絵 と当時の仏教理解
『三宝絵』は、当時の貴族社会の共通した仏教理解を反映しているだけでなく、源為憲自身の主体的選択も加わっている。尊子内親王という若い女性への配慮や、朝廷・国衙に関わる公的な仏事と私的な仏事の区別などが、為憲の立場や関心のあり方を示唆する。末法思想が広まる中で、浄土信仰に頼らずとも仏教の教えを実践できることを示唆しているとも解釈できる。
1. 当時の貴族社会における仏教受容 感覚と審美の重視
『三宝絵』は、当時の貴族社会における仏教理解の一端を示している。同時代の仏教受容の形態として、仏事への参加が、教義の内容理解よりも、感覚的・審美的な体験として重視されていた点が挙げられる。仏事における功徳は、僧侶の読経・説法の「音」といった聴覚的な要素や、儀式の荘厳さといった視覚的な要素を通して得られるものとして捉えられていたと考えられる。 そのため、仏事の内容を深く理解することが必ずしも重視されていなかったと考えられる。これは、当時の貴族社会における仏教信仰が、教義の理解よりも、儀式や感覚的な体験を重視する傾向にあったことを示唆している。
2. 僧侶の役割 読経 説法による功徳と法施の重要性
『三宝絵』において、僧侶は仏事の中心的存在であり、読経・説法を通して功徳をもたらす重要な役割を担っていた。多くの仏事において、僧侶による読経や説法の「声(音)」が功徳の源泉として強調されている。涅槃会においても、僧侶が唱える涅槃経を聴聞することが勧められている。 しかし、功徳は「音」だけから得られるものではなく、僧侶から参加者への施し、つまり法施も重要な要素である。文殊会などでは、僧侶が三帰五戒を授けるなど、宗教的な法施も行われていた。この法施は、物質的な布施と並んで、あるいはそれ以上に重要なものとして位置づけられていたと考えられる。
3. 公私の仏事と為憲の立場 朝廷 国衙と私的な信仰
『三宝絵』に描かれる仏事には、朝廷や国衙が関わる公的なものと、私的なものがある。公的な仏事が多い点は、為憲の文人貴族としての立場や、当時の社会構造を反映していると考えられる。 為憲自身の仏教理解は、単に当時の貴族社会の共通認識を反映したものではなく、彼自身の主体的選択も加わった結果であると言える。 『三宝絵』全体の目的は、総序にあるように尊子内親王の心を励まし慰めることにあったと考えられるが、同時に、当時の仏教理解を反映させつつ、為憲自身の仏教観も表現されていると言える。
4. 末法思想と 三宝絵 浄土信仰によらない末法克服の可能性
『三宝絵』は、末法思想が広まっていた当時の社会状況の中で制作されたと考えられる。しかし、同絵巻は浄土信仰などに依拠することなく、仏事への参加を通して末法を克服できる可能性を示唆していると言える。 これは、当時盛んだった浄土信仰とは異なるアプローチであり、為憲独自の仏教理解を示している。 『三宝絵』全体を通して、日本における仏教の繁栄の様子が示されているとすれば、為憲は像法末において教と行の持つ意味や機能を提示し、末法克服の可能性を示そうとしたのではないかと推測できる。この点は、今後の研究においてさらに検討を進める必要がある。
