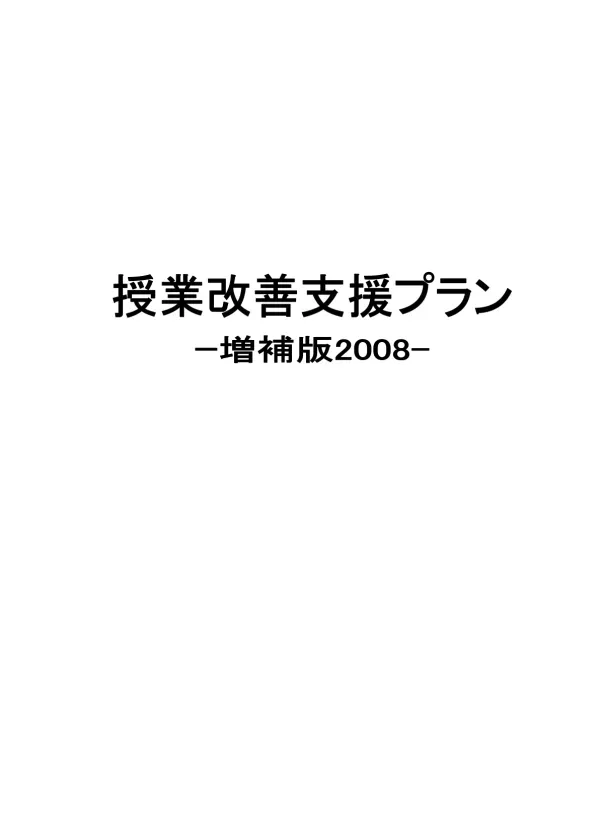
三重県学力向上:授業改善支援プラン
文書情報
| 著者 | 三重県教育委員会 |
| instructor | 森脇健夫 (三重大学教育学部教授) |
| 学校 | 三重県教育委員会 |
| 専攻 | 教育学 |
| 出版年 | 平成20年度(2008年度) |
| 文書タイプ | 報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 5.91 MB |
概要
I.全国学力 学習状況調査結果分析と授業改善
本資料は、全国学力・学習状況調査の結果を基に、授業改善のための分析と具体的な取り組みを提示しています。特に、正答率が低い問題(読解力、表現力、思考力を問う問題など)に焦点を当て、その課題を明らかにしています。語彙力不足や、条件に沿った記述が苦手な生徒が多いことなどが指摘されており、国語、算数/数学両方の教科で改善が必要であることが示唆されています。三重県や津市の教育委員会が作成した指導資料なども活用し、指導改善に繋げるための具体的な提案がなされています。特に、書く活動の充実や、家庭学習との連携が重要視されています。
1. 全国学力 学習状況調査の結果概要と課題
本資料は、全国学力・学習状況調査の結果に基づき、児童生徒の学力状況と課題を分析しています。特に、正答率が低かった問題について詳細な分析が行われ、その原因究明と改善策が提案されています。問題1では、インタビューにおける質問の仕方や内容の評価に関する問題で、正答率は比較的高いものの、無回答率も高く課題が見られました。問題2は、物語文の読解力、登場人物の心情把握、条件に沿った記述能力を問う問題で、正答率は低い結果となりました。特に、登場人物の心情を的確に捉え、条件に沿って記述することに課題が見られました。問題3は、資料からの情報抽出、整理、自分の考えを記述する能力を問う問題で、正答率は非常に低く、無回答率も高くなっています。これは、資料から必要な情報を的確に選び出し、自分の考えを論理的に記述する能力に課題があることを示しています。これらの結果から、児童生徒の読解力、表現力、思考力、特に条件に沿って記述する能力の向上が喫緊の課題であることが明らかになりました。
2. 読解力 表現力 思考力の現状と具体的な課題
調査結果の分析から、児童生徒の読解力、表現力、思考力に課題があることが示唆されました。具体的には、物語文において人物の心情や場面の様子を叙述から正確にとらえ、条件に沿って記述する能力に課題が見られました。正答率が低い問題には、「〜を書く」といった説明を求める問題が多く、記述能力の育成が重要であることが示唆されます。また、複数の資料を読み解き、それらを関連付けて自分の考えを記述する能力についても課題が見られました。これは、情報収集能力や論理的思考力、表現力の不足を示唆しており、多様なテキストを読み解く能力の育成が重要であることがわかります。さらに、語彙力不足も課題の一つとして挙げられ、多くの言葉に触れさせ、言葉の意味を深く理解させる指導の必要性が強調されています。特に、漢字の意味を手がかりに語句の意味を推測し、辞書を活用する習慣を育むことが重要であるとされています。
3. 授業改善に向けた具体的な方策と指導のポイント
調査結果を踏まえ、授業改善に向けた具体的な方策が提案されています。読解力の向上には、多様な読み方(登場人物への感情移入だけでなく、客観的な視点からの批評など)を取り入れること、説明的文章の学習を充実させること、古典作品の学習にも配慮することが重要です。表現力、思考力の向上には、書く活動の充実が不可欠です。児童が意欲的に書く活動に取り組めるよう、目的意識を持たせ、丁寧な指導を行うことが大切です。また、文章の推敲においては、主語と述語の関係、接続助詞の使い方など、様々な観点を意識させる指導が必要になります。さらに、友だちの作品を参考にしたり、感想を出し合ったりする活動を通して、表現のよさや効果を学ぶことが提案されています。 これらの指導を通して、児童生徒の読解力、表現力、思考力を総合的に高めるための具体的な方策が示されています。
4. 家庭学習の役割と教員の研修 連携の重要性
家庭学習の重要性も強調されています。授業内容と関連させた発展的な課題を与えたり、保護者と連携して家庭学習を促すことが、児童生徒の学習意欲向上に繋がると考えられています。しかし、家庭学習を単なる習慣づけとして捉えるのではなく、児童生徒の自律性を尊重し、発展的に考えさせる課題を提示することが重要であると指摘されています。教員においては、校内外の研修や研究会への積極的な参加、指導計画作成における教職員間の協力体制の構築が、児童生徒の意欲向上に繋がるとして重要視されています。また、津市教育委員会が作成した指導資料などの活用も推奨されており、学校全体で授業改善に取り組む姿勢が求められています。これらの取り組みを通して、継続的な検証改善サイクルを確立し、児童生徒の学力向上を図ることが目指されています。
II.課題の明確化と改善策の提案
調査結果からは、読解力、特に非連続型テキストの読解や、表現力、思考力の不足が大きな課題として浮き彫りになっています。正答率の低い問題においては、条件に合わせた記述や、複数の資料を関連付けて読み解く能力の低さが顕著です。そのため、授業改善においては、主体的な学習態度の育成、発問による思考の深化、十分な発言・活動時間の確保などが重要になります。また、国語科だけでなく、すべての教科で書く活動を学習過程に位置づけることが提言されています。さらに、家庭学習における発展的な課題の提示や、保護者への効果的な働きかけも重要であると結論づけています。
1. 読解力 特に条件付き記述問題における課題
全国学力学習状況調査の結果分析から、児童生徒の読解力、特に条件に沿った記述を行う能力に課題が見られました。問題2では、物語文の読解を基に、本文中の言葉を用い、特定の条件(例えば「〜こと」で終わるように書く)を満たしながら記述する問題で正答率が低く、課題が明確になりました。多くの児童が、登場人物の心情を捉えているにも関わらず、条件を満たした記述ができていない、あるいは条件を無視した回答をしているケースが多く見られました。これは、指示された条件を正確に理解し、それに沿って記述する能力の不足を示しています。また、無回答率も高く、問題文の指示を理解し、記述するという行為自体に抵抗感を持っている児童も少なくないと推測されます。このことから、単に物語文を読解する能力だけでなく、目的や意図に応じて、条件や字数制限などを考慮しながら、効果的に文章を作成する能力の育成が重要であることが示唆されます。これは、単元の指導計画において、読む活動だけでなく、書く活動の指導を効果的に組み合わせる必要があることを意味しています。
2. 多様なテキストの読解と情報活用能力の不足
問題3では、図書館だよりやグラフなどの複数の資料から必要な情報を取り出し、整理し、自分の考えを記述する問題で正答率が極めて低くなりました。これは、複数の資料を関連付けて読み解き、そこから得た情報を基に自分の考えを明確に表現する能力の不足を示しています。特に、グラフからの情報読み取りや、その情報を基にした考察、そしてそれを80字以上100字以内に記述するという条件を満たすことに困難を示す児童が多く見られました。無回答率も高く、課題の深刻さがわかります。この課題を克服するためには、様々な種類の資料(図表、グラフなど)を読み解くための指導を充実させることが重要です。単に情報を抽出するだけでなく、複数の資料を関連付けて考え、自分の考えを明確に記述する練習を積む必要があります。また、目的や意図に合った情報選択、整理、そして条件に則った表現方法を学ぶための指導が不可欠です。これは、国語科だけでなく、社会科や理科など、あらゆる教科における情報活用能力の育成に繋がる重要な課題です。
3. 書く活動の充実と指導方法の改善
調査結果から明らかになった課題を踏まえ、書く活動の充実と指導方法の改善が強く求められています。 児童が意欲的に書く活動に取り組むためには、教師による丁寧な指導が不可欠です。児童が相手や目的意識を持って、書きたい、伝えたいという気持ちになれるような授業展開や、一人ひとりに寄り添ったフィードバックが重要になります。単に書く技術を教えるだけでなく、何をどのように書けばよいかを具体的に指導し、児童が自分の考えを明確に表現できるようサポートすることが大切です。また、文章の推敲においては、主語と述語の関係、接続助詞、句読点の使い方、常体と敬体の使い分けなど、様々な観点を意識した指導を行う必要があります。さらに、誤字脱字だけでなく、表現のよさや効果を評価する視点も取り入れることで、より質の高い文章作成能力の育成が期待できます。これらの改善策により、児童の読解力や思考力を高め、表現力を豊かに育むことを目指す必要があります。
III.教員研修と学校全体の取り組み
教員の研修参加の促進と、学校全体での教育目標の共有が、児童生徒の学力向上に大きく影響することが示唆されています。授業改善のための研修会への積極的な参加が推奨され、その効果を教育活動に反映させることが重要視されています。特に、基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力の育成、主体的に学習に取り組む態度の育成、そして言語活動の充実が、新学習指導要領の理念に基づいた授業改善の方向性として示されています。また、教職員間の協力体制の構築も、効果的な指導改善に不可欠です。さらに、特別支援教育への理解を深める研修も重要視されています。
1. 教員研修の重要性と具体的な取り組み
学力向上のためには、教員の継続的な研修が不可欠であることが強調されています。資料では、教職員が校内外の研修や研究会に積極的に参加し、その成果を教育活動に反映させていることが、児童生徒の意欲向上に繋がる可能性を示唆しています。具体的な研修の取り組みとして、三重県総合教育センターや志摩市教育委員会、三重大学の講師を招いた校内研修などが紹介されています。研修の内容は、新学習指導要領に基づき、「基礎的・基本的な知識・技能の習得」、「思考力・判断力・表現力の育成」、「主体的に学習に取り組む態度」、「言語活動の充実」を目標に据え、特に「主体的な学習態度」の育成を重視した内容となっています。研修では、小学校国語A問題を分析するなど、具体的な問題解決に繋がる実践的な内容が重視されていることがわかります。また、外部講師を招へいするなど、研修の質を高めるための積極的な取り組みが行われている点が示されています。さらに、保護者への家庭学習促進のための働きかけについても言及されており、学校と家庭の連携の重要性が示唆されています。
2. 学校全体の教育目標の共有と協働体制の構築
学力向上に向けた取り組みを効果的に推進するためには、学校全体の教育目標の共有と教職員間の連携が重要であると述べられています。資料では、「学校の教育目標やその達成に向けた方策について、全教職員の間で共有し、取り組んでいるか」という点に言及しており、教育目標の共有と学校全体の取り組みの重要性が強調されています。これは、教職員同士が協力し合い、指導計画を作成し、授業改善に熱心に取り組むことが、児童生徒の意欲向上に繋がるとの考えに基づいています。具体的には、指導計画の作成にあたって教職員同士が協力し合っていること、そして、校内外の研修や研究会に参加し、その成果を教育活動に積極的に反映させていることが、児童生徒の学力向上に資する取り組みとして挙げられています。これらの取り組みを通して、学校全体で一貫性のある教育活動を展開し、児童生徒の成長を支援していくことが目指されています。さらに、特別支援教育についての研修も重要視されており、インクルーシブ教育への意識の高さがうかがえます。
3. 研修時間の確保と体制整備の必要性
教員の研修参加を促進するためには、教育委員会を含めた体制として、教員に研修時間を保証する配慮が必要不可欠であると指摘されています。教員の多忙化や休日におけるクラブ活動などの兼務により、研修会への参加が困難であるという現実的な問題が提示されています。しかし、研修への参加は、教員自身の成長に大きく貢献し、実践的な知識やスキルを習得できる貴重な機会であると強調されています。資料では、研修会への参加は、単に知識を得るだけでなく、教師自身の理解度を明確にし、自己成長に繋がる効果的な手段であることを示唆しています。そのため、研修時間の確保は、教員の専門性向上という観点からも、非常に重要な課題として捉えられています。 教育委員会や学校は、教員の研修参加を積極的に支援するための体制整備を行う必要があり、時間的な制約を超えた効果的な研修システムの構築が求められていると言えるでしょう。
IV.関連性の高い項目と今後の展望
調査結果の分析から、生徒の動機づけと強く関連する項目として、多様な考えを引き出す発問、生徒の発言・活動時間の確保、挑戦的な課題の提示などが挙げられています。一方で、家庭学習の習慣づけを重視するあまり、生徒の学習意欲が低下する傾向もみられました。そのため、家庭学習の課題は、生徒の自律性を尊重し、発展的に考えさせる内容にすることが重要です。 学力調査の結果を効果的に活用し、継続的な検証改善サイクルを確立することで、さらなる学力向上を目指していく必要があります。多気郡教育指導室では、基礎学力検討委員会を設置し、具体的な学習内容の検討を進めています。
1. 生徒の動機づけと関連性の高い指導方法
調査結果からは、生徒の動機づけと強い相関を示す指導方法がいくつか明らかになりました。生徒の様々な考えを引き出したり、思考を深めたりするような発問や指導、生徒の発言や活動時間を確保した授業展開、そして学習規律の徹底などが、生徒の学習意欲を高める上で特に重要であると示唆されています。さらに、生徒に将来の夢や仕事について考えさせる指導、そして発展的な学習の指導も、高い関連性を示しています。これらの指導方法は、生徒自身に課題に取り組ませ、自ら考え、発表させることを重視しており、生徒の主体性を尊重し、自律的な学習を促すアプローチであると言えるでしょう。 また、国語科では発展的な学習指導、書く習慣を付ける授業、様々な文章を読む習慣を付ける授業、算数科では実生活との関連を図った授業が、生徒の動機づけを高める上で有効であることが示されています。これらのことから、生徒が積極的に学び、主体的に課題に取り組む授業設計と、教員の積極的な関わりが、生徒の学習意欲の向上に大きく貢献することがわかります。
2. 家庭学習の効果的な実施と学習習慣の醸成
家庭学習については、授業内容と関連させた発展的な課題を与え、生徒が自ら考え、学ぶ機会を提供することが重要であることが示されています。 調査では、家庭学習のねらいが「学習習慣づけ」に偏っている場合、生徒の勉強への熱意は高くないという負の相関が見られました。これは、家庭学習が生徒にとって「やらされている」と感じられるものでは、かえって学習意欲を低下させる可能性を示唆しています。家庭学習は、生徒が自主的に取り組めるような内容にすること、そして「自律性」を感じられるような課題設定を行うことが重要になります。 一方、学級全体で取り組む課題やテーマ、朝の読書時間の設定、様々な文章を読む習慣付けといった取り組みは、生徒の動機づけと正の相関を示しており、これらの取り組みが学習意欲を高める上で有効であることが示唆されています。家庭学習においても、これらの要素を考慮した課題設計を行うことで、より効果的な学習習慣の醸成が期待できます。
3. 今後の展望と継続的な検証改善サイクルの必要性
本調査の結果を踏まえ、今後、より効果的な教育活動を展開していくためには、継続的な検証と改善サイクルの確立が不可欠です。津市教育委員会が作成した指導資料を参考にしている学校が多い一方、「取組を対象学年だけでなく学校全体で行うこと」、「調査問題を授業の中で活用すること」については、学校間の取り組み状況に差が見られました。今後、これらの点について、学校間の連携を強化し、より一貫性のある取り組みを進める必要があります。また、多気郡教育指導室では、多気郡教育委員会連合会の依頼を受け、「基礎学力検討委員会」を設置し、国・県・郡レベルでの学力調査の結果を踏まえた分析・検討を行っています。これは、地域の実情に合わせた具体的な学習指導内容を検討し、現場の先生方が活用しやすい資料を作成していくための取り組みです。 これらの継続的な取り組みを通じて、児童生徒の学力向上を目指していく必要があります。
