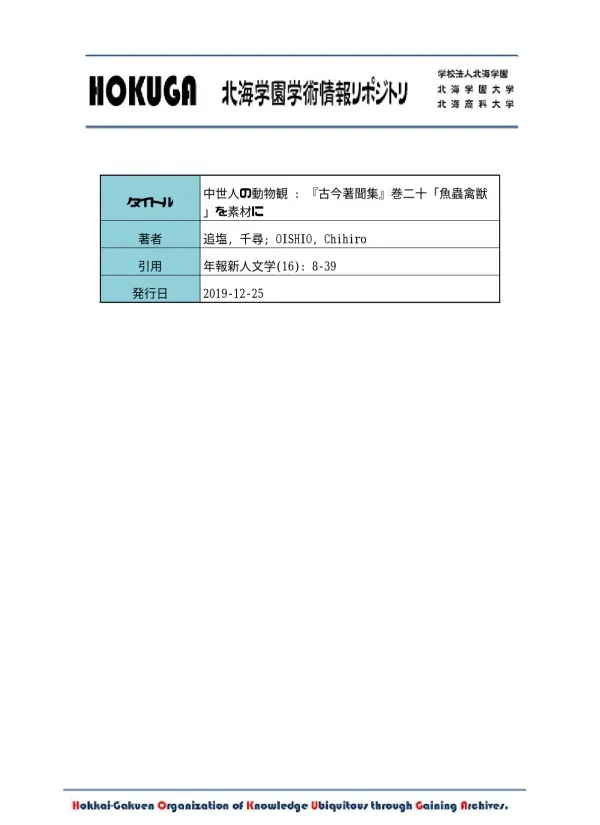
中世動物観:『古今著聞集』巻二十
文書情報
| 学校 | 大学名(本文からは特定できません) |
| 専攻 | 歴史学 |
| 出版年 | 不明(1980年代後半以降と推測できる記述あり) |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 905.10 KB |
概要
I. 古今著聞集巻二十における動物譚の分析
本稿は、中世説話集である『古今著聞集』(1254年成立)の巻二十「魚蟲禽獣」を分析対象とし、鎌倉時代を含む中世における人間と動物の関係、特に動物に関する知識や認識について考察する。特に、巻二十に多く収録されている動物譚に着目し、動物の特性、存在形態(野生・飼育など)、人間との関わり方などを検討する。先行研究として、中村禎里氏の一連の研究が挙げられるが、巻二十に関する具体的な分析は少ない。本研究では、巻二十に収録された説話(約70話)を素材に、動物譚における動物の描写から中世の人々の動物観を探る。
1. 研究の目的と先行研究
本稿は、中世における人間と動物の関係を、『古今著聞集』巻二十「魚蟲禽獣」を素材に検討することを目的とする。既存研究においては、時代を区切って掘り下げた研究は少なく、それぞれの時代に即した研究の必要性が指摘されている。特に『古今著聞集』巻二十は、鎌倉期の説話が過半数を占め、貴族社会の外側へと視野を広げているとされる(7)。西尾光一氏は巻二十を多彩で充実した巻と評価する(8)ものの、永積・西尾両氏とも具体的な分析は行なっていない。歴史学的研究は1980年代後半から本格化し、近年盛んになっていると言える(3)。中村禎里氏による一連の研究は人間と動物の関係史研究において重要な役割を果たしている(4)が、多くの研究は古代から近現代までの通史的なものが多い(5)。本稿では、巻二十の基本的な整理を行い、今後の検討方向を明らかにするとともに、『古今著聞集』の貴族的な百科事典的性格を踏まえ、中世において必要とされていた動物に関する知識を探る。
2. 巻二十の構成と収録内容
巻二十は、序文に相当する第六七二話から始まり、計約70話が収録されている。ただし、七二二~七二六話(後世の抄入)は考察対象から除外する。各説話の動物を「魚・虫・禽・獣」に分類するが、『古今著聞集』自体はこのような分類をしていないため、本稿では筆者による分類を用いる。虫偏のつく動物(蛇や蛙など)の分類には、『倭名類聚抄』(源順撰、十世紀初頭成立)巻十九「蟲・豸類」の基準(有足・無足)を参考にしている。巻二十には、飼い猫の不思議な現象(六八六話)や、狐の自己犠牲(六八一話)など、多様な動物譚が収録されている。これらの説話を通して、中世の人々の動物観を探ることが本研究の重要な課題である。また、巻二十の説話の舞台は、京都とその周辺地域(摂津、山城、近江、奈良など)が大部分を占める点にも注目する必要がある。
3.先行研究との比較検討
本研究では、『古今著聞集』巻二十の説話と先行する説話との比較検討も行う。例えば、六七五話(醍醐天皇と犬)は、『富家語』や『古事談』と比較検討することで、『古今著聞集』における動物譚の独自性を明らかにする。また、六七三話(龍馬)は、『今昔物語集』巻十一―六と比較することで、『古今著聞集』における動物の描写の差異を分析する。その他にも、複数の先行説話を持つ話をいくつか取り上げ、先行説話において動物が主役でないものが、『古今著聞集』では動物説話として分類されている点を明らかにする。これらの比較を通して、『古今著聞集』巻二十における動物譚の選定基準や、動物の描写における独自性を明らかにする。
4. 動物の種類と人間との関係
巻二十に登場する動物の種類と頻度を分析し、人間社会との関わりを考察する。登場頻度の高い動物として、鷹(禽)、馬・蛇・猿・牛・犬(獣)が挙げられる。これらの動物の用途(馬:乗馬、競馬、運搬、牛:神事、贈答、犬:忠義など)や、人間との関係性を個々の説話から分析する。特に、飼育動物と野生動物の区別、動物の役割や扱い方などに着目する。また、猫と鼠、蛇の特性などについても、複数の説話を総合的に分析することで、中世の人々にとって動物がどのような存在であったのかを明らかにする。例えば、猫は愛玩動物として飼育され、鼠は猫の餌となる一方、作物を荒らす害獣でもあることがわかる。
5. 古今著聞集 の百科事典的性格と今後の課題
『古今著聞集』は百科事典的な性格を持つ書物とされているが、動物に関する記述は現代の事典のように網羅的ではない。しかし、当時の知識人にとって必要な動物に関する知識が説話を通じて語られていると考えられる。本稿では、各説話における動物の特性や存在形態を整理し、中世の人々の動物に関する知識を明らかにする。巻二十の構成、特に動植物に関する記述が巻末に多く配置されている点については、『倭名類聚抄』などの先行文献と比較検討し、その意味を考察する。田中宗博氏の指摘する「混沌」という側面についても検討するが、百科事典的性格という視点から、その整合性をどのように考えていたのかという点に焦点を当てる。今後の課題としては、絵巻物などの資料を用いたより詳細な分析、動物の種類や人間との関係性の更なる深掘りなどが挙げられる。
II. 巻二十の概要と動物の種類
『古今著聞集』巻二十は、序文に相当する第六七二話から始まり、様々な動物が登場する説話を収録している。動物の種類は、魚、虫、禽、獣に分類されるが、『古今著聞集』自身は細かな分類を行っていないため、本稿では独自の分類を用いる。巻二十に登場する動物の種類と頻度を分析し、特に頻度の高い動物(馬、蛇、猿、牛、犬など)に焦点を当てる。絵巻物(『鳥獣人物戯画』など)も参照し、中世における動物の種類と人間社会との関係を明らかにする。
1. 巻二十の構成と範囲
『古今著聞集』巻二十は、序文に相当する第六七二話から始まり、多数の動物が登場する説話を収録している。本稿では、後世の抄入とされる七二二~七二六話を除く、約70話を分析対象とする。『古今著聞集』全体は二十巻三十編合計六四六話からなり、各編の説話数は平均二十一~二十二話程度である。本稿では、永積安明・島田勇雄校注『古今著聞集〈日本古典文学大系〉』を主に使用し、必要に応じて西尾光一・小林保治校注『古今著聞集〈新潮日本古典集成〉』も参照する。巻二十は、動物を「魚・虫・禽・獣」などに分類しているわけではないため、本稿では独自の分類基準を用いる。特に、蛇や蛙など、虫偏のつく動物の分類は、『倭名類聚抄』の「蟲・豸類」の基準(有足・無足)を参考に検討する。
2. 巻二十に登場する動物の種類と頻度
巻二十には、様々な動物が登場するが、その種類と頻度を分析することが重要である。本文では、表を用いて巻二十に登場する動物の種類と説話番号を一覧表示している。この一覧から、それぞれの動物の登場頻度を把握し、特に頻度の高い動物を特定する。さらに、中世における動物の種類を把握するため、『新版絵巻物による日本常民生活絵引』の総索引や聖衆来迎寺蔵『六道絵』中の「畜生道」幅に描かれている動物の種類も参考にする。澁澤敬三氏らの『新版絵巻物による日本常民生活絵引』は『鳥獣人物戯画』を含んでいないため、それを加えたリストを作成し、巻二十に登場する動物が中世において一般的なものであったかどうかの検証を行う。しかしながら、膨大な絵巻物を分析し、魚虫類の内訳を詳細に分別することは困難であり、今後の課題となる。
3. 動物の分類と存在形態
巻二十に登場する動物を分析する上で、動物の存在形態(野生か飼育か)を明確に区別する必要がある。しかしながら、野生と飼育の区別は必ずしも明確ではない。例えば、六八三、六九〇、七〇四、七〇五、七一四話に登場する鳥は、野生から捕獲後飼育されたと考えられるが、その過程を踏まえる必要がある。本稿では、説話中の存在形態から判断し、野生と飼育のいずれかに分類している。また、京都が舞台となっている説話が全体の約7割を占めるという点も考慮する必要がある。これは、畿内中心の視点からの記述であることを示しており、登場する動物の種類にも反映されていると考えられる。
III. 心ある 動物と畜生道
巻二十の序文には、「禽獣魚蟲、皆雖不能言、各似有所思者也」という記述があり、動物にも「心」があるという認識が示されている。これは「一寸の虫にも五分の魂」という有名な喩えと同様の考えである。本稿では、動物に「心」があるという視点から説話を分析し、特に、動物の行動や人間との関わりを通して示される「心」の概念を検討する。また、畜生道との関連性についても考察する。田中宗博氏の指摘を踏まえつつ、巻二十における動物譚が畜生道観をどのように反映しているか、あるいは否定的に描かれている部分と肯定的に描かれている部分の両面から分析する。
1. 心ある 動物観の考察
『古今著聞集』巻二十の序文(第六七二話)には、「禽獣魚蟲、其彙且千、皆雖不能言、各似有所思者也」という記述があり、動物にも心があり、思考や感情を持っていると解釈できる。筆者はこの序文の記述を重視し、巻二十の動物譚における動物の描写を、「心」を持つ存在として分析する。この「心」という概念は、広く知られる「一寸の虫にも五分の魂」という表現と共通するものであり、十三世紀半ばには一般化していたと考えられる。しかしながら、「心」の解釈には幅があり、霊験譚的な要素との関連性も考慮する必要がある。巻十七「変化」の説話(例:六〇九話)と比較検討することで、「心」の概念の多様性や、人間との関係性における違いを明らかにする。
2. 畜生道との関連性
巻二十は仏教編ではないため、動物譚であっても畜生道との関連性は希薄であるが、田中宗博氏は巻二十において畜生道が否定的に語られていると指摘している。しかし、必ずしもそうではない例も存在する。例えば、六八九話では平治の乱で死去した平康忠が黒まだらの犬に転生し、後白河院に現れるという話がある。この話では、畜生への転生よりも、院への忠誠心が強調されている。同様に、七一九話では、智願上人に仕えた尼が馬に転生し、上人を支え続けるという話が語られる。この場合も、転生よりも馬の忠実さが強調されており、「執心」は煩悩ではなく、強い思慕を表していると言える。これらの例から、巻二十における畜生道観は単純な否定的なものではなく、多様な解釈の可能性があることが示唆される。
3. 畜生道の肯定的 否定的側面の分析
田中宗博氏の指摘通り、巻二十には畜生道を否定的に捉えている話もある。例えば、六九八話では、如法経を書写する上人が猿に「畜生の身くちおしとは思はぬか」と問いかける場面がある。これは畜生の限界性を示唆している。しかし、この話では馬主の情けにより猿の行為が賞賛されるなど、畜生道の否定的な側面のみが強調されているわけではない。七一〇話では、阿弥陀経の持経者が牛として畜生道に堕ちたことを「あはれなる事也」と表現しているが、これは気の毒という意味か、感動という意味かは解釈が分かれる。また、「犬畜生」という表現も登場するが、これは必ずしも犬への侮蔑・罵倒を示すものではない。これらの例から、巻二十における畜生道観は複雑であり、一概に否定的なものとは言い切れないことがわかる。巻二十全体の整合性を理解するためには、動物譚における多様な表現を丁寧に分析する必要がある。
IV. 動物の特性と人間との関係
巻二十に登場する動物の特性と人間との関係を、個々の説話を分析することで明らかにする。特に、馬、蛇、猿、猫、鼠など、登場頻度の高い動物に焦点を当て、それぞれの動物の用途、役割、人間社会における位置づけなどを考察する。例えば、馬は乗馬、競馬、運搬など多様な用途で用いられ、牛は農耕や神事に関わっていたことが分かる。また、猫と鼠の関係、蛇の特性(執念深さ、嫉妬深さなど)についても詳細に分析する。これらの分析を通じて、中世の人々が動物をどのように認識し、利用していたのかを明らかにする。
1. 動物の登場頻度と人間生活との関連性
『古今著聞集』巻二十に登場する動物の頻度を分析すると、魚や虫は目立ったものがないが、禽類では鷹、獣類では馬、蛇、猿、牛、犬が多く登場する。特に馬、牛、犬は飼育動物であり、人間生活との密接な関係を示唆している。これらの動物の登場頻度の高さは、当時の人間生活において、これらの動物が重要な役割を担っていたことを反映していると考えられる。 一方、虫類の登場が少ない点については、中世において虫類は特に注目されていなかった可能性も示唆されており、『倭名類聚抄』なども参考にしながら、その理由について考察する必要がある。
2. 主要動物の特性と用途の分析
登場頻度の高い動物について、その特性と人間社会における用途を詳細に分析する。例えば、馬は乗馬や競馬、運搬に使用されていたことが分かる。農耕に関する記述が少ないのは、当時の農耕が主に牛によって行われていたためと考えられる。また、六九八話で猿が盗んだ馬は、本来は進物や売買の対象であった可能性を示唆している。牛も同様で、六七九話のように神物として扱われつつも、売買の対象となっていたと考えられる。七〇二話では、藤原公経が中原師季に牛、犬、鴨などを賜ったという記述があり、牛が贈答の対象として一般的であったことを示している。このように、動物は単なる家畜や害獣ではなく、多様な用途や役割を持っていたと考えられる。
3. 蛇と猫 鼠の特性と人間との関係
馬に次いで登場頻度の高い蛇は、人間との関わりにおいて、婚姻を結ぶべきではないという認識があったと考えられる。蛇は、執念深い(六九五話)や嫉妬深い(七二〇話)という特性も示されている。猫と鼠については、巻二十での記述は少ないが、複数の話を総合的に分析することで、当時の認識を明らかにする。猫は愛玩動物として飼育され、名前がつけられ、鼠などを餌としていた。また、捕獲した鼠などを飼い主に提供するなど、飼い主との深い繋がりを示唆する行動も見られる。鼠は家屋内外に出入りし、猫の餌となり、畑の作物を食い荒らす害獣としての側面を持つ。
4. 猿の多様な役割と動物の多角的側面
猿は野生と飼育の両方の形態で登場し、馬屋の守護神としての役割や、芸をする愛玩動物としての側面を持つなど、多様な役割を担っていたことがわかる。七一六話では、芸をする猿が登場し、愛玩動物としての側面が強調されている。一方、六九八話では、猿が馬を盗むという行為を通じて、畜生の限界性と同時に、人間からの評価や賞賛の可能性も示唆している。これらの例から、『古今著聞集』における動物は、一義的な側面のみならず、多角的な側面を持つものとして描写されていることがわかる。動物の行動や人間との関わりを通して、当時の人々の動物観を探る上で、これらの多様な側面を分析することが重要である。
V. 巻二十の構成と百科事典的性格
『古今著聞集』巻二十の構成(特に、巻末に動植物に関する記述が多い点)と、百科事典的性格について検討する。巻二十の構成は、『倭名類聚抄』などの先行文献の構成と比較検討することで、その意図を探る。 『倭名類聚抄』との比較を通して、中世における知識体系と動物に関する情報の整理方法について考察し、『古今著聞集』が当時の知識をどのように反映しているか、また、その全体的な整合性について議論する。
1. 巻二十の構成と 倭名類聚抄 との比較
『古今著聞集』巻二十は、動物に関する説話を集めた編であり、その構成と内容を分析することで、中世における動物に関する知識や認識を明らかにする。巻二十の構成は、部門別百科事典としての性格を帯びており、特に巻末に動植物に関する記述が多い点に注目する。この構成は、『倭名類聚抄』の構成と類似性が見られる。 『倭名類聚抄』は二十巻本であり、巻十八・十九に「魚蟲禽獣」が配置されている点、『古今著聞集』と共通する特徴である。更に、近代の『古事類苑』や『万有百科大事典』でも動植物編が巻末に置かれていることを指摘し、この構成の意図について考察を進める。ただし、『倭名類聚抄』の構成やその継承のされ方については、更なる検討が必要である。
2. 百科事典的性格と情報の整理方法
『古今著聞集』巻二十は、現代の事典のように各動物について網羅的に解説されているわけではない。しかし、当時の知識人にとって必要な動物に関する知識が、説話を通じて伝えられていると考えられる。本稿では、各説話から動物に関する情報を抽出し、表三に示すように動物の特性と存在形態(役割・用途・扱い方など)を整理する。登場頻度の高い動物(馬、蛇、猿、牛、犬など)について、これらの情報を総合的に整理することで、中世の人々の動物に関する知識体系を明らかにする。 このアプローチは、当時の人々が動物についてどのような総合的な認識を持っていたのかを解明する上で有効である。
3. 混沌 と整合性の問題
田中宗博氏の指摘するように、巻二十は雑多で多様な情報が錯綜しており、「混沌」とした印象を与える。しかし、単に混沌としていると捉えるのではなく、その整合性について検討する必要がある。 『古今著聞集』が百科事典的な性格を持つ書物であるという視点から、その整合性を考えていく。多くの動物は複数の話で語られており、それらを総合的に検討することで、動物に関する知識の整理方法や、当時の知識体系を理解することができる。 この検討を通じて、田中氏のいう「混沌」が、単なる無秩序な情報ではなく、ある種の意図的な構成である可能性も示唆される。
