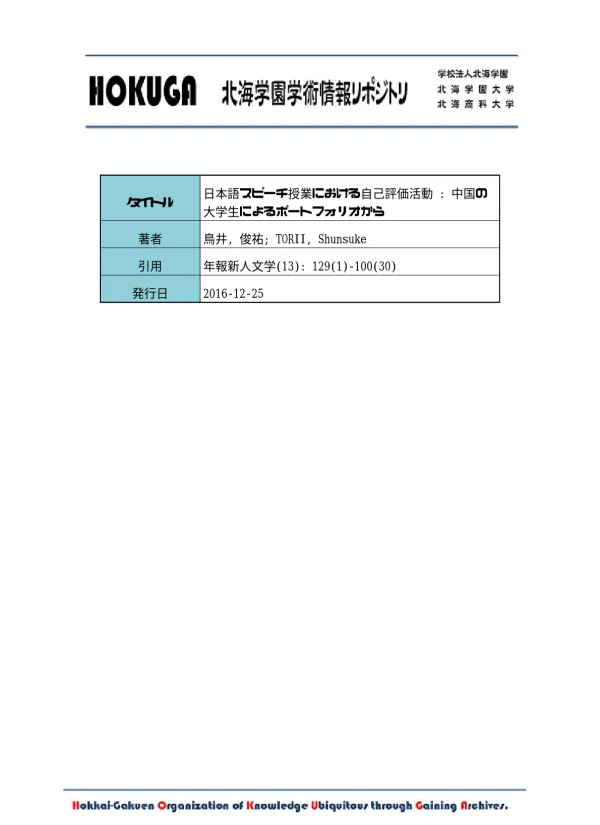
中国大学生:日本語スピーチ授業の自己評価
文書情報
| 著者 | 鳥井 俊祐 |
| 専攻 | 日本語教育 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 437.99 KB |
概要
I.自己評価と他者評価を組み合わせた自律学習促進に関する研究
本研究は、中国浙江省の私立大学日本語学科2年次学生(2011-12年度「日本語朗誦と演講」受講生)を対象に、ポートフォリオ作成を通して自律学習を促進するための自己評価と他者評価の有効性を検証したものです。日本語スピーチ授業において、自己評価を他者評価(ピア・フィードバック)の前後(自己評価Ⅰ、自己評価Ⅱ)で実施し、その変化を分析しました。さらに、学期末には質問紙調査を行い、KJ法を用いて自己評価活動に関する学生の意識を質的に分析しました。 研究対象は、選択科目「日本語朗誦と演講」(全17回、各80分)の受講生です。
1. 研究の背景と目的
本研究は、中国の大学生を対象とした日本語スピーチ授業において、自律学習を促進するための効果的な方法として、ポートフォリオ作成活動と、自己評価と他者評価の組み合わせに着目しています。1990年代半ばから日本語教育分野では自律学習の重要性が認識され、様々な実践が行われてきました。中国においても「自主学習」の重要性が認識され、学習者主体の自律学習が提唱されています。教育評価においては、形成的評価が導入され、自己評価がその重要な要素として位置付けられています。小山(1996)は自己評価を自律学習促進の必要不可欠な要素と位置づけ、彭瑾・徐敏民(2013)も自己評価による自律学習促進を指摘しています。近年、中国の日本語教育においてポートフォリオが注目されており、第二言語教育におけるポートフォリオの効果として、学習意欲の向上や目標指向性の強化などが挙げられています。本研究では、自己評価と他者評価を組み合わせたポートフォリオ作成活動が、中国の大学生における日本語スピーチ学習の自律学習促進にどのように効果を発揮するかを実証的に検証することを目的としています。先行研究では、自己評価と他者評価を組み合わせた実践例はありますが、自己評価の前後(他者評価の有無)における変化を詳細に分析した研究は不足しています。特に、中国の大学生を対象とした研究は少ないため、本研究はこれらの点を明らかにすることを目指しています。
2. 研究方法
本研究は、浙江省の私立大学日本語学科2年次学生を対象とした、2011-12年度開講の選択科目「日本語朗誦与演講」(全17回、各80分)で実施されました。授業内では、ポートフォリオ作成活動と自己評価、他者評価(ピア・フィードバック)、教師フィードバックを行いました。自己評価は、他者評価前(自己評価Ⅰ)と後(自己評価Ⅱ)に実施し、記述内容を分析しました。学生は、肯定的評価と否定的評価を日本語または中国語で記述しました。教師フィードバックは研究者が日本語で記述しました。分析にあたっては、自己評価Ⅰと自己評価Ⅱの記述内容を肯定的評価と否定的評価の割合で比較分析し、出現頻度の高い評価項目を特定しました。学期末には、自己評価活動に関する意識調査を実施し、得られた記述はKJ法を用いて分析しました。質問紙調査では、ピア・フィードバックを「相互評価」、教師フィードバックを「教師からの評価」と言い換えて、学生の理解度を容易にしました。 分析においては、自己評価項目の出現頻度や肯定的・否定的評価の割合に加え、学生の記述内容を質的に分析することで、自己評価と他者評価の組み合わせの効果を多角的に検証しました。
3. 研究結果
自己評価Ⅰと自己評価Ⅱの比較分析の結果、自己評価Ⅱ(他者評価後)では否定的評価の割合が大きく増加しました。第1回発表では音声に関する評価、特に発音・アクセント・イントネーションへの言及が増加し、第2回発表では文法・語彙・表現に関する評価、特に文法・語彙の正確さへの言及が増加しました。これは、他者評価を通して学生が自身の弱点に気づき、より詳細な自己分析を行うようになったことを示唆しています。一方、態度に関する評価は減少しました。意識調査の結果、学生は自己評価とピア・フィードバックの組み合わせに肯定的な認識を示し、学習者間の相互交流促進、自己分析の促進、日本語スピーチの問題点の意識化といった有利性を高く評価しました。教師フィードバックについても、その専門性と有用性を高く評価する意見が多く見られました。 自己評価の内容分析では、評価の焦点が、他者評価を受ける前と後で変化している可能性が示唆されました。具体的には、他者評価前にはスピーチのテーマや具体例といった内容面に焦点が当てられていたのに対し、他者評価後には具体例への焦点がより強くなりました。また、自己評価には、研究者作成の評価項目にない、学習者独自の視点(自信や緊張など)が含まれていました。
II.自己評価Ⅰと自己評価Ⅱの比較分析
自己評価Ⅰ(他者評価前)と自己評価Ⅱ(他者評価後)を比較した結果、自己評価Ⅱでは否定的評価が増加する傾向が見られました。特に、第1回発表では音声(発音・アクセント・イントネーション)に関する評価、第2回発表では文法・語彙・表現に関する評価の増加が顕著でした。これは、他者評価によって、学生が自身の日本語スピーチにおける具体的な弱点に気付き、より詳細な自己分析を行うようになったことを示唆しています。一方で、態度に関する評価は減少しました。
1. 自己評価Ⅰと自己評価Ⅱの肯定的 否定的評価割合の比較
自己評価Ⅰ(他者評価前)と自己評価Ⅱ(他者評価後)の肯定的評価と否定的評価の割合を比較分析した結果、自己評価Ⅰでは肯定的評価と否定的評価の割合がほぼ同等でしたが、自己評価Ⅱでは否定的評価が約6割を占め、肯定的評価よりも否定的評価の割合が大幅に増加しました。これは、他者評価を取り入れることで、学生が自身の発表における問題点により強く意識するようになったことを示唆しています。 この傾向は、発表者自身の発表に対する否定的な評価の傾向が強いという村田(2004)の研究結果とも合致します。本研究では、他者評価を取り入れることで、自己評価において否定的なフィードバックが増加する傾向が確認されました。これは、他者からの客観的な視点が、自己評価におけるより厳格な自己分析につながった可能性を示唆しています。しかしながら、この結果が必ずしもネガティブなものではなく、自己認識の向上や学習意欲の向上につながる可能性も考慮する必要があります。
2. 自己評価項目の変化 音声 文法 語彙 表現 態度
自己評価項目別に見ると、第1回発表の自己評価Ⅱでは音声に関する評価、特に「発音・アクセント・イントネーション」が最も増加しました。これは、他者評価を通して、学生が自身の日本語スピーチにおける音声面にこれまで以上に注意を払うようになったことを示しています。第2回発表の自己評価Ⅱでは、割合は小さかったものの、文法・語彙・表現に関する評価、特に「文法・語彙の正確さ」の増加が目立ちました。これは、他者評価を経て、学生が日本語スピーチにおける言語面にも注意を払うようになったことを示しています。興味深いことに、第2回発表の自己評価Ⅱでは態度に関する評価が減少しました。これは、他者評価によって具体的な言語面への意識が高まった結果、態度面への意識が相対的に低下した可能性が考えられます。 これらの結果から、他者評価は学生の自己評価の焦点を変える効果を持つことが示唆されます。初期段階では音声面への意識を高め、その後、文法・語彙・表現といった言語面への意識を高めるという段階的な変化が見られました。
3. 学習者による新たな評価項目の出現
分析の結果、自己評価Ⅰと自己評価Ⅱの両方において、研究者によって作成された評価項目にはない、学習者自身による新たなカテゴリーが見られました。これらの新たなカテゴリーには「自信」や「緊張」といった、スピーチにおける心理的な側面に関する記述が多く含まれていました。「自信満々でスピーチします」「もっと自信がほしい」「ちょっと緊張します」「緊張しなくていい」といった具体的な記述が見られました。これは、村田(2004)が指摘しているように、学習者が教師とは異なる視点で発表を評価していることを裏付ける結果と言えます。学生は、教師の評価項目とは異なる、自身の主観的な経験や感情に基づいた評価項目を自ら創出しており、自己評価における多様な視点の存在が明らかになりました。 これらの新たなカテゴリーは、自己評価における客観的な評価項目に加え、学習者の内的状態を反映する重要な情報源として捉えることができるでしょう。今後の研究では、これらの心理的な側面と日本語スピーチ能力や自律学習との関連性をより詳細に分析する必要があると考えられます。
III.自己評価活動に関する意識調査
質問紙調査の結果、学生は自己評価とピア・フィードバックの組み合わせに肯定的な認識を示しました。特に、学習者間の相互交流促進、自己分析の促進、日本語スピーチの問題点の意識化といった有利性を高く評価していました。教師フィードバックについても、その専門性と有用性を高く評価する意見が多く見られました。これらの結果は、自己評価と他者評価を組み合わせた学習活動が、学生の自律学習促進に有効であることを示唆しています。
1. 自己評価とピア フィードバックの組み合わせに関する意識
学期末に実施した質問紙調査では、自己評価とピア・フィードバック(相互評価)の組み合わせに関する意識について分析しました。KJ法を用いた分析の結果、学生の記述は「意義の認識」と「実践の仕方」の2つのカテゴリーに分類されました。「意義の認識」はさらに「有利性の認識」、「肯定性の認識」、「有用性の認識」の3つのサブカテゴリーに分けられ、「有利性の認識」が最も多く言及されていました。学生からは、「学習者間の交流が増え、学習がより楽しくなる」「他人と自分の立場から、自分をよりよく知ることができる」「それぞれの見方が異なるので、自分の問題点をよりよく理解できる助けとなる」といった記述が見られました。これらの記述は、自己評価とピア・フィードバックの組み合わせが、学習者間の相互交流を促進し、自己分析を深め、日本語スピーチにおける問題点を明確化することに繋がったと学生が認識していたことを示しています。一方、「実践の仕方」に関する記述からは、この組み合わせによる自己評価活動の実施に困難を感じている学生もいたことが分かりました。
2. 教師フィードバックに関する意識
質問紙調査では、教師フィードバック(教師からの評価)に関する意識についても調査しました。分析の結果、学生の記述は「意義の認識」に集約され、さらに「有利性の認識」、「有用性の認識」、「重要性の認識」の3つのサブカテゴリーに分類されました。「有利性の認識」に関する記述は、「教師の評価は専門的な評価である」「自分の欠点が理解できる」「一目ですぐに自分の問題点が分かる」といった教師フィードバックの専門性と問題点発見への有効性を示すものでした。「有用性の認識」では、「先生の意見はとても役に立った」「スピーチの進歩に大きな助けになった」といった記述があり、教師フィードバックの学習効果への有用性を示しています。そして「重要性の認識」では、「先生からの意見は大切だと思う」といった記述があり、教師フィードバックの重要性を認識する学生が多かったことが示されました。これらの結果から、教師フィードバックは、学生にとって専門的な視点からの評価であり、学習上の問題点を明確化し、スピーチ能力の向上に役立つと認識されていることが分かります。
IV.結論と今後の課題
本研究は、中国の大学生を対象とした日本語スピーチ授業において、ポートフォリオを用いた自己評価と他者評価の組み合わせが、自律学習を促進する上で有効であることを示しました。 今後の課題としては、授業成績との関連性分析や、より大規模な調査による結果の一般化可能性の検証などが挙げられます。
1. 研究の結論
本研究は、中国の大学生を対象とした日本語スピーチ授業において、ポートフォリオ作成活動と、自己評価と他者評価(ピア・フィードバック)の組み合わせが、自律学習の促進に有効であることを示しました。自己評価とピア・フィードバックの組み合わせは、学習者間の相互交流を促進し、自己分析を深め、日本語スピーチにおける問題点の意識化に繋がることが分かりました。また、教師フィードバックは、専門的な視点からの評価として高く評価され、学習上の問題点の明確化やスピーチ能力の向上に役立つと認識されていました。これらの結果から、本研究で用いた自己評価と他者評価を組み合わせた学習方法は、中国の大学生における日本語スピーチ学習の質的向上に貢献する可能性が示唆されました。 ただし、本研究は特定の大学、特定の授業、限定された人数での調査結果であるため、その一般化可能性についてはさらなる検証が必要です。今回の調査で得られた知見を踏まえ、より広範な対象者や多様な学習状況における効果検証を進めることが重要です。
2. 今後の課題
本研究の今後の課題としては、まず、日本語スピーチ授業の成績との関連性を分析する必要があります。自己評価活動が、学生の最終的なスピーチ能力や授業成績にどのような影響を与えているのかを定量的に検証することで、本研究の結論をより強固なものにできます。また、サンプル数の少なさも課題です。より多くの学生を対象とした大規模な調査を実施することで、今回の結果の一般化可能性を高め、より信頼性の高い結論を得ることが可能となります。さらに、自己評価活動における学習者個々の特性や学習スタイルを考慮したより精緻な分析も必要です。例えば、自己評価に対する苦手意識を持つ学生への支援方法や、より効果的なフィードバック方法の開発などが考えられます。 その他、本研究では主に日本語スピーチ授業を対象としていますが、他の日本語学習活動や学習内容への適用可能性についても検討していく必要があります。 これらの課題に取り組むことで、より効果的な自律学習支援システムの構築に貢献できると考えられます。
