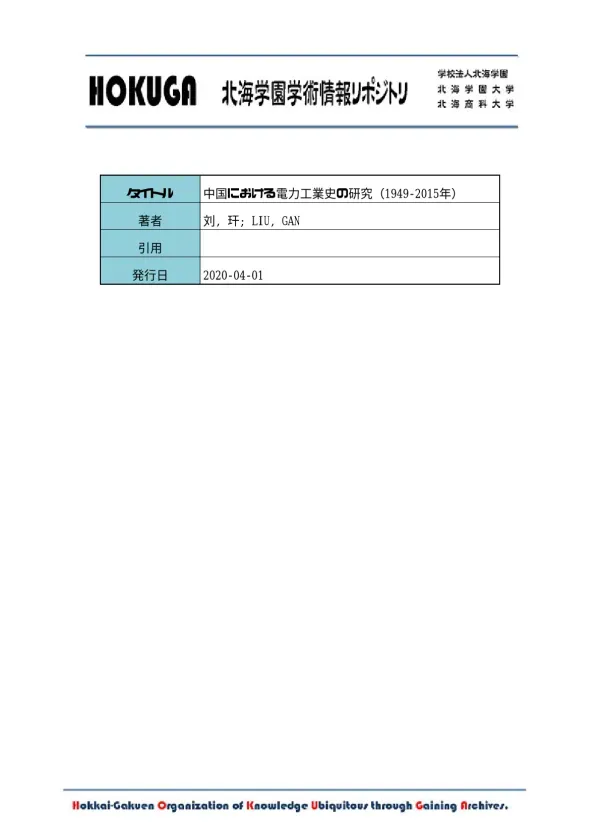
中国電力工業史:1949-2015年
文書情報
| 著者 | Liu, Gan |
| 学校 | 北海商科大学大学院商学研究科 |
| 専攻 | 商学 |
| 文書タイプ | 博士論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.04 MB |
概要
I.中国電力管理体制の変遷と 電力体制改革 1949年 1980年代
本節では、1949年以降の中国の電力管理体制の変遷を、主に電力管理組織の変遷に基づいて分析します。初期は「政企合一」・「官辦不分」の垂直一体型の独占経営体制が特徴でした。中央集中化から地方分散化への移行、そして「大躍進」後の調整期における管理体制の再編について記述します。この時期の重要なキーワードは「政企合一」、「官辦不分」、「垂直一体型」、「独占経営」、「高度集中」です。東北電業管理局、華東電業管理局、西北電業管理局などの設立・廃止、および電力価格体系の変遷なども重要なポイントとなります。計画経済の下での電力供給不足の問題も重要な課題として取り上げられます。
1. 1949年 1950年代 初期の電力管理体制
1949年以降、中国の電力管理体制は、燃料工業部の設立と第一期五カ年計画の開始を機に、徐々に統一的な体制へと整備されていきました。この初期段階では、電力管理の主管部門は「多重身分(様々な管理権限を所有)」を持ち、管理内容は重層的でした。伝統的な電力管理体制の特徴として、「政企合一」、「官辦不分(行政と経営の一体化)」、「垂直一体型」、「独占経営」、「高度集中」などが挙げられます。中央政府による強い統制の下、電力供給は計画経済に基づいて行われ、電網は中央政府が主導する体制でした。京津唐電網と東北電網は省を跨ぐ大規模な電網として運営され、中央政府が直接管理していました。しかし、この体制では、地方の電力事情への対応が遅れがちであり、電力の合理的な利用が阻害されるという問題がありました。また、企業管理における計画権、人事権、財政権は下級機関に委譲されましたが、減価償却や修繕といった維持管理は十分に行われていなかったという課題も指摘されています。電力価格も統一された体系が確立され、効率に基づいた価格調整の仕組みが導入され始めました。しかし、地域によって価格差があり、特に東北地区は、当初水力発電が主体だったため関内よりも低い価格体系が維持されていました。
2. 大躍進と調整期 1958年 1965年
1958年から始まった「大躍進」政策は、電力工業にも大きな影響を与えました。当初は、工業発展、特に新工業区建設のための電力供給拡大が重視されました。「一・五」計画では火力発電所建設が中心となり、ソ連の援助も得て大規模な発電所建設プロジェクトが推進されました。しかし、「大躍進」は計画経済の限界を露呈させ、資源配分の混乱や、重複建設、盲目的な生産といった問題を引き起こしました。1961年頃には大躍進の熱狂が収束し、中国経済は調整期に入ります。電力工業では「調整・堅固・充実・向上」の「八字方針」に基づき、管理体制の再編が行われました。遼吉電業管理局や瀋陽電力建設局の廃止、東北電業管理局、華東電業管理局、西北電業管理局、雲南電業管理局、山東電業管理局、山西電業管理局、内蒙古電業管理局、寧夏電業管理局、四川電業管理局、広東電業管理局、貴州電業管理局といった、多くの地方電業管理局が設立・改組されました。これは、中央集権的な管理体制から地方分権的な体制への転換を意味します。この期間、発電設備容量は増加しましたが、計画経済の弊害により、電力不足が深刻な問題として残りました。また、北京電業管理局は北京電力公司と改名し、「トラスト管理方式」の試行が行われましたが、その詳細な内容は本文からは読み取れません。この調整期には、中央政府による計画と総合的な均衡への努力が不十分だったこと、中央の指揮権を離れた基本建設が行われたこと、重複建設や盲目的な生産が顕著だったことなどが問題視されました。電力不足を解消するため、旧電力設備の補修・改良と計画的な発電所建設が重視され、火力発電所を中心に、水力発電所の建設も進められました。しかし、工業と農業のアンバランスの是正のため、工業部門の基本建設投資は削減されました。
3. 文化大革命期とその後の電力管理 1966年 1980年
文化大革命期には、電力工業も政治的影響を強く受けました。「全国電力使用規則」が政治優先主義の観点から批判され、改定を余儀なくされました。政治優先主義が強調され、電力使用者に対する罰則規定などが削除されるなど、規則の内容が簡素化されました。しかし、この簡素化された規則の執行は困難を極め、電力使用者の滞納金は増加しました。電力供給不足は依然として大きな問題であり、多くの地域で厳しい停電が続きました。東北、京津唐、華北、中原などの電網では、発電能力を超える負荷がかけられ、低周波・低電圧での送電を余儀なくされるなど、生産活動に支障をきたしました。この状況を改善するため、「五・五」計画では、発電所の建設を優先し、効率的な発電設備の生産を加速させること、水力発電と火力発電の同時進行、大規模発電所と小規模発電所の同時進行、計画的な電力使用と節電の徹底、電網の安全確保などが求められました。地方政府による「集資辦電」政策は、この頃から奨励され始めました。しかし、地方政府による過剰な行政関与、電源配置の不合理、投資の分散化、小規模発電所の乱立など、新たな問題も発生し始めました。 「三・五」計画では、人民の衣食住問題の解決と国防建設の強化が中心課題とされましたが、ベトナム戦争の拡大により、戦備体制の強化が優先され、十分な調整政策の実施は困難でした。この期間、電力工業の調整任務は順調に進展し、生産規模の追求は是正され、コスト削減が実現したとされています。発電設備容量と発電量は増加しましたが、電力供給不足は解消されませんでした。
II.改革開放期における 電力体制改革 と 政企分離 1980年代 1990年代
1980年代以降の改革開放期は、電力体制改革が加速された時期です。政企分離を進め、市場メカニズムの導入が試みられました。「集資辦電」政策による地方政府主導の発電所建設の増加、電力供給の地域主義化、そしてそれに伴う問題点(電源配置の不合理、環境問題など)を分析します。電網整備の進展(500キロボルト送電網の形成など)と、その後の「省電力公司」の設立、エネルギー部の設置と廃止、そして電力工業部の再編といった組織的変化も重要な内容です。キーワードとして「集資辦電」、「省電力公司」、「エネルギー部」、「電力工業部」、「電網整備」、「省為実体」などが挙げられます。華能国際電力開発公司などの設立も重要な出来事です。
1. 集資辦電 政策と地方政府の役割拡大
1980年代以降、中国では改革開放政策の下、電力部門にも大きな変化が訪れました。特に重要なのが「集資辦電」政策です。この政策により、地方政府は電力開発に積極的に関与するようになり、発電所の建設が加速化しました。地方政府は、それぞれの地域の経済発展を促進するため、発電所の建設を積極的に進め、結果として、石炭資源の豊富な地域には火力発電所が集中するなど、電源配置の不合理が生じるようになりました。 地方政府主導による発電所建設の増加は、電力供給の地域主義化を招き、電網全体の効率的な運営を阻害する要因となりました。また、地方政府による過剰な行政関与が電力開発における様々な問題を引き起こし、環境問題や運輸インフラへの負担増加なども懸念されるようになりました。投資の分散化も進み、地方政府の投資を統一的に計画的に統制することが困難になるなど、新たな課題も浮上しました。小型発電機を主体とした発電所の乱立も目立ち始め、規模経済の効果を発揮できない発電所が多く建設され、資源と資金の有効活用が阻害されるという問題も発生しました。電力消費構造も変化し始め、軽工業の電力消費は増加し、農業用電力消費も増加傾向にありました。特に「郷鎮工業」の電力消費が急拡大し、農村経済の発展を反映しました。1985年には農村電力消費のうち32.4%を占めるようになり、副業加工用と郷鎮工業用で農村電力消費の半分以上を占めるようになりました。
2. 電網整備の進展と 省電力公司 の設立
「七・五」計画期に入ると、中国では電網整備が本格化しました。500キロボルト送電線によるネットワークが形成され始め、全国的な「聯合電網」建設に向けた第一歩が踏み出されました。西北電網を除く五大電網において、500キロボルト輸配電線ネットワークの構築が進められました。葛洲壩-上海間の500キロボルト輸配電線も運用開始されました。1990年時点では、35キロボルト以上の輸配電線が45.5万キロメートルに達していました。その後、「八・五」計画期には、さらに電網規模が拡大し、220キロボルト以上の輸配電線が3万1117キロメートル新たに架設されました。省レベルでの自主管理を行う電網も発展し、全国の都市と大部分の農村に電網が張り巡らされるようになりました。「三峡ダムプロジェクト」の建設開始に伴い、全国電網の連結問題も議題として取り上げられるようになりました。この電網整備の進展は、省レベルの電力会社、「省電力公司」の設立と密接に関連しています。省電力公司は、省内の電力建設、発電、電力供給、電力消費を管理する責任を持ち、中央と地方の財産所有権に応じて収支計算を行い、損益の自己責任を実行する独立採算制の組織でした。省を跨ぐ電網の統合も模索され、省を跨ぐ電網は独立採算制の経済組織として運営され、省内電網も独立採算制を実行する経済組織として運営される電網連合管理体制が構築されるようになりました。
3. エネルギー部から電力工業部へ 政企分離 と 簡政放権
1988年、水利電力部は廃止され、石炭工業部、石油工業部、原子力工業部を統合したエネルギー部が設立されました。エネルギー部は全国のエネルギー産業を統合的に管理する役割を担い、エネルギー政策の決定、エネルギーバランスの調整、エネルギーの合理的な利用と開発促進などを主な職務としていました。しかし、1993年にはエネルギー部が廃止され、電力工業部が再び設立されました。この機構改革は、電力部門における「政企分離」と「簡政放権」の徹底的な実現と、電力工業の統一的な管理を実現することを目的としていました。電力工業部の任務は、電力事業の発展戦略の立案(生産、建設、投資などの重大問題、電力生産の協調体制構築、統一的な電網整備、企画、政策、法規の制定など)と国有資産の価値保全、増殖に限定されました。この改革は、会社法に基づく調査・点検を進め、電力会社が運営する小中学校や病院などの公益施設と資産を政府管理に移譲することを促しました。 華能国際電力開発公司の設立もこの改革の一環として挙げられ、外資の積極的な活用を目指したものです。この会社は、中国銀行、華潤公司、水利電力部の対外公司、そして「圧油」辦公室の共同出資で設立され、外資利用による発電事業を推進する役割を担いました。 この後、1996年には国家電力公司が設立されました。国家電力公司は行政管理機能を持たず、電力工業部などの行政管理と監督を受ける独立法人として設立されました。政企分離を徹底するため、電力事業に関する電力工業部の権限はすべて企業に委譲されました。しかし、国家電力公司の設立だけでは、予算、財務、電力価格などの管理において課題が残りました。
III. 電力体制改革 の深化と市場化への移行 1990年代後半 2000年代
この期間は、電力体制改革の深化と市場化への本格的な移行が特徴です。国家電力公司の設立、発電と電網の分離、そして電力市場の形成を目指した取り組みが中心となります。しかし、国家電力公司は依然として「省為実体」の影響を受け、市場化の進展には課題が残りました。政企分離の徹底、省を跨ぐ電網の統合、農村電力体制の改革といった具体的な政策や、それらに伴う問題点(電力取引メカニズムの不備、電力資源の利用効率低下など)を分析します。キーワードは「国家電力公司」、「発電・送電分離」、「電力市場」、「省為実体」、「三公調度」などです。電力監督委員会(電監会)の設立も重要な出来事です。
1. 国家電力公司の設立と電力システム改革
1990年代後半から2000年代にかけて、中国の電力システム改革は大きく進展しました。1996年、国務院は「国家電力公司」を設立する通知を発出し、政府機能の転換、政企責任の分離、電力工業体制改革の深化を目指しました。国家電力公司は行政管理機能を持たず、電力工業部などの監督下で運営されることになり、政企分離が推進されました。電力工業部が保有していた権限は企業に委譲され、行政管理から企業管理への転換が図られました。しかし、国家電力公司は国家計画委員会や財政部などの政府機関による管理・監督を受け、予算や財務、電力価格などの決定においては依然として政府の関与が強く残りました。大中型電力建設プログラムや年度計画は、電力工業部と国家計画委員会の承認が必要であり、国家電力公司の経営方針が十分に反映されないという問題がありました。資金調達に関しても、国家開発銀行からの融資は国家政策に大きく依存しており、国家電力公司の独立性が限定されていました。発電会社と電網会社との関係も課題で、発電会社は電網会社への電力販売に依存する構造が変わらず、電力市場の形成には至っていませんでした。
2. 発電 送電分離と電力市場化への取り組み
国家電力公司設立後も、電力システム改革は継続され、発電と送電の分離が推進されました。1998年の「電力工業体制改革の深化に関する問題に関する意見」では、発電・送電分離の推進、政企分離の堅持、省級電力会社の改革深化、全国電網の連結加速化、農村電力体制改革の推進などが挙げられています。発電と送電の分離は、電力市場の形成に不可欠なステップとして位置づけられ、電網調整の公平性、公正性、透明性、発電所間の平等な競争などを促進することで電力価格の引き下げを目指していました。しかし、「省為実体」という体制の下では、省を跨ぐ電力市場の形成や電力資源の最適配置は困難でした。省レベルが独立採算制を維持する中で、省を跨いでの電力取引や協調は容易ではありませんでした。このため、省レベルの電力会社を再編し、発電と送電を分離する動きが進展しました。東北、華北、華東、華中、西北電業管理局をはじめ、各地の電力工業局は廃止され、発電会社と送電会社が分離独立した体制へと移行しました。具体的な例として、西北電力集団公司と陝西省電力公司の分離、南方電力聯営公司、華東・華中・西北電力集団会社の改組などが挙げられます。電力需給バランスが回復すると、電網における「三公調度」(公開性、公平性、公正性)が求められるようになりました。発電市場の運営と監督の規則制定、発電企業間の競争促進などが課題として挙げられました。
3. 電力監督委員会 電監会 の役割と電力価格体系
電力市場化の進展に伴い、電力市場の監督・管理体制の整備も重要課題となりました。電力監督委員会(電監会)は、全国統一の電力監督・管理システム構築、電力取引機構(電力調度・取引センター)の設立・指導といった役割を担いました。しかし、電監会の監督・管理に必要な法的根拠が不十分だったため、職務執行に課題がありました。政府各部門間の職能の重複や矛盾も、電監会の活動の制約要因となりました。電力価格体系についても改革が進められました。2005年、国家発展改革委員会(国家発改委)は「電力価格の実施辦法に関する通知」を公布し、電力価格の各種実施方法を詳細に定めました。「輸配電価格」は重要な要素で、「共用電網利用価格」、「特定電網利用価格」、「補助サービス価格」から構成されることになりました。コストと収益を管理する方式への移行が目指されましたが、この価格体系改革の詳細な効果や影響については、文書からは読み取れません。2000年には、電力行政管理職能の調整に関する意見が発表され、省・自治区・直轄市の電力管理機構の整理が徹底されました。北京など27の省級電力工業局の電力行政管理職能が省級経済貿易委員会に移管されました。これにより、電力工業部の華北、東北、華東、華中、西北の大区電業管理局や管轄地域内の省級電力工業局は廃止されました。 この一連の改革によって、発電と送電の分離、電力市場の形成、そして効率的な電力供給体制の構築が目指されましたが、同時に、国有企業改革の進展、社会主義的市場経済との適合性といった課題も残されました。
IV.電力市場の形成と 電力体制改革 の現状 2000年代以降
2000年代以降は、電力市場の形成と電力体制改革の更なる深化が課題となります。発電・送電・配電の分離、市場化の推進、そして「棄水、棄風、棄光、棄核」といった電力資源の有効活用問題が重要な論点です。「統購統銷」体制からの脱却、電力取引メカニズムの改善、そして市場競争の促進に向けた取り組みが分析されます。国家発展改革委員会(国家発改委)の役割、そして電力市場の監督・管理体制の整備が重要なテーマとなります。キーワードとして「国家発改委」、「棄水、棄風、棄光、棄核」、「統購統銷」、「電力市場化」などが挙げられます。
1. 電力市場形成に向けた課題と電力監督委員会
2000年代以降、中国では電力市場の形成と電力体制改革の更なる深化が目指されました。電力需給バランスが回復する中で、電網の運営には「三公調度」(公開性、公平性、公正性)が求められ、発電企業間の競争促進が重要課題となりました。しかし、発電と送電・配電を一手に担う垂直的な独占体制の弊害は依然として残っており、電力市場の完全な形成には至っていませんでした。電力監督委員会(電監会)は、全国統一の電力監督・管理システム構築、電力取引機構(電力調度・取引センター)の設立・指導などを主な職務としていましたが、法的根拠の不備や他政府部門との職能の重複・矛盾など、様々な課題を抱えていました。 市場経済における監督・管理の概念と、国家による直接コントロールとの間のずれも問題でした。電力価格体系に関しても、国家発展改革委員会(国家発改委)が電力価格の実施方法に関する通知を公布し、輸配電価格、共用電網利用価格、特定電網利用価格、補助サービス価格などを規定しましたが、市場化への移行には依然として多くの課題が残されていました。 省級電力会社は、省レベルを経営の単位とする「省為実体」を基礎としており、省を跨ぐ電力市場の形成や電力資源の最適配置を阻害する要因となっていました。 このため、2002年には新たな電力体制改革が着手されました。これは、発電・送電・販売を一手に掌握する垂直的な独占体制の弊害を除去することを目的としたものでした。
2. 発電 送電 配電分離と電力市場の更なる整備
2000年代以降の電力体制改革は、発電、送電、配電の分離をさらに推進することを目指しました。発電と送電の分離は進みましたが、配電部門との関係や電力市場の整備には更なる努力が必要でした。 電力供給過剰の問題も顕在化し、「棄水、棄風、棄光、棄核」現象と称される、水力、風力、太陽光、原子力発電の有効活用が課題となりました。この問題の背景には、電網企業による発電企業からの「統購統銷」(統一買い付け、統一販売)という取引状況が根本的に変化していなかったことが挙げられます。発電企業は電力を電網会社に販売するだけで、電力消費者側も電力の選択権が限られていました。そのため、発電企業は計画に基づいて電力を生産する傾向が残り、大容量・高効率な発電設備の活用が十分に進んでいませんでした。電力価格の決定においても、市場メカニズムの導入は不十分でした。電力価格の決定には国家発改委や他の政府機関の関与が強く、市場価格との乖離も存在していました。このため、電力取引メカニズムの抜本的な見直しと、市場化の更なる促進が求められていました。 国有資産監督管理委員会(国資委)は、国有資産の価値保全・増殖に重点を置き、電力政策を国家発改委に統一化し、電力工業に対する管理・監督を規範化しました。しかし、社会主義的市場経済との適合性という課題は、依然として残っていました。
3. 電力供給過剰と電力資源の有効活用
2000年代以降、中国では電力供給過剰の問題が顕在化しました。これは、発電設備の増強と電網整備の進展により、電力供給能力が電力需要を上回ったことが原因です。しかし、この電力供給過剰は、電力資源の有効活用という新たな課題をもたらしました。「棄水、棄風、棄光、棄核」現象は、水力、風力、太陽光、原子力などの再生可能エネルギーや原子力発電が、電力需要の不足により発電を停止せざるを得ない状況を指します。これは、電力市場における電力取引メカニズムの欠陥を露呈していました。電網企業による発電企業からの「統購統銷」(統一買い付け、統一販売)体制では、発電企業も電力消費者も電力を自由に選択することができません。発電企業は計画に基づいて電力を生産し、電網会社に販売するのみで、効率的な電力供給体制の構築が阻まれていました。電力資源の利用効率向上のためには、電力市場の更なる整備と、発電企業と電網企業、そして電力消費者間の自由な取引を促進するメカニズムの構築が不可欠でした。この問題解決には、電力市場における競争促進、電力取引メカニズムの改善、そして電力資源の最適配分を実現する政策が必要でした。
