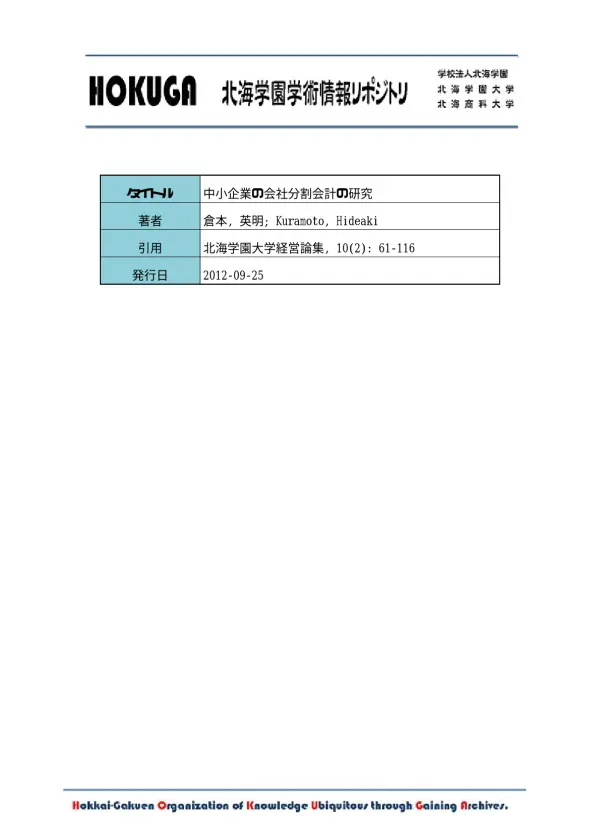
中小企業の会社分割とハイブリッド証券
文書情報
| 著者 | 筆者 |
| instructor/editor | 早川豊 先生 |
| school/university | 北海学園大学大学院経営学研究科 |
| subject/major | 経営学 |
| 文書タイプ | 博士学位論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.20 MB |
概要
I.中小企業の抱える課題と会社分割 ハイブリッド証券の活用
本論文は、中小企業が抱える事業承継問題、形骸化した株主構成、非効率な事業多角化といった課題に対し、会社法改正後の会社分割制度とハイブリッド証券の活用を提案している。特に、会社分割による事業再編において、柔軟化された支払対価としてハイブリッド証券を利用することで、中小企業の経営持続性向上に繋がるとしている。会計処理においては、大企業向けの会計基準とは異なる、中小企業会計指針を考慮する必要性を指摘している。
1. 中小企業を取り巻く経営課題
中小企業は、事業承継、形骸化した株主構成、非効率な事業多角化といった深刻な経営課題に直面している。事業承継においては、親族経営が中心であるため、高齢化による経営者の引退に伴い、後継者への円滑な承継が大きな問題となる。子孫間の確執などを回避するため、事業分離による承継方法が模索されている。
株主構成の問題は、1990年の商法改正以前の発起人7名以上という規定に起因する。中小企業では親族や知人に発起人を依頼することが多く、結果として、経営方針や事業展開に関して株主間の意見対立が生じやすくなっている。さらに、株主の死亡による相続発生時には、株式譲渡制限規定が適用されないケースが多く、会社にとって好ましくない株主の参入を招き、複雑な株主構成を招く要因となっている。
従来、中小企業は収益源確保のため事業多角化を進めてきたが、日本の経済成熟と経済情勢の不透明化により、多角化が負担となり、非効率経営に陥るケースも増加している。そのため、経営資源を自社の得意分野に集中させる必要性が高まっている。
2. 会社法改正と中小企業の対応
2006年5月1日に施行された会社法は、旧商法を大幅に見直し、バブル崩壊後の低迷する景気を浮揚させることを目的としている。この会社法改正は、中小企業が抱える問題解決にも繋がる可能性を秘めている。具体的には、最低資本金制度の廃止、組織再編時の支払対価の柔軟化、種類株式制度の拡充などが挙げられる。最低資本金制度の廃止により、設立や事業拡大における障壁が低くなる。支払対価の柔軟化は、合併や会社分割において、株式以外の財産を対価として認めることで、より多様な再編手法が可能となる。種類株式制度の拡充は、企業のニーズに合わせた柔軟な資本構成設計を可能にする。これらの改正は、中小企業の経営課題解決に大きく貢献すると期待されている。
3. 会社分割とハイブリッド証券の提案
本論文では、会社法改正を踏まえ、中小企業の抱える問題への対策として、会社分割制度とハイブリッド証券の活用を提案している。会社分割は、事業部門の権利義務を分割先会社に移転する手続きであり、支払対価の柔軟化により、ハイブリッド証券が有効な手段となる。ハイブリッド証券は、負債と資本の両方の性質を持つ証券であり、中小企業の資金調達や資本構成の最適化に役立つ可能性を秘めている。また、会計処理においては、大企業と異なる中小企業の状況を考慮し、中小企業会計指針に基づいた適切な処理を行う必要があると主張している。2011年7月26日付け日本経済新聞の記事を引用し、ハイブリッド証券を活用した経営の継続性維持を図る非上場企業の動きを紹介している。
II.会社分割手続きと会計処理
会社分割の手続き、特に吸収分割と新設分割における具体的な流れと、それに伴う会計処理について解説している。分割における権利義務の承継、労働契約承継法の適用、株主への事前開示事項など、実務的な側面にも触れている。ハイブリッド証券の活用についても、分割対価の選択肢として検討している。会計処理に関しては、大企業と中小企業の会計基準の違いを踏まえ、中小企業会計指針に沿った会計処理の重要性を強調している。
1. 会社分割手続きの概要
このセクションでは、会社分割手続き、特に吸収分割と新設分割の手順について解説している。吸収分割では、分割会社(B社)の全ての権利義務が存続会社(A社)に承継される。この際、承継する権利義務の内容は、契約書(例として「承継権利義務明細表」が挙げられている)に詳細に記載される。また、会社財産の善管注意義務について、分割契約締結後から効力発生日までの期間、A社とB社は善良な管理者としての注意義務を負うと規定されている。労働契約の承継は、労働契約承継法およびその施行規則に従って行われ、B社の従業員への通知と異議申し立ての機会が規定されている。さらに、債権者への情報提供として、吸収分割契約の内容、分割対価の相当性など、法定事前開示事項を株主総会開催の2週間前までに両社の本店に備え置く必要があるとされている。これらの手続きは、商業登記の完了をもって完結する。
2. 会社分割における会計処理
会社分割における会計処理について、大企業と中小企業の違いを明確に解説している。大企業は、金融商品取引法に基づく会計基準や会計基準適用指針に従って会計処理を行うが、中小企業は、会計情報へのニーズが異なるため、大企業向け基準の適用は現実的ではないとされている。中小企業においては、中小企業会計指針が参考として示されているものの、強行規定ではないため、中小企業は会計基準や適用指針を超えて、より質の高い透明性の高い会計を目指せる可能性を示唆している。具体例として、B社の建物や機械器具の減価償却処理についても触れ、減耗摩耗や陳腐化といった減価要因を会計上適切に認識するための処理方法が解説されている。中小企業が作成する貸借対照表、損益計算書等の利用者は限られており、経理体制も大企業と比較して貧弱であるため、会計処理の簡素化と透明性向上のための工夫が必要とされている。
III.ハイブリッド証券の評価と中小企業への適合性
ハイブリッド証券の資本性の評価方法について、格付会社の手法なども参考に説明している。中小企業においては、上場企業と異なり株主数が少なく株式譲渡制限も多いことから、ハイブリッド証券の発行手続きが比較的容易であると指摘。特に、劣後債や永久債といったハイブリッド証券を、中小企業の資金調達手段として積極的に検討すべきだと主張している。資本構成の最適化に役立つと結論付けている。
1. ハイブリッド証券の資本性評価
このセクションでは、ハイブリッド証券の資本性評価について、主に普通株式との類似性に着目した評価方法が解説されている。ハイブリッド証券の発行には株主総会の特別決議が必要となるが、上場しておらず株式譲渡制限のある中小企業では、株主の変動が小さく、発行手続きが比較的容易であるため、ハイブリッド証券の活用が適しているという主張がなされている。
資本性評価においては、格付会社の手法が参考とされており、格付の歴史や、信用格付業者制度の設立(2010年4月1日)についても言及されている。 格付会社は、ハイブリッド証券の満期がないという点に着目し、普通株式に近い性質を持つほど資本性の評価が高くなるとする。転換社債や強制転換条項付き株式など、普通株式への転換条項が付されたハイブリッド証券は、転換の可能性が高いほど普通株式との近似性が高く評価される。転換の可能性の判断には、転換の強制性・任意性、転換価格の水準、転換期間などが考慮される。ステップアップ条項など、利息や配当が自動的に引き上げられる条項が付されている場合は、発行会社は早期償還を望み、投資家も早期回収を望むため、資本性評価は低くなる傾向がある。また、普通株式の配当規制についても触れ、配当財源の有無や経営者の判断が配当額に影響する点を解説している。最後に、中小企業の負担を考慮した上で、資本性評価による分類の枠組みを示す必要性が述べられている。
2. 中小企業におけるハイブリッド証券の活用
中小企業が経営を持続するためには自己資本の充実が重要であり、そのためには普通株式の発行が最善策であるが、経営への介入を避け、資金調達手段として社債発行を検討する時代に入ったと主張されている。中小企業は、大企業と比較して信用力が低いため社債発行の機会が少ないのが現状であるが、信用力向上を目指し、社債発行を積極的に検討すべきであるとされている。
中小企業が現実的に発行できるハイブリッド証券として、劣後債、永久債、転換社債型新株予約権付社債、優先株式、議決権制限株式、取得請求権付株式、全部取得条項付種類株式などが挙げられている。大企業のように専門スタッフや外部専門家を容易に活用できない中小企業にとって、これらのハイブリッド証券は現実的な選択肢となる。ハイブリッド証券の発行により、自己資本を充実させ、信用力を高めることが中小企業の経営持続可能性を高める鍵となる。日本経済新聞の記事を引用し、ハイブリッド証券を活用して自己資本充実と経営継続を図る非上場企業の事例を紹介している。
IV.貸借対照表への表示と経済的実質
普通株式、普通社債、ハイブリッド証券を発行した場合の貸借対照表への表示方法について解説。特に、ハイブリッド証券の種類(株式系、社債系)によって表示が異なる点を明確にしている。中小企業の会計情報の透明性と適正性を確保するため、経済的実質を適切に反映した表示の重要性を強調している。また、新株予約権付少人数私募債といった具体的な例も示している。
1. 証券発行時における貸借対照表の表示
このセクションでは、普通株式、普通社債、そしてハイブリッド証券を発行した場合の貸借対照表における原則的な表示方法について解説している。株式系ハイブリッド証券の発行時の表示は普通株式と同様である一方、社債系ハイブリッド証券(劣後債や永久債)の表示は普通社債と同様であると説明されている。ただし、新株予約権付社債については、一括法と区分法という2種類の会計処理方法があり、それぞれ表示方法が異なる点に注意が必要であるとされている。中小企業においては、株主数が少なく、株式譲渡制限が多いことから、会社が望まない株主が存在する可能性は低いため、株主総会での特別決議も比較的容易であり、ハイブリッド証券の発行手続きを進めやすいとされている。
2. 中小企業における会計基準と経済的実質
中小企業の会計処理においては、大企業とは異なる会計情報へのニーズを考慮する必要があると指摘されている。大企業や上場企業は、金融商品取引法が定める会計基準や会計基準適用指針に則って会計処理を行うが、中小企業においては、これらの基準をそのまま適用することは現実的ではない。中小企業会計指針は、中小企業が拠ることが望ましい会計処理や注記を示しているが、強行規定ではないため、中小企業はより高質で透明性の高い会計を目指せる可能性があると主張している。中小企業が作成する計算書類の利用者は限られており、経理体制も大企業に比べて貧弱であるといった現状も踏まえ、経済的実質を適切に評価し、会計情報の透明化と適正化を図るための会計処理の重要性が強調されている。具体的には、新株予約権付少人数私募債を例に挙げ、低利率または無利息であっても、新株予約権が付与されることで社債を引き受けてもらえる可能性を示している。また、資本金の増加に伴う登録免許税や、資本金・資本準備金の取崩し手続きについても触れている。
