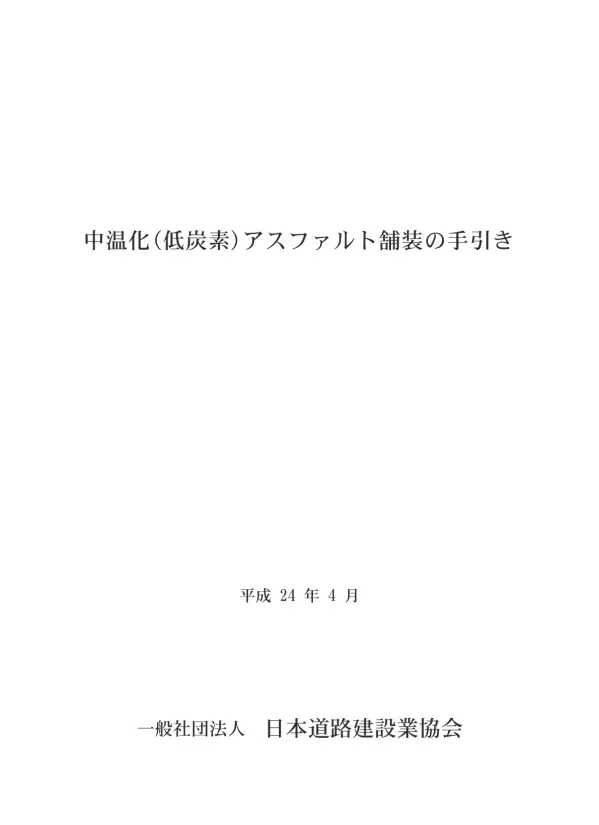
中温化アスファルト舗装技術ガイド
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.23 MB |
| 専攻 | 土木工学 (Civil Engineering) |
| 文書タイプ | 技術資料 (Technical Document) |
概要
I.中温化アスファルト混合物 WMA の製造と施工
本資料は、中温化アスファルト舗装におけるCO2排出量削減と施工性向上を目的とした中温化技術について解説しています。中温化剤(発泡系、粘弾性調整系、滑剤系)の種類や、プラントミックスとプレミックスの製造方法の違い、ならびに低炭素アスファルト舗装を実現するための効果的な施工計画の立案について述べています。グリーン購入法に基づく特定調達品目への追加も踏まえ、再生アスファルトやポーラスアスファルトへの適用拡大に向けた取り組みも紹介しています。特に、製造温度を30℃程度低減した中温化混合物を用いた場合の、締固め性能、耐久性、早期交通開放の可能性などを詳細に分析しています。 具体的な数値データや事例研究、例えば、燃焼設備調整やホットビン管理、100t以上の連続製造によるCO2削減効果の検証などが含まれています。また、橋面舗装や薄層舗装などへの適用事例も示され、施工温度低減による効果が強調されています。
1. 中温化アスファルト舗装の目的と適用効果
中温化アスファルト舗装は、加熱アスファルト混合物の製造・施工温度を低減する中温化技術を用いた舗装であり、製造温度の低減による燃料消費量の削減と二酸化炭素排出量の抑制が期待できることから、低炭素アスファルト舗装とも呼ばれています。 その適用効果としては、CO2排出量削減に加え、補修工事における早期交通開放(規制時間短縮)による渋滞緩和、舗設許容時間の延長による日当たり施工量の増加と工期短縮、夏期施工時の初期わだちの抑制などが挙げられます。本資料では、製造温度を通常よりも30℃程度低減した中温化混合物を主に記述していますが、施工条件や気象条件によっては20℃程度の低減を目標とする場合や、30℃を大きく上回る温度低減が可能な特殊添加剤を用いる場合もあることを明記しています。中温化技術は、後述する特殊添加剤(中温化剤)の添加、あるいはフォームドアスファルトの使用によって、製造および施工温度を低減することを可能にする技術です。通常の加熱アスファルト混合物の製造温度は、中温化技術を適用しない同種の混合物の配合設計書における混合温度、あるいは事前審査制度における認定書等で示されている製造温度を参考にします。ただし、寒冷期には、通常加熱混合物の製造温度を暖温期よりも若干高めに設定することがあり、その場合の製造温度も通常温度に含めます。
2. 中温化アスファルト混合物の製造方法とプラントにおける留意点
中温化アスファルト混合物の製造方法は、プラントミックスとプレミックスの2種類があります。プラントミックスは、混合物製造時に特殊添加剤あるいはフォームドアスファルトを用いる方法で、プレミックスは、あらかじめアスファルトと特殊添加剤を改質アスファルト製造工場で均一に混合した中温化混合物用アスファルトを用いる方法です。アスファルトプラントにおける中温化混合物の単位時間あたりの製造能力は、通常加熱混合物の製造時とほぼ同じですが、設定された温度条件で製造するために、燃焼設備の調整やホットビンに貯蔵された加熱骨材の処理などが不可欠です。特に、1日に通常加熱混合物と中温化混合物を繰り返し製造する場合や、中温化混合物自体の製造量が少ない場合には、不必要な燃料消費につながり、期待するCO2排出量削減効果が得られない可能性があるため注意が必要です。例えば、製造温度を低減してCO2排出量削減を目的とした工事では、少なくとも100t以上の中温化混合物を連続して製造することが望ましいとされています。中温化技術にはいくつかの種類があり、設計図書に示されていない場合は、その中から選択する必要があります。プラントミックスを用いる場合は、中温化剤を添加するタイミング、添加後の混合時間の設定、あるいは添加時の安全作業方法などを確認しておく必要があります。また、発泡系の中温化混合物の中には、発泡の継続時間に制約を受けるものもあるため、施工場所までの搬送距離や搬送時間などを考慮しなければならない場合があります。
3. 中温化剤の添加量の設定と試験練りのポイント
中温化剤の添加量は、混合温度および締固め温度を目標温度に低減させても、通常加熱混合物と同等の密度(通常加熱混合物との密度比100±0.5%)が得られ、同時に必要な混合物性状も確保されていることを確認して設定します。ここで、「通常加熱混合物と同等の密度」とは、厳密には通常加熱混合物との密度比で100%ですが、マーシャル供試体作製時の密度のバラツキや過去の施工実績などを考慮に入れ、100±0.5%とします。「必要な混合物性状」についても、厳密には通常加熱混合物の各混合物性状値(マーシャル安定度、残留安定度、動的安定度等)と同一と見なせる性状値であることが必要となりますが、工事関連図書等において規格値が示されている場合には、その規格値を満足すれば良いものとします。メーカー推奨値または実績があり、通常加熱混合物と同等の締固め性と品質が得られることが確認されていれば、その添加量を基本として良いものとします。通常加熱混合物との締固め特性や混合物性状を比較する場合は、中温化アスファルトのベースとなっている一般的なアスファルトでの配合設計も行います。配合設計の手順は、通常加熱混合物の場合と同様であり、対象となる混合物に応じて、適切な手順書を参照します。中温化混合物を初めて製造する場合は、骨材の含水比に応じた骨材流量やバーナ開口度、混合時間の設定、中温化剤の添加方法、中温化アスファルト使用の場合の搬入方法などを事前に確認しておく必要があります。中温化混合物は、通常加熱混合物に比べ骨材加熱温度が低いため、目標とする骨材加熱温度や加熱前の骨材含水比によっては、バグフィルターの結露など、プラント設備に影響を与える場合があります。そのため、通常加熱混合物の製造との違いに留意し、事前にプラント設備各所の確認を行うことが望ましいです。試験練りにおいては、骨材の配合比やアスファルト量、中温化剤添加量、中温化混合物の製造温度および混合時間の決定などを行います。
4. 中温化混合物の製造上の留意点とCO2排出量削減効果の算出
中温化混合物は、通常加熱混合物と同様に、アスファルトプラントにおいて適切な温度管理・品質管理のもとで製造します。温度管理や品質管理の方法や頻度は、通常加熱混合物と同様で良いでしょう。ただし、中温化技術は、密粒度アスファルト混合物やポーラスアスファルト混合物、再生加熱アスファルト混合物など、様々な混合物へ適用されるので、それぞれの混合物の製造上の留意点を参考に、製造手順や品質確認項目を定めておくことが望ましいです。混合物製造1tあたりの燃料消費量、CO2排出量およびCO2排出量削減効果の算出手順の一例を示します。アスファルト混合物製造時、コールドフィーダの流量やドライヤのバーナ開口度などが安定した時点で、単位時間あたりの燃料消費量とアスファルト混合物製造量を測定します。計測時間は、燃料消費のバラツキを考慮して連続製造において100分程度以上が望ましいです。単位時間あたりの燃料消費量は、プラント操作盤に備わっている計器などから読み取ります。また、燃料消費量の計測時間はストップウォッチ等で計測します。単位時間あたりのアスファルト混合物製造量は印字記録から算出します。中温化混合物のCO2排出量削減効果を確認する場合は、混合物製造時のCO2排出量は、アスファルトプラントに設置されている流量計等から読み取った製造時の単位時間あたりの燃料消費量を基に求めることができます。混合物の製造量が少なく、骨材の含水比が大きい場合は、コールドフィーダの流量やドライヤのバーナ開口度などが安定しないため、燃料消費量が適切に計測できないことがあるので注意が必要です。
5. 中温化混合物の舗設作業と温度管理
中温化混合物の舗設作業に関する一般的な事項は、「舗装施工便覧(平成18年版)」を参照します。中温化混合物は、通常加熱混合物と同様に、アスファルトフィニッシャによる敷きならしからローラによる転圧終了までの連続作業を迅速に行う必要があります。基準試験は、管理や検査に必要な数値をあらかじめ求めておくこと、中温化混合物に用いる素材の品質、混合物の品質を確認するためなどに実施します。これらが設計図書で規定されている場合は、受注者が基準試験を実施し、その結果については発注者が確認・承諾します。なお、素材については製造者の試験成績表、配合設計についてはアスファルト混合物事前審査制度に合格していれば、その配合設計書を基準試験に代えて用いることができます。転圧作業は、一般に、初転圧、二次転圧、仕上げ転圧が行われます。それぞれの段階における温度管理の目標値は、中温化混合物の製造温度を考慮し、所要の締固め度が得られる範囲で適切に設定します。この場合、例えば、ローラの締固め作業の中で、二次転圧の終了温度の目安を70℃程度(一般的な通常加熱混合物の場合は70℃~90℃)とし、各段階での転圧目標温度を設定すると良いでしょう。アスファルトプラントに温度の印字記録装置を有している場合は、そのデータを利用して温度管理を行うと良いでしょう。中温化混合物を舗設する際の各施工段階における温度管理は、通常加熱混合物と同様にされます。一般には、敷きならし温度、初転圧温度、二次転圧温度、仕上げ転圧温度などについて、施工計画で設定した目標値を元に舗設時の温度管理を行います。
II.中温化剤の種類と特性
中温化剤は、その作用メカニズムによって発泡系、粘弾性調整系(A, B)、滑剤系の3種類に分類されます。それぞれの特性と、プラントミックスとプレミックスにおける添加方法の違いを説明しています。特に、粘弾性調整系は高温域での粘弾性を調整することで製造・施工温度の低下を可能にし、滑剤系はアスファルトと骨材界面の潤滑性を高めて締固め性能を向上させます。発泡系は、微細な泡の発生・分散によって見掛け上のアスファルト容積を増やし、混合性と締固め性を向上させます。
1. 中温化剤の種類と分類
中温化アスファルト混合物に用いられる中温化剤は、その作用メカニズムによって大きく3種類に分類されます。一つ目は発泡系で、アスファルトモルタル内に微細な泡を発生・分散させることで、見かけ上のアスファルト容積を増やし、混合性と締固め性を向上させる効果があります。このタイプは、いずれもプラントミックス方式で用いられます。二つ目は粘弾性調整系です。一定以上の温度で液体として作用し、常温域で固体状態に転換するタイプ(A)と、アスファルトと同様の組成を持つタイプ(B)があります。どちらも高温域での粘弾性を調整することで、混合物全体の製造・施工温度の低下を可能にします。そして、供用温度域での粘弾性は中温化剤無添加のものと同等になるため、混合物の品質は確保されます。三つ目は滑剤系で、アスファルト粘度への影響が少なく、中温化剤の融点以上になるとアスファルトに溶融し、アスファルトと骨材界面の潤滑性を高めます。これにより、骨材間の摩擦抵抗が低減され、少ないエネルギーで締固め性を達成できるという特徴があります。これらの中温化剤は、プラントミックスタイプが多く用いられますが、プレミックスタイプとして使用できるものもあります。プレミックスタイプは、アスファルトと中温化剤を改質アスファルト製造工場で事前に均一に混合したものを用いる方法です。
2. 各中温化剤の作用メカニズムと適用方法
発泡系中温化剤は、アスファルトモルタル内に微細な泡を発生・分散させることで、混合性と締固め性を向上させます。この効果は、舗設後の温度低下と共に消失し、混合物の品質は維持されます。粘弾性調整系Aは、高温域での粘弾性を調整することで、製造・施工温度を低減させます。粘弾性調整系Bは、アスファルトと同様の組成を持ち、その特性はAと同様です。どちらのタイプも、供用温度域での粘弾性は中温化剤無添加の場合と同等になります。滑剤系中温化剤は、アスファルト粘度への影響が小さく、融点以上でアスファルトに溶融してアスファルトと骨材界面の潤滑性を高め、骨材間の摩擦抵抗を低減させます。この潤滑効果により、少ないエネルギーで締固め性が得られます。 これらの中温化剤の添加方法は、プラントミックスタイプが一般的ですが、プレミックスタイプも存在します。プラントミックスタイプでは、添加タイミングや混合時間、安全作業方法の確認が重要です。発泡系の場合は、発泡継続時間への配慮も必要です。中温化技術による混合物製造温度の低減は、骨材加熱温度を低く設定するため、使用する骨材の含水比の状態に注意が必要です。アスファルトプラントでは、骨材を種類別に貯蔵し、相互に混ざり合ったり、ゴミ、泥などが混入しないようにすることは当然ですが、特に降雨にさらされないように十分な対策をとる必要があります。
III.中温化アスファルト混合物の製造と品質管理
中温化混合物の製造は、通常の加熱アスファルト混合物と同様のアスパルトプラントで行われます。ただし、骨材加熱温度が低いことや、中温化剤の添加タイミング、混合時間、発泡系の持続時間といった点に留意が必要です。品質管理においては、目標温度低減幅を考慮した混合温度と締固め温度での供試体作成、通常の加熱混合物と比較した密度(100±0.5%)の確認が重要です。また、CO2排出量削減効果の検証には、単位時間あたりの燃料消費量とアスファルト混合物製造量の測定が不可欠であり、少なすぎる製造量では期待される効果が得られない点も指摘されています。
1. 中温化混合物の製造工程と温度管理
中温化混合物の製造は、通常の加熱アスファルト混合物と同様にアスファルトプラントで行われ、適切な温度管理と品質管理が不可欠です。温度管理や品質管理の方法、頻度は通常加熱混合物と同様で問題ありません。しかしながら、中温化技術は密粒度アスファルト混合物、ポーラスアスファルト混合物、再生加熱アスファルト混合物など様々な混合物に適用できるため、それぞれの混合物の製造上の留意点を考慮し、製造手順や品質確認項目を事前に定めておくことが重要です。中温化混合物の製造においては、骨材の加熱温度が通常より低いため、骨材の含水比に十分注意する必要があります。プラント内では骨材の種類別貯蔵、混入物の防止、特に降雨対策が重要となります。プラントミックス方式の場合、中温化剤の添加タイミング、添加後の混合時間、安全作業方法の確認が不可欠です。発泡系中温化剤を使用する場合は、発泡の継続時間にも配慮する必要があります。CO2排出量削減効果を検証する際には、単位時間あたりの燃料消費量とアスファルト混合物製造量の正確な測定が必須です。製造量が少なく、骨材含水比が大きいと、燃料消費量の適切な計測が困難となるため注意が必要です。少なくとも100t以上の連続製造が、CO2削減効果を最大限に発揮するために推奨されます。
2. 中温化剤添加量の設定と品質確認
中温化剤の添加量は、目標温度に低減させても通常加熱混合物と同等の密度(100±0.5%)と必要な混合物性状が確保されることを確認して決定されます。密度は、マーシャル供試体作製時のバラツキや過去の施工実績を考慮し、100±0.5%の範囲内で評価されます。混合物性状は、工事関連図書等の規格値を満たすか、もしくはメーカー推奨値や実績に基づき、通常加熱混合物と同等の締固め性と品質が得られることを確認します。中温化アスファルトのベースとなる一般的なアスファルトを用いた配合設計も、比較のために行われます。配合設計手順は通常加熱混合物と同様です。初めて中温化混合物を製造する際には、骨材の含水比に応じた骨材流量やバーナ開口度、混合時間の設定、中温化剤の添加方法、中温化アスファルト使用時の搬入方法などを事前に確認する必要があります。また、骨材加熱温度が低いことから、バグフィルターの結露などプラント設備への影響も考慮する必要があります。試験練りでは、骨材配合比、アスファルト量、中温化剤添加量、製造温度、混合時間などを決定します。特に、出荷実績がない場合は、通常加熱混合物と中温化混合物を目標温度で製造し、マーシャル供試体による密度比較や各種性状試験を行います。中温化技術によっては、混合物製造から供試体作製まで一定時間の養生が必要な場合もあります。プレミックス方式では、製品ごとの取扱い方法を確認した上で製造準備を行う必要があります。試験練りは、一般的に通常加熱混合物と同様の手順で行います。
IV.中温化アスファルト混合物の舗設と耐久性
中温化混合物の舗設作業は、通常の加熱アスファルト混合物と同様に行われますが、温度管理が重要です。早期交通開放の可能性についても言及されており、温度低下の速さから交通規制時間の短縮効果が期待できます。 国土交通省の調査では、中温化舗装のわだち掘れ量やMCI(維持管理指数)が通常の舗装とほぼ同等であり、耐久性に対する懸念は少ないと結論づけられています。 空港滑走路の補修工事における事例も紹介されており、夜間施工と散水冷却を組み合わせることで、早期開放を実現した成功例が示されています。
1. 中温化混合物の舗設作業と温度管理
中温化混合物の舗設作業は、通常加熱混合物と同様、アスファルトフィニッシャによる敷きならしからローラによる転圧終了までの一連の作業を迅速に行う必要があります。「舗装施工便覧(平成18年版)」も参照ください。各施工段階における温度管理は、敷きならし温度、初転圧温度、二次転圧温度、仕上げ転圧温度などについて、施工計画で設定した目標値に基づいて行われます。二次転圧終了温度の目安は、70℃程度(通常加熱混合物は70~90℃)とされ、製造温度を考慮して適切に設定する必要があります。アスファルトプラントに温度の印字記録装置がある場合は、そのデータを活用して温度管理を行うことが推奨されます。施工後には、適切な形式で工事記録を保存することが重要です。工事結果の記録は、中温化舗装技術の改善だけでなく、維持管理計画のための基礎資料となります。工事内容、施工時の外気温、敷きならし温度、転圧温度などの温度データ、使用した骨材の含水比、施工機械の編成、転圧回数などをできる限り詳細に記録しておくことが推奨されます。
2. 中温化舗装の早期交通開放と交通規制時間短縮効果
交通規制を伴う補修工事において、中温化混合物を使用することで、混合物温度が低いことから交通開放までの規制時間を短縮できます。規制時間を同じにすれば日施工量を増やせるため、工期の短縮も可能です。規制時間や工期の短縮は、補修工事における交通渋滞の緩和にも繋がり、交通車両の排気ガスや騒音等の沿道環境の改善にも寄与します。空港滑走路の補修工事の事例では、全層42cmの帯状厚層打換えと平均厚16cmの全面切削オーバーレイに中温化混合物を適用し、夜間の厳しい時間制約のもとで舗設し、翌朝からの早期開放を目指しました。この工事では、シックリフト工法による30℃低減の大粒径アスコンの他に、表層・基層にも30℃および50℃低減の2種類の中温化混合物が用いられました。特に荷重条件が厳しい航空機のタイヤが接触する走行部や滑走路端部には、50℃低減の中温化混合物と散水冷却を組み合わせることで、供用開始時の舗装表面温度を50℃以下にすることができました。試験舗装の事例では、基層3層と表層1層を同日施工し、舗装体内部温度を熱電対で測定することで、交通開放時期を検討しました。結果、通常加熱混合物と比較して、30℃低減した中温化混合物では内部温度の降下速度が速く、交通開放温度(舗装表面温度50℃以下)に達するまでの時間が約2時間短縮されました。交通開放までの規制時間短縮効果には幅があり、混合物の温度低下が舗設時の気象条件、表層・基層施工厚、製造時の設定温度などに影響されますが、同一の気象条件と施工条件下では少なくとも30分程度の時間短縮効果があると推察されます。
3. 中温化舗装の耐久性に関する調査結果
国土交通省関東地方整備局管内の直轄国道で施工された中温化舗装(製造温度を30℃程度低減)の耐久性について、施工後2ヶ月~10年程度経過した路面性状データを用いた調査が行われました。この調査では、中温化舗装と、同じ路線の近隣で同時期に施工された通常舗装における路面性状値の区間平均値を比較・検討しました。調査区間における中温化混合物は、表層に適用された区間が2箇所、基層に適用された区間が8箇所、アスファルト安定処理に適用された区間が3箇所でした。調査結果の一部は図表に示されています。中温化舗装(中温化技術適用区間)は、わだち掘れ量、MCI(Maintenance Control Index:維持管理指数)ともに、従来の通常舗装(従来舗装区間)とほぼ同等と評価されており、現時点では耐久性に関する懸念は少ないとされています。MCIは、路面のひび割れ率、わだち掘れ量、平坦性から計算される指数です。
V.今後の展望
グリーン購入法に基づく特定調達品目への中温化アスファルト混合物の追加により、その普及が期待されています。しかし、再生加熱アスファルト混合物やポーラスアスファルト混合物への適用はまだ限定的です。国土交通省では、これらの混合物への適用拡大に向けた検証試験が実施されており、今後の展開が注目されます。CO2排出量削減という観点から、様々な種類のアスファルト混合物への幅広い適用と、早期実現のための普及促進策が重要となります。
1. 中温化技術の普及拡大に向けた取り組み
2010年2月、中温化アスファルト混合物はグリーン購入法に基づく特定調達品目に追加され、本格的な普及段階を迎えています。これは、地球温暖化対策におけるCO2排出量削減への貢献が期待される中温化技術の社会的意義の高まりを示しています。しかしながら、中温化技術の舗装工事全体における実績はまだ少なく、特にCO2削減の観点からの適用は限定的でした。 再生加熱アスファルト混合物やポーラスアスファルト混合物などは、グリーン購入法に基づく特定調達品目においては、実績が少ないため、適用外とされています。国土交通省では、これらの混合物への適用に関する検証を試験工事で実施し、その追跡調査等の結果に基づいて、特定調達品目における制限の解除に向けて働きかけています。特に再生加熱アスファルト混合物は、我が国における加熱アスファルト混合物の製造量に占める割合が大きく、CO2排出総量の削減に大きく影響するため、当該混合物への適用検討が強く求められています。中温化技術は、10数年前から試験施工が行われ、各種用途に幅広く適用されながら技術的にも着実に進歩してきましたが、舗装工事全体から見た実績は少なく、地球温暖化抑制というCO2削減の観点からの適用は限定的でした。しかし、グリーン購入法に基づく特定調達品目への追加により、今後、広範な適用が期待できる状況になっています。
2. 中温化技術によるCO2排出量削減効果の検証事例
中温化技術によるCO2排出量削減効果は、いくつかの事例研究で検証されています。切削オーバーレイ工事(表層5cm)において、製造温度を30℃低減した再生骨材配合率30%の中温化混合物を舗設し、通常加熱混合物との比較が行われました。その結果、混合物1tあたり3.7kg-CO2/tの低減、約18%の削減効果が確認されました。別の切削オーバーレイ工事(t=5cm)では、通常加熱混合物と30℃低減した中温化混合物を比較し、アスファルトプラントにおける燃料使用量からCO2排出量を算出しました。その結果、中温化混合物は通常加熱混合物に比べて、製造時のCO2排出量が14.6%削減されたことが確認されました。これらの事例は、中温化技術がアスファルト混合物の製造過程におけるCO2排出量削減に有効であることを示しています。環境面からの適用を考えれば、舗装分野におけるCO2排出量の抑制に関し、アスファルト混合物製造時での削減が図れる中温化技術が有効であることは確かです。より一層CO2を削減していくためには、各種の混合物に幅広く適用するとともに、早期実現のための普及段階における対策が必要となります。
