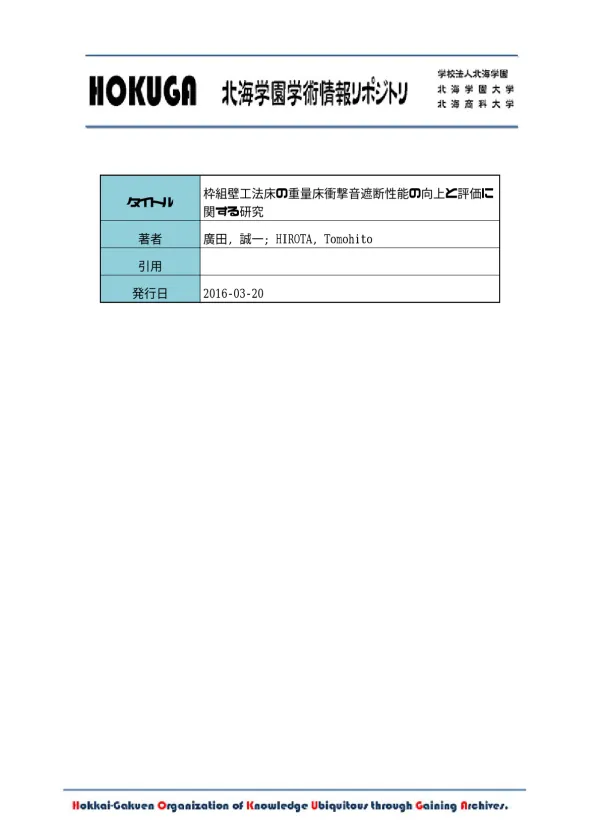
乾式二重床:遮音性能向上への検討
文書情報
| 著者 | Hirota, Tomohito |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 8.70 MB |
概要
I.木造共同住宅における重量床衝撃音問題と乾式二重床構造
本研究は、木造共同住宅、特に枠組壁工法における重量床衝撃音問題の解決に焦点を当てている。現状、多くの自治体では公営住宅の木造化を進めているものの、床衝撃音遮断性能はRC造に劣り、特に重量床衝撃音の対策は困難である。そのため、乾式二重床構造が有効な対策として注目されている。
1. 北海道における木造公営住宅の現状と課題
木材利用促進の流れを受け、北海道ではRC造中心だった公営住宅を木造化する動きが進んでいる。多くの自治体条例では、住宅性能表示制度を利用し、重量床衝撃音遮断性能を表示することが義務付けられている。基準となるのは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく相当スラブ厚(重量床衝撃音)11cm以上の仕様である。しかし、実測値はRC造の民間分譲マンションと比較して著しく劣っており、木造共同住宅の重量床衝撃音遮断性能の向上は喫緊の課題となっている。少なくともRC造公営住宅と同等、できれば民間分譲マンションに匹敵する性能の確保が求められる。 軽量床衝撃音と重量床衝撃音の違いも明確にされており、軽量床衝撃音は比較的対策が容易だが、重量床衝撃音は木造住宅において対策が難しく、普及が進んでいない現状が指摘されている。本研究では、この技術的に困難な重量床衝撃音の低減に焦点を当てている。
2. 重量床衝撃音と軽量床衝撃音の違いと対策の難しさ
床衝撃音は重量床衝撃音と軽量床衝撃音に分類される。軽量床衝撃音は、海外のように室内で靴を履く生活を想定したもので、床の表面を柔らかくすることで衝撃時間を長くし、ピークの衝撃力を低下させる対策が比較的容易である。一方、重量床衝撃音は、日本の室内で靴を脱いで生活する状況を想定したものであり、木造住宅のような軽量な床構造では対策が非常に難しい。多くの研究が行われているものの、効果的な対策は未だ普及しておらず、本研究ではこの重量床衝撃音の低減に焦点を当てている。 従来、重量床衝撃音の評価には逆A特性に基づくL等級の評価曲線が用いられてきたが、この評価方法では主観評価との相関が低いという課題が指摘されている。そのため、本研究では、ラウドネスや最大A特性床衝撃音レベル(LiA,Fmax)など、主観評価との相関性の高い指標を用いた評価方法の検討も行われる。
3. 乾式二重床構造による重量床衝撃音遮断性能向上への期待
木造床の重量床衝撃音遮断性能を向上させるには、駆動点インピーダンス、つまり面密度と曲げ剛性を高めて振動を抑制することが基本となる。しかし、RC造床スラブと同等の性能を得るには、RC造と同等の駆動点インピーダンスが必要であり、これが木造床での重量床衝撃音対策の困難さを示している。 そこで、RC造床スラブ厚が薄かった時代に普及した湿式浮床工法のように、緩衝層を持つ浮床工法が軽量な木造住宅への適用において有効であると考えられる。特に、首都圏のRC造マンションで普及している乾式二重床構造は、スラブ面の不陸調整が不要、設備配管が可能、軽量床衝撃音遮断性能の向上が期待できるといったメリットがあり、重量床衝撃音遮断性能の向上も目指せることから本研究で注目されている。しかし、初期の乾式二重床構造では、スラブ素面よりも性能が低下するケースが多く、その性能向上のための研究が数多く行われてきた。
4. 高倉ら 豊田らの研究と乾式二重床構造の性能に関する知見
高倉らの研究では、RC造における現場測定に基づき、支持脚の接着方法、床高さ、防振ゴムの形状や硬度、床端部支持方法(際根太の有無など)、床端部隙間、吸音体の効果、施工方法(床先行工法、壁先行工法)など、様々な要素が重量床衝撃音レベルに与える影響が報告されている。 豊田らの研究では、乾式二重床構造の支持脚と空気層のバネによる振動伝搬について数値シミュレーションを行い、支持脚のバネ定数や空気抜きの有無が重量床衝撃音遮断性能に及ぼす影響を明らかにしている。これらの研究成果は、乾式二重床構造の性能を最適化し、重量床衝撃音遮断性能を向上させるための重要な知見を提供している。 また、共同住宅と戸建住宅における遮音対策に関するアンケート調査の結果、共同住宅では施工前の質問が多いものの入居後の不満は少ない傾向がある一方、戸建住宅では施工前の質問は少ないが、入居後に不満を訴える人が多いことが示されている。この差は、共同住宅では標準仕様として遮音対策が施されているのに対し、戸建住宅ではそうではない場合が多いことが原因と考えられる。
II.重量床衝撃音の評価方法と課題
従来のL数による評価方法は、主観的なうるささとの相関が低いという課題がある。本研究では、ラウドネスや最大A特性床衝撃音レベル (LiA,Fmax)といった、主観評価との相関性の高い指標を用いて重量床衝撃音を評価する。ゴムボール衝撃源を用いた評価方法も検討されている。
1. 従来の重量床衝撃音評価方法 L数による評価と限界
従来、重量床衝撃音の評価には、逆A特性に基づくL等級の評価曲線が用いられてきました。これは日本建築学会規準や日本住宅性能表示基準にも採用されており、多くの測定データが蓄積されています。しかし、JIS制定後の研究では、このL数による評価方法に課題が指摘されています。主観評価実験の結果、心理尺度構成値はL数よりも、ラウドネスや最大A特性床衝撃音レベル(LiA,Fmax)、オクターブバンド毎の算術平均値などとの相関が高いことが多数報告されています。つまり、L数は必ずしも人の感じる「うるささ」を正確に反映しているとは言えないのです。 このことは、L数だけを指標とした設計では、実際にはうるさく感じられる可能性があることを意味します。より正確な評価と、居住者の体感に合わせたより適切な対策を講じるためには、従来の方法を見直す必要性が示唆されています。より実態に即した評価指標の活用が求められています。
2. 主観評価との高い相関を示す新たな評価指標の提案
従来のL数による評価方法の限界を踏まえ、本研究では、主観評価との相関性の高い新たな評価指標の活用を提案しています。具体的には、ラウドネスや最大A特性床衝撃音レベル(LiA,Fmax)が挙げられます。ラウドネスは、人の感じる音の大きさをより正確に表現できる指標ですが、算出に手間がかかるというデメリットがあります。一方、最大A特性床衝撃音レベル(LiA,Fmax)は、ラウドネスと高い相関を示しながらも、現場での簡易な測定に適しているため、実務的な側面からも有効な指標と考えられます。 佐藤らの研究では、床衝撃音を「うるさく感じる割合」と最大A特性床衝撃音レベルの関係性が示されており、この指標を用いることで、設計段階から居住者の体感に配慮した設計が可能になります。様々な先行研究でも、最大A特性床衝撃音レベルと主観評価との高い相関性が確認されており、本研究でもこの指標を重視した評価を行うことで、より効果的な対策工法の開発に繋げることが期待されます。 また、ゴムボール衝撃源を用いた評価方法についても言及されており、日常的な歩行音に近い衝撃力を再現できる点から、より現実的な評価を行う上で有効な手段として位置付けられています。
3. ゴムボール衝撃源を用いた評価方法の有効性と課題
人の歩行とゴムボール衝撃源の衝撃力は波形が異なるため、ピーク衝撃力だけを比較することはできません。しかし、住宅内でタイヤ衝撃源のような強い衝撃が発生することは稀であると考えられることから、日常的に発生する人の歩行と同程度の衝撃力を持つゴムボール衝撃源を用いた評価が、「うるさく感じない床」の設計には重要になります。 特に、ゴムボール衝撃源0.1m落下を評価基準として用いることが効果的であるとされています。ただし、佐藤らの研究では、ゴムボール衝撃源の落下高さ(0.1m、0.5m、1.2m)と最大A特性床衝撃音レベルの相関関係も示されており、落下高さによる影響についても考慮する必要があることを示唆しています。 したがって、ゴムボール衝撃源を用いた評価方法の有効性と同時に、衝撃力の大きさや落下高さによる影響を適切に評価・検討することが重要であり、より精緻な評価手法の確立が今後の課題と言えるでしょう。
III.乾式二重床構造の性能と影響要因
乾式二重床構造の床衝撃音遮断性能は、駆動点インピーダンス(面密度と曲げ剛性)に大きく依存する。支持脚の接着方法、床高さ、防振ゴムの特性、施工方法(床先行工法など)といった要素が性能に影響を与える。高倉ら、豊田らの研究は、これらの影響を数値シミュレーションや実験で明らかにしている。
1. 乾式二重床構造の概要と特徴
乾式二重床構造は、首都圏を中心にRC造民間分譲マンションで普及している工法です。主な特徴として、スラブ面の不陸調整が不要であること、スラブ上に設備配管などが可能であること、そして軽量床衝撃音遮断性能の向上と、重量床衝撃音遮断性能がスラブ素面の性能を下回らない点が挙げられます。図2.12に示されているように、軽量床衝撃音に関しては性能向上効果が明確に示されています。しかし、普及当初は重量床衝撃音遮断性能がスラブ素面を下回るケースも多く、その性能向上のため多くの研究が行われてきました。 一般的な構成としては、上から木質フローリング、パーティクルボード(20mm)、支持脚(プラスチックまたは鋼製で高さが様々)、ゴムという層状構造となっています。パーティクルボードの寸法は600mm×1820mmが多く用いられています。床衝撃音遮断性能を確保するためには、幅木とフローリング間に隙間を設ける、壁際の根太には防振根太を用いるなどの納まりに注意が必要であり、詳細については第4章と第5章で解説されています。
2. 乾式二重床構造の性能に影響を与える要因
乾式二重床構造の性能、特に重量床衝撃音遮断性能に大きく影響を与えるのは、駆動点インピーダンスです。これは、面密度と曲げ剛性によって決定されます。高倉らの研究(例:2.11)では、RC造の現場測定結果に基づき、支持脚の接着方法、床高さ、防振ゴムの形状や硬度、床端部支持方法(際根太の有無など)、床端部隙間、吸音体の効果、施工方法(床先行工法、壁先行工法)など、様々な要素が重量床衝撃音レベルに影響を与えることを明らかにしています。 豊田らの研究(例:2.12)では、数値シミュレーションを用いて、乾式二重床構造の支持脚と空気層のバネによる振動伝搬メカニズムを解明し、支持脚のバネ定数や空気抜きの有無が重量床衝撃音遮断性能に大きな影響を与えることを示しています。これらの研究から、乾式二重床構造の性能は、構成要素や施工方法など、様々な要因の複雑な相互作用によって決定されることがわかります。そのため、性能を最適化するためには、これらの要因を詳細に検討する必要があります。
3. 乾式二重床構造における設計上の留意点と今後の研究開発
乾式二重床構造の設計においては、床衝撃音遮断性能を確保するためのいくつかの留意点があります。具体的には、幅木とフローリング間に隙間を設けること、壁際の根太には防振根太を用いることなどが挙げられます。これらの納まりに関する詳細は、第4章と第5章で詳しく解説されています。 RC造床に乾式二重床構造を施工した場合の研究は数多く行われており、衝撃源の加振力と床衝撃音レベル低減量の関係、端部の納まり、床先行工法など、多くの課題が解明されてきました。しかし、木造床についても同様の検討が必要であり、特に木造床における床衝撃音遮断性能の等級は、相当スラブ厚(重量床衝撃音)11cm以上の仕様でLi,Fmax,r,H(1) -65程度が得られると考えられていますが、これを超える性能を一般化するためには、乾式二重床構造の仕様と性能の関係を詳細に把握し、性能を予測できるモデルの構築が重要となります。
IV.入居者の遮音対策に関する認識とニーズ
アンケート調査によると、入居者の多くが居住住宅の遮音性能について認識が不足しており、特に木造共同住宅では入居前後の認識にずれがある。入居者は床衝撃音遮断性能の向上と、性能表示の促進を望んでいる。
1. 住宅の遮音対策に関する認知度調査
居住者の遮音対策に関する認知度を把握するため、「あなたが住んでいる住宅には、住戸間などに音を伝えにくくする対策が行われていますか?」という質問を含むアンケート調査を実施しました。その結果、「わからない」という回答が最も多く、次いで「何も行われていない」という回答でした。この2つの回答を合わせると、全体の約9割を占めています。これは、賃貸住宅の場合、契約時に事業者から遮音性能に関する説明がない限り、入居者はその性能を認識できないことを示唆しています。 特に、遮音性能が問題になりやすい木造共同住宅においては、事業者と入居者間で遮音性能に関する十分な確認が行われていない可能性が高いことが懸念されます。この結果は、遮音性能に対する認識の低さと、情報提供の不足を浮き彫りにしています。より明確な情報提供と、入居者側の遮音性能に対する理解を深めるための啓発活動が必要であると考えられます。
2. 共同住宅と戸建住宅における遮音対策に関する意識の比較
アンケート調査では、共同住宅と戸建住宅における遮音対策に関する意識についても比較検討されました。その結果、共同住宅では施工前の質問が多く、入居後の不満は少ない傾向が見られました。一方、戸建住宅では施工前の質問は少なく、入居後に不満を訴える人が多い傾向が見られました。自由記述による分析からは、共同住宅ではモルタル38mmやせっこうボード15mm×2の追加、天井懐への吸音材設置、独立天井+せっこうボード増張りといった標準的な遮音対策が実施されているケースが多いことが判明しました。 対照的に、戸建住宅では遮音対策が標準で実施されていないケースが多く、これが入居後の不満増加に繋がっていると考えられます。この結果は、共同住宅と戸建住宅で遮音対策に対する意識やニーズが大きく異なることを示しており、それぞれの住宅形態に適した遮音対策と情報提供のあり方を考える上で重要な示唆となります。特に戸建住宅においては、遮音対策に関する情報提供の充実と、適切な対策の普及促進が求められます。
3. 入居者のニーズ 遮音性能の向上と性能表示の促進
アンケート調査の結果から、入居者は現状の住宅の遮音性能に満足しておらず、性能向上と性能表示を強く望んでいることが明らかになりました。特に、床衝撃音に関する不満が多く、より高い遮音性能を持つ住宅へのニーズが非常に高いことがわかります。このニーズに応えるためには、遮音性能の向上はもちろんのこと、その性能を客観的に示すための性能表示の促進が不可欠です。 現在、北海道庁では北海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合研究所と共同で、民間賃貸共同住宅の簡易な性能表示に関する社会実験等を行っています。また、夕張市のように、民間賃貸住宅建設の補助金交付要件として遮音性能を確保させる事業も行われており、自治体レベルでの取り組みも進められています。これらの取り組みをさらに推進し、より多くの民間賃貸共同住宅で遮音性能が表示されるようになれば、入居者の意識向上にも繋がり、遮音性能の改善と普及に大きな弾みとなることが期待されます。
V.乾式二重床構造の性能予測と最適化
本研究では、枠組壁工法床に乾式二重床構造を施工した場合のデータ蓄積を行い、際根太の仕様の違い、幅木の空気抜きの有無、支持脚の位置関係といった要因が床衝撃音レベルに与える影響を実験的に明らかにした。駆動点インピーダンスの向上によって、床衝撃音レベルを効果的に低減できることが示された。
1. 枠組壁工法床への乾式二重床構造施工とデータ蓄積
本研究では、木造共同住宅における重量床衝撃音遮断性能の向上を目指し、枠組壁工法床に乾式二重床構造を施工した場合のデータ蓄積を行いました。 乾式二重床構造の性能に影響を与えると考えられる要因として、「際根太の仕様の違い」、「幅木の空気抜きの有無」、「枠組壁工法床の根太と乾式二重床構造の支持脚の位置関係」の3点に着目し、実験的検討を通してそれらの影響を明らかにすることを目的としています。 実験では、インパクトハンマ(PCB086D20)を用いて加振を行い、振動速度と衝撃力を測定しました。加振点は1点につき3回測定し、振動速度と衝撃力は3回のエネルギー平均値として算出されました。測定データはFFTにより周波数分析され、1/3オクターブバンド毎の値、さらにオクターブバンド毎に合成した値を用いて分析が行われました。
2. 駆動点インピーダンスと床衝撃音レベルの関係
実験結果の分析では、駆動点インピーダンスと床衝撃音レベルの関係に着目しました。125Hz帯域では、床衝撃音レベルは局部的なインピーダンス変化の影響をほとんど受けず、ほぼ一定の値を示しました。これは、この帯域ではゴムボール衝撃源による加振の影響範囲が広く、狭い範囲での変動は平均化されるためと考えられます。一方、63Hz帯域と125Hz帯域では、根太方向において端部(1170mm)になるほど駆動点インピーダンスレベルの上昇が見られ、特に63Hz帯域では、この上昇に伴って床衝撃音レベルも低下していました。 他の周波数帯域では、駆動点インピーダンスと床衝撃音レベルの関係は必ずしも明確ではありませんでした。このことから、乾式二重床構造の性能予測においては、周波数特性を考慮したより詳細な検討が必要であることが示唆されます。また、JIS A 1440-2:2007では「床衝撃音レベル低減量」が定義されていますが、枠組壁工法床やゴムボール衝撃源を使用するケースは含まれていないため、本研究では「床衝撃音レベル差」という表現を用いています。
3. 性能予測のための検討 駆動点インピーダンスと床衝撃音レベルの関係 衝撃源の種類の影響
乾式二重床構造面材部分の駆動点インピーダンスは、床衝撃音レベルに大きな影響を与える重要な指標です。 本研究では、試験室において木造床に乾式二重床構造を施工した場合の床衝撃音レベルと乾式二重床構造面材部分の駆動点インピーダンスの関係を実験的に明らかにしました。 その結果、床衝撃音レベル差は、タイヤ衝撃源よりもゴムボール衝撃源を用いた場合に大きくなる傾向が見られました。さらに、駆動点インピーダンスレベル差と曲げ剛性レベル差、面密度レベル差との関係についても検討を行い、これらの指標が床衝撃音レベルにどのように影響するかを明らかにしました。 タイヤ衝撃源とゴムボール衝撃源の比較では、63Hz帯域で最大+10dB、125Hz帯域で最大+12dBといった床衝撃音レベル差が確認されました。先行研究では、RC造床に乾式二重床を施工した場合の床衝撃音レベル低減量は、本研究で得られた床衝撃音レベル差よりも小さい傾向が報告されており、これは基本床の駆動点インピーダンスの違いによるものと考えられています。これらの結果を基に、より高性能な乾式二重床構造の開発、さらには木造床に適した乾式二重床構造の開発が期待されます。
VI.主観評価実験と結果
主観評価実験では、ゴムボール衝撃源を用いて、異なる仕様の枠組壁工法床とRC造床の重量床衝撃音を比較した。その結果、ラウドネス最大値レベルが心理尺度構成値との相関が最も高く、次に**最大A特性床衝撃音レベル (LiA,Fmax)**が続いた。L数との相関は最も低かった。
1. 主観評価実験の方法 一対比較実験と刺激呈示
第6章では、異なる床構造を持つ枠組壁工法床の重量床衝撃音について、主観評価実験を実施しました。実験は一対比較法を用いて行われ、被験者には2つの異なる床構造からの衝撃音を提示し、どちらが「気になる」かを判断してもらいました。 床衝撃音のサンプルは、日本建築総合試験所の箱型試験室(受音室容積70m3)の鉄筋コンクリート床(150mm厚、2.7m×3.7m)と、建築研究所残響室(受音室容積208m3)に施工された4種類の木造枠組壁工法床(3.0m×4.0m)を使用しました。RC造床は、北海道のRC造公営住宅で使用されている木質フローリングを置き敷きしたもので、木質フローリングの裏面には厚さ3mmのエチレン酢酸ビニル樹脂が取り付けられています。枠組壁工法床は、ベースとなる枠組壁工法床に乾式二重床構造を施工したものです。 刺激呈示においては、画面に提示された言葉の書いてあるボタンを押させる方法を用い、被験者は一度の実験で同時に1名参加しました。被験者には2刺激が提示された後にボタンを押させ、実験はボールについては衝撃源落下地点を2つと5種類の床、落下高さ2種類の組み合わせで20刺激を用い、前後入れ替えと同一刺激も含めて400対の聴取を行いました。被験者1名につき1種類の実験につき1試行の実験を行いました。
2. 実験結果 RC造床との比較と心理尺度構成値との相関
実験の結果、ゴムボール衝撃源を用いて加振した全ての床構造において、コンクリート床よりも「うるささ」が小さいと評価されました。これは、木造枠組壁工法床に乾式二重床構造を施工することで、重量床衝撃音の低減効果が得られることを示唆しています。 さらに、心理尺度構成値との相関を検討した結果、ラウドネス最大値レベルが最も高く、次に最大A特性床衝撃音レベル(LiA,Fmax)が続き、L数が最も低い値となりました。この結果は、ラウドネスや最大A特性床衝撃音レベルが、人の感じる「うるささ」をより正確に反映していることを示しています。 床中央部加振と端部加振の比較では、ラウドネス最大値レベルと心理尺度構成値の関係において、床中央部加振の方が端部加振よりも「気になる程度」が大きいという結果が得られました。この傾向はRC造床よりも枠組壁工法床で顕著に現れました。これは、RC造床では低い周波数帯域で端部と中央部の周波数特性に差が大きく、木造床では高い周波数帯域で差が大きくなる傾向があるためと考えられます。
3. 評価方法の検討 ラウドネス 最大A特性床衝撃音レベル L数の比較
本研究では、床衝撃音の評価方法についても検討を行いました。その結果、心理尺度構成値との相関は、ラウドネス最大値レベルが最も高く、次に最大A特性床衝撃音レベル(LiA,Fmax)が続き、L数が最も低いという結果が得られました。このことは、従来広く用いられてきたL数による評価方法よりも、ラウドネスや最大A特性床衝撃音レベルを用いる方が、人の感じる「うるささ」をより正確に反映できることを示しています。 ラウドネスは、人の感じる音の大きさをより正確に表現できる優れた指標ですが、計算に手間がかかるという課題があります。一方、最大A特性床衝撃音レベルは、ラウドネスと高い相関を示しながらも、現場で容易に測定できるという利点があります。そのため、設計現場においては、比較的簡単に使用できる最大A特性床衝撃音レベルを有効な単一数値評価量として活用することが有効だと考えられます。 この研究結果は、今後、より適切な床衝撃音対策工法の開発や、設計基準の策定に役立つ重要な知見となると考えられます。特に、最大A特性床衝撃音レベルを用いた簡易な評価方法の普及は、木造住宅の遮音性能向上に大きく貢献すると期待されます。
VII.今後の課題と展望
木造共同住宅の床衝撃音遮断性能向上のためには、乾式二重床構造の最適化、性能表示制度の活用促進、簡易な性能評価方法の開発、さらには、官民連携による情報発信が重要である。カナダNRCのように、具体的な仕様と性能データを公開することも有効な手段となる。
1. 木造共同住宅における重量床衝撃音対策の更なる高度化
本研究で得られた知見を基に、木造共同住宅の重量床衝撃音対策をさらに高度化していく必要があります。現状、日本住宅性能表示制度における相当スラブ厚11cm以上の仕様は、RC造公営住宅並みの性能を確保できる基準となっていますが、民間分譲マンションに匹敵する性能を確保するには、更なる工夫が必要です。 本研究で検証した乾式二重床構造は、現状考えられる最良の工法の一つですが、他の工法でも同様の性能が実現できる可能性があります。一つの工法に固執するのではなく、多様な視点から新たな工法開発を進め、その成果を積極的に情報発信していくことが重要です。カナダ国立研究機構(NRC)のように、壁・床・天井の仕様とその性能データを公開する取り組みは、今後の遮音工法普及のカギとなるでしょう。 枠組壁工法床に乾式二重床工法を用いた実績を増やし、国の性能表示制度に具体的な仕様を示す、または特別評価方法認定を受けることが、工法の普及促進に不可欠です。
2. 性能表示の促進と簡易な評価方法の普及
民間賃貸共同住宅において、床衝撃音遮断性能の実態把握は困難ですが、入居者は現状の遮音性能に満足しておらず、性能向上と性能表示を強く求めています。北海道庁と北海道立総合研究機構建築研究本部北方建築総合研究所による社会実験や、夕張市における補助金交付事業のように、官民一体となった性能表示の促進が重要です。 性能表示の普及により、入居者の意識が高まり、遮音性能の向上が促進されると考えられます。そのため、ゴムボール衝撃源と最大A特性床衝撃音レベルを用いた迅速で簡易な評価方法の普及が望まれます。この方法であれば、現場での測定が容易になり、より多くの住宅で遮音性能を表示することが可能となるため、入居者にとって有益な情報提供に繋がります。 現状、大手建材メーカー数社からLi,Fmax,r,(H1)-60を満足する仕様が販売されていますが、現場での測定結果の情報や、工法の種類が限られているなどの課題があります。木造床の遮音工法は、研究開発に多大な時間とコストを要するため、官民一体となった取り組みが不可欠です。
3. 研究開発体制の構築と情報共有の重要性
木造床の遮音工法の研究開発には、多くの時間とコストを要するため、大手メーカー以外での開発が進んでいないのが現状です。この状況を変えるには、官民連携による研究開発体制の構築が不可欠です。 また、木造住宅に関する遮音工法の講習会もほとんど開催されていません。遮音工法に関する設計情報を提供する講習会を積極的に開催していくことで、設計者や施工者の知識・技術向上を図り、高性能な遮音工法の普及を促進する必要があります。 本研究で得られた知見は、現状考えられる最良の工法の一つを示していますが、更なる性能向上のためには、乾式二重床構造の面材部分の駆動点インピーダンスを高めること、そして木造床に最適化された乾式二重床構造の開発が期待されます。これらの取り組みを通して、木造建築における重量床衝撃音問題の解決に貢献していくことが、今後の課題であり、展望です。
