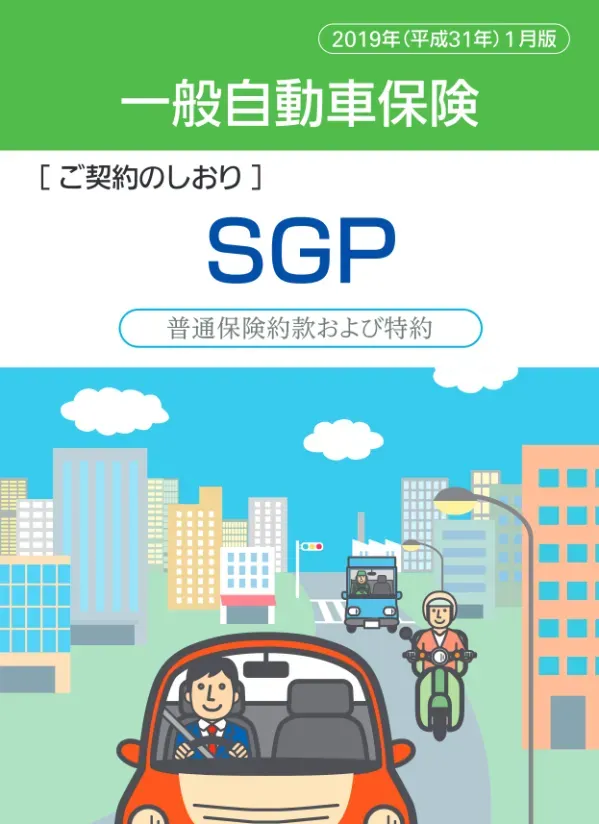
事故対応ガイド|損保ジャパン日本興亜
文書情報
| 著者 | 損保ジャパン日本興亜 |
| 会社 | 損保ジャパン日本興亜 |
| 場所 | 東京都新宿区西新宿 |
| 文書タイプ | 保険契約約款 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.66 MB |
概要
I.対象車両と代理店業務
本自動車保険は、車検済みの登録自動車と検査対象軽自動車が対象です。取扱代理店は、損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、告知受付、契約締結、保険料の領収、契約管理などの代理業務を行います。代理店を通して契約された保険は、損保ジャパン日本興亜との直接契約となります。この自動車保険は、お客様の安心を第一に考え、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
1. 対象車両の明確化
本資料において保険の対象となる自動車は、自動車検査(いわゆる「車検」)の対象である登録自動車と検査対象軽自動車に限定されています。これは、保険適用を受ける車両を明確に規定し、保険契約の範囲を限定することで、保険金支払いの迅速化と不正請求の防止に繋がる重要な規定です。 車検を受けていない車両、あるいは登録されていない車両は、本保険の対象外となります。 この点について、契約者には明確に理解していただく必要があります。 対象車両の範囲を限定することで、保険会社はリスク管理をより効果的に行い、保険料設定の精度を高めることができます。 保険契約締結前に、車両の登録状況や車検の有効期限などを確認することは、契約者にとっても重要な手続きとなります。 不適切な車両が保険の対象となることを防ぎ、保険契約の透明性を確保する上でも、この対象車両の限定は極めて重要です。
2. 取扱代理店と損保ジャパン日本興亜との関係
取扱代理店は、損保ジャパン日本興亜との委託契約に基づき、保険業務の一部を代行しています。具体的には、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、そして契約の管理業務など、保険契約成立に関わる重要な業務を代理店が担っています。この委託契約は、損保ジャパン日本興亜が代理店業務を効率的に運営するために不可欠な仕組みであり、お客様にとって、より身近で迅速な保険サービスの提供を可能にしています。ただし、代理店は損保ジャパン日本興亜の代理として業務を行っているため、最終的な契約責任は損保ジャパン日本興亜にあります。 代理店を通じて契約が成立した場合でも、保険契約は損保ジャパン日本興亜との直接契約として有効に成立する旨が明記されており、契約者にはこの点を明確に理解していただくことが重要です。 代理店と損保ジャパン日本興亜との明確な役割分担と責任の所在は、保険契約の透明性と信頼性を確保する上で極めて重要です。
3. 損保ジャパン日本興亜への情報提供
契約締結後、損保ジャパン日本興亜は、国内外のグループ会社や提携先会社に、契約者情報の一部を提供する可能性があります。これは、より良い商品・サービスの案内や提供、およびリスク評価などに利用される可能性があり、保険サービスの向上に繋がる目的で情報提供が行われます。ただし、この情報提供において、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴などのセンシティブな個人情報(要配慮個人情報)は、法令等に従い厳格に管理され、利用目的が限定されます。 契約者は、この情報提供について、事前に十分に理解しておく必要があります。 プライバシー保護の観点から、どのような情報が提供されるのか、提供先はどこなのか、といった詳細な情報が契約者に開示されることが重要です。情報提供の範囲や方法、そしてデータセキュリティに関する具体的な対策が、契約者の信頼感を高める上で不可欠です。 損保ジャパン日本興亜は、これらの情報提供について、透明性を確保し、契約者の権利を保護する責任を負っています。
II.個人情報の取扱い
損保ジャパン日本興亜は、保険契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、契約履行、付帯サービス提供、自動車保険や各種サービスの案内、アンケート実施などに利用します。個人情報の取り扱いについては、法令を遵守し厳重に管理いたします。センシティブな個人情報は、法令に基づき適切に取り扱います。
1. 利用目的の明示
損保ジャパン日本興亜は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損保ジャパン日本興亜が取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施などに利用することを明示しています。これは、個人情報の利用目的を明確にすることで、透明性を高め、契約者の権利保護に繋がる重要な事項です。 具体的な利用目的として、保険金支払いの可否判断、契約内容に基づくサービス提供、新たな商品・サービスの案内などが挙げられています。これらの利用目的は、保険業務の円滑な遂行に必要不可欠なものであり、契約者もその妥当性を理解する必要があります。 また、アンケートの実施についても、サービス向上のための重要な情報収集手段として位置付けられています。 ただし、これらの利用目的は、あくまで契約に基づく範囲内で行われ、それ以外の目的には利用されないことが保障されています。個人情報保護法に基づく適切な取り扱いと、契約者への透明性の高い情報開示が求められます。
2. 情報の取得 利用 提供
損保ジャパン日本興亜は、上記の利用目的を達成するために、必要範囲内で個人情報の取得、利用、提供、登録を行います。これは、保険契約の締結や履行、付帯サービスの提供、さらにはリスク管理やサービス向上のための活動に不可欠な手続きです。 個人情報の取得は、契約者から直接の情報提供、あるいは関連会社からの情報提供など、様々な経路で行われる可能性があります。 利用にあたっては、常に目的を限定し、必要な範囲に限定することが重要です。 提供に関しても、法令に基づいた適切な手続きが行われ、第三者への不正な漏洩などが起こらないよう、厳重な管理体制が求められます。 これらの個人情報の取り扱いに関する手続きは、個人情報保護法などの関連法令を遵守して行われることが前提となります。 契約者には、これらの情報提供の範囲と方法について、明確に理解しておく必要があります。
3. センシティブ情報の取扱い
保健医療情報など、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴といったセンシティブな情報(要配慮個人情報)についても、本契約において取り扱う可能性があります。これらの情報は、法令に従い、厳格な管理体制の下で利用されます。 センシティブな情報は、特にプライバシー保護の観点から、その取り扱いに細心の注意を払う必要があります。 利用目的は、法令等に従い厳格に限定され、契約者の同意なしに、本来の利用目的以外には使用されないことが保障されます。 これらの情報の適切な管理と、不正アクセスや漏洩防止のためのセキュリティ対策は、損保ジャパン日本興亜にとって重要な責務です。 契約者も、自身のセンシティブな情報がどのように扱われるのかを理解し、必要に応じて適切な質問を行う権利を有しています。
III.補償範囲
補償対象者は、契約自動車の正規乗車装置内搭乗者です。契約自動車の運行による事故で、自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合、自動車保険の補償の対象となる場合があります。契約自動車の所有者も特定の条件下で補償対象となる可能性があります。
1. 契約自動車搭乗者
補償の対象となる主な者は、契約自動車の正規の乗車装置、またはその装置のある室内に搭乗中の方です。ただし、隔壁などで通行できないように仕切られた場所は除かれます。この規定は、保険の適用範囲を明確に示しており、契約自動車の利用状況と補償範囲を明確に結びつけることで、保険金支払いの判断基準を明確にしています。 乗車装置内という限定的な条件は、保険金不正請求の防止やリスク管理の観点から重要です。 契約者には、この補償範囲を理解し、保険契約の範囲内で自動車を使用することが求められます。 また、この規定は、保険契約締結前に、契約者自身で乗車可能な範囲を理解し、必要に応じて保険内容の確認を行うことを促すものと言えるでしょう。 保険会社は、この明確な規定に基づき、迅速かつ公正な保険金支払いを目指します。
2. 契約自動車運行による事故と自動車損害賠償保障法
契約自動車の運行に起因する事故によって身体に傷害を負った場合、その損害について自動車損害賠償保障法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限り、補償の対象となります。 これは、自動車損害賠償保障法による補償と重複して保険金が支払われることを防ぎ、保険金の不正利用を抑制するための重要な規定です。 自動車損害賠償保障法は、自動車の運行によって発生した事故における被害者への補償を目的とした法律であり、この法律に基づく補償が既に認められている場合は、本保険による二重の補償は行われません。 契約者には、この法律の仕組みと本保険との関係性を理解することが求められます。 この規定は、保険金の支払いにおける明確な基準を示すことで、契約者と保険会社双方にとって公平な保険契約の運営に貢献します。 契約締結前に、自動車損害賠償保障法の範囲と本保険の補償範囲の相互関係を理解しておくことが重要です。
3. 契約自動車所有者の補償
特定の条件下では、契約自動車の所有者も補償対象となる可能性があります。 ただし、この場合も、事故状況や損害賠償請求権の有無など、いくつかの条件が満たされる必要があります。 具体的には、無過失事故の特則などが適用されるケースがあり、事故の状況によって補償の可否が判断されます。 契約自動車の所有者に対する補償範囲は、契約内容や事故状況によって大きく異なるため、詳細な条件については、保険約款をよく確認する必要があります。 契約者には、保険契約締結前に、所有者に関する補償内容を十分に理解し、必要であれば保険会社に確認を行うことをお勧めします。 この規定は、契約自動車の所有者にも一定の保護を与えることで、より包括的な補償を提供しようとする保険会社の姿勢を示しています。
IV.個人賠償責任特約
個人賠償責任特約は、日常生活での事故(例:自転車事故)で他人にケガや損害を与えた場合に、法律上の損害賠償責任を補償するオプションです。損保ジャパン日本興亜の同意を得た示談費用なども補償対象です。日本国内で発生した事故には示談交渉サービスが付きます。
1. 補償対象となる事故と範囲
個人賠償責任特約は、日本国内・国外を問わず、記名被保険者、その配偶者、同居のご親族、別居の未婚のお子様が日常生活において起こした偶然な事故による他人のケガや財物損害を補償する特約です。自転車運転中の事故なども含まれます。この特約は、日常生活における不慮の事故によって生じる法律上の損害賠償責任をカバーすることで、契約者の経済的な負担を軽減することを目的としています。 具体的には、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊した場合に発生する損害賠償金が補償対象となります。 事故の種類は、日常生活で起こりうる様々な事故を想定しており、幅広い状況に対応できるよう設計されています。 ただし、故意による行為や業務上の過失による事故などは、補償の対象外となります。 契約者には、この特約の補償範囲を十分に理解し、必要に応じて保険会社に確認を行うことが求められます。
2. 示談費用等の補償
個人賠償責任特約では、損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された示談費用、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁費用なども補償対象となります。これは、事故発生後の対応において、契約者が弁護士などの専門家に依頼する場合の費用負担を軽減することを目的としています。 示談交渉は、事故発生後のトラブル解決に不可欠なプロセスであり、その費用負担を軽減することで、契約者の精神的な負担を軽減する効果も期待できます。 ただし、損保ジャパン日本興亜の同意が必要であるため、契約者は事前に保険会社に相談し、同意を得る必要があります。 この同意を得る手続きは、契約者にとってやや複雑な部分であり、保険会社による丁寧な説明が求められます。 また、示談交渉サービスは、日本国内で発生した事故に限定されるという点にも注意が必要です。
3. 付帯サービス
日本国内で発生した事故に限り、示談交渉サービスが付帯されます。このサービスは、事故発生後の手続きを円滑に進めるためのサポートであり、契約者にとって大きなメリットとなります。示談交渉は、法律的な知識や交渉スキルが必要な複雑な手続きとなる可能性があるため、専門家のサポートは契約者にとって大きな安心材料となります。 専門家によるサポートを受けることで、契約者は、より迅速かつ有利な解決を期待できます。 この示談交渉サービスは、個人賠償責任特約の付加価値を高め、契約者の安心感を向上させる重要な要素と言えるでしょう。 ただし、このサービスは日本国内の事故に限定されるため、海外での事故の場合は、契約者は自身で対応する必要があり、その点を理解しておくことが重要です。
V.割引制度
ASV割引:契約車両がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)搭載の自家用乗用車の場合、保険料が9%割引されます。安全運転割引:自家用乗用車(8車種)で6Sまたは7S等級、かつ「ポータブルスマイリングロード」アプリの運転診断を利用した場合は、運転履歴に基づき保険料が割引されます。自動車保険料を安くしたい方は、これらの割引制度をご利用ください。
1. ASV割引
契約車両がAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を搭載した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)の場合、保険料が割引されるASV割引制度があります。AEBとは、カメラやレーダーなどで前方の物体や車両を検知し、衝突の危険性があると判断した場合、ドライバーに警告し、必要に応じて自動的にブレーキを作動させる装置です。この装置の搭載は、事故発生率の低減に繋がるため、保険料の割引対象となっています。 割引率は9%と設定されており、安全運転を促進する効果が期待できます。 ただし、ファミリーバイク特約など、一部の特約には割引が適用されない場合があります。 契約者は、自身の車両がASV割引の対象となるかどうか、事前に確認する必要があります。 この割引制度は、安全運転技術の向上と保険料の低廉化を同時に実現するための、重要なインセンティブとして機能します。
2. 安全運転割引
契約車両が自家用8車種で、契約等級が6S等級または7S等級の場合、記名被保険者がスマートフォンアプリ「ポータブルスマイリングロード」の「運転診断」機能を利用し、運転診断を実施すると、その運転履歴に基づいた割引スコアに応じて保険料が割引されます。 この割引制度は、安全運転を促し、事故リスクを低減することを目的としています。 スマートフォンアプリの利用は、運転行動のデータ収集と分析を可能にし、客観的な評価に基づいた割引を実現しています。 割引スコアは、運転履歴に基づいて算出されるため、安全な運転を心がけるほど大きな割引が期待できます。 ただし、割引率は運転スコアによって変動するため、契約者は自身の運転状況と割引率の関係を理解しておく必要があります。 また、この割引制度は、特定の車種と等級に限定されている点に注意が必要です。
VI.安心更新サポート
個人契約の自家用車(8車種)、二輪車、原動機付自転車の場合、一部を除き安心更新サポート特約が付帯されます。連絡が取れない場合でも、通知期限までに更新拒否の申し出がない限り、前年と同等条件で自動更新されます。自動車保険の更新手続きをスムーズに行うための制度です。
1. 安心更新サポート特約の自動付帯
記名被保険者が個人で、契約自動車の用途車種が自家用8車種、二輪自動車、または原動機付自転車の場合、一部の契約を除き、安心更新サポート特約が自動的に付帯されます。この特約は、契約更新時の手続きを簡素化し、契約者の負担を軽減することを目的としています。 契約更新時における連絡がつかないといった事態が発生した場合でも、一定の条件下では自動的に更新される仕組みとなっています。これは、契約者の利便性を向上させ、契約継続をスムーズに行うための重要な機能です。 この自動更新の仕組みは、契約者にとって大きなメリットとなりますが、更新を希望しない場合は、通知期限までに必ず取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に連絡する必要があります。 契約者は、この特約の条件と手続きを事前に理解し、自身の状況に応じて適切な対応をとることが重要です。 この特約は、契約者の安心を第一に考え、保険契約の継続を円滑に進めるための配慮を示すものです。
2. 更新手続きと連絡義務
万が一、契約更新時に契約者と連絡が取れない場合、通知期限までに取扱代理店もしくは損保ジャパン日本興亜、または契約者から契約を更新しない旨の申し出がない限り、前年と同等条件で自動的に契約が更新されます。これは、契約者の不注意による契約切れを防ぎ、継続的な保険の保障を提供するための措置です。 しかしながら、契約更新を希望しない場合は、通知期限までに必ず取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に連絡する必要があります。この連絡義務は、契約者自身の責任において履行されるべき重要な事項です。 連絡が遅れた場合、意図せず契約が更新され、追加の保険料が発生する可能性があるため、注意が必要です。 契約者は、更新時期を事前に把握し、自身の希望を明確に伝えるため、期日までに必ず連絡を行うよう心がけるべきです。 この特約は、契約者と保険会社双方の責任と役割を明確化することで、契約の円滑な更新を支援するものです。
VII.契約変更 中断
契約条件の変更は、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店に事前に連絡が必要です。契約中断(廃車、譲渡、車検切れ等)の場合も、中断特則により中断前の等級を引き継げる場合があります。自動車保険の契約内容変更や中断に関する手続きは、代理店または損保ジャパン日本興亜にお問い合わせください。
1. 契約条件の変更手続き
契約内容の変更は、通知事項以外の場合、事前に損保ジャパン日本興亜または取扱代理店に連絡する必要があります。これは、契約内容の変更に伴い、保険料の追加や減額、あるいは補償範囲の変更などが発生する可能性があるため、事前に保険会社に届け出ることで、円滑な手続きと正確な保険料計算を可能にするための規定です。 契約条件の変更手続きは、契約者と保険会社双方にとって重要な手続きであり、事前に連絡することで、トラブルや誤解を未然に防ぐことができます。 変更手続き前、つまり追加保険料の支払い前などに事故が発生した場合、保険金が支払われない場合や、変更前の契約条件が適用される可能性があります。 契約者は、契約内容の変更を検討する際には、保険会社に確認を取り、変更手続きの詳細を十分に理解する必要があります。 この規定は、契約の透明性を高め、不測の事態を回避するための重要な手続きを定めています。
2. 契約中断と中断特則
契約自動車の廃車、譲渡、リース業者への返還、車検切れ、盗難、災害、記名被保険者の海外渡航などにより、一時的に契約を中断する場合は、中断後の新たな契約に対して、中断前の契約内容や事故件数などを考慮した等級や事故有係数適用期間を適用できる場合があります。これは、契約の中断によって保険等級が下がることを防ぎ、契約者の負担を軽減するための制度です。 契約中断を希望する場合は、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店に申し出が必要です。 中断後の新たな契約において、中断前の契約状況が考慮されるため、契約期間が途切れても、過去の運転状況が評価に反映されます。 ただし、契約の中断日(契約の解約日または満期日)の翌日から起算して13ヶ月以内に連絡がない場合は、中断前の契約状況は考慮されなくなる可能性があります。 契約者は、契約中断を検討する際には、中断特則の内容をよく理解し、必要な手続きを適切な時期に行う必要があります。
VIII.契約自動車の譲渡
契約期間中の契約自動車譲渡は、保険契約の権利義務は譲渡人に移転しません。権利義務を譲渡する場合は、損保ジャパン日本興亜または取扱代理店に事前に連絡し手続きが必要です。手続き前の事故は補償対象外となる可能性があります。
1. 契約自動車譲渡時の権利義務
契約期間中に契約自動車を譲渡した場合、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利と義務は、譲受人へは移転しません。これは、保険契約が契約自動車の所有者ではなく、契約者との間に成立しているためです。 保険契約は、契約者と保険会社との間の合意に基づいて成立しており、契約自動車の所有権の移転は、保険契約自体に影響を与えません。 よって、契約自動車の譲渡は、保険契約の解除を意味するものではなく、契約者は引き続き保険契約上の義務を負うことになります。 譲渡によって生じた事故などに対しては、契約者は保険会社に対して責任を負うことになります。 この規定は、保険契約の法的根拠と責任の所在を明確にすることで、契約者と保険会社間の紛争を予防する役割を果たします。
2. 権利義務の譲渡手続き
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利と義務を譲渡する場合は、事前に取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に連絡し、手続きを行う必要があります。これは、保険契約の譲渡手続きを適切に行うことで、新たな所有者への保険適用や保険金請求を円滑に進めるための規定です。 手続きは、保険会社への適切な通知と、必要書類の提出などから構成されます。 手続きが行われる前に発生した損害や傷害については、保険金が支払われない可能性があります。 契約者は、自動車を譲渡する際には、この手続きを確実に完了させることで、自身と譲受人の双方を保護する必要があります。 この規定は、保険契約の譲渡手続きを明確化することで、契約者と保険会社双方にとって公平かつ安全な手続きを保証します。
IX.複数車両所有者への対応
複数車両所有者の場合、車両入替手続きにより等級を引き継げる場合があります。廃車等の場合は中断証明書を発行できます。自動車保険の複数車両に関する手続きは、代理店または損保ジャパン日本興亜にお問い合わせください。
1. 車両入替手続きによる等級 事故係数適用期間の引継ぎ
複数の自動車を所有するお客様が、契約自動車を廃車、譲渡、またはリース業者へ返還した場合、所有する他の自動車との車両入替手続きを行うことで、等級および事故有係数適用期間を引き継げる可能性があります。これは、複数台の車を所有する顧客にとって、保険等級を維持し、保険料の負担を軽減するための重要な制度です。 この手続きによって、契約自動車の変更があっても、過去の運転実績を反映した保険等級を維持できるため、保険料の増加を抑えることが期待できます。 手続きの詳細については、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に問い合わせる必要があります。 車両入替手続きの可否は、契約条件や事故状況など、いくつかの要素によって影響を受けるため、事前に保険会社に確認することが重要です。 この制度は、複数車両所有者にとって、保険契約の継続性を確保し、経済的な負担を軽減するための配慮を示しています。
2. 中断証明書の発行
契約自動車を廃車、譲渡、またはリース業者へ返還した場合、所有する他の自動車の契約について「中断証明書」を発行できます。中断証明書は、保険契約を一時的に中断した場合でも、中断前の契約状況を証明する重要な書類です。 この証明書は、将来、新たな自動車への保険契約を締結する際に、中断前の等級や事故係数適用期間などを引き継ぐための重要な役割を果たします。 中断証明書は、損保ジャパン日本興亜以外の保険会社でも有効な場合があり、保険会社の変更を検討している顧客にとっても有益な制度です。 中断証明書に関する詳細な情報や手続きについては、取扱代理店または損保ジャパン日本興亜に問い合わせることで確認できます。 この制度は、契約の中断によって生じる不利益を最小限に抑え、契約者の利便性を向上させるためのものです。
X.損害保険契約者保護機構
損保ジャパン日本興亜が経営破綻した場合、保険金支払いが一定期間凍結または削減される可能性があります。損害保険契約者保護機構による保護制度についてご確認ください。
1. 保険会社の経営破綻と保険契約者保護
引受保険会社が経営破綻した場合、または事業継続が困難となり、法令に基づき契約条件の変更が行われた場合は、契約時にお約束した保険金や解約返戻金のお支払いが、一定期間凍結されたり、金額が削減される可能性があります。これは、保険会社が倒産した場合でも、契約者が全く保護されない事態を防ぐための制度です。 損害保険契約者保護機構は、保険会社の経営破綻によって契約者に生じる不利益を軽減するために設立された機関であり、この機構による保護制度が適用される可能性があります。 保険金や解約返戻金のお支払いが遅延したり、減額される可能性があるため、契約者は、このリスクを事前に理解しておく必要があります。 この機構による保護の内容や手続きは、複雑なため、保険会社からの詳細な説明と、必要であれば専門家への相談が必要となる場合があります。 契約者は、保険会社を選ぶ際に、この機構による保護の範囲や手続きについても確認することが重要です。
文書参照
- 損保ジャパン日本興亜公式ウェブサイト (損保ジャパン日本興亜)
- 損保ジャパン日本興亜問い合わせ検索 (損保ジャパン日本興亜)
- 損保ジャパン日本興亜マイページ (損保ジャパン日本興亜)
