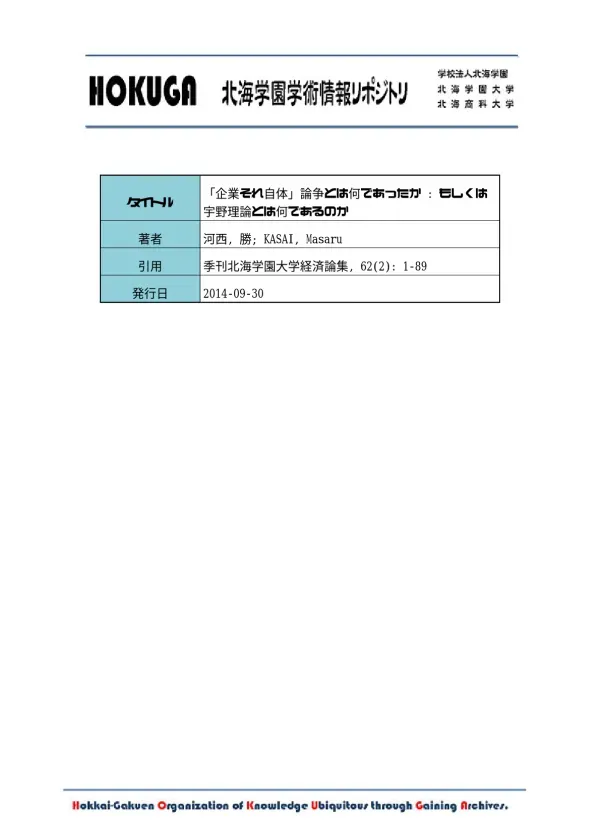
企業それ自体論争:宇野理論と現代企業
文書情報
| 著者 | 河西 勝 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.61 MB |
概要
I.ラーテナウの構想とワイマール共和国の経済状況
ワイマール共和国期におけるラーテナウの「株主なき株式会社」構想は、第一次世界大戦後の社会化論争や1929年の世界恐慌といった激動の時代背景において、強い反論を招きました。当時の経済的・政治的不安定さが、ラーテナウの改革案への期待と同時に恐怖を生み出したのです。この時代、所有と経営の分離が急速に進み、レッセフェール的な世界市場体制は崩壊しました。ベルサイユ条約やワシントン条約による新たな国際秩序は、脱資本主義的な方向への移行を示唆していました。
1. ラーテナウの株主なき株式会社構想とその批判
この節では、Walter Rathenauの提唱した「株主なき株式会社」構想、あるいは株式会社の生産共同体への転換構想が詳細に分析されています。この構想は、株主に何ら財貨の見返りを期待させない点が特徴です。しかし、ワイマール共和国の政治・経済的激動、特に1929年末の世界恐慌の勃発と同時に、ラーテナウの主張に対して激しい反論が巻き起こりました。戦後の社会化論争、社会化委員会の設置、1918年12月のレーテ議会での社会化問題論争など、当時の社会情勢がラーテナウの構想に対する反応に大きく影響を与えたことが指摘されています。人々は、構造改革と経済不況という厳しい状況下で、ラーテナウの構想に期待する一方で、その急進的な内容に恐怖を感じていたのです。この時代の混乱と不安定さが、ラーテナウの構想への複雑な反応を生み出した背景として強調されています。
2. 第一次世界大戦後の経済体制変化と所有 経営分離
第一次世界大戦を境に、ドイツの企業経営は劇的な変化を遂げました。戦前は、自由主義国家における平等な契約関係に基づく資本所有と生産手段所有が支配的でしたが、戦後は契約関係の政治化が進み、取締役経営者による資本・生産手段・労働者への管理支配(分離法人統治、分離法人金融)へと移行しました。この変化は、レッセフェール世界市場(パックス・ブリタニカ)の崩壊と、1919年のベルサイユ条約および1922年のワシントン条約による新たな国際政治・経済・安全保障体制の成立に対応したものでした。これらの転換は、資本主義的内的発展では説明できない、世界史的な脱資本主義的状況への移行を示唆しています。特に、原料購入や製品販売において国家権力との政治的・軍事的な協働が不可避となった点が指摘されています。一方、ハウスマンやネッターといった学者は、企業を資本主義的企業の一つのバリエーションと見なし、企業自治を強調しました。彼らは、国家の役割を従来の夜警国家以上に拡大することを想定しておらず、ナチス政権の成立を予期していませんでした。
3. ワイマール共和国の崩壊とナチス政権下の企業
ワイマール共和国の成立と存続は必ずしも保証されておらず、1920年代の相対的安定期を経て、1930年代にはベルサイユ条約体制・ワシントン条約体制と共に崩壊しました。ドイツの所有と経営の分離企業は、1933年以降のナチス政権の広域経済政策への協調によって生き残りを図りました。ナチズムは、ラーテナウの「企業それ自体」という概念を表面上は否定しながらも、国家権力の政治・経済融合の基礎としてほぼ全面的に取り込みました。大戦間の世界政治・経済体制とその崩壊、そして所有と経営の分離企業との間の協調と対立は、第二次世界大戦後のブレトンウッズ体制と新たなドイツ共同決定制度によって克服されました。この節では、ワイマール共和国の政治・経済的不安定さが、企業経営に大きな影響を与え、ナチス政権の台頭によってさらに複雑な状況が生まれたことが示されています。
II.株式会社の進化と所有 経営分離
個人企業から株式会社への移行過程において、所有と経営の分離がどのように発生したかが分析されています。初期段階では、家族や友人からの資金調達に依存していましたが、株式市場の発展に伴い、外部資本調達が可能となり、戦略経営者と機能経営者の役割分担が明確になりました。最終的には、多くの普通株が分散所有されることで、所有と経営の完全分離が達成されます。この過程は、純粋資本主義社会における資本と支配の同一性の崩壊を示しています。
1. 株式会社の三段階発展モデルと所有 経営分離のプロセス
この節では、株式会社の進化と所有・経営分離のプロセスを三段階で説明するモデルが提示されています。第一段階は、固定資本形成のために家族や近隣からの長期的な資金調達に依存する個人企業の段階です。第二段階では、個人企業が株式会社へと形態転換し、株式市場を通じて外部資本を調達するようになります。この段階で、戦略経営者と機能経営者の役割分担が明確になり、株式取引所の役割が強調されることで所有と経営の分離が始まります。第三段階では、所有者と戦略経営者の分離がさらに進展し、戦略的、機能的、作業的経営が専門的な経営者によって完全に担われるようになります。同時に、会社の普通株はビジネス運営に関与しない投資家によって広く分散所有されるようになり、所有と経営の完全分離が達成されるという流れが示されています。このモデルは、所有と経営の分離が段階的に進行する過程を明確に示しています。
2. 所有と経営の分離における戦略経営者と機能経営者の役割
株式会社の形態転換において、戦略経営者と機能経営者の役割分担が重要な役割を果たすことが強調されています。戦略経営者は株式市場を通じて外部資本を調達し、企業全体の戦略を決定する役割を担います。一方、機能経営者は専門的な知識・スキルを活かして、個々の部門の経営を担います。この役割分担は、企業規模の拡大と経営の複雑化に伴い、ますます重要性を増していきます。株式市場の発展は、外部資本調達を容易にし、戦略経営者の役割を強化する一方で、所有と経営の分離を促進する重要な要因となります。株式取引所などの外部機関の役割も強調され、所有者と経営者の間の関係が変化していく過程が示されています。この節では、所有と経営の分離が、企業の組織構造と経営体制の変化と密接に関連していることが示唆されています。
3. 完全分離後の株式会社における所有者と経営者の関係
所有と経営の完全分離が達成された後の株式会社の姿が描かれています。この段階では、戦略的、機能的、作業的経営のすべてが専門的な経営者によって担われ、株主はビジネス運営に何らの役割も果たしません。大量の普通株が広く分散所有されている状態は、所有者と経営者の間の関係が完全に分離されていることを示しています。この状態は、従来の資本主義的企業における「資本と支配の同一性」が崩壊した状態を表しており、この変化が現代株式会社の重要な特徴の一つであると捉えられています。この節では、所有と経営の分離がもたらす、企業の構造とガバナンスにおける変化が分析されています。 John (1995)の研究が、この三段階モデルの根拠として引用されています。
III.ドイツにおける株式会社とユニバーサルバンキング
ドイツにおける株式会社の発展は、イギリスと対照的でした。イギリスでは比較的遅れた大規模法人化と、国内産業への投資不足が課題でした。一方、ドイツでは、ユニバーサルバンキングとリレーションバンキングが、重工業企業の成長を強力に支えました。特に、ドイツの大銀行(例:ドイチェバンク)は、株式発行の引受け、顧客企業への融資、株主総会における投票権行使など、多様な金融サービスを提供し、企業の成長と固定資本形成を促進しました。ラントシャフト的信用制度も、農業近代化に貢献しました。
1. ドイツとイギリスの株式会社発展における相違点
この節では、ドイツとイギリスにおける株式会社の発展過程における顕著な違いが論じられています。特に、ドイツの産業株式会社の急速な成長と、イギリスにおけるその相対的な遅れが比較検討されています。イギリスではイノベーションが小さく、大規模法人化も遅れており、資本需要の急激な増加は見られなかったとされています。さらに、イギリスの銀行は海外投資に偏っており、国内産業への資金供給が不足していたため、技術革新を促進するような金融活動は限定的でした。これに対して、ドイツではユニバーサルバンキングとリレーションバンキングが、企業の成長を強力に推進したとされています。この比較分析は、イギリスの金融システムとドイツの金融システムの優劣を暗に示唆しており、ドイツのユニバーサルバンキングモデルが、その経済発展に大きく貢献したという主張が読み取れます。ガーシェンクロン(1962、久保訳2000)などの従来の見解も参照しながら、両国の株式会社発展の不均等性を詳細に分析しています。
2. ドイツにおけるユニバーサルバンキングとリレーションバンキングの役割
ドイツにおける株式会社の発展において、ユニバーサルバンキングとリレーションバンキングが重要な役割を果たしたことが強調されています。ユニバーサルバンキングとは、商業銀行業務と投資銀行業務を統合した形態であり、ドイツの大銀行は、このモデルを通じて、重工業企業への資金供給、株式発行の引受け、株主総会における投票権行使など、幅広い金融サービスを提供していました。リレーションバンキングは、銀行と企業との緊密な関係に基づくもので、銀行は顧客企業の経営に深く関与し、その成長を支援しました。このユニバーサル・リレイションバンキングシステムは、水平的および垂直的統合によって巨大化したドイツの産業株式会社が、大量の原材料輸入と製品輸出を実現するための資金調達を可能にしました。さらに、ドイツ東北部ではラントシャフト的信用制度(地主金融組合)が、工業と同様のユニバーサル・リレイションバンキングを展開し、農業近代化と糖業における株式会社企業の発展を促進しました。この節では、ドイツ特有の金融システムが、その経済発展、特に大規模な株式会社の台頭を支えたメカニズムが解説されています。
3. イギリスの株式会社と金融システム
イギリスの株式会社発展の状況は、ドイツとは対照的でした。多くのイギリスの工業株式会社は、パートナーシップを大規模化したに過ぎず、ドイツのような急激な成長は遂げませんでした。穀物生産部門の自給率が8%まで低下したにもかかわらず、不動産抵当制度はドイツほど発展しませんでした。しかし、イギリスでも商業、銀行業、鉄道を含む様々な企業において、国際競争力を維持し成長するための固定資本形成が、地方やロンドンの証券市場を通じた莫大な資金調達によって行われていたことも事実です。これらの企業は、19世紀中葉以降発展した鉄道会社ほどの大規模ではありませんでしたが、世界水準から見て相当規模の株式会社として発展しました。この節では、ドイツとイギリスの金融システムと株式会社発展の相違点を比較することで、ドイツにおけるユニバーサルバンキングの独自性をより明確に示す記述となっています。Landes(1965)の研究が参照されています。
IV.戦時課税と株式会社の対応
第一次世界大戦中の高率な累進付加税は、企業の内部留保と自己金融を促進しました。高額所得者は、税負担を軽減するために、法人証券への投資を減らす傾向にありました。このことは、資本と支配の分離を加速させる要因の一つとなりました。また、戦時課税における法人税と個人所得税の分離も重要な変化でした。
1. 第一次世界大戦と累進付加税の導入
第一次世界大戦下のドイツでは、戦費調達のため税制改革が行われ、累進付加税が導入されました。法人の正常税率は個人の4%から6%に引き上げられ、これは事業体レベルでは存在しない累進付加税を埋め合わせるための措置でした。 これにより、法人と個人の所得税が初めて公式に分離されました。しかし、戦費の増加は続き、1918年には歳入と累進付加税の両方をめぐる懸念が深まりました。さらに法人に対してのみ戦時超過利益税率の引き上げが適用され、個人所得に対する累進付加税の最高税率も1917年の50%から1918年には65%へと引き上げられました。結果として、法人税率と個人の最高付加税率の差は、1913年のわずか4%から1918年には55%へと大幅に拡大しました。この急激な税制変更が、企業経営、特に株式会社にどのような影響を与えたのかが、この節の主要な分析テーマとなっています。Bank (2010)の研究が、この税制変化に関するデータを提供しています。
2. 累進付加税の高税率と企業の自己金融化
高率な累進付加税の影響として、富裕層が法人証券への投資意欲を失った点が指摘されています。1919年までに、10万ドルの課税所得がある者は6万1千ドルの納税を要求され、3万5千ドルの所得者でも6千ドル以上の納税を強いられました。納税後の富裕層は、以前と同様の額の所得を保有しておらず、生活費を減らす理由もないため、新たな投資への支出を大幅に減らすことになります。この状況下で、企業は高税率を回避するために、利益の内部留保と自己金融を強化するインセンティブを持つようになりました。つまり、高税率は、企業の自己資本比率を高め、外部資金への依存度を下げる方向に働いたのです。この自己金融の増加は、レッセフェール金融システムの終焉と対応する現象として捉えられています。Prion (1934)の研究が、この自己金融化の傾向を裏付けています。
3. 戦時課税と所得再分配政策
この節では、戦時課税と所得再分配政策の関係性が分析されています。一次大戦以降、所得再分配を目標とする財政政策が、累進所得税率の大幅な引き上げを伴いました。その結果、企業は内部留保と自己金融を肥大化させる傾向が強まりました。また、20世紀後半の資本市場のグローバル化においては、企業の国際競争力強化のため、所得税から消費税への転換が検討される可能性が示唆されています。この課税システムの変更が、財政や国政にどのような影響を与えるか、また法人税制にどのような問題を生じるのかが、国際比較の観点から議論されています。この節では、異なる時代・異なる国の課税システムの違いと、それらが企業経営に与える影響について考察が行われています。Daunton (2002)の研究は、ドイツとイギリスの戦前・戦後の税制の違いを比較する際に参照されています。
V. 企業それ自体 の学説と株式会社法の変遷
ワイマール共和国期においては、**「企業それ自体」**という概念が台頭しました。これは、企業を単なる個人主義的利害追求の場ではなく、独自の法的性格を持つ存在と捉えるものです。この学説は、ワイマール憲法の「所有は義務を伴う」という理念と関連しており、株式会社法の改革要求に影響を与えました。1897年商法典は、急速な経済変化に対応できず、1930年代には包括的な改革が求められました。ナチス政権下では、「企業それ自体」の学説は、国家社会主義的な方向へ利用されました。
1. 企業それ自体 の学説の台頭と背景
ワイマール共和国期において、「企業それ自体 (Unternehmen an sich)」の学説が台頭しました。この学説は、企業を単なる株主個人の利害追求のための組織ではなく、独自の法的性格と目的を持つ、特別な存在と捉えるものです。この考え方の背景には、戦時中にドイツで発展した社会主義的アイデアや、1918年8月11日のワイマール共和国憲法の精神が影響を与えています。憲法における「所有は義務を生む」という原則は、個人の権利と共同体への義務の結びつきを強調し、戦後の法廷や法律家の思考に大きな影響を与えました。この「企業それ自体」の学説は、株主の個人主義的コントロールに対する制限を目的としており、企業の社会的責任を重視する考え方を反映しています。この節では、この学説が台頭した歴史的・社会的な背景と、その基本的な考え方について説明されています。
2. 1897年商法典と会社法改正の必要性
1897年商法典の一部をなすドイツ会社法は、1884年の議会制定法の修正に基づいて制定されましたが、後の時代の経済・法律現象を全く予想していませんでした。コンツェルン、トラスト、カルテル、子会社、持ち株会社といった現代的企業形態への対応、株券と債券の中間形態のような新たな金融手法、大戦後の税制や労働法の変化、会計報告書の正式な監査など、当時の会社法には考慮されていなかった重要な事項が数多く存在しました。ワイマール共和国時代、ドイツは戦争、インフレ、復興、世界恐慌と相次ぐ困難に見舞われ、これらが会社法の改正を必要とする事態をもたらしました。特に1930年代には、経済発展に対応した会社法の抜本的な改革が強く求められるようになったのです。Riecher (1996)の研究が、ワイマール共和国時代の会社法改正の動きについて言及しています。
3. 会社法改正の試みと 企業それ自体 学説の影響
会社法の包括的な改革要求は、1926年のドイツ法律家協会第34回大会で既に提起され、1930年には法務省によって会社法草案が作成されましたが、議会上程には至りませんでした。1931年の大審院判決は、当時の経済恐慌の中で極めて重要な問題を処理し、その内容は後に1937年の新会社法に編入されました。これらの法改正の試みは、主に三つの課題に焦点を当てていました。一つは、制定法に未対応の事態への対策、二つ目は違法・適法のグレーゾーンにある取引・手法の規制、三つ目は、ナチスの政権掌握後、国家社会主義原則との整合性を図ることでした。 「企業それ自体」の学説は、株主の個人主義的コントロールを制限し、企業の社会的責任を強調するものであり、ワイマール共和国時代の会社法改正に大きな影響を与えました。Mann (1937)の研究は、この時代の会社法改正の過程と「企業それ自体」学説の影響について詳しく分析しています。特に、多数派株主の権利行使は企業の利益と一致しなければならないという考え方や、企業それ自体の利益を優先する考え方が強調されています。
VI.ケインズの視点と現代株式会社
ケインズは、ベルサイユ条約を批判し、大企業の自己社会化傾向、つまり所有と経営の分離を論じました。彼の考えは、当時の反資本主義的な世相を反映していました。ハウスマンやネッターは、株式会社を資本主義的経済発展におけるバリエーションと捉え、その本質的な資本主義的原理を軽視する傾向がありました。現代株式会社は、公共機関的性格を帯び、資本と支配の分離という特徴を持つと分析されています。
1. ケインズの思想とワイマール共和国の状況
この節では、John Maynard Keynesの思想とワイマール共和国の社会経済状況との関連性が論じられています。ケインズは、ベルサイユ条約を厳しく批判し、特にドイツにおいて高い知名度を誇っていました。彼の1926年のベルリン大学での講義「レッセフェールの終わり―私的経済と公共経済を結びつける理念―」は、大企業の自己社会化傾向、特に所有と経営の分離について論じており、当時の反資本主義的な世相を反映していました。ケインズは、ワイマール共和国における株式法の議論の文脈において、広範な支持を獲得しました。これは、彼の主張が、時代の反資本主義的な感情を的確に捉えていたためと考えられます。Riechers (1996)の研究は、ケインズの思想がワイマール共和国の社会状況にどのように受け止められたかを分析する上で参照されています。
2. ケインズの 平和の経済的帰結 における戦前ヨーロッパの評価
ケインズは1919年の著書『平和の経済的帰結』において、第一次世界大戦前のヨーロッパ経済を高く評価しています。彼は、戦前ヨーロッパにおける固定資本の蓄積を、富の平等な分配が実現していた社会ではありえなかったものとして捉え、資本家階級が蓄積に貢献したことを肯定的に評価しています。しかし、同時に、戦前経済の不安定要因を指摘し、それらが第一次世界大戦後の平和条約の性質とその帰結を正しく評価するために考慮されなければならないと主張しています。この節では、ケインズが戦前ヨーロッパの経済的繁栄と不安定性の両面を認識していたことが示されています。彼の分析は、現代の株式会社のあり方を考える上で重要な視点を与えています。ケインズは、戦前ヨーロッパの蓄積習慣が、ヨーロッパの均衡を維持する上で不可欠な条件であったと述べています。
3. ハウスマンとネッターの視点 現代株式会社の解釈
この節では、HausmannとNetterの視点から現代株式会社がどのように解釈されているかが論じられています。Hausmannは、株式会社形態を、資本と労働の闘争といった特殊事情を度外視した、現代企業における一つの形態と位置づけています。彼は、現代株式会社の特性を論じる際には、その適用における影響力や様々な機構の機能を正当に評価することが重要だと主張しています。Netterは、株式会社を資本主義的経済発展におけるバリエーションと捉え、その本質的な資本主義的原理を軽視する傾向がありました。両者の見解は、ラーテナウの「企業それ自体」論に対して、その社会主義的側面を弱める意図的な歪曲であると批判的に評価されています。この節では、HausmannとNetterの解釈が、三段階論の欠如によって、資本主義的株式会社の延命のためのバリエーション論に過ぎないことが指摘されています。彼らが経済学原理、特に宇野理論に基づく段階論を理解していなかったことが、その誤った解釈の根拠として示されています。
