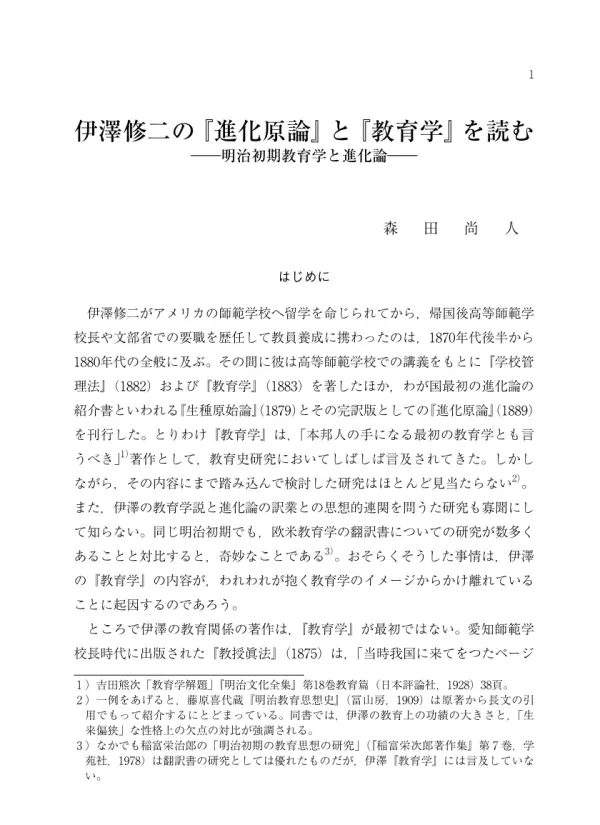
伊澤修二の教育学と進化論:明治期教育史研究
文書情報
| 著者 | 森田尚人 |
| 学校 | 小西中和教授退職記念論文集 |
| 専攻 | 教育史、思想史 |
| 出版年 | 平成(年) |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 621.83 KB |
概要
I.伊澤修二の教育学と進化論 アメリカ留学の影響
本稿は、明治初期の教育者である【伊澤修二】の教育思想と進化論に関する業績を分析する。特に、彼がアメリカ合衆国【ブリッジウォーター師範学校】に留学した経験が、彼の著作である『教育学』と『進化原論』にどう影響を与えたかを考察する。彼の『教育学』は、当時としては珍しい【本邦人の手になる最初の教育学】と評され、教育史において重要な位置を占める。しかしながら、その内容に関する詳細な研究は少ない。また、伊澤の【進化論】翻訳とその教育学説との思想的連関についても、十分に解明されていない。この空白を埋めるべく、ブリッジウォーター師範学校での講義ノートや、同校校長である【ボイデン】の教育理念、そして伊澤が深く関わった【学制】制定の背景などを検討する。
1. 伊澤修二の教育活動と主要著作
伊澤修二は明治時代後半から、アメリカ留学を経て高等師範学校長や文部省要職を歴任し、教員養成に尽力しました。この間に『学校管理法』と『教育学』を著し、特に『教育学』は「本邦人の手になる最初の教育学」と評され、教育史研究においてしばしば言及されています。しかしながら、その内容に関する詳細な分析は不足しており、その教育学説と進化論翻訳との思想的関連についても研究が進んでいません。 明治初期の欧米教育学翻訳に関する研究が盛んなことを考えると、この状況は特筆すべき点です。 伊澤の教育関連著作として、『教育学』以外にも愛知師範学校長時代に執筆した『教授眞法』が存在します。これは単なる翻訳ではなく、伊澤自身の意見を織り込んだ独自の著作であることが、橋本美保氏による詳細な分析によって明らかになっています。 本稿では、これらの著作を分析し、伊澤の教育思想と進化論との関係を明らかにすることを目指します。
2. 教育学 の内容と背景 ボイデンの講義とホプキンスの影響
伊澤修二の『教育学』は、ブリッジウォーター師範学校長ボイデンの心理学講義を基に執筆されたと推測されます。幸いにも、伊澤がボイデンの講義を筆写したノートが残されており、それが『教育学』の構成に大きく影響を与えていることがわかります。 ボイデン講義は、ホプキンスの『人間研究概説』に大きく依存しており、ホプキンスはスコットランド常識哲学派に属していました。 つまり、『教育学』は、スコットランド常識哲学派の精神哲学の系譜に位置づけられる心理学を基盤としています。 しかし、伊澤が学んだこの心理学は、後の実験心理学の発展によって忘れ去られることになります。 この点に着目し、スコットランド学派の精神哲学とダーウィン進化論が伊澤によってどのように理解され、統合されたのかを解明することが本稿の重要な課題です。 既存研究では『教育学』の内容にまで踏み込んだ分析が不足しているため、本稿での詳細な検討が必要不可欠です。
3. 進化論翻訳と伊澤の科学観 生種原始論 と 進化原論
伊澤修二は『生種原始論』の翻訳を行い、後にそれを元に『進化原論』を刊行しました。彼はこの翻訳を「我国に進化論を輸入してこれを国民の知識とした最初の本」と自負しています。 当時、ダーウィン進化論は日本においてまだ広く知られておらず、伊澤の翻訳は日本の進化論受容において重要な役割を果たしました。 『進化原論』の翻訳作業は比較的早く完了していたと推測されますが、何らかの事情で出版が遅れた可能性があります。 伊澤が地質学に強い関心を持っていたことは、彼の『進化原論』翻訳においても見て取れますが、原著で重要な部分を訳出していない点など、不可解な点も残されています。 本稿では、これらの点を踏まえつつ、伊澤の科学観、特に進化論への理解と、彼の教育思想との関連性を明らかにします。
II.学制と近代教育 欧米の影響と日本独自の展開
明治政府による【学制】制定は、欧米諸国の教育制度を参考にしながら、日本の社会状況に合わせた独自の展開を見せた。特に、【ジェファーソン】の教育理念である機会均等と、【スペンサー】の社会進化論が、学制の思想的基盤に影響を与えたと考えられる。また、文部省要職にあった【田中不二麻呂】や、学監として招かれたアメリカ人【マレー】、そして自由民権運動をリードした【福澤諭吉】といったキーパーソンが、日本の近代教育システムの構築に重要な役割を果たした。彼らの思想や政策が、国民皆学の理念や、中央集権的な教育行政の確立にどう繋がったのかを分析する。
1. 学制の理念と欧米諸国の教育制度
明治5年公布の学制は、欧米の教育制度を参考にしながら、日本の近代化を目的としたものでした。文部省は、全国を大学区、中学区、小学区に分割する学区制を採用し、国民皆学を目指しました。この学区制は、フランスの制度を参考にしていますが、国民全てに同一の学校組織を提供するという単線型制度は、アメリカの学校制度の影響も受けている可能性が示唆されています。 学制の序文である「被仰出書」には、「自今以後一般の人民必す邑に不學の戸なく家に不學の人なからしめん事を期す」という、四民平等と国民皆学を謳う理念が明示されています。この機会均等の理念は、ジェファーソンがヴァージニア州議会に提案した「知識の一般的普及に関する法案」と類似しており、文部省が小学校設置に注力した点からも、ジェファーソンの理念との親和性が見て取れます。 しかし、学制制定過程における草案の多くは国家の富強を目的とする一方、「被仰出書」は個人の立場からの論述が目立つことが指摘されています。
2. 学制における機会均等と個人の立身出世
学制は、機会均等を謳う一方で、立身出世主義的な側面も持ち合わせていました。為政者にとって、立身出世主義は、身分や階層に関係なく国民の中から優秀な人材を選抜するメカニズムでした。ジェファーソンも、「もっとも才能ある者をゴミ溜めのなかからくまなく捜し出して、公費によってグラマースクールの教育を受けさせる」と述べており、この点は学制の理念と合致します。 「被仰出書」が個人の教育の有用性を強調しているのは、この立身出世主義と機会均等という二つの側面を結びつけるためだと考えられます。 福澤諭吉は、『学問のすゝめ』において「天ハ人ノ上ニ人ヲ造ラズ」という自然権思想と功利主義倫理を統合しており、この思想は「被仰出書」の精神と深く関わっています。福澤はスペンサーの思想にも影響を受けており、明治5年の教育思想は、スペンサーよりも福澤の思想の影響を強く受けていると指摘されています。 学制、自由教育令、改正教育令といった一連の教育改革を理解するには、これらの思想的背景を考慮する必要があります。
3. 田中不二麻呂とマレー アメリカの影響と中央集権化
文部省要職を歴任した田中不二麻呂は、学制制定に大きな役割を果たしました。彼はアメリカ合衆国の公教育制度に強い関心を抱いており、岩倉使節団への参加を通してその認識を深めました。 田中は、アメリカ人マレーを文部省の学監として招聘し、マレーは日本の教育行政に大きな影響を与えました。 マレーは、中央集権的な教育行政の必要性を主張し、「教育に関することは、之ヲ命令スル等ノ権ハ挙テ文部省ニ付セザルヲ得ズ」と述べています。これは、アメリカにおける義務教育制度の導入経験を基にした主張でした。 マレーを単なる文化相対主義者と見る従来の解釈に対しては批判的な見解が存在し、マレーは中央集権的教育行政を日本に導入しようとしていたと指摘されています。 欧米における強制就学法の動きは、自由放任主義の時代から始まっていたことを考えると、田中やマレーの積極的な国家論は、時代背景を考慮する必要があります。
III.ブリッジウォーター師範学校での学び 教育実践と心理学
伊澤修二の【ブリッジウォーター師範学校】における留学生活は、彼の教育思想形成に大きな影響を与えた。同校では、自然科学、特に地質学が重視されており、これは後に彼が【進化論】の翻訳に着手する動機となったと考えられる。また、同校での心理学教育は、【ホプキンス】の教科書『人間研究概説』を基盤としており、これは【スコットランド常識哲学派】の伝統に基づいたものであった。伊澤の『教育学』は、ボイデンの講義内容、特にホプキンスの心理学をまとめたものであると推測される。そのため、伊澤の教育学は、実験心理学ではなく、当時のアメリカにおける精神哲学の流れを反映している。
1. ブリッジウォーター師範学校での留学生活と教育内容
伊澤修二は、文部省の派遣によりマサチューセッツ州立ブリッジウォーター師範学校に留学しました。 留学期間中は、18歳から24歳代の男子学生、16歳から20歳代の女子学生と共に、週6日、1日数時間の授業を受けました。 残された講義ノートから、伊澤の勉学への熱意がうかがえます。 音楽以外の科目は比較的容易に習得し、特に科学の才能は高く評価されたと伝えられています。 しかし、当時のカリキュラムには宗教や倫理学が含まれておらず、これはボイデン校長を始めとする教育関係者が、制度的な整備だけでは教職精神の向上に繋がらないと考えていたためです。 学校長の人格が生徒の模範となるという考え方が重視されており、制度化による弊害を危惧していた様子が伺えます。
2. ブリッジウォーター師範学校の教育理念と特徴
ブリッジウォーター師範学校は、創設当初から自然科学系科目を重視していました。 コナント校長時代にはこの傾向がさらに強まり、マサチューセッツ州南西部の繊維・製靴産業の発展状況を反映した教育が行われていたと推測されます。 アメリカ教員養成史において「ブリッジウォーターの伝統」と呼ばれる特徴として、小学校教員養成課程と中等学校教員や教育専門家の養成課程を併設していた点が挙げられます。 これは、師範学校の福音主義的起源とアカデミズムの伝統を統合しようとするものであり、単一課程制のオスウェーゴー師範学校とは対照的です。 ボイデン校長在任中には、高等課程が導入され、修業年限も延長されました。 ボイデンは、高等課程の導入が生徒の士気向上や学校水準の向上に繋がるという考えを持っていました。
3. 心理学教育 スコットランド常識哲学派とホプキンスの影響
ブリッジウォーター師範学校における心理学教育は、スコットランド常識哲学派の伝統に基づいていました。 ボイデン校長は、ホプキンスの『人間研究概説』を教科書として使用していたと推測され、伊澤の『教育学』は、この講義内容、特に心理学の部分をまとめたものだと考えられます。 ホプキンスは、心理学を道徳哲学と論理学の基礎と位置づける精神哲学の伝統に、生理学研究に基づいた有機体の概念を結びつけていました。 彼の教科書は進化論の影響を反映しており、心の問題を有機体としての人間存在から説き起こしていました。 しかし、このスコットランド学派の精神哲学に基づく心理学は、後に実験心理学の発展によって忘れ去られることとなります。 伊澤が『教育学』で取り上げた心理学は、実験心理学とは異なるアプローチであり、この点に注目する必要があります。
4. ブリッジウォーターでの学びと伊澤の今後の研究への影響
伊澤はブリッジウォーター師範学校を卒業後、ローレンス科学学校に進学しました。 進学の動機としては、学校間のアーティキュレーションを理解するため、そして国民に確実な科学的知識を普及させるために西洋の科学思想を学ぶ必要性を感じていたことが挙げられます。 ローレンス科学学校では、師範取調の立場を考慮しつつ、物理学、化学、生物学など幅広い科学科目を学び、特に地質学に強い関心を抱きました。 この地質学への関心が、後に進化論の紹介へと繋がる重要な要素となります。 ハクスリーのアメリカ訪問と公開講演が、伊澤の進化論への関心に影響を与えたと考えられます。 伊澤は、その後東京高等師範学校校長に再任された際に、心理学を復活させ、実験心理学の発展にも関心を示していたとされています。
IV. 進化原論 翻訳と日本の進化論受容
伊澤修二は、【ハクスリー】の著作を翻訳した『進化原論』によって、日本に進化論を紹介した先駆者の一人である。彼の翻訳は、単なる科学的知識の伝達にとどまらず、当時の社会状況や政治思想にも影響を与えた。特に、【スペンサー】の社会ダーウィニズムは、自由民権運動や国家主義といった様々な政治イデオロギーと結びつき、激しい論争を巻き起こした。伊澤自身も、後にスペンサーの社会有機体論に基づいて国家主義的な主張を行うようになる。しかし、彼の翻訳の初期の目的は、あくまでも進化論を科学理論として紹介することであった。
1. 伊澤修二による進化論翻訳 生種原始論 と 進化原論
伊澤修二は、ダーウィンの『種の起源』を翻訳した『生種原始論』と、ハクスリーの著作を翻訳した『進化原論』を著しました。伊澤自身は、『進化原論』を「我国に進化論を輸入してこれを国民の知識とした最初の本」と位置づけています。帰国当時の日本においては、進化論は未だ広く知られておらず、東京大学綜理の加藤弘之先生でさえ、進化論を知らなかったと記述されています。しかし、『進化原論』の出版までに状況は変化し、石川千代松によるモースの講義録『動物進化論』の出版や、加藤弘之を巻き込んだ「人権論争」など、進化論が社会的な議論を巻き起こすようになっていました。 スペンサーの社会ダーウィニズムは、自由民権派の平等主義や国家主義の両方に利用され、激しい政治論争を引き起こしました。伊澤自身も後にスペンサーの社会有機体論を基に国家主義を主張するようになりますが、『進化原論』出版時の彼の意図は、進化論を純粋に科学理論として紹介することであったと推測されます。
2. 進化原論 翻訳における特徴と未解明な点
『生種原始論』は第一篇とされ、『進化原論』にほぼそのまま収録されていることから、翻訳作業は比較的短期間で完了していたと考えられます。しかし、出版が中断された理由や、地質学的方法に関する部分が『進化原論』で大幅に欠落している点などは、不明な点として残されています。 伊澤の地質学への強い関心は、進化論紹介の動機づけになったと考えられますが、この未訳部分と彼の地質学への関心の関連性、そしてモースとの関係性なども、今後の研究課題となります。 ハクスリーのアメリカ訪問と公開講演が、伊澤の翻訳に影響を与えた可能性も指摘されています。ハクスリーは進化論についてニューヨークで複数回の公開講演を行い、全米で話題をさらっていました。
3. 日本の進化論受容と社会への影響 モースの役割と人権論争
モースは日本で初めて進化論の講義を行った人物であり、彼の講義は進化論への関心を高めるきっかけとなりました。 モースの講義は石川千代松によって『動物進化論』として出版され、さらにモース自身も連続講演を行い、大きな反響を呼びました。 モースと親交のあったマレーは、日本の教育行政にも大きな影響を与えており、学制に関わった人々は、アメリカで流行していた進化論が日本社会に浸透していく時代を経験していました。 一方、明治10年代には、加藤弘之が進化論を用いて天賦人権説を批判したことをきっかけに「人権論争」が起こり、スペンサーの社会ダーウィニズムは激しい政治論争を巻き起こしました。 この論争は、スペンサーの思想が自由民権派の平等主義と国家主義の両方に利用されたことを示しており、進化論が日本の社会思想に大きな影響を与えたことを示しています。
V. 教育学 における道徳教育 ボイデンとアメリカ師範学校の伝統
伊澤修二の『教育学』における道徳教育論は、ブリッジウォーター師範学校校長【ボイデン】の教育理念の影響を強く受けている。ボイデンは、教師の【人格形成】と【感化訓育】を重視していた。アメリカ師範学校の伝統として、福音主義的信仰とベーコン以来の実証主義的科学観が調和的に発展していたことが、伊澤の道徳教育論の基盤となっている。彼の道徳教育は、個人の自由な選択と社会的な義務との調和を模索するものであり、後の日本の【修身教育】にも影響を与えたと考えられる。
1. 伊澤修二 教育学 における道徳教育の特質
伊澤修二の『教育学』は、ブリッジウォーター師範学校での学び、特にボイデン校長の教育理念の影響を強く受けています。 伊澤は、ボイデン校長の教育を「其師範教育が実に能く教育の真理を実際に行って」いると高く評価し、帰国後の教育活動の指針としたと述べています。 『教育学』では、教育の目的を智育・徳育に加え、ボイデン校長の考え方を踏襲しつつも独自に体育を加えています。これは、単なる能力開発ではなく、「人物」、つまり人格形成を重視する伊澤の独自の視点です。 しかし、『教育学』においては、道徳を成り立たせる根本原理の探求は避けられており、これは後の日本の修身教育を考える上で象徴的な点です。 伊澤の道徳教育論は、ボイデン校長の「感化訓育」から大きな影響を受けており、教師の模範となる人格形成が重視されています。
2. ボイデン校長の教育理念とアメリカ師範学校の伝統
ボイデン校長自身は道徳に関する著作を残していませんが、その人格が生徒の模範となっていました。 福音主義の信仰復興運動の影響下で設立されたアメリカの師範学校では、教師の道徳的人格の形成が強く重視されていました。 ボイデンは、教育には心に正しい行為を生じさせることと知識を獲得させることの二重の目的があると説いており、伊澤もこの点を踏襲しています。 しかし、伊澤はボイデンの教育理念を完全に受け継いだわけではなく、『教育学』では、自発的な選択と義務という相反する側面のバランスを重視する独自の立場を示しています。これは、功利主義倫理に基づくものであり、善行による喜びと悪行による苦しみを「本性(良心)」として捉えています。
3. スコットランド学派の精神哲学とホプキンスの影響
伊澤の『教育学』は、ボイデンの講義内容、特にホプキンスの『人間研究概説』に基づいた心理学を基盤としています。 ホプキンスはスコットランド学派の精神哲学の伝統を受け継ぎ、心理学を道徳哲学と論理学の基礎と捉えていました。 彼の心理学は、プロテスタントの福音主義的信仰とベーコン以来の帰納・演繹の哲学を両立させており、19世紀後半のアメリカの教員養成において重要な役割を果たしていました。 伊澤の『教育学』は、進化論の影響も受けているものの、それ以前のスコットランド学派の精神哲学に基づいた心理学説の紹介です。 ベーコン哲学の伝統を受け継いだ帰納・演繹の哲学、つまり実証主義の系譜に位置づけられる点においては、進化論以前と以後において連続性を見出すことができます。 しかし、実験室での実験的方法を科学心理学の成立の基準とするならば、伊澤の心理学は歴史において忘れ去られたものと言えるでしょう。
4. 道徳教育における未解決の課題 国民道徳の基盤
伊澤の徳育論は、道徳を成り立たせる原理の探求を避け、ボイデン校長の「感化訓育」に依拠しています。 アメリカにおける道徳的人格の形成は、キリスト教信仰という確固とした共通基盤があったからこそ可能でした。 しかし、日本の社会においては、キリスト教信仰が共通基盤として存在しないため、国民道徳を支えるものは何かという問題は、喫緊の課題となります。 森有礼が文部大臣時代に、修身教育において教科書を用いずに教師の言行を模範とすることを決定したことは、伊澤の教育理念との関連性も考えられます。 しかし、学校制度の普及が一段落した時点で、国民の道徳を支える基盤という問題は、日本においても重要な課題として浮上せざるを得なくなります。
