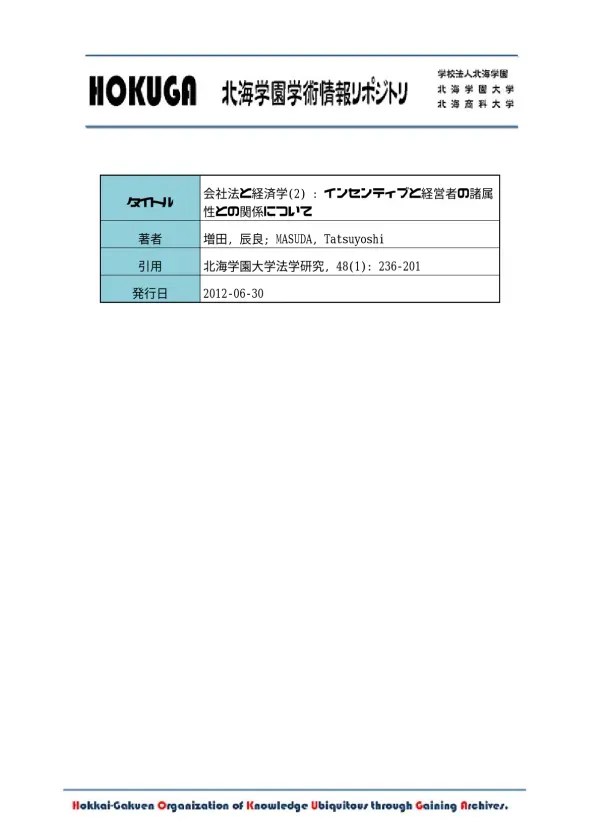
会社法と経営者属性:組織変更のインセンティブ効果
文書情報
| 著者 | 増田 辰良 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 研究ノート |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 540.16 KB |
概要
I.会社法が経営者に与えるインセンティブ
本稿は、会社法が経営者の意思決定に与えるインセンティブを検証する。特に、組織変更(法人化、法人間変更、個人事業化など)に焦点を当て、資本金規制撤廃、合同会社の設立認可など、会社法が起業促進、事業形態選択に与える影響を分析する。中小企業の事業形態変更における経営成果との関連性、ビジネス・エンジェルからの資金調達との関連性も考察する。 分析には、日本政策金融公庫のデータ(2007年8月時点、開業後5年以内企業)を使用する。重要な発見として、株式会社への法人化は、高い信用力、大きな資金調達額、良好な経営成果、事業規模拡大意欲と関連していることが挙げられる。
1. 会社法におけるインセンティブの機能と評価
会社法の規制内容と運用成果は、対象となる経営者の属性との関係において評価されるべきであると、本文では述べられています。そのため、会社法がどのような属性を持つ経営者に組織変更(個人事業の法人化、法人間での組織変更、法人の個人事業化)のインセンティブを与えることができるのかを検証することが重要になります。 この検証は、会社法が経済主体の意思決定に影響を与えるインセンティブとしての機能を有しているという前提に基づいています。市場経済における価格メカニズムと同様に、法や制度、道徳も経済主体の意思決定に影響を与えるインセンティブとして機能すると考えられています。 新たな立法や法改正の効果を測定することは、法律の評価だけでなく、将来の法改正を適切に行うためにも不可欠であり、法のインセンティブ機能を理解する上で重要です。本稿では、会社法制定以前のデータを用いて分析を行うため、現行会社法よりも広い範囲の組織変更を対象としています。
2. 起業を促進するインセンティブ 資本金規制撤廃と合同会社設立
会社法は、起業を促進するインセンティブとして、資本金規制の撤廃と合同会社の設立を可能にしました。株式会社設立者は「取引上の有利性」、有限会社設立者は「資本金の制約」を設立理由として挙げていた過去のデータ(増田・伊東、2011)を踏まえると、資本金規制撤廃は株式会社設立の促進に繋がると考えられます。実際、会社法施行後(2006年5月1日)には、小規模な株式会社設立が大幅に増加しています(中小企業白書2008年版)。 また、合同会社は、株式会社と持分会社の利点を組み合わせた事業形態として創設されました。有限責任と定款自治を両立させ、小規模事業者にとって有効な形態となっています。インターネットビジネスの普及なども背景に、小額資本での事業運営が可能となり、資本金規制撤廃の背景の一つと考えられます。経済産業省(2010)のデータでは、企業間電子商取引の割合は増加傾向にあります。合同会社の設立件数も増加しており、法の目的と件数の関係については、更なる検証が必要となります。
3. 組織変更における定款自治の拡大と機関設計の自由度
会社法は、定款自治を拡大することにより、会社設立時の組織形態を柔軟に選択できるインセンティブを提供しています。定款(会社の組織と活動に関する根本規則)に記載できる事項を、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分類し、特に相対的記載事項と任意的記載事項を大幅に増加させることで、会社はそれぞれの事情に合わせた定款を作成できるようになりました。 最低資本金規制の撤廃により、資本金1円からでも会社設立が可能となり、現物出資も認められています。これにより、起業時の資金負担が軽減され、起業意欲を高める効果が期待されます。 さらに、会社法は、株式の譲渡制限に応じて会社を公開会社と非公開会社に分類し、非公開会社では取締役会の設置や取締役の任期について柔軟な対応を可能にしています。機関設計の自由度を高めることで、事業の実情に合った組織形態を選択できるようになっています。ただし、これらの規定は会社法制定以前のデータに基づいている点に留意が必要です。
4. 事業形態選択へのインセンティブ 税制と有限責任事業組合
事業形態の選択(個人事業か法人形態か)は、税制の影響も大きく受けます。日本では、小規模個人事業主の法人化(法人成り)において、給与所得控除が課税所得を大きく減らすことができるため、節税対策として法人化が検討されるケースがあります。田近・八塩(2005)と八塩(2006)の研究は、この節税効果を裏付ける実証研究として挙げられます。 また、有限責任事業組合(LLPに類似)は、法人ではない組合形態ですが、有限責任と定款自治が認められており、人材集約型共同事業や産学連携による起業に有効です。合同会社と異なり、パススルー課税となるため、節税効果が大きくなる場合もあります。しかし、法人格を持たないため、他の事業形態への組織変更はできません。会社法は、これらの多様な事業形態選択を可能にすることで、経営者にとってより効率的な組織選択を促進するインセンティブを提供しています。
5. 会社法とその他の法制度との相互補完性
会社法のインセンティブ効果は、会社法単独ではなく、他の法制度との相互補完性において評価されるべきです。例えば、会社法の起業促進策は、雇用政策と補完関係にあります。会社法による起業促進は、雇用拡大という政策目標に貢献します。さらに、起業支援政策(資金援助や経営ノウハウ提供)も、会社法と補完的に機能します。 産業活力再生特別措置法の改正を受けて、会社法の組織再編手続きが簡略化された例からも、会社法が他の法制度と連携して政策目標を実現していることが分かります。 法(ルール)の存在を前提とした制度全体の効率性と、その法が存在しない場合の効率性を比較することで、より望ましい成果を生み出すインセンティブを持つ法を設計すべきです。会社法の規制内容と運用成果は、経済主体が作り上げる制度全体の効率性との関係(相互補完性)から評価されるべきです(神田・藤田、1998)。
II.事業形態の変更と経営者の諸属性
事業形態(個人事業、株式会社、有限会社、合同会社)変更における経営者の属性を分析する。分析の結果、法人化した経営者は、高い最終学歴、役員・管理職経験、事業運営経験を有し、大都市に立地している傾向がある。開業動機は「事業経営への興味」が多く、「自由な仕事」を望む経営者は個人事業を継続する傾向を示した。開業資金調達においては、株式会社への法人化****経営者はビジネス・エンジェルからの調達額が大きい。事業継承に関しては、法人形態の経営者は既に継承者と協働しているケースが多い。これらの結果は、会社法のインセンティブが雇用拡大、事業継承に貢献する可能性を示唆している。
1. データソースと分析方法
本稿の分析は、日本政策金融公庫総合研究所(旧国民生活金融公庫総合研究所)が2008年に発表したアンケート調査データに基づいています。このデータは、2006年4月から9月にかけて同公庫が融資を行った、開業後5年以内の企業(開業前を含む)に関するものです。調査時点は2007年8月です。データソースには、事業形態変更の理由や手法に関する情報は含まれておらず、開業時と調査時点における事業形態のみが確認できます。そのため、会社法制定以前のデータを用いて分析が行われており、現行会社法が規定する範囲よりも広い組織変更が分析対象となっています。分析手法としては、カイ二乗検定と分散分析を用いて、事業形態の変更と経営者の諸属性との関係が検証されています。
2. 経営者の人的属性と事業形態変更
分析の結果、現在も個人事業主のままである経営者は、法人化した経営者よりも若い年齢で開業している傾向があります。法人形態から個人事業へ変更した場合も同様です。これは、個人事業が法人形態よりも開業への意思決定が容易である可能性を示唆しています。開業動機については、個人事業を継続する経営者は「自由に仕事がしたい」という動機を、法人化する経営者は「事業経営に興味がある」という動機を多く挙げています。 分析対象となった企業は極めて小規模であり、法人形態では企業規模が一般的に大きいものの、この分析ではその規模は限定的です。 配偶者の職業も事業形態変更に影響を与えている可能性があります。例えば、夫が法人化する際に、妻の収入がリスク軽減に繋がるケースなどが考えられます。
3. 経営資源と事業成功 事業継承
株式会社へ法人化する経営者、または株式会社を維持している経営者は、高い信用力を持ち、ビジネス・エンジェルからの開業資金調達額が大きい傾向があります。これらの経営者は、高い最終学歴、役員や管理職経験、過去の事業運営経験を有し、大都市に立地していることが多いです。特に法人間で組織変更をしている経営者は、複数の事業を運営しているケースが多いです。 株式会社へ法人化する経営者の経営成果(収入、売上高、採算)は良好であり、将来も事業規模を拡大したいと考えている傾向が強いです。雇用規模も大きく、事業継承に関しても、既に継承者と協働しているケースが多いです。これらの傾向は、法人形態が事業の安定性と継続性に寄与していることを示唆しています。サンプルの約半分は後継者を決めておらず、特に個人事業主のまま、または法人形態から個人事業へ変更した経営者でその割合が高い傾向が見られました。
4. 今後の研究課題
本稿では、開業時と調査時(5年間)の2時点における事業形態の変更を分析しましたが、これは静的な分析です。より詳細な分析のためには、パネルデータを用いて事業形態の変更を時系列で追跡し、経営者の選択行動に影響を与えるインセンティブを明らかにする必要があります。動学的な視点を取り入れることで、法の運用成果をより正確に評価できます。 また、本稿では、事業形態を変更する理由や手法に関する情報は含まれていませんでした。将来の研究では、これらの情報も収集することで、より詳細な分析が可能になります。 本研究の知見は、会社法が事業組織のスムーズな変更を可能にするインセンティブを与え、雇用拡大や事業継承に貢献する可能性を示唆していますが、因果関係については、より厳密な計量分析による検証が必要となります。
III.今後の研究課題
本研究は2時点(開業時と2007年8月)のデータに基づいているため、事業形態変更の動学的側面の解明には限界がある。パネルデータを用いた時系列分析による更なる検証が必要である。また、有限責任事業組合のような他の事業組織形態との比較検討も今後の課題として挙げられる。更に、会社法とその他の法制度(雇用政策、起業支援政策など)との相互補完性についても、より詳細な分析が必要である。
1. データの期間制限とパネルデータの活用
本稿では、開業時とアンケート調査時(2007年8月、開業後5年以内)の2時点における事業形態の変更を分析対象としています。しかし、この期間はわずか5年間であり、より長期的な視点での分析が求められます。そのため、今後の研究課題として、パネルデータを用いた時系列分析が挙げられます。パネルデータを用いることで、事業形態の変更を動学的に追跡し、経営者の選択行動に影響を与えるインセンティブをより詳細に明らかにすることができます。 現在の分析は静的なものであり、長期的な影響や変化を捉えることができません。時系列データを用いた分析により、会社法のインセンティブが、経営者の事業形態選択、雇用拡大、事業継承といった意思決定にどのような影響を与えているのか、より深く理解できるようになるでしょう。法の運用成果は静的ではなく、動学的に評価されるべきであるという点も強調されています。
2. 事業形態変更の理由と手法に関する情報収集
本稿で使用されたデータソースには、事業形態を変更する理由や、その際に用いられた手法(合併、株式交換、分割、営業譲渡など)に関する情報は含まれていません。開業時と調査時点の事業形態しか確認できないため、詳細な分析には限界があります。 今後の研究では、事業形態変更の理由や手法に関する情報を収集することが重要です。これにより、経営者の意思決定プロセスをより深く理解し、会社法のインセンティブがどのように作用しているかを分析できます。 例えば、法人化の理由が税制上の優遇措置によるものなのか、事業拡大戦略によるものなのか、といった点を明確にすることで、会社法のインセンティブの効果をより正確に評価できるようになります。 また、事業形態変更の手法によって、手続きの複雑さや費用などが異なる可能性があり、それらが経営者の意思決定に影響を与えている可能性も考えられます。
3. 因果関係の厳密な検証と計量分析の深化
本稿では、会社法が事業組織をスムーズに変更できるようなインセンティブを発揮することが、雇用拡大や事業継承に良好な影響を与え、最終的に利益の確保に繋がる可能性を示唆しています。しかし、これはあくまで可能性であり、因果関係については、より厳密な検証が必要です。 今後の研究課題として、より高度な計量分析手法を用いて、会社法のインセンティブと経営成果、雇用拡大、事業継承との因果関係を厳密に検証することが挙げられます。 例えば、潜在的な交絡変数を考慮した回帰分析などを行い、会社法のインセンティブ以外の要因の影響を除外することで、より信頼性の高い結果を得ることができます。 また、異なる事業形態や規模の企業を対象とした分析を行うことで、会社法のインセンティブ効果の普遍性や限界についても検証できます。
4. その他の事業組織形態との比較検討
本稿では、主に株式会社、有限会社、個人事業を対象としていますが、有限責任事業組合など、他の事業組織形態も存在します。これらの形態との比較検討を行うことで、会社法のインセンティブが、より広い文脈の中でどのように機能しているかを理解することができます。 有限責任事業組合は、法人格を持たないものの、有限責任と定款自治を両立させている特徴があります。この形態と、株式会社や有限会社を比較することで、それぞれの事業形態のメリット・デメリット、および会社法のインセンティブが各形態に与える影響の違いを明らかにできる可能性があります。 また、各事業形態の設立件数や経営状況のデータを用いた比較分析を行うことで、会社法のインセンティブ設計の改善に繋がる知見が得られると考えられます。 これらの比較分析は、より効果的な法制度設計に貢献するでしょう。
