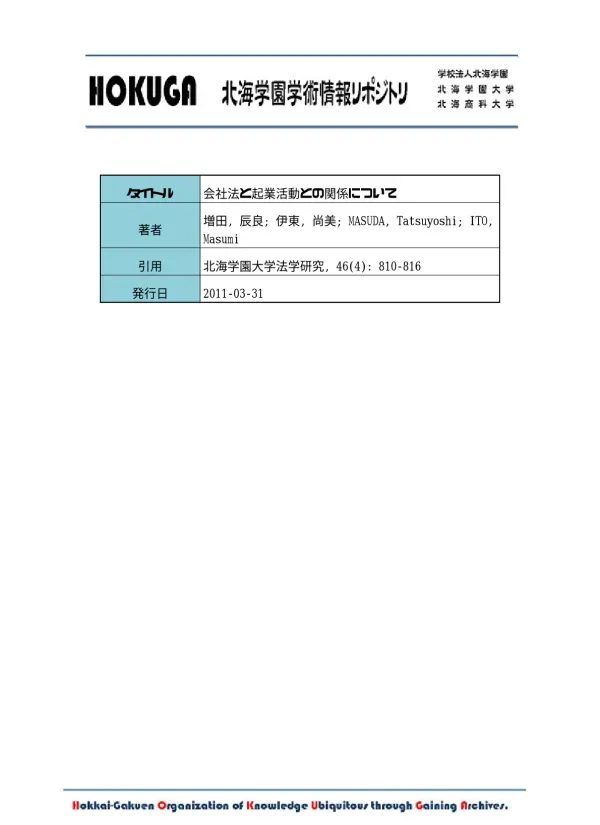
会社法と起業:設立手続きと経営成果
文書情報
| 著者 | 増田 辰良 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.97 MB |
概要
I.会社法改正と起業形態の選択
本稿は、2006年5月施行の改正会社法が起業に与える影響、特に事業形態の選択(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、個人経営)と経営成果の関係を、国民生活金融公庫(現・日本政策金融公庫)のデータ(2002年4月~9月、2377人の起業家)を用いて分析したものです。改正会社法は、法文の現代語化、制度間の整合性確保、社会経済情勢への対応を目的としており、特に合同会社の創設は、有限責任と定款自治の拡大により小規模起業を促進すると期待されています。最低資本金規制の撤廃も、起業の容易化に繋がると考えられています。
1. 会社法改正の目的と背景
2006年施行の会社法改正は、大きく3つの目的を掲げていました。まず、法文の現代語化(片仮名文語体から平仮名口語体への変更)と、その過程における内容調整です。これは、法律の理解度向上と運用効率化を目指したものでした。次に、それまで頻繁に行われてきた商法改正に伴う諸制度間の整合性確保です。法体系全体の整合性を図り、矛盾や不備を解消することで、よりスムーズな事業運営を可能にする狙いがありました。最後に、社会経済情勢の変化への対応です。これは、実業界からの強い要望を受け、時代のニーズに合わせた制度の見直しが行われたことを示しています。これらの目的は、日本経済の活性化と企業活動の円滑化に寄与することを目指したものでした。改正会社法は、単なる法文の改定ではなく、日本の企業活動を取り巻く環境変化への対応策として位置付けられています。特に、中小企業の起業促進や、多様な事業形態への対応が重要な要素となっています。
2. 新しい事業形態 合同会社の創設と最低資本金規制の撤廃
改正会社法において最も注目すべき点は、株式会社と任意組合の長所を融合した新たな事業形態である『合同会社』の創設です。合同会社は、株式会社と同様に、出資者の責任を有限責任(出資額の範囲内)に限定することができます。同時に、定款によって柔軟な経営ルールを定めることができる『定款自治』の拡大も実現しました。これにより、利益や権限の配分を自由に設計することが可能になり、資金力に乏しい起業家やグループによる起業を促進することが期待されています。また、改正会社法では、従来必要とされていた最低資本金の限度額が撤廃されました。これは、資本金1円からでも会社設立が可能になったことを意味し、起業のハードルが大きく下がったと言えるでしょう。この最低資本金規制の撤廃は、中小企業の設立促進に大きく貢献すると期待され、特に、資金調達に苦労する起業家にとっては大きなメリットとなります。さらに、金銭以外の財産(現物出資)を認めることで、起業時の資金負担を軽減する効果も期待できます。ただし、合同会社の場合、出資に係る金銭の全額払込みまたは金銭以外の財産の全部給付が必要となる点には注意が必要です。
3. 事業形態選択と経営成果に関する先行研究のレビュー
本稿では、起業家が事業形態を選択する際に考慮する要素と、その選択が経営成果に与える影響について、先行研究をレビューしています。先行研究では、起業家は事業形態(株式会社、パートナーシップ、個人経営、ジョイントベンチャーなど)の選択に最大の関心を寄せており、特にサービス業や小売業ではその傾向が強いことが指摘されています。また、株式会社は他の事業形態と比較して外部からの資金調達が容易であり、それが企業成長に繋がるとの推測もあります。いくつかの先行研究では、法人形態(株式会社など)の企業の方が、個人企業と比べて売上高や雇用者数が大きく増加していることが示されています。しかしながら、法人形態が必ずしも外部金融において有利であるとは限らないという指摘もあります。税制面についても、アメリカにおける二重課税問題のように、法人形態の選択意欲に影響を与える要因があることが指摘されています。これらの先行研究を踏まえ、本稿では国民生活金融公庫のデータを用いた独自の分析を行い、起業時の事業形態選択と経営成果の関係について検証しています。
4. 小規模企業における 右腕者 の存在と役割
小規模企業において、起業家の重要なパートナーとなる人物を「右腕者」と定義し、その存在と役割に注目しています。この「右腕者」は、会社法における意思決定機関(株主総会、取締役会など)に相当する役割を担っていると捉えることができます。会社法改正により、特に公開会社以外の企業では機関設計の自由度が高まったため、この「右腕者」の役割は、経営成果に大きな影響を与える可能性があります。本稿では、株式会社、有限会社、個人経営の各事業形態において、「右腕者」の有無や役割を分析することで、機関設計が経営成果に与える効果を検証しています。この分析を通して、小規模企業における組織設計の最適化や、経営戦略の策定に役立つ知見を得ることが期待されます。特に、起業時の意思決定において、「右腕者」の選定がいかに重要であるかを明らかにすることを目指しています。
II.株式会社の機関設計と剰余金配当
株式会社では、株主総会と取締役の設置が義務付けられています。改正会社法は定款自治を拡大し、取締役会、監査役会、監査役、委員会等の機関設計の自由度を高めました。また、剰余金(利益)の配当に関しても、旧商法に比べ自由度が高まり、いつでも配当が可能となりました(ただし、配当後の純資産額が300万円を下回る場合は不可)。
1. 株式会社の必須機関と定款自治の拡大
株式会社においては、株主総会と取締役の設置が法律で義務付けられています。株主総会は出資者である株主で構成され、会社の最高意思決定機関としての役割を担います。取締役は株主のために会社の業務を執行する者であり、取締役会設置会社では取締役会の構成員として経営に関する意思決定に関与し、代表取締役を監督する役割も担います。取締役会を設置しない会社では、取締役が直接業務執行を行います。改正会社法では、これらの必須機関以外については、定款自治の原則に基づき、各会社が任意に機関(取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人、委員会、執行役など)を設置できるようになりました。この定款自治の拡大により、企業は自社の規模や経営形態に最適な機関設計を行うことが可能になり、柔軟な経営体制の構築が促進されると考えられます。ただし、公開会社の場合は、取締役会(取締役3名以上)の設置と代表取締役の選任が義務付けられている点に注意が必要です。取締役の任期は原則として2年です。
2. 剰余金配当の自由化
改正会社法では、旧商法と比較して、剰余金(利益)の分配に関する規制が緩和され、配当の自由度が高まりました。剰余金は、総資産額から総負債額と資本金額を差し引いた金額として定義され(446条1項)、株主への配当は株主総会での普通決議(過半数による多数決)によっていつでも行えるようになりました(453条、454条1項)。旧商法では中間配当と期末配当のみが認められていましたが、改正により、企業の状況に応じて柔軟に配当を行うことが可能になりました。これは、株式を保有すること自体で配当金を得ようとする投資家にとって大きなメリットとなります。しかし、配当はあくまでも会社に余裕資金がある場合に限定されます。余裕資金がない状態で配当を行うと、債権者への支払いが滞ってしまう可能性があるためです。また、配当後の純資産額が300万円を下回る場合は、剰余金の配当はできません(453条、458条)。
3. 取締役会設置の有無と機関設計の類型
株式会社においては、取締役会を設置するかどうかによって機関設計の選択肢が変化します。取締役会を設置しない会社は、会社法施行前の有限会社の機関と同様となり(326条2項)、監査役を設置することもできます。監査役を設置しない場合は、株主が直接経営監督に関与する機会が増えることになります。取締役会を設置しない会社では、3種類の機関類型が考えられます。一方、取締役会を設置する会社では、監査役会または監査役、もしくは委員会のいずれかを設置する必要があります(327条2項)。大会社以外の全株式譲渡制限会社で会計参与を設置した場合はこの限りではありません(327条2項但書)。委員会設置会社には会計監査人の設置が義務付けられ(327条5項)、監査役会または監査役を設置する会社では、会計監査人の設置は任意です。公開会社と同様に、会計参与の設置も自由に選択できます。このように、取締役会を設置する会社では6種類の機関類型が考えられます。それぞれの機関の役割分担と、それらが経営効率や企業ガバナンスに与える影響を検討することが重要です。
III.持分会社 合名会社 合資会社 合同会社 の特徴
持分会社は、個人的な信頼関係に基づく少人数の事業形態です。社員の地位である持分の譲渡には原則として他の社員全員の承諾が必要です。合同会社は、株式会社と任意組合の利点を兼ね備え、有限責任と定款自治が認められています。アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)を参考に創設されたことから、日本版LLCとも呼ばれています。合同会社では、労務出資は認められません。
1. 持分会社の概念と特徴
持分会社は、株式会社とは異なり、個人的な信頼関係に基づいて少数の出資者によって構成される事業形態です。出資者は「社員」と呼ばれ、その社員の地位を「持分」といいます。この持分は、株式会社の株式のように自由に譲渡できるものではなく、原則として他の社員全員の承諾が必要です(585条1項)。これは、持分会社が個人的な信頼関係を重視した組織であることを示しています。持分会社の類型としては、合名会社、合資会社、そして合同会社の3種類があります。合名会社は全ての社員が無限責任を負い、合資会社は社員の一部が無限責任、一部が有限責任を負います。一方、合同会社は全ての社員が有限責任となります。これらの違いは、社員の責任範囲や経営形態に影響を与えます。小規模な事業においては、設立手続きの容易さや、親密な関係に基づく経営が求められるケースが多く、これらの持分会社形態が適している場合が多いと考えられます。
2. 合同会社の特徴 有限責任と定款自治の拡大
合同会社は、株式会社と任意組合の利点を組み合わせた新しい事業形態として、改正会社法によって創設されました。株式会社と同様に、出資者の責任は出資額の範囲内に限定される有限責任を有します。さらに、定款によって経営ルールを自由に定めることができる定款自治が大きく拡大されており、利益や権限の配分についても柔軟な設計が可能となっています。これは、任意組合と同様のメリットです。これらの特徴から、資金力に乏しいながらも、起業家精神に富んだ個人やグループが比較的容易に事業を始めることができる、魅力的な事業形態として期待されています。アメリカ合衆国のLLC(Limited Liability Company)を参考に創設されたことから、日本版LLCと呼ばれることもあります。しかしながら、合同会社では労務出資は認められていない(576条1項6号)点に注意が必要です。これは、株式会社とは異なる重要な違いです。
3. 持分会社と株式会社との比較 株式譲渡制限と設立手続き
株式会社と持分会社の大きな違いの一つに、株式の譲渡制限があります。株式会社では、全ての株式について譲渡を制限する規定を定款に置くか、一部でも譲渡制限のない株式を発行するかどうかによって、非公開会社と公開会社に分類されます。これに対し、持分会社は、個人的な信頼関係に基づく少人数の出資者から構成されることが想定されており、持分の自由な譲渡は制限されます。小規模でスタートする企業にとって、設立手続きの容易さは重要な要素です。設立手続きの容易性を考慮すると、株式会社では中小会社や非公開会社、持分会社では合同会社が比較的選びやすい事業形態と考えられます。これは、設立に必要な手続きや要件の複雑さ、資本金に関する規制などを考慮したものです。しかしながら、事業規模や成長戦略、資金調達の方法など、様々な要因を総合的に考慮して、最適な事業形態を選択する必要があります。
IV.起業時の事業形態と経営成果の関係 分析結果
分析の結果、起業家の多くは個人経営を選択しており、後に法人化を検討している傾向が見られました。株式会社を選択した起業家は、取引上の有利性や資金調達の容易さを理由に挙げています。有限会社は、資本金の制約を理由に選択する起業家が多かったものの、改正会社法による最低資本金規制の撤廃により、株式会社への移行が促進される可能性が示唆されています。右腕者の存在は、特に個人経営において売上高の増加に大きく貢献していることが分かりました。また、法人形態を選択した起業家は、従業員規模の拡大や事業内容の多角化といった成長志向が強い傾向がありました。
1. データソースと分析対象
本分析は、国民生活金融公庫(現・日本政策金融公庫)総合研究所が2003年に実施したアンケート調査データ(2002年4月から9月にかけて融資を受けた開業後1年以内の起業家2377人)に基づいています。このデータは、起業後の初期段階にある経営者を対象としている点が特徴です。先行研究との大きな違いは、データソースが国民生活金融公庫の融資顧客である点です。分析対象となる起業家の属性(性別、年齢、経験など)や、開業時の事業形態(株式会社、有限会社、個人経営など)、開業動機、経営ビジョン、資金調達方法、経営成果(売上高など)に関するデータが用いられています。このデータを用いることで、起業家自身の属性や経営状況、そして事業形態の選択と経営成果との関連性を詳細に分析することを目指しています。ただし、本データは起業の回数や方法(新規設立、合併など)に関する情報を含んでいないため、起業家タイプの分類(初めての起業家、複数の事業を手がける起業家など)は行われていません。
2. 開業時の事業形態別分析 個人経営の割合と法人化傾向
アンケート調査結果によると、開業時の事業形態では個人経営が最も多く(サンプル数の64.4%)、次いで有限会社、株式会社の順となっています。これは、個人経営が登記などの煩雑な法手続きが少ないため、起業家が選択しやすい事業形態であることを示唆しています。しかし、アンケート調査時(平均15ヶ月後)の事業形態を見ると、個人経営が減少し、株式会社や有限会社への法人化が増加していることが分かります。これは、起業家が初期段階では手続きの容易さを重視した個人経営を選択し、その後事業の成長に合わせて法人化を進めている可能性を示唆しています。この法人化の傾向は、会社法改正による影響を分析する上で重要な要素となります。さらに、事業形態別に「右腕者」(経営のパートナー)の採用状況を見ると、株式会社では仕事を通じた友人・知人や社員、有限会社では配偶者や社員、個人経営では配偶者が多く採用されていることが分かりました。これは、事業形態によって、経営における協力体制や役割分担に違いがあることを示唆しています。
3. 経営成果と事業形態 右腕者の関係
分析では、開業費用、開業資金額、売上高などの経営成果と、事業形態、右腕者の有無、右腕者の役割との関係を検証しています。開業費用や開業資金額は、株式会社が最も多く、資金調達の容易さも株式会社が最も高い傾向が見られました。経営成果についても、株式会社は開業時の目標月商額が高く、実際の月商額も高くなっています。しかし、目標月商額に対する達成率では、有限会社が最も高いという結果も得られています。右腕者の有無については、特に個人経営において、右腕者の存在が売上高の増加に大きく貢献していることが明らかになりました。これは、右腕者が経営上の意思決定や業務執行において重要な役割を担っていることを示唆しています。また、右腕者の役割(経理・財務、営業・渉外、接客・サービスなど)と経営者の役割との関係についても分析を行い、役割分担が経営成果に与える影響を検討しています。資金調達方法についても、事業形態によって、自己資金、国民生活金融公庫からの融資、友人・知人からの借入金など、利用方法に違いが見られました。
4. 会社法改正の成果と今後の課題
本分析の結果、多くの起業家が初期段階では個人経営を選択し、その後法人化を目指す傾向があることが分かりました。そのため、会社法改正と法人化の関連性をさらに詳細に分析する必要があります。日本の法人化は、節税対策との関連で議論されることが多いですが、本稿では法人化している個人事業主の雇用成長率なども分析する必要性を示唆しています。これは、法人化による税収減というデメリットと、雇用創出というメリットを総合的に評価する必要があるためです。また、会社法改正により最低資本金規制が撤廃されたことで、株式会社での起業が促進される可能性が高まっています。実際、改正後には資本金300万円未満の株式会社の設立が大幅に増加しているというデータもあります(中小企業白書2008年版)。本稿の分析結果から、成長志向の強い起業家は、資金調達の容易さから株式会社を選択する傾向がある一方で、成長志向が低い起業家は設立や解散が容易な事業形態を選択する傾向が示唆されます。今後の課題としては、より多くのサンプル数を用いた分析や、より包括的なデータの収集、分析を通して、本稿の結論の一般化を進めることが挙げられます。
V.今後の課題
本研究では、国民生活金融公庫の融資を受けた起業家を対象としているため、サンプル数の増加やデータソースの拡充が必要となります。また、起業の回数や方法、法人化と雇用成長率の関係、業種による違いなど、さらなる分析が求められます。特に、改正会社法施行後の法人化の動向や、その経済効果について詳細な検証が必要となります。
1. データの限界とサンプル数の拡大
本研究で使用したデータは、国民生活金融公庫(現・日本政策金融公庫)が融資した顧客を対象としたものであり、その結論を一般化するには限界があります。より包括的な結論を得るためには、サンプル数を増やし、より多様な企業や起業家を網羅したデータを用いた分析が必要不可欠です。現在のデータソースでは、起業の回数や方法、具体的には初めての起業(novice entrepreneurs)なのか、過去に廃業経験のある起業家(serial entrepreneurs)なのか、あるいは複数の事業を並行して行う起業家(portfolio entrepreneurs)なのかを区別することができません。また、新設合併、新設分割、株式移転など、企業設立に至る経緯についてもデータからは読み取ることができません。これらの情報を加えることで、会社法改正が起業活動に与える影響をより詳細かつ正確に分析することが可能になるでしょう。より精緻な分析を行うことで、会社法改正の効果をより明確に評価することができます。
2. 法人化 法人なり と雇用成長率の分析
本稿の分析では、多くの起業家が個人経営から始めて、後に法人化を目指す傾向があることが示唆されました。そのため、会社法改正の施行と法人化の関連性をより詳細に分析することが重要です。特に、法人化は節税対策と関連して議論されることが多いですが(本文3節参照)、法人化している個人事業主の雇用成長率を分析する必要があります。もし、法人化によって雇用成長率が高まるのであれば、税収減というデメリットを相殺するだけのメリットがあると言えるでしょう。この点については、より詳細なデータ分析を通して検証する必要があります。分析対象を広げることで、法人化が経済全体に及ぼす影響、特に雇用創出への貢献度を正確に評価することが可能となります。また、法人化の意思決定に影響を与える要因についても、より深く探る必要があります。
3. その他の分析対象の検討
本研究では、分析に用いたデータの制約から、いくつかの重要な要素を詳細に検討することができませんでした。例えば、起業家の属性として性別と職業キャリアを採用しましたが、その他の属性(年齢、経験年数など)や、より詳細な職業分類も分析に含めることで、より多角的な分析結果が得られると考えられます。また、右腕者の役割に関する分析においては、アンケート調査の複数回答形式というデータの特性上、因子分析や主成分分析を用いて主要な役割を特定化し、より精密な分析を行う必要性が残されています。さらに、業種ダミー変数を用いた分析結果についても、本稿では煩雑さを避けるために省略しましたが、今後の研究では、業種による違いを詳細に検討する必要があります。これらの課題に取り組むことで、会社法改正の効果をより多角的に評価し、より実効性のある政策提言を行うことが可能となります。
