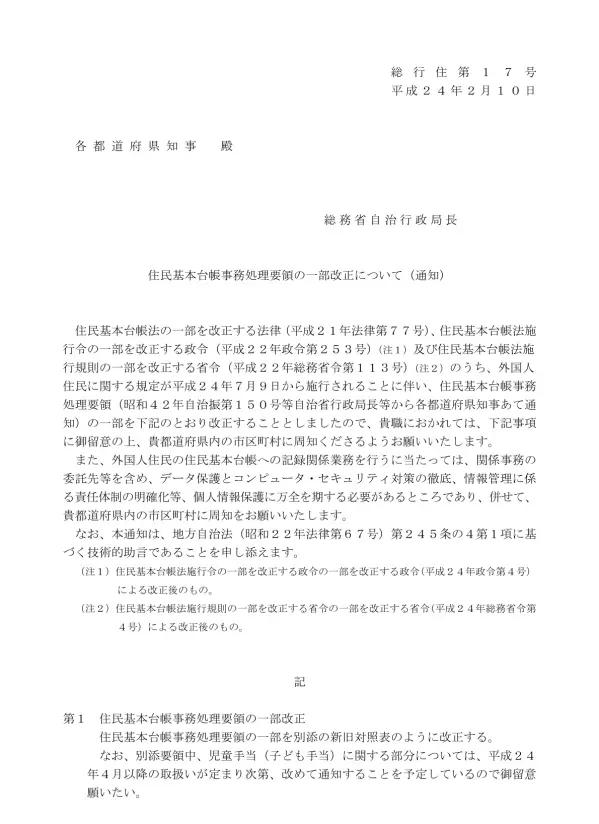
住民基本台帳事務処理要領改正
文書情報
| 著者 | 総務省自治行政局長 |
| 会社 | 総務省 |
| 文書タイプ | 通知 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 711.32 KB |
概要
I.住民票の記載事項変更と外国人住民への対応
この通知は、平成24年7月9日より施行された住民基本台帳法の一部改正に伴う、住民基本台帳事務処理要領の改正について説明しています。特に、外国人住民に関する規定の変更が重点で、住民票への氏名、出生年月日、性別、国籍・地域、住所等の記載に関する事項、および在留カードとの整合性について詳細に解説しています。住民票コードの取扱いについても変更があり、個人情報保護の観点からの厳格な運用が求められています。特に、外国人住民の通称の記載に関する規定も新たに追加されています。
1. 住民票記載事項の変更点 外国人住民への対応
住民基本台帳法の改正(平成21年法律第77号、平成22年政令第253号、平成22年総務省令第113号)に伴い、住民基本台帳事務処理要領が変更されました。特に、平成24年7月9日施行の外国人住民に関する規定の改定が重要なポイントです。住民票への氏名、出生年月日、性別、本籍、戸籍といった基本事項に加え、新たに国籍・地域、外国人住民となった年月日、法第30条の45の表の下欄に掲げる事項の記載が規定されています。これらの記載事項は、入管法及び入管特例法に基づき交付された在留カード等の記載と一致する必要があります。特に、中長期在留者については、この整合性が厳しく求められます。また、住民票の様式は法定されておらず、市町村が住民の利便性を考慮し、簡明かつ平易な様式を創意工夫することが推奨されています。外国人住民の通称の記載についても、申出があれば、居住関係の公証のために必要と認められる場合は記載することが義務付けられました。 データ保護とコンピュータ・セキュリティ対策の徹底、情報管理責任体制の明確化など、個人情報保護に万全を期する必要性が強調されています。
2. 住民票の記載における注意点 世帯主の氏名 国籍 地域 通称
外国人と日本人の混合世帯の場合、住民基本台帳法の適用除外されている外国人が世帯主に相当する場合でも、世帯主の氏名には日本人の世帯員のうち世帯主に最も近い地位にある者の氏名を記載し、実際の世帯主である外国人の氏名は備考欄に記入することとされています。国籍・地域については、在留カード等に記載されている内容を記載し、無国籍者も含まれます。出生による経過滞在者については、法務大臣からの通知を待って職権で修正します。国籍喪失による経過滞在者については、国籍喪失届や国籍喪失報告の記載を確認し、職権で国籍・地域の記載を行います。帰化や国籍取得の場合は、新規に住民票コードを記載します。以前住民票コードを記載された国外転出者が国内に転入する際は、都道府県知事または指定情報処理機関から本人確認情報の提供を受け、以前の住民票コードを確認の上、記載します。通称の記載は、外国人住民から通称の記載を求める申出書の提出があり、居住関係の公証のために必要と認められる場合に限り、記載が義務付けられます。
3. 職権記載と届出がない場合の対応
届出がない場合、届出義務者への催告を行い、それでも届出がない場合は、事実を確認の上、職権で記載を行います。転入者については、前住所地市町村長に照会し、記載事項と前住所地を確認します。日本の国籍を有しない者については前住所地に照会します。事実確認には実地調査が適当です。住民票に記載する際は「○○につき職権記載」とその事由、記載を行った年月日を記入します。 この手続きは、住民票の記載、消除、氏名、出生年月日、性別、住所、住民票コードの修正についても同様に行われます。市町村長はこれらの修正を行った際には、本人確認情報を電気通信回線を通じて都道府県知事に通知する必要があります。通知する本人確認情報の内容も規定されています。
II.住民票の写し等の交付に関する手続きの変更
住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付請求手続きについても、改正内容が反映されています。請求者の本人確認が厳格化され、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類の提示が必須となります。また、特定事務受任者(弁護士、行政書士など)による請求についても規定が明確化されています。不正な目的による請求への対応についても言及されています。
1. 住民票の写し等の交付請求手続き
住民基本台帳法に基づき、住民票の写しや住民票に記載された事項に関する証明書の交付請求手続きが規定されています。請求者は、自分の氏名と住所、および請求の対象となる者の氏名(外国人の場合は氏名または通称)などの所定事項を明確に示す必要があります。請求者が本人であることを明確にするために、法令に基づき交付された書類の提示が求められます。具体的には、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証などが例示されており、市町村長が適当と認める書類も含まれます。 本人確認は慎重に行われ、必要に応じて口頭での質問による補足が行われます。職員証など写真のない書類の場合や、口頭での確認が不十分な場合は、関係機関への照会など、より厳格な確認が行われる場合もあります。 交付請求書や申出書は、定型的な様式を作成し、原則としてこれらに記載させるか、請求者識別カードを使用して端末機に入力させることが適当とされています。住民票コードの記載については、請求者の理解を得た上で、できる限り省略した写しを交付することが推奨されています。
2. 住民票写し交付請求における本人確認書類
住民票の写し等の交付請求に際しては、請求者本人の確認が不可欠です。本人確認のためには、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証などの官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書(本人の写真が貼付されたもの)の提示が求められます。これ以外にも、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証など、法律またはこれに基づく命令で交付された書類も認められます。市町村は、提示された書類が偽造・変造されていないか、券面の特性などを踏まえて厳格に確認する必要があります。特に、写真が貼付されていない職員証などの場合や、口頭での確認が不十分な場合は、関係機関への照会など、さらなる確認が必要となる場合があります。 請求者が、自身の権利行使や義務履行、国または地方公共団体の機関への提出、正当な理由のある利用などの目的で住民票の写しが必要とする場合は、一定の事項のみが表示された写しを交付することが認められています。特定事務受任者(弁護士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など)からの請求についても同様の規定が適用されます。
3. 特定の目的での住民票写し交付と不当な請求への対応
住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長以外の市町村長に対して、戸籍の表示、個別事項、任意事項、通称の記載および削除に関する事項の記載を省略した住民票の写しの交付を請求できます。ただし、交付地市町村長は、請求が不当な目的によることが明らかな場合は、その請求を拒否することができます。 住民票の写し等の交付請求や申出を行う際には、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求や申出の場合と同様に、定型的な請求書や申出書の様式を作成し、原則としてこれらに記載させること、または請求者識別カードの使用により端末機に入力させることが適当です。 また、法第30条の43において、告知要求の制限、利用制限などが設けられており、秘密保持義務によって保護されている情報に関わる請求に対しても、交付地市町村長はこれらの規定の趣旨を請求者に十分説明し、理解を得た上で対応する必要があります。
III.住民基本台帳カードの運用と本人確認
住民基本台帳カードの運用についても、改正法に基づいた変更が加えられています。カード技術基準に沿った運用が求められ、本人確認の方法、特に暗証番号照合を含む手続きが詳細に説明されています。住民基本台帳カード以外の本人確認書類の取扱いについても、偽造・変造防止の観点から厳格な確認が求められています。
1. 住民基本台帳カードを用いた本人確認
住民基本台帳カードは、本人確認において重要な役割を果たします。請求書の提出時点で有効期間内の住民基本台帳カードが、本人確認書類として利用可能です。本人確認は、カードの暗証番号を照合し、本人確認情報を取得して、申請書に記載された事項と照合することで行われます。 住民基本台帳カード以外の書類による本人確認は、その表面記載事項等に基づき本人確認情報 を取得し、申請書に記載された事項と照合することによって行われます。ただし、住民基本台帳カードに半導体集積回路が組み込まれており、その機能に不具合がある場合のみ、住民基本台帳カード以外の書類による本人確認と同様の方法で本人確認を行うことができます。 本人確認書類については、市区町村が券面の特性などを適格に把握できるものについては、偽造・変造がないことを目視で厳格に確認します。それ以外の書類については、氏名等の修正跡など、偽造・変造が疑われる点がないか確認する必要があります。 15歳未満の者や成年被後見人に対しては、直接住民基本台帳カードを交付することは適当ではありません。
2. その他の本人確認書類と確認手順
住民基本台帳カードの他に、運転免許証、健康保険被保険者証など、法律またはこれに基づく命令で交付された書類も本人確認書類として使用できます。さらに、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、猟銃・空気銃所持許可証など、公益性が高いと認められる書類も含まれます。市町村は、これらの書類が偽造・変造されていないか厳格に確認する必要があります。 半導体集積回路が組み込まれた運転免許証については、券面表示ソフトウェアを用いて、半導体集積回路に記録された情報(氏名、生年月日、有効期限、顔写真)と券面事項が一致することを確認する必要があります。 住民基本台帳カードの暗証番号照合ができた場合、または半導体集積回路付き運転免許証の情報と券面事項が一致した場合を除き、他の本人確認書類を追加で提示させることで、交付申請者が本人であることを厳格に確認する必要があります。確認できない場合は、照会書を送付するなどの対応が必要となります。 本人確認書類として、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書なども考えられます。
3. 住民基本台帳カードの記載事項と情報管理
住民基本台帳カードには、住民票に記載又は記録されている氏名(外国人住民で通称がある場合は氏名と通称)、出生年月日、性別、住所、有効期限、写真などの情報が記録されます。氏名や住所の字数が多く、カードの表面に記載できない場合は、裏面の追記領域などに記載し、「何字加入」等と明記して職印を押します。 カードの半導体集積回路には、表面に記載した情報と同じ内容が記録されます。 住民基本台帳カードに関する技術的基準(平成15年総務省告示第392号)に沿った運用が求められ、市町村はこれらの規定を遵守する必要があります。 住民票の記載、消除、または氏名、出生年月日、性別、住所、住民票コードの修正があった場合、市町村長は本人確認情報を電気通信回線を通じて都道府県知事に通知する必要があります。
IV.異動等情報の利用 提供に関する規定
住民票の記載事項の修正や消除に関する異動等情報の取扱いについて、都道府県知事への情報提供義務が規定されています。電子署名に係る法律に基づき、指定認証機関への情報提供についても触れられています。市町村と都道府県、関係機関との連携の重要性が強調されています。
1. 異動等情報の定義と通知義務
住民票の記載事項の修正や消除に関する情報を「異動等情報」と定義し、その取扱いが規定されています。市町村長は、住民票の記載、消除、または氏名(外国人住民で通称がある場合は氏名と通称)、出生年月日、性別、住所、住民票コードについて、全部または一部の修正を行った場合、本人確認情報を電気通信回線を通じて都道府県知事に通知する義務があります。軽微な修正は除かれます。都道府県知事は、これらの通知があった旨の情報(異動等情報)を、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づき、指定認証機関に提供することができます。この規定は、個人情報の保護と正確な情報管理の徹底を目的としています。 都道府県知事は、氏名、出生年月日、性別、または住所の全部または一部について住民票の修正(軽微な修正を除く)、または住民票が消除された旨の通知があった場合、これらの通知があった旨の情報を異動等情報として取り扱います。
2. 異動等情報の保存と提供先
都道府県知事は、異動等情報を電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律第34条第1項の規定により指定認証機関に認証事務を行わせた上で、同法第35条に規定する事務の処理のため、電気通信回線を通じて指定認証機関に提供することができます。この際、都道府県知事は、異動等情報を一定期間保存する必要があります。 都道府県区域外の市町村で海外からの転入または職権記載があった場合、開示請求などを通じて本人からの申し出があった場合などは、市町村から都道府県への適切な連絡が必要とされています。 これらの規定は、住民基本台帳情報の正確性と一貫性を維持し、関係機関との連携を円滑に行うためのものです。情報の共有や利用にあたっては、法令で定められた範囲内で、個人情報保護に最大限の配慮が必要です。
3. 関係機関との連携と情報提供
市町村は、住民基本台帳に関する業務において、関係機関との連携を強化することが求められています。例えば、住民票の写しの交付や閲覧に関する手続きにおいて支援が必要な場合、選挙管理委員会との連携が重要になります(「選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項について」平成17年3月25日総行選第7号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)。 同様に、市町村内の関係各部局への必要な情報の提供を通じて、連携を強化することが求められています。 これらの連携強化は、住民サービスの向上と行政効率の改善に大きく寄与し、正確かつ迅速な情報伝達を可能にします。 特に、外国人住民に関する情報は、入国管理局などの関係機関との連携が不可欠であり、情報共有の仕組みを整備し、個人情報保護に十分配慮しながら、スムーズな情報伝達を確立することが重要です。
V.届出書の様式と手続き
転入届、転出届などの届出書の様式と規格は法定されていませんが、市町村が適切な様式を整備する必要があるとされています。特に、付記転出届による住基ネットを通じた転出証明書情報の送信について説明されています。また、届出に際しての虚偽の申告に対する罰則についても言及されています。
1. 届出書の様式と規格 法定されていない柔軟性
転入届、転出届などの届出書の様式と規格は法律で定められていません。そのため、各市町村が独自の届出書用紙を用意することが適切です。ただし、郵便等による届出も想定されるため、所定の届出書以外の書式による届出も受理する必要がある点に注意が必要です。市町村は、住民の利便性を考慮し、簡明で平易な様式にするよう工夫することが推奨されています。 特に、令第24条の2で定める事項が付記された転出届(付記転出届)については、住基ネットを通じて転出証明書情報を送信できるため、手続きの効率化に繋がる重要な届出書です。同一世帯の全部または一部が同時に転出する場合で、住民基本台帳カードの交付を受けている者があるときは、付記転出届を利用することで、住基ネットを用いた迅速な情報伝達が可能になります。ただし、付記転出届を提出した場合は、転入届の際に住民基本台帳カードの提示が必要となる点に留意する必要があります。
2. 届出書の審査と確認事項 転入届の審査における注意点
届出書の審査にあたっては、いくつかの点に注意が必要です。国外から転入した者や、やむを得ない理由で転出証明書を提出できない者については、戸籍と照合したり、他市町村に本籍を有する者については戸籍に記載または記録されている事項について照会するなどして事実を確認の上、住民票を作成または記載します。 国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者の資格に関する附記がされた転入届を受理する際には、「転入をした年月日」と転出証明書に記載された「転出の予定年月日」の連続性を確認し、その間に傷病等についての保険給付などに関する国民健康保険や後期高齢者医療に関する事務の処理に支障がないように注意深く審査を行う必要があります。 医療保険制度や公的年金への加入状況についても、届出書に記載させたり、他の方法で確認するなどの対応が適切です。 届出書への記載事項、手続き、および審査基準は、法令に基づき、正確かつ適切に行われる必要があります。虚偽の届出や届出不履行に対する罰則についても、関係法令に基づき厳格に運用されることになります。
VI.複数国籍世帯への対応と移行措置
複数国籍世帯、特に外国人住民と日本人との混合世帯への対応について、仮住民票からの移行措置に関する手続きが詳細に説明されています。改正法附則に基づく届出期限や、住民票記載事項の修正手続き、罰則についても明確に示されています。外国人登録証明書の取扱いについても、在留カード又は特別永住者証明書とみなして扱うことなどが規定されています。
1. 届出書の様式と規格 法定様式なし 市町村の柔軟な対応
住民異動届出書の様式と規格は法令で定められていません。そのため、各市町村において、独自の届出書用紙を用意することが適当です。ただし、転出届については、郵便等による届出も想定されるため、所定の様式以外の書式による届出も受理する必要があります。 市町村は、住民の利便性を考慮した簡明で平易な様式を工夫することが望ましいとされています。特に、付記転出届は、同一世帯の一部または全部が同時に転出する場合、住民基本台帳カード交付済みの世帯員がいる場合に利用され、住基ネットを通じて転出証明書情報を送信できます。この手続きは、転出証明書発行の手間を省き、行政効率の向上に貢献します。しかし、付記転出届を提出した場合は、転入届の際に住民基本台帳カードの提示が必要になる点に注意が必要です。
2. 転入届の審査 転出証明書提出困難事例への対応
転入届の審査においては、国外からの転入者や、やむを得ない理由で転出証明書を提出できない者の場合、戸籍との照合や本籍地への照会などを行い、事実関係を確認する必要があります。 国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者資格に関する附記のある転入届では、「転入をした年月日」と転出証明書の「転出の予定年月日」にずれがないか確認し、保険給付等の処理に支障がないように留意する必要があります。 また、医療保険制度や公的年金への加入状況についても、届出書への記載や別途の確認などを行い、正確な情報を把握するよう努める必要があります。 審査にあたっては、戸籍、他市町村の住民基本台帳、社会保険庁または都道府県における記録などを参照し、事実関係を丁寧に確認することが求められます。
3. 届出不備時の対応と罰則規定
届出に基づき住民票の記載等を行うべき場合に届出がないときは、届出義務者に対して届出を催告する必要があります。催告後も届出がない場合は、当該事実を確認し、職権で住民票に記載を行い、「○○につき職権記載」等と事由および記載を行った年月日を記入します。 この手続きは、転入届だけでなく、住民票の記載、消除、氏名、出生年月日、性別、住所、住民票コードの修正などにも適用されます。 なお、虚偽の届出や正当な理由のない届出不履行に対しては、5万円以下の過料が科せられる可能性があるため、届出に関する正確性と責任の重要性を改めて認識する必要があります。 市町村は、これらの規定を周知徹底し、円滑な住民異動事務の処理に努めることが求められます。
