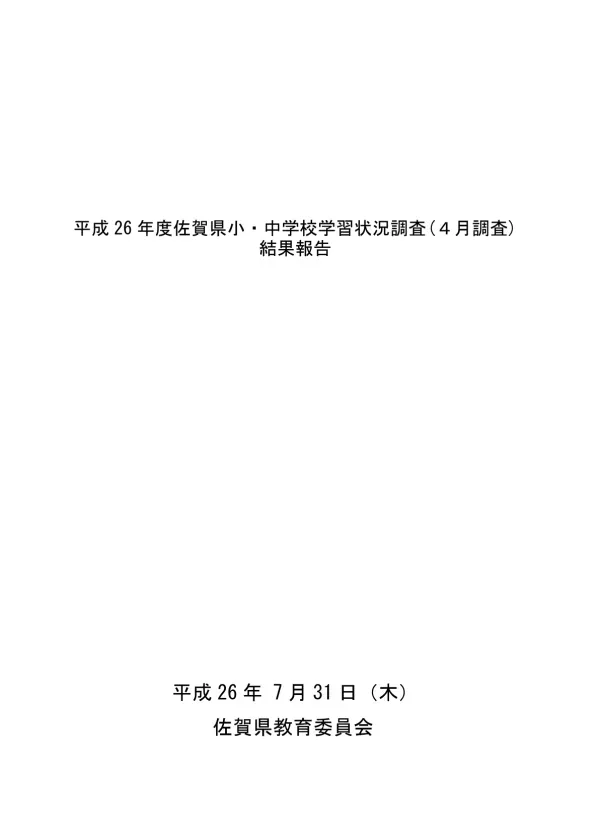
佐賀県学力調査:到達基準と正答率分析
文書情報
| 学校 | 佐賀県教育委員会 |
| 専攻 | 教育学 |
| 出版年 | 2014 |
| 場所 | 佐賀市 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 8.26 MB |
概要
I.小学校 中学校における国語の到達基準と課題
本調査は、小学校と中学校の児童生徒を対象とした学力調査の結果に基づいています。到達基準として設定された「期待正答率」を用い、修正エーベル法に基づいて分析されました。国語においては、漢字の読み書きは概ね良好でしたが、「読むこと」と「書くこと」を関連付けた複合的な問題、特に自分の考えを根拠を明確にして書く力に課題が見られました。具体的な課題としては、文脈理解、登場人物の心情把握、意見の交換と文章の書き直しなどが挙げられます。特に、小学6年生では伝統的な言語文化に関する背景知識の不足が読み取り能力の低さに影響している可能性が示唆されました。中学校では、引用を意識した学習活動の不足が指摘されています。
1. 到達基準と期待正答率の設定
本調査では、児童生徒に求められる正答率の目標値を「到達基準」として設定し、修正エーベル法に基づき、小問毎に「期待正答率」を設定、集約することで経年比較を可能にしています。「期待正答率」は問題の特性や難易度に応じて判断され、「十分達成」「おおむね達成」の2つの基準値が設けられています。各小問は関連性(基礎的・基本的、発展的・応用的)と困難度で分類され、分析が行われています。この到達基準と期待正答率の設定が、国語力に関する分析の基盤となっています。
2. 漢字の読み書きと複合的な言語運用能力
小中学校ともに、文脈に即した漢字の読み書きは概ね良好な結果を示しました。しかしながら、「読むこと」と「書くこと」を関連付けて考えをまとめるなど、複合的な操作を伴う問題への解答には課題が見られました。特に、文章や資料を読んだ後に、条件に応じて自分の考えを書くこと、すなわち、読解力と記述力を統合した複合的な言語運用能力に課題が顕在化しています。この点は、今後の指導において重点的に取り組むべき重要なポイントです。
3. 小中学校における国語の具体的な課題
「おおむね達成」の基準を下回った主な設問として、「話す・聞く」における話し合いと意見検討、「書く」「読む」「言語知識・理解・技能」における根拠を明確にした意見記述(標語の解釈や表現効果の記述など)が挙げられます。「十分達成」を上回った設問は、「話す・聞く」における資料活用による効果的な話術、「書く」における心情描写の工夫、「読む」における登場人物の心情や行動の理解など、比較的基礎的な読解・記述能力に関連するものでした。これらの結果から、高度な読解力や記述力、特に自分の考えを論理的に表現する能力の育成が喫緊の課題であることが分かります。
4. 小学6年生と中学生の課題 詳細分析
小学6年生では、伝統的な言語文化に関する内容の文章において、生徒が読み取るための背景知識が不足している傾向が指摘されました。また、条件付きの読み取り問題(要旨把握、必要情報抽出など)の正答率が低かったことから、条件に合わせた情報処理能力の育成が重要であることが示唆されます。中学生においては、話し合いにおける自分の意見表明や、引用を意識した学習活動の不足が課題として挙げられています。さらに、説明的な文章において、中心となる事柄の把握や事実と意見の区別など、文章構造の理解を深めるための指導の必要性が示されています。
5. 国語力向上のための指導改善策
国語力向上のためには、「条件」に合わせた記述力の育成、読解力との関連付け、根拠に基づいた意見交換、目的や意図に応じた表現方法の学習、文学作品における登場人物の心情や場面の理解、そして日々の漢字学習の継続が重要です。 中学生においては、討論会や様々な場面での意見表明、メモを活用した思考整理、引用の意識付け、同一作者・テーマの作品比較など、多様な学習活動を取り入れることが効果的です。 これらの指導改善策を通じて、児童生徒の複合的な言語運用能力の向上を目指していく必要があります。
II.算数 数学における正答率と課題分析
算数・数学では、「数と計算」、「数と式」の基礎的な問題は正答率が高かったものの、記述式問題、特に数学的表現を用いた理由説明に課題が見られました。中学校では関数の領域(比例・反比例、表・式・グラフの関連付け)、小学校では図を基にした式作成に課題が顕著でした。具体的な課題としては、分数を含む一元一次方程式の解法、具体的な事象における数量関係の把握と方程式作成、扇形の面積と中心角の関係理解などが挙げられます。また、日常事象の数理的把握の苦手意識や、問題の複雑化による理解度の低下も指摘されています。立式における言葉の式や数直線の活用、計算結果と問題場面の比較による演算決定の振り返り指導の必要性が示唆されました。
1. 基礎的な計算問題と記述式問題における正答率の差
「数と計算」「数と式」領域の基礎的な四則演算問題は、小中学校ともに高い正答率を示し、ドリル学習などの効果が認められました。しかし、記述式問題、特に数学的な表現を用いて理由を説明する問題では、小中学校ともに課題が見られました。これは、単なる計算能力だけでなく、数学的な思考力や表現力を問う問題への対応力が不足していることを示唆しています。特に、数学的根拠に基づいた説明能力の育成が重要であることが分かります。
2. 中学校における関数領域と小学校における図形問題の課題
中学校では、関数(比例・反比例、式・グラフ・表の関連付け)の理解に課題が見られました。これは、異なる表現形式を関連付けて理解する能力の不足を示しています。一方、小学校では、図形を基に式を作ることに課題が見られ、図形と数量の関係を理解し、式に表現する能力の育成が重要であることが示唆されます。これらの結果は、数学的な概念の理解と、それを様々な表現形式で扱う能力を同時に育成する必要があることを示しています。
3. 具体的な課題 方程式 図形 数量関係の理解
「おおむね達成」を下回った主な設問は、「数と式」領域における分数を含む一元一次方程式の解法、具体的な事象における数量関係の把握と方程式の作成、「図形」領域における扇形の面積と中心角の比例関係の理解などでした。これらの問題は、数学的な概念の理解に加え、問題文から必要な情報を選び出し、適切な式や解法を選択する能力を必要とします。これらの能力の不足が、正答率の低さに繋がっていると考えられます。
4. 日常事象の数理的把握と問題解決能力の育成
多くの児童生徒が、日常の事象を数理的に捉えることに苦手意識を持っていることが分かりました。そのため、日常生活や他教科の学習場面において、事象から規則性を読み取ったり、数量関係を的確に解釈し表現する活動を取り入れることが必要です。また、問題が複雑になると理解が難しくなる傾向が見られることから、既習内容の活用や問題解決に必要な情報の選択・整理能力の育成が重要です。 さらに、小数や分数を含む問題に対しても正しく立式できるよう、言葉の式や数直線などを活用した指導が求められます。
5. 指導改善のための具体的方策
算数・数学の指導改善のためには、数学的表現を用いた理由説明の充実、関数領域における表、式、グラフの関連付け学習、図形問題における図と数量の関係理解、日常事象の数理的把握、問題解決に必要な情報の選択・整理能力の育成、そして、小数や分数を含む問題への対応力強化が不可欠です。 さらに、誤答分析に基づいたきめ細やかな指導、作図指導における手順の意味理解、言葉と図の関連付け、問題場面の整理など、多角的な指導方法の改善が求められます。
III.学習環境と児童生徒の意識
学習環境面では、電子黒板等のICT機器の活用による授業内容の理解度向上への効果が示唆されていますが、その効果的な活用方法については、小学校と中学校で意識の差が見られました。家庭環境面では、テレビゲームの時間増加と教科平均正答率の低下の相関関係が確認され、また携帯電話やスマートフォンの利用時間の長さと正答率の低下の相関も示唆されました。学校生活では、「学校での生活は楽しい」「友達と会うのは楽しい」と回答する児童生徒の割合が減少傾向にあり、学級経営の重要性が強調されています。授業における目標提示や学級内での話し合い活動は多くの学校で行われていますが、地域差も見られました。家庭学習の促進においても、学校と家庭の連携強化の必要性が示唆されています。
1. ICT機器の活用と授業理解度
電子黒板や大型テレビなどのICT機器の活用は、授業内容の理解度向上に繋がっている可能性が示唆されています。しかし、その活用方法や授業への導入方法については、小中学校で意識の差が見られ、中学校では職員間の共通理解が不足している傾向がありました。小学校では8割以上の教師が共通理解を図っているのに対し、中学校では6割程度にとどまっていることから、中学校におけるICT機器の効果的な活用方法に関する指導の充実が課題として挙げられます。家庭学習の充実という観点からも、更なる改善が必要だと考えられます。
2. 家庭学習時間と学習成果の関係
家庭生活に関する調査では、テレビやビデオ・DVDの視聴時間は減少傾向にあるものの、テレビゲームやインターネット、メールの利用時間は増加傾向にあります。そして、これらの利用時間の長さと教科平均正答率の低下の間に相関関係が見られました。つまり、学習時間確保の妨げとなる可能性がある余暇活動の時間を適切に管理する必要があることを示唆しています。特に、携帯電話やスマートフォンの利用時間の長さと正答率の低下の相関関係は、早急な学校での対応策の検討が必要であることを示しています。
3. 学校生活における児童生徒の意識
「学校での生活は楽しい」「友達と会うのは楽しい」という質問への肯定的な回答が減少傾向にあることから、児童生徒の学校生活への満足度が低下している可能性が示唆されます。これは、友達関係の希薄化を示しており、友達同士の認め合い、励まし合いを促進することで、安心して学習に取り組める環境づくりが重要となります。学級経営を基盤とした授業づくりが、学習意欲向上に大きく影響することを示しています。また、「授業の内容がよく分かる」「将来役に立つ」という回答も減少傾向にあり、児童生徒の学習への有用感を持たせる授業改善の必要性が示唆されています。
4. 家庭学習の現状と学校 家庭間の連携
宿題の出し方については、小中学校ともに具体的な指導が行われているものの、宿題の内容やその質については、職員間での共通理解に違いが見られました。また、児童生徒の宿題に対する意識も低下傾向にあることから、家庭学習の充実のためには、学校と家庭間の連携強化が重要です。具体的には、家庭学習を促す働きかけや、宿題の内容について職員間の共通理解を図ることで、家庭学習の定着を図る必要があります。テレビやゲーム等の利用時間管理と家庭学習時間の確保についても、家庭との連携を強化する必要があります。
5. 授業改善に向けた取り組み状況
授業の冒頭で目標を示す活動は、小学校では全ての学校、中学校でも高い割合で行われています。学級やグループでの話し合い活動も小学校では広く行われていますが、中学校では地域差が見られました。児童生徒が自分で調べたことを文章に書く指導についても、地域差が見られました。国語、算数・数学において保護者への家庭学習促進の働きかけは、小学校では地域差が少なく高い傾向にあり、中学校では藤津地域・東松浦地域が高い傾向が見られました。これらの結果から、授業における目標設定や話し合い活動は多くの学校で行われているものの、家庭学習への働きかけや、児童生徒の主体的な学習活動の促進については更なる工夫が必要であることがわかります。
