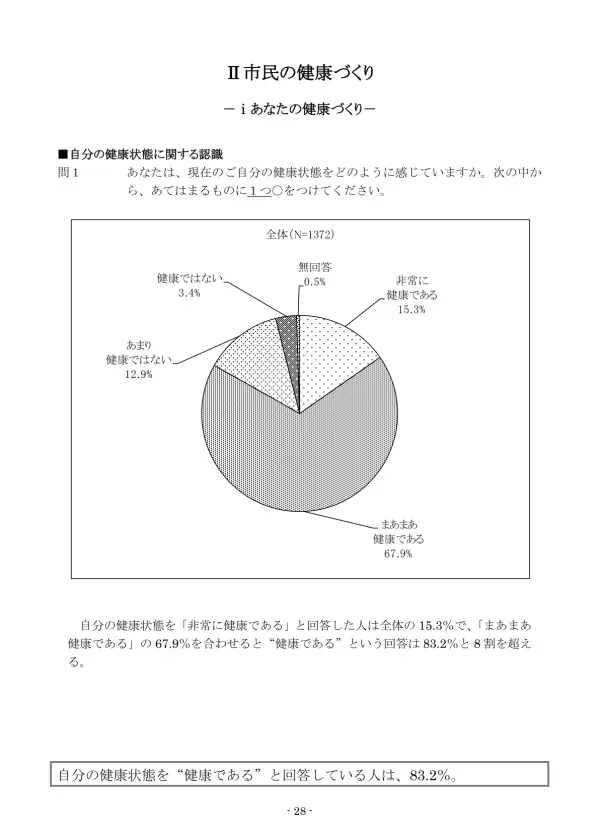
健康意識調査:市民の健康状態と取り組み
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 7.73 MB |
| 専攻 | 公衆衛生学、健康科学など |
| 文書タイプ | 調査報告書、研究報告書 |
概要
I.健康づくりのための取り組み Health Promotion Initiatives
本調査では、健康づくりにおける取り組みとして、「十分な睡眠と休養」(49.4%)、「栄養や食事への注意」(47.3%)が最も高い割合を占めていました。年代別に見ると、18~40歳代は「十分な睡眠と休養」、50歳代以上は「栄養や食事への注意」を重視する傾向が見られました。健康診断や運動、ストレス軽減も重要な要素として挙げられています。
1. 健康づくりのための主要な取り組み Main Health Promotion Initiatives
健康増進・維持のために最も多くの人が取り組んでいることは、「十分な睡眠と休養」(49.4%) でした。 次いで「栄養や食事に注意すること」(47.3%)、「ストレスをためないこと」(32.3%)、「運動すること」(29.9%)と続きます。これらの項目は、健康維持において非常に重要な要素であることが示唆されています。年代別に見ると、18歳~19歳、20歳代~40歳代では「十分な睡眠と休養」が最も重視されており、50歳代~70歳代以上では「栄養や食事に注意すること」が最も高い割合を占めていました。これは年齢とともに、睡眠の質や食事内容に対する意識の変化が反映されている可能性があります。その他、定期的な健康診断の受診、病気の早期受診・治療、適正体重の維持、健康知識の増進、禁煙、飲酒量の抑制なども、健康づくりのために意識されている項目として挙げられています。これらの結果から、健康的な生活習慣の重要性が改めて確認されました。
2. 健康に関する情報収集方法 Methods of Obtaining Health Information
健康づくりに関する情報の入手方法は、「テレビからの情報」(56.9%)が最も多く、次いで「インターネットからの情報」(26.4%)、「雑誌や本からの情報」(23.7%)、「新聞の記事」(22.0%)と続きます。これは、テレビやインターネットが、一般的にアクセスしやすい情報源であることを示しています。性別では、男女ともに「健康づくりや体力づくりのため」の情報収集が最も多い傾向にあり、女性が64.4%、男性が63.8%という僅かな差にとどまりました。年代別では、30歳代~70歳代以上は「健康づくりや体力づくりのため」の情報収集が最も多く、全体傾向と一致しています。しかし、20歳代では「ダイエットのため」の情報収集が最も多く、年齢層による健康への関心の違いが見て取れます。これらの結果から、健康情報へのアクセス方法や、健康に対する関心の多様性が示唆されています。
3. 健康診断の受診状況と結果への対応 Health Check up Status and Responses to Results
健康診断の受診状況は、「毎年受けている」(59.4%)が最も高く、次いで「過去に受けたことがある」(29.1%)となっています。性別では、男性は「正常ではない値があった」と回答した割合が高く(58.2%)、女性(46.7%)と比較して11.5ポイントの差がありました。年代別では、50歳代と60歳代で「正常ではない値があった」割合が5割を超えており、全体傾向と同様です。一方、40歳代と70歳代以上では、全体の傾向よりも低い数値となっています。健康診断の結果に対しては、「医療機関を受診した」(53.9%)が最も多く、次いで「食生活を見直した」(33.2%)、「医師や保健師等による保健指導を受けた」(26.0%)、「意識的に運動をするようになった」(17.4%)と続きます。これらの結果は、健康診断の結果を踏まえた適切な対応がなされている一方で、年齢や性別による健康への意識や行動の違いが示唆されています。
II.健康に関する情報入手源 Sources of Health Information
健康づくりに関する情報源は、「テレビ」(56.9%)、「インターネット」(26.4%)が主要な手段でした。性別・年代による大きな違いは見られませんでしたが、20歳代は「ダイエット」目的の情報収集が多い傾向が見られました。
1. 主要な情報源と利用率 Primary Information Sources and Usage Rates
健康に関する情報入手源として、テレビが56.9%と最も高い利用率を示しました。これは、テレビが幅広い層にリーチし、健康情報番組なども多く放送されているためと考えられます。インターネットも26.4%と高い利用率を示しており、手軽に様々な情報にアクセスできる点が人気の理由でしょう。雑誌や本(23.7%)、新聞記事(22.0%)も一定数の利用が見られ、これら従来からの情報源も依然として重要であることが分かります。これらの結果から、健康に関する情報入手には、多様なメディアが利用されていることがわかります。特にテレビとインターネットの利用率の高さが目立ち、現代社会における情報収集手段の変化を反映していると言えるでしょう。今後、健康情報の発信においては、これらの主要メディアへのアプローチが重要になります。
2. 性別による情報収集目的の違い Differences in Information Gathering Purposes by Gender
性別による情報収集目的の違いでは、男女ともに「健康づくりや体力づくりのため」が最も高い割合を占めていました。女性が64.4%、男性が63.8%と僅差ではありますが、女性の方が若干高い数値となっています。このわずかな差は、女性が健康に関する情報に、より積極的な関心を示している可能性を示唆しています。しかし、この差は統計的有意差があるかどうかは明記されておらず、さらなる分析が必要です。この調査結果を基に、男女間の健康に関するニーズを的確に捉えた情報提供を行うことが重要になります。
3. 年代による情報収集目的の違い Differences in Information Gathering Purposes by Age
年代別に見ると、30歳代から70歳代以上では、「健康づくりや体力づくりのため」の情報収集が最も高い割合を占め、全体傾向と一致しています。これは、この年齢層が健康維持に高い関心を持っていることを示しています。しかし、20歳代では、「ダイエットのため」の情報収集が最も多いという結果が得られました。これは、20歳代が健康維持というよりも、容姿や体重管理といった美容に関する情報に強い関心を抱いていることを示唆しています。年齢層によって健康への関心の焦点が異なっているため、情報提供においては、各年代層のニーズに合わせた戦略が重要であることが分かります。年齢層に合わせたターゲティング広告や、各年代層に特化した情報発信を行うことが効果的と考えられます。
III.健診受診状況と取り組み Health Check up Status and Follow up Actions
健康診断の受診状況は、「毎年受診」(59.4%)が最も多く、「過去に受診経験あり」(29.1%)がそれに続きます。「異常値あり」と回答した人のうち、「医療機関を受診」した割合が53.9%と最も高く、食生活の見直しも重要な対応策として挙げられています。
1. 健診受診状況 頻度と年代別傾向 Health Check up Frequency and Age Specific Trends
健康診断の受診状況は、「毎年受けている」が59.4%と最も高く、次いで「過去に受けたことがある」が29.1%でした。これは、健康への関心の高まりと、定期的な健康管理の重要性の認識の高まりを示唆しています。性別では、男性は「正常ではない値があった」と回答した割合が58.2%と女性(46.7%)よりも高く、11.5ポイントの差がありました。これは、男性の方が健康上の問題を自覚している割合が高い、もしくは、健康診断で異常値が出やすい体質である可能性が考えられます。年代別では、50歳代と60歳代で「正常ではない値があった」割合が5割を超えており、年齢とともに健康問題への懸念が高まる傾向が見て取れます。一方で、40歳代と70歳代以上では、この割合が全体平均を下回っており、年齢層による健康への意識や行動に違いがあることが示唆されます。これらの結果は、健康診断の受診率向上のためには、年齢層や性別を考慮した啓発活動が必要であることを示しています。
2. 健診結果への対応 具体的な行動と割合 Responses to Health Check up Results Specific Actions and Percentages
健康診断の結果に対しては、「医療機関を受診した」が53.9%と最も多く、次いで「食生活を見直した」(33.2%)、「医師や保健師等による保健指導を受けた」(26.0%)、「意識的に運動をするようになった」(17.4%)と続きます。これは、健康診断の結果を踏まえて、具体的な行動変容が促されていることを示しています。特に、医療機関への受診率の高さが目立ち、健康問題に対して積極的な対応が取られていると言えるでしょう。一方で、「食生活を見直した」や「運動をするようになった」といった割合は、医療機関受診に比べて低く、健康問題への対応には、医療機関への受診だけでなく、生活習慣の見直しも重要な要素であることがわかります。これらの結果から、健康診断の結果を効果的に活用し、生活習慣病予防につなげるための支援体制の構築が重要であることが示唆されます。
3. 健診結果への対応 性別と年代別の傾向 Responses to Health Check up Results Gender and Age Specific Trends
健診結果への対応に関する性別・年代別の分析では、男女ともに「一度も受けたことがない」と回答した割合が高いことが分かりました。特に男性(51.6%)は女性(38.8%)に比べて12.8ポイント高くなっており、男性の方が健康診断の結果に対する対応が遅れている傾向にあることが示唆されます。年代別では、18歳~19歳、20歳代~60歳代では「一度も受けたことがない」が最も多く、70歳代以上では「過去に受けたことがある」が最も多いという結果でした。また、40歳代~70歳代以上では、「毎年受けている」割合が全体平均よりも高くなっています。これらのことから、年齢層や性別によって、健康診断の結果に対する意識や行動に大きな差があることが分かります。より効果的な健康増進を図るためには、年齢や性別といった要因を考慮した上で、適切な啓発活動や支援策を講じる必要があると言えるでしょう。
IV.がん検診受診状況と理由 Cancer Screening Status and Reasons
がん検診の受診率は、種類によって異なりますが、「職場の健診で受診できたから」が主要な理由です。一方で、受診していない理由として「面倒だから」が最も多く挙げられており、年代やがんの種類によって理由に違いが見られました。特に、大腸がん検診、胃がん検診、子宮がん検診、乳がん検診、肺がん検診に関するデータが詳細に示されています。
1. がん検診受診状況 きっかけと年代別傾向 Cancer Screening Status Reasons and Age Specific Trends
がん検診の受診状況に関する調査では、受診した人の主な理由として「職場の健診で受診できたから」が最も多く挙げられました。これは、職場の健康診断ががん検診へのアクセスを容易にしていることを示しています。具体的な数値は、大腸がん検診で39.2%、乳がん検診で29.5%、子宮がん検診で25.8%など、がんの種類によってばらつきが見られました。年代別では、20歳代~60歳代では「職場の健診で受診できたから」が主な理由であるのに対し、70歳代以上では「必要だと思っているから」が最も高い割合を示しました。このことから、年齢とともに、健康への意識が高まり、自発的に検診を受けようとする傾向が強まることが考えられます。 また、家族・知人からの勧めや無料クーポンなども、検診受診のきっかけとして一定数の割合を占めており、これらの要因も効果的に活用することで受診率向上に繋がる可能性が示唆されます。
2. がん検診受診状況 性別による違い Cancer Screening Status Gender Differences
がん検診受診のきっかけに関する性別の比較では、男女ともに「職場の健診で受診できたから」が最も高い割合を占めていました。しかし、男性の方が女性よりもこの理由を挙げる割合が高く、特に肺がん検診では男性が56.7%、女性が34.7%と大きな差が見られました。この差は、男性の方が職場の健康診断制度を利用しやすい環境にあること、または、女性は他の理由(例えば、婦人科検診への抵抗感など)で受診率が低い可能性が考えられます。これらの性差を考慮した上で、より効果的ながん検診の普及策を検討していく必要があります。例えば、女性向けのがん検診プログラムの充実や、よりアクセスしやすい検診体制の構築などが考えられます。
3. がん検診未受診理由 主な要因と年代別傾向 Reasons for Not Undergoing Cancer Screening Main Factors and Age Specific Trends
がん検診を受診していない理由として、「面倒だから」が最も多く挙げられました。これは、がん検診への受診が、時間的な制約や心理的な負担を伴うことを示唆しています。具体的な数値は、大腸がん検診で23.4%、子宮がん検診で26.3%など、がんの種類によって若干のばらつきが見られました。年代別では、18歳~19歳は「検診を受ける場所や申し込み方法がわからないから」、20歳代は「検診を受けに行く時間がないから」、30歳代は「検診料金が高いから」、40歳代は「検診を受けに行く時間がないから」、70歳以上は「既に医療機関を受診しているから」がそれぞれ主要な理由として挙げられています。これらの結果から、年齢層によってがん検診へのアクセスや受診を妨げる要因が異なることが分かります。年齢層に応じた対策、例えば、若年層への情報提供の充実や、高齢者への個別支援、検診費用の軽減策などが、受診率向上に繋がる可能性が考えられます。
V.受動喫煙防止への意識と対策 Awareness and Measures for Passive Smoking Prevention
受動喫煙に関する意識調査では、「喫煙場所以外では吸わない」(79.4%)、「子どもや妊産婦、病気の人が居る場所では吸わない」(74.8%)が上位にランクインしました。受動喫煙防止の対策を希望する施設・場所としては「医療機関」(65.9%)、「保育園、高齢者施設など社会福祉施設」(59.3%)が挙げられています。
1. 受動喫煙防止への意識 具体的な行動と割合 Awareness of Passive Smoking Prevention Specific Actions and Percentages
受動喫煙防止への意識調査では、「喫煙場所以外では吸わない」が79.4%と最も高く、次いで「子どもや妊産婦、病気の人がいる場所では吸わない」が74.8%、「混雑している場所では吸わない」が69.2%、「公共的な場所では吸わない」が59.0%という結果でした。これらの結果から、多くの人が受動喫煙の害を理解し、一定の配慮をしていることがわかります。特に、「喫煙場所以外では吸わない」という意識の高さが目立ち、マナー遵守の意識が浸透しつつあると言えるでしょう。性別では、女性(82.0%)の方が男性(76.4%)よりも「喫煙場所以外では吸わない」という回答が多く、5.6ポイントの差がありました。年代別では、18歳~19歳と30歳~70歳以上では全体傾向と同様に「喫煙場所以外では吸わない」が最も多く、18歳~19歳では「子どもや妊産婦、病気の人がいる場所では吸わない」も同率一位でした。20歳代では、「子どもや妊産婦、病気の人がいる場所では吸わない」が最も高い割合を示していました。これらの結果から、年齢層や性別によって受動喫煙防止への意識に違いがあることが示唆されています。
2. 受動喫煙防止対策の希望場所 優先順位と年代別傾向 Desired Locations for Passive Smoking Prevention Measures Priorities and Age Specific Trends
受動喫煙防止対策を推進してほしい場所として、「医療機関」が65.9%と最も多く、次いで「保育園、高齢者施設など社会福祉施設」が59.3%という結果になりました。これは、これらの施設が特に、受動喫煙の影響を受けやすい人々が利用する場所であるためと考えられます。性別による差はほとんど見られず、男女ともに「医療機関」への対策を強く望んでいることが分かりました。年代別では、全年代層で「医療機関」が最も多く、60歳代~70歳代以上では7割を超えています。このことから、受動喫煙防止対策は、年齢層を問わず、広く社会的な合意が形成されていると考えられます。特に、医療機関や社会福祉施設においては、受動喫煙防止対策の徹底が強く求められていることが示唆されています。これらの施設における対策強化と、その啓発活動の重要性が改めて示されました。
VI.歯 口腔の健康 Dental and Oral Health
歯の健康に関する意識調査では、「歯磨きを1日2回以上」(65.4%)、「歯間ブラシも使用している」(30.0%)が高く、定期的な歯科健診の受診率は19.2%でした。歯科健診を受けなかった理由として「歯や歯ぐきに問題がないから」が最も多く挙げられています。かかりつけ歯科医の受診理由としては「痛み等症状や気になることがあった時」が77.9%と圧倒的に多いです。
1. 歯の健康に関する意識と習慣 Awareness and Habits Regarding Dental Health
歯の健康に関する意識調査では、「歯磨きを1日2回以上行っている」と回答した人が65.4%と最も多く、口腔ケアの重要性が認識されていることがわかります。さらに、「歯間ブラシも使用している」と回答した人は30.0%、「定期的に歯科健診を受けている」人は19.2%、「歯石は年1回以上取っている」人は18.9%という結果でした。これらのことから、歯磨きの習慣は比較的定着しているものの、歯科健診の受診率や専門家による歯石除去の頻度は、まだ十分とは言えない状況がうかがえます。より積極的な口腔ケアの推進と、歯科健診の受診促進のための啓発活動が重要であると考えられます。特に、定期的な歯科健診の受診率向上に向けた対策を講じることで、口腔内の疾患を早期発見し、適切な治療につなげることが重要です。
2. 歯科健診未受診理由 主な要因と対策 Reasons for Not Undergoing Dental Check ups Main Factors and Countermeasures
歯科健診を受診しなかった理由として、「歯や歯ぐきに問題がないから」が32.7%と最も多く、次いで「忙しい、時間がないから」(29.2%)、「面倒だから」(21.9%)、「痛くなってから治療することで十分だから」(21.0%)という結果でした。「歯や歯ぐきに問題がないから」という理由が多いことは、健康な状態を維持しているというポジティブな側面と、問題がない限り受診する必要性を感じていないというネガティブな側面の両方を示しています。一方、「忙しい、時間がない」や「面倒」といった理由も無視できません。これらの要因に対処するためには、時間や場所の制約が少ない検診システムの構築や、受診への心理的なハードルを下げるような啓発活動が効果的であると考えられます。また、「痛くなってから治療」という考え方の改善のため、定期検診の重要性を啓発していくことが重要です。
3. かかりつけ歯科医の受診理由 定期受診の現状と課題 Reasons for Visiting a Regular Dentist Current Status of Regular Check ups and Challenges
かかりつけ歯科医を受診する理由として、「痛み等症状や気になることがあった時」が77.9%と圧倒的に多く、これは、多くの場合、痛みなどの自覚症状が出てから初めて歯科医院を受診するという現状を示しています。一方、「症状の有無に関係なく定期的に行く」と回答した人は23.0%、「歯科医院から歯科健診受診等の通知があった時」と回答した人は14.9%でした。これらのことから、定期的な歯科健診の受診率は依然として低い状況にあることがわかります。症状が出てから受診するのではなく、定期的な健診による早期発見・早期治療の重要性を啓発し、予防意識の向上を図ることが重要です。また、かかりつけ歯科医を持つことのメリットを周知し、定期的な受診を促すための対策を講じる必要があります。例えば、歯科医院からの定期的な連絡や、予防歯科に関する情報提供などが考えられます。
VII.体格とBMI Body Composition and BMI
身長・体重、BMIに関するデータが提示され、「18.5以上25未満(ふつう)」が最も多いと報告されています。男性の肥満割合(BMI25以上)は女性のそれを上回っています。
1. BMI分布 全体と性別 年代別の傾向 BMI Distribution Overall and Gender Age Specific Trends
今回の調査では、BMIに基づいた体格の分析が行われました。全体として、最も多かったのは「18.5以上25未満(ふつう)」の範囲で、これは健康的なBMI範囲に該当します。性別による比較では、男女ともにこの範囲に属する人が最も多いという結果でしたが、「25以上(肥満)」の割合は男性(26.4%)が女性(14.9%)を大きく上回っており、11.5ポイントもの差がありました。この結果は、男性の肥満率が女性よりも高いという、既知の傾向と一致しています。年代別では、全年代層において「18.5以上25未満(ふつう)」の割合が最も高く、特に18歳~19歳、30歳代~40歳代、70歳以上では全体平均をやや上回る結果となりました。これらの結果から、BMIの分布は性別や年齢によって異なることがわかります。特に、男性の肥満率の高さと、若年層および高齢層における健康的なBMI範囲への属する割合の高さは、注目すべき点です。
