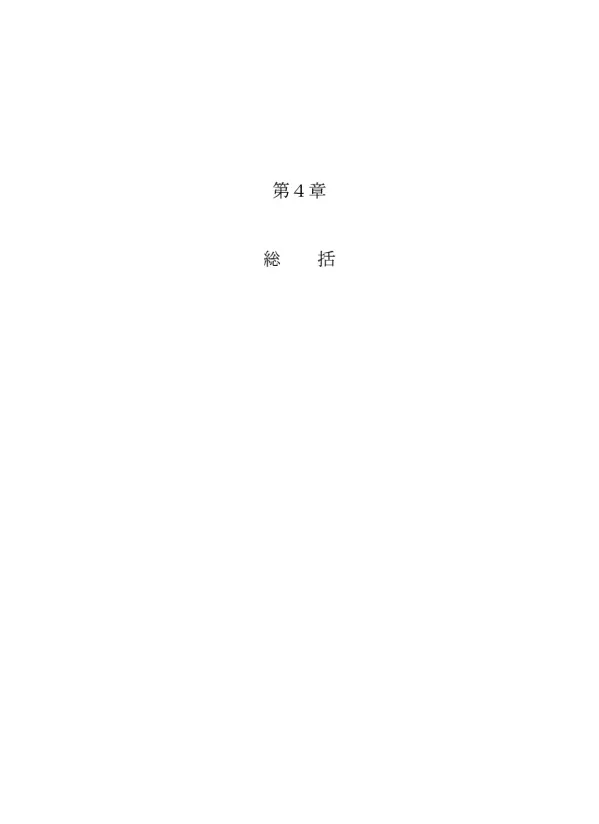
先史琉球の生業と交易:国家形成への道
文書情報
| 著者 | Kinoshita Naoko |
| 学校 | 熊本大学 (University of Kumamoto) |
| 専攻 | 考古学 (Archaeology), 人類学 (Anthropology), 動物学 (Zoology) |
| 文書タイプ | 共同研究報告書 (Joint Research Report) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.02 MB |
概要
I. 7世紀の奄美 沖縄諸島の生業と交易 用見崎遺跡とナガラ原東貝塚の調査成果
本報告書は、1995~1997年の奄美大島用見崎遺跡と1998年の伊江島ナガラ原東貝塚の発掘調査を基に、6~7世紀の奄美・沖縄諸島の生業と交易、そして国家形成を多角的に分析したものです。考古学、人類学、動物学の専門家7名による共同研究であり、層位・問題意識の共有、現場での試料採取など綿密な調査を実施しました。用見崎遺跡は7世紀頃、ナガラ原東貝塚は6世紀頃のものと推定されています。貝塚からは、ヤコウガイを始めとする多様な貝類、植物遺体、脊椎動物遺体などが大量に出土し、当時の自然環境と生活様式を復元する上で重要な手がかりを提供しています。特にナガラ原東貝塚からは炭化イネとムギが発見され、この時代の農耕の存在を示唆しています。この発見は、琉球列島の農耕の始まりに関する議論に大きな影響を与えます。
1. 用見崎遺跡とナガラ原東貝塚 遺跡の概要と年代
本研究の中心となるのは、奄美大島に位置する用見崎遺跡と、伊江島にあるナガラ原東貝塚です。用見崎遺跡は、海運路に面した立地から、ヤコウガイ(Lunatica) の集中的な採集が行われていた可能性が高いと推測されています。一方、ナガラ原東貝塚は、比較的短期間に形成された貝塚であり、闊唇鳳凰螺(Tricornis latissimus)などの貝類が九州方面へ供給されていた人々の食料残渣が堆積したと考えられています。出土遺物や貝符などの型式学的検討から、用見崎遺跡は7世紀頃、ナガラ原東貝塚は6世紀頃のものと推定されています。これらの遺跡の調査成果は、6~7世紀の奄美と沖縄諸島の状況を理解するための重要な手がかりとなります。特に、6世紀における奄美諸島と大和朝廷を結ぶ貝殻交易への奄美人の関与の可能性、南九州との交流による兼久式土器(平底土器)の誕生、対照的に南九州の影響を受けなかった沖縄諸島における在地土器(尖底土器)の継続的な使用などが示唆されています。伊江島ナガラ原東貝塚からはイネとムギの炭化種子も発見され、これらの穀物が交易品として持ち込まれた可能性や、穀物生産者による季節移動の可能性などが示唆されていますが、その起源については今後の研究が待たれます。
2. 6 7世紀の奄美 沖縄諸島の自然環境と生活 植物 動物 貝類遺体からみた復元
高宮広町、樋泉岳二、黒住耐二の研究では、植物遺体、脊椎動物遺体、貝類遺体の分析を通じて、6~7世紀の奄美・沖縄諸島の自然環境と生活様式が復元されています。黒住耐二は、陸産微小貝類の分析から用見崎遺跡周辺が開放的な環境であったこと、ナガラ原東貝塚付近では海岸林の広がりが時間とともに変化していたことを示しました。陸産微小貝類は、花粉やプラントオパールでは分析が困難な砂丘地における古環境復元に有効な指標であると指摘されています。また、マイマイやマルタニシなどの貝類が、それぞれ畑地や水田の存在を示す指標となり得るものの、ナガラ原東貝塚周辺ではそれらの存在を示す証拠は乏しく、6~7世紀において生産経済への移行を示す証拠は微小貝類からは得られなかったと結論づけています。樋泉岳二は脊椎動物遺体の分析から、3種類の漁法パターン(選択性の低いサンゴ礁魚類一括漁獲、選択性の高い大型魚類を狙った漁獲、沿岸浅瀬における回遊性小型魚の季節漁)を明らかにし、用見崎遺跡とナガラ原東貝塚における漁業活動の特質を比較検討しています。貝錘は選択性の低い漁法に関連した道具である可能性も指摘されています。さらに、貝塚時代の奄美・沖縄諸島は照葉樹林に覆われていたが、グスク時代以降に森林伐採が進んだこと、貝塚時代の沿岸環境は現在とほぼ変わらなかったことなども明らかになっています。脊椎動物遺体分析からは、貝塚時代後期後半にはブタが大陸から持ち込まれた可能性が高いことも示唆されています。
3. 6 7世紀の奄美 沖縄諸島の居住形態
杉井健による居住形態に関する研究では、沖縄諸島、先島諸島、奄美諸島の新石器時代から近世までの住居193例(沖縄諸島・先島諸島)と40例(奄美諸島)を分析し、地域間の比較が行われています。新石器時代では竪穴式住居が主流であり、奄美諸島と沖縄諸島に大きな違いは見られないものの、竪穴式住居が確認されない先島諸島とは対照的です。沖縄諸島における住居形態の大きな変化は、竪穴式住居が主体であった貝塚時代後期から、掘立柱建物が主流となったグスク時代への移行に見られます。また、火処(炉や竈)の変遷についても検討されており、沖縄諸島の炉は近世まで一貫して炉であったこと、天井のない焚口をもつ竈が近世に成立したことなどが指摘されています。喜界島ハンタ遺跡出土のグスク時代以降の竈状施設は、九州本島との関連を探る上で重要な手がかりとなると考えられています。さらに、火処と密接に関連する土器の底部形状についても言及されており、奄美諸島の甕が南九州の影響を受けているのに対し、沖縄諸島ではその影響が少なく、独自の生活様式が維持されていたことが指摘されています。これらの分析から、非ヤマト的地域における国家形成に関する比較研究の展望が示唆されています。
II.農耕の始まりと社会経済構造
甲元真之による「琉球列島農耕のはじまり」では、那覇市那崎原、久米島ヤジャーガマ遺跡に加え、ナガラ原東貝塚出土の植物遺体と土器編年を分析し、グスク時代以前の農耕を裏付ける証拠を示しています。穀物の炭化状態から、何らかの処理方法が用いられていた可能性が示唆されました。樋泉岳二は「脊椎動物遺体群からみた奄美・沖縄の環境と生活」で、3種類の漁法パターンを提唱。貝錘などの漁具も分析されています。黒住耐二は「貝類遺体からみた奄美・沖縄の自然環境と生活」において、陸産微小貝類分析から遺跡周辺の環境を復元し、ナガラ原東貝塚付近に水田や畑地が存在した可能性は低いと結論づけています。杉井健は居住形態の変化に着目し、竪穴式住居から掘立柱建物への移行を分析、奄美と沖縄の地域差を明らかにしています。
1. 琉球列島における農耕の始まり 考古学的証拠と論点
甲元真之による研究では、考古学的な視点から琉球列島の農耕開始時期を検討しています。考古学において農耕を論じるためには、栽培過程における具体的な行為と地上の痕跡の関連性を検証する必要性を強調し、遺構内からの種子の分析や種子自体の年代測定が重要であると述べています。グスク時代以前の農耕の存在を示す証拠として、那覇市那崎原、久米島ヤジャーガマ、伊江島ナガラ原東の3遺跡を挙げ、これらの遺跡から穀物が伴って出土している点を指摘しています。特にナガラ原東貝塚からは炭化状態の穀物が発見されており、これは縄文時代の堅果類の処理方法の民俗例などを参考に、火を使用した何らかの処理方法と関連している可能性が示唆されています。さらに、最近の後期土器編年案に基づき、ナガラ原東貝塚出土の穀物と共伴する土器の底部形状、突帯の特徴、調整の特徴などを分析し、それらの土器がアカジャンガー式土器というよりも、次のフェンサ下層式土器に近い時期のものであることを示唆しています。また、ナガラ原東貝塚における14C年代の層位的逆転を指摘し、現在の層位は撹乱を受けているか、層位認定が誤っている可能性を指摘しています。このため、14C年代値は共伴する尖底土器の年代とみなすべきだと主張しています。 甲元は、那崎原、ヤジャーガマ遺跡とナガラ原東貝塚の穀物出土状況を比較検討し、グスク時代以前に農耕が確立していたと結論づけています。
2. 自然環境と生活 植物 貝類 脊椎動物遺体分析による復元
高宮広町、樋泉岳二、黒住耐二による研究では、植物遺体、貝類遺体、脊椎動物遺体の分析から、6~7世紀の奄美・沖縄諸島の自然環境と生活様式が復元されています。黒住耐二は陸産微小貝類分析から、用見崎遺跡周辺は当時開けた環境であり、ナガラ原東貝塚周辺では海岸林の開け方が時期によって変化していたことを明らかにしました。陸産微小貝類は、砂丘など花粉やプラントオパール分析が困難な場所での古環境復元に有効な指標であるとされています。 また、マイマイやマルタニシが畑地、水田の存在を示す指標となり得るものの、ナガラ原東貝塚周辺ではそのような証拠は乏しく、6~7世紀に生産経済に移行する必然性は見られないと結論づけています。一方、ナガラ原東貝塚におけるミドリアオリ(Pinctada fucata)の集中投棄状況から、遺構面は台風などの撹乱を受けていないことが示唆されています。両遺跡からは潮間帯岩礁の中・小型二枚貝やアマオブネ類が多く出土しており、その利用目的については今後の検討が必要とされています。樋泉岳二は、脊椎動物遺体分析から3種類の漁法パターン(選択性の低いサンゴ礁魚類一括漁獲、選択性の高い大型魚類を狙った漁獲、沿岸浅瀬における回遊性小型魚の季節漁)を提案し、用見崎遺跡とナガラ原東貝塚の漁労活動の特性を明らかにしています。貝錘は、選択性の低い漁法に関連した道具であった可能性が示唆されています。さらに、貝塚時代の奄美・沖縄諸島は照葉樹林に覆われていたものの、グスク時代以降の森林伐採により森林が縮小した可能性も示唆されています。
3. 貝塚時代からグスク時代への変化 動物資源利用と家畜化
樋泉岳二と黒住耐二の研究は、貝塚時代からグスク時代への変化を、動物資源の利用という視点から考察しています。樋泉岳二は、貝塚時代の脊椎動物資源利用は、前期から後期まで漁労とイノシシ狩りを中心としたパターンが継続していたと指摘しています。貝塚時代後期後半には、大陸からブタが持ち込まれた可能性が高いとされています。黒住耐二は、貝類遺体の分析結果から、グスク時代における貝類利用の変化(大型のサンゴ礁産貝類から小型の内湾・干潟産貝類への変化)について論じています。この変化は、環境変化よりも社会的な要因による可能性が高いと結論づけています。ナガラ原東貝塚で発見された炭化イネとムギは、交易による入手だけでなく、穀物を生産する人々の季節的移動の可能性も示唆しており、農耕の開始と国家形成の関連性については、更なる研究が必要であると指摘されています。 特に、那崎原段階以降の人口動態や農耕社会の成立過程の解明が今後の課題として挙げられています。
III.貝交易と国家形成 9 13世紀の交易ネットワーク
木下は「貝交易と国家形成」で、9~13世紀の貝殻交易、特にヤコウガイの交易に着目し、琉球列島の国家形成との関連を論じています。用見崎遺跡出土の開元通宝とヤコウガイは、唐との交易を示唆する重要な証拠です。ヤコウガイは中国、そして大和朝廷でも需要が高く、博多の商人による積極的な交易活動があったと推測されます。徳之島の須恵器窯の成立も、この交易ネットワークと深く関わっている可能性が高いです。新里亮人による「滑石製石鍋の基礎的研究」では、九州・沖縄における滑石製石鍋の分布を詳細に分析。11~13世紀の琉球全域での消費と、石鍋模倣土器の出現が、社会経済構造の変化を反映していることを指摘しています。
1. 貝殻交易の動向と琉球圏の形成 9 13世紀の交易ネットワーク
木下による研究では、9世紀から13世紀にかけての貝殻交易の動向を分析し、グスク時代を特徴づける琉球圏の形成過程と琉球列島の国家形成との関連性を明らかにしようとしています。この研究は、1997年の用見崎遺跡発掘で、多数のヤコウガイと共に開元通宝が出土したことを契機としています。木下は、7世紀以降中国唐王室で需要が高まった螺鈿細工の材料であるヤコウガイを、9世紀頃までは琉球列島が供給していた可能性を指摘し、その交易ネットワークを詳細に分析しています。その論考の前提として、9~10世紀に大和で唐様式の螺鈿が継承され、11世紀に発展、12世紀に成熟、13世紀に貝素材がヤコウガイからアワビなどに変化したという螺鈿工芸史の成果が用いられています。9~11世紀、大和における螺鈿工芸の発展と宋や新羅への輸出需要の高まりが、博多の商人を琉球列島へと向かわせる原動力となり、ヤコウガイ獲得のための積極的な南下を促したと推測されています。11世紀に徳之島に開業した須恵器窯は、博多商人によるヤコウガイとの交換品生産を目的として設立された可能性が示唆されています。須恵器、滑石製石鍋、陶磁器などを携えた商人がヤコウガイを求めて先島諸島まで到達し、交易品が琉球列島全域に広がった結果、共通した畑作中心の農耕や社会階層化が進展したと論じています。13世紀後半、ヤコウガイ交易の終焉後、琉球王国は東アジアとの独自の交易を始めるだけの経済力を有するようになっていたと結論付けています。
2. 滑石製石鍋の基礎的研究 流通と地域社会への影響
新里亮人による「滑石製石鍋の基礎的研究」では、九州・沖縄地方から出土した888例の滑石製石鍋の分布を詳細な一覧表と分布図を用いて示し、今後の研究のための基礎資料を提供しています。11世紀から13世紀にかけて、滑石製石鍋が琉球列島全域で消費され、同時に石鍋模倣土器が出現した事実が注目されています。この時代を境に、沖縄諸島では貝塚時代、先島諸島では無土器時代がそれぞれ終焉し、両地域で農耕社会が成立したことから、石鍋が時代変化の重要な指標となることを強調しています。石鍋は、把手付の早期型と鍔付の後期型に大別され、その分布から琉球列島への石鍋は博多など北部九州からの直接搬入の可能性が高いとされています。一方、沖縄諸島の石鍋模倣土器は、把手付早期型を模倣しており、後期型の鍔付石鍋の影響を受けていない点が注目されています。この選択性については、朝岡康二の「釜は竈と、鍋は囲炉裏と密接に結びつく」という指摘を引用し、火処の形態との関連性が予測されています。これらの分析を通じて、石鍋の流通と地域社会への影響が考察されています。
3. 交易と国家形成 農耕との関連性と今後の課題
ナガラ原東貝塚からの炭化イネ・ムギの発見は重要な成果ですが、国家形成との関連性については、まだ十分な説明がなされていないと指摘されています。一方、銭貨、滑石製石鍋、貝殻交易に関する分析は、国家形成との関連性が比較的明確に示されています。しかし、これらの交易に関する研究は9世紀以降に集中しており、生業に関する議論との間に時間的なずれが生じています。報告書は、琉球の国家形成が農耕と交易の両輪によって実現したとしながらも、両者の関連性を十分に統合できていない点を課題として挙げています。これは、プロジェクトリーダーである木下の責任であると述べられています。また、土壌サンプルの分析が完了しておらず、今後の発掘調査方法の改善も必要であるとされています。考古学発掘の一回性と破壊性を踏まえ、より質の高い最終報告書の作成を目指した研究であると締めくくられています。
