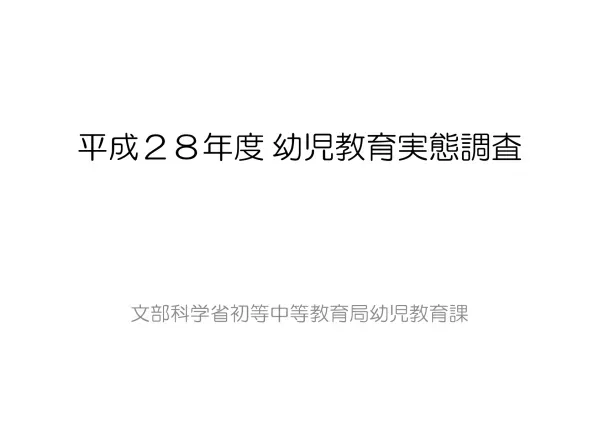
全国幼児教育施設設置状況調査
文書情報
| 専攻 | 幼児教育 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 776.98 KB |
概要
I. 市町村における公私立幼稚園 保育所 幼保連携型認定こども園の設置状況
本調査では、1,377市町村(79.1%)において、幼稚園、保育所、または幼保連携型認定こども園が設置されていることが明らかになりました。これは、日本の幼児教育における多様な施設形態の存在を示しています。都道府県別では、幼保連携型認定こども園の行政窓口は「首長部局」が最も多い割合を占めています。
1.1 市町村における幼稚園 保育所 幼保連携型認定こども園の設置状況
この調査では、平成28年5月1日時点における市町村の幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園の設置状況を分析しています。その結果、1377市町村(全体の79.1%)において、幼稚園、保育所、または幼保連携型認定こども園のいずれか、もしくは全てが設置されていることが明らかになりました。これは、日本の幼児教育を取り巻く環境において、多様な施設形態が存在していることを示す重要なデータです。この多様性は、地域特性や保護者のニーズに応じた柔軟な対応を可能にしている一方で、施設間の連携や教育の質の均一化といった課題も孕んでいると考えられます。今後の幼児教育政策において、この多様性を活かしつつ、質の高い教育を提供するための施策の検討が必要となるでしょう。調査は、各市町村における幼児教育施設の整備状況を把握することを目的としており、地域格差やニーズの多様性などを分析するための基礎データとして活用されます。今後、より詳細な分析を行うことで、地域ごとの課題の特定や、効果的な幼児教育施策の立案に繋げることが期待されます。
1.2 都道府県における幼保連携型認定こども園の行政窓口
都道府県レベルでの幼保連携型認定こども園の行政窓口の設置状況についても調査が行われました。その結果、最も多い割合を占めたのは「首長部局」で、41都道府県(87.2%)が該当します。「教育委員会」が窓口となっているのは3都道府県(6.4%)、「首長部局及び教育委員会」が窓口となっているのは同じく3都道府県(6.4%)でした。この結果から、幼保連携型認定こども園の行政運営において、首長部局が中心的な役割を担っていることが分かります。しかし、教育委員会が関与しているケースもあることから、都道府県によって行政運営の体制に違いがある可能性も示唆されます。これらの違いが、幼保連携型認定こども園の運営や幼児教育政策の展開にどのような影響を与えているのか、更なる分析が必要でしょう。また、窓口の明確化や連携強化が、幼保連携型認定こども園の円滑な運営に不可欠であると考えられます。
II. 公私立幼稚園 幼保連携型認定こども園の行政窓口
都道府県レベルでは、幼稚園の行政窓口は「公立は教育委員会、私立は首長部局」が83.0%を占め、市町村レベルでは、公立・私立両方の幼保連携型認定こども園が設置されている市町村においては、「公立・私立とも教育委員会」が最も多い割合を示しました。これは、幼児教育に関する行政運営の現状を表しています。
2.1 都道府県における幼稚園 幼保連携型認定こども園の行政窓口
都道府県レベルでは、幼稚園と幼保連携型認定こども園の行政窓口の担当部署について調査が行われました。その結果、幼稚園については、「公立は教育委員会、私立は首長部局」が39都道府県(83.0%)と最も多い割合を占めていました。これは、公立幼稚園と私立幼稚園の運営形態の違いを反映していると考えられます。公立幼稚園は教育委員会、私立幼稚園は首長部局という分担は、日本の幼児教育行政における伝統的な役割分担を示していると言えるでしょう。しかし、この割合が100%ではないことから、その他の形態の行政窓口が存在している可能性も示唆されており、都道府県によって行政運営の仕組みに違いがあることが分かります。この違いが、幼稚園の運営や幼児教育政策に与える影響については、さらなる分析が必要となります。特に、私立幼稚園の運営支援や、公立・私立を問わず幼児教育の質の向上を図るための施策を検討する上で、この行政窓口の現状を踏まえた対応が求められます。
2.2 市町村における幼保連携型認定こども園の行政窓口
市町村レベルでは、公立・私立の幼保連携型認定こども園が両方設置されている市町村と、公立のみ設置されている市町村で、行政窓口の状況が異なっていました。公立・私立両方が設置されている市町村では、「公立・私立とも教育委員会」が65市町村(72.2%)と最も多く、教育委員会が中心的な役割を担っていることが分かります。一方、公立のみ設置されている市町村では、「教育委員会」(44市町村、43.1%)と「首長部局」(45市町村、44.1%)がほぼ同数の割合を示しており、行政窓口の担当部署に明確な傾向は見られませんでした。この違いは、市町村の規模や組織体制、あるいは幼保連携型認定こども園の設置状況など、様々な要因が関係している可能性があります。それぞれの状況に応じた適切な行政運営のあり方について、更なる検討が必要となるでしょう。また、市町村における行政窓口の明確化によって、園の運営支援や幼児教育政策の円滑な推進に貢献できる可能性があります。
III. 幼児教育に関する政策プログラムの策定状況
都道府県の80.9%、幼稚園又は幼保連携型認定こども園が設置されている市町村の25.5%で、幼児教育に関する政策プログラムが策定済みです。人口規模別に見ると、大規模市町村での策定率が高い傾向が見られました。これは、幼児教育への地域的な取り組みの差を示唆しています。
3.1 都道府県における幼児教育に関する政策プログラムの策定状況
この調査では、都道府県レベルでの幼児教育に関する政策プログラムの策定状況について分析しています。調査結果によると、38都道府県(80.9%)で政策プログラムが策定済みであることが分かりました。これは、都道府県が幼児教育の推進に積極的に取り組んでいることを示す重要な指標と言えます。都道府県レベルでの高い策定率は、幼児教育の重要性が広く認識され、地域全体で質の高い幼児教育の提供体制を構築しようとする動きが活発であることを示唆しています。しかしながら、全ての都道府県で策定されているわけではないことから、地域間での幼児教育政策の推進状況にばらつきがあることも考えられます。今後、策定されていない都道府県において、どのような課題が存在するのか、また、既に策定済みの都道府県においては、政策プログラムの実効性をどのように高めていくのかといった点について、更なる検討が必要となります。この調査結果を基に、幼児教育の質の向上を目指した効果的な政策立案や、地域間格差の是正に向けた取り組みが期待されます。
3.2 市町村における幼児教育に関する政策プログラムの策定状況
市町村レベルでの幼児教育に関する政策プログラムの策定状況についても調査が行われました。幼稚園または幼保連携型認定こども園のいずれか、もしくは両方が設置されている市町村を対象に調査した結果、356市町村(25.5%)で政策プログラムが策定済みであると回答がありました。これは、都道府県レベルと比較して低い数値となっており、市町村レベルでは、幼児教育に関する政策プログラムの策定が必ずしも進んでいない現状が示唆されました。この低い策定率には、市町村の規模や財政状況、あるいは行政の優先順位など、様々な要因が影響していると考えられます。地域の実情に合わせた柔軟な対応が必要となる一方、幼児教育の重要性を改めて認識し、市町村レベルでの政策プログラムの策定を促進するための施策が求められます。特に、小規模な市町村においては、財政的な支援や専門家の育成など、より具体的な支援体制の構築が必要となるでしょう。この調査結果を踏まえ、幼児教育の均等化を図るための政策的取り組みが今後の課題となります。
IV. 幼児教育アドバイザー 幼児教育センターの設置状況
幼児教育センターは、都道府県では11都府県(23.4%)、市町村では29市町村(1.7%)に設置されています。特に人口5万人以上の市町村では設置率が4.2%と高くなっています。幼児教育の支援体制整備の現状を示すデータです。
4.1 幼児教育センターの設置状況 都道府県
この調査では、都道府県における幼児教育センターの設置状況について分析しています。調査結果によると、11都道府県(23.4%)で幼児教育センターが既に設置されていることが明らかになりました。幼児教育センターは、幼稚園教諭、保育士、保育教諭に対する研修機会の提供や、幼児教育に関する研究成果の普及・啓発、各園からの教育相談などを行う地域の拠点として重要な役割を担っています。11都道府県での設置は、これらの機能の重要性が認識され、地域レベルでの幼児教育の質向上に向けた取り組みが進んでいることを示唆しています。しかしながら、設置率は23.4%にとどまっており、多くの都道府県ではまだ設置されていない、もしくは設置に向けた準備段階にあることが分かります。幼児教育の質を均一的に向上させるためには、全国的に幼児教育センターの設置を進める必要があると言えるでしょう。今後、幼児教育センターの設置促進に向けた政策的支援や、既存のセンターの機能強化が課題となります。特に、地方部など、地理的な制約のある地域においては、効果的な支援策の検討が必要となるでしょう。
4.2 幼児教育センターの設置状況 市町村
市町村レベルでの幼児教育センターの設置状況についても調査が行われました。その結果、29市町村(1.7%)で幼児教育センターが設置されていることが明らかになりました。人口規模別にみると、人口規模5万人以上の市町村では4.2%が幼児教育センターを設置しており、人口規模が大きい市町村ほど設置率が高い傾向が見られました。このことから、市町村レベルでの幼児教育センターの設置は、人口規模や財政力などの要因に影響を受けている可能性が示唆されます。幼児教育センターの設置は、地域における幼児教育の質向上に貢献する重要な要素である一方、設置率が低いことから、多くの市町村では、まだ専門的な支援体制が整っていない現状が示されています。今後、特に小規模な市町村においては、財政的な支援や人材育成、あるいは複数の市町村で共同運営を行うなどの工夫が必要となるでしょう。また、幼児教育センターの機能を代替するような地域連携体制の構築なども検討課題となります。
V. 幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有状況
幼稚園の園長、教頭、教諭の82.0%が幼稚園教諭免許状と保育士資格を併有しています。これは、幼児教育従事者の資格保有状況を表しています。
5.1 幼稚園教諭免許状と保育士資格の併有状況
本調査では、幼稚園の園長、教頭、教諭の資格保有状況として、幼稚園教諭免許状(普通免許状)と保育士資格の併有状況を分析しています。調査の結果、全体で82.0%の園長、教頭、教諭が両方の資格を有していることが分かりました。この高い割合は、幼稚園教諭と保育士の役割が近年ますます近接し、両方の専門性を有することが求められる傾向にあることを示唆しています。これは、幼保連携型認定こども園の増加や、保育の質の向上に対する社会的な要請の高まりといった背景が考えられます。また、この結果から、多くの幼稚園教諭が保育の専門知識やスキルを有していることが分かります。このことは、幼稚園教育の質の向上に大きく貢献していると考えられますが、一方で、資格取得のための負担や、両方の資格を有することによる業務負担の増加といった課題も存在する可能性があります。今後の幼児教育のあり方について、資格の取得支援や、教員の働き方改革といった観点からの検討が必要となるでしょう。
VI. 市町村における幼小接続の状況
市町村の幼小接続状況は、「ステップ2」(年数回の交流はあるが、接続を見通した教育課程編成は行っていない)が57.6%(1,002市町村)と最も多く、連携から接続への移行段階にあることがわかります。この調査は、幼児教育と小学校教育の円滑な接続の現状を示しています。
VII. 幼稚園教員 保育教諭への研修の実施状況
公立幼稚園教員に対する研修実施率は高く、多くの団体で公立幼稚園以外の施設も参加していました。特に新規採用教員研修及び10年経験者研修以外の研修では、91.9%(57団体)の団体で公立幼稚園以外の施設の参加がありました。これは、幼児教育における継続的な人材育成の取り組みを表しています。
7.1 幼稚園教員対象研修への公立幼稚園以外施設の参加状況
平成27年度の実績に基づき、都道府県・指定都市が行う幼稚園教員対象の研修への、公立幼稚園以外の施設の参加状況を分析しています。公立幼稚園教諭に対する新規採用教員研修は67団体中63団体(84.1%)が実施しており、そのうち53団体(84.1%)で公立幼稚園以外の施設が参加していました。10年経験者研修も67団体中54団体(約80.6%)が実施し、31団体(57.4%)で公立幼稚園以外の施設が参加していました。新規採用教員研修及び10年経験者研修以外の教員研修は67団体中62団体(91.9%)が実施し、そのうち57団体(91.9%)で公立幼稚園以外の施設が参加していました。園長研修は67団体中50団体(78.0%)が実施し、39団体(78.0%)で公立幼稚園以外の施設が参加していました。これらのデータから、都道府県・指定都市レベルの研修には、公立幼稚園以外の施設(私立幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所など)が積極的に参加していることが分かります。このことは、幼児教育関係施設間の連携強化や、教員間の相互理解促進に研修が貢献していることを示唆しています。ただし、参加率が100%ではないことから、全ての施設が研修に参加できているとは限らない点に留意が必要です。今後、より多くの施設が参加できるよう、研修内容や実施方法の改善、参加促進策の検討が重要となります。
7.2 公立幼保連携型認定こども園の保育教諭対象研修への公立幼保連携型認定こども園以外施設の参加状況
公立幼保連携型認定こども園の保育教諭を対象とした研修についても、同様の分析が行われています。新規採用教員研修は67団体中24団体(約35.8%)が実施し、18団体(75.0%)で公立幼保連携型認定こども園以外の施設が参加していました。10年経験者研修は67団体中11団体(約16.4%)が実施し、8団体(72.7%)で公立幼保連携型認定こども園以外の施設が参加していました。新規採用教員研修及び10年経験者研修以外の研修は67団体中27団体(約40.3%)が実施し、全てで公立幼保連携型認定こども園以外の施設が参加していました。園長研修は67団体中15団体(約22.4%)が実施し、13団体(86.7%)で公立幼保連携型認定こども園以外の施設が参加していました。幼稚園教員と比較して、公立幼保連携型認定こども園の保育教諭を対象とした研修の実施率は低い傾向にありますが、参加している研修においては、他の施設からの参加率が高いことが特徴です。これは、幼保連携型認定こども園が、幼稚園や保育所と連携して運営されているケースが多いことを反映していると考えられます。今後の課題としては、研修の実施率向上と、より効果的な研修内容の検討が挙げられます。
7.3 私立施設の教員研修参加に関する実施要項
新規採用教員研修または10年経験者研修を実施したと回答した都道府県・指定都市のうち、実施要項において私立幼保連携型認定こども園の保育教諭の参加を認めているのは、新規採用教員研修で36団体(55.4%)、10年経験者研修で28団体(50.9%)でした。同様に、私立幼稚園教員の参加を認めているのは、新規採用教員研修で38団体(58.5%)、10年経験者研修で30団体(54.5%)でした。このデータは、公立の研修に私立の教員が参加できるかどうか、という点に着目した分析です。多くの都道府県・指定都市で私立施設の教員の研修参加が認められているものの、参加率は100%に達していないことが分かります。研修への参加を促進するためには、私立施設の事情を考慮した研修内容の工夫や、参加しやすい体制の構築が重要になります。例えば、時間や場所の柔軟性、費用負担の軽減といった点について、更なる検討が必要でしょう。また、私立施設の教員が研修に参加することで、公立・私立間の連携強化や、幼児教育の質向上に繋がる可能性があります。
VIII. 幼稚園における保育所 幼保連携型認定こども園及び小学校との連携状況
調査回答園の80.3%が保育所、幼保連携型認定こども園、または小学校との幼児・児童交流を実施、73.6%が教師同士の交流を実施していました。公立幼稚園での連携率が高い傾向が見られました。このデータは、幼児教育における園と園、園と学校の連携状況を示しています。平成27年度の実績では、小学校との教育課程編成に関する連携を行った幼稚園は全体の59.5%でした。
8.1 幼児と児童の交流状況
平成27年度の実績に基づき、幼稚園における保育所、幼保連携型認定こども園、小学校との連携状況について、幼児と児童の交流状況を分析しています。調査対象となった幼稚園全体で、保育所、幼保連携型認定こども園、または小学校のいずれか、もしくは複数との交流を行った幼稚園は80.3%でした。公立幼稚園では98.0%と非常に高い割合を示していますが、私立幼稚園では70.1%にとどまっています。この違いは、公立と私立の幼稚園における教育方針や、地域との連携体制の違いなどが影響している可能性があります。幼児と児童の交流は、異年齢間での相互作用や、小学校へのスムーズな移行を支援する上で重要な要素です。公立幼稚園において交流が盛んな背景には、地域との密接な連携や、教育委員会による積極的な推進などが考えられます。一方、私立幼稚園では、独自の教育プログラムや運営体制が、他園との連携に影響を与えている可能性も考えられます。今後、私立幼稚園における交流促進のための支援策や、園と地域との連携強化を図るための施策の検討が必要となります。
8.2 教師同士 教師と保育士の交流状況
幼稚園における保育所、幼保連携型認定こども園、小学校との連携状況について、教師同士、または教師と保育士の交流状況を分析しています。調査の結果、保育所、幼保連携型認定こども園、または小学校のいずれか、もしくは複数との交流を行った幼稚園は全体の73.6%でした。この結果から、多くの幼稚園が、他施設との人的な交流を通して連携を図っていることが分かります。公立幼稚園では92.1%と高い割合を示している一方、私立幼稚園では62.9%にとどまっています。この差は、公立幼稚園が地域全体を視野に入れた連携を重視していること、また、教育委員会などによる積極的な支援体制が構築されていることが関係していると考えられます。他施設との連携は、幼児教育の質向上や、園児の育成にとって重要な要素です。人的な交流を通して得られる情報や、共有できる経験は、教育内容の改善や、より効果的な指導方法の確立に繋がる可能性があります。今後、私立幼稚園における連携促進のための支援策や、連携体制の強化が求められます。
8.3 教育課程の編成に関する小学校との連携状況
幼稚園における小学校との連携状況について、教育課程の編成に関する連携状況を分析しています。平成28年度の教育課程編成にあたり、小学校との情報交換などの連携を行った幼稚園は全体の59.5%でした。この数値は、幼児と児童の交流や教師間の交流と比較して低い割合となっています。小学校との教育課程の連携は、幼小接続を円滑に進める上で非常に重要です。幼稚園と小学校で教育内容を共有したり、学習内容を接続したりすることで、園児の小学校へのスムーズな移行を支援できると考えられます。連携率が低い背景には、小学校との連携体制の未整備、あるいは、具体的な連携方法の確立が進んでいないといった課題が考えられます。今後の課題としては、幼稚園と小学校間の連携強化のための支援策の充実が挙げられます。例えば、連携のための研修プログラムの提供や、連携事例の共有などが有効な手段となるでしょう。また、地域全体を巻き込んだ連携体制の構築も重要です。
IX. 幼保連携型認定こども園における小学校との連携状況
幼保連携型認定こども園の80.9%が小学校との児童交流を実施しており、教育課程編成において小学校との情報交換等の連携を行った園は全体の58.5%でした。これは、幼保連携型認定こども園における小学校との連携の現状を表しています。
9.1 幼保連携型認定こども園と小学校の児童交流状況
平成27年度の実績に基づき、幼保連携型認定こども園における小学校との連携状況を分析しています。まず、小学校の児童と交流を行った幼保連携型認定こども園の割合は、全体の80.9%でした。この高い数値は、幼保連携型認定こども園が、小学校との連携を重視していることを示しています。公立と私立の施設を比較すると、公立では62.3%、私立では57.6%となっており、大きな差は見られません。この児童交流は、小学校への円滑な移行を支援する上で重要な役割を果たしていると考えられます。具体的には、小学校の授業参観や、合同での行事、体験入学などを通して、小学校生活への準備を促したり、小学校教員と保育教諭間の連携を強化したりする効果が期待できます。幼保連携型認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を統合した施設であるため、小学校との連携を強化することで、幼児期から小学校への接続をよりスムーズにすることが期待されます。この高い交流率は、幼保連携型認定こども園が、小学校との連携を重視した運営を行っていることを示す重要な指標です。
9.2 幼保連携型認定こども園と小学校の教師間の交流状況
幼保連携型認定こども園と小学校の連携状況として、教師間の交流についても調査が行われています。具体的な交流方法としては、指導案の共同作成、カリキュラムに関する協議、地域連絡協議会への参加、小学校の授業参観や行事への参加、小学校教諭による園への来園と意見交換などが挙げられています。これらの交流を通して、幼保連携型認定こども園と小学校間の相互理解が深まり、教育課程の接続に関する協議が行われていることが分かります。具体例として、小学校1年生と年長児の交流活動や体験入学などが紹介されています。これらの取り組みは、小学校入学への不安軽減や、スムーズな学校生活への移行を支援する上で効果的であると考えられます。また、地域連絡協議会への参加や、小学校教諭の園への来園などを通して、行政や地域社会との連携も強化されていることが分かります。こうした多様な連携活動は、幼保連携型認定こども園が、地域社会全体を巻き込んだ幼児教育・保育を推進していることを示しています。
9.3 教育課程の編成に関する小学校との連携状況
幼保連携型認定こども園における小学校との連携状況として、教育課程の編成に関する連携状況についても分析しています。平成28年度の教育課程の編成にあたり、小学校との情報交換等の連携を行った幼保連携型認定こども園は、全体の58.5%でした。この数値は、児童との交流率(80.9%)と比較してやや低い割合となっています。教育課程の連携は、幼小接続を円滑に進めるために非常に重要です。園と小学校で教育内容を共有したり、学習内容を接続したりすることで、子どもたちの学びを継続的にサポートできると考えられます。連携率が低い背景には、小学校との連携体制の未整備、あるいは、具体的な連携方法の確立が進んでいないといった課題が考えられます。今後、幼保連携型認定こども園と小学校間の連携強化を図るための具体的な支援策の検討が必要となるでしょう。例えば、連携のための研修プログラムの提供や、連携事例の共有などが有効な手段となります。また、地域全体を巻き込んだ連携体制の構築も重要です。
X. 幼稚園における子育て支援活動の実施状況
平成27年度、調査回答園の94.7%が子育て支援活動を実施していました。(公立:95.9%、私立:94.0%)。 預かり保育を含む様々な支援活動が行われており、幼児教育を支える地域社会の取り組みが示されています。具体的な活動内容や実施日数、課題なども明らかになっています。
10.1 子育て支援活動 預かり保育を除く の実施率
平成27年度における幼稚園の子育て支援活動(預かり保育を除く)の実施状況について分析しています。調査対象となった幼稚園全体の94.7%で、子育て支援活動が実施されていることが分かりました。公立幼稚園では95.9%、私立幼稚園では94.0%と、公立・私立間で大きな差は見られません。この高い実施率は、幼稚園が地域社会における子育て支援の中核的な役割を担っていることを示しています。多くの幼稚園が、地域の子育て家庭を積極的に支援していることがうかがえます。この結果から、幼稚園が、教育機関としての役割だけでなく、地域社会への貢献という側面も担っていることが分かります。保育時間外の支援や、未就園児への対応など、幼稚園が地域社会に提供する多様なサービスは、子育て家庭にとって大きな支えとなっています。今後、子育て支援活動の更なる充実を図るためには、幼稚園への支援体制の強化や、活動内容の多様化、質の向上などの取り組みが重要となるでしょう。
10.2 子育て支援活動の内容別実施率 平均実施日数
子育て支援活動の内容別実施率と平均実施日数(1園当たり)について、複数の回答を許容する形で調査が行われています。調査対象となった全ての幼児とその保護者を対象とした事業の実施率と年間平均実施日数は、具体的な数値は本文中に記載されていませんが、グラフ等で示されているものと推察されます。この部分の詳細は、本文中の表やグラフを参照する必要があります。しかし、この調査から、幼稚園が様々な内容の子育て支援活動を実施していることが分かります。例えば、未就園児の保育や、保護者向けの相談会、子育てに関する情報の提供など、多様なニーズに対応した活動が行われていると推察されます。これらの活動は、地域社会の子育て環境の向上に大きく貢献していると考えられます。今後の課題としては、各活動内容の実施率や実施日数の詳細な分析を通じて、より効果的な支援策の検討や、課題の明確化を行うことが重要になります。特に、施設設備や人材、経費などの制約を考慮した上で、持続可能な支援体制の構築が求められます。
10.3 子育て支援活動の実施日数等 平成28年6月
平成28年6月1日から30日までの1ヶ月間における子育て支援事業(子育て情報の提供を除く)の実施状況について、1週間当たりの実施日数、1日当たりの実施時間、専任の担当者数などを調査しています。具体的な数値は本文中に記載されていませんが、グラフ等で示されているものと推察されます。この部分の詳細は、本文中の表やグラフを参照する必要があります。この調査から、子育て支援活動の実施状況に関する詳細なデータが得られていると考えられます。1ヶ月間の活動状況を分析することで、活動の頻度や時間、担当者配置などの実態を把握でき、より効果的な支援体制の構築に役立てることができます。また、活動の実施にあたり、施設設備、教職員の負担、経費確保、人材確保、教職員の能力不足、ボランティア確保などの課題も示唆されています。これらの課題を解決するためには、幼稚園への適切な支援体制の構築や、人材育成、経費の確保などの政策的な取り組みが重要となります。
XI. 幼稚園における預かり保育に関する実施状況
多くの幼稚園で預かり保育が実施されていますが、その実施状況や課題(施設設備、教職員の負担、経費確保、人材確保など)も明らかになっています。これは、預かり保育の現状と課題を示しています。
11.1 預かり保育実施状況 全体
平成28年6月1日現在、預かり保育を実施している幼稚園の状況について、平成27年度の実績を基に分析しています。調査の結果、8901園(公立2549園、私立6352園)で預かり保育が実施されていることが分かりました。これは、多くの幼稚園が、保護者の就労状況などに配慮し、保育時間外の預かり保育を提供していることを示しています。公立と私立の幼稚園を比較すると、私立幼稚園の方が預かり保育を実施している割合が高い傾向が見られます。これは、私立幼稚園において、保護者のニーズに応じた柔軟な運営がしやすい環境にあることなどが関係していると考えられます。預かり保育は、保護者の就労支援や、子育て家庭の負担軽減に大きく貢献するサービスです。しかしながら、預かり保育の提供体制には、施設設備の制約、教職員の負担増加、経費確保の困難さ、保育士などの確保の困難さ、教職員の能力不足、ボランティア確保の困難さといった課題も存在することが示唆されています。これらの課題への対応策を検討していくことが重要です。
11.2 預かり保育実施状況 長期休業日
平成28年6月1日現在、預かり保育を実施している幼稚園の、平成27年度における長期休業日の預かり保育の実施状況についても調査が行われています。具体的な数値は本文中に記載されていませんが、長期休業日における預かり保育の実施状況に関するデータが提示されていると推察されます。この部分の詳細は、本文中の表やグラフを参照する必要があります。長期休業期間中の預かり保育は、特に保護者にとって重要なサービスとなります。しかし、長期休業中は、通常時と比較して、教職員の確保や、保育内容の工夫などがより困難になる可能性があります。この調査では、長期休業日における預かり保育の実施状況を分析することで、その現状や課題を把握し、より効果的な支援策を検討するための基礎データを得ることが目的です。長期休業期間中の預かり保育の提供体制の充実には、教職員の勤務条件の改善、人材確保のための対策、経費の確保など、様々な課題への対応が必要です。この調査結果を基に、より質の高い預かり保育を提供するための施策が検討されることが期待されます。
