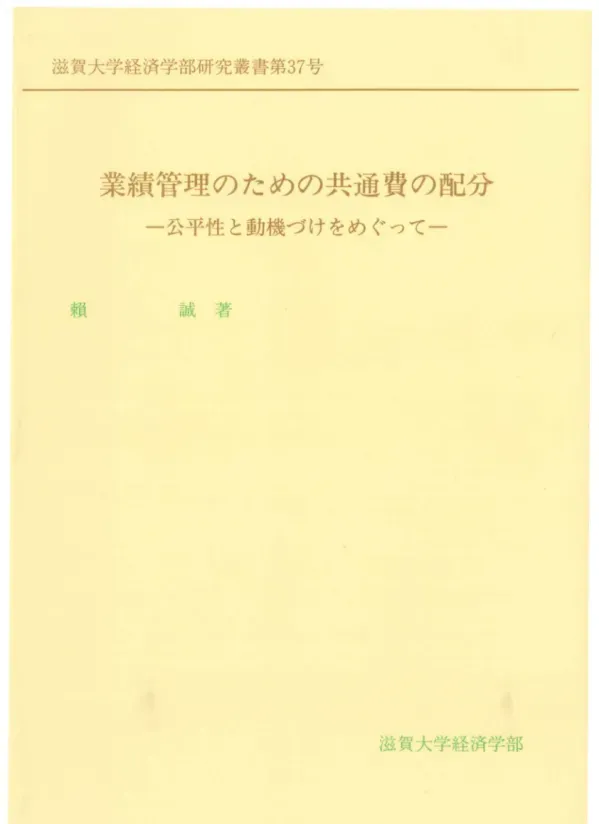
共通費配分と業績管理:公平性とモチベーション
文書情報
| 著者 | 頼 誠 |
| instructor/editor | 玉木輿乗 先生 |
| 学校 | 滋賀大学経済学部 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 研究叢書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 6.06 MB |
概要
I.共通費配賦の課題と解決策 回転寿司の例えから
本論文は、企業における共通費配賦(間接費配分)の問題を、回転寿司におけるビール代と寿司代の負担割合の例えを用いて解説しています。寿司代は直接費、ビール代は共通費として、その公平な配分が業績管理会計における重要な課題であると指摘。原価配分のあり方によって従業員のモチベーションや逆機能的行動が左右されることを示し、インセンティブとして機能する原価配分の重要性を強調しています。
1. 回転寿司の例えによる共通費配賦問題の導入
本論文は、企業における共通費配賦の問題点を分かりやすく説明するために、回転寿司における食事代の負担を例に挙げています。3人の人物(先輩と後輩2人)が回転寿司店で食事をし、寿司代とビール代をどのように負担するかが問題提起として提示されています。寿司代は各人が食べた量に応じて明確に負担できるため直接費または個別費と定義され、一方、複数人で共有したビール代は誰がどれだけ飲んだか不明なため、間接費または共通費として扱われます。この例えを通して、コストの発生原因が明確な場合とそうでない場合のコスト配分における違い、そして容易に合意が成立しない場合のコンフリクト発生を明確に示しています。この導入部は、読者に共通費配賦問題の本質を直感的に理解させるための巧妙な手法となっています。企業におけるコスト配分における課題と、その解決策を探るための出発点として、このシンプルな例えは非常に効果的です。特に、直接費と間接費、個別費と共通費といった会計用語を、日常生活に即した状況を用いて説明することで、専門知識がない読者にも理解しやすいよう配慮されている点が優れています。
2. 原価配分の重要性と岡野浩教授の 築像
製品の収益性や価格決定といった問題においては、正確なコスト計算(原価計算)が重要です。しかし、事業部の業績評価などにおいては、コストの公平な配分がより重要性を持ちます。なぜなら、公平な配分は逆機能的行動を抑制し、従業員のモチベーションを高揚させる効果があるからです。さらに、原価配分は組織メンバーの行動に影響を与え、現実を変えるための積極的なツールとして活用できる可能性も示唆されています。岡野浩教授は、原価配分をこのように積極的に活用する手法を「築像」と呼んでいます(岡野(1995))。例えば、製品の表面積や重量に応じて製造間接費を配賦することで、より小さな製品を設計・生産するインセンティブを与えるという具体的な例が示されています。この節では、原価計算という従来の会計的アプローチに加え、原価配分を戦略的な経営ツールとして捉える新しい視点を提示しています。特に、「築像」という概念の導入により、原価配分が単なるコスト計算を超えた、組織行動変容のための強力な手段となりうることを示唆している点が重要です。この考え方は、後述される共通費配賦問題の解決策を考える上で重要な視点となります。
II.原価配分をめぐる論争 肯定論と否定論
19世紀後半以降、企業の複雑化・大規模化に伴い、間接費の増加と原価配分の問題が顕在化しました。公平性や効率性を重視した様々な配分スキームが提案されてきましたが、Scapensらの研究(1991)は、複雑な配分方法よりも簡便な方法が実務では多く用いられることを示しています。エイジェンシーモデルは、共通費配賦がエイジェント(従業員)の行動をコントロールする手段として用いられる理由を説明しています。ABC分析(Activity-Based Costing)は正確な原価計算を目指しますが、全ての間接費を特定の活動に関係付けることは困難であるとされています。
1. 原価配分問題の発生背景 19世紀後半からの複雑化
Scapens et al.(1991)の研究によると、原価配分が重要な問題として認識されるようになったのは19世紀後半からとのことです。この時代、事業の複雑化と大規模化が進み、鉄道や工業の発展に伴う巨額な設備投資により間接費が急増しました。さらに、生産活動の複雑化は監視、プランニング、コントロール、調整といった管理活動の増加を招き、間接費の増大を加速させました。意思決定の効率化のため、公平性、協調性、効率性を兼ね備えた配分スキームの提案もなされましたが、Scapensらは、これらの高度なスキームは利害関係者間の共通理解や高度な数学的素養を必要とするため、実務においてはより簡便な方法が優先される傾向にあると指摘しています。例外として、水資源の共同設備費用配分におけるシャプレイ配分の適用や、米国における電話料金システムなどが挙げられています。これらの歴史的背景と、理論と実務の乖離が、原価配分問題の複雑さを浮き彫りにしています。特に、間接費の増加と、それを適切に配分するための高度な方法と簡便な方法のトレードオフは、現代の管理会計においても重要な課題となっています。
2. エイジェンシー モデルによる共通費配分の説明
Zimmerman(1979)は、理論的には共通費の配分に対する批判があるにもかかわらず、実務では広く行われている理由を、エイジェンシー・モデルを用いて説明しています。このモデルでは、プリンシパル(上司)がエイジェント(部下)に意思決定権限を委譲し、エイジェントがプリンシパルの意図した行動をとるように、結果に応じて報酬を与える関係を想定しています。モデルの重要な特徴として、プリンシパルがエイジェントの行動を完全に観察できないこと、そしてプリンシパルとエイジェントの間に選好のコンフリクトが存在することが挙げられます。エイジェントは自身の厚生を優先して、プリンシパルの利益を最大化しない意思決定を行う可能性があるため、共通費の配分方法を操作することでエイジェントの業績評価や報酬に影響を与え、逆機能的行動をコントロールしようとするのです。このモデルは、共通費配分が単なるコスト配分ではなく、従業員の行動を誘導するための重要な管理ツールとして機能していることを示唆しています。特に、情報非対称性と代理問題という経済学的な枠組みを用いることで、実務における共通費配分の根拠を理論的に説明しようとする試みは注目に値します。
3. ABC分析と簡便法の現状 理論と実務のギャップ
間接費の規模が無視できないほど大きくなったことから、恣意的な配分は深刻な問題となりました。そこで、正確な原価計算の技法としてABC分析(Activity-Based Costing)が登場しました。ABC分析は、得られた情報を基にプロセスの改善やコスト削減を目指すABM(Activity-Based Management)へと発展していきます。しかし、ABC分析ではすべての間接費を特定の活動に関係付けることはできないと仮定しており、営業単位間や営業とサービス職能間の協力関係を前提としているため、配分プロセスにおけるコンフリクトは考慮されていません。にもかかわらず、実務では簡便な原価配分方法が好まれる理由について、配分のベネフィットがコストを上回ると判断されているからだと説明されています。Zimmerman(1979)やDemski(1976, 1978)のエイジェンシー理論は、共通費の配分方法や報酬システムの変化が動機付け効果に与える影響を分析可能にしました。実務の問題点を探り、理論に基づいた改善策を実務に導入するアプローチも重要です。理論的に公平な配分方法の代替案を複数用意しておくことは、実務への適用可能性を高める上で大きな意義を持ちます。
III.相互満足的配分とパワーによる配分
公平な配分を実現するためのアプローチとして、相互満足的配分が注目されています。シャプレイ配分は、協力ゲームの理論に基づいた配分方法ですが、必ずしも相互の満足を保証するものではありません。そのため、交渉力や貢献度を反映したパワーによる配分も検討されています。しかし、小林哲夫教授は、交渉パワーの相違を考慮することが会計情報の公正性や中立性の要件に反しないかという問題点を指摘しています。負担能力に基づく配分や、HorngrenのCost Accountingで示される売上高や粗利益を配分ベースとする方法も存在します。
1. 相互満足的配分の概念とシャプレイ配分
コストの公平な配分を追求するアプローチとして、相互満足的配分が挙げられます。この概念では、関係者全員が配分結果に納得するような配分方法を目指します。シャプレイ配分は、協力ゲーム理論に基づいた代表的な相互満足的配分方法の一つです。シャプレイ配分は、各部門の協力による貢献度を考慮して、公平な配分を実現しようと試みます。しかし、この方法は必ずしも相互の満足を保証するものではなく、特に結合原価の節約に大きく貢献した部門が、貢献度の低い部門に比べて不満を感じる可能性が指摘されています(Hamlen等)。これは、シャプレイ配分が協力によって生じた総価値を部門間で均等に配分するためです。また、各部門が自由に提携を形成できるわけではない現実を考えると、各部門が各提携に加わる確率が等しいというシャプレイ配分の仮定が常に成り立つとは限りません。さらに、管理者がリスク中立的ではないという点も考慮しなければなりません。これらの点から、シャプレイ配分は理論的には優れていても、実務への適用には課題が残ることを示唆しています。会計担当者(アカウンタント)は、相互満足的配分のための交渉を支援する責任と、配分の効率性を示す責任の両方を負う立場にあります。シャプレイ値は前者には有用な情報を提供しますが、後者については必ずしも十分ではありません。
2. パワーによる配分 交渉力と貢献度の反映
相互満足的配分を実現するための方法として、交渉力や貢献度を反映したパワーに基づく配分が提案されています。これは、シャプレイ配分などの既存の方法が抱える問題点を克服するための新たなアプローチです。しかし、この方法にも限界があります。小林哲夫教授が指摘するように、交渉パワーの差を考慮することが、会計情報の公正性や中立性の要件に反しないかどうかは重要な問題です。Ayresは、相互満足的配分が成立するためには、シャプレイモデルやその他のモデルの仮定が適用可能で、経験的な裏付けが必要であると述べています。社会心理学的な提携理論の研究成果をコストアロケーションに応用する試みも続けられています。管理会計の中心的役割はマネジメントコントロールにありますが、現代では組織メンバーの自律的な行動を促すエンパワメント、権限委譲と責任追及が重要視されています。しかし、公式的な権限以外にも様々なパワーの源泉が存在するため、パワーによる配分も複雑な要素を含むことを示唆しています。HorngrenのCost Accountingでは、因果関係が不明確な場合は売上高や粗利益を配分ベースとして選択できるとしています。これは、原価発生原因主義を第一義としながら、負担能力主義や受益基準に基づいた配分も許容する柔軟なアプローチです。責任会計の発達により利害調整が重要な課題となり、公平な配分をめぐる議論が深まっています。
3. 公平性の概念 平等主義 功利主義 そして 仁 の概念
公平な配分をめぐる議論では、様々な視点が提示されています。負担能力に応じた配分は、結果の平等に近づけるという平等主義的な立場から支持される一方、業績の伸び悩みを招く可能性も指摘されています。機会均等という観点からは、配分ベースの選択自体に公平性が求められます。Harsanyiの配分基準のように、配分ベースをランダムに選択する方法は、機会均等を実現する一つの方法となり得ますが、配分ベースのグループ決定段階で操作が行われる可能性も考慮しなければなりません。功利主義は、個人の効用の和を最大化することを目標とし、同額の共通費を配賦されても、売上高や利益の大きな部門ほど、部門管理者はより小さな非効用しか感じない可能性を示唆しています。この観点から、負担能力に応じた配分は、効用の和の最大化に貢献すると考えられます。小倉(1982)は、利得配分の「仁」の概念を原価配分に適用しています。これは、各プレイヤーへの共通費配分の組み合わせにおいて、最大の不満を最小化する配分を選択するという考え方です。これらの様々な公平性の概念は、コストアロケーション問題における公平性の多様性を示しています。どの基準が最も適切かは、組織の状況や目的によって異なることを示唆しています。
IV.責任会計と原価配分 管理可能性原則と業績評価
責任会計においては、管理可能性原則に基づき、管理不能なコストを原価配分するのは望ましくないという主張があります。しかし、実際には共通費の配分が行われているケースが多く、その理由は情報効果によるベネフィットが大きいからだと解釈されています。業績評価においては、貢献差益や純利益が用いられることもありますが、管理可能利益を用いることが適切とされる場合もあります。日本企業では、欧米企業と比較して「結果」よりも「プロセス」や「潜在能力」を重視する傾向があり、能力考課も報酬に大きく影響します。岡野浩教授の提唱する「築像」は、原価配分を組織メンバーの行動に影響を与えるコントロールツールとして積極的に活用する方法論です。
1. 管理可能性原則と共通費配分の是非
責任会計においては、管理可能性原則が重要な役割を果たします。この原則は、管理者がコントロール可能な費用のみを評価に含めるべきという考え方です。事業部長の業績管理という観点から見ると、共通費を部門に配分すべきではないとする配分否定論が存在します。その根拠は、管理不能なコストを配分すると、逆機能的行動を引き起こす可能性があるという点です。事業部長の業績評価は、短期業績差益や貢献差益(事業部帰属可能費用をすべて控除したもの)で行うべきという意見はこの原則に基づいています。貢献差益から更に本部費や共通費配賦額を控除した純利益は、事業部の収益性評価のみに用いるべきだとする主張もあります。しかし、純利益による業績測定が目標整合性のある意思決定を導く可能性がある場合は、純利益を事業部長の業績評価に用いることも妥当と考える意見もあります。いずれにせよ、業績評価は事業部長に不公平感を与えず、企業目的の達成を動機付けるものでなければなりません。管理不能なコストの配分は、事業部長のモチベーションを低下させ、かえって企業全体の業績悪化を招く可能性があるため、慎重な検討が必要です。 管理可能性原則の徹底が、公正な評価と目標達成へのモチベーション向上に繋がるという点が強調されています。
2. 業績評価尺度 貢献差益 純利益 管理可能利益
事業部長の業績評価においては、貢献差益、純利益、管理可能利益など、様々な尺度が用いられます。貢献差益は、事業部が直接的にコントロール可能な費用を除いた利益であり、管理可能性原則に則った評価指標と言えます。純利益は、貢献差益から本部費や共通費配賦額を控除したもので、事業部の収益性を測る指標として使用されることもありますが、管理不能な要素が含まれるため、評価指標としては必ずしも適切とは言えません。管理可能利益は、事業部がコントロール可能な費用のみを考慮した利益であり、事業部長の責任と権限を明確に示す指標となります。事業部長の業績評価においては、管理可能利益を用いることが一般的ですが、必ずしもそうとは限りません。欧米企業では「結果」重視の傾向が強い一方、日本企業では「結果に至るプロセス」や「潜在能力」を重視する傾向があり、能力考課や態度意欲考課も報酬に大きく影響します。そのため、日本企業では、不完全な管理会計情報と報酬の結合による弊害(事業部長への不公平感、長期業績軽視)を回避するために、結果よりも能力や努力を報酬に反映させる傾向があると考えられます。業績評価における尺度の選択は、企業文化や組織構造、そして評価の目的を考慮して慎重に行われる必要があります。
3. 日米企業の業績評価における違いと責任会計の変革
業績評価における日米企業間の違いも重要な論点です。欧米企業では「結果」重視の傾向が強いのに対し、日本企業では「結果に至るプロセス」「実力」「潜在能力」が重視されます。日本企業では能力考課や態度意欲考課が報酬に大きく影響し、短期的財務情報だけでは不完全な管理会計情報と報酬を結合することによる弊害(不公平感、長期業績軽視)を回避しようとする傾向が見られます。この違いは、企業文化や雇用慣習、組織構造の違いに起因すると考えられます。特に、日本企業における終身雇用制や内部昇進制度は、能力開発や協力関係を重視する文化を反映していると考えられます。しかし、グローバル化や雇用環境の変化により、日本的経営の要素間の整合性が崩れ始めているため、新たな業績評価システムの構築が必要となっています。責任会計は、不完全なシステムであり、環境や組織の変化、企業のグローバル化に伴い進化していくべきです。特に、職能横断的なインタラクションを妨げないように変革し、戦略の創発や組織学習を促進するシステムへと進化させる必要があると主張されています。 日米企業の比較を通して、責任会計システムの多様性と、それぞれの状況に適したシステム設計の重要性が示唆されています。
V.組織構造と原価配分 日米比較
本論文では、日本企業と欧米企業における責任会計と原価配分のあり方の違いを分析しています。日本企業では、終身雇用制や内部昇進といった制度がモチベーションや協力関係に影響を与えている一方、欧米企業では個人の業績と報酬の結びつきが強い傾向があります。継続的改善やチーム活動といった、日本的経営の特徴も考察されています。Aタイプ組織(縦方向の情報の流れ)とJタイプ組織(水平的コミュニケーション重視)の違いも論じられています。調査対象企業として、大規模運送会社(C社)、大規模化学企業(E社)、中規模ハイテク産業企業(H社)の情報が示されています。 管理会計の情報が不完全であることを踏まえ、長期的な視点や能力・努力の評価を重視する日本企業特有のインセンティブシステムについて考察されています。
1. 日米企業における責任会計の違い
この節では、日本企業と欧米企業における責任会計の運用方法の違いについて考察しています。欧米企業では、責任会計が非常に重要視されており、個人の業績と報酬を強く結びつける傾向があります。一方、日本企業では、責任会計は欧米企業ほど重要視されておらず、その運用方法も異なります。例えば、予算管理の方法においても、日米間で大きな違いが見られます(頼(1989))。理念によるコントロールは日米共通ですが、日本企業の特徴として、人事考課に基づいた長期的な評価、昇進に伴う昇給、技能形成の評価、他者との協力関係の評価などが挙げられます。これらの要素が統合されたインセンティブシステムは、日本企業特有の組織風土を反映しています。欧米のコントロール技法を取り入れる際には、日本企業が持つ長所を損なわないように注意する必要があります。特に、近年、日本の終身雇用制が崩れ、日本的経営の要素間の整合性が失われつつある中で、新たな組み合わせを考える必要性が指摘されています。個人の業績と報酬の結合は、職務内容や職位によっても難易度が異なり、管理職ほど会計上の業績と報酬の連動割合が高くなる傾向が見られます。単純作業のブルーカラーは、ホワイトカラーと同様に議論することはできません。
2. 日本的経営の要素と成果主義導入のリスク
日本企業における特有の経営方式や制度には、それぞれに理由があります。長期雇用による生活の安定、技能形成、協力関係を維持するシステム、個人の能力とやる気を引き出すための重複した職務区分とコミュニケーションの仕組み、長期的な評価と昇進に連動した給与による長期的な競争など、これらの要素が複雑に絡み合って日本型経営を支えています。組織活性化のために成果主義を導入することは、これらの日本型経営の長所を損なうリスクがあります。したがって、欧米のコントロール技法を取り入れる際には、これらの要素を考慮し、日本企業が持つ強みを活かしつつ、新たな仕組みを構築していく必要があると指摘されています。特に、個人業績と報酬の結合においては、職務内容や職位によって難易度が異なり、単純作業に従事するブルーカラー労働者と、ホワイトカラーの管理職を同列に議論することはできないと注意喚起されています。成果主義導入によるリスクを最小限に抑えながら、組織の活性化と持続可能な成長を実現するための戦略的なアプローチが求められます。
3. 組織構造とコントロール Aタイプ組織とJタイプ組織
組織構造と原価配分の関係についても言及されています。Aタイプ組織は、縦方向の情報の流れによって管理される組織で、分業と職務割当による効率性向上を目指し、作業と問題解決が分離されています。一方、Jタイプ組織は、垂直的コミュニケーションを前提としながらも、水平的コミュニケーションを促進する機構が重要な役割を果たす組織です。現場での体験や知識の共有を通じて、労働者集団が自ら問題を発見し解決する能力を重視する組織です。個人の業績評価が競争を促進する一方で、水平的な情報の流れやチームワークを阻害する可能性も指摘されており、報酬と業績の結合においては、個人の業績評価よりも集団の業績評価のウェイトを高めることが重要です。継続的改善やチーム活動に見られる水平的な情報の流れや協力は、日本企業のコントロール方法と類似しており、欧米の個人主義的な環境下でも有効な可能性があると示唆されています。しかし、人材不足や従業員の技能開発の遅れなど、継続的改善を実現する上での困難さも指摘されており、米国におけるMade in Americaで指摘されているように、従業員の小グループ管理や部門間の配置転換を含む経営訓練が不足している企業が多いという現実が、継続的改善の困難さを物語っています。組織構造の違いが、コントロール方法や原価配分のあり方に影響を与えることを示唆しています。
