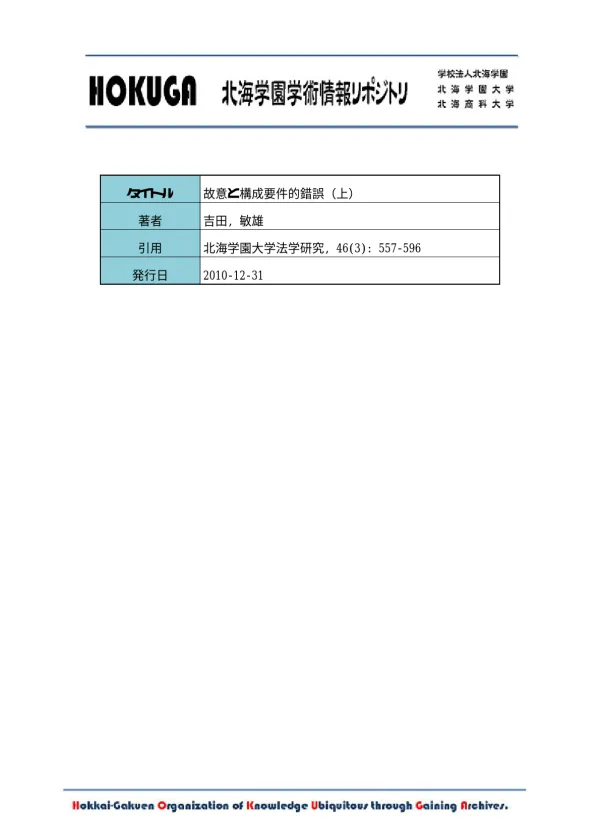
刑法における故意の定義と構成要件
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 713.30 KB |
| 専攻 | 刑法 |
| 文書タイプ | 講義ノート |
概要
I.故意 Ko i の定義と種類 確定的故意 目的的故意 未必の故意
本論文は、日本の刑法における**故意(Ko-i)**の概念を詳細に考察しています。故意には、確定的故意(Kakuteki ko-i)、目的的故意(Mokuteki ko-i)、**未必の故意(Mihitsu no ko-i)**の3種類が存在し、それぞれ結果発生に対する認識の程度が異なります。確定的故意は結果発生を確実なものと認識した場合、目的的故意は目的達成のために結果発生を容認した場合、未必の故意は結果発生の可能性を認識しながらも、それを容認する意思を持つ場合に成立します。これらの違いを、**構成要件(Kouseiyouken)**の認識、認識(Ninshiki)の明晰性、そして結果発生に対する確実性の認識という観点から詳細に分析しています。特に未必の故意については、結果の容認と、**過失(Kasitsu)**との区別が重要な論点となっています。
1. 確定的故意
確定的故意とは、法律が結果の発生を単に可能性としてではなく、確実なものと考える場合に成立する故意です。行為者は、結果の発生を確実なものとして認識していることが必要です。これは、結果の発生が行為者の支配下にあり、その発生を確実視しているという強い認識を示唆します。 例えば、毒物を服用させ、確実に死亡させようとした場合などが該当します。 この場合、結果の発生に対する認識の明確さ、確実性が重要な要素となります。 単なる可能性の認識では不十分であり、ほぼ確実に結果が発生すると認識していることが必要となります。 この確実性の認識は、客観的な状況証拠だけでなく、行為者の主観的な認識も考慮されます。 したがって、確定的故意の成立判断においては、行為者の心理状態、具体的には結果発生に対する確信度を慎重に検討する必要があります。
2. 目的的故意
目的的故意は、行為者が目的とする行為の結果として、特定の結果が実現することを認識している場合に成立します。 行為者にとって、その結果を実現することが問題となる場合、目的的故意が問われます。この場合、行為者は結果の発生を意図しており、その実現を目的として行為に及んでいるため、結果発生に対する認識は確定的故意と同様に明確で強いものとなります。 例えば、金品を奪うために他人を傷害するような場合が挙げられます。 行為者は傷害という結果を直接意図しているわけではありませんが、金品を奪うという目的を達成するためには傷害という結果が不可欠であると認識しています。この認識の明確さと、目的達成のための手段としての結果発生の容認が、目的的故意の成立要件となります。 目的的故意の判断においては、行為者の主観的な目的と、客観的な結果との関連性が重要なポイントとなります。
3. 未必の故意
未必の故意は、行為者が結果発生の可能性を認識しながらも、その結果の発生を容認し、行為に及んだ場合に成立します。 認識の面では不確実さが伴い、意欲の面では内面的な葛藤(行為者にとって結果自体が望ましくないという要素)が存在します。 結果発生の可能性の程度が問題となりますが、単なる可能性の認識だけでは不十分で、かなり高い蓋然性で結果が発生すると予測する場合に認められるとされています。 例えば、多くの歩行者の中に車を突っ込む可能性を十分認識しながら運転を続けた場合、または、危険な薬品を販売した結果、購入者が死亡する可能性を認識しながらも販売した場合などが挙げられます。 未必の故意の成立においては、結果発生の可能性に対する認識の程度、行為者の結果に対する態度(容認・甘受)、そして一般的な常識人であればそのような行為を控えるであろうという判断基準が考慮されます。 認識のある過失との区別が重要であり、結果の容認という点が決定的な要素となります。 結果の発生が行為者の希望に沿わなくても、故意が成立する可能性がある点に注意が必要です。
II.構成要件 Kouseiyouken と認識 Ninshiki の関係
構成要件(Kouseiyouken)の実現に関する認識(Ninshiki)の程度が、故意(Ko-i)の成立に大きく影響します。構成要件に該当する事実を認識していなければ故意は否定されます。しかし、認識の程度は、確定的故意、目的的故意、未必の故意によって異なります。例えば、殺人罪(Satsujin-zai)においては、被害者の死亡を確実、あるいは可能性として認識していたか否かが重要になります。判例(Hanrei)を参考に、具体的な事例を通して構成要件と認識の関係が解説されています。
1. 構成要件要素への認識の必要性
故意の成立には、犯罪の構成要件に該当する事実に対する認識が不可欠です。 客観的な構成要件要素に対応する認識が現実的に存在していなければ、故意は否定されます。 この認識は、単なる事実の認識にとどまらず、その事実が犯罪構成要件を満たすものであるという理解を含みます。 例えば、他人を傷害した行為が傷害罪の構成要件を満たすものであることを認識している必要があります。 単なる身体的接触という事実認識だけでは不十分であり、その行為が法律上、傷害罪に該当するという認識が必要となります。 この認識の有無は、故意の有無を判断する上で非常に重要な要素であり、構成要件に関する錯誤や、違法性に関する錯誤は、故意の成立に大きな影響を与えます。 したがって、構成要件要素への認識の有無、そしてその認識の程度を正確に把握することが、故意の成立を判断する上で非常に重要となります。
2. 認識の明晰性と故意の否定
故意の成立には、構成要件要素に対する認識の明晰性も求められます。 認識自体が条件付きであったり、結果の発生が不確かな場合、故意は否定される可能性があります。 これは、行為者が結果発生を確信していたか、それとも単なる可能性として認識していたかに依存します。 例えば、結果の発生が不確実なまま行為に及んだ場合、故意は否定される可能性が高くなります。 また、行為者が構成要件を誤解していた場合も、故意の否定につながる可能性があります。 この場合、行為者の認識の曖昧さが問題となり、客観的な状況証拠だけでは判断が難しくなることがあります。 したがって、故意の有無を判断する際には、構成要件要素に関する行為者の認識の明晰性、そしてその認識の程度を総合的に検討する必要があります。 意図的な行為と、偶発的な行為との区別も重要な要素です。 特に結果が不確実な場合、その不確実性に対する認識の程度が、故意の成立に大きく影響します。
3. 認識と意欲の組み合わせ
故意の成立には、認識に加え、意欲も重要な要素となります。 確定的故意、目的的故意、未必の故意のいずれにおいても、行為者の意欲が考慮されます。 例えば、未必の故意の場合、結果発生の可能性を認識しているだけでなく、その結果発生を容認する意欲も必要となります。 単に結果発生の可能性を認識しているだけでは不十分で、その結果を甘受する意思があることが、未必の故意の成立要件となります。 この意欲は、行為者の心理状態を反映しており、客観的な状況証拠だけでは判断できない部分があります。 したがって、故意の成立を判断する際には、行為者の認識と意欲の両方を考慮し、その組み合わせによって故意の成立を判断する必要があります。 この認識と意欲の組み合わせは、行為者の主観的な心理状態に基づいて判断されるため、客観的な証拠だけでは判断が難しい場合があります。 判例においても、行為者の心理状態を詳細に分析することで、故意の成立が判断されています。
III.判例研究 具体的な事例分析
本論文では、様々な判例(Hanrei)を引用し、故意(Ko-i)の成立要件を具体的に解説しています。例えば、贓物故買罪(Soubutsu kokubai-zai)、自動車運転致死傷罪など、様々な犯罪類型における故意の判断基準が、判決文を分析することにより示されています。これらの判例分析を通して、**認識(Ninshiki)の程度、結果発生に対する確実性の認識、そして法益侵害(Houeki shin-gai)**の可能性に関する認識などが、故意の成立にどう影響するかを明らかにしています。特に、未必の故意に関する判例分析は、その曖昧さを解消する上で重要です。
1. 贓物故買罪に関する判例
昭和23年3月16日の判例(刑集2・3・227)では、贓物故買罪における故意の成立要件が検討されています。 この判例では、贓物であることを知って買い受けた場合に罪が成立するものの、必ずしも買い受ける物が贓物であることを確定的 に知っていなければならないわけではないと判断されています。 贓物である可能性を認識しながらも、敢えて買い受けた場合も、故意が成立するとされました。この判例は、未必の故意の成立要件を示唆するものであり、結果(贓物の購入)が発生する可能性を認識しながらも、その可能性を容認して行為に及んだ場合、故意が認められるという点に注目すべきです。 この判例は、確定的認識がなくても、結果発生の可能性を認識していれば故意が成立しうることを示す重要な事例として挙げられています。 確実な認識と可能性の認識の違い、そしてその認識に基づいた行為者の意思決定が、故意の成立にどう影響するかを理解する上で、この判例は示唆に富んでいます。
2. 自動車運転致死傷罪に関する判例
文書には、盆踊り帰り等の多数の歩行者に対し、自動車を衝突させる危険性を十分認識しながら運転を続けた事例が言及されています。 この事例は、前方不注意による正常な運転ができない虞があり、加えて前照灯故障による無灯火での夜間運転という状況下で行われたものでした。 この場合、結果(歩行者への衝突による傷害・死亡)が発生する可能性を認識しながらも、危険な運転を続けた行為者の責任が問われます。 この事例は、未必の故意の観点から分析されており、高い蓋然性で結果が発生すると予期できる状況下での行為が、故意として評価される可能性を示しています。 また、この判例では、行為者の認識と、客観的な危険性の程度との関係が問題となります。 行為者が認識していた危険性の程度、そして一般的な常識人であればそのような危険を認識し、回避すべきであったという点が、故意の成立判断において重要な要素となることが示唆されています。
3. 不作為の殺人に関する判例
東京高判昭和62年9月22日判タ661・252では、自動車のトランクに重傷の被害者を押し込み、走行中に死亡させた事例が取り上げられています。 この事例は、不作為による殺人に関するもので、行為者が被害者の死亡を予見できたか否かが争点となりました。 この判例では、行為者が被害者の生命に危険があることを予見していたと判断され、未必の故意が認められました。 被害者の状態を認識し、死亡の可能性を予見しながらも、放置した行為が、結果発生を容認する意思と解釈されたと考えられます。 この判例は、積極的な行為だけでなく、不作為についても、結果発生の可能性を認識し、それを容認する意思があれば、未必の故意が成立することを示す重要な事例です。 行為者の不作為が、結果発生にどの程度寄与しているか、そしてその行為が一般常識から見て許容されるか否かが、故意の成立判断において重要な要素となります。
IV.故意と過失 Kasitsu の区別
故意(Ko-i)と過失(Kasitsu)の区別は、刑法上の責任を問う上で非常に重要です。本論文では、認識(Ninshiki)の有無、結果発生に対する態度、そして法益侵害(Houeki shin-gai)に対する認識の有無などを比較することで、故意と過失を明確に区別しています。特に未必の故意は、過失と非常に近いため、その違いを明確にするための議論が展開されています。 この区別は、構成要件の成立に直接影響するため、非常に重要なポイントです。
1. 認識の有無と結果発生への態度
故意と過失の区別において最も重要な点は、結果発生に対する認識の有無と、その認識に基づく行為者の態度です。故意には、結果発生を積極的に、もしくは消極的に容認する意思が含まれます。 一方、過失は、結果発生の可能性を予見しながらも、それを回避する注意義務を怠った場合に成立します。 つまり、故意は結果発生をある程度予測しながらも、それを容認した状態、過失は結果発生の可能性を予見しつつも、それを回避すべき注意義務を果たさなかった状態と言えるでしょう。 この認識の有無、そして結果発生に対する積極的・消極的な容認の有無が、故意と過失を区別する上で重要な要素となります。 未必の故意は、この両者の境界領域に位置づけられ、結果発生の可能性を認識している点では過失と類似しますが、結果発生を容認する点で故意と共通する要素を持ちます。 そのため、未必の故意と過失との明確な区別が、この議論における重要な課題となっています。
2. 一般常識人による判断基準
故意と過失の区別においては、一般常識人であればそのような法益侵害の可能性を無視してそのまま行動することは許されない、と判断する程度の危険性がある場合に、あえてその行為を行ったかどうかが重要な判断基準となります。 これは、行為者の認識の程度だけでなく、客観的な危険性の程度も考慮する必要があることを意味します。 たとえ行為者が結果発生の可能性を認識していたとしても、その危険性が一般的に見て軽微なものであれば、故意は否定される可能性があります。 逆に、一般常識人であれば容易に予見できる程度の危険性があったにもかかわらず、それを無視して行為に及んだ場合、故意が成立する可能性が高くなります。 この一般常識人による判断基準は、行為者の主観的な認識だけでなく、客観的な状況証拠も考慮して判断されるため、具体的な事例ごとに慎重な検討が必要です。 特に未必の故意においては、この一般常識人による判断基準が、故意と過失の区別を明確にする上で重要な役割を果たします。
3. 未必の故意と認識のある過失の峻別
未必の故意と認識のある過失を峻別する上で決定的な要素は、「結果の容認」です。 結果の発生が行為者の希望に沿わなければならないという意味ではありません。 結果の発生を積極的または消極的に認識したとき、故意があるとされ、消極的容認でも十分であるとする説もあります。 しかし、結果の容認という点に着目することで、単なる結果発生の可能性の認識にとどまらず、その結果をある程度受け入れる意思があったかどうかが、重要な判別基準となります。 この結果容認の有無を判断する際には、行為者の心理状態、動機、そして客観的な状況証拠などが総合的に考慮されます。 この点において、結果の容認を重視する見解と、行為動機に重点を置く見解が存在し、両者の見解の違いを理解することが、未必の故意と認識のある過失の峻別において重要になります。 結果の容認の有無は、客観的な状況証拠だけでなく、行為者の主観的な心理状態を詳細に分析することで判断されるため、複雑なケースも存在します。
