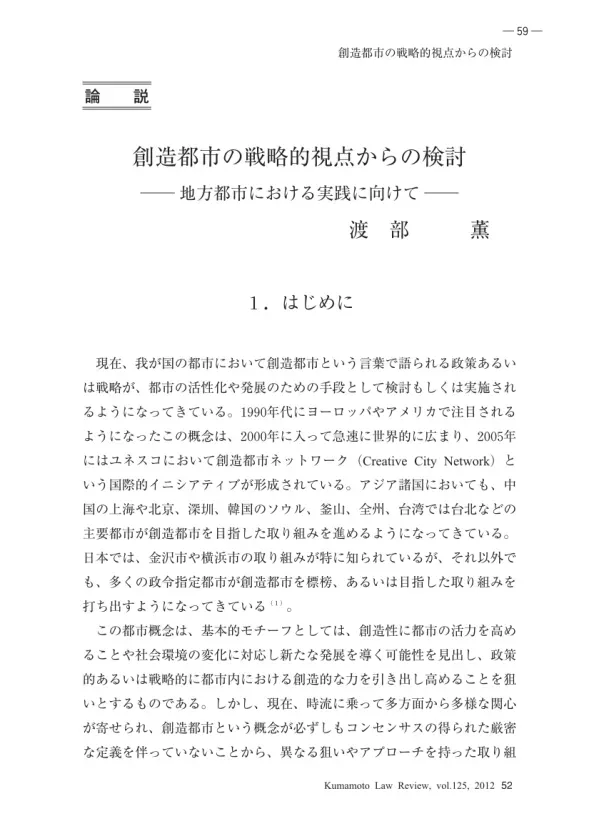
創造都市戦略:地方都市活性化への道
文書情報
| 著者 | 渡部薫 |
| 専攻 | 都市計画、地域政策、文化政策など |
| 文書タイプ | 論文、研究報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 803.77 KB |
概要
I.創造都市概念の多様性と課題
本論文は、創造都市という概念を日本の地方都市、特に中規模都市の文脈で検討する。創造都市をめぐる研究は、文化産業・創造産業振興、従来の文化政策など多様な視点から展開されているが、都市全体の運営という戦略的視点が不足している現状を指摘する。特に、ランドリーやエーベルトの都市ガバナンス論、フロリダの創造的階級論など、異なるアプローチが存在し、創造都市の定義自体にコンセンサスがない点を問題視する。
1. 創造都市研究の現状と課題 多様なアプローチと戦略的視点の欠如
日本の都市において、創造都市政策や戦略が活性化・発展のための手段として注目されている。1990年代に欧米で始まり、2000年代に入って世界的に広がり、2005年にはユネスコ創造都市ネットワークも設立された。アジア諸国でも主要都市が創造都市化に取り組んでいる。しかし、日本の創造都市研究は、文化産業・創造産業振興や自治体文化政策など、多様な視点が混在しており、都市全体の運営という戦略的視点が不足している。多くの研究が個別の政策に焦点を当てており、都市全体のガバナンスや実現方法に関する研究は少ない。創造産業振興や観光と連携した文化政策に偏っており、必ずしも戦略的視点が欠けているわけではないものの、創造都市本来の中核的な主張である都市発展を見据えたガバナンスのあり方や実現方法について論じたものが少ない。文化経済学だけでなく、地域経済学、産業組織論、経済地理学など多様な分野からアプローチがあるものの、地域産業論にとどまり、創造都市論として捉えるには不十分な点が多い。都市論としての視点が欠けている点も課題である。
2. 創造都市概念の多様な定義とコンセンサスの欠如
創造都市という概念は、1980年代以降のヨーロッパにおける文化を主要手段とする都市政策に対する批判的考察から生まれた。従来の経済的手段に偏った都市再生政策ではなく、市民の潜在能力を引き出し、都市問題を解決するために都市の創造性を活用すべきだと主張する。エーベルトらは、芸術文化の創造的作用に着目し、ハード・ソフト両面から充実した文化インフラストラクチャーを持つ都市が、イノベーションを促進し、創造的問題解決能力を育むと論じる。ランドリーは、社会経済的構造変動に柔軟に対応する都市の自己変革を創造性に結びつけて主張し、その著作で創造都市概念を世界に広めた。しかし、創造都市の概念は論者によって異なり、明確な定義がないため、個々の政策や研究は創造都市を名乗りながら、本来の領域とは異なる方向に進んでしまっている。そのため、創造都市概念を再検討し、日本の地方都市のガバナンスや発展戦略として適切かどうかを問う必要がある。
3. 主要論者の主張と相違点 ランドリー エーベルト フロリダ 佐々木
ランドリーやエーベルトらは、創造都市を創造的な力を活用した自己変革を促す都市ガバナンスと、その実現方法に重点を置く。フロリダは、創造産業を含む知識産業の発展に不可欠な創造的階級に着目し、彼らが好む環境(創造的コミュニティ)の重要性を主張する。この主張は都市政策で注目され、創造産業の育成・振興が創造都市論の主要テーマとなる契機となった。佐々木は、市民の創造活動、革新的な都市経済システム、政策形成能力の高い自治体職員の活動などを創造都市の条件として挙げ、都市内循環的なメカニズムを備えた内発的な都市経済システムとそれを支えるガバナンスを重視する。ランドリーもフロリダも創造産業の重要性を認めるが、ランドリーらは都市の自律的なガバナンスに、フロリダは創造的階級の誘引に重点を置くなど、主張に違いが見られる。佐々木はランドリーの議論を発展させ、より具体的な都市経済システムとガバナンスのあり方を提示している。
II.創造都市論の主要な論点
ランドリーらは、都市の自己変革を促すガバナンスモデルとして創造都市を提示。エーベルトらは、文化インフラストラクチャーとアクター間のネットワークによるイノベーションとインプロビゼーションを強調。一方、フロリダは創造的階級の誘引を重視し、創造的コミュニティ形成による創造産業振興を論じる。佐々木は、自己革新能力を持つ都市経済システムとガバナンスの重要性を指摘する。これらの論者は、文化産業・創造産業の重要性を認めつつも、創造都市の本質は創造性を活用した都市ガバナンスにあると主張する。
1. ランドリーとエーベルトの創造都市論 ガバナンスと創造的自己変革
チャールズ・ランドリーを中心としたグループは、文化を経済的手段とみなす従来の都市再生政策ではなく、市民の潜在能力を引き出すことを重視する創造都市論を提唱した。これは、都市が変化する環境の中で自律的に運営・発展するための戦略であり、創造性を活用した都市ガバナンスのあり方と、その実現方法を提示している。エーベルトらは、芸術文化の創造的効果に着目し、自由な文化活動や充実した文化インフラストラクチャーが、イノベーションを促進し、創造的問題解決能力を育むと主張する。彼らは、都市内のアクター間のネットワークを重視し、創造的な文化活動がネットワークを通じてインプロビゼーション的に連鎖反応を起こし、既存のシステムに変化をもたらす可能性を示唆している。ランドリーは著書『創造的都市』で、社会経済的構造変動に直面した都市や地域が、自己変革を行う必要性と可能性を、地域住民の創造性に結びつけて論じている。これらの論者にとって、創造都市は単なる文化産業・創造産業の振興策ではなく、創造的な力を活用した都市の自律的なガバナンスのあり方そのものを意味する。
2. フロリダの創造都市論 創造的階級と創造的コミュニティ
リチャード・フロリダは、アメリカ諸都市の発展とその担い手である創造的階級に着目し、創造産業の発展について論じる。彼は、知識産業の発展には創造的階級の存在が不可欠であり、都市が発展するためには、創造的階級が好む条件を満たす必要があると主張する。フロリダは、そのような条件を満たす都市環境を「創造的コミュニティ」と名付け、優れた都市景観や文化施設、活気のあるストリートライフやナイトライフ、そして何よりも多様性、開放性、寛容性といった社会文化的環境を重要視する。創造的階級を惹きつける環境づくりこそが、都市政策の必要性であると主張し、文化産業・創造産業に焦点を当てた議論を展開する。フロリダの主張は都市政策の現場で注目を集め、創造産業の育成・振興が創造都市論の主要テーマとなる一因となった。
3. 佐々木の創造都市論 自己革新能力を持つ都市経済システムとガバナンス
佐々木は、創造都市を「市民の創造活動の自由な発揮に基づき、文化と産業における創造性に富み、脱大量生産の革新的で柔軟な都市経済システムを備え、グローバルな環境問題やローカルな地域社会の課題に対して創造的問題解決を行える創造の場」と定義する。その中で特に重要な概念が「自己革新能力に富んだ経済システム」であり、これは都市内循環的なメカニズムを備え、文化的生産を支える都市経済システムを意味し、都市の内発的経済基盤を形成する。このシステムは、大学、文化施設、住民参加システム、政策形成能力の高い自治体職員の活動によって支えられている。佐々木はランドリーらの議論を踏まえ、より具体的に創造都市の中核構造として都市内循環的なメカニズムを備えた内発的な都市経済システムを提示し、それを支える都市ガバナンスのあり方について論じている。ランドリー、エーベルト、フロリダの主張には相違点があるものの、文化産業・創造産業の重要性を認め、市民全体の創造性の向上を重視している点は共通している。
III.創造都市戦略推進のための課題
創造都市を戦略として推進する上での課題として、(1) 創造性を担うアクターとそのネットワーク、(2) 創造性を引き出す要因(文化・芸術の創造的効果など)、(3) 創造的な環境と都市ガバナンスのあり方、の3点を提示。特に、アクター間の協働と自律性を重視し、ビジネスの論理とのバランス、行政のセクショナリズム克服、文化的プロジェクトの意味作用への配慮などを重要課題とする。社会的格差の問題や文化・芸術の創造的自律性の維持についても、創造都市戦略において慎重に検討すべき点として指摘する。熊本市などの地方都市における実践例を踏まえ、中規模都市の特性に合わせた創造都市戦略の必要性を強調する。
1. 創造都市戦略推進におけるアクターの重要性 多様なアクターの連携とガバナンス
創造都市戦略を効果的に推進するには、創造性を担う多様なアクター(市民、企業、自治体など)の存在と、それらの間の連携、コミュニケーションが不可欠である。単に創造的人材を誘致するだけでなく、アクター間の結びつき方、関係性、コミュニケーションのあり方を戦略的にデザインする必要がある。アクター間のネットワークにおいて、強い権力が働かない水平的な構造が求められ、アクターの自律性と協働が促進されるガバナンスが重要となる。ビジネスの力が強すぎると創造性を圧迫する可能性があり、創造性の追求とビジネスの論理のバランスを取ることが重要である。 行政主導のヒエラルキー構造では、アクターの活動を制約したり、創造的な力の円滑な伝達を妨げたりする可能性があるため、アクター間の自律と協働を促進するガバナンスが不可欠であるとされる。
2. 創造性を引き出す要因 文化 芸術の創造的効果と効果的な活用方法
創造都市論では、人々の潜在能力や創造性を引き出すものとして文化・芸術の創造的効果が注目されている。文化・芸術への投資による市民参加は、創造的アイデアやイノベーションの源泉となり、市民に自信と活力を与える。ランドリー、後藤(2008)、マークセン=キング(2003)らは、文化・芸術の創造的効果を論じ、市民の能力を高めるエンパワメント策として位置づけている。しかし、文化・芸術が創造性を高めるメカニズムは十分に解明されていない。ナント市や金沢市の例のように、文化・芸術への公共投資が都市全体の創造的な活力を向上させる効果は認められるものの、巨額の予算や長い時間を要するケースもある。そのため、目的や条件に応じた効果的な方法を判断するためには、文化・芸術の作用に対する原理的な理解に基づき、政策対象を細分化して作用のプロセスや条件を検討する必要がある。
3. 創造的な環境と都市ガバナンス 生活の質 文化インフラ 社会的制度
創造的な人材を引き付け、創造的能力を発揮させるためには、都市の生活の質、フロリダが論じる創造的コミュニティのあり方、社会的雰囲気、文化的インフラストラクチャー、創造の場、創造活動を阻害しない社会的制度、行政の関わり方、ソーシャル・キャピタルなどが重要となる。これらの要素は相互に関連しており、複雑な問題を含んでいる。特に、都市の生活の質の向上は、創造的人材の誘致だけでなく、市民全体の創造性を高める上で重要であり、創造都市戦略は他の戦略や政策と連携させることが可能である。都市内のアクター間のネットワークにおいて、創造的な活動が連鎖的に影響し、循環メカニズムとそれを支える構造が形成されることが理想的である。エーベルトらが論じる、アクター間の連鎖反応による既存システムの変革も、このような循環メカニズムの形成が前提となる。
4. 創造都市戦略における政策協働とガバナンス セクショナリズム克服とネットワーク組織
創造都市戦略では、関連する政策間の協働が不可欠である。文化は教育、産業・経済、観光、都市計画など多くの分野と結びつくため、文化政策部門と他部門の連携が重要となる。セクショナリズムや垣根意識は創造的な営為の大きな障害となるため、それらを克服する必要がある。資源配分や政策の優先順位を決定する際、創造都市の実現と運営という目的を明確に設定し、戦略的に判断する必要がある。都市ガバナンスにおいては、アクター間の自律的な意思決定を可能にする水平的なネットワーク組織が理想的である。現実的には行政が中心的な役割を果たすため困難だが、少なくともこのような関係性を考慮したガバナンスの組み立てが必要となる。この組織形態は、環境変化への柔軟な対応、自己変革、創造的・イノベーティブな能力を高める効果が期待される。
5. 創造都市戦略の実践上の課題 社会的格差 文化 芸術の自律性 意味作用
創造都市戦略の実施に伴い、社会的格差の拡大、文化・芸術の自律性の損なわれ、文化・芸術の政策的利用による地域社会への意味作用の問題が懸念される。創造産業振興に重点を置く都市では、創造的人材の活躍と、機会に恵まれない人々との間の格差が生じる可能性がある。文化・芸術を経済的目的に利用することで、本来の意義や価値、社会的役割が損なわれる可能性や、文化・芸術の質や多様性に影響を与える可能性がある。行政の関与が創造の自律性を損ない、批判的役割や社会革新の役割を低下させる懸念もある。これは市場の力とどのように向き合うかという問題に帰着する。グラスゴー市の例では、イメージ戦略が地域社会で大きな論争を引き起こしたものの、結果的に地域活性化に繋がった事例がある。文化プロジェクトは、地域社会に大きな意味作用を与えることを考慮し、慎重に検討する必要がある。
IV.創造都市戦略の実践的検討課題
創造都市の実現には、政策協働とガバナンス体制の構築が不可欠。ネットワーク組織を理想型として、現実的なガバナンスのあり方を模索する必要がある。文化・芸術の経済的利用と創造的自律性のバランス、文化プロジェクトの意味作用への配慮、社会的包摂の確保などを具体的な課題として挙げる。創造都市は単なる文化産業・創造産業振興策ではなく、都市の持続的な自立戦略であることを再確認する。
1. 創造都市実現のための要件 アクター 刺激 環境 ガバナンス
創造都市の運営と実現のためには、戦略的な視点に基づいた検討が必要である。基本的構成要素として、アクター(創造性を担う主体)、行動への刺激、アクターが活動するための環境、そして都市全体の運営体制であるガバナンスの4つのファクターが挙げられる。アクターに関しては、アクター自体とアクター間の関係の2点に分け、(1)創造性を担うアクターの存在とその状況、(2)アクター間の結びつき方や関係性、(3)創造性を引き出す要因、(4)これらのファクターを支える環境・文化、(5)ガバナンスに関わる要因、といった点を検討すべきである。アクター間の関係においては、強い権力が働かず、アクターの自律と協働を促進するガバナンスが求められる。ビジネスの力は重要だが、強すぎると創造性を圧迫する可能性があるため、バランスが重要となる。創造性を引き出す要因としては、文化・芸術の創造的効果が注目されており、市民参加によるエンパワメントが重要視される。しかし、その効果や効率的な方法については、更なる研究が必要である。
2. 文化 芸術の活用と創造都市戦略 創造的効果 自律性 意味作用への配慮
創造都市戦略においては、文化・芸術の創造的効果の活用が重要となるが、その効果を最大限に引き出すためには、文化・芸術の作用に対する原理的な理解に基づいた、より詳細な検討が必要である。文化・芸術を経済目的のために利用することで、本来の意義や価値、社会的役割が損なわれる可能性、文化・芸術の質や多様性に影響を与える可能性、そして創造の自律性が損なわれる可能性がある点にも注意が必要である。行政の関与は、市場の力とどのようにバランスを取るかという問題に直結する。芸術家は古くから市場や権力と対峙しながら創造性を発揮してきた歴史があり、現代においても市場との関係を無視できない現実がある。創造性の追求とビジネスの論理のバランスこそが、創造都市の持続性を支える鍵となるが、このバランスを保つことは容易ではないため、戦略においては大きな課題となる。また、文化プロジェクトが地域社会に与える意味作用にも配慮が必要であり、特定の意味に特権的地位を与えることで、地域社会の混乱を招く可能性もある。
3. 創造都市戦略の課題 社会的包摂 政策協働 ガバナンス体制の構築
創造都市戦略における重要な課題として、社会的包摂、政策協働、ガバナンス体制の構築が挙げられる。創造都市は、創造的能力の高い人の活躍の場を広げる一方で、社会的格差を広げる可能性や、社会的な弱者を疎外する可能性も指摘されている。特に文化産業・創造産業に重点を置く都市では、この問題が深刻化する可能性がある。そのため、すべての市民の創造性を高める取り組みが必要となる。行政内部における政策協働と、行政の枠を超えたガバナンス体制の構築も重要であり、特に文化政策は教育、産業・経済、観光、都市計画など多くの分野と結びつくため、部門間の連携が不可欠である。セクショナリズムの克服が重要であり、ネットワーク組織を理想型として、現実的なガバナンスのあり方を模索する必要がある。文化・芸術を経済的目的に利用することで創造の自律性を損なう可能性があり、創造的な力と市場の力とのバランスをどのように取るかが、創造都市戦略の大きな課題となる。
