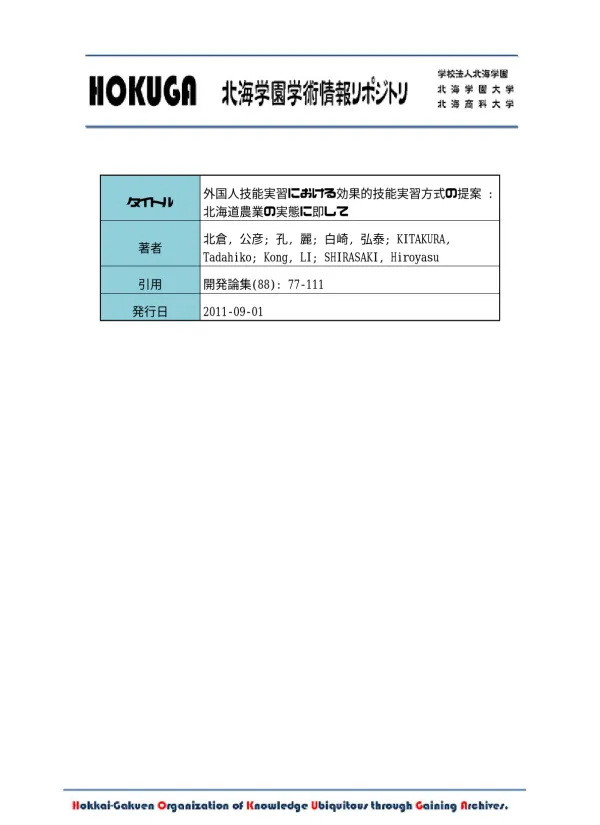
効果的技能実習:北海道農業の課題解決
文書情報
| 著者 | 北倉 公彦 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 経済学部 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 774.36 KB |
概要
I.技能実習制度の現状と課題 歴史と問題点
1993年、労働力不足を背景に「研修・技能実習制度」が開始されました。当初は単純労働者の受け入れを排除する政府方針との妥協点として誕生したため、低賃金労働力という認識が根強く残っています。研修生側も労働者意識が高く、研修手当や時間外労働に関する不満も存在します。入管法改正(1989年)で「研修」の在留資格が追加され、JITCOなどの団体が制度運営に関わっています。しかし、悪徳ブローカーの存在や強制労働の疑いなど、様々な問題が指摘され、制度の見直しを求める声が高まっています。アメリカ国務省の報告書(2007年)も、技能実習制度における強制労働の可能性を指摘しています。
1. 技能実習制度の創設と背景
1970年代後半からの労働力不足を背景に、1993年に「技能実習制度」が創設されました。これは、研修1年、技能実習2年の計3年間の制度で、研修修了後に所定の要件を満たした者に対して雇用関係の下で就労が認められ、より実践的な技術・技能の習得を目的としています。しかしながら、この制度は、政府の基本方針である『外国人の単純労働者の受け入れは認めない』という原則との妥協から生まれたものであり、受け入れ側には低賃金労働力としての認識が根強く残っている点が問題視されています。一方、研修生側も労働者としての自覚を持ち、低い研修手当や、認められていない時間外労働への不満を抱えているという現状があります。この制度の根本的な矛盾が、後の様々な問題を引き起こす要因の一つとなっています。
2. 入管法改正と外国人研修制度の発足
1989年12月、『出入国管理及び難民認定法』(入管法)の改正が行われ、外国人の在留資格に「研修」が追加されました。これにより、従来の「公的機関型」や「企業単独型」に加え、「団体監理型」による外国人研修生の受け入れが可能となり、「外国人研修制度」が発足しました。この制度は、技能実習制度の前身ともいえるものであり、その後の技能実習制度の枠組みにも影響を与えています。厚生労働省の『研修・技能実習制度研究会報告』では、研修1年+技能実習2年の体系を、初めから雇用関係の下で3年間の実習とすることを提言。実習修了時には技能検定3級レベル以上の受験を義務付け、合格者のみ「企業単独型」での再入国・再実習を認めるという提案もなされました。農協などが第一次受入機関となる「団体監理型」研修は限定的にしか認められない点が特徴です。
3. 制度の問題点と見直しへの要請
研修生を斡旋する悪徳ブローカーの存在や、様々な問題が顕在化してきたため、技能実習制度の継続の可否を含め、制度の見直しを求める意見が強まってきました。2007年6月には、アメリカ国務省が発表した『2007年人身売買報告書』において、外国人研修制度の名の下に一部の外国人が強制労働を強いられている可能性が指摘され、日本政府に調査と制度改善が求められました。この報告書は、国内における制度批判に加え、国際的な批判も招いた重要な出来事です。これらの問題点の指摘は、技能実習制度のあり方そのものを問うものであり、抜本的な改革の必要性を強く示唆しています。 日本経済団体連合会も2007年3月に『外国人材受入問題に関する第二次提言』を発表し、制度のメリットを認めつつ、不正行為への罰則強化などを求めています。これらの動きは、技能実習制度の将来を左右する重要な転換期にあることを示しています。
II.技能実習制度の改善提案と議論
技能実習制度の抜本的見直しを求める声の中、様々な提案がなされています。例えば、経済団体連合会は制度の存続を認めつつ、罰則強化を提言。一方、自民党は「外国人労働者短期就労制度」の創設を提案し、最長3年間の在留、家族滞在不可、業種・職種制限なしなどを謳っています。これらの提案は、技能実習生の法的保護強化、不正行為への対応、受入企業の責任明確化などを焦点としています。特に、日本語能力や技能レベルの向上、再入国・再実習の条件設定などが議論の中心となっています。
1. 経済団体連合会の提言と制度存続
日本経済団体連合会は2007年3月、『外国人材受入問題に関する第二次提言』において、現行の技能実習制度の受入側と送出側の双方にとってのメリットを認め、制度の存続を主張しました。ただし、不正行為があった受入機関に対する受入停止期間を3年から5年に延長するなど、罰則の強化を提言しています。これは、制度の改善と同時に、不正行為の抑止を図るための重要な取り組みです。また、研修生・技能実習生の不適正な在留に対する帰国措置の強化なども含まれており、制度の運用面における厳格化が求められていることがわかります。これらの提言は、制度の継続と改善を両立させるための現実的なアプローチといえます。
2. 自民党の 外国人労働者短期就労制度 創設提案
当時の自民党は、法務大臣当時から「外国人労働者短期就労制度」の創設を主張していた長勢甚遠氏を座長とする「外国人労働者問題プロジェクト・チーム」を発足させ、2008年7月に『外国人労働者短期就労制度の創設の提言』を発表しました。この提言では、①研修・技能実習制度を廃止し、「短期就労」を新設、②最長3年間の滞在を許可するものの家族滞在は認めない、③受入企業の業種、労働者の職種・技能に制限を設けない、④受入団体の許可制度を新設し、総受入人数と受入枠を決定、⑤企業ごとの受入人数は現行制度と同様、⑥企業には労働関係法規の遵守、宿舎の確保、渡航費負担などの義務を負わせる、⑦健康保険、雇用保険、労災保険は通常の労働者と同様の適用とする、といった内容が盛り込まれています。さらに、日本語能力や技能が一定レベルに達し、一度母国に帰国することを条件に、2年間の再実習を認めることも提案されています。これは、技能実習制度とは異なる新たな枠組みの提案であり、制度改革の議論において重要な選択肢の一つとして位置づけられています。
3. 技能実習制度改革の焦点 法的保護と不正行為への対応
技能実習制度の改革においては、実習生の法的保護の強化が重要なポイントとなっています。入管法や労働基準法などの関連法規、不正行為への対応方法、実習生の権利保護に関する情報を、技能習得活動前に講習で提供することが必要とされています。これは、実習生を守るための具体的な方策であり、制度の透明性と信頼性を高める上で不可欠です。また、受入企業には労働関係法規の遵守、適切な住環境の提供、渡航費・帰国準備金の負担などの義務を課すことで、実習生の権利をより確実に保障する仕組みづくりが求められています。 これらの提案は、技能実習制度の抱える問題点を解決し、より健全な制度運営を目指すための重要な取り組みと言えるでしょう。同時に、監理団体や受入企業の責任を明確化し、不正行為を抑制するための強力な対策が求められています。
III.技能実習生の講習 日本語学習プログラム試案
技能実習制度において、入国直後の講習は非常に重要です。講習時間は技能実習1号の活動時間の6分の1以上(事前講習ありの場合は12分の1以上)と規定されています。講習内容は、日本語、生活一般知識、入管法・労働法、技能等習得に資する知識の4科目です。日本語学習は特に重要視され、多くの時間を割く必要があります。しかし、日本語学習プログラムの内容や実施体制には改善の余地があります。 A農協とB農協の事例では、日本語教育方法や講習時間、地域との交流、生活環境などに違いが見られ、それぞれ課題と改善策が提示されています。特に、北海道のケースでは、農閑期があるため、技能実習生の滞在期間が1年未満となることが多く、それに合わせた日本語学習プログラムの必要性が強調されています。
1. 入国直後講習の実施体制 監理団体の負担と課題
技能実習制度における入国直後の講習は、技能実習1号の活動時間の6分の1以上(事前講習受講済みの場合は12分の1以上)を要し、特定の場所で集団的に実施する必要があります。このため、数週間にも及ぶ講習に必要な会場確保や講師の手配が監理団体にとって大きな負担となっています。特に、労働関係法に関する講義には専門知識を持つ外部講師が必要となるため、費用や人員確保が課題となります。この講習体制の整備は、技能実習制度の円滑な運用にとって不可欠でありながら、監理団体にとって経済的・人的な負担が大きいことが問題点として挙げられています。より効率的で負担の少ない講習体制の構築が求められています。
2. 日本語学習プログラム 効果的な学習方法と動機付け
入国管理局は、入国当初の講習で実習生が日常生活や技能実習に支障がないレベルの日本語能力を習得することを期待しており、監理団体はそれに対応する体制と計画を整備する必要があります。日本語学習の重要性は広く認識されていますが、効果的な学習方法の確立が課題となっています。 本文では、A農協とB農協の事例を比較し、日本語学習方法の違いを分析しています。A農協は座学中心で日常生活や実習に必要な日本語を教え、技能検定対策も行っているのに対し、B農協は公共施設の利用方法やゴミ処理方法などを体験を通して教えている点が挙げられています。日本語学習の講師の質や経験も学習効果に影響を与える要因の一つとして考察されています。さらに、実習生自身の学習意欲を高めるための動機付けも重要であり、日本の文化や歴史、若者文化などを学習内容に取り入れることが提案されています。具体的には、「て形」の習得を重視した日本語教育や、日記作成による学習継続の促進などが提案されています。
3. 関連作業の取り込みと実習計画の改善
技能実習計画においては、関連作業の取り込みが課題となっています。多くの場合、対象作物に関する技能等に限定されており、農業経営という観点からは、より幅広い技能の習得が望まれます。A農協ではきのこ栽培、B農協ではメロン栽培に限定されている点が指摘されています。これは、入国管理局やJITCOの審査基準が反映された結果と考えられますが、実習生の能力開発という観点からは、より多様な技能習得機会を提供することが必要です。 北海道A農協の一括受入・分散実習方式は、監理団体が講習を一括して実施し、農家に派遣するという新たな試みです。これにより、受入農家の負担軽減と効率的な日本語学習の両立を目指していますが、費用負担増加という課題も存在します。 入国管理局の審査基準に合致しやすいことを理由に、安易に前例に倣った技能実習計画を作成する傾向を改め、実情に合った計画を作成し、入国管理局と協議を重ねる必要があると指摘されています。
IV.実習計画と関連作業 課題と改善策
技能実習計画は、職種・作業範囲、スケジュール、指導体制、安全衛生などを明確にする必要があります。技能実習1号終了時の到達目標(例:技能検定基礎2級)を設定し、関連作業は総活動時間の2分の1以内と規定されています。しかし、関連作業の範囲が狭く、実習生の能力開発の幅を狭めているという課題があります。北海道A農協の「一括受入・分散実習方式」は、監理団体に講習を一括して実施させ、農家に派遣するモデルとして注目されています。この方式は、受入農家の負担軽減と効率的な日本語学習の両立を目指しています。また、技能実習計画作成においては、入国管理局の審査基準を満たすだけでなく、実習生の育成や経営状況にも配慮した柔軟な対応が求められています。
1. 技能実習計画の基準と課題
技能実習1号における実習計画の基準として、①技能実習の職種・作業範囲の明確化、②具体的なスケジュール、カリキュラム、指導体制、安全衛生等の詳細な記述、③関連する技能等の修得は総活動時間の2分の1以内、④技能実習1号終了時の到達目標の設定(技能検定レベルや受験時期の明記)、⑤所定労働時間は週40時間以内、1日8時間以内などが挙げられます。しかし、A農協ではきのこ栽培、B農協ではメロン栽培といったように、対象作物に限定された技能習得計画となっている点が問題視されています。これは、入国管理局やJITCOの審査基準が影響していると考えられ、農業経営の観点からは、より幅広い技能習得を可能にする計画の必要性が示唆されています。 JITCOは、必須作業、関連作業、周辺作業の割合について目安を示していますが、実習計画の作成にあたっては、入国管理局の審査を通過しやすいという理由だけで前例に倣う傾向が強く、実情に即した計画作成が求められています。
2. 関連作業の重要性と拡大の必要性
技能実習計画において、関連作業の適切な取り込みが重要です。関連作業は、技能実習2号への移行対象職種・作業において「日本人労働者が通常従事する技能等」を修得するための活動でなければならず、総活動時間の2分の1以内と規定されています。関連作業を適切に取り入れることで、実習内容の幅を広げ、帰国後の実習生の活躍の場を広げる可能性があります。しかし、現状では、A農協、B農協の事例に見られるように、関連作業の範囲が狭く、対象作物に関する技能等に限定されているケースが多く見られます。これは、入国管理局やJITCOの審査基準が影響していると考えられますが、農業経営の観点から、より広い領域の技能習得を可能とする関連作業の拡大が検討されるべきです。 トマト・大根・キャベツ、イチゴ・ブドウなど複数の作物を対象とした実習計画の例も存在しており、より柔軟な対応が求められています。
3. 北海道A農協の 一括受入 分散実習方式 課題と展望
北海道A農協は、2011年からきのこ栽培農家の実習生について、長野県飯田市の「企業連合事業協同組合」を一括受入・分散実習方式で実施しています。この方式では、企業連合事業協同組合が実習生を一括して受け入れ、講習を飯田市で実施した後、A農協の農家に派遣します。この方式は、受入農家と農協の事務負担軽減、濃密な日本語学習の実現というメリットがある一方で、相応の費用負担が発生するというデメリットもあります。 この方式は、監理団体の役割を明確化し、コスト削減や中国の送出し機関との交渉力強化にもつながる可能性を示しています。北海道での一般化を検討する際には、職業紹介事業を行う監理団体の選定、実習実施状況の確認体制の構築などが課題となります。 企業連合事業協同組合は、道内の水産加工企業とも同様の方式をとっており、北海道内にも事務所を構え担当者を常駐させることで、実習生へのサポート体制を強化しようとしています。
V.実習生からの要望と今後の展望
技能実習生からの要望として、日本語学習の充実、地域との交流促進、生活環境の改善などが挙げられています。技能実習生の多くは20~30代の未婚女性で、近年は高学歴者も増加しています。彼らのニーズを踏まえ、より効果的な日本語学習プログラムの開発、充実した生活環境の提供、地域社会との円滑なコミュニケーション促進が重要です。TPP対応や過疎地域の農業維持という観点からも、技能実習制度の弾力的な運用、そして、将来的な「短期就労制度」への移行なども検討課題として残されています。
1. 実習生からの要望 日本語学習 生活環境 地域交流
A農協とB農協の中国人技能実習生への聞き取り調査結果によると、実習生からの主な要望として、日本語学習の充実、地域との交流の促進、生活環境の改善などが挙げられています。日本語能力については、技能実習や日常生活に「困らない程度」と回答する実習生が多いものの、個人差が大きい点が指摘されています。コミュニケーションの円滑化のためには、日本語指導の強化が強く求められています。生活面では、おおむね満足しているものの、パソコン購入の容認や買い物への不便さ解消などの要望もありました。地域交流に関しても、地域住民とのコミュニケーションを深め、日本のことをより深く理解したいという意欲が見られます。これらの要望は、実習生がより良い環境で技能習得に励み、日本での生活を充実させるための重要な要素となっています。
2. 実習生の属性変化と背景
調査対象となった技能実習生は、20~30代の未婚女性が中心ですが、大学卒、専門学校卒、高校卒など高学歴者が多く、以前の中学卒が一般的だった状況とは大きく異なっています。中には大学3年生在学中の人もいます。地方大学卒業者の中には、地元で就職が困難なため技能実習に参加しているという声も聞かれました。この傾向は、日本の地方における就職難という社会問題と、技能実習制度との関連性を示唆しています。高学歴化は、実習生側の能力や期待値の変化を反映しており、制度の対応も変化させていく必要があることを示しています。
3. 北海道における技能実習の特殊性と今後の展望
北海道では、気候の影響により冬の農閑期が存在するため、多くの技能実習生の滞在期間は1年未満、総実習時間は約1300時間程度です。これは、他府県での2~3年間にわたる実習とは大きく異なる点です。そのため、北海道の技能実習生は、8ヶ月程度の滞在期間に必要な日本語能力を習得することが重要になります。 実習生が楽しく日本語を学習し、技能を習得し、日本文化を理解し、実習生活全体を充実させるためには、何らかの動機付けが必要です。 帰国後、日本の農業技術を自国に還元するためには、日本や実習先の農業事情を理解することが不可欠であり、この点を踏まえた日本語学習プログラムの開発が重要です。 今後、TPP対応や過疎地域の農業維持のためには、労働集約的な施設型農業への転換が必要であり、そのためには労働力の確保が不可欠です。技能実習制度の弾力的な運用、あるいは将来的な「短期就労制度」への移行などが検討課題として残されています。
