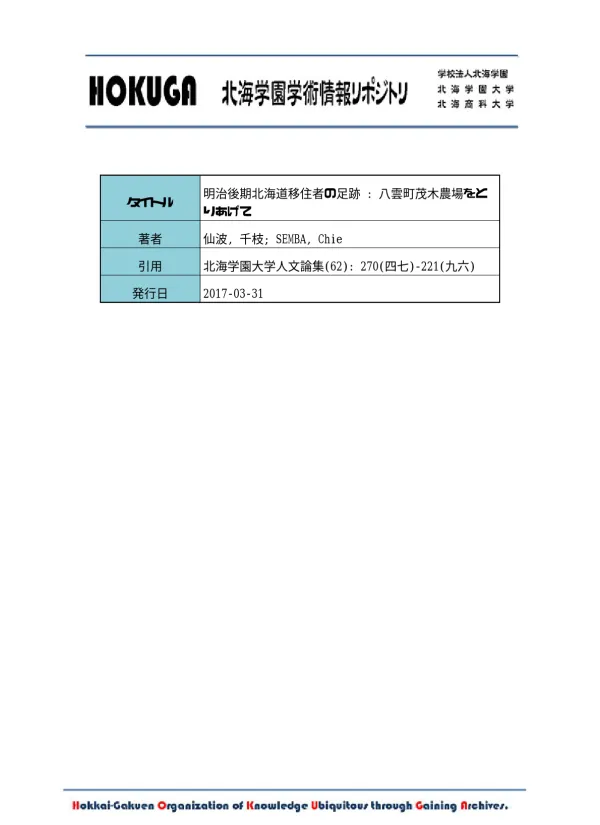
北海道八雲町茂木農場:明治後期移住史
文書情報
| 著者 | Senba, Chie |
| 専攻 | 歴史学 (History) / 北海道研究 (Hokkaido Studies) |
| 文書タイプ | 論文 (Article) / 学位論文 (Thesis - 可能性あり) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.30 MB |
概要
I.北海道八雲町茂木農場の開拓と発展
明治時代後期、北海道八雲町に設立された**茂木農場(Mogi Farm)は、本稿の主題である。多くの埼玉県児玉郡からの移住者(Iju)**によって開拓されたこの農場は、当初は粗悪な土地であったものの、八雲村に隣接していたため耕地として発展の可能性を秘めていた。特に、遊楽部川沿岸の肥沃な土地は農作物の栽培に適していた。**開拓(Kaitaku)**の過程において、茂木清兵衛をはじめとする多くの開拓者たちの努力と、移住者同士の強い地縁による結束が、農場の長期的な存続に大きく貢献したと言える。初期の農場は、米などの自給生産に加え、養蚕や養鶏などの副業も盛んであった。
1. 茂木農場の地理的条件と初期の状況
文書によると、茂木農場は山がそびえ、渓谷が深く、広さは狭く、土地の質も粗悪であったと記述されています。しかしながら、八雲村に隣接しているため、将来耕地となる可能性は高いとされています。遊楽部川沿岸は、川の流れが蛇行し、支流が合流する平坦な場所で、草木が繁茂し、土壌は肥沃であるとされています。ただし、その面積はそれほど広くありませんでした。北海道庁編の移住者成績調査にも言及されていますが、具体的な内容は本文からは読み取れません。移住地としての魅力は十分とは言えないとされており、これは、土地の質や面積の狭さなどが関係していると考えられます。 初期の開拓は困難を極めたと推測されますが、八雲村への近接性と遊楽部川沿岸の肥沃地が、後の発展の礎となったと言えるでしょう。この地理的条件と初期の困難な状況が、茂木農場の歴史において重要な出発点となっています。
2. 茂木農場の設立と初期の開拓者
茂木農場は、八雲村への移住が盛んだった時期に開設されました。本稿は、茂木農場の開設とその後の経緯を追うことを通じて、その歴史を明らかにしようとしています。明治38年10月25日、指令第4586号によって、熊本県玉名郡鍋村の立山哲壮から茂木清兵衛への隣接区画の譲渡が行われています。貸付台帳には、茂木清兵衛の住所として埼玉県児玉郡本泉村大字太駄村54番地が記載されています。これは、埼玉県児玉郡からの移住者が多いことを示唆しており、彼らの開拓努力が茂木農場の発展に大きく貢献したと考えられます。高知県の大井治秋が茅部郡森村の土地を購入して坂本農場とした事例も触れられており、当時の土地取得や開拓の状況の一端が示されています。 また、明治32年11月以降、寅治とその実父五郎七は後志国磯谷郡南尻別村の国有未開地の貸付を願い出て開拓に乗り出したという記述も見られます。これは、当時の開拓における困難さと、開拓者たちの強い意志を示すエピソードと言えるでしょう。
3. 茂木農場と地域社会との関わり
茂木農場は、単なる農場としてではなく、地域社会と深く関わって発展していきました。教授場の開設にあたっては、鉛川および大関農場の住民から寄付が募られ、校舎が新築されたという記述があります。これは、地域住民の農場への協力と一体感を示す重要な事例です。移住前の茂木家と柴崎家の養子縁組は、両家の強い結束を示しており、茂木農場の長期的な存続の一因となったと考えられます。明治40年には、八雲村に大関尋常小学校付属鉛川特別教授場が開設され、後に八雲尋常高等小学校付属鉛川特別教授場となりました。大正9年には児童数が最多の67名に達したと記録されています。これは、農場周辺の地域社会の発展と、教育への関心の高さを示しています。昭和8年には、元鉛川神社と元茂木農場神社(八幡神社)が合併し、現在地に遷転したと記述されています。これらの記述は、茂木農場が地域社会に深く根付いていたことを示しています。
II.茂木農場の所有者と経営変遷
**茂木農場(Mogi Farm)**の所有者は、明治43年から昭和10年にかけて複数回に渡って変更された。初期の所有者である茂木清兵衛から始まり、原鉄五郎、山村芳夫、秋山専蔵、植木義三郎、植木リク、樫部保と続き、最終的には北海道拓殖銀行が所有権を取得した。所有者が変わっても、柴崎玄治郎を中心とした住民たちの努力により、農場は継続的に運営され、**酪農(Rakuno)**へと転換していく。
1. 明治期から大正期の所有者変遷
文書には、茂木農場の戦前期における所有者変遷が記述されています。明治43年9月5日には茂木清兵衛(埼玉県児玉郡本泉村)が所有者として記録されています。その後、大正4年5月7日には原鉄五郎(埼玉県児玉郡若泉村)、大正5年1月11日には山村芳夫(滋賀県犬立郡彦根町)、大正6年6月9日には秋山専蔵(宮城県栗原郡姫松村)、大正7年8月3日には植木義三郎(兵庫県武庫郡精道村)、大正10年11月19日には植木リク(東京市芝区)と、比較的短い期間で所有者が何度も変更されています。これらの所有者変更の背景や理由については、文書からは直接的には読み取れません。しかし、所有者の出身地が様々であること、また、東京や近隣の府県出身者も含まれていることから、農場の経営状況や社会情勢の変化を反映している可能性が考えられます。 植木リクは、植木義三郎の妻であり、義三郎はこの頃死亡したと推測されます。所有者の変遷は、農場の経営状況や社会情勢の変化と密接に関連していると考えられ、その詳細な解明は今後の研究課題と言えるでしょう。
2. 大正期後半から昭和初期の所有者と経営の安定
大正12年7月7日には樫部保(東京市牛込区)が所有者となり、昭和2年5月28日には神林知雄(東京市牛込区)が所有者となりました。所有者の変遷は続いたものの、この期間、柴崎玄治郎を中心とした住民たちの努力により、農場は継続的に運営されていました。これは、所有者の変更があっても、農場経営の基盤が住民たちの強い結束によって支えられていたことを示しています。 所有者が変わろうとも、日々の営みを続けた住民たちの強さが茂木農場の特色であり、その継続性において重要な役割を果たしたと言えるでしょう。神林知雄の父である虎雄も、昭和5年に現代海戦概念図などを寄付しており、これも地域との強い結びつきを示唆しています。 この期間は、所有者の変遷はあるものの、住民による安定した経営が維持されていたことが、重要なポイントと言えます。
3. 北海道拓殖銀行への所有権移転とその後
最終的に、茂木農場は函館区裁判所における競売を経て、昭和10年6月3日、株式会社北海道拓殖銀行の所有地となりました。同銀行は、茂木農場だけでなく周辺の土地も取得したと記述されています。これは、北海道拓殖銀行が、この地域への更なる開発や投資を計画していた可能性を示唆しており、茂木農場の経営は新たな段階に入ったことを意味します。 この所有権移転は、茂木農場の歴史における大きな転換期であり、それまでの住民による経営から、企業による経営への移行を示しています。 この移転の背景や、その後の農場の経営状況については、文書からは詳細な情報が得られませんが、北海道拓殖銀行による取得は、茂木農場の歴史において重要な節目を示す出来事であると言えるでしょう。
III.酪農への転換と地域社会への貢献
大正時代以降、茂木農場(Mogi Farm)では酪農が主要な産業となり、住民たちは次第に酪農技術を習得し、収入の向上に繋げた。牛乳や乳製品の需要の高まりを受け、農場の酪農は成功を収め、地域社会にも貢献した。特に、関東大震災後の関税免除により、安価な外国産乳製品が流入する逆風の中でも、八雲町における北海道煉乳株式会社の存在が地域酪農を支えた。この成功は、農家の生活向上に大きく寄与し、**農業(Nogyo)**における新たな可能性を示した。
1. 酪農への転換と技術習得
文書によると、茂木農場の住民たちは、大正時代以降、酪農業を導入することに成功しました。これは、それまでの農業形態からの大きな転換であり、住民たちの努力と適応能力の高さを示しています。 所有者が変わっても、柴崎玄治郎を中心とした住民たちは日々の営みを続け、酪農技術を習得し、徐々に収入を向上させていった様子がうかがえます。冬季には上鉛川の山林や田下の木工所へ出稼ぎに行くこともあったと記述されており、酪農以外の収入源も確保していたことがわかります。これは、酪農経営の不安定さを補うための戦略であり、住民たちの生活の知恵を示しています。 彼らは、単に酪農を行うだけでなく、収入につなげるための知恵を身につけ、生活を向上させていった様子が記述されており、当時の厳しい環境下における住民たちの努力と工夫が伺えます。
2. 酪農の成功と地域社会への経済的貢献
酪農への転換は、茂木農場にとって大きな成功をもたらしました。毎月牛乳の代金を得られるようになったことは、稲作中心の農業とは大きく異なる点であり、経済的な安定をもたらしたと考えられます。 関東大震災後は、乳製品の関税が免除された結果、安価な外国産乳製品が増加するなど、乳製品製造業には逆風が吹きましたが、八雲町では北海道煉乳株式会社が存在し、地域酪農を支えたと記述されています。これは、地域産業としての酪農が、外部からの競争にもある程度対応できる体制を築いていたことを示唆しています。 山間部出身者にとって、五町歩の土地を持つことは夢のようなことであったと記述されており、たとえそれが自分の土地ではなかったとしても、酪農による収入が生活向上に大きく貢献したことがわかります。
3. 酪農と異なる職業観 そして地域社会との連携
茂木農場における酪農の成功は、単なる経済的な成功にとどまらず、住民たちの職業観にも変化をもたらしました。自給用の米生産を目指す人々とは異なる職業観が、酪農経営を支えたと推測できます。 毎月牛乳の代金を得られるという安定した収入は、稲作と大きく異なる点であり、生活の安定と向上に繋がったと考えられます。 また、小鹿野町からの移住者が多い茂木農場において、地縁による強い結束が、農場を離れても生活を可能にする背景となっていたと記述されています。これは、地域社会との連携が、農場の発展と住民たちの生活安定に貢献したことを示しています。 酪農という産業を通して、茂木農場の住民たちは経済的な自立を達成し、同時に地域社会との緊密な連携を築き上げたと言えるでしょう。
IV.農民美術と木彫り熊
茂木農場では、**木彫り熊(Kihori Kuma)**の制作も盛んであった。伊藤政雄氏をはじめとする住民たちは、**農民美術(Nomin Bijutsu)**として高い評価を得た木彫り熊を制作し、地域文化の活性化にも貢献した。伊藤政雄氏は、八雲村創業者以来の小学校長である伊藤直太郎氏の弟であり、その温厚な人柄と高い技術が木彫り熊制作を支えた。また、寒山十倉兼行氏も指導にあたった。
1. 伊藤政雄と木彫り熊の制作
茂木農場では木彫り熊の制作が盛んであり、その代表的な人物として伊藤政雄が挙げられています。伊藤政雄は、八雲村創業者以来の小学校長である伊藤直太郎の弟であり、大新で農業に従事していました。彼の作品は木彫りの部で第一等を受賞しており、その温厚な人柄と高い技術が評価されています。 彼の作品は、同町砂蘭部の伊藤政治氏が刻んだ熊を始め、狸や稲荷、お雛様、蒔絵の柄箸など多様な作品が含まれており、長野農民美術研究所の作品を参考にしていると考えられています。 これらの作品は、田園生活者の趣味向上に新しい光を与えるものとして高く評価されており、伊藤政雄の技術と芸術性が、茂木農場の文化の一端を担っていたことがわかります。
2. 寒山十倉兼行による指導と農民美術の隆盛
伊藤政雄以外にも、東京で日本画を学んだ後、大関尋常小学校付属夏路特別教授場で教員をしていた寒山十倉兼行が、木彫り熊制作の指導にあたっていました。兼行は芸術家気質が強調されることが多いですが、彼は茂木農場の酪農家でもありました。 彼は哲学的なものに関心を持ち、独自の芸術世界を築き上げ、洋行計画が頓挫した後は、酪農の傍ら彫刻作品を制作することに専念していきました。 伊藤・十倉らの指導を受けた者の中には、模倣に疑問を感じ、独自性を追求する者もいたと記述されています。これは、農民美術の独自性と発展を示しており、地域に根付いた独自の芸術文化が育まれていたことを物語っています。 昭和2年に秋田県で開催された北海道奥羽六県連合副業共進会で伊藤政雄が第一等を獲得したことが、他の住民たちの木彫り熊制作への関心を高めるきっかけとなったと推察できます。
3. 木彫り熊の制作と地域文化への貢献
木彫り熊の制作は、茂木農場の住民たちの生活の一部であり、地域文化を形成する重要な要素でした。 制作に携わった人々は、単に趣味として制作していたわけではなく、地域社会に貢献する活動として捉えていた可能性があります。 彼らの作品は、単なる工芸品ではなく、農民美術として評価されており、これは、彼らの生活や文化、そして自然環境に対する深い理解に基づいていると考えられます。 ロシアの農民の営みに影響を受けた山本鼎が、大正8年12月に日本農民美術練習所を長野県に開設していたという記述もあり、当時の農民美術運動との関連性を示唆しています。 茂木農場における木彫り熊の制作は、地域社会に独自の芸術文化を根付かせ、その発展に貢献したと言えるでしょう。
V.茂木農場と周辺地域
**茂木農場(Mogi Farm)**周辺の土地は、大正末期には函館で海運業を営む宮本武之助によって購入されている。これは、八雲町が海運業者から注目されていたことを示唆している。また、農場の発展は、旧会津藩士が斗南ヶ丘で行った開拓の精神を受け継いでいると推測できる。 **北海道(Hokkaido)**における農業発展の一端を垣間見ることができる。
1. 茂木農場周辺の土地取得と海運業との関連
茂木農場周辺の土地は、大正末期に函館で海運業を営む宮本武之助によって購入されています。この事実は、八雲町が当時、海運業者から注目されていたことを示唆しています。 海運業との繋がりは、農場の経済活動や物資の輸送において重要な役割を果たしていた可能性があり、農場の発展と地域経済の動向を理解する上で重要な要素と言えます。 宮本武之助による土地取得の具体的な目的や背景については文書からは読み取れませんが、この事実は、茂木農場とその周辺地域が、当時、経済的にも重要な位置を占めていたことを示唆する重要な情報です。 この土地取得は、茂木農場単体の歴史だけでなく、八雲町の経済発展や地域社会の動向を考察する上で重要な要素となります。
2. 旧会津藩士と斗南ヶ丘開拓との関連性
文書では、茂木農場が位置する地域が、明治3年に旧会津藩が斗南藩となり、藩庁を設けて開拓を行った斗南ヶ丘に隣接していることが触れられています。この記述は、茂木農場の開拓の歴史と、旧会津藩士の開拓精神との繋がりを示唆しています。 旧会津藩士たちが下北にかけた想いを汲み取っているという表現から、茂木農場の開拓者たちは、彼ら先人の開拓精神を受け継いでいた可能性があります。 この歴史的背景は、茂木農場の開拓における精神的な支柱や、住民たちの土地に対する意識を理解する上で重要な要素と言えるでしょう。 斗南ヶ丘開拓の歴史と茂木農場の歴史を比較検討することで、この地域の開拓史における新たな知見が得られる可能性があります。
3. 茂木農場と地域社会の繋がり そして地縁の重要性
文書全体を通して、茂木農場は地域社会と深く結びついて発展してきたことがわかります。 農場の住民たちは、地域社会との繋がりを大切にしており、その結束の強さが農場の長期的な存続に貢献したと考えられます。特に、小鹿野町からの移住者が多いことから、地縁による結束が、農場を離れた後の生活を可能にする背景となっていたと推測できます。 これは、単に経済的な繋がりだけでなく、精神的な支えや助け合いといった、人々の繋がりを重視する文化が茂木農場と地域社会に存在していたことを示唆しています。 この地縁による結束は、茂木農場が困難な状況を乗り越えて発展してきた要因の一つであり、地域の社会構造や人々の生活様式を理解する上で重要な要素となります。
