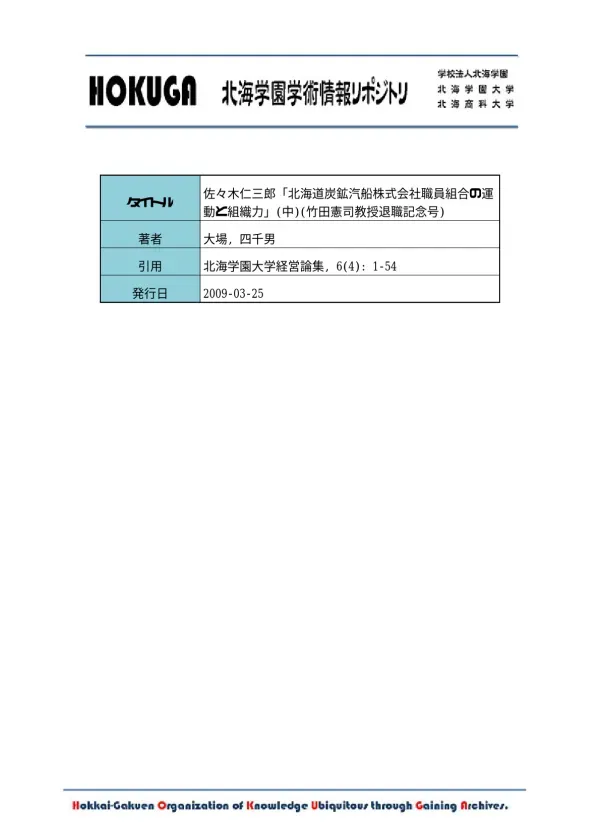
北海道炭鉱汽船合理化闘争史
文書情報
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 840.23 KB |
| 著者 | 大場 四千男 |
| 文書タイプ | 論文 |
概要
I.不当解雇と労働争議 Wrongful Dismissal and Labor Disputes
北炭(Hokutan)は多数の従業員を**不当解雇(fudō kaiko)**し、大規模な労働争議を引き起こしました。解雇された約100名は北炭退職社員会を結成、解雇撤回を要求し、北炭社連の誕生直後には29名の解雇撤回を勝ち取りました。この事件は、**石炭(sekitan)**業界における労働組合の力と、**労働争議(rōdō sōgi)**の激しさを示す重要な出来事でした。
1. 北炭における不当解雇問題の発覚と組合の対応
文書によると、北炭(Hokutan)による解雇には、誰が見ても不当解雇と思われる者が含まれていました。中には、解雇理由の説明を職場長に連日求める者もいたとあります。 解雇された者の中には、解雇直後に別の炭鉱で再就職し、労働組合の役員として活動していた者もいたと記述されており、解雇の不当性を示唆する記述となっています。この状況を受け、第三次解雇の対象となった約100名は、北炭退職社員会を結成し、解雇撤回を要求して闘うことを決議しました。これは、会社側の行為に対する強い反発と、労働組合による組織的な抵抗の始まりを示しています。具体的な行動としては、14名の炭鉱代表者が上京し、本店との交渉を行いました。この交渉は、北炭社連の誕生直後に行われたものであり、北炭社連はその運動を受け継ぎ、団体交渉を通じて29名の解雇撤回を実現させました。これらの29名は昭和21年9月1日付で復職を果たしました。会社側は、従来通りの存続が決まったことを祝し、労使協力による業績伸展を謳い文句に、職員一人当たり平均1092円の一時金を支給しました。この一時金支給は、表面的な労使協調を演出するものであった可能性を示唆しています。
2. 労働争議の激化と会社側の対応
不当解雇問題に端を発した労働争議は、その後も激化の一途を辿りました。北炭労連は、本店、札幌、小樽支店の3箇所を無期限ストにする実力行使に出ました。スト参加者の減収は労連のカンパで保障するという合意がなされていたことが記述されています。しかし、小樽の組合が反対し、本店が保留という結果となり、ストは中止せざるを得ませんでした。会社の一方的な措置を阻止できず、組合側は闘いの矛を収めることになったとあります。この時点では、北炭職連は労働協約の交渉中で、人事権の同意権確保のために闘っていました。天塩炭鉱の廃山問題に関しても、組合員は廃山を止む無しと考える一方で、労働協約交渉との関連で組合員の犠牲を回避するため、実力行使も辞さないという姿勢を示していたことが記述されています。具体的な要求としては、炭鉱廃止に伴う特別手当の支給などが挙げられていました。結果的に天塩炭鉱職員組合は昭和26年3月23日に解散し、組合員はそれぞれ新たな職場へと向かいました。この一連の出来事は、北炭における労働組合と経営陣の対立が激しく、労働者の立場が非常に厳しい状況にあったことを示しています。
II.賃金三原則とドッジライン Wage Principles and the Dodge Line
1948年、芦田内閣の総辞職後、第二次吉田茂内閣が成立。GHQは賃金三原則と経済安定九原則を発表し、日本の経済自立路線を推進しました。これは、賃金抑制と企業の自立化を促す**ドッジライン(Dodge Line)**政策につながり、北炭を含む日本の企業に大きな影響を与えました。この政策は、後の労働争議にも大きく関わります。
1. 賃金三原則と経済安定九原則の発表
昭和23年10月、芦田内閣の総辞職に伴い第二次吉田茂内閣が発足しました。日本経済の自立を掲げていたGHQは、翌月『賃金三原則』を発表、更に12月には『経済安定九原則』を指令しました。『賃金三原則』は、賃上げによる補給金の増額や赤字融資、物価に影響する公定価格の値上げを禁止し、ストライキ中の石炭企業への融資を停止するというものでした。一方、『経済安定九原則』は、均衡予算、徴税促進、賃金安定、信用拡張の制限、物価統制強化、為替統制強化、輸出促進、増産、食糧供出改善といった内容で、経済の安定化を目指していました。これらの原則は、企業に対して自立体制の確立を、労働者に対しては生産性向上に基づく賃上げを強制する政府の方針を示すものでした。 この政策は、企業の自主的な経営努力を促す一方、労働者の賃金上昇を生産性と結びつけることで、インフレ抑制と経済安定を目指したものでした。これは、戦後の日本経済において、アメリカの影響下で進められた重要な経済政策でした。
2. ドッジラインの導入と経済政策の転換
翌昭和24年2月には、アメリカのジョセフ・M・ドッジが来日し、アメリカの経済援助や国内補助金に頼る「竹馬経済」からの脱却、自主化路線を提唱しました。これがいわゆる「ドッジライン」です。ドッジラインは、緊縮財政、通貨改革、貿易自由化などを中心とする経済政策で、インフレ抑制と経済の安定化を図ることを目的としていました。この政策は、GHQの指令に基づいた賃金三原則や経済安定九原則と連携しており、戦後日本の経済復興に大きな影響を与えました。 ドッジラインは、日本経済の自立を促進するための政策として位置づけられていましたが、同時に、賃金抑制や緊縮政策によって労働者層に大きな負担を強いる側面もありました。この政策は、後の労働争議や社会問題にも繋がる重要な政策転換点となりました。特に石炭業界は、このドッジライン政策の影響を大きく受け、合理化や企業再編を迫られることになります。
III.希望退職募集とストライキ Voluntary Retirement and Strikes
朝鮮戦争特需後の景気後退を受け、北炭は1951年、職員の**希望退職(kibō taishoku)**募集を実施。組合は当初反対しましたが、退職金増額を目当てとする組合員もいたため、勧誘・勧告を阻止する条件でこれを容認。しかし、その後も合理化が進み、1953年には全山一斉ストが発生。これは、**合理化(gōrika)**を進める会社と、雇用を守る労働組合との激しい対立を示しています。組合員71名を含む112名が退職しました。
1. 希望退職募集の開始と組合の対応
朝鮮戦争特需の終焉を見据え、各石炭会社は合理化を推し進め、自主経営体制の強化を図りました。北炭もその例外ではなく、天塩鉱の廃止問題が解決した直後の昭和26年5月2日、職員を対象とした希望退職の募集を発表しました。職連は、基本的に人員削減に反対していましたが、退職金増額を期待して退職を希望する組合員がいることを把握していました。そのため、会社による一方的な退職勧告を阻止するため、個人への退職勧告を行わないことを会社に確約させ、希望退職募集を容認しました。募集締め切りまでに、組合員71名を含む社員112名が退職しました。北炭70年史では、退職者数を115名と記していますが、この食い違いは、資料の誤差や、その後の追加退職者の発生を示唆する可能性があります。希望退職募集の過程において、会社側の当初発表が不十分であったこと、そして人員不足の中で減員による労働強化が組合員に圧し掛かっている現状から、今後の会社動向には十分な警戒が必要であると認識されていました。組合員から直接聞き取った退職理由には、「楽しく働くことができない」といった職場環境に関する問題が多く含まれており、これは深刻な問題として受け止められました。締め切りの5月31日には、予想をはるかに超える40名以上の追加応募があり、これは個々の事情の複雑さを示すものでした。勧誘や勧告といった作為的な行為が見られなかった点は、希望退職募集の本質的な解釈とは別として評価すべき点です。
2. 各山元職組の対応と闘争方針の修正
各山元職組は、職制を通して組合員の「肩叩き」が行われることを警戒し、希望退職募集業務の担当者を指名ストに入れ、業務拒否を行いました。しかし、職階者の中には、組合の警戒をすり抜けて組合員に退職を勧告したり、逆に「大丈夫だ」と宣伝して組合員を離反させるなど、組織的な妨害工作を行う者もいました。このような状況下で、純粋に自由意思で退職を希望する組合員からは、全面阻止の方針と闘い方への懸念、闘争方針の修正を求める声が上がりました。この事態を受け、拡大闘争委員会は方針を修正しました。修正された方針は、1)純粋な希望退職は認める、2)希望退職募集後に解雇通告を受けた者は一括返上する、3)解雇通告を受けた者には給与補償を行う、というものでした。会社は9月19日時点で、夕張103名、平和48名、幌内103名、空知67名、合計321名の組合員からの希望退職を受け付けました。職連は、このままでは会社の思惑通りになると判断し、会社に希望退職募集の中止を求め、9月25日から全山職組の無期限ストを指令しました。しかし、夕張以外の各職組は、希望退職者が既に予定数に達していることを理由に戦術転換を求め、最終的には夕張職組を重点としたストとなりました。最終交渉の結果、会社提案をほぼ認める形でストは妥結し、石炭鉱業合理化臨時措置法の制定という結果に繋がりました。
IV.石炭産業の合理化と三鉱分離 Rationalization of the Coal Industry and Separation of Three Mines
エネルギー革命と貿易自由化により石炭業界の将来が不透明となる中、北炭は経営再建のため、**三鉱分離(sankō bunri)**と大規模な人員整理を計画。**希望退職(kibō taishoku)募集を複数回実施し、多くの従業員が退職を余儀なくされました。これに対し、労働組合はストライキ(suto)を繰り返して抵抗しますが、最終的には三鉱の分離独立という形で事態は収束しました。 この過程で、多くの労働争議(rōdō sōgi)**が発生し、組合員の動揺も大きくなりました。
1. 石炭業界を取り巻く厳しい状況と北炭の合理化
朝鮮戦争終結後の世界的景気低迷により、日本の石炭業界は需要減退と貯炭増加という深刻な問題に直面しました。この状況を受け、石炭資本は合理化を強力に進める一方で、政府に対して石炭対策の緊急樹立、重油・輸入炭消費の調査など、保護・助成策を求めました。昭和28年には、高炭価問題が表面化し、鉄鋼・硫安業界から大幅な価格引き下げ要求が出され、政府は通産省に単価引き下げの具体策検討を指示しました。各石炭会社は、増産体制の構築や中小炭鉱の復帰を促すなど、対応に追われました。全国の出炭量は4500万トンに達し、需要も増加しましたが、北炭は原料炭供給の逼迫、一般炭の貯炭急減という厳しい状況にありました。その後、昭和31年に東京ガス、富士鉄と長期契約を締結し、原料炭の70%を安定供給できる体制を構築したことで、販売の合理化、生産の安定化、経理面の改善に繋がりました。しかし、これらの努力にも関わらず、石炭業界全体としては、エネルギー革命や貿易自由化など、更なる合理化圧力にさらされることになります。
2. 北炭の三鉱分離計画と労働組合の対応
エネルギー革命による石炭業界の衰退、貿易自由化による国内炭保護政策の後退、夕張災害による金融圧迫といった厳しい経営環境下で、北炭は生き残りを賭けて大胆な経営再編に乗り出しました。それは、三鉱(万字、美流渡、赤間)の分離と、希望退職募集による大幅な人員削減でした。会社側は、金融逼迫、貿易自由化によるコスト削減圧力、政府の石炭鉱業保護政策への期待薄れ、他社の急速な合理化、夕張災害による甚大な損害などを理由に、三鉱分離と希望退職募集を提案しました。しかし、労働組合側は、会社側の提案が、長計協定に抵触し、労使間の信義にもとるものだと反発しました。会社側は、再建にはこの方法しかない、現状では白紙撤回はできないと主張し、労働組合側は一方的な再建案の強行を阻止すると反論し、共同団交は決裂しました。希望退職募集開始と同時に全山一斉24時間ストが行われ、その後もストライキは繰り返され、会社側は希望退職募集を複数回に渡って実施しました。最終的に、職員395名、鉱員1314名にのぼる応募者がありましたが、会社は更なる減員が必要だと主張し、三鉱を分離し、租鉱炭鉱として新会社を設立するという計画を発表しました。この計画は、労働組合と会社との激しい対立と、厳しい経営状況を表すものです。
3. 闘争方針の転換と三鉱分離の決断
三鉱分離計画に対する北炭職連の第12回闘争委員会では、分離対象三鉱の組合員の大半が、残留もしくは他鉱への配置転換を希望していることが明らかになりました。エネルギー革命下の厳しい石炭事情、他社の合理化の進展、三井三池争議の結果などを鑑み、三鉱分離撤回を目標とした闘争を継続することが困難であると判断されました。組合員の中には、ヤマへの愛着から、労働条件の多少の悪化を容認しても残って働きたいという意見が多くありました。これらの状況から、闘争方針は条件闘争への転換を余儀なくされました。 北炭職連は、三鉱分離反対という指標を掲げた闘争には参加できないとしながらも、新会社を認めず、組合員を北炭従業員として就労させ、地位保全のための仮処分を札幌地裁に申請するなど、独自の行動方針を決定しました。 この決定は、組合員の実情と業界の現実を踏まえた、苦渋の決断であったと言えるでしょう。 この後、新会社の就労が開始され、万字、美流渡、赤間鉱において労組側は「北炭従業員」として強行就労しました。この三鉱分離は、石炭産業の合理化と企業再編を象徴する出来事であり、労働組合と会社との間の複雑な関係と、厳しい現実を反映した結果となりました。
V.北炭建設 森林工業への社員移籍 Transfer of Employees to Hokutan Construction and Hokkaido Forest Industries
北炭は、北炭建設株式会社と北海道森林工業株式会社への社員移籍を提案。組合は当初反対しましたが、厳しい石炭業界の状況と、雇用維持を考慮し、条件交渉を経て移籍を容認しました。この移籍は、北炭の企業再編における重要な局面であり、**合理化(gōrika)**政策の一環として位置づけられます。
1. 北炭建設 北海道森林工業への社員移籍提案
昭和38年3月1日、北炭は職連と都連に対し、北炭建設株式会社および北海道森林工業株式会社に出向中の社員をそれぞれの会社に移籍させる提案を行いました。同時に、木材部鹿の谷駐在(木挽場)の非組合員1名と組合員4名も北海道森林工業への移籍を提案しました。これは、北炭の企業再編の一環として、関連会社への人員配置転換を図るものでした。この提案は、単なる人員配置転換ではなく、北炭の経営戦略、ひいては石炭産業全体の構造変化を反映したものであったと考えられます。会社側の意図としては、人員整理と同時に、関連事業への投資を促進し、経営の多角化を図ることで、石炭産業の不透明な将来に備えるという狙いがあったと推測されます。 しかし、組合側は、38年度計画のみの協議には応じず、42年度までの長期計画の提示を要求しました。会社側はこれに応じず、協議は長期休会に入りました。
2. 労使協議の再開と神威 空知鉱閉山問題
その後、4月9日に労使協議会が再開され、5月4日までに各鉱業別の分科会で協議が進められました。職連は職員分科会で職員に関する問題を検討していました。この中で、会社は神威鉱の閉山に続き、空知鉱も昭和39年9月末に閉山するという重大な提案を行いました。この提案は、組合にとって受け入れがたいものであり、急遽職労連合同闘争委員会が組織され、闘争態勢が整えられました。会社との対立は、移籍問題から更に深刻な閉山問題へと発展しました。第50回臨時大会では対置要求が決定され、北炭職連は6月14日、労連と共に統一要求書を会社に提出しました。6月17日からは札幌で交渉が始まり、7月3日までに11回の統一交渉と5回の職連分科会が行われ、対立点が明確になりました。7月8日には炭労、職労連が通産省との折衝を行い、9日から東京交渉を開始しましたが、進展はありませんでした。7月22日、会社側は、政府の石炭政策と石炭鉱業審議会の経過から、空知鉱と神威鉱は当初の提案通り閉山するか、または両鉱を統合して第二会社とするしかないとの回答をしました。組合側は、北炭の枠内で両鉱の存続を求め、再考を促しました。しかし、その他の諸条件の改訂についても不満があったため、職労連は7月24日一斉1時間50分スト、7月26日には一斉24時間ストを通告しました。このストライキは、会社側の合理化策に対する組合側の強い抵抗を示しています。
3. 妥結と神威鉱閉山 空知鉱分離独立
7月31日、団体交渉は第一分科会(空知・神威鉱の件)、第二分科会(諸条件の件)、第三分科会(幌内鉱業所の件)、第四分科会(職連関係の件)に分かれて徹夜で交渉が行われ、8月1日午前9時30分にようやく諒解点に達しました。職労連はストを解除し、神威鉱の事実上の閉山と、空知鉱の北炭からの分離独立(10月1日新会社発足)が決まりました。この結果、会社側の合理化策は、組合側の抵抗にもかかわらず、部分的に容認された形となりました。この妥結は、石炭産業の衰退という現実を反映したものであり、労働組合も、現実的な対応を迫られたことを示しています。 この過程で、空知鉱と神威鉱の閉山問題、そして北炭建設・北海道森林工業への社員移籍問題が、北炭の企業再編における大きな転換点となったことがわかります。
VI.空知鉱業所の合理化と神威 空知鉱の閉山 Rationalization of the Uchi Mine and Closure of Kamui and Uchi Mines
石炭鉱業調査団の来山を受け、空知鉱業所は独自に合理化案を発表。人員縮小、生産性向上、賃金体系の是正などを盛り込みました。最終的に神威鉱は閉山、空知鉱は北炭から分離独立することとなり、これも**合理化(gōrika)政策と石炭(sekitan)**業界の厳しい現実を反映した結果となりました。
1. 石炭鉱業調査団の来山と空知鉱業所の合理化計画
昭和37年8月4日、空知鉱業所は青木茂所長名で告示を発表しました。その内容は、石炭鉱業調査団の来山と、不良炭鉱のスクラップ強化という方針に基づき、個々の炭鉱の将来が検討されるというものでした。赤字の炭鉱はスクラップ(閉山)の対象となることが明示され、空知鉱業所もその対象となる可能性が高いとされました。そのため、空知鉱業所は、合理化を推進し、スクラップ対象から脱却するために従業員の協力を求めるというものでした。 同時に、会社は空知職組、空知労組、神威労組に対し、人員縮少、標作引上げ、賃金の慣行是正、職場規律の確立、出稼向上対策、福利厚生関係の緊縮など13項目にわたる合理化案を提示しました。この合理化案は、空知鉱業所の存続をかけた、極めて厳しい内容のものでした。電灯料、水道料、清掃費などは新会社が決定することになりましたが、石炭については現物支給か金額支給かは別として現状維持を目指しました。職連と都連は、会社の将来と石炭鉱業の現状を踏まえ、止むを得ない措置と判断しつつも、移籍後の労働条件については現行水準の確保を目指し、関係者との交渉を重ね、3月19日に合意に達しました。しかし、この合理化計画は、空知鉱業所のみならず、周辺地域全体に大きな不安を与えたのです。
2. 神威鉱閉山と空知鉱分離独立の決定
会社による合理化提案と石炭鉱業調査団の来山は、空知地域全体に大きな不安をもたらしました。その中で、昭和38年3月1日、会社は職連と都連に対し、北炭建設株式会社および北海道森林工業株式会社に出向中の社員の移籍を提案しました。組合側は、38年度計画だけの協議には応じず、42年度までの長期計画の提示を要求、会社側はこれに応じず長期休会に入りました。しかし、4月9日に労使協議会が再開し、協議が続けられる中、会社は神威鉱の閉山に続き、空知鉱も39年9月末に閉山するという重大な提案をしました。これにより、職労連合同闘争委員会が組織され、会社との対立が激化しました。第50回臨時大会で対置要求を決定した北炭職連は、6月14日に労連と共に統一要求書を会社に提出、札幌、東京での交渉が行われましたが進展は見られませんでした。7月22日、会社は政府の石炭政策などを理由に、空知鉱と神威鉱の閉山、もしくは統合による第二会社設立を回答しました。組合側は北炭の枠内での存続を強く求めましたが、7月24日には一斉1時間50分スト、26日には一斉24時間ストに突入しました。 最終的に、8月1日の交渉で妥結に至り、神威鉱は事実上閉山、空知鉱は北炭から分離し、10月1日に新会社として発足することになりました。
