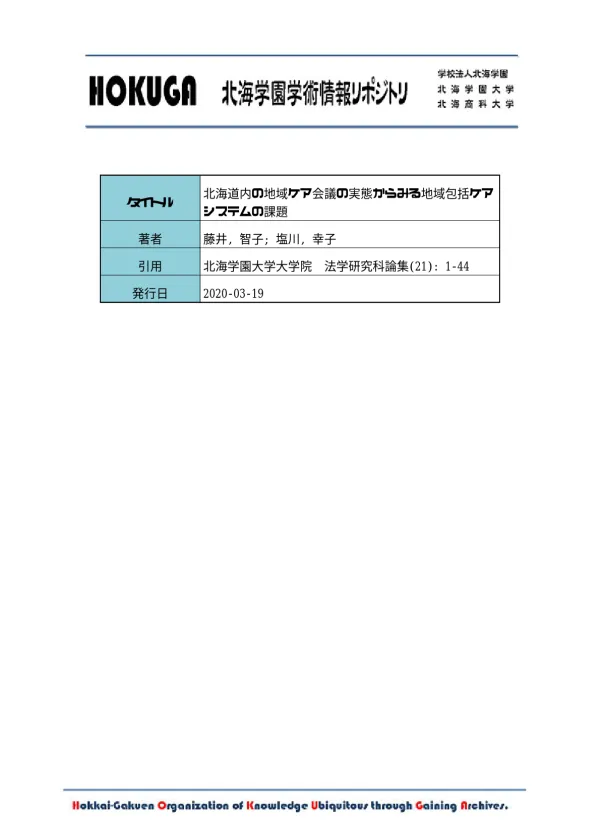
北海道版地域包括ケア:地域ケア会議の実態調査
文書情報
| 著者 | 藤井 智子 |
| 学校 | 法学研究科 |
| 専攻 | 法学 |
| 文書タイプ | 論集 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.93 MB |
概要
I.高齢化が進む地域における地域包括ケアシステムの現状と課題
本研究は、北海道の地域包括支援センターにおける地域ケア会議の実態と課題を明らかにすることを目的とした。特に、超高齢社会における高齢者介護の困難さ、医療資源の少なさ、医師不足、多職種連携の不足といった問題に焦点を当て、地域包括ケアシステムの構築に向けた課題を調査した。特に、小規模自治体における地域包括ケアシステムの推進における困難さ、行政と医療機関の連携不足、地域ケア会議の有効性などを分析した。
1. 高齢化の進展と地域包括ケアシステムの必要性
日本の高齢化は加速しており、2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、要介護高齢者が大幅に増加すると予測されている。このため、厚生労働省は2025年を地域包括ケアシステム完成の目標年としている。地域包括ケアシステムは、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援を包括的に確保する体制を指す。 このシステムの構築は、各自治体に義務付けられている。 高齢化に伴い、医療や介護を必要とする高齢者の増加、介護力の弱い単身世帯や高齢者夫婦世帯の増加といった社会問題も顕在化しており、2011年の改正において「地域包括ケアシステム」の推進が重点政策となった。 以前はケアマネジメントの質向上や予防ケアプランの立案が課題だったが、高齢化の急速な進展により、より包括的な支援体制の構築が急務となっている。
2. 地域包括ケアシステム構築における課題 医療資源の不足と多職種連携の難しさ
特に小規模で過疎化が進む地域では、医療資源の不足や財政上の課題から、地域包括ケアシステムの構築が困難を極めている。医療機関、特に医師の不足は深刻な問題であり、医療機関との連携強化が不可欠であるにも関わらず、医師の地域ケア会議への参加率は低い。これは、医療機関の忙しさ、地域包括ケアシステムに対する理解不足、行政との連携不足など複数の要因が複雑に絡み合っているためと考えられる。 御調町における公立みつぎ総合病院を中心とした成功事例は、医療機関と行政が一体となり改革を進めた点が成功の鍵となったことを示している。しかし、このような成功事例は稀であり、多くの地域では、医療機関との連携構築に大きな課題を抱えているのが現状である。 また、地域包括支援センターの設置形態(直営・委託)によっても、行政と医療機関の連携状況や地域ケア会議の実施状況に差が見られる。委託の場合、行政の関わり方や委託先の機関の力量によって、地域包括ケアシステムの推進に大きなばらつきが生じる可能性がある。
3. 地域ケア会議の現状と課題 効果的な運営のための改善点
地域ケア会議は、情報交換、地域連携、地域課題の発見と検討、ケアマネジメント支援などに活用されているが、政策立案や地域づくりに繋がる取り組みは不足している。 会議の企画・運営においては、議題・テーマの絞り込みや地域の課題分析に困難を感じている包括支援センター職員が多い。また、医療職への参加依頼が難しい、会議の合意形成が難しい、参加者の問題意識に温度差がある、といった課題も指摘されている。 さらに、小規模自治体では、地域ケア会議の参加者が固定化し、活発な議論が展開されない傾向も見られる。 業務体制の面では、職員の多忙さ、人材不足、業務の整理の必要性などが課題として挙げられており、これらの問題が会議の質や計画的な運営を阻害している可能性がある。 地域ケア会議の活性化のためには、参加者の意識向上、医療機関との連携強化、会議運営スキルの向上、そして何より、自治体職員による積極的な推進姿勢が求められる。
4. 保険者 自治体 の役割と地域包括ケアシステムの未来像
地域包括ケアシステムの構築において、保険者である自治体の役割は極めて重要である。しかし、委託型の地域包括支援センターからは、行政のビジョン不足や保険者としての責任感の欠如といった批判の声が上がっている。 自治体職員は、地域包括ケアシステムをまちづくりの重要な要素と捉え、職員の意識改革や財政面での支援を積極的に行う必要がある。 地域包括ケアシステムの構築には、明確な目標設定と、その目標達成に向けた評価指標の策定が必要不可欠である。 広島県のように、定量と定性評価を組み合わせた評価指標を作成し、行政の役割を明確にすることが有効な手段となるだろう。 北海道のような広域な地域では、広域的な医療連携の取り組みも重要となる。 自治体職員は、地域への愛着を高め、医療職との連携を強化し、粘り強く地域包括ケアシステムの構築に取り組む姿勢が求められる。 このシステムは、単なる行政サービスではなく、地域住民の安心安全な生活を支える総合的な計画であることを理解し、実践していく必要がある。
II.地域ケア会議の実施状況と課題
アンケート調査の結果、地域ケア会議は主に情報交換・情報共有、地域連携、地域課題の発見と検討を目的として実施されていることが分かった。しかし、政策立案や地域づくりに繋がる会議は少なく、医療職、特に医師の参加率が低いことが課題として挙げられた。医療職の参加が少ない原因として、時間的な制約、連携の希薄さ、地域包括ケアシステムに対する認識の相違などが考えられる。また、会議の企画・運営においても、課題分析、テーマ設定、医療職との連携に困難を感じている包括支援センター職員が多いことが明らかになった。
1. 地域ケア会議の目的と実施状況
アンケート調査によると、地域ケア会議の主な目的は「情報交換・情報共有」「地域連携(ネットワーク構築)」「地域課題の発見と検討」「ケアマネジメント支援」であり、これらの目的で会議が実施されているケースが全体の過半数を占めている。その他、「地域づくり」「学習会」「サービスや資源の開発」「政策立案」「地域人材育成」なども目的として挙げられているが、特に「地域に必要な取り組みとして政策の立案」は11.9%と低い割合にとどまっている。会議のテーマとしては、認知症対策を中心とした個別の事例検討が多く、独居高齢者、高齢者夫婦世帯、高齢者と障がい児を持つ世帯、多問題家族、身寄りのない高齢者などへの支援が検討されている。疾患別では、認知症、がん、精神疾患、MCI、終末期疾患などが多くを占めている。支援内容は生活支援、外出支援、自立支援、経済問題、高齢者虐待への対応など多岐に渡る。
2. 医療職の参加率の低さとその要因
地域ケア会議への医療職の参加率は、医師が11.9~12.7%と低い。看護職は約4割、リハビリ関連職種は約36%、薬剤師は約24%の参加率となっている。医師の参加率が低い理由としては、医師を参集範囲としていない地域包括支援センターが約1/4存在すること、約半数のセンターが医療職への参加依頼に困難を感じていることが挙げられる。医療職への参加依頼が難しい要因として、医療職の時間的な制約、忙しさによる遠慮、行政との関係性の希薄さ、会議の目的や意見を求める内容が不明確な点などが考えられる。特に小規模市町村では、医療職自体が少ないため、この傾向が強い可能性がある。また、医療職、特に医師は地域の実情や課題に無関心である、あるいは地域包括ケアに対する理解が低いという批判的な意見も存在する。
3. 地域ケア会議の運営における課題 企画 運営の困難さ
地域ケア会議の企画・運営においては、多くの地域包括支援センターが困難を感じている。特に、議題・テーマの絞り込みと地域の課題分析に課題を感じている割合が高い。具体的な課題としては、検討すべき個別事例の提供が不確実であること、会議の準備に十分な時間を確保できないこと、参加者間の温度差や拒否感があること、会議での合意形成が難しく発展につながらないことなどが挙げられる。また、会議の司会・進行方法についても、約3割のセンターが課題を感じており、ファシリテーションスキルの向上が必要とされている。 小規模自治体では、会議参加者が固定化し、日頃から連絡が取れる関係であるため、全体討論が行われず、会議の目的が不明確になるという課題もある。 これらの課題は、職員の多忙さ、人材不足、業務体制の未整備なども影響している可能性が高い。
4. 直営と委託における地域ケア会議の比較と課題
地域包括支援センターの設置形態(直営・委託)によって、地域ケア会議の実施状況や課題に違いが見られる。直営では学習会が多く開催され、保健師の出席率が高い傾向がある。一方、委託では地域連携や地域づくりに重点が置かれ、人口規模の大きい地域ではクリニックの医師の参加が多い傾向にある。 直営と委託の両方において、医療職、特に医師の参加率が低いという共通の課題が見られる。委託の場合、行政のビジョン不足や保険者としての役割を自覚していないという批判が寄せられており、行政との連携強化が強く求められている。 地域ケア会議の継続的な実施には、職員の異動や委託先の変更による影響も考慮する必要がある。 全体として、地域ケア会議は地域包括ケアシステム構築に重要な役割を担う一方、その効果的な運営には、多くの課題が山積していることが明らかになった。
III.直営と委託における地域ケア会議の比較
地域包括支援センターの設置形態(直営・委託)による違いも分析された。直営では保健師の出席率が高く、病院医師の参加率も高かったが、委託では開業医・クリニックの参加が多かった。直営では在宅医療の推進や計画策定に関するテーマが多く取り上げられていた一方、委託では地域連携や地域づくりに重点が置かれていた。委託先の地域包括支援センターからは、行政の地域包括ケアシステムに対するビジョン不足や、保険者としての責任を果たしていないという批判的な意見が多くみられた。
1. 地域包括支援センターの設置形態と地域ケア会議
地域包括支援センターの設置形態は、直営と委託に大別される。調査対象の地域では、委託が76%、直営が24%となっており、委託方式が主流であることがわかる。市区町村単位で見ると、「直営のみ」55.8%、「委託のみ」36.4%、「直営・委託両方」7.9%と、直営のみの割合がやや高いものの、委託方式も広く普及している。この設置形態の違いが、地域ケア会議の実施状況や内容にどのような影響を与えているのかを分析することが重要となる。介護保険制度は、市町村が保険者となり、給付と負担が連動する地方分権的な仕組みであるため、市町村の考え方によって地域差が生じる可能性があり、直営と委託では行政の関与の度合いが異なり、その結果として地域ケア会議へのアプローチや運営方法にも違いが現れることが予想される。
2. 直営と委託における地域ケア会議のテーマと参加者の違い
地域ケア会議で取り上げるテーマは、直営と委託で若干の違いが見られる。直営では、在宅医療の推進や計画策定、専門職による学習会といった行政主導の課題が多く取り上げられる傾向がある。一方、委託では、地域連携や地域づくりといった、より地域住民に密着したテーマが中心となる。個別事例検討においては、認知症をベースとした家族関係や財産管理などの生活支援に関するテーマが、直営・委託ともに多く見られる。医療職の参加状況においても、直営では病院医師の参加率が高く、委託では開業医やクリニックの医師の参加が多い傾向が見られる。これは、委託先の地域包括支援センターの規模や立地、そして地域における医療機関の分布状況などに影響されていると考えられる。保健師の出席率は直営の方が有意に高く、これは保険者としての姿勢が直営においてより明確に反映されていることを示唆している。
3. 直営と委託における課題 連携の難しさや行政への批判
直営と委託の地域包括支援センター、双方において、医療職との連携に課題が見られる。直営では、医療職が地域の実情に無関心である、あるいは地域包括ケアに対する理解が低いという批判的な意見が出ている一方で、医療職の参加によって会議が活性化するという期待も同時に存在する。委託では、医療職との連携の難しさを行政に伝えなければならないという課題があり、行政側の意識や対応が問われる。さらに、委託型の地域包括支援センターからは、行政への批判的な意見が多く寄せられている。具体的には、行政のビジョン不足、行政担当者の意識の低さ、現状分析の不足、保険者としての役割の自覚不足などが挙げられており、行政が地域包括ケアシステム構築において、明確な方向性を示し、責任ある役割を果たすことが求められている。これらの課題は、地域包括ケアシステムの構築と持続可能性を脅かす要因となるため、早急な改善策が必要となる。
IV.地域包括ケアシステム構築に向けた提言
地域包括ケアシステムの成功には、行政と医療機関の緊密な連携、多職種連携の強化、地域ケア会議の活性化が不可欠である。特に、医師や訪問看護師などの医療職の積極的な参加を促進するための施策が必要となる。自治体職員は地域包括ケアシステムの構築における責任を自覚し、地域づくりの視点を取り入れ、政策立案に繋がる会議運営を心がける必要がある。また、明確な評価指標の策定と共有も重要である。御調町のような成功事例を参考に、北海道の各市町村において、それぞれの地域特性に合わせた地域包括ケアシステムの構築を進めるべきである。
1. 行政と医療機関の連携強化 地域包括ケアシステムの中核
地域包括ケアシステムの構築には、行政と医療機関の連携強化が不可欠である。調査結果からも、医療職、特に医師の地域ケア会議への参加率が低いことが大きな課題として浮き彫りになった。この問題の解決には、医療機関の理解促進と積極的な参加を促す取り組みが重要となる。診療時間外の連携強化、地域包括ケアシステムに対する共通理解の醸成、行政側からの粘り強い働きかけなどが有効な手段となるだろう。 御調町の事例のように、行政と医療機関が一体となって改革を進めることが理想的な姿と言える。この連携強化は、直営型の地域包括支援センターにおいては比較的容易に実現できる可能性があるが、委託型の場合、行政と委託先の医療機関との連携を強化するための戦略が必要となる。特に小規模自治体においては、医療資源の不足も課題となるため、広域的な医療機関との連携を視野に入れた対応も重要である。
2. 地域ケア会議の活性化 多職種連携と効果的な運営
地域ケア会議の活性化は、地域包括ケアシステムの成功に大きく貢献する。そのためには、多職種連携の推進、特に医療職の積極的な参加が不可欠である。会議の目的を明確化し、医療職が貢献できる場、そして意見を交換できる場とする必要がある。会議の企画・運営においては、議題の絞り込み、地域の課題分析、医療職への参加依頼、そして司会進行といった様々な点で改善の余地が見られる。そのため、ファシリテーションスキルの向上、計画的な会議運営、そして参加者間の共通認識の醸成が重要となる。 また、地域ケア会議は、個別事例検討にとどまらず、地域づくり、政策立案へと繋がるような発展性を持たせる必要がある。そのためには、地域課題の抽出、解決策の検討、政策提言、地域資源の開発といった、より広範な視点を取り入れることが求められる。
3. 保険者 自治体 の役割 明確なビジョンと評価指標の提示
地域包括ケアシステムの構築において、保険者である自治体の役割は非常に重要である。しかし、今回の調査結果からは、自治体のビジョン不足や責任感の欠如といった課題が指摘されている。特に委託型の地域包括支援センターからは、行政への強い不満や批判が表明されており、行政による明確な方向性の提示と、保険者としての責任ある行動が求められる。 自治体職員は、地域包括ケアシステムをまちづくりと捉え、職員の意識改革、財政面での支援を強化する必要がある。 地域包括ケアシステムの目標達成を測るための明確な評価指標の策定と、その共有も重要となる。広島県が作成した「地域包括ケアシステムの評価指標」を参考に、定量と定性両面からの評価を行い、行政の役割を明確化していくべきである。 北海道のように、広域的な医療連携を推進する取り組みも、地域の実情に応じて必要となるだろう。
4. 自治体職員の意識改革と地域への愛着 持続可能な地域包括ケアシステムに向けて
地域包括ケアシステムの構築と持続可能性を確保するためには、自治体職員の意識改革が不可欠である。地域包括ケアシステムは、単なる行政サービスではなく、住民の安心安全な生活を支える総合的な計画であるという認識を持つことが重要となる。そのためには、自治体職員一人ひとりが地域への愛着を高め、地域住民と一体となって課題解決に取り組む姿勢が求められる。 地域ケア会議は、多様な職種、そして意思決定権を持つリーダー層の参加を得ることで、政策立案に繋がる場として機能させる必要がある。 自治体職員は、地域における課題を的確に把握し、医療職を含む関係者との連携を強化することで、より効果的な地域包括ケアシステムを構築することが期待される。 困難な課題に積極的に取り組み、実践を通して経験を積み重ね、地域包括ケアシステムを作り上げていくという自負と覚悟を持つことが重要である。
