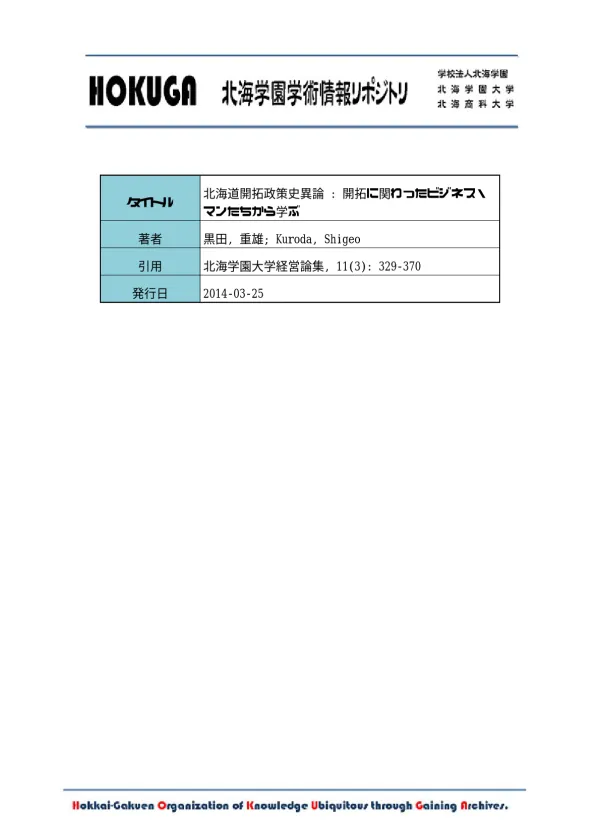
北海道経済活性化:小口輸出とビジネスマンの役割
文書情報
| 著者 | 黒田 重雄 |
| 文書タイプ | 論説 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 2.81 MB |
概要
I.北海道の交易と経済発展 歴史的視点からの考察
本稿は、北海道の経済史、特に交易と経済発展について、歴史的視点から考察する。古くから道外や海外との活発な交易が行われていた北海道は、現代においてその要素を大きく失っている。資源の乏しい日本において貿易は不可欠であり、特に北海道は貿易収支の黒字化が経済活性化の鍵を握る。近年の急激な円安傾向やTPP参加への動きなど、国内外の経済状況も北海道経済に影響を与えている。
1. 北海道の交易 過去と現在の対比
この節では、北海道の経済史における交易の役割を過去と現在とで対比的に論じています。かつて北海道は道外や海外との活発な交易拠点であったと記述されていますが、現代ではその活気は失われ、著者はその現状に衝撃を受けていると述べています。 千年以上続いた交易の衰退が、現代北海道経済に与える影響の大きさを強調しており、この歴史的な変化が、現代の経済政策を考える上での重要な背景となっていることを示唆しています。日本全体が資源の乏しい国であることを踏まえ、貿易立国として外国からの輸入と輸出に依存している現状が説明されています。 そのため、日本全体の貿易収支の黒字化が経済維持に不可欠であり、北海道経済においても貿易が重要な役割を果たしていることが示唆されています。 この節は、北海道経済の現状を理解する上で、歴史的な背景を理解する重要性を強調しています。現代の経済状況を分析する上で、歴史的な視点を取り入れる必要性が示されている点も重要です。
2. 現代北海道経済の現状と課題
この節では、2013年時点の北海道経済の現状と課題が分析されています。著者の所属する会合からの案内状の内容に触れながら、近隣諸国との政治的摩擦、急激な円安傾向、TPP参加に向けた政策展開など、北海道経済を取り巻く複雑な状況が説明されています。 日本総合研究所の2013年8月発表の日本経済展望を引用し、日本全体の景気回復傾向と対照的に、北海道の景気回復の遅れが指摘されています。道内総生産(名目GDP)の減少と全国シェアの低下、低い経済成長率といった厳しい経済状況が具体的な数値と共に示されており、北海道経済の脆弱性が強調されています。 この状況分析は、後の節で展開される北海道経済活性化の議論のための重要な前提となっています。道外地域と比べて回復が遅れている現状が示され、その原因を探るための分析へと繋がっていることが、この節の重要な役割と言えます。
3. 北海道経済における貿易の重要性と今後の展望
この節では、北海道経済における貿易の重要性が改めて強調されています。資源の乏しい日本において、貿易は経済成長に不可欠であり、北海道も例外ではないと指摘されています。貿易収支の黒字が不可欠な日本の経済状況を踏まえ、北海道経済においても、貿易、特に道産品の輸出振興が経済活性化の鍵となると示唆されています。 世界的な食糧不足や食の安全・安心への関心の高まりを背景に、食料自給率の高い北海道が、経済活性化のチャンスを捉えるべきであると主張しています。 日本市場の成熟化という新たな状況も踏まえ、海外市場への進出が不可欠であると結論づけています。この節は、道産品の輸出振興という具体的な経済活性化策を示唆しており、続く節での詳細な議論への導入部となっています。
II.近江商人 北前船 そして北海道水産業
江戸時代、近江商人は北前船を利用して北海道、特に松前藩を中心に水産物交易を盛んに行い、身欠き鰊やカニの缶詰などの加工も進めた。これは北海道経済の近代化において重要な役割を果たした。近江商人の活動は、北海道の水産業の発展に大きく貢献したと言える。 北海道経済は水産業から始まり、その後農業、鉱工業へと移行していく過程をたどった。
1. 近江商人と北前船による北海道水産物交易
この節では、江戸時代における近江商人による北海道での水産物交易の盛況が記述されています。近江商人は北前船を用いて、松前を中心に北海道全域で水産物交易を活発化させたとされています。北前船は江戸時代から明治時代にかけて日本海で活躍した北国廻船であり、近江商人はその中心的な存在でした。彼らは近江の特産品と北海道の道産品を交換することで莫大な利益を得ており、身欠き鰊やカニの缶詰などは彼らによって発明されたと言われています。この交易は、北海道の水産業発展に大きな影響を与え、北海道経済の基礎を築いた重要な要素であったと推測できます。記述からは、近江商人が単なる交易業者ではなく、水産物の加工技術の発展にも貢献していたことが読み取れます。 北前船という具体的な交易手段や、身欠き鰊やカニの缶詰といった具体的な商品が挙げられており、当時の交易の活況が具体的に描写されています。
2. 近代北海道産業構造の変遷と水産業の役割
この節は、近代北海道の産業構造の変遷を概観し、その中で水産業が果たした役割を分析しています。近代北海道の産業は水産業から始まり、その後農業の比率が増加し、最終的に鉱工業が中心となるという三段階の発展過程が説明されています。農業経済学者である湯沢誠の分析に触れ、水産業、農業、そして工業という順序で産業構造が変化していった過程を説明しています。この変遷は、北海道という辺境新開地の開発における産業構造の典型的なパターンを示している可能性を示唆しています。水産業は初期の北海道経済を支えた基盤産業であった一方、その衰退と同時に農業、そして工業への移行という流れが、北海道経済の成長と構造変化を理解する上で重要な要素となっています。 この節では、北海道経済のダイナミズムと産業間の相互関係について、歴史的な視点から考察している点が重要です。
III.開拓時代の北海道移住と農業開発 上島正の事例
明治時代、北海道の開拓は政府主導で行われたが、個人による開拓も盛んだった。長野県出身の上島正は、札幌で米作に成功し、多くの同郷の人々を誘致して信濃開墾地を形成した。この事例は、北海道の農業開発における個人の役割と、地域社会の形成について示唆に富む。上島は、札幌諏訪神社の創設にも貢献した。
1. 上島正による札幌での開墾と信濃開墾地の形成
この節では、明治時代の北海道開拓において、長野県出身の上島正が札幌で開墾に着手し、大きな成功を収めた様子が詳細に記述されています。上島は役人の反対を押し切り、札幌で米作に挑戦し、成功を収めました。その成功を機に、明治15年には故郷の上諏訪に戻り、30名以上の人々を連れて札幌に移住させました。移住者たちは、郷里の土地や家財道具を全て売却し、多額の資金を持って北海道に移り住みました。この資金は現在の価値で600万円から1000万円に相当し、広大な土地の購入や人夫の雇用が可能であったと推測されます。 上島は札幌歴史資料館の『札幌の歴史を築いた先人達』にも名を連ね、花園・東皐園の建設や札幌諏訪神社の創設など、多大な功績を残した人物として紹介されています。 この節では、上島正という個人の開拓活動が、北海道の農業開発に与えた具体的な影響が、彼の行動と成果を通して詳細に描かれています。
2. 厚別における信濃開墾地の成功と上島の役割
この節では、上島正が中心となって開拓された厚別(現在の札幌市白石区)の信濃開墾地の成功が取り上げられています。白石の人々からは開拓に適さない土地と見なされていた厚別において、上島のアドバイスの下、移住者たちは殆どが米作に成功しました。彼らはその開拓地を「信濃開墾地」と名付け、「北海道信濃会」を設立し、郷里の名前である「信濃」を冠した様々な活動を行いました。この成功は、上島が持っていた開拓に関する知識や技術、そしてリーダーシップによるところが大きかったと推測できます。 この節では、上島が単に開墾を成功させただけでなく、地域社会の形成にも貢献したことが強調されています。「信濃開墾地」という地名や「北海道信濃会」という組織の設立は、郷土意識と地域社会の形成が密接に結びついていたことを示唆しています。 上島の行動は、個人の努力と地域社会の連携によって開拓が成功した好例として提示されています。
3. 上島の移住の動機と北海道開拓政策
この節では、上島正が故郷の上諏訪から多くの人々を北海道に連れてきた背景にある動機と、当時の北海道開拓政策との関連性が考察されています。上島は、一度は捨てた故郷に残された人々の幸せを願って、彼らを北海道に連れてきた可能性が示唆されています。これは、単なる経済的な成功だけを目的とした移住ではなく、故郷の人々への強い思い入れに基づいた行動であった可能性を示しています。 同時に、この節では、当時の太政官日誌や北海道開拓政策に関する記述が引用され、政府による土地の分割統治や開拓政策との関連が示唆されています。信濃国の藩が北海道の開拓を命ぜられなかったことなども触れられ、当時の開拓政策の複雑な側面が示唆されています。 この節は、上島正の個人的な動機と、当時の政府による北海道開拓政策の双方を考察することで、北海道開拓の歴史をより多角的に理解する上での重要な視点を与えています。
IV.北海道経済の近代化と大型プロジェクト
北海道の近代化は、青函トンネル建設、札幌オリンピックなど数々の大型プロジェクトによって推進された。しかし、苫小牧東部工業基地の停滞や、企業誘致における課題も見られた。近年注目されるのは、環境アセスメントの重要性と、道産品の輸出振興である。
1. 北海道経済近代化における大型プロジェクトの展開
この節では、北海道経済の近代化において重要な役割を果たした大型プロジェクトが列挙されています。青函トンネル建設、札幌オリンピック、石狩湾新港建設、苫小牧東部工業基地建設など、多岐にわたるプロジェクトが挙げられており、これらが北海道経済の発展に貢献した側面が示唆されています。しかしながら、これらのプロジェクトの進捗状況は必ずしも順調ではなかったという点も強調されています。世界臓器移植センターの設置やロケット発射宇宙基地の建設といった、先端技術に関連するプロジェクトも含まれています。これらのプロジェクトは、北海道の経済構造を変化させ、国際的な競争力を高めることを目指していたと推測されます。 プロジェクトの規模の大きさと、その多様な分野への広がりを強調することで、北海道経済の近代化における積極的な取り組みが示されています。同時に、必ずしも全てのプロジェクトが成功したわけではなく、課題も存在したことが示されている点も重要です。
2. 大型プロジェクトの停滞と環境問題への意識の高まり
この節では、大型プロジェクトの多くが思うように進捗しなかった原因について分析が行われています。特に、道外の大手製造企業の工場誘致を狙ったプロジェクトが停滞したことが指摘されており、苫小牧東部工業基地の停滞がその代表例として挙げられています。 1978年に北海道が制定した北海道環境影響評価条例(環境アセスメント条例)が、多くのプロジェクトの中止に繋がったと説明されています。環境アセスメントの強化は、環境問題への意識の高まりを示しており、経済開発と環境保全のバランスが課題となっていることを示唆しています。 第三セクター方式の企業もアセスメントに係って事業中止に追い込まれた事例が示され、環境規制の強化が経済活動に及ぼす影響の大きさが強調されています。この節は、北海道経済の近代化において、環境問題への対応が重要な課題となっており、経済開発と環境保全の調和が今後の課題であることを示唆しています。
3. 企業誘致戦略の課題と比較事例 アメリカ合衆国との対比
この節では、北海道における企業誘致戦略の課題が論じられています。当初は道外の大手製造業者の誘致が推進されましたが、期待された成果は得られませんでした。その原因として、企業の国際化の進展や、北海道の誘致戦略の不十分さが指摘されています。 1988年のアメリカ視察での経験が紹介され、アメリカの州による日本企業誘致戦略の巧妙さが強調されています。アメリカの戦略は、土地の広さや地代の安さといった北海道と共通する魅力に加え、税優遇措置や子供の教育のための学校建設といった、より具体的な誘致策を提示していたことが対比的に示されています。 この比較を通じて、北海道の企業誘致戦略の改善の必要性が示唆されています。 アメリカの企業誘致戦略を事例として示すことで、北海道がより魅力的な投資先となるためには、どのような点を改善すべきかが明確に示されています。
V.道産品輸出振興と経済活性化 産業クラスターとイノベーション
北海道経済の活性化には、道産品の輸出振興が不可欠である。食料自給率の高い北海道は、世界的な食糧問題への対応において重要な役割を担う。そのためには、産業クラスターの形成による産学官連携、一村一品運動の発展、そして道産品販売体制におけるイノベーションが求められる。ホタテ貝のアラから繊維を抽出する技術開発や、農産副産物を活用したバイオ燃料製造などは、その可能性を示す好例である。
1. 道産品輸出振興の必要性と現状
この節では、北海道経済の活性化のためには道産品の輸出振興が不可欠であると主張しています。世界的な食糧不足や食の安全・安心への関心の高まりを背景に、食料自給率201%(カロリーベース)を誇る北海道が、この状況を経済活性化の絶好のチャンスと捉えるべきだと強調しています。 しかしながら、日本の輸出額が総生産の10%であるのに対し、北海道のそれはわずか1%に過ぎないという現状が示されています。この大きな開きが、北海道経済の抱える課題の深刻さを示しています。日本市場の成熟化も踏まえ、海外市場、特に19億人もの人口を抱える東アジア地域への進出が必須であると結論付けています。上海、香港、台湾、シンガポールなどでの北海道物産展が成功を収めている実績も紹介され、海外市場における道産品の潜在的な可能性が示唆されています。この節は、道産品輸出振興の必要性を強調するだけでなく、具体的な市場や実績を挙げることで、その実現可能性を示唆しています。
2. 道産品販売体制のイノベーションと産学官連携
この節では、道産品輸出振興を実現するための販売体制の改革、つまりイノベーションの必要性が論じられています。モノづくり企業はモノづくりに専念し、販売は専門の流通業者に任せることで、生産性向上と市場拡大を両立させるべきだと主張しています。 モノづくりと販売を兼務する現状では、どちらの面も中途半端になりがちであると指摘し、インターネット販売にも限界があることを示唆しています。 効率的な販売体制の構築には、産学官連携が不可欠であり、北海道庁も中心的な役割を果たす必要があると強調しています。 かつての日本が「日本株式会社」と呼ばれたように、政府主導による輸出振興が有効であった事例を挙げ、北海道も同様のアプローチを模索すべきだと提案しています。 この節では、具体的な企業事例(ベネトン社)を挙げつつ、従来の枠にとらわれない新しい販売体制の構築の必要性を説いています。
3. 新製品開発と産業クラスター構想
この節では、北海道における新製品開発の現状と、産業クラスター構想との関連性が説明されています。 かつての一村一品運動から生まれた地域特産品に加え、産業クラスター構想の下、産学官連携によるITやバイオテクノロジー関連の新製品が開発されています。バイオテクノロジーやナノテクノロジーなどの技術を活用した製品開発が盛んに行われている現状が示されています。具体例として、千歳科学技術大学におけるホタテ貝のアラからの繊維抽出技術開発や、農産副産物からのバイオ燃料製造などが挙げられています。 これらの事例は、北海道の農業や水産業といった既存産業の副産物を活用した、付加価値の高い新製品開発の可能性を示しています。 一村一品運動や産業クラスター構想といった具体的な政策と、それらから生まれた新製品開発の現状を示すことで、北海道経済の活性化に向けた取り組みの成果と今後の展望が示されています。
VI.新しい経済発展モデル 玉送り理論と産学官連携
北海道経済の将来像に向けて、玉送り理論に基づいた新しい経済発展モデルの構築が提唱されている。これは、モノが人から人へ、産業から産業へと渡っていくことで経済が活性化するという考え方である。このためには、産学官連携による取り組みが不可欠であり、北海道庁もビジネス行動の先頭に立つ必要がある。
1. 北海道経済活性化のための新しい経済発展モデル
この節では、北海道経済の活性化に向けた新しい経済発展モデルとして、「玉送り理論」と産学官連携の重要性が論じられています。従来の経済予測モデルとは異なり、「玉送り理論」はモノが人から人へ、産業から産業へと渡っていく過程に着目し、その過程に関わる人々や産業が潤うことで経済が発展するという考え方です。この理論は、経済発展理論で著名なO.ハーシュマンの後方連関・前方連関の考え方を発展させたものと言えるでしょう。 この新しいモデルにおいては、モノづくり企業はモノづくりに専念し、流通業者が販売や市場開拓に注力することで、生産性と効率性が向上すると考えられています。 北海道の現状では、モノづくり企業が販売まで兼務しているケースが多く、この体制の見直しが必要であると指摘されています。 この節では、北海道経済の現状分析を踏まえ、より効率的で持続可能な経済発展のための新しい枠組みの提案が行われています。
2. 玉送り理論 の具体例と産学官連携の必要性
この節では、「玉送り理論」に基づく具体的な経済活性化策が示唆されています。 まず、千歳科学技術大学を中心としたホタテ貝のアラからの繊維抽出技術開発が、世界的な発明として注目されている点が挙げられています。これは、既存資源の高度利用による新たな産業創出の可能性を示す好例です。 また、農産副産物であるデンプン粕や規格外小麦からエタノールを製造し、自動車燃料として活用する試みも紹介されています。 これらの例は、「玉送り理論」に基づき、一つの産業から別の産業へと経済効果が波及していく可能性を示しています。 これらの取り組みを成功させるためには、産学官連携が不可欠であり、北海道(庁)も中心的な役割を担う必要があると強調されています。 従来の政府支援の在り方ではなく、北海道庁自らもビジネス行動の先頭に立ち、輸出振興を図る「日本株式会社」方式を踏襲する必要性が示唆されています。
3. 市場開拓と流通過程の改善 既存産業の活性化
この節では、モノづくり企業が市場開拓に注力できるよう、流通過程の改善が重要であると主張しています。 モノづくり企業にとって最大の課題は、買い手の存在(市場)の有無であり、いくら良い製品を作っても市場がなければ利益につながらないと指摘しています。 そのため、市場性のある製品を作るだけでなく、それを効率的に運ぶ仕組み、つまり流通機能の充実が不可欠であると強調しています。 北海道の現状では、メーカーが生産と販売を兼務しているケースが多く、これでは生産活動に専念することが難しく、結果として製品の質や生産効率が低下すると考えられています。 より良い製品づくりに専念できるよう、流通業者による販売や市場開拓を促進する仕組み作りが、経済活性化の鍵となると結論づけています。 この節は、具体的な課題を提示し、その解決策として流通過程の改善と役割分担の明確化を提案することで、より実践的な経済活性化策を示唆しています。
