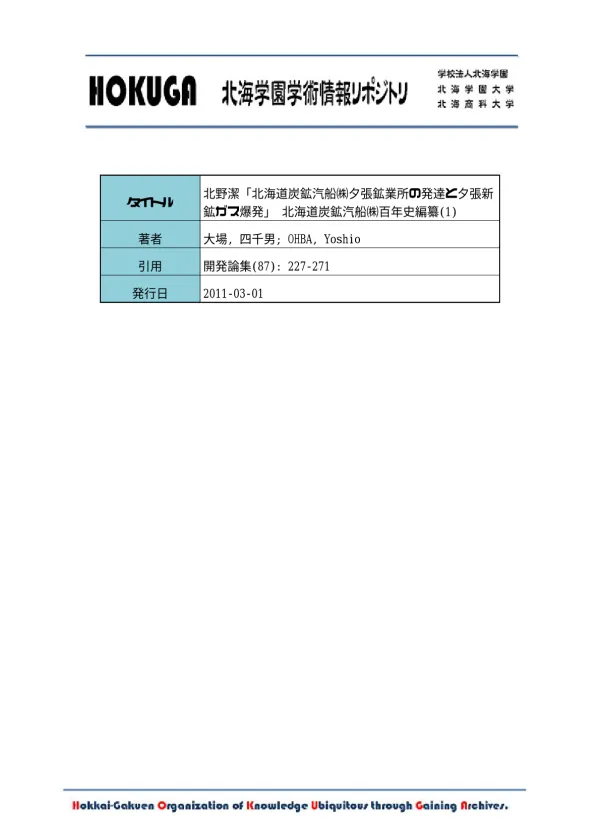
北炭百年史:北野潔が見た夕張
文書情報
| 著者 | 北野潔 |
| instructor | 大場四千男 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 経営学部 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.08 MB |
概要
I.北炭 Hokutan の隆盛と衰退 夕張炭鉱 Yubari Coal Mine を中心とした歴史
本資料は、日本の石炭産業衰退期における北炭(Hokutan)、特に夕張炭鉱(Yubari Coal Mine)の歴史を、昭和初期から終焉までを辿る。高度経済成長期には、北野潔氏ら係員の活躍により、機械化(傾斜生産方式、カッペ採炭など)を推進し経営基盤を確立。しかし、石油業法制定によるエネルギー革命(石炭から石油へ)で深刻な経営悪化へ。労働争議も頻発し、合理化、閉山が繰り返された。夕張市にとっても、北炭の盛衰は町の命運に関わる一大イベントであった。
1. 北炭の勃興期と北野潔氏の役割
この節では、昭和21年の北野潔氏の入社から高度経済成長期にかけての北炭の成長が描かれている。北野氏は夕張鉱業所二鉱に配置され、復興期の石炭増産に貢献、傾斜生産方式の推進役を務めた。その後係員に就任し、昭和30年代前後には鉄柱カッペ採炭を中心とした機械化を推進、長壁式量産出炭体制の確立に尽力した。北野氏を代表とする係員層の中間管理者層の勤労革命が、荻原吉太郎社長の下、北炭の自立経営を支え、開坑から販売までを統合する大手炭鉱企業へと成長させた様子が記述されている。この期間における北炭の成功は、高度な技術と効率的な経営、そして現場の労働者の努力の賜物であったと言える。
2. 石油ショックと石炭産業の危機
昭和36年の石油業法制定は、石炭産業に大きな転換点を迎えた。石油の安価な大量輸入と高い熱効率は、エネルギー革命の担い手として石油産業を飛躍的に発展させた。外資系石油会社を中心とする石油産業は、中近東産油国からの原油を低価格で大量輸入し、精製することで、国内炭価格を下回る石油価格をエネルギー市場に確立した。この結果、石炭から石油へのエネルギー転換は避けられず、石炭鉱業はスクラップ&ビルドの時代を迎えた。日本の石炭政策は、この激変の中で石炭鉱業の生存を維持することに苦心した様子がうかがえる。この節は、石油ショックが日本の石炭産業に与えた壊滅的な打撃と、その後の苦しい対応について詳述している。
3. 戦後復興期における労働力と労使関係
終戦後の混乱期、北炭は労働力の補充に苦心した。補充された労働力は終戦後の引揚者や東北からの農家出身者などが多く、熟練労働者(先山)の不足が深刻な問題となった。労働力の質の問題に加え、資材の老朽化も生産性の回復を妨げた。著者は採炭夫として入社し、現場の労働者の実態を目の当たりにする。多くの労働者が刺青を入れており、労働意欲や技術レベルは必ずしも高くなかったという実情も記述されている。一方、終戦直後の混乱とインフレ克服のための闘争を経て、労働協約が締結され、労使関係は一旦落ち着くも、その後は地域闘争に発展、山猫ストなどのサボタージュ行為が横行し、夕張炭鉱は揺れ動いた。この節は、戦後日本の炭鉱における労働力確保の困難さ、労働者の質の多様性、そして労使間の複雑な関係性を克明に描いている。
4. カッペ採炭の技術革新と合理化への取り組み
この節では、カッペ採炭を中心とした採炭技術の進歩と、それに伴う合理化の取り組みが記述されている。1.2mカッペから1.3mカッペへの移行や、二方連続採炭への挑戦など、技術的な改善が生産性向上に繋がった一方で、炭壁の崩壊防止対策、カッペ先端の支持率、コッターピンの強度など、新たな技術的課題が浮上した。また、合理化運動に伴い、標準作業量の設定や工数換算方式の導入などが試みられたが、労働組合との交渉は難航し、長期ストライキも発生した。この節では、技術革新と合理化の両面における困難さと、労働組合との関係性を示す重要な事例が紹介されている。
5. 珪肺法制定と社会情勢の変化
昭和30年には珪肺法が制定され、職業病対策が開始された。全鉱健康診断の実施により、労働者の健康問題への意識が高まった。一方、高度経済成長期における好景気の中で、政治情勢も激動期を迎えていた。夕張炭鉱労働組合(夕炭労)出身の大矢正氏が参院選で当選するなど、労働組合の政治への影響力が強まった。しかし、好景気と政治的対立は、労働争議の激化や社会不安にも繋がるなど、複雑な社会情勢が描写されている。この節は、社会政策、政治、労働運動という多角的な視点から、昭和30年代の社会情勢と、それらが炭鉱労働者に及ぼした影響を捉えている。
6. 北炭ショックと夕張炭鉱の閉山へ向かう道
昭和45年5月、北炭は夕張新鉱開発計画に関連して、夕張二鉱、平和鉱、清水沢鉱の閉山を発表、いわゆる「北炭ショック」を引き起こした。この発表は夕張市の総合開発計画を根底から覆し、市民生活に大きな影響を与えた。多くの鉱員が離山し、夕張の街は大きな混乱に陥った。同時に、熟練労働者の育成システムである先山制が機械化によって変化し、従来の集団労働の形態が崩れつつあった。この変化は、鉱員たちの不安を増幅させ、離山を加速させる要因となった。この節は、北炭の合理化政策が夕張の街と炭鉱労働者に与えた衝撃と、社会構造の変化が労働者心理に与えた影響について、詳細に描かれている。
II.機械化採炭の導入と労働問題
高度経済成長期、北炭は採炭の機械化に力を入れた。ウエストファリヤ製 WDCCやWジブコールカッターの導入は生産性向上に貢献したが、同時に労働条件の悪化や、熟練労働者(先山)不足といった課題も発生。標準作業量の設定や科学的管理法の導入が試みられるも、労働争議(山猫ストなど)も発生し、労使関係は緊迫した。
1. 機械化採炭の導入と技術的課題
この節では、北炭における機械化採炭の導入と、その過程で発生した技術的な課題が述べられている。ウエストファリヤ製WDCCやWジブコールカッターの導入により採炭効率は向上したものの、ケーブルハンドラーの未整備による人力でのケーブル引き上げ作業、ロング切羽におけるコールカッターのジブ回転不良、炭壁の崩壊防止、カッペ先端の支持不足(1.20Mカッペで0.3トンの出炭)、コッターピンの強度不足といった問題が発生した。これらの問題に対処するため、工夫が凝らされた臨機応変な対策が講じられ、例えば、落葉材による面切り打柱、空木組の井桁構造、ジブへの木材切れ端の挿入などが試みられた。これらの試行錯誤を通じて、機械化採炭は着実に進歩していったものの、常に新たな技術的課題に直面していたことがわかる。
2. 二方連続採炭への挑戦と標準作業量の設定
機械化採炭の更なる高度化として、二方連続採炭の実現が目指された。しかし、コールカッター本体の深側への移動、ロング面の馬背部分の越えなど、技術的な困難に直面した。DCCのスクレーパーによる緊急締め付け運転など、様々な工夫がなされたものの、時間的な制約から一方採炭が中心となった。それでもカッペ採炭は全鉱に普及し、昭和26年にはカッペ採炭による標準作業量の設定と科学的管理法の導入が提起された。この標準作業量の設定は、生産性向上と合理化を目的としたものであったが、同時に労働組合との交渉や労働条件に関する問題を孕んでいたことが、後の記述から読み取れる。この節は、技術的進歩と生産性向上への努力、そして合理化に向けた取り組みと、それに伴う困難さを示している。
3. 石炭企業合理化運動と労使交渉
この節は、昭和26年頃から開始された「石炭企業合理化運動」と、それに伴う北炭と労働組合との交渉について述べている。北炭では天塩坑の閉山など赤字炭鉱の整理が行われ、労働組合も操作問題に前向きに取り組んだ。具体的には、工数換算方式の導入が交渉の中心課題となったが、明治・大正生まれの熟練労働者への理解を促すことが困難を極めた。増産と合理化を両立させる努力が続けられたものの、昭和27年には63日間の長期ストライキが発生。このストライキは、貯炭量の増加、炭価の値引き、そして101億円にのぼる借入金という経営危機の中で、合理化問題を巡る労使間の対立を深める結果となった。この節は、合理化運動における労使間の緊張関係、長期ストライキの発生、そして経営危機という厳しい状況が描写されている。
4. 労働組合の役割と生活協同組合の設立
合理化策への反発から、労働者自身による生活の維持・向上を目指す動きとして生活協同組合が発足した。これは、会社側の合理化策だけでは労働者の生活を守れないという現場の危機感を反映している。また、昭和30年の珪肺法制定は、炭鉱労働者の職業病対策の第一歩となったが、労働者には自覚症状がないまま病状が進行する可能性があり、一抹の不安が残る結果となった。昭和31年には夕張炭鉱労働組合出身の大矢正氏が参院選で当選するなど、労働組合の政治的影響力が増大。しかし、選挙における不正疑惑に関与したとして、関係者が逮捕される事件も発生し、職場の人間関係にも影響を与えた。この節は、労働組合の政治的活動、労働者の生活を守るための努力、そして職業病対策といった多様な側面から、この時代の炭鉱労働者の状況を描写している。
5. 1.3Mカッペ導入と労働条件の改善
従来の1.2Mカッペに代わる1.3Mカッペの導入が検討され、試作品による試験が行われた。試験の結果、1.3Mカッペは保安上の効果が高い一方で、重量増加と作業の強化による労働負担の増大が課題となった。労働組合は、この問題に対し、1.3Mカッペの重量を1.2Mカッペと同重量にすること、そして手当の改善などを条件に、条件闘争に終止符を打った。この協定は原料炭の急増という状況を背景に、ガス鉄鋼関係の活況、長期販売契約の締結といった企業側の思惑も反映していると考えられる。この節では、技術革新と労働条件、企業経営の状況、そして労使交渉の複雑な相互関係が示されている。
III.夕張新鉱 Yubari New Mine 開発と北炭の再建努力
**夕張新鉱(Yubari New Mine)**開発は北炭の再建計画の中核であった。しかし、目標とする生産量(5,000トン)の達成には至らず、資金繰りの悪化、人員不足に苦しむ。幌内炭鉱ガス爆発事故(死者25名)などの重大災害も相次ぎ、再建計画は修正を余儀なくされた。この過程で、労働組合との交渉、人員配置転換、閉山、そして会社分割といった厳しい決断が迫られる。
1. 夕張新鉱開発の開始と初期の課題
夕張新鉱の開発は北炭の再建計画の中核として位置づけられ、着工から2年8ヶ月を経て、第1立坑とベルト斜坑が貫通した。本格操業開始に向け、夕張一鉱と平和鉱からの人員移行が計画されたが、安全面や労災問題など、多くの困難に直面した。新鉱への職員の派遣、目標出炭量1万7000トン達成への努力などが記述されている。しかし、操業開始直後には人車脱線事故が発生し、死者2名、負傷者5名という痛ましい事故が起きてしまった。人員確保、安全対策、そして生産目標達成という、いくつものハードルが初期段階から立ちはだかったことが分かる。
2. 夕張新鉱における生産性向上への取り組みと課題
夕張新鉱では、生産性向上を目標に、機械化促進による採炭能率のアップが目指された。しかし、三方連続採炭の実施に伴う請負給の作業形態や標準作業量に関する提案は、労働組合から労働強化と賃金引き下げにつながるものとして反対され、合理化反対闘争へと発展した。最終的には交渉を経て妥結に至り、全鉱操作と出炭奨励給の制度が実施された。一方で、現場では切羽条件の急激な変化により、ドラムカッターの使用が困難となるケースもあり、ホーベル採炭などによる対応が試みられた。 また、坑道の盤圧対策として、当初1Mの留間でベタ丸矢木とIビームアーチを使用していたが、アーチの変形が激しかったため、枠間を狭めるなどの改良が行われた。 この節では、生産性向上のための様々な取り組みと、それらを阻む技術的・人的な課題、そして労働組合との交渉の経緯が示されている。
3. 幌内炭鉱ガス爆発事故と再建計画への影響
昭和50年11月、幌内炭鉱で発生したガス爆発事故は、北炭の再建計画に大きな影響を与えた。事故現場では、坑内火災の様相を呈し、一刻も早い消火対策が必要であったが、現地監督官の許可が出ず、消火活動が遅れた。最終的に全坑水没に至り、25名の死者・行方不明者を出した。この事故は、社会問題として大きく取り上げられ、幌内炭鉱の再建問題は石炭鉱業審議会などで議論された。再建案として、常盤地区の残炭掘削による縮小案が検討されたが、これは炭鉱の事実上の閉鎖を意味するものであった。 この事故を受けて、夕張新鉱の人員配置、清水沢炭鉱の存続、そして東部開発計画の延期など、北炭全体の再建計画が大きく見直されることになった。
4. 夕張新鉱の生産目標未達成と再建計画の修正
夕張新鉱は、当初5000トン体制を目指していたが、実際には4300トンから4500トンの生産能力にとどまった。目標未達の状況は、資金不足という新たな危機をもたらし、再建計画の見直しを余儀なくされた。萩原吉太郎会長は、緊急増産のための休日出炭態勢、責任ある計画出炭の確保などを盛り込んだ修正再建案を提案。 また、化成工業所の閉鎖も決定し、多くの従業員が北炭を去ることになった。この修正再建案は、政府、支援金融機関、ユーザーなどの厳しい監視下で承認され、その後も、様々な課題に直面しながら、再建への道が模索された。この節では、再建計画の修正、資金繰り問題、そして企業の縮小といった、北炭の厳しい経営状況が示されている。
5. 夕張新鉱閉山と北炭職員組合の解散
最終的に、夕張新鉱は閉山、そして北炭職員組合は解散へと至った。閉山決定に至るまでの過程では、地元夕張市での大規模な再建要求集会や、札幌・東京での抗議活動などが行われた。 しかし、管財人から事実上の閉山・全員解雇が提案され、組合は抗議のストライキや、関係者への座り込みなど、様々な手段で抵抗を試みた。 最終的には閉山が決定し、従業員の再就職支援や、病院移管問題など、多くの課題が残された。 この節は、夕張新鉱閉山という北炭の終焉と、それに伴う労働組合の解散、そして夕張市への大きな影響について述べられている。山中通産大臣や横路知事の対応についても触れられている。
IV.北炭の終焉と夕張市の未来
度重なる経営悪化、災害、そして石炭産業の衰退により、北炭はついに経営破綻を迎える。生産部門の分離・独立、職員組合の解散といった劇的な変化が起こり、夕張炭鉱も閉山へ。夕張市は、北炭の閉山によって大きな打撃を受け、再開発への模索を始める。この出来事は、日本の石炭産業の歴史における重要な転換点であり、夕張の街の未来を大きく左右する出来事となった。
1. 北炭の経営破綻と生産部門の分離独立
長年の経営悪化、相次ぐ災害、慢性的な出炭不振、そして石炭産業全体の衰退により、北炭は経営の存続が危ぶまれる状況に陥った。危機脱出の策として、生産部門を分離独立させるという決断が下された。これは、企業の存続を賭けた、非常に困難な決断であった。この決定に伴い、14年以上の歴史を持つ北炭職員組合は解体され、新設会社ごとに独立した組合が結成され、新たな組織である北炭職員組合協議会が設立された。この組織再編は、北炭の歴史における大きな転換点であり、今後の労働条件や福利厚生などの問題解決に向けた新たな段階への移行を示している。
2. 石炭産業の危機と政府の対応
貯炭量の急増は、石炭産業を新たな危機に突き落とした。政府は、景気回復の遅れによる鉄鋼生産の停滞や円高による国内炭価格の高騰をその原因として挙げている。しかし、原料炭については、鉄鋼生産の停滞による消費減はあるものの、依然として大量の輸入炭が消費されている状況である。政府の「国内炭の優先使用」という原則を貫くならば、国内原料炭の供給過剰は吸収可能であったはずである。一般炭についても、石炭火力発電の新設には時間がかかるため、需要増は見込めないという政府の見解は、長年にわたる政府への増設要求を無視してきた結果と言えよう。政府の対応は、石炭産業の抱える根本的な問題への対処を欠いた、安易なものであったと批判されている。
3. 夕張新鉱の危機と緊急対策
分社化後、夕張新鉱は出炭不振により資金繰りが悪化し、深刻な危機に直面した。人員不足は深刻で、安定生産に必要な人員を確保することは不可能と判断された。このため、清水沢炭鉱からの出向という緊急措置が取られ、坑内従業員113名、社員7名が派遣された。この措置は、市中の民間ユーザーなどから好感を持たれ、王子製紙、秩父・宇部セメントの油炭転換、苫東火力発電所からの大量受注など、内外情勢の好転に繋がった。しかし、この好転は一時的なものであり、根本的な解決には至らなかったことが、後の記述から読み取れる。この節は、夕張新鉱の具体的な危機的状況と、その場しのぎの緊急対策が示されている。
4. 夕張新鉱閉山と再開発への展望
様々な努力にも関わらず、夕張新鉱は閉山へと追い込まれた。閉山決定前には、地元夕張市で再建を求める大規模な集会が開かれ、札幌や東京でも支援団体による抗議活動が行われた。しかし、管財人から事実上の閉山・全員解雇が提案され、24時間ストや無期限の座り込みといった抗議行動も展開された。最終的には閉山が決定し、従業員は再就職先を探さなければならなくなった。 この節は、夕張新鉱閉山決定までの経緯、そして労働者たちの抵抗と閉山後の再就職支援、更には再開発への展望などが記述されている。 山中通産大臣や横路知事の対応も重要な要素として挙げられており、政府や地方自治体の役割についても示唆されている。
