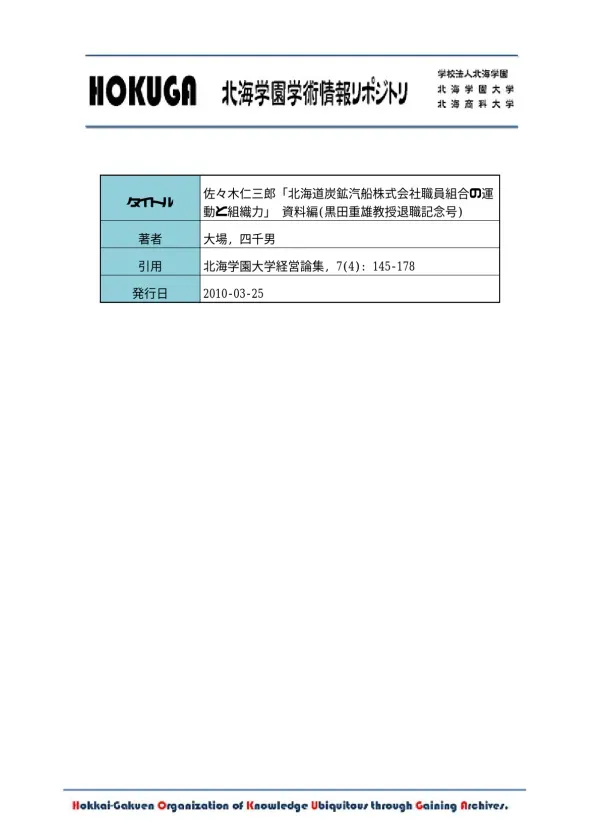
北炭職員組合運動と組織力
文書情報
| 著者 | 大場 四千男 |
| subject/major | 労働運動史, 産業関係史, 北海道史 |
| 文書タイプ | 資料編 (黒田重雄教授退職記念号) |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 717.92 KB |
概要
I.清水沢炭鉱閉山と労働条件に関する交渉
1955年、北海道夕張市の清水沢炭鉱閉山に伴い、北炭夕張炭鉱職員組合と会社間で激しい交渉が行われました。組合は完全雇用を前提に、退職金、解雇予告手当、再雇用に関する条件交渉に臨みましたが、会社は閉山に伴う退職者への交付金の使用方法を巡り、組合と対立しました。交渉は難航し、日額、月額の賃金、各種手当(出納手当、臨時入坑手当、通勤手当、住込手当など)についても、多くの争点が浮上しました。最終的に、組合は不満ながらも閉山を受け入れ、再雇用や就職斡旋に関する合意に至りました。 閉山理由は、平安8尺層と10尺層の採掘における、断層や炭層の傾斜などによる生産性低下と保安上の問題が挙げられています。調査委員会は、自然条件の劣悪さを閉山の主因と結論付けました。
1. 清水沢炭鉱閉山の提案と組合の対応
1955年1月14日、会社側から清水沢炭鉱閉山提案がありました。夕張職員組合は、直ちに清水沢炭鉱閉山に伴う調査委員会を設置し、1月28日には入坑調査を実施。その結果を踏まえ、組合は完全雇用を前提とした条件交渉を開始しました。交渉の主な焦点は、退職者への対応、再雇用、そして労働条件でした。会社側は閉山に伴う交付金を退職者への支払い充当を主張する一方、組合側は個人の労務債権であるとして、その使用に問題があると主張、意見が対立しました。 この初期段階では、交付金の使用方法をめぐる対立が大きな障壁となり、交渉は平行線をたどりました。組合側は、諸条件が決定しない限り、所要人員や移行人員の協議も遅れると判断し、精力的な交渉継続を決定しました。複数回の職員分科会や地区委員会が開催されましたが、会社提案と組合提案の開きが大きく、特に交付金問題では意見が対立し、交渉は難航しました。 組合は、閉山は避けられないものの、組合員への影響を最小限に抑えるため、完全雇用、適切な退職金、再雇用、そして労働条件の維持を強く求めて交渉を続けました。
2. 労働条件に関する詳細な交渉と争点
労働条件に関する交渉では、日額、月額賃金、各種手当(出納手当、臨時入坑手当、通勤手当、住込手当など)が詳細に議論されました。 文書からは、施行本数によって日額賃金が異なり、40本未満で230円、40本以上で300円、80本以上で440円という具体的な金額が確認できます。月額手当についても、複数の金額が提示され、それぞれ異なる条件や職種に対応していることが分かります。 さらに、北海道炭鉱手当、別居手当、社宅外居住手当、診療所在勤手当、技術員手当といった、様々な手当の金額や支給条件も交渉の対象となりました。 これらの手当の金額は、扶養家族の有無や勤務年数などによって変動し、複雑な計算式に基づいている部分もありました。 欠勤に対する減率についても議論され、欠勤日数に応じて賃金から差し引かれる割合が、条件によって異なっていたことが示唆されます。 これらの複雑な労働条件の詳細を巡る議論が、交渉をさらに難航させた要因の一つであったと考えられます。
3. 交渉の妥結と今後の対応
長時間にわたる交渉の結果、組合は、会社側の清水沢炭鉱閉山を最終的に受け入れることとなりました。 しかし、これは組合にとって容易な決断ではなく、文書からは強い不満が読み取れます。 妥結に至った背景には、交渉の長期化によって、所要人員や移行人員の協議が遅れるという懸念があったこと、そして移行問題の解決が不可欠であったことが挙げられます。 具体的な妥結内容として、退職者に対する労使による就職斡旋委員会の設置、北炭夕張炭鉱株式会社、北炭真谷地炭鉱株式会社、北炭幌内炭鉱株式会社への坑内係員の再雇用(55年7月末までに完了)、再雇用後の労働条件の継続努力などが確認できます。 解雇予告手当として平均賃金の30日分が支給されることも合意されました。 期末手当、帰郷旅費、年次有給休暇残日数慰労金については、石炭鉱業合理化臨時措置法の範囲内で支給されることになりました。 夕張新炭鉱への再雇用者の通勤計画と住宅計画の明示も会社側に求められました。 これらの合意事項は、組合員にとって可能な限り不利益を軽減するための努力の結果として得られたものと考えられます。
II.清水沢炭鉱閉山に関する調査委員会報告
清水沢炭鉱閉山に関する調査委員会は、会社提示の炭量と実際の炭量に大きな差があることを確認しました。特に、南部区域の平安8尺層は計画を上回る採掘実績を上げた一方で、10尺層は断層や炭層の乱れにより、大幅な減産を余儀なくされました。10尺現区域も上下盤の乱れと強い炭層傾斜により採掘困難な状態でした。これらの自然条件の劣悪さを鑑み、調査委員会は生産能率の向上と収支の改善は困難であり、閉山もやむなしとの結論を下しました。 委員会は協議会、夕張職組、清水沢地区副委員長、保安委員など計6名で構成されました。
1. 調査委員会の設置と構成
清水沢炭鉱閉山提案を受け、夕張職員組合は調査委員会を設置しました。委員会は、執行部の鋭意検討の結果、協議会2名、夕張職組2名、清水沢地区副委員長1名、保安委員1名、合計6名で構成されました。 55年2月6日に行われた第5回地区委員会で委員会の構成が決定され、直ちに調査活動が開始されました。調査の重点は、会社が提示した清水沢炭鉱の閉山に伴う炭量に関するものでした。 会社側はまず、清水沢炭鉱の概況と炭量に関する説明を行い、その後質疑応答が行われ、直ちに坑内調査に移行しました。 調査委員会は、第一斜坑群、連絡ベルト斜坑、第二斜坑群、第三斜坑群、排気立坑などの坑道構造を詳細に確認し、現区域、西部区域、南部区域などの各区域における採掘状況の実態調査を実施しました。
2. 坑内調査と生産状況の分析
1月28日、鈴木炭鉱長、松田次長、伊藤管理課長が出席するなか、清水沢炭鉱において坑内調査が行われました。調査班は2班に別れ、10尺現区域方面などを調査しました。調査結果、10尺層では計画70万5千トンに対し、41万5千トンしか採掘できず、29万トンの大幅な減産が見られました。 主な原因は、炭層の褶曲と断層群による稼行不能と、それに伴う計画切羽への影響でした。 南部区域では、平安8尺層が計画28万9千トンに対し40万2千トンと計画を上回る実績を上げたものの、53年度に終掘しており、10尺層は平和断層の派生断層群により採掘区域が狭まり、地上表示物件維持保護のため計画中止せざるを得ない区域もありました。 10尺ベルト卸No.2掘進では断層による80mの落差が判明し、25万3千トンの計画出炭が不可能になりました。さらに、代替ロングとして計画された4片8尺后向下炭ロングも、炭丈が1メートル程度と少なく、以前の上炭払で溜まった坑道内の水が問題となり、経済性と保安確保の面から採掘が困難と判断されました。
3. 調査委員会の結論と閉山判断
調査委員会は、平安8尺層の採掘完了、10尺層における断層と炭層の乱れによる採掘区域の縮小、そして10尺現区域における上下盤の乱れと強い炭層傾斜などを踏まえ、現状では生産性向上と収支改善は望めないと結論付けました。 特に、南部区域の平安8尺層は53年に採掘完了しており、その後10尺層の採掘に当たっては、平和断層の派生断層群による面長減、片盤長減が深刻な問題でした。 10尺現区域は上下盤の乱れ、断層、炭層の傾斜が非常に強く、採掘は事実上不可能であり、保安確保にも大きな問題がありました。 4片后向下炭についても、溜水対策や経済性の問題から採掘を避けるべきだと判断されました。 これらの状況を総合的に判断した結果、調査委員会は、自然条件の劣悪さ、生産性・収支の悪化、そして石炭政策の見直しがない限り存続は困難であるとして、55年4月末日をもって清水沢炭鉱閉山もやむなしとの結論を下しました。完全雇用を前提とした諸条件の交渉を、組合は会社に対して要求しました。
III.自然発火事故と復旧作業
1980年8月、北炭夕張炭鉱で自然発火事故が発生し、坑内全域の入坑者592名が出坑しました。事故発生後、救護隊が現場に急行し、通気遮断や冷却作業などを行い、事故の沈静化に努めました。その後、復旧作業に関する労使交渉が行われ、復旧作業の基本方針が協定されました。 この方針に基づき、通気系統の再整備や坑道の修復などの作業が進められ、早期の復旧を目指しました。間接経費の節減や職場規律の厳正化なども合意事項に含まれていました。 復旧作業期間中の休日採炭や4交替制についても協議されました。
1. 自然発火事故の発生と初期対応
8月27日22時51分頃、現場巡回中の係員が異常を発見し、指令室に通報。指令室は直ちに坑内全域の入坑者全員(592名)に出坑指令を出しました。事故の原因は自然発火とされ、罹災者は報告されていません。事故発生後、迅速な対応がとられ、まず0時15分に全員の出坑を確認。続いて0時40分から救護隊と職員計50名弱が南排気斜坑部に進入し、FA流送準備やビニール幕による通気遮断を開始しました。 その後、新炭鉱59名、真谷地13名、幌内11名など合計83名の救護隊が順次入坑し、入気側密閉、排気側散水、坑道の偵察などの作業を実施しました。しかし、密閉個所内のCH濃度が5%に達したため、10時20分に全員退避命令が発令され、11時20分までに全員が出坑しました。 この初期対応は、人的被害をゼロに抑えることに成功したものの、主要排気坑道を密閉せざるを得ない重大な事態となり、全面復旧には相当の時間を要することが明らかになりました。
2. 応急対策と復旧計画
事故発生後、応急対策として、南排気斜坑部での通気遮断や散水、そして坑道偵察などが行われました。8月29日以降は本格的な復旧作業に向けた検討と実施に移行。9月30日には現段階での応急対策の方針が出されました。 この方針では、通気骨格の確保、第二立坑周辺坑底坑道の放水による冷却と山固め、−600L中央第一立入の放水による冷却と山固め、−600L中央第二立入と南排気斜坑の密閉放棄などが含まれていました。 また、第二立坑の通気量を考慮した切羽整備作業や西部全区域の山固め補修作業なども計画されました。 9月23日には本格的な復旧計画が説明され、通気系統再整備のための代替坑道掘進計画が示されました。計画には、第二立坑第二連絡坑道切替、−650中央排気風道、ベルト斜坑−690目抜、北第三盤下連絡坑道、南第二下段排気立入、南第二排気立入切替、南盤下添坑道など、複数の坑道の掘進や改修が含まれていました。 作業期間は、10月上旬から56年3月末までと長期に及ぶものでした。
3. 復旧作業の基本方針と労使協定
会社存続のため、早期復旧が喫緊の課題となり、労使は「復旧作業の基本方針」を策定しました。この方針は、関係各界の厳しい状況を踏まえ、労使の徹底した自己努力を前提としていました。 具体的には、従前の対労組協定書に基づく職場規律と作業管理の再確認、復旧期間中の間接経費節減、従前の協定書に基づく出稼向上対策による復旧作業員の確保、そして復旧作業期間中の職場規律の厳正化などが盛り込まれていました。 さらに、所定休日の復旧作業(切羽条件によっては休日採炭も実施)、4交替制の実施(別途協議)、そして55年10月4日と56年1月4日の出勤者への出勤奨励給(時間割基礎額の1.25倍)の支給などが決定されました。 これらの基本方針に基づき、9月23日には団体交渉が行われ、会社生存を前提とした解決が図られ、協定書が締結されました。この協定は、早期復旧を目指し、労使双方の徹底した協力体制を確立することを目的としていました。
IV.組合の財政と運営
組合は、北寮の運営や組合費の改定について協議しました。北寮は組合員の共有財産であり、健全な運営を継続することが確認されました。組合費は、健全財政の運営のために値上げすることが決定されました。 また、組合は会社との共同運命体としての認識を強め、会社安定まで協議会を継続する方針を示しました。
1. 組合費の値上げと健全財政運営
組合の財政状況に関する議論では、55年度の組合費を現行より150円値上げすることが決定されました。これは、組合の健全な財政運営を確保するための措置として講じられたものです。 値上げの必要性は、組合活動の維持、そして将来的な展望を見据えた活動の継続を確保するために不可欠と判断されたためです。 組合費の値上げは、組合員の負担増につながるため、慎重な検討が行われたと考えられます。 この決定は、組合員の協力の下、健全な財政運営を実現するための重要な一歩として位置付けられています。
2. 北寮の運営継続と課題
組合が所有する北寮の運営についても議論が行われました。本年度の収支見込みは、組合員の協力によって若干の収益が見込まれ、来年度の利用状況も含め収支トントンとなる見込みであると報告されています。 北寮は組合員の共有財産として位置付けられており、その維持・運営は組合の重要な責任であると認識されています。 そのため、北寮の運営は継続されることとなりましたが、健全な運営を継続するためには、宿泊費の値上げ、補助費の積極的な獲得、そして更なるアピールによる利用促進など、いくつかの課題が提示されています。 宿泊費の値上げについては、組合員への配慮を十分に行い、値上げ額や時期は協議会委員会に一任されることになりました。
3. 協議会体制の維持と今後の展望
組合は、会社との関係性、そして組合内部の体制についても議論を行いました。 会社との関係性については、分離以来、独立独歩を目標としていたものの、実際には逆の方向に進んでいる現状を憂慮し、会社と組合の共同運命体としての関係を改めて認識しています。そのため、会社が安定するまでは、協議会体制を継続することが決定されました。 組合内部の体制については、各組合間の調整と指導機関としての協議会の重要性が強調され、協議会の安定を目指し、単年度毎の議論だけでなく、将来展望も視野に入れた運営が求められています。 ただし、各組合の財政状況や協議会の財政状況を考慮し、現状の組合費3.3%以内であれば、現行機構を継続することが好ましいと判断されました。 重大な体制変化が生じた場合は、組対委を設置して検討することが決定されました。
