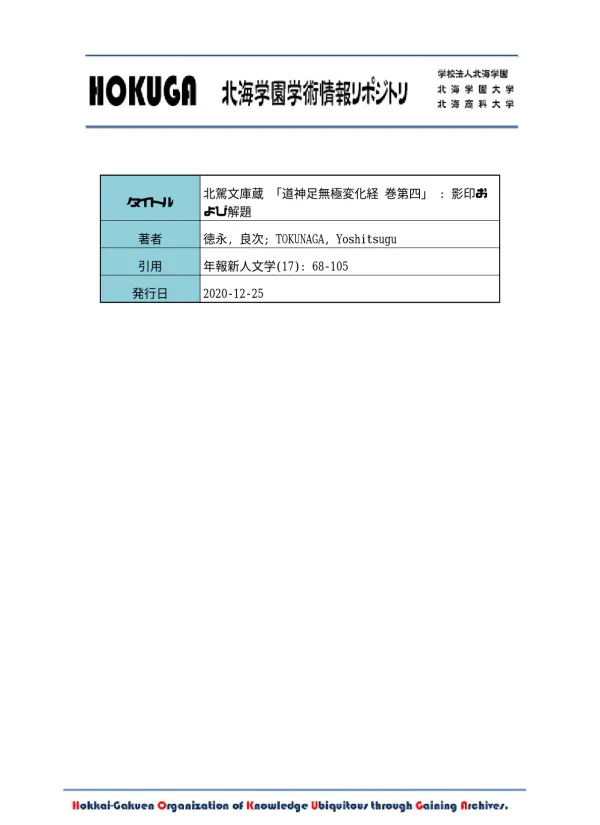
北駕文庫宋版経典:道神足無極変化経巻第四
文書情報
| 著者 | 徳永 良次 |
| 学校 | 北海学園大学 |
| 専攻 | 仏教学、東洋史学、もしくは関連分野 |
| 文書タイプ | 学術論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 6.07 MB |
概要
I.北駕文庫蔵 道神足無極変化経巻第四 宋版一切経の貴重な一巻
本資料は、学校法人北海学園の『北駕文庫』が所蔵する、宋版一切経の一部である『道神足無極変化経巻第四』の影印と解題です。開元寺版と推定されるこの一巻は、中国宋時代の靖康元年(1126年)刊行で、非常に良好な保存状態を保っています。本文は一紙あたり半面六行、一行十七字、全三十六行で、「張元印造」の印が確認できます。北駕文庫は明治四十四年、浅羽靖校長により設立され、多くの古写本、古刊本、特に「國書」の収集に力を注ぎました。大正三年の『北駕文庫蔵書畧目録』には約三万一千冊の蔵書が記録されています。本資料の北駕文庫への収蔵経緯は不明ですが、今後の調査に期待したいところです。本経は、仏教経典『忉利天為母説法経』の異訳とされ、『仏書解説大辞典』にも記述があります。 宋版一切経は、蜀版、東禅寺版、開元寺版、思渓版、碩砂延聖院版の五度の開版事業があり、日本にも多数輸入されました。現在、日本各地の寺院に宋版一切経が散逸して残存していますが、本資料はそれらの中でも特に貴重な一巻と言えるでしょう。
1. 資料の概要と北駕文庫
本稿では、学校法人北海学園の北駕文庫が所蔵する『道神足無極変化経 巻第四』を紹介する。これは、南宋時代の靖康元年(1126年)刊行と推定される開元寺版宋版一切経の一部である。筆者は以前、北駕文庫蔵書畧目録(大正三年刊行)を参考に概略を紹介したが、今回は北海学園の協力を得て、原本調査、撮影、影印、解題を行うことができた。 北駕文庫は明治四十四年、浅羽靖校長により設立され、特に國書の収集に力を入れていた。設立当初は約一万五千冊、大正三年の目録では約三万一千冊の蔵書があったと記録されている。本資料『道神足無極変化経 巻第四』もその中に含まれるが、具体的な収蔵経緯は不明である。 資料の状態は、十二世紀の印刷本としては非常に良好であり、当初の折本装の状態が保たれている。ただし、表紙は後補であり、江戸時代のものと推定される。また、裏打ち補修が少なくとも二回行われている。本文は一紙あたり半面六行、一行十七字、全三十六行で構成され、印造印「張元印造」が確認できる。第十紙裏には墨書「二」があるが、その意味は不明である。 内題と尾題は共に「道神足無極変化経 巻第四」であり、各紙の版心には原則として千字文「被」の箱番号、略経名、紙数、刻工名が刻まれるが、第一紙は刻工名のみ、第四紙は紙数が無い。各紙の寸法はほぼ共通しているが、第十紙のみ横幅が異なる。
2. 道神足無極変化経の内容と宋版一切経
『道神足無極変化経』は、仏書解説大辞典(第八巻248頁)によると、仏が忉利天で母を教化せしことを記した経典で、雑阿含経、増一阿含経などを背景に生まれた大乗経典とされる。精神的な母、般若波羅蜜を説く点が特徴である。北駕文庫所蔵のものは、本来四巻構成の経典の巻第四のみである。 宋版一切経は、経・律・論に加え、中国で成立した仏典注釈書も含まれる、一定の秩序で構成された仏典コレクションである。中国では開元釈教録、貞元新定釈教目録が作成され、書写、印刷による一切経の制作が行われた。 宋代には、蜀版(972-977年)、東禅寺版(1080-1112年)、開元寺版(1112-1151年)、思渓版(1126-1132年)、碩砂延聖院版(13世紀)の五度の開版事業があり、日本にも多数輸入された。 本資料の刊記「福州管内衆縁就開元寺雕造毘盧大蔵経」から、開元寺版であることがわかる。開元寺版は、東禅寺版と異なり、巻末に施財刊記が多いのが特徴だが、本書には見られない。 本書の内題などに記される「被」は、千字文の百三十八番目「化被草木」の「被」で、箱番号を示している。醍醐寺蔵宋版一切経と一致する点も興味深い。一切経の構成や巻数も版本によって異なっており、思渓版は約5900巻、蜀版は約6600巻など、大きな違いがある。
3. 日本における宋版一切経の現状と本資料の位置づけ
日本への宋版一切経の輸入は平安時代末期から始まり、鎌倉時代には全国各地に広まった。高山寺のような大寺院だけでなく、中小寺院にも複数部の一切経が存在した時期もあった。 現在、日本には中尊寺、最勝王寺、喜多院、増上寺、称名寺、岩屋寺、本源寺、長瀧寺、教王護国寺、醍醐寺、知恩院、宮内庁書陵部などに、まとまった量の宋版一切経が散在している。これらは、東禅寺版、開元寺版、思渓版などが混在している。 本資料と同じ開元寺版を含む寺院は、上記のリストから最勝王寺、称名寺、本源寺、醍醐寺、知恩院、宮内庁書陵部などである。 しかし、もともと四十三蔵以上あった宋版一切経は、歴史の中で減少しており、本資料の伝来については確実な手掛かりはない。日本国内だけでなく、東アジア全体の宋版一切経の状況を考慮する必要がある。
II.北駕文庫と宋版一切経の関連性
北駕文庫は明治四十四年、浅羽靖によって設立された。設立趣意書には、特に「國書」の収集への強い意志が記されています。本資料『道神足無極変化経巻第四』は、その収集活動の中で北駕文庫に収蔵されたものと考えられます。しかし、具体的な収蔵経緯は不明です。 本資料は開元寺版の宋版一切経に属し、他の現存する宋版一切経(中尊寺、最勝王寺、喜多院、増上寺、称名寺、岩屋寺、本源寺、長瀧寺、教王護国寺、醍醐寺、知恩院、宮内庁書陵部など)と比較検討する必要があるでしょう。特に、醍醐寺蔵宋版一切経との比較において、箱番号「被」の対応関係が注目されます。 高山寺との関連についても、過去の所蔵状況を考慮し、今後の調査が必要と考えられます。
1. 北駕文庫の設立と収集活動
北駕文庫は明治四十四年、当時の皇太子(後の大正天皇)の北海道行啓を記念して、北海中学校の校長であった浅羽靖によって設立された。浅羽靖は設立趣意書の中で、図書の充実、特に「國書」の収集を重視しており、自身の蔵書だけでなく、友人や知人にも寄贈を呼びかけた。その結果、設立当初は約一万五千冊に達し、大正三年に発行された『北駕文庫蔵書畧目録(第一巻)』では、外国書や雑誌を除いても約三万一千冊に増加していた。浅羽靖は江戸時代以前の木版本の蒐集にも力を注ぎ、国内外の関係者から多くの寄贈を得ていたことがわかる。 本資料である『道神足無極変化経 巻第四』も、この活発な収集活動の一環として北駕文庫に収蔵されたものと考えられる。しかし、現状では、この一巻がどのような経緯で北駕文庫にもたらされたのかは明らかになっていない。今後、残された記録類の調査を通じて、その収蔵過程の解明が期待される。
2. 本資料と宋版一切経 そして現存状況との比較
本資料『道神足無極変化経 巻第四』は、開元寺版宋版一切経の一部である。宋版一切経は、「天地玄黄」で始まる千字文が付された経箱に収蔵されるのが一般的であり、本資料の内題などに記されている「被」は千字文の百三十八番目「化被草木」の「被」に該当する箱番号である。この番号は、醍醐寺蔵宋版一切経(東禅寺版、一部開元寺版を含む)の記載と一致する。 日本に現存する宋版一切経は、中尊寺、最勝王寺、喜多院、増上寺、称名寺、岩屋寺、本源寺、長瀧寺、教王護国寺、醍醐寺、知恩院、宮内庁書陵部などに所蔵されているが、その種類は開元寺版、東禅寺版、思渓版などが混在している。 本資料は、これらの現存する宋版一切経と比較検討することで、その位置づけや来歴をより明確にできる可能性がある。特に、同じ開元寺版が含まれる寺院との比較は重要となるだろう。また、高山寺との関係性についても、過去の所蔵状況などを考慮した更なる調査が必要とされている。
3. 宋版一切経の輸入と日本の仏教
日本に宋版一切経が最初に輸入されたのは、平安時代末期の鳥羽殿経蔵の福州版(東禅寺版と開元寺版の混合)であるとされている。その後、鎌倉時代には多数の宋版一切経がもたらされ、畿内だけでなく東北、関東、九州に至る全国各地の寺院に広まった。当時、それほど規模の大きくない寺院でも、三蔵もの一切経(内、二蔵は宋版)を所有していた例があり、宋版一切経の輸入がいかに盛んだったかがわかる。 高山寺聖教目録には、「唐本」として宋版一切経(福州版)の記述があり、東経蔵の一切経は宰相僧都眞遍の寄進による書写本とされている。近年では、愛知県知多郡岩屋寺所蔵の思渓版一切経が、少なくとも十三世紀後半から十四世紀中頃までは高山寺にまとまった形で所蔵されていたことが明らかになっている。 これらの事実は、宋版一切経の輸入と受容が日本の仏教に与えた影響の大きさを示唆している。本資料『道神足無極変化経 巻第四』も、その流れの中で北駕文庫に伝来したと考えられるが、その詳細な経緯は今後の研究課題である。
III.宋版一切経の種類と日本への伝来
中国宋代には、蜀版、東禅寺版、開元寺版、思渓版、碩砂延聖院版など複数の宋版一切経が作成され、日本にも多数輸入されました。平安時代末期には鳥羽殿経蔵に福州版(東禅寺版と開元寺版の混合)が輸入されたとされ、鎌倉時代には全国各地に広まりました。現存する宋版一切経は、多くの寺院(中尊寺、最勝王寺など)に散在しており、その種類も開元寺版、東禅寺版、思渓版などが混在しています。 本資料である『道神足無極変化経巻第四』は、その中でも開元寺版に分類される貴重な一巻であり、その来歴の解明は今後の課題です。
1. 中国における宋版一切経の諸版本
中国では10世紀の北宋時代に皇帝太宗によって勅版一切経が完成した後、書写ではなく印刷による一切経の制作が盛んに行われるようになった。その最初のものは、制作された土地の名を取って「蜀版一切経」と呼ばれ、巻子本の体裁をとっている(972-977年)。その後、11世紀後半には福州閩県の東禅等覚院(後に東禅寺)で「東禅寺版」(または「福州版」、1080-1112年)が作成された。これは折本装で、紺色の帙表紙に金字で表題と千字文を記し、版心に略経名、巻次、丁数、刻工名が刻まれている。 同じ福州閩県では、開元寺においても「開元寺版」(または「毘盧蔵」、1112-1151年)が作成された。開元寺版は、東禅寺版と同様に折本装だが、歴代住持が勧進僧となって助縁を募ったため、巻末に施財刊記が刻まれていることが多い点が異なる。さらに、12世紀には思渓円覚院で「思渓版」(または「円覚蔵」、1126-1132年)が、一族によって開版されたため施財刊記がなく、版心が紙の継ぎ目で見えないのが特徴である。黄表紙に墨書で題と千字文が記されている。 13世紀には南宋・蘇州の碩砂延聖院で「碩砂延聖院版」が制作されたが、途中で罹災したため中断、14世紀に元代になって追雕が完了した。折本装だが表紙は茶・赤褐色となっている。このように、宋代には複数回にわたり一切経の開版事業が行われ、その体裁や表紙の色、形式なども異なっている。一切経の巻数も版本によって異なり、思渓版は約5900巻、蜀版は約6600巻など、大きな差が見られる。
2. 日本への宋版一切経の輸入と伝播
日本に宋版一切経が初めて輸入されたのは、平安時代末期の鳥羽殿経蔵の福州版(東禅寺版と開元寺版の混合)であるとされている。その後、鎌倉時代には多数の宋版一切経が日本にもたらされ、畿内のみならず東北、関東から九州に至るまで全国各地に広まった。 当時、規模のそれほど大きくない寺院でも、ある時期には三蔵もの一切経(そのうち二蔵は宋版)を所有していたことがあり、宋版一切経、特に最新のものが盛んに輸入されていたことがわかる。 高山寺聖教目録には、高山寺が所有していた一切経について、「一部唐本 納西経蔵」、「一部納東経蔵」とあり、「唐本」が宋版一切経であり福州版であると推定されている。一方、東経蔵の一切経は宰相僧都眞遍の寄進による書写本とされている。 また、近年では、愛知県知多郡の岩屋寺が所蔵する思渓版一切経が、少なくとも13世紀後半から14世紀中頃までは高山寺にまとまった形で所蔵されていたことが明らかになった。これらから、宋版一切経は、当時日本の仏教界において非常に重要な役割を果たしていたことがわかる。しかし、現存する宋版一切経の数は、当初の大量の輸入から比べると大幅に減少し、その伝来過程の解明は今後の課題である。
3. 現存する宋版一切経と本資料との関係
現在、日本には中尊寺、最勝王寺、喜多院、増上寺、称名寺、岩屋寺、本源寺、長瀧寺、教王護国寺、醍醐寺、知恩院、宮内庁書陵部などにまとまった量の宋版一切経が現存する。これらの宋版一切経には、開元寺版、東禅寺版、思渓版などが混在している。 本資料『道神足無極変化経 巻第四』は開元寺版であるため、同様に開元寺版を含む寺院(最勝王寺、称名寺、本源寺、醍醐寺、知恩院、宮内庁書陵部など)と比較検討することで、本資料の来歴を推測できる可能性がある。 しかし、もともとは四十三蔵以上も輸入された宋版一切経が、長い歴史の中で罹災や戦乱、自然災害などを経て、現存するものは大幅に減っているため、本資料の正確な伝来過程を明らかにすることは難しい。 本資料が、他の宋版一切経のコレクションに由来するものか、あるいはそれ以外の経路で日本に伝わってきたものか、さらには東アジア圏外から伝わってきたものかの可能性も考えられる。今後の更なる調査によって、本資料の来歴が解明されることを期待したい。
