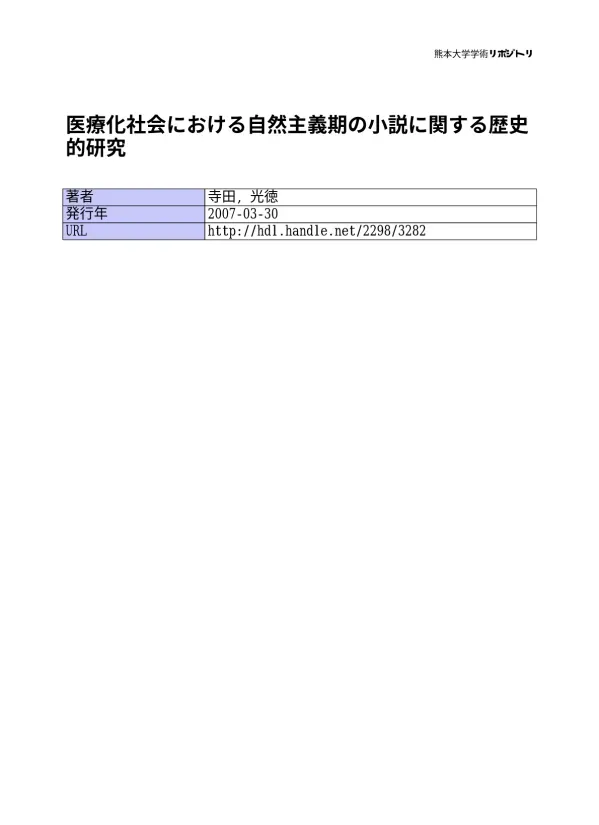
医療化社会と自然主義小説
文書情報
| 著者 | 寺田 光徳 |
| 学校 | 熊本大学 |
| 専攻 | 文学 |
| 出版年 | 2006 |
| 文書タイプ | 研究成果報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.08 MB |
概要
I.世紀フランスにおける医療制度と社会 医師 と 保健士 の役割
本論文は、19世紀フランスの写実主義・自然主義文学作品、特にフローベールの『ボヴァリー夫人』を分析することで、当時の医療制度と社会構造を探ります。医師は医学博士(博士)と保健士の二種類に分類され、その役割と社会的地位、収入格差などが医療化の進展にどう影響したかを考察します。ヴァントーズ法(1803年)による医師の国家資格制度の確立や、薬剤師の役割を担うジェルミナル法(1803年)についても分析し、医療における専門職の分業と競争、そしてそれに伴う問題点(闇医療など)を明らかにします。重要な登場人物として、ボヴァリー夫人、ラリヴィエール博士、カニヴェ博士、薬剤師オメーなどが挙げられます。
1. 19世紀フランスの医療制度 医師の二種類とヴァントーズ法
19世紀初頭のフランスでは、医師は医学博士(博士)と保健士の2種類に分類されていました。これは、医療の専門性と社会的地位に大きな影響を与えました。特に、1803年に制定されたヴァントーズ法は、医師の国家資格制度を確立し、医師の養成と管理を一元化しようとする試みでした。しかし、この制度はすぐに十分な数の医師を確保できず、特に保健士については、その能力や資格に不安が残る部分がありました。保健士は貧しい、無能力といった非難に晒されることもありましたが、七月王政期以降は、国民の医療化を着実に進める上で重要な役割を果たしたと評価されています。このヴァントーズ法は、当時のフランス社会における医療の現状と課題を浮き彫りにしています。医師の資格、教育、そして社会的地位に関する様々な問題が、この法制定によって明らかになったと言えるでしょう。特に、博士と保健士という二種類の医師が存在したことは、医療の質やアクセスに影響を与えた重要な要素です。また、この制度の不完全さや、それに伴う社会問題も、この時代における医療の複雑さを示しています。
2. 保健士の役割と限界 ボヴァリー夫人の事例分析
フローベールの『ボヴァリー夫人』に登場するシャルル・ボヴァリーは保健士として描かれています。彼は反足術という高度な外科手術を試みますが、失敗し患者の足を切断するという重大な事態を招きます。この事例は、当時の保健士の医療技術の限界や、医療行為における法規制の甘さを示しています。また、ボヴァリーの手術を地方紙『ルーアンの灯』で宣伝した薬剤師オメーの存在も重要です。オメーは闇医療を行っており、ボヴァリーとの関係も複雑です。オメーは薬剤師として上位の資格を持ち、知識も豊富だったのに対し、ボヴァリーは能力に劣る保健士として描かれています。この二人の関係は、当時の医療制度における専門職間の力関係や、資格制度の不完全さを反映していると言えます。ボヴァリーの手術失敗とその後の処置、そしてオメーの闇医療は、当時のフランスにおける医療の現状と社会の状況を反映する象徴的な出来事と言えるでしょう。特に、司法当局の監視の甘さも、当時の医療における問題点の一つとして示唆されています。
3. 医師と薬剤師 医薬分業と闇医療の問題
1803年のジェルミナル法は、薬剤師の国家管理を制度化しました。これは、医薬分業の概念を導入する試みでしたが、実際には医薬分業は十分に浸透しておらず、薬剤師が闇医療を行うケースも見られました。薬剤師オメーは、処方箋に基づく薬の販売に加え、医者に対抗して闇医療を公然と行っていました。これは、医薬分業という概念が社会に定着するまでに時間が必要だったこと、そして当時の医療制度における規制の不完全さを示しています。医者の視点からはオメーの行為は非難されるべきですが、地方では医師と薬剤師が不足しており、医療のアクセスが限定されていたという事情も考慮する必要があります。このことから、闇医療の発生には、社会構造や医療制度の不備といった背景も関わっていたことが分かります。また、医師と薬剤師の関係は、協力関係であると同時に競争関係でもありました。これは、当時の医療現場における複雑な力関係を反映しています。オメーとボヴァリーの関係は、この医薬分業と闇医療の問題を象徴的に表していると言えるでしょう。
4. 都市と地方の医療格差 医師の分布と医療アクセス
19世紀フランスでは、都市部と地方部で医師の分布に大きな偏りがありました。高収入が見込める都市部に医師が集中し、地方部、特にブルターニュ地方では医師不足が深刻な問題でした。この医療格差は、医師の開業場所の自由度と、博士と保健士という二種類の医師の存在によって生じました。博士は全国どこでも開業可能でしたが、保健士は審査委員会の管轄県内に限定されていました。このことは、医師の分布に地理的な不均衡を生み出し、医療アクセスに大きな影響を与えたと考えられます。1881年の統計では、住民2537人当たり1人の医師という割合であり、地方部では5000人以上に1人の医師しかいない地域もありました。パリのような大都市と、ブルターニュ地方のモルビアン県などの地方部の状況を比較すると、その格差は歴然としています。この医療格差は、単なる地理的な問題ではなく、社会経済的な要因と深く結びついた複雑な問題であったと言えるでしょう。この状況は、当時のフランス社会における貧富の差や、地域間の経済格差を反映しています。
II.主要な感染症と近代医学の発展 コレラ 天然痘 結核
19世紀フランスを襲ったコレラ、天然痘、結核といった主要な感染症は、近代医学の発展を促す重要な要因となりました。コレラ流行(1832年、1848年、1853年、1865年)は公衆衛生政策の転換点となり、パリ改造など都市環境の改善に繋がりました。また、天然痘に対する種痘法の普及や、結核菌の発見(1882年、コッホ)は、感染症対策における画期的な進歩でした。これらの感染症の蔓延と対策は、人々の医療に対する意識、そして近代医学の確立に大きく貢献しました。特に、細菌学の進歩(パスツール)は、感染症に対する理解と治療法の開発に革命をもたらしました。
1. コレラと19世紀フランス 流行と公衆衛生政策
19世紀のフランスは、コレラの大流行に見舞われました。歴史家ピエール・ダルモンはコレラを「ペストとコレラ」と表現し、その脅威の大きさを示しています。1832年のコレラ大流行は、フランスにおけるコレラ対策の転換点となりました。それまでは、悪臭(瘴気)が病気の原因だと考えられていましたが、コレラが貧しい地区で多く発生したことから、庶民の住環境と雑居性が問題視されるようになりました。1853年にはオスマンによるパリ改造が開始され、都市の衛生環境改善が進められました。しかし、『十九世紀ラルース大辞典』によれば、その後もコレラは繰り返し流行しており(1884年、1848年、1853年、1865年)、パリでも多くの犠牲者を出しました。1883年のエジプトにおけるコレラ流行において、コッホがコレラ菌を発見したことは、コレラ研究における画期的な進歩でした。この発見は、コレラ対策に大きな影響を与え、公衆衛生政策と近代医学の進歩を促す重要な出来事となりました。コレラの流行は、単なる疫病の蔓延ではなく、社会構造や公衆衛生政策、そして近代医学の発展に深く関わる重要な歴史的出来事と言えるでしょう。
2. 天然痘と種痘 近代医学における予防医学の進歩
天然痘も19世紀フランスにおける大きな問題でした。ゾラの『壊滅』には、普仏戦争中の野戦病院における天然痘患者の惨状が描かれています。天然痘に対する対策としては、種痘が行われていましたが、『十九世紀ラルース大辞典』によると、ウシ天然痘病毒の保存が難しいことから、天然痘膿疱から直接天然痘液汁を接種する手法が用いられていたとあります。この方法は、種痘医が常に膿疱を持った生身の人間を確保しなければならないという、大きな困難がありました。ワクシニアウイルスという人工的なウイルスが開発されたものの、その有効性や安全性の確認には、ウイルスの存在が確認される時代を待つ必要がありました。天然痘に対する種痘法は、近代医学における予防医学の進歩を示す重要な事例です。しかしながら、当時の科学技術の限界や、ウイルスの存在そのものが未解明だったことなどから、種痘法の普及やその有効性には大きな課題が残されていました。この天然痘に対する取り組みは、近代医学の進歩と、その限界を同時に示していると言えるでしょう。
3. 結核と病理学 病理解剖学と細菌学の発展
結核も19世紀フランスにおいて重要な感染症でした。 かつては「phtisie」と呼ばれていた結核は、ラエネックの聴診器や病理解剖の発展により、「tuberculose」という新たな病理学的理解へと移行していきます。しかし、この認識の変化は医学界に浸透するのに半世紀を要しました。 ヴィルマン(1865-1868)は結核の伝染性を明らかにしましたが、伝染の証拠提出には至らず、コーンハイムとサロモンセンによる接種実験(1870-1880)でそれが確認されました。一方、パリ医学部のペテール教授は結核を遺伝性のものと主張し、結核患者は他の患者と隔離されませんでした。1882年にコッホが結核菌を発見したにもかかわらず、結核の死亡率はすぐには低下しませんでした。これは、結核菌の特殊性や、細菌学の進歩が社会に浸透するまでに時間を要したことを示しています。結核に関する病理学史は、近代医学の進歩と、その社会への浸透における時間差を浮き彫りにしています。ビシャの病理解剖学やコッホの結核菌発見といった発見は、近代医学の基礎を築いた重要な出来事であると言えるでしょう。
III.アルコール中毒と社会問題 ゾラの 居酒屋 における描写
ゾラの『居酒屋』は、19世紀後半のフランスにおけるアルコール中毒問題をリアルに描き出しています。特に、労働者階級におけるアルコール中毒の蔓延とその社会問題が詳細に描かれており、当時の社会状況を反映しています。この作品は、医療化という視点からも重要で、アルコール依存症が単なる道徳的問題ではなく、社会構造と密接に関連した医療問題であることを示しています。また、反アルコール・キャンペーンの勃興とその社会運動についても考察します。重要なキーワードとして、モンマルトル、労働者階級、社会運動などが挙げられます。
1. ゾラの 居酒屋 アルコール中毒と労働者階級の描写
エミール・ゾラの『居酒屋』は、19世紀後半のパリ、モンマルトルを舞台に、労働者階級の生活とアルコール中毒の問題を描いています。ゾラは、出版者ラクロワへの手紙の中で、『居酒屋』の構想として、「今日の労働者家庭の活写」「パリの一労働者が…どのように失墜していくか…内部からえぐり出そうとするドラマ」を挙げています。そして、「事実を語り、事実の率直な提示をすることによって、下層階級のために大気と光と教育を要望する」ことを目的としていたと述べています。そのため、作品には労働者の貧困や、アルコール依存症による家庭崩壊といった、当時の社会問題が赤裸々に描かれています。ゾラは、俗語や自由間接話法を用いるなど、リアルな描写を追求しており、その表現は当時の読者から批判を受けるほどでした。この作品は、アルコール中毒という問題を単なる個人の堕落としてではなく、社会構造や経済状況と深く結びついた問題として捉えている点で重要です。
2. アルコール中毒問題と社会運動 反アルコール キャンペーン
19世紀後半、第三共和政期に入ると、アルコール中毒は社会問題として認識され、社会運動が活発化しました。1873年には「フランス禁酒協会」が設立され、『禁酒』という機関誌を発行するなど、積極的に反アルコール・キャンペーンを行っていました。この協会は学者や知識人、医師などによって構成されていましたが、それ以外にも、様々な階級の人々を対象とした民衆的な団体も登場しました。1896年には「反アルコール中毒フランス連合」が設立され、運動はさらに広がっていきました。これらの運動は、アルコールの危険性を訴え、節酒を呼びかけることを中心課題としていました。こうした社会運動の高まりを受け、1915年には高濃度のアブサンが法律によって禁止されました。このアブサンの禁止は、反アルコール・キャンペーンの成果を示す象徴的な出来事です。ゾラの『居酒屋』は、こうした社会運動の背景と、アルコール中毒問題の深刻さを示す重要な文学作品と言えるでしょう。
3. アルコール中毒に対する社会学的視点 ビュレの分析
ビュレは、アルコール嗜癖を「貧しい階級のなかのもっとも堕落した部分」に見る一方、「大都市の貧民」に一般化し、さらに未開人との比較にまで踏み込んでいます。これは、アルコール中毒を単なる個人の問題としてではなく、社会階層や人種といった要素と結び付けて論じていることを示しています。社会学では、社会的規範からの逸脱を医学的な問題として扱う「逸脱の医療化」という概念が用いられますが、ビュレの分析は、それ以上に、アルコール嗜癖を持つ人々を生物学的な視点から「異質なもの」として捉えていると言えるでしょう。これは「逸脱の人種化、生物化、自然化」と表現することもできます。ビュレの意見は、アルコール中毒という問題を、医学的、社会学的な多角的な視点から分析する上での一つの重要な視点を示していますが、同時に、その分析には偏見や差別的な要素が含まれている点も留意する必要があるでしょう。
IV.地方における医療 医師の分布と医療格差
19世紀フランスでは、都市と農村部における医師の分布に大きな格差が存在しました。特に、ブルターニュ地方などでは、医師不足が深刻な問題でした。この医療格差は、医師の収入と密接に関連しており、高収入が見込める都市部に医師が集中する傾向がありました。博士と保健士の二種類が存在したことも、医療格差の一因となっています。この医療格差は、社会構造と経済状況と深く結びついており、医療化の進展における大きな課題であったと言えるでしょう。 リヨン、マルセイユ、トゥールーズ、ボルドーといった主要都市と、ブルターニュ地方のモルビアン県などの状況を比較対照することで、この格差を分析します。
1. 医師の分布と医療格差 都市部と地方部の比較
19世紀フランスでは、医師の分布に都市部と地方部で大きな偏りがありました。これは、主に経済的な要因によるものでした。高収入が見込める都市部には医師が集中し、一方、地方部、特にブルターニュ地方では深刻な医師不足が問題となっていました。1881年の統計によると、国全体の平均では住民2537人あたり1人の医師という割合でしたが、ブルターニュ地方のモルビアン県では、その割合は住民5274人あたり1人でした。対照的に、パリを擁するセーヌ県では、住民662人あたり1人の医師という高い医師密度を示していました。この医師の偏在は、医師の収入に大きく影響しました。博士は全国どこでも開業可能でしたが、保健士は審査委員会の管轄県内に限定されていました。このため、医師たちは高収入が見込める都市部への開業を志向し、結果として地方部での医療格差が拡大しました。 ノルマンディー、ピカルディー、南西部フランス、プロヴァンス地方などは比較的医療化が進んでいたのに対し、ブルターニュ地方は医療化が遅れていた地域として挙げられています。
2. 博士と保健士 資格制度と医療提供体制
19世紀フランスの医師には、医学博士(博士)と保健士の2種類がありました。この2種類の医師の存在も、医療格差に影響を与えていました。博士は全国どこでも開業可能で、保健士は審査委員会の管轄県内に限定されていましたが、県内であれば自由に移動でき、原則として自由競争でした。この資格制度の違いは、収入格差に繋がりました。博士は保健士よりも高い収入を得ることができ、結果として、都市部には博士が多く、地方部には保健士が多いという状況が生まれていました。しかし、都市と農村、富裕層と貧困層といった診療対象への棲み分けによって、博士と保健士はフランスの医療化に貢献しました。 1892年に保健士制度が廃止される直前まで、この二種類の医師による医療提供体制が維持されていました。この保健士制度の廃止は、フランスの医療制度における大きな転換点となります。
3. 地方における医療の課題 ベナシスの事例
医師ベナシスは、貧しい村の改良事業に尽力しました。これは、地方における医療の問題点と、医師が果たす役割の多様性を示す事例です。彼は医業の傍ら、小郡の郡長となり、村の経済発展のため、籠製造業の振興や道路建設を行いました。また、クレチン病患者を含む住民のための住宅建設にも取り組みました。これにより、村の経済は活性化し、食糧事情の改善も実現しました。ベナシスの活動は、医療行為のみならず、社会基盤整備や経済活動の活性化まで範囲を拡大したことを示しています。この事例は、地方における医療が、単に病気の治療という枠を超えて、住民の生活全般に影響を及ぼすものであることを示しています。ベナシスの活動は、地方における医療の課題と可能性を同時に示す、象徴的な事例と言えるでしょう。グルノーブル街道に接続する郡道の建設など、具体的な取り組みが記述されている点も重要です。
