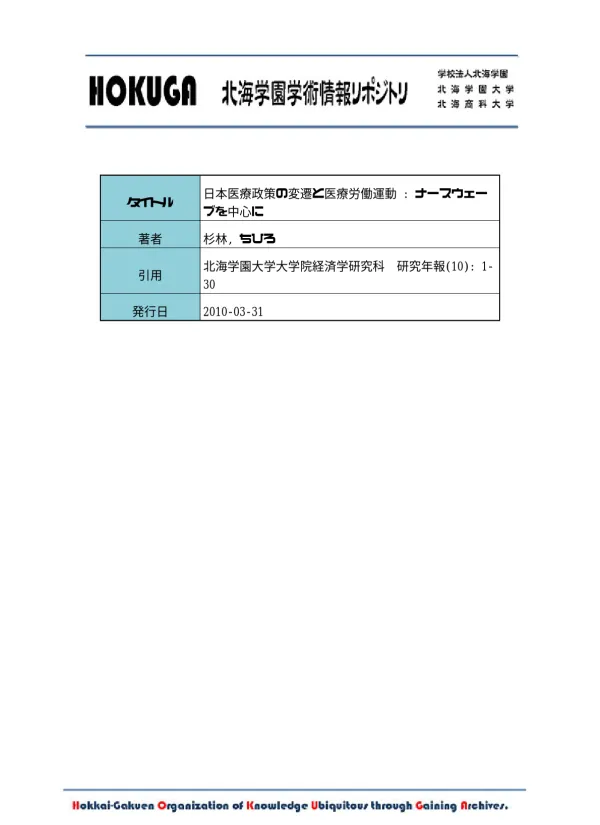
医療崩壊と過労死:医師・看護師不足の危機
文書情報
| 著者 | 杉林 |
| 学校 | 北海学園大学大学院経済学研究科 |
| 専攻 | 経済学 |
| 文書タイプ | 研究年報 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.92 MB |
概要
I.日本の医療現場における 看護師不足 と 過労死 問題
2005年の調査では、日本の看護職員の86.1%が超過密労働によるミスやニアミスを経験しており、患者の安全が脅かされていることが明らかになった。これは深刻な看護師不足の一因であり、医療労働者の過労死問題とも深く関連している。医師の労働実態調査でも、80時間以上の勤務が3割を超え、休暇ゼロの医師も3割近くに上るなど、超長時間労働が常態化している。医療事故の増加は国民の医療不信を招いている。2006年の福島県立大野病院産科医逮捕事件はその象徴的な例であり、医療界に大きな衝撃を与えた(2008年無罪判決)。
1. 看護職員の過密労働と労働条件悪化
2005年の看護職員の労働実態調査では、看護現場の過密化と労働条件の悪化が深刻な問題として浮き彫りになった。調査によると、86.1%の看護職員が超過密労働の中でミスやニアミスを経験しており、患者の生命と安全が脅かされている実態が明らかになった。この過密労働は、看護職員の疲労困憊、離職、燃え尽き症候群を招き、深刻な看護師不足の悪循環を生み出している。 この状況は、単に個々の看護職員の負担増という問題にとどまらず、医療の質の低下や患者への安全確保という、より大きな社会問題へと発展していることを示唆している。長時間労働による身体的・精神的な負担は、医療従事者の健康を著しく損ない、ひいては医療現場全体の機能低下につながる可能性がある。 そのため、労働時間や業務量の軽減、労働環境の改善は喫緊の課題であり、抜本的な対策が必要不可欠と言えるだろう。現状のままであれば、医療現場の崩壊という最悪の事態も避けられない可能性がある。
2. 医師の過労死ライン超えの勤務実態
2006年の医師の労働実態調査では、過労死ラインである週80時間以上の勤務をしている医師が3割を超えているという衝撃的な結果が示された。さらに、前月の休みがゼロだったと回答した医師も3割近くにのぼるなど、医師の過酷な労働環境が浮き彫りになった。特に、日勤後に宿直を行い、その翌日に再び日勤を行うという32時間勤務(8+16+8)を経験した医師は8割以上おり、超長時間労働が医療現場で日常的に行われていることがわかる。この長時間労働は、医療ミスのリスク増加や、医師自身の健康被害、ひいては医療崩壊に繋がる可能性が高い。医師の働き方改革、労働時間管理の徹底、適切な人員配置の確保など、抜本的な対策が求められている。 医師不足や医療制度の問題も背景にあると推測されるため、これらの問題点についても同時並行的に解決していく必要があるだろう。
3. 医療現場の変化と過密労働の増加
近年、医療現場は医療技術・医療機器の発展・高度化、医療法改定、健康保険法改定など、めまぐるしい変化を遂げている。例えば、ある病院では一般病院を選択したものの、在院日数が長くなると診療報酬が下がるため、急性期病棟維持のため在院日数短縮を余儀なくされ、ベッド回転率の上昇、業務過密化が生じている。在院日数の短縮は、仕事の密度を高め、患者の入れ替わりも多くなるため、業務量は増加する。医療制度の変化が、急性期病棟の過密労働を加速させていると分析できる。 この過密労働は、医療従事者の負担増加、ミスやニアミスの増加、ひいては医療事故のリスク増加に直結する。そのため、医療制度改革や診療報酬体系の見直し、医療提供体制の再構築などを含め、医療現場の持続可能性を確保するための抜本的な対策が必要不可欠となる。
4. 医療事故と国民の医療不信
医療現場の過密化や長時間労働は、医療事故の増加にも繋がっている。医療事故の中には、医師や看護師が刑事事件として起訴され、有罪判決を受けたケースもあり、国民の医療不信を招く大きな原因となっている。2006年の福島県立大野病院産科医逮捕事件は、その象徴的な事例である。この事件は逮捕から2年半後に無罪判決が出されたものの、産婦人科学会や日本消化器外科学会、全国医師連盟など多くの医療関連団体が声明を発表するなど、医療界に大きな衝撃と議論を巻き起こした。 医療事故の防止には、労働環境の改善による医療従事者の負担軽減が不可欠である。同時に、医療制度や医療提供体制の改革、医療従事者への教育・研修の充実など、多角的なアプローチが必要不可欠だと言える。
II.医療制度改革と 医療費抑制 政策の影響
戦後の高度経済成長期、国民皆保険制度の導入により医療費は急増。オイルショック以降、医療費抑制政策が推し進められ、1980年代には医師・看護婦数の抑制、医学部定員削減が行われた。これは現在の深刻な医師不足、看護師不足につながった。国民健康保険制度は高齢化社会における財政負担の増加に直面し、保険料滞納問題も深刻化している。健康保険制度における診療報酬政策の変遷も、医療現場の過密化に影響を与えた。低所得層は保険外負担の増大により、社会的入院を余儀なくされるケースも増加している。
III.医療労働運動の歴史と課題
戦前の聖職者意識から脱却し、戦後、医療労働者は労働組合を結成し、賃金闘争や労働条件改善運動を展開してきた。日本医労連は医療労働者の最大組織であり、看護婦を中心とした運動を展開。夜勤制限闘争(2・8闘争)や賃金闘争、保育所問題への取り組みなど、様々な課題に取り組んできた。准看護婦制度の廃止と看護制度の一本化、看護業務の見直しも重要な課題となっている。しかし、看護婦確保法制定後も、2交替制導入や業務委譲などによる労働条件の悪化が続いている。国立病院・療養所の統廃合反対運動も、医療労働運動の重要な一環である。
IV.具体的な闘争と成果
日本医労連は、春闘での賃上げ交渉、看護師の増員要求、夜勤体制の改善、院内保育所の確保など、様々な闘争を展開してきた。1990年代にはナースウェーブや看護婦110番といった運動で、社会問題化に成功した事例も。しかしながら、医療経営者の合理化、低医療費政策によって、労働条件の悪化は依然として大きな課題となっている。国立病院・療養所の統廃合反対運動では、住民との連携により、一定の成果を挙げている。全日赤、済生会、厚生連などとの連携も重要である。
