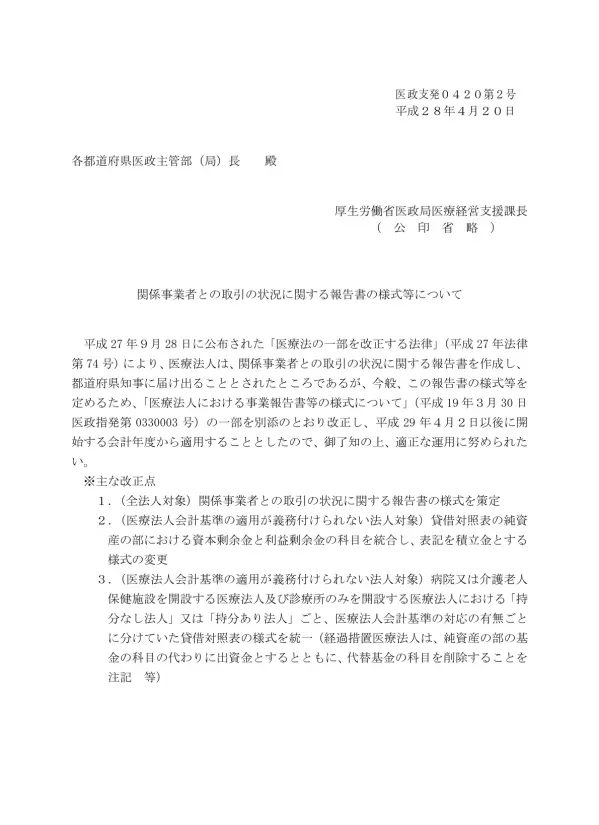
医療法人報告書様式改定
文書情報
| 著者 | 厚生労働省医政局医療経営支援課長 |
| 学校 | 厚生労働省 |
| 専攻 | 医療経営 |
| 場所 | 東京 |
| 文書タイプ | 通知 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.43 MB |
概要
I.医療法人における関係事業者との取引状況報告書の様式改正について
平成27年法律第74号による医療法改正を受け、医療法人における関係事業者との取引状況報告書の様式が改正されました。改正は平成29年4月2日開始の会計年度から適用され、すべての医療法人に関係事業者との取引状況に関する報告書の提出が義務付けられました。主な改正点は、報告書の様式策定と、一部医療法人における貸借対照表の純資産部の科目統合(資本剰余金と利益剰余金の統合、積立金への表記変更)です。新法の医療法人と経過措置型医療法人では異なる様式が適用されます。
1. 医療法改正と報告書様式の変更
平成27年9月28日公布の医療法の一部を改正する法律(平成27年法律第74号)により、医療法人は関係事業者との取引状況に関する報告書を作成し、都道府県知事に届け出る義務が課せられました。この報告書の様式等を定めるため、「医療法人における事業報告書等の様式について」(平成19年3月30日医政指発第0330003号)の一部が改正され、平成29年4月2日開始の会計年度から適用されることとなりました。改正のポイントは、すべての医療法人に適用される関係事業者との取引状況に関する報告書の様式の策定です。これにより、関係事業者との取引の透明性を高め、医療法人の健全な運営を図ることが目的です。 さらに、医療法人会計基準の適用が義務付けられていない医療法人に関しては、貸借対照表の純資産の部における資本剰余金と利益剰余金の科目を統合し、表記を積立金に変更する様式変更も含まれています。この変更は、会計処理の簡素化と一貫性を図ることを目的としています。 改正法の施行日以降に設立された医療法人、または改正法施行日前に設立され、施行日以降に定款または寄附行為の変更の認可を受けた医療法人(新法の医療法人)と、経過措置として旧法の規定が適用される医療法人(経過措置型医療法人)では、報告書の様式が異なります。それぞれの法人の状況に合わせた適切な様式を使用する必要があります。これらの変更によって、医療法人の会計処理の透明性と正確性が向上することが期待されます。
2. 新旧様式の比較と適用範囲
改正によって、医療法(昭和23年法律第205号)第51条第1項の事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、及び第46条の4第7項第3号の監査報告書の様式が変更されました。特に、関係事業者との取引に関する報告書は、すべての医療法人に義務化された重要な変更点です。 一方、医療法第51条第2項の医療法人の財産目録、貸借対照表、損益計算書の様式については、財産目録は「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成28年4月20日医政発0420第5号)の様式第三号、貸借対照表及び損益計算書は医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号)の様式第一号及び第二号に準拠することとされています。これは、会計基準の適用状況によって様式を使い分ける必要があることを示しています。改正前後の様式を比較することで、変更点の明確化と、適切な様式の選択が容易になります。 新法の医療法人と経過措置型医療法人では、適用される様式が異なる点にも注意が必要です。それぞれの法人の状況を正確に把握し、適切な様式を選択することが、法令遵守の観点から重要です。
3. 改正による具体的な変更点
今回の改正では、大きく分けて2つの変更点が挙げられます。まず、すべての医療法人を対象とした関係事業者との取引状況に関する報告書の様式の策定です。これにより、関係事業者との取引の状況を統一的な様式で報告することが可能となり、情報開示の透明性が向上します。 次に、医療法人会計基準の適用が義務付けられていない医療法人に対して、貸借対照表の純資産の部の資本剰余金と利益剰余金の科目を統合し、積立金と表記する変更が行われました。これは会計処理の簡素化を図るためのもので、会計情報の理解しやすさ向上にも繋がると考えられます。 これらの変更は、医療法人の会計処理の標準化、透明性の向上、そして監査の効率化に貢献すると期待されています。具体的な様式や変更内容については、関連資料を参照する必要がありますが、関係事業者との取引に関する情報の開示が強化された点が、今回の改正の大きなポイントです。
II.監査方法の概要
監査は、理事会出席、理事への聴取、決裁書類閲覧、施設調査、事業報告徴求、会計帳簿調査、そして財産目録、貸借対照表、損益計算書(関係事業者との取引がある場合は関係事業者との取引の内容に関する報告書も含まれる)の監査を含みます。複数監査人の場合は「私たち」と表記します。
1. 監査対象範囲と主要な監査手順
監査は、医療法人の財務状況と業務執行状況の双方を網羅的に評価することを目的としています。具体的には、理事会等の重要な会議への出席、理事等からの職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本部および主要な施設における業務および財産の状況調査、そして事業報告の徴求といった手順が踏まれています。これらの手順を通じて、医療法人の運営状況に関する包括的な情報を収集しています。 さらに、事業報告書および会計帳簿等の調査を行い、計算書類の監査を実施しています。計算書類には、財産目録、貸借対照表、損益計算書が含まれており、関係事業者との取引がある医療法人については、関係事業者との取引の内容に関する報告書も監査対象となります。社会医療法人債を発行する医療法人に関しては、純資産変動計算書とキャッシュ・フロー計算書、附属明細表も監査対象に含まれます。これらの監査を通じて、医療法人の財務状況の正確性と信頼性を確保し、会計処理の適正性を検証しています。監査人は、これらの手順を体系的に実行することで、客観的で信頼性の高い監査結果を導き出します。複数監査人の場合は、「私たち」と表記することにも留意すべきです。
2. 監査報告書の対象と内容
監査対象となる計算書類は、基本的には財産目録、貸借対照表、損益計算書です。しかし、医療法人の状況によっては、これらに加えて他の書類も監査対象となります。具体的には、関係事業者との取引がある場合は、関係事業者との取引の内容に関する報告書も監査対象となります。これは、関係事業者との取引の透明性を高めるために重要なステップです。 また、社会医療法人債を発行する医療法人の場合は、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、および附属明細表も監査対象となります。これは、債権者保護の観点からも重要な情報開示であり、監査の重要性を示しています。これらの書類は、医療法人の財務状況、経営状況、そして関係事業者との取引状況を包括的に示すものであり、監査報告書の内容を正確に反映する必要があります。 監査報告書には、監査人が行った監査手順と、その結果に基づいた結論が記載されます。監査報告書は、医療法人の財務諸表の信頼性を担保する重要な書類であり、その内容の正確性と客観性が求められます。
III.医療法人会計基準適用上の留意事項
このセクションでは、医療法人が作成する事業報告書等の会計情報(財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、附属明細表)作成に関する基準と様式が規定されています。棚卸資産の評価方法、基本財産の取扱い、リース取引の会計処理、貸倒引当金、有価証券の評価、退職給付引当金、事業損益と事業外損益の区分、継続事業の前提に関する注記など、重要な会計方針や注記事項が詳細に説明されています。特に、純資産変動計算書の作成方法や注記事項については、重要な情報が含まれています。また、重要性の原則の適用についても言及されています。
1. 会計情報の作成基準と様式
このセクションでは、医療法人が作成する事業報告書等の会計情報に関する基準と様式が示されています。具体的には、医療法第51条第2項の医療法人が、同条第1項の規定により作成する事業報告書等のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、および附属明細表の作成基準、様式などが規定されています。これらの書類は、医療法人の財務状況を正確に把握するために不可欠なものです。 運用指針では、これらの会計情報を適切に作成するための具体的な基準と様式が示されており、医療法人はこの指針に従って書類を作成する必要があります。平成26年3月19日医政発0319第7号で周知された医療法人会計基準については、従前通りの取扱いとされています。ただし、会計基準の適用状況によって様式を使い分ける必要があるため、医療法人はそれぞれの状況に適した様式を選択する必要があります。このセクションは、医療法人の会計処理の正確性と透明性を確保するために、非常に重要な役割を果たしています。
2. 会計処理方法の決定と経理規程
会計基準と運用指針は、医療法人で必要とされる会計制度のうち、法人全体に係る部分のみを規定しています。医療法人は、定款または寄附行為の規定により、様々な施設の設置や事業を行うことが可能であり、施設や事業によって会計処理が異なる場合があります。そのため、各医療法人は、自らの状況に合わせた具体的な会計処理方法を決定する必要があります。 この決定においては、各施設や事業の会計基準(明文化されていない部分については、一般に公正妥当と認められる会計基準を含む)を考慮した総合的な解釈が重要となります。 各医療法人は、経理規程を作成するなどして、具体的な処理方法を明確化し、文書として記録しておく必要があります。これは、会計処理の透明性と一貫性を確保するために不可欠な手続きです。 例えば、収益業務に関しては、内部管理上の区分において収益業務に固有の部分について別個の貸借対照表等を作成することが推奨されています。この場合、収益業務会計から一般会計への繰入金の状況についても注記する必要があります。このように、医療法人の会計処理は複雑な要素を含んでおり、適切な経理規程の作成と遵守が求められます。
3. 主要な会計処理に関する留意事項 棚卸資産 基本財産 リース取引など
このセクションでは、棚卸資産の評価方法、基本財産の取扱い、リース取引の会計処理、貸倒引当金、有価証券の評価、退職給付引当金など、具体的な会計処理に関する重要な留意事項が複数示されています。 棚卸資産の評価方法は、先入先出法、移動平均法、総平均法が原則ですが、最終仕入原価法も使用可能です。基本財産については、貸借対照表や財産目録に表示区分は不要ですが、その変動額を注記する必要があります。リース取引はファイナンスリースとオペレーティングリースに分類され、会計処理方法が異なります。 貸倒引当金は、徴収不能と認められる債権に対して計上されます。ただし、負債総額が200億円未満の医療法人では、法人税法の繰入限度額相当額を計上することもできます。有価証券は、満期保有目的であれば償却原価法が原則ですが、重要性が乏しい場合は適用除外も認められます。 退職給付引当金は、企業会計における実務上の取扱いと同様ですが、適用時差異の処理方法に留意すべき点が記載されています。これらの会計処理に関する詳細な規定は、医療法人の会計処理の正確性と一貫性を確保するために不可欠です。重要性の原則も会計処理において重要な要素として繰り返し述べられています。
IV.医療法人の計算に関する事項
平成27年法律第74号及び平成28年厚生労働省令第96号による医療法及び医療法施行規則の改正により、医療法人の計算に関する規定が整備されました。改正法は平成29年4月2日から施行されました。このセクションでは、改正法施行にあたり、医療法人の計算に関する留意事項がまとめられています。特に、監査報告書の提出期限と未提出時の扱い、理事会と社員総会・評議員会での承認手続きが重要です。また、関係事業者との取引に関する注記については、既存の様式に準じること、会計基準を適用している場合は、関係事業者に関する注記例と同一の様式であることが強調されています。
1. 医療法改正と計算に関する規定の整備
平成27年9月28日公布の「医療法の一部を改正する法律」(平成27年法律第74号)と、同日公布の「医療法施行規則及び厚生労働省の所管する法令の規則に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第96号)により、医療法(昭和23年法律第205号)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)が改正され、医療法人の計算に関する規定が整備されました。これらの改正は、平成29年4月2日から施行されました。改正の目的は、医療法人の会計処理の透明性と正確性を高め、健全な運営を確保することです。 改正された規定では、医療法人の会計処理に関する様々な事項が具体的に規定されており、医療法人はこれらの規定を遵守して会計処理を行う必要があります。地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づき、これらの改正内容に関する技術的助言が通知されています。医療法人関係者は、これらの改正内容を理解し、適正な運用に努めることが求められます。 特に、監査報告書の提出期限と、期限までに提出されなかった場合の取り扱い、理事会の承認、社員総会または評議員会での承認手続きなど、重要な手続きが明確化されています。これらの手続きを適切に履行することで、医療法人の会計処理の透明性と信頼性を高めることができます。
2. 監査報告書提出期限と承認手続き
監査報告書の提出期限までに監査報告書の内容が通知されない場合、財産目録、貸借対照表、損益計算書については、通知期限日に公認会計士等の監査を受けたものとみなすこととされています。これは、監査報告書の提出が医療法人の会計処理において非常に重要であることを示しています。 監査を受けた事業報告書等は、理事会の承認を受けなければなりません。さらに、理事会の承認を受けた事業報告書等は、社員総会または評議員会に提出し、その承認を受ける必要があります。これは、医療法人の経営における意思決定のプロセスを明確化し、透明性を高めるための重要な手続きです。 関係事業者との取引に関する注記については、「医療法人における事業報告書等の様式について」(平成19年3月30日医政指発第0330003号)に示されている様式に沿って報告することとされています。会計基準を適用している場合は、「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」(平成28年4月20日医政発0420第5号)の関係事業者に関する注記例と同一の様式を使用する必要があります。これらの規定により、医療法人の会計処理は厳格に管理され、信頼性が確保されます。
3. 必要書類の作成と公告 及び監査の必要性
会計基準を適用する医療法人が作成する書類は、別紙「作成及び公告が必要な書類について」で確認する必要があります。この別紙では、作成および公告が必要な書類とその内容が具体的に示されており、医療法人はこの内容に従って書類を作成し、公告を行う必要があります。 特に、医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号)で定める貸借対照表及び損益計算書の 作成及び公告には注記も含むこととされています。社会医療法人債発行法人については、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年厚生労働省令第38号)が適用されます。 負債総額が100億円以上の医療法人、または医療機関債を発行する医療法人で、特定の条件を満たす場合は、公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられています。これらの条件には、医療機関債の発行による負債総額、発行総額、購入人数などが含まれます。監査を受けることが望ましいケースも示されており、医療法人は、これらの規定を十分に理解し、適切に対応する必要があります。
V.作成及び公告が必要な書類
貸借対照表、損益計算書、財産目録など、作成及び公告が必要な書類がリストアップされています。社会医療法人債発行法人については、社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則が適用されます。 監査の必要性についても、負債額や医療機関債発行状況に応じて規定が示されています。
1. 作成 公告が必要な書類のリスト
このセクションでは、医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号)に基づき作成・公告が必要な書類がリストアップされています。このリストには、貸借対照表と損益計算書が含まれており、これらの書類の作成と公告には注記も含まれると明記されています。 重要なのは、社会医療法人債を発行する医療法人については、医療法人会計基準に加え、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年厚生労働省令第38号)も適用される点です。これは、社会医療法人債発行法人の会計処理が、通常の医療法人とは異なる基準に従うことを示しています。 従って、医療法人は、自らの状況(社会医療法人債発行の有無など)に応じて、適用される規則を正確に把握し、それに従って必要な書類を作成・公告する必要があります。このセクションは、医療法人が法令を遵守するために、作成・公告しなければならない書類を明確に示しています。 書類作成においては、会計基準や関連規則を正確に理解し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。
2. 監査の必要性に関する規定
このセクションでは、医療法人の監査の必要性に関する規定が記述されています。医療法第51条第2項の医療法人については、公認会計士または監査法人による監査を受けることが規定されています。 さらに、医療機関債を発行する医療法人の場合、負債総額が100億円以上、または1会計年度の発行総額が1億円以上(銀行が全額を引き受ける場合は除く)、あるいは1会計年度の購入人数が50人以上のいずれかの条件を満たす場合にも、公認会計士または監査法人による監査を受ける必要があります。 これらの条件を満たさない場合でも、医療機関債を発行する医療法人は、公認会計士または監査法人による監査を受けることが望ましいとされています。これは、医療機関債発行によるリスク管理の観点から重要な点です。 負債総額が100億円以上の医療法人についても、公認会計士または監査法人による監査または指導を受けることが望ましいとされており、医療法人は、自らの財務状況を考慮し、適切な監査体制を整備する必要があります。このセクションは、医療法人の財務の健全性を確保するための監査体制の重要性を強調しています。
VI.現地法人への出資に関する事項
現地法人への出資額は、直近会計年度の貸借対照表の繰越利益積立金の範囲内とし、医療法人会計基準を適用した会計処理を行うことが求められています。このセクションでは、会計基準の適用が強調されています。
1. 作成 公告が必要な書類の特定と基準
このセクションでは、医療法人会計基準(平成28年厚生労働省令第95号)で定められた貸借対照表と損益計算書の作成と公告について規定しています。これらの書類の作成と公告には、注記を含めることが求められています。 重要な点として、医療法人会計基準で定められた貸借対照表と損益計算書は、注記も含めて作成・公告しなければならないと明記されていることです。これは、会計情報の透明性と正確性を確保するための重要な要素です。 また、社会医療法人債を発行する医療法人については、上記に加え、「社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年厚生労働省令第38号)に従う必要があり、通常の医療法人とは異なる基準が適用される点に注意が必要です。 このセクションは、医療法人が作成しなければならない書類を明確に示すことで、法令遵守を促し、会計処理の透明性と正確性を確保することを目的としています。 医療法人は、自らの状況に合わせた適切な書類を作成・公告しなければならないことを理解することが重要です。
2. 監査の必要性と基準
このセクションでは、医療法人の監査の必要性について、負債額や医療機関債の発行状況を基準として規定しています。具体的には、医療法第51条第2項の医療法人については、公認会計士または監査法人による監査を受けることが規定されています。 さらに、医療機関債を発行する医療法人は、医療機関債の発行により負債総額が100億円以上となる場合、または1会計年度における発行総額が1億円以上(銀行が全額を引き受ける場合は除く)、あるいは1会計年度における購入人数が50人以上のいずれかの条件を満たす場合には、公認会計士または監査法人による監査を受ける必要があります。 これらの条件に加えて、負債総額が100億円以上の医療法人についても、公認会計士または監査法人による監査または指導を受けることが望ましいとされています。 医療機関債を発行する医療法人においては、これらの条件に該当するかどうかを注意深く確認し、必要に応じて公認会計士または監査法人による監査を受ける必要があります。これは、医療法人の財務状況の透明性と信頼性を確保するために不可欠な手続きです。
