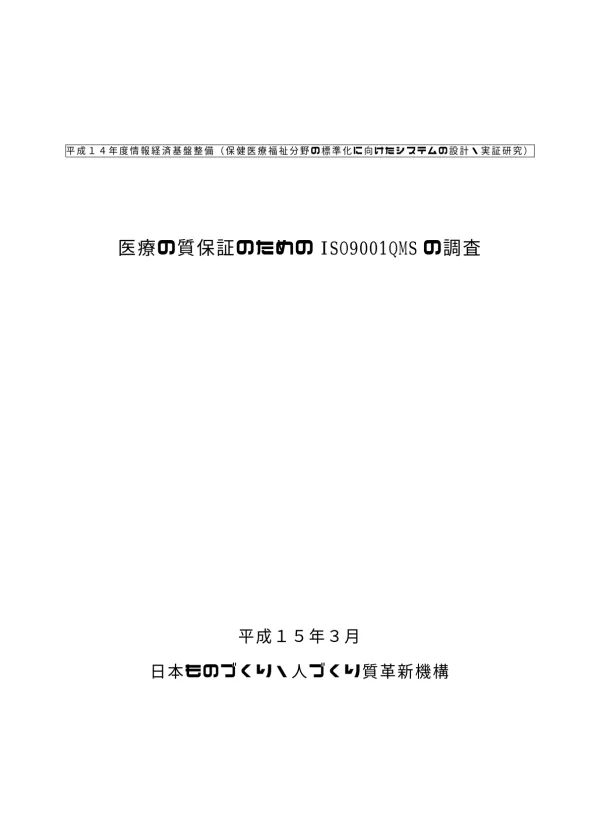
医療ISO9001:品質マネジメントシステム構築ガイド
文書情報
| 著者 | 日本ものづくり・人づくり質革新機構 |
| 専攻 | 医療経営、品質管理、公衆衛生 |
| 会社 | 日本ものづくり・人づくり質革新機構 |
| 文書タイプ | 調査報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.63 MB |
概要
I.医療機関におけるISO9001導入と品質マネジメントシステム構築
本調査研究は、医療機関における品質マネジメントシステム(QMS)構築と、特に医療版ISO9001の適用を促進することを目的とする。具体的には、医療現場における「品質」と「品質保証システム」の概念を整理し、医療機関への適用上の課題を検討。その上で、医療機関に最適化されたシステムモデルを提案し、医療版ISO9001適用指針などの作成を行う。さらに、作成した指針と教育テキストを、ISO9001 QMS導入を目指す医療機関および既に認証を取得済みの医療機関に適用し、適用性評価と改善点の抽出を行う。患者満足度の向上も重要な目標である。
1. 品質マネジメントシステム QMS 調査と医療分野への適用
本研究はまず、医療分野における「品質」と「品質保証システム」の概念を包括的に整理することを目的とする。 既存の品質マネジメントシステムに関する調査を行い、医療現場特有の課題や問題点を詳細に検討する。この調査結果を基に、医療機関の実情に合致した、より効果的なシステムモデルの構築を目指す。 医療現場の現状分析から、既存の枠組みでは対応しきれない特有の課題を洗い出し、それらに対応できる柔軟性と実用性を備えたシステムモデルの開発に注力する。 最終的には、実用的な医療版ISO9001適用指針の作成を目指す。 この指針は、これからISO9001 QMSを導入しようとする医療機関、そして既にISO9001 QMS認証を取得済みの医療機関の双方にとって、実用的な指針となることを目指している。 本研究を通して、医療機関における品質マネジメントシステム導入の障壁を解消し、更なる質の向上に貢献することを目指す。
2. 医療版ISO9001適用指針および教育テキストの作成と適用性評価
前段階の調査結果を基に、医療機関の現状に最適化されたシステムモデルと、具体的な運用のための「医療版ISO9001適用指針」を作成する。 この指針は、医療現場における特有の課題を踏まえ、実践的な内容となるように配慮されている。 同時に、指針の理解を深めるための教育テキストも作成する。 作成した指針と教育テキストは、ISO9001 QMS導入を検討中の医療機関や、既に認証を取得した医療機関で実証的に適用される。 その適用状況を綿密に調査することで、指針やテキストの実効性を検証し、更なる改善に繋げるフィードバックを得る。 この評価を通して、医療版ISO9001の有効性を客観的に示し、更なる普及促進を図る。 目標は、医療の質の向上と患者満足度向上に貢献する、実用性の高い指針と教育テキストを提供することである。
3. 水戸総合病院と東京衛生病院におけるISO9001導入事例研究
本研究では、水戸総合病院と東京衛生病院におけるISO9001導入事例を詳細に分析する。 水戸総合病院は、日本医療機能評価機構の評価結果を踏まえ、プロセス重視のISO9001認証取得を選択した。 この病院の事例からは、ISO9001導入によるチーム医療の質向上や、患者満足度向上などの具体的な成果が確認できる。 一方、東京衛生病院は2003年12月の審査登録を目標に、ISO9000を活用した質管理体制の整備に着手した。 この病院の事例は、導入初期段階におけるプロセス整理やPDCAサイクル導入のプロセスを示し、今後の改善への示唆を与える。 両病院の成功事例と課題を比較検討することで、医療機関におけるISO9001導入の成功要因と、そのための戦略を明確にする。 これらの事例研究を通して、医療機関における品質マネジメントシステム構築のベストプラクティスを提示する。
II.医療の質の定義と評価 患者満足度との関連
医療の質は、技術的要素、人的要素、アメニティの3要素から構成されると考えられる。その評価においては、患者満足度調査が代表的な手法であり、近年増加している。しかし、患者が医療の技術的側面を適切に評価できるかという点については議論があり、患者満足度は必ずしも医療の質を完全に反映する指標とは限らない。本研究では、これらの点を踏まえ、医療の質向上と患者満足度向上のための効果的な品質マネジメントシステム構築を支援する。
1. 医療の質に関する定義と構成要素
医療の質に関する定義は多様だが、比較的理解しやすいのは、技術的要素、人的要素、アメニティの3要素から構成されるという考え方である。技術的要素は、診断や治療の正確性、有効性といった客観的な指標で評価できる側面を指す。人的要素は、医師や看護師といった医療従事者と患者の間のコミュニケーション、共感、信頼関係といった、より主観的な要素を含む。アメニティは、病院の施設環境、清潔さ、快適さといった、患者の滞在体験に影響を与える要素である。これらの要素は相互に関連し合い、総合的に医療の質を決定づけていると言える。近年では、医療機関における品質評価において、患者満足度調査が広く用いられるようになってきている。
2. 患者満足度 医療の質評価指標としての妥当性と限界
患者満足度は、医療の質を評価する上で重要な指標として用いられる一方、その妥当性については議論がある。患者は、医療の技術的な側面を専門的な知識なしに評価することが困難であるという指摘がある。患者の身体的・精神的状態も、客観的な意見表明を阻害する可能性がある。迅速な医療介入、検査、評価を行う状況では、患者が現状を完全に理解できない可能性も指摘されている。さらに、医療従事者と患者の目標が一致しない場合もあり、評価の客観性を損なう要因となる。文化的な背景や、患者の年齢、教育レベル、社会経済的地位、健康状態なども患者満足度に影響を与えるため、患者満足度を医療の質を測る唯一の指標として用いることには限界がある。
3. 患者満足度に関する専門家の見解と議論
Donabedian(1980)は、患者満足度が医療の質評価において重要な要素であるとしながらも、患者が医療の技術的側面を評価できるかについては断定を避けている。Pascoe(1983)は、患者満足度を、ヘルスケアサービスに関する患者の経験全体への反応として定義している。Vuori(1987)は、患者満足度を(a) ケアの質の特性であり認識されかつ望まれるアウトカム、(b) ケアの質に関する患者の見解を表す指標、(c) 医療の質の前提条件かつ必要条件と述べている。一方、患者の評価能力に関する疑問も提起されている。米国の議会技術評価局(1988)は、患者は医療の人間関係的な側面の評価には適格だが、技術的側面の評価には他の情報源が必要だと指摘している。しかし、患者が技術的側面も評価できると考える研究者もいる(Meterkoら、1990)。これらの異なる見解は、患者満足度を医療の質評価に用いる際の注意点を示唆している。
III.ISO9001の医療機関への適用 製品とプロセスの定義
ISO9001規格を医療機関に適用する際の課題として、医療における「製品」の定義が挙げられる。E.コッドマン医師は、医療における製品を患者の転帰(End Result)と定義した。しかし、ISO9001規格の「製品」の定義をそのまま医療に適用するには、いくつかの矛盾が生じる。本研究では、医療における製品を、臨床アウトカム達成のためのプロセスと捉え、プロセス指向の品質マネジメントシステム構築を提案する。
1. 医療における 製品 の定義に関する課題
ISO9001規格は、製造業の製品を主な対象として構築されたため、医療機関への適用にあたっては、「製品」の定義を明確にすることが重要となる。E.コッドマン医師は、病院の製品は患者の転帰(End Result)であると主張した。この考え方を基に、医療における製品を「企図されたアウトカム」と解釈することもできる。しかし、この解釈では、ISO9001規格の「製品の保存」「不適合製品の管理」といった項目との間に矛盾が生じる。医療におけるアウトカムは、プロセスで完全に制御できるものではなく、多くの要因に影響を受けるため、製造業の製品と同様に扱うことには限界がある。そのため、医療機関におけるISO9001適用にあたっては、製品の定義を慎重に検討し、規格との整合性を確保する必要がある。
2. 医療行為とISO9001規格の プロセス との関連性
医療機関が提供するものは、製造業のプロセスとは異なり、行為そのものであるという視点もある。この場合、意図されたアウトカムは製品の目的と捉えられ、製品というよりも「良い」「悪い」と形容される品質に関わるものとなる。しかし、この考え方ではISO9001規格の「プロセスの監視及び測定」という項目が無意味になってしまう。製造業ではプロセスが製品を作る過程であり、品質保証において最も重要な管理対象だが、医療では行為自体が製品となるため、品質を作り込む場としてのプロセスがなくなる。したがって、医療機関へのISO9001適用においては、製品とプロセスの定義を明確にし、規格の各項目を医療の実情に適切に読み替える必要がある。 臨床アウトカムに関連する医療は、対人サービスだけでなく、患者に見えないところで様々な業務活動が行われるプロセスも含む。
3. 医療機関における製品 サービスの多様性と顧客の多様なニーズへの対応
医療機関は、風邪の患者とがん患者では、顧客要求事項とその優先度、提供すべきアウトプット(製品)が異なるため、多様な製品を扱う百貨店のような存在である。そのため、医療機関は自院で扱える患者(群)を明確にし、製品仕様あるいは標準的な製品設計(=診療方針)を事前に商品リスト(ショッピングリスト)に明示するべきである。 顧客範囲についても、患者だけでなく、地域社会、従業員、保険団体、社会全体といったステークホルダーを広く考慮する必要がある。インフラ整備などは従業員を含めて考えるべきであり、顧客という言葉が使われる場面ごとに、どの範囲を顧客と考えるべきか検討する必要がある。 ISO9001規格の顧客要求事項を満たすことで顧客満足度向上を目指すという目的は、医療機関にも適用可能だが、そのための製品やプロセスの定義、そして顧客範囲の明確化が、医療機関へのISO9001導入成功の鍵となる。
IV.水戸総合病院と東京衛生病院におけるISO9001導入事例
水戸総合病院では、日本医療機能評価機構の評価を踏まえ、プロセス重視のISO9001認証取得を選択。手順書や記録類の再構築により、チーム医療の質向上と患者満足度向上を実現した。東京衛生病院では、2003年12月を目標にISO9000を活用した質管理体制の整備に着手し、業務プロセスの整理とPDCAサイクルの導入を進めた。両病院の事例から、医療機関におけるISO9001導入と品質マネジメントシステム構築の成功要因を分析する。
1. 水戸総合病院におけるISO9001導入 日本医療機能評価機構の評価とISO9001認証取得
水戸総合病院(築42年、日立製作所企業立病院)は、各部門の役割分担を明確にするツールとして、(財)日本医療機能評価機構の評価受審を検討した。しかし、同機構の評価はストラクチャー中心であり、42年の歴史を持つ同病院では認定に不安を感じ、プロセス重視のISO9001認証取得を決定した。これは、事務職員にとってISOが聞き慣れない言葉ではなかったという背景も影響している。品質方針達成のため、全職員への品質方針・品質目標の周知徹底、患者満足度の測定・分析、経営資源の適切な提供、定期的な見直しによる継続的改善などを実施。インシデント発生時の対応についても、ランク別にセーフティマネジャー部会または医療事故予防対策委員会で対応し、病院全体でフォローアップする体制を構築した。PDCAサイクルの徹底により、リスク管理意識の向上と患者満足度の向上を実現した。
2. 水戸総合病院におけるISO9001導入による成果
水戸総合病院は、ISO9001のマネジメントシステム構築・運営を優先し、成功事例を生み出した。具体的には、これまで分散化し部署に埋没していた手順書や記録類を顕在化、再構築することでチーム医療の質を確保。院長のビジョンに基づき、各職員が目標を持って取り組む体制を構築し、患者中心の医療の質向上を実現した。これらの成果は、ISO9001導入によって、これまで顕在化していなかった問題点を明確化し、組織的な改善活動を行うことで得られたものである。 この成功事例は、医療機関におけるISO9001導入による具体的なメリットを示しており、他の医療機関にとっても貴重な参考となる。
3. 東京衛生病院におけるISO9001導入 プロセス指向とPDCAサイクルの導入
東京衛生病院は、2003年12月の審査登録を目標にISO9000を活用した質管理体制の整備に取り組んだ。2003年1月からの約2ヶ月間は、ISO9001の規格要求事項には触れず、病院業務を構成するプロセスの整理に注力。この段階で「プロセス指向」と「PDCA」の重要性を職員に自覚させることに重点を置いた。6月頃までに現状の実務プロセスの整理を終え、その後、規格要求事項と照らし合わせてシステムを補強していく計画であった。このアプローチは、ISO9001の規格を理解する前に、まず自院の業務プロセスを詳細に把握し、改善すべき点を明確にすることで、より効果的な導入を目指したことを示している。 この事例は、医療機関におけるISO9001導入の段階的なアプローチを示す好例と言える。
V.医療版ISO9001適用指針および教育テキストの開発と評価
本研究では、医療機関におけるISO9001導入を支援するための医療版ISO9001適用指針と教育テキストを開発した。開発した指針とテキストは、水戸総合病院と東京衛生病院の事例などを参考に、医療現場の実情に即した内容となっている。開発された教材の有効性を検証するため、東京衛生病院で導入教育セミナーを実施し、参加者からのフィードバックを得て、改善点を抽出した。PDCAサイクルに基づき、テキスト内容の改善や教育方法の改良を進める。
1. 医療版ISO9001適用指針と教育テキストの開発目的
本研究では、医療機関におけるISO9001導入を促進するため、医療現場の実情に即した「医療版ISO9001適用指針」と、その理解を促す教育テキストの開発を行う。 日本ではISO9001に基づく審査登録を受けた適合組織は29,000件を超えるが、「医療及び社会事業」分野はわずか140件、病院は20~30件程度にとどまっている。 これは、医療現場におけるISO9001の認知度が低いこと、および医療現場特有の業務プロセス(職種間をまたがるユニットプロセスの連鎖)への適用が難しいことなどが原因と考えられる。 そこで、医療現場のニーズに合致した指針とテキストを提供することで、医療機関におけるISO9001の導入促進、ひいては医療の質向上を目指している。 特に、プロセス指向とPDCAサイクルの考え方を、医療現場で実践できるよう支援することを目指している。
2. 医療版品質保証体系図とプロセスチャートの開発
医療版ISO9001適用指針の開発と並行して、医療機関における品質保証体制を視覚的に捉えるための「医療版品質保証体系図」と、各プロセスの流れを明確にするためのプロセスチャートを開発する。 体系図は、システム全体の構成を明確にし、プロセスチャートは、時間、部門・責任者、業務内容、方法といった要素を整理することで、各プロセスの可視化と理解を促進する。 これら図表を活用することで、複雑な医療現場の業務プロセスを分かりやすく表現し、ISO9001の各要求事項との対応関係を明確にする。 医療現場特有の多職種連携を踏まえ、ユニットプロセスの連鎖を明確に表現することで、横断的なプロセスアプローチの考え方を浸透させることを目指している。 これらのツールは、ISO9001導入における計画立案、実施、評価、改善といったPDCAサイクルの円滑な運用を支援する。
3. 教育テキストの開発と適用性評価 東京衛生病院での導入教育セミナー
開発した教育テキストは、東京衛生病院でのISO9001導入教育セミナーで活用され、その適用性評価が行われた。 セミナー参加者と推進チームメンバーから、テキスト内容、講義方法、教育スケジュールなどに関するフィードバックを得て、改善点の抽出を行う。 テキストは、図表やフローチャートを積極的に活用し、医療現場の業務事例を取り上げることで、理解しやすい内容を目指した。 しかし、テキスト内容の理解しにくさ、講義における解説と質疑応答の必要性、教育スケジュールの事前提示など、改善すべき点も指摘された。 これらの指摘を踏まえ、次年度以降、医療現場の問題を解決しながら、テキストの内容と講義方法を改善し、より効果的な教育テキストへと成熟させていく。
