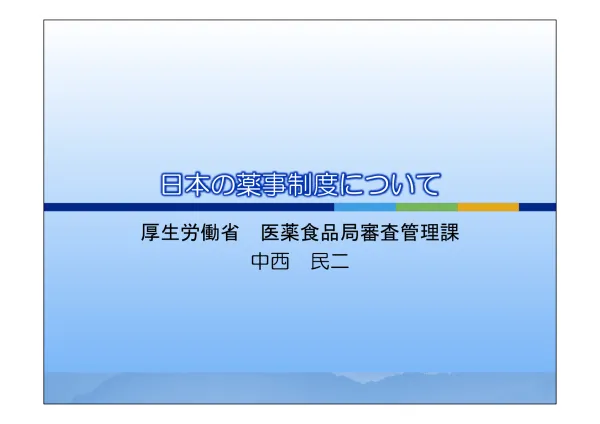
医薬品製造販売とGMP適合性
文書情報
| 学校 | 大学名(不明) |
| 専攻 | 薬学部または関連学科 |
| 出版年 | 不明 |
| 場所 | 不明 |
| 文書タイプ | 講義資料またはテキスト |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 3.89 MB |
概要
I.医薬品製造販売承認と許可 GMP 遵守と PMDA の役割
本資料は、日本の医薬品製造販売に関する規制を概説しています。医薬品を製造販売するには、厚生労働大臣による製造販売承認と、製造販売業者許可、そして製造所における**製造業許可(認定)**が必要です。これらの許可取得には、医薬品の品質、有効性、安全性に関するデータの提出と審査が不可欠であり、GMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令)への適合性が求められます。PMDA(医薬品医療機器総合機構)は、GMP適合性調査や承認審査において重要な役割を果たします。承認申請書には、販売名、成分分量、製造方法、用法用量、効能効果、貯法・有効期間、規格・試験法等が詳細に記載され、承認後に承認事項となります。原薬等登録原簿(MF)制度は、原薬等の製造方法に関する情報を保護しつつ、製剤承認申請を効率化する仕組みです。
1. 医薬品製造販売に必要な承認と許可
医薬品を製造販売するには、厚生労働大臣による製造販売承認が必須です。 これは、医薬品の品質、有効性、安全性を確認するための審査を経て得られる承認です。 同時に、製造販売業者としての許可も必要となります。業者は、医薬品の製造、品質管理、そして製造販売後の安全管理に対して責任を持つことができる体制であることを証明する必要があります。さらに、医薬品を製造する製造所においては、製造業の許可(認定)も必要となります。この許可は、製造業者が医薬品を製造する能力を有することを示すことで取得できます。これらの承認と許可取得には、申請手続きや審査、そしてGMP(Good Manufacturing Practice)への適合性が求められます。
2. 製造販売承認の要件と審査プロセス
製造販売承認を得るための要件は、医薬品の品質、有効性、安全性の確保に重点が置かれています。申請者は、これらの項目に関するデータを収集し、PMDA(医薬品医療機器総合機構)による厳格な審査を受けなければなりません。審査では、提出されたデータの妥当性だけでなく、製造工程におけるGMP遵守状況も確認されます。具体的には、製造所における製造管理及び品質管理基準の徹底が求められます。審査に合格した製品のみが製造販売承認を得ることができ、市場に出荷されます。この承認プロセスは、国民の健康を守る上で非常に重要な役割を果たしています。承認審査、許可(認定)要件調査、そしてGMP適合性調査(工場に対する調査)といった段階を経て、最終的な承認が下りるまでには、時間と労力がかかります。
3. GMP遵守とPMDAの役割
GMP(医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令)は、医薬品の製造過程における品質管理の基準を定めたものです。製造販売業者は、GMPに準拠した製造工程を確立し、維持することが求められます。PMDAは、これらの基準の遵守状況を調査・監査する役割を担っており、GMP適合性調査を実施します。これは、製造所の施設、設備、手順、そして従業員のスキルなど、製造工程のあらゆる側面を包括的に評価するものです。PMDAによる調査・監査の結果は、製造販売承認の可否に大きな影響を与えるため、製造販売業者はGMPの遵守に万全を期す必要があります。 また、PMDAは厚生労働省令で定める基準(薬局等構造設備規則等)に基づいて、外国製造業者の認定も行っています。
4. 承認申請書の構成と内容
製造販売承認申請書には、販売名、成分分量、製造方法、用法用量、効能効果、貯法、有効期間、規格・試験法など、医薬品に関するあらゆる情報が詳細に記載されます。これらの情報は、承認後、承認事項として法的拘束力を持ちます。申請書には、CTD(医薬品電子申請共通技術文書)の第一部(各国の行政文書)に準拠した形式が用いられることが一般的です。 さらに、添付文書(案)など、各地域に特異的な文書も含まれる場合があります。申請書の内容は、審査において厳しくチェックされるため、正確性と完全性が求められます。
II.製造販売承認申請と審査 CTD と MF の活用
製造販売承認申請は、**CTD(医薬品電子申請共通技術文書)に基づき行われます。申請資料には、品質、有効性、安全性に関するデータに加え、製造販売業者許可と製造業許可(認定)**に関する情報も含まれます。MF(原薬等登録原簿)制度は、原薬等の製造業者による情報開示の範囲を制御する仕組みで、製剤承認申請者は、MFに登録された情報を利用できます。MFに登録される情報は、製造方法、製造工程管理、品質管理試験、規格及び試験方法、安定性試験、貯蔵方法及び有効期間などです。PMDAは、MFを利用した製剤の承認審査を行います。
1. CTDに基づく承認申請
医薬品の製造販売承認申請は、CTD(医薬品電子申請共通技術文書)に基づいて行われます。CTDは、医薬品規制当局への申請資料作成を標準化するための国際的なガイドラインです。申請資料には、医薬品の品質、有効性、安全性に関するデータが網羅的に含まれます。 特に、品質に関するデータは、製造工程、品質管理試験、安定性試験の結果など、詳細な情報が求められます。また、製造販売業許可、製造業許可(認定)に関する情報も申請資料に含まれます。これらの資料は、PMDA(医薬品医療機器総合機構)などの審査当局に提出され、審査が行われます。審査当局は、提出された資料に基づいて、医薬品の承認可否を判断します。申請資料の正確性と完全性は、承認獲得に不可欠です。申請者は、CTDの要件を満たすように資料を作成する必要があります。
2. 原薬等登録原簿 MF 制度の活用
原薬等登録原簿(MF)制度は、原薬等の製造業者(国内外)が、製造方法などのノウハウを製剤の承認申請者に開示したくない場合に、その情報をMFとして登録しておく制度です。製剤承認申請者は、PMDA(審査当局)に提出する申請資料の一部を、このMFに登録された情報で代替することができます。これにより、申請資料の簡素化や、知的財産の保護に役立ちます。MFに登録される情報は、製造方法、製造工程管理、品質管理試験、規格及び試験方法、安定性試験、貯蔵方法及び有効期間など、原薬に関する重要な情報が含まれます。MF登録を行うことができるのは、国内外の原薬等製造業者等です。ただし、外国の事業者がMF登録を申請する場合には、国内において当該登録等の事務を行う者として、原薬等国内管理人を選任する必要があります。MFは、製剤承認申請を効率化するための重要なツールとなっています。
3. MF登録事項の位置づけと審査当局の役割
MFに登録される情報は、製剤の製造販売承認申請書の一部を代替するものであり、製剤に係る審査の際、CTDの第3部(モジュール3)に相当する部分として扱われます。PMDAは、MFに登録された情報の妥当性について審査を行うわけではありません。MF登録が受け付けられても、その内容について審査当局の承認が得られたことにはなりません。 MF登録は任意であり、登録を行うかどうかの判断は申請者自身が行います。ただし、MFを利用した製剤の承認審査においては、登録事項が審査の対象となります。そのため、MF登録を行う際には、登録に必要な形式が整っているか、必要な資料が添付されているかを確認する必要があります。MF登録者は、登録された情報について責任を負う必要があります。
III.製造方法の記載と承認申請対象 軽微変更届出 と 一部変更承認申請
承認申請書の製造方法欄には、具体的な工程が詳細に記載されます。工程の一部変更には、軽微変更届出または一部変更承認申請が必要となります。軽微変更届出は、影響の少ない変更に対して行われます。一方、影響が大きい変更に対しては、一部変更承認申請が必要となり、PMDAによる審査を受けます。
1. 製造方法の承認申請書への詳細な記載
承認申請書には、医薬品の製造方法が詳細に記載される必要があります。 これは、製造工程の再現性と品質の確保を検証するためです。具体的な記載例として、反応条件(温度、時間、使用する試薬の量など)、精製工程、結晶化、乾燥などの工程が、数値や単位を明確に含めて記述されます。 この記載の正確さと網羅性は、審査において重要な評価項目となります。不正確な記載や重要な工程の欠落は、承認申請の却下につながる可能性があります。そのため、申請者は、製造方法を正確かつ詳細に記述する必要があります。また、承認申請書には、成分分量、用法用量、効能効果、貯法、有効期間、規格・試験法なども記載されます。これら全てが承認後に承認事項となり、製造販売において遵守すべき事項となります。
2. 軽微変更届出と一部変更承認申請の違い
製造方法に変更を加える場合、その変更の程度によって、軽微変更届出と一部変更承認申請のいずれかを選択する必要があります。軽微な変更、例えば、製造工程における些細な修正などは、軽微変更届出の対象となります。一方、製造方法に大きな変更を加える場合、例えば、原料の変更、製造工程の大幅な変更、重要な工程パラメータの変更などを行う場合は、一部変更承認申請を行う必要があります。一部変更承認申請は、PMDAによる審査が必要となるため、軽微変更届出よりも手続きが複雑で、時間がかかります。申請者は、変更内容の影響範囲を適切に判断し、適切な手続きを選択する必要があります。変更内容が承認事項に影響を与えるかどうか、また、品質、有効性、安全性に影響を与えないかなどを慎重に検討する必要があります。
3. 一部変更承認申請対象の例
文書からは、具体的な一部変更承認申請の対象となる例として、製造工程における反応条件、精製工程、結晶化、乾燥などの変更が挙げられます。例えば、反応温度や反応時間、使用する溶媒の種類や量、精製方法、乾燥温度や乾燥時間などの変更は、一部変更承認申請の対象となる可能性が高いです。これらの変更は、医薬品の品質、有効性、安全性を左右する可能性があるため、PMDAによる厳格な審査が必要です。申請者は、変更によって生じる可能性のあるリスクを事前に評価し、適切な対策を講じる必要があります。また、変更の理由や変更後の工程の妥当性を明確に示す資料を提出する必要があります。申請資料には、変更前後の製造方法の比較、変更による品質、有効性、安全性への影響評価などが含まれる必要があります。
IV.海外製造所のGMP調査 国内製造所との違い
海外製造所のGMP適合性調査は、国内製造所と同様に厳格に行われます。調査にあたっては、日本のGMP省令に基づく情報提供と、製品標準書、基準書、手順書などの文書準備が求められます。承認申請書との齟齬がないよう、細心の注意が必要です。
1. 国内製造所と同等の厳格なGMP調査
海外製造所に対するGMP適合性調査は、原則として国内製造所と同等の厳格さで実施されます。これは、医薬品の品質、有効性、安全性を確保するためには、製造場所を問わず、同じ基準を適用することが不可欠であるためです。調査では、製造施設の設備、製造工程、品質管理体制などが詳細に評価されます。日本のGMP省令に準拠した製造が行われているかどうかが、重要なチェックポイントとなります。調査にあたっては、事前に製造業者に対して日本のGMP省令等の情報を提供し、理解を深めてもらうことが重要です。また、調査事項に応じて回答できる担当者を確保し、調査が円滑に進められるよう体制を整えておく必要があります。
2. 必要な文書の準備と情報提供
海外製造所におけるGMP調査では、日本のGMP省令で要求される製品標準書、基準書、手順書に該当する文書の準備が不可欠です。これらの文書は、製造工程の詳細、品質管理の方法、そして安全管理の体制などを示すものであり、調査官による審査の対象となります。これらの文書が不備であったり、日本のGMP省令と整合性が取れていない場合は、調査結果に悪影響を与えます。 また、調査前に、日本のGMP省令等の情報を製造業者に提供し、理解を促すことが重要です。これにより、調査がスムーズに進み、不必要な指摘を減らすことができます。 さらに、承認申請書との齟齬(成分・分量欄の規格、製造条件等)がないように、細心の注意を払う必要があります。
3. 海外製造所でよく見られる指導事項
海外製造所に対する実地調査においては、承認申請書との齟齬(成分・分量欄の規格、製造条件等)がしばしば指摘されます。これは、申請書に記載された内容と、実際の製造状況に差異がある場合に発生します。また、日本のGMP省令で要求される文書が不足していたり、適切な内容が記載されていない場合も指摘事項となります。さらに、製造工程の管理、品質管理、そして安全管理に関する手順書や記録が不十分な場合も、改善を求められる可能性があります。これらの指導事項は、医薬品の品質、有効性、安全性の確保に直結するため、製造業者は、日本のGMP省令を十分に理解し、遵守することが求められます。調査の結果を踏まえ、必要な是正措置を講じることが重要です。
文書参照
- 医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ
