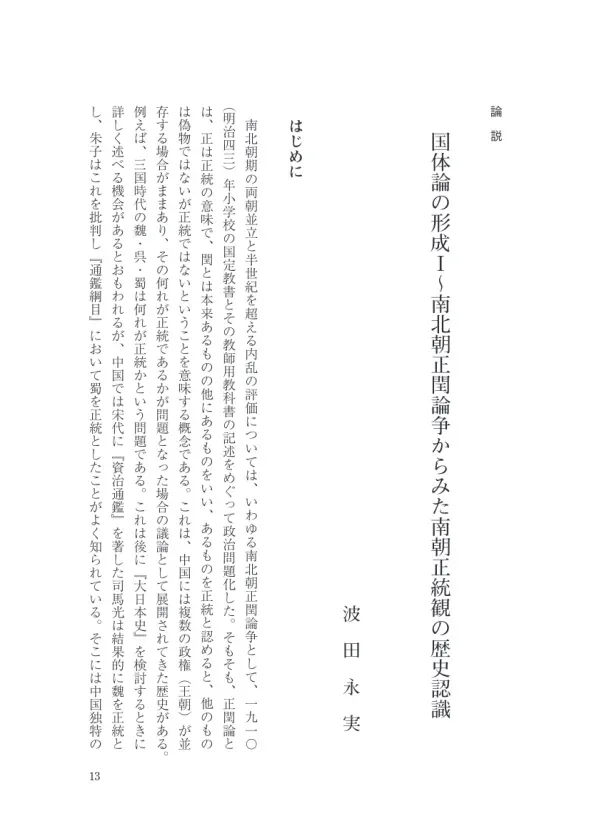
南北朝正閏論争と南朝正統観
文書情報
| 著者 | 波田永実 |
| 専攻 | 歴史学 |
| 文書タイプ | 論文 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 1.79 MB |
概要
I.南北朝以前の皇統問題 継体天皇から後三条天皇まで
本稿は、南北朝正閏論争の背景を理解するために、平安朝以前の皇位継承における問題点を考察します。特に、継体天皇の評価、安閑・宣化・欽明天皇の継承問題(両朝並立説を含む)、壬申の乱における天武天皇と大海人皇子の関係、そして平安時代の嵯峨天皇と弟の淳和天皇、仁明天皇と文徳天皇の兄弟相続による皇統迭立など、皇位継承の混乱と分裂の事例を分析します。これらの事例は、後の南北朝時代の皇統分裂を理解する上で重要な前提となります。後三条天皇の譲位と院政開始は、摂関家の全盛期終焉と新たな皇位継承問題の始まりを示しています。重要な人物として、藤原良房、白河天皇、崇徳上皇、後白河天皇などが挙げられます。
1. 継体天皇とその後の皇統 継承問題の発生
この節では、まず継体天皇の皇位継承における評価の難しさ、そしてその後の安閑天皇、宣化天皇、欽明天皇への皇位継承について論じています。特に、宣化朝と欽明朝が並立していたとする学説(喜田貞吉、林家辰三郎らによる)が紹介され、『古事記』『日本書紀』『上宮聖徳法王帝説』『百済本紀』などの史料の記述矛盾からの解釈が根拠として示されています。しかし、この説を否定する見解も存在すると指摘されています。この時点での皇位継承は、必ずしも明確な一系図として描けず、後の南北朝時代の混乱につながる皇統の不安定要素が既に存在していたことが示唆されています。安閑天皇と宣化天皇が同母兄弟で、欽明天皇が異母弟であったという血縁関係も、継承問題の複雑さを物語っています。この節では、具体的な史料の分析は避けられていますが、後の南北朝時代の皇位争いの前段階として、皇位継承の曖昧さと複雑さがすでに存在したことを示唆する重要な部分となっています。
2. 壬申の乱と皇統 天武天皇と大海人皇子
壬申の乱における皇位継承問題が取り上げられています。大友皇子を天皇と認める『大日本史』の立場からすれば、弘文天皇(近江朝)と大海人皇子(後の天武天皇)の並立という問題が生じます。しかし、本文では大友皇子の即位を認めたとしても、大海人皇子による皇位簒奪という見方も存在すると指摘し、天武系の皇統が孝謙・称徳天皇で途絶え、天智系の皇統が復活した経緯が、正統な皇統の復位として論じられる可能性を示しています。『大日本史』の見解が、この正統性の問題において重要な役割を果たすことを示唆しています。この節では、壬申の乱という大きな事件を通して、古代における皇位継承が必ずしも一筋縄ではいかないことを示しており、血縁関係や政治力だけでなく、歴史の解釈によって正統性が大きく変わる可能性があることを示唆しています。この皇位継承の複雑さは、後の南北朝時代の正閏論争の理解においても重要な背景となっています。
3. 平安時代の皇統迭立 兄弟相続と政治的力学
平安時代の皇位継承における事例として、嵯峨天皇と淳和天皇、仁明天皇と文徳天皇の兄弟相続が取り上げられています。嵯峨天皇が弟の淳和天皇を立て、仁明天皇も同様に兄弟関係が皇位継承に関わったことが記述されています。 嵯峨天皇と平城天皇(高丘親王)の関係、承和の変における皇太子の廃立、そして嵯峨朝と平城上皇の「二所の朝廷」といった分裂状態なども、皇位継承における政治闘争の激しさや複雑さを示す事例として挙げられています。これらの事例を通して、兄弟相続が皇統迭立を招きかねない状況を生み出し、天皇の病気や政治的駆け引きが皇位継承に大きく影響を与えていたことが示されています。藤原良房の台頭も、皇統継承に影響を与えた重要な要素として触れられています。この節は、平安時代の皇位継承における不確定要素を示すことで、南北朝時代の皇位争いの歴史的文脈を理解するための重要な背景を提供しています。
4. 後三条天皇と院政 摂関家と皇統の一元化
後三条天皇の即位と院政開始は、摂関家の全盛期終焉と皇統の一元化への転換期として論じられています。後三条天皇が摂関家出身の母を持たなかったことが、この転換期の重要な要因として示唆されています。白河天皇への譲位とその後の院政、そして冷泉天皇と円融天皇の兄弟相続から迭立への展開も、藤原道長の政治的介入を通して説明されています。後三条天皇の意向とは裏腹に、実子ではなく異母弟の実仁親王、そして輔仁親王が皇位継承候補者として浮上した経緯が、藤原北家摂関流の影響力を示す例として提示されています。この後三条天皇の時代は、皇位継承において兄弟相続が迭立につながる可能性を示すとともに、政治勢力の介入が皇位継承に決定的な影響を与えた時代であったことがわかります。 この節は、摂関家の影響力と皇位継承の複雑な関係を示し、南北朝時代における政治的力学の理解に繋がる重要な部分となっています。
II.南北朝時代の皇統迭立と正閏論争
後嵯峨天皇の死後、持明院統と大覚寺統による皇統迭立が始まり、南北朝時代へと突入します。この皇統迭立は、幕府の介入と、後嵯峨天皇の遺詔(その存在自体に異論あり)をめぐる解釈の相違が原因でした。後醍醐天皇は建武の新政で鎌倉幕府を倒しますが、足利尊氏による反乱で失敗、吉野に逃れて南朝を開きます。光厳天皇を擁立した北朝と、後醍醐天皇の南朝との対立、つまり正閏論争が激化します。重要な人物として、後深草天皇、亀山天皇、後宇多天皇、花園天皇、光厳天皇、後小松天皇などが挙げられ、文保の和談や神器の扱いも論点となります。
1. 後嵯峨天皇の死と皇統迭立 持明院統と大覚寺統
後嵯峨天皇の崩御後、持明院統と大覚寺統の皇統迭立が始まった経緯が説明されています。この迭立は、後嵯峨天皇の遺詔の存在とその解釈、そして鎌倉幕府の政治的介入が大きく関わっていたとされています。 後嵯峨天皇の遺詔は明文化されたものではなく、その内容や時期についても異説があり、『増鏡』や『梅松論』などの史料を基に、その真偽や解釈が議論されています。特に『梅松論』は、後嵯峨天皇の遺命の内容と時期について詳細な記述を含んでいますが、その記述の信憑性についても検討する必要があります。後深草天皇と亀山天皇の兄弟相続、そしてその後の後宇多天皇、後二条天皇、邦良親王、そして後醍醐天皇といった皇位継承の複雑な流れが、持明院統と大覚寺統の対立を背景に説明されています。後宇多天皇の「素意」や「遺詔」も、大覚寺統への皇統継承の意志を示すものとして解釈されていますが、これについても、様々な解釈の可能性が存在する点も指摘されています。 この節では、南北朝時代の皇統分裂の端緒となった後嵯峨天皇の死後の状況と、持明院統と大覚寺統の迭立の始まりについて、様々な史料や解釈を交えながら説明しています。
2. 建武中興の失敗と南北朝対立 後醍醐天皇と足利尊氏
後醍醐天皇による建武の新政と、その後の足利尊氏による反乱、そして南北朝の対立が詳述されています。後醍醐天皇は建武の新政で鎌倉幕府を倒しますが、足利尊氏の反乱によって新政は崩壊し、後醍醐天皇は吉野に逃れて南朝を開きます。尊氏は光厳天皇を擁立し北朝を形成し、これによって南北朝時代が始まります。この南北朝対立は、単なる武力衝突だけでなく、皇統の正統性をめぐる激しい論争(正閏論争)を伴いました。 光厳天皇の践祚は、花園上皇の院宣によって行われたとされ、その正当性についても様々な解釈が提示されています。後醍醐天皇と光厳天皇の在位期間が重なった時期があり、この期間を「両帝並立」と捉える見解も存在します。 教師用教科書における記述が、南朝正統論者から批判された点についても触れられており、教科書が南北両朝を対等に扱っていること、そして後嵯峨天皇の遺詔を曖昧に扱っていることが問題視されたことが分かります。 この節では、建武中興の成功と失敗、そして南北朝対立の始まりについて、後醍醐天皇と足利尊氏という主要な人物を中心に、その経緯と背景が説明されています。
3. 正閏論争の焦点 南朝正統論と北朝正統論
南北朝正閏論争において、南朝正統論者が問題とした点を分析しています。南朝正統論の立場からは、後嵯峨天皇の遺詔、北条氏による光厳天皇の擁立、そして足利尊氏による光明天皇の擁立などが、北朝の正統性を否定する根拠として挙げられています。『南北朝正閏論纂』などの史料を引用しながら、南朝正統論の主張が詳細に解説されています。 南朝正統論が大きな流れになった背景として、「水戸の修史事業」(『大日本史』の編纂)の影響が指摘されており、『大日本史』の南朝正統論が国史界に大きな影響を与えたことが強調されています。国定教科書と教師用教科書における南北朝の記述についても、南朝正統論者の批判が紹介され、教科書の記述が両朝を対等に扱っていること、そして後嵯峨天皇の遺詔の扱いが曖昧であることが問題視されていたことがわかります。 この節は、正閏論争における南朝正統論の主張とその根拠を詳細に解説し、その論争の背景にある歴史認識の違いを浮き彫りにしています。
4. 神器と南北朝合一 正統性の問題と歴史解釈
光明天皇に授けられた神器の真偽をめぐる議論が紹介され、『太平記』や『神皇正統記』『園太暦』といった史料からの解釈が提示されています。神器が偽器であった可能性、そして後醍醐天皇の策略などが議論されています。後小松天皇の即位と南北朝合一についても、南朝正統論者の見解と、実際の経緯との違いが指摘されています。南朝正統論者は、南北朝合一を北朝による南朝の事実上の併呑と捉えていたのに対し、実際には後小松天皇の即位は、安徳天皇の際に失われた神器の回収と同様の経緯で、神器の接収を通して行われたとされています。 この節では、神器という象徴的な存在を通して、南北朝合一の経緯と、南朝正統論者の歴史認識とのずれが示されています。 さらに、南朝正統論の台頭を促した楠木正成の再評価、『大日本史』の編纂事業、そして「忠臣」の顕彰といった要素も、この節に関連する重要な要素として触れられています。これらの要素が、正閏論争の枠を超え、近代日本の国体論形成にまで影響を与えたことが示唆されています。
III.正閏論争と国定教科書 教師用教科書における歴史記述
南北朝正閏論争は、学校教育における歴史記述にも影響を与えました。南朝正統論者は、国定教科書や教師用教科書が、幕府の介入と後醍醐天皇の正当性を曖昧に扱っていると批判しました。特に、後嵯峨天皇の遺詔の解釈、光厳天皇の践祚、そして光明天皇の践祚などを巡って議論が展開されました。『大日本史』の南朝正統論が、この論争に大きな影響を与えたことは注目に値します。教科書における南北朝記述の客観性と正統性が、論争の中心的な争点でした。
1. 南北朝正閏論争の争点 南朝正統論者の主張
この節では、南北朝正閏論争において南朝正統論者たちが何を問題視していたのかを明らかにしています。論争の過程で出版された『南北朝正閏論纂』という論文集・資料集が重要な資料として用いられ、その「緒論」から南朝正統論の立場が示されています。南朝正統論者たちは、大きく分けて三点を問題視していました。一つ目は、後嵯峨天皇の遺詔があったにもかかわらず、鎌倉幕府の介入によって両統迭立が持ち込まれたこと。二つ目は、元弘の乱において北条氏が光厳天皇を践祚させたこと。そして三つ目は、建武の頃に足利尊氏が光明天皇を践祚させたことです。これらの出来事が、南朝正統論者にとって北朝の正当性を否定する重要な根拠となっています。また、南朝正統論が大きな流れとなった契機として、「水戸の修史事業」(『大日本史』の編纂)が挙げられており、同書の南朝正統論が国史界に大きな影響を与えたことが説明されています。明治維新後、南朝の正統性が認められ、南朝方の功臣への贈位や国民教育への影響も触れられています。この節は、南北朝正閏論争の中心的な論点を明確に示し、その背景にある歴史認識の違いを浮き彫りにしています。
2. 国定教科書と教師用教科書への批判 両朝並立論への異議
この節では、国定教科書と教師用教科書における南北朝時代の歴史記述について、南朝正統論者からの批判が紹介されています。南朝正統論者たちは、教科書が南北朝を対等に扱っていること、特に後嵯峨天皇の遺詔の存在やその影響を曖昧に扱っていることを問題視していました。具体的には、教科書が「南北両朝の対立」という表現を用いていないこと、そして教師用教科書においても、後嵯峨天皇の遺詔を十分に反映していないと批判されています。 しかし、本文では、国定教科書と教師用教科書が今日の南北朝史の通説的理解を提示していると反論し、両教科書とも簡潔かつ客観的に記述している点を指摘しています。後嵯峨天皇の遺詔に関する記述について、明文化された遺詔は存在せず、後嵯峨天皇自身の意思表示が曖昧であったこと、そして幕府が後嵯峨天皇の妃である大宮院に伺いを立てて亀山天皇の皇統を継承させた経緯が説明されています。この節では、教育現場における歴史記述と、正閏論争における歴史認識の違いが、具体例を挙げて示されています。特に、教科書記述における客観性と、南朝正統論者の歴史観との間の相違点が論点となっています。
3. 後嵯峨天皇の 遺詔 と光厳天皇 光明天皇の践祚 正統性の根拠
この節では、後嵯峨天皇の「遺詔」、光厳天皇、そして光明天皇の践祚をめぐる議論が詳しく展開されています。後嵯峨天皇の遺詔は明文としては存在せず、その内容や解釈について様々な見解が存在していることが説明されています。南朝正統論者は、後嵯峨天皇が亀山天皇の皇統を継承させる意図を持っていたと主張する一方で、その意思表示が曖昧であったため幕府が介入し、両統迭立が成立したと解釈しています。光厳天皇の践祚については、北条高時が花園上皇の院宣を得て光厳天皇を擁立した経緯が説明され、院宣が政治に大きな影響力を持っていたことが示されています。 光明天皇の践祚についても、足利尊氏が光厳上皇と豊仁親王を奉じ、さらに院宣を得て光明天皇を擁立した経緯が説明され、これも南朝正統論者によって批判されています。 南朝正統論者の主張、そして教師用教科書における説明と比較することで、南北朝正閏論争における歴史解釈の違いが明確に示されています。この節では、主要な出来事の解釈を通して、正閏論争における論点と、それに対する様々な解釈が提示されています。
4. 南朝正統論と歴史記述 建武中興と明治維新
この節は、南朝正統論の主張と、その歴史記述における特徴を分析しています。南朝正統論にとって最も重要な論点の一つに、足利尊氏の反乱と光明天皇の践祚の問題が挙げられています。南朝正統論者たちは、光明天皇の践祚を、尊氏の叛逆によるものと捉え、その正当性を否定しています。一方、教師用教科書では、南北両朝を対等視した記述が見られます。この記述の違いが、正閏論争の根幹をなす歴史認識の違いを示しているとしています。さらに、南北朝合一における後小松天皇の即位についても、南朝正統論者による批判的な解釈が紹介されています。南朝正統論者は、後小松天皇の即位を北朝による南朝の事実上の併呑と捉え、これを「父子の礼」による譲位ではなかったと主張しています。 この節では、南朝正統論者の主張を詳細に分析し、その歴史認識が、建武中興の評価や明治維新への影響にまで及んでいることを示唆しています。特に、南朝「忠臣」の再評価と顕彰が、正閏論争と近代日本の国体論形成に深く関わっている点が強調されています。
IV.水戸学と皇国史観における南北朝史観
近代に入り、水戸学、特に後期水戸学と皇国史観は、南北朝正閏論争に大きな影響を与えました。『大日本史』の編纂事業は、南朝正統論を強く主張し、楠木正成などの南朝「忠臣」を顕彰しました。この思想は、天皇の絶対性を強調する国体論と深く結びついており、明治維新を建武中興の理想実現と位置付ける解釈を生み出しました。尊皇攘夷思想、そして戦前の天皇機関説批判なども、この流れに含まれます。重要な人物として、徳川光圀、藤田東湖、平泉澄などが挙げられます。
1. 水戸学と南北朝正閏論争 南朝正統論の台頭
この節では、近世における南北朝正閏論争と水戸学、特に『大日本史』編纂事業との関わりが論じられています。南朝正統論が近世に台頭した契機として、楠木正成の再評価が挙げられていますが、徳川光圀による『大日本史』の編纂事業が決定的な役割を果たしたとされています。 『大日本史』において南朝正統論が強く主張され、南朝側の忠臣たちが高く評価されたことが、後世の南北朝史観に大きな影響を与えたとされています。光圀自身も林家史学の影響を受けながら独自の史観を形成し、『大日本史』においては南朝正統論を明確に示したとされています。この節では、水戸学における歴史認識が、正閏論争において南朝正統論を支持する立場を取ったこと、そしてそれが後の国民意識にも影響を与えたことを示しています。特に、『大日本史』の編纂事業が、南朝正統論の普及に決定的な役割を果たしたことが強調されています。また、湊川神社の正成顕彰碑の建立なども、その具体的な事例として挙げられています。
2. 後期水戸学と皇国史観 国体論への影響
この節では、後期水戸学と皇国史観が、南北朝史観、ひいては国体論の形成にどのような役割を果たしたのかが論じられています。 前期水戸学の「尊皇敬幕」という立場とは異なり、後期水戸学は「斥覇」(幕府批判)の立場をとり、建武中興の失敗の原因を足利尊氏の謀叛や武士の二心、国民の無関心などに求める見解が紹介されています。高須芳次朗や平泉澄といった戦前の代表的な論者の主張が紹介され、彼らの主張が水戸学と皇国史観とを直接的に結びつけるものとして位置づけられています。 平泉澄は、『建武中興の本義』において、後醍醐天皇の倒幕の企ては量仁親王(光厳天皇)の立太子以前からのものであったと主張し、後醍醐天皇の建武新政を明治維新の原型と捉えています。 また、天皇の絶対性と臣民の滅私奉公を強調する皇国史観が、久米邦武事件や南北朝正閏論争を起点に形成され、昭和初期には国体論の中心的価値観となったことが示されています。この節は、水戸学と皇国史観が、南北朝正閏論争や国体論に与えた影響を、具体的な論者や著作を挙げて分析しています。
3. 忠臣 顕彰と国体論 楠木正成と南朝正統論
この節では、水戸学における「忠臣」の顕彰、特に楠木正成崇拝と国体論との関係について論じています。『大日本史』の南朝正統論が後世に与えた影響として、楠木正成を代表とする「忠臣顕彰」が大きく取り上げられています。 徳川光圀、朱舜水、そして三宅観瀾といった人物が、楠木正成を高く評価していたことが述べられ、藤田東湖、相沢正志斎、青山拙斎といった後期水戸学の論者たちも楠公崇拝を行っていたことが指摘されています。 この「忠臣顕彰」は、単なる人物崇拝ではなく、天皇中心の国家観(国体論)と深く結びついており、南朝の忠臣たちが、日本国民の「あるべき姿」の模範とされたことが示唆されています。明治維新後も、南朝方の功臣が祭神とされた神社の創建が盛んに行われたことなども、この「忠臣顕彰」の流れを示す事例として挙げられています。 この節では、楠木正成への崇拝を通して、南朝正統論と国体論が密接に結びついていたことを示しており、皇国史観形成への歴史的背景を説明しています。
4. 荻生徂徠の贈位問題と皇国史観 国体論の矛盾
この節では、荻生徂徠の贈位問題を取り上げ、皇国史観における国体論の矛盾点を示唆しています。 荻生徂徠が贈位から除外された理由について、その中国崇拝が国体論上問題視された可能性が示唆されていますが、明確な理由は明らかではありません。 この贈位問題における政府の意図や、徂徠とその学派への価値判断が、正閏問題と関連付けて考察されています。 この節は、比較的短い記述ですが、皇国史観における国体論の矛盾や、その歴史的背景を理解する上で重要な示唆を与えています。特に、犬養毅の尽力にもかかわらず、徂徠が贈位されなかった点に、政府の何らかの意図があった可能性が示唆され、それは正閏問題と関連付けられています。
