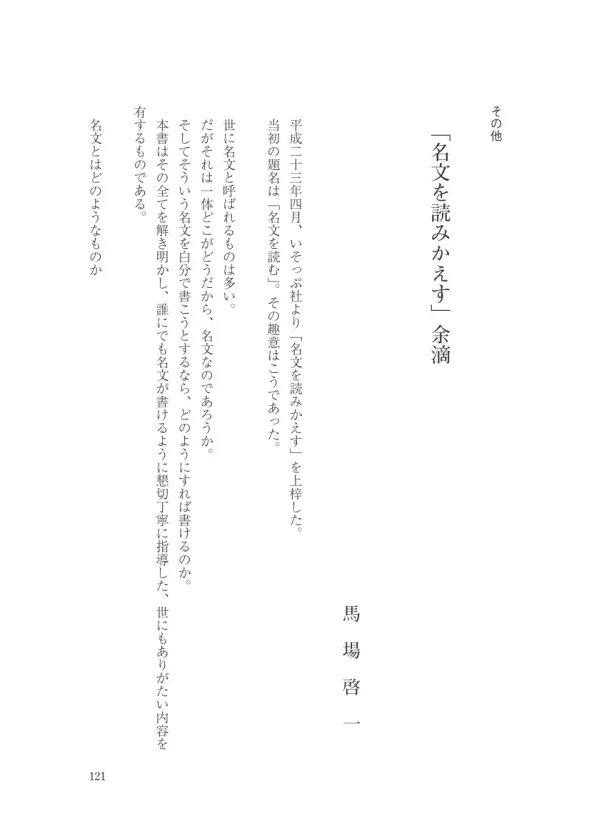
名文の書き方:名文とは何か?
文書情報
| 会社 | いそっぷ社 |
| 文書タイプ | 書籍 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 0.96 MB |
概要
I.名文とは何か その 資格 と 実際
本書『名文を読みかえす』は、名文とは何かを徹底的に探求する。山口瞳、開高健、村上春樹など著名な作家たちの作品を例に、日本語表現の粋、薀蓄、純粋さ、正統性など、名文の様々な側面を分析する。文章術の奥深さと、読みやすい文章を書くためのヒントが満載だ。名文の例文を通して、日本語の表現力と文章構成の巧みさを学ぶことができる。
1. 名文の定義と特徴 様々な作家の視点から
本書では、単に「名文」と呼ばれる文章の定義や特徴を、多角的に分析しています。山口瞳の粋、開高健の薀蓄、村上春樹の純粋さ、夏目漱石の正統性、森鴎外の剛毅、伊丹十三の才気、高橋義孝の抑制、丸谷才一の叡智、土屋耕一の含羞、和田誠の生気といった、様々な作家の文体や特徴を挙げ、それぞれの作家の文章に共通する名文としての要素を検討することで、名文の定義を多角的に探っています。それぞれの作家の個性的な表現方法が、どのように名文としての資格を満たすのか、具体例を挙げながら考察することで、読者に名文への理解を深めてもらうことを目指しています。単なるテクニック論ではなく、名文を生み出す背景にある精神性や作家自身の姿勢にも触れ、より深い理解へと導きます。
2. 名文の例文分析 具体的な表現方法の考察
いくつかの例文を提示し、名文の特徴を分析することで、具体的な表現方法について考察しています。例えば「落語国・紳士録」の例文では、江戸っ子の独特な口語表現が持つ魅力と、それを他の言語に翻訳する際の困難さを分析しています。また、「ふれもせで」の例文では、「だ」「である」という助動詞の力強い表現と、現代語における「です」「ます」体の曖昧さを比較検討することで、文章の力強さと誠実さを伝える表現方法を具体的に示しています。さらに、「ニホン語日記」の例文では、井上ひさしの指摘を引用し、簡潔な文章構成の重要性と、日本語の表記における視覚的な効果を解説しています。これらの例文分析を通して、名文における具体的な表現方法や構成の技巧を学び、読者自身の文章作成能力の向上に繋げることを意図しています。
3. 名文における 書く ことと 話す ことの区別 誤解と真意
本書では、書き言葉と話し言葉を混同することによる問題点を指摘しています。「小説の経験」の例文を通して、日本語文章における記号の乱用や、反語表現の過剰使用といった、話し言葉の影響を受けた表現が、文章の明快さを損なう可能性を解説しています。明快でストレートな表現こそが、真の名文に求められる要素であり、相手に媚びることなく、堂々と自分の意見を述べることの大切さを主張しています。単なる文法論にとどまらず、文章を書く上での姿勢や心構えについても深く掘り下げることで、読者に名文を書くための精神的な支えとなるような内容となっています。 読みやすさだけでなく、文章の本質的な力強さを追求する視点が示されています。
II. だ である 体と現代語の 文章 表現
日本語の文章において「だ」「である」体と「です」「ます」体の使い分けは重要だ。著者は「だ」「である」体がより力強く、誠意が伝わる表現だと主張する。一方、「です」「ます」体は媚びるような印象を与え、読みやすい文章とは言えない場合もある。例文を通して、それぞれの効果的な活用法を解説する。日本語表現の文章の資格を理解するための重要なポイントとなる。
1. だ である 体と です ます 体の比較 表現のニュアンスの違い
この章では、日本語の文章表現において「だ」「である」体と「です」「ます」体の違いについて論じています。著者は、「です」「ます」体には媚びるようなニュアンスが含まれ、相手にへりくだる印象を与えかねない、と指摘しています。一方「だ」「である」体は、より直接的で力強い印象を与え、誠意が伝わりやすいと主張しています。 具体的には、「です」「ます」体は上から目線で命令口調に聞こえたり、猫なで声のように感じられることもあると例示し、一方「だ」「である」体にはそのような上から目線や不自然さがなく、力強く、誠意が伝わる、と解説しています。 この違いは、文章全体の印象を大きく左右するため、適切な使い分けが重要であると結論づけています。 文章の表現方法として、単に文法的な正確さだけでなく、読者に与える印象や、伝えたいニュアンスを的確に表現する重要性を訴えています。
2. 例文による具体的な分析 ふれもせで の事例
「ふれもせで」という例文を提示し、上記の説明を裏付ける分析を行っています。この例文を通して、「だ」「である」体が、単に「上手い」「読ませる」といった技巧的な問題ではなく、「きちんと額面通り伝わっているか」という、文章の本質的な課題に直結することを示しています。 「です」「ます」体を使うことで、文章が巧妙で洗練されたものになるというわけではないことを、具体例を用いて説明することで、読者にとって分かりやすく、実践的な助言を提供しています。 「だ」「である」体を使用することで、文章に真っ当で力強い印象を与えられる一方、「です」「ます」体では詐欺師のような印象を与えてしまう可能性もある、という極端な表現を用いることで、読者の注意を惹きつけ、この表現方法の重要性を強調しています。 単なる文法解説ではなく、文章表現における「誠意」や「力強さ」といった、より深いレベルでの表現方法の検討が行われている点が特徴です。
III.句読点と 日本語 の 文章 構成
井上ひさし氏の指摘を踏まえ、日本語の文章は簡潔に書くべきだと本書は提唱する。日本語特有の漢字、平仮名、カタカナの混在が、視覚的に句読点の役割を果たすことを示し、読みやすい文章を作るための工夫を提案する。例文を分析することで、効果的な文章の分割方法を学ぶことができる。文章術において、簡潔で分かりやすい文章を書くことは重要だ。
1. 日本語文章における句読点の役割 視覚的な効果と簡潔性
この節では、日本語の文章における句読点、特に漢字、ひらがな、カタカナの混在が視覚的に文章を区切り、読みやすさを向上させる役割について論じています。著者は、日本語では句読点に頼ることなく、これらの表記方法の組み合わせによって、文の区切りや意味のまとまりを自然に表現できている点を指摘しています。 比較的長い文章の例を挙げ、その文章をより簡潔で読みやすいものにするために、文章を分割する方法を提案しています。これは、日本語の表記方法の特性を理解し、それを効果的に利用することで、より分かりやすい文章を作成できることを示唆しています。 単に句読点を置くだけでなく、日本語の特性を活かした視覚的な工夫によって、読みやすさと理解度を向上させることができるという点が強調されています。 井上ひさし氏の意見も引用し、文章は短く、簡潔に書くべきであるという主張を補強しています。
2. 例文分析 ニホン語日記 における文章構成の検討
「ニホン語日記」の例文を用いて、具体的な文章構成の検討を行っています。比較的長い文章を例に、句読点に頼らずに、漢字、ひらがな、カタカナの使い分けによって、視覚的に文章を区切り、読みやすさを向上させる方法が示されています。 著者は、元の文章をより簡潔で分かりやすい表現に書き換えることで、日本語の文章構成における視覚的な効果を実証しています。 この分析を通して、日本語の文章を書く際には、句読点だけでなく、漢字、ひらがな、カタカナの使い分けといった視覚的な要素も考慮することで、より効果的な文章構成を実現できることが示唆されています。 文章作成における到達点はない、という結論も示されており、常に改善と探求を続ける姿勢の重要性が示されています。
IV.小説における話し言葉と書き言葉の混同と 文章 の 正統性
著者は、小説などで話し言葉と書き言葉を混同する際の注意点について論じる。英語の影響と思われる記号の乱用や「反語」の使いすぎは、文章の正統性を損なうと指摘する。読みやすい文章を書くには、明快でストレートな表現を心がけるべきであり、相手に媚びる必要はないと強調する。名文は、姑息な手段ではなく、堂々とした品格ある書き方で生まれると結論づける。
1. 話し言葉と書き言葉の混同 日本語文章における記号の乱用と問題点
この節では、小説などの文章において、話し言葉と書き言葉が混同されることによる問題点を指摘しています。特に、日本語文章に本来不要な記号が過剰に使用されることや、英語の文章の影響を受けた表現方法について、好ましくない例として挙げられています。これらの表現は、文章の明快さを損ない、読み手の理解を妨げる可能性があると指摘されています。日本語の文章は、基本的に記号を必要としないシンプルな構造であるため、不必要な記号の多用は、かえって文章の理解を困難にする可能性があると論じています。 また、話し言葉の影響を受けた表現として「反語」が挙げられ、それが相手におもねるような卑屈な印象を与えてしまう可能性があることを解説しています。 文章の本来的な力強さや誠実さを損なう可能性があるため、注意が必要であると結論づけています。
2. 明快でストレートな表現の重要性 文章の 軽さ への誤解
明快でストレートな文章表現の重要性が強調されています。文章が明快でストレートであることを「軽い」と誤解する傾向があることについて、著者は強い懸念を示しています。 むしろ、明快でストレートな文章は、力強く、説得力のある文章であると主張しています。 相手に同意を得ながら書く必要はなく、堂々と自分の意見を述べるべきであり、反論は相手がするものだと論じています。 文章の「味わい」や「滋味」は、姑息な手段ではなく、堂々とした姿勢で、品良く書くことで得られるものだと結論づけています。 読みやすさだけでなく、文章の力強さや品格といった要素が、真の名文には不可欠であると主張しています。
V.予言と現実 日本語 による 文章 表現の力
二〇〇〇年に何かが変わるという予言が、二〇〇〇年に菅直人氏が首相になったという現実と結びつけられる。著者は、この予言の的中を文章の力、予知能力と関連付けて考察する。この章では、日本語の表現力と、文章が持つ潜在的な力について示唆を与えている。文章術の観点からも興味深い内容となっている。
1. 予言の記述と現実の事象 2010年の出来事との関連性
この節では、1996年時点で2010年に何かが変化すると予言していた記述と、2010年に菅直人が唐突に総理大臣になったという現実の出来事を関連付けて考察しています。 この予言が現実と一致した事実に注目し、文章表現の力、ひいては予知能力のようなものについて言及しています。 菅直人が総理大臣になった経緯、鳩山由紀夫前総理の辞任といった政治的な状況も説明に加え、予言の的中をより強調しています。 単なる偶然の一致ではなく、文章に込められた何らかの力や、予見的な視点があったのではないかという示唆を含んでいます。 この部分では、文章表現が持つ潜在的な力や影響力について、興味深い事例を通して読者に問いかけています。
2. 文章表現の力と予知能力 考察と疑問提起
予言の的中を踏まえ、文章表現の持つ潜在的な力や、著者の予見能力について考察しています。 1996年時点での予言が、2010年の現実と一致したという事実は、単なる偶然の一致なのか、それとも著者の洞察力や、文章表現の力によるものなのか、という疑問を提起しています。 この部分では、文章表現が現実世界に及ぼす影響力、あるいは予言的な側面といった、通常は議論されないようなテーマについて触れています。 菅直人の就任という出来事を、単なる政治的な出来事としてではなく、文章表現の力という観点から考察することで、読者に新たな視点を提供しています。 著者は、この予言の背景や、その的中をどのように解釈するべきかについて、読者に考えさせることを意図していると考えられます。
VI.戦後の国語改革と 日本語 の未来
志賀直哉氏の戦後直後の発言を引用し、国語改革の困難さと日本語の未来への懸念を提起する。フランス語を国語に採用するという大胆な提案は、当時としては奇抜な考えだったが、日本語の衰退という問題提起は今なお重要である。この章では、日本語の維持・発展という観点からの重要な議論がなされている。
1. 志賀直哉の提案と戦後日本の状況 国語改革の困難さ
この節では、戦後間もない頃に志賀直哉氏が提唱した、国語改革の困難さと、ひいては日本語の未来への懸念について論じています。 志賀直哉氏は、国語改革は不可能であるとして、フランス語を国語に採用するという、当時としては極めて異例な提案を行ったと記述されています。これは、戦後の混乱期における、言語に対する危機感の表れであると解釈できます。 著者は、志賀直哉氏の提案を、単なる奇抜なアイデアとして片付けるのではなく、改めて考え直す必要があると主張しています。 日本語の現状に対する危機感を共有し、今後の日本語のあり方について、読者に考えさせることを意図しています。 この部分では、歴史的な文脈と、現代社会における日本語の問題点を結びつけることで、読者に強い印象を与えています。
2. 日本語の衰退と未来への懸念 志賀直哉氏の予見性
志賀直哉氏の、国語改革の不可能という主張と、日本語の衰退という予見について考察しています。 フランス語への置き換えは現実的ではないものの、日本語が今後ますます無力になる可能性という彼の指摘は、現在においても無視できない現実の問題であると強調しています。 著者は、志賀直哉氏の主張が、単なる時代の空気を反映した意見ではなく、未来を見据えた予見的な発言であった可能性を示唆しています。 この部分では、過去の偉人の言葉を通して、現代社会における日本語の問題点を浮き彫りにし、読者に警鐘を鳴らしています。 日本語の衰退という問題に対して、読者に意識を高めさせ、真剣に考える契機となるような記述となっています。
VII.作家個性の反映と 文章 の お約束
安岡章太郎の作品を例に、作家個々の表現方法と読者への影響について考察する。特定の表現が許される作家と、そうでない読者との違いなど、文章術における「お約束」について論じられている。名文と個性の関連性について考える上で重要なポイントである。
1. 作家と読者 表現の許容範囲の違い
この節では、作家と読者における文章表現の許容範囲の違いについて論じています。安岡章太郎のような著名な作家であれば、ある種の過激な表現や、通常では許されない表現を用いることが許容される一方で、一般の読者にはそうした表現は許されない、という「お約束」のようなものがあると指摘しています。 これは、作家と読者の間には、経験や力量、そして社会的立場といった違いがあり、それによって表現の許容範囲も異なってくることを意味しています。 安岡章太郎の例を通して、作家の個性が文章表現にどのように反映されるか、そしてその表現が読者に与える影響について考察しています。 この部分は、文章表現における「個性の許容」と「規範」の微妙なバランスについて示唆を与えています。
2. 安岡章太郎の文章における ヒドイ 表現と読者への影響
安岡章太郎の作品における「ヒドイ」表現を例に、作家の個性が文章表現にどのように影響するか、そしてその表現が読者に与える影響について考察しています。 安岡章太郎であれば許される表現も、一般の読者には許されないという、一種の暗黙の了解のような「お約束」が存在することを指摘しています。 これは、作家の力量や経験、そして読者の期待値といった、様々な要因が絡み合っていることを示しています。 作家の表現方法と、それが読者に与える影響、そして文章表現における規範といった、複雑な問題を提起しています。 この部分では、文章表現における自由度と責任感という相反する要素について、読者に考えさせることを意図しています。
