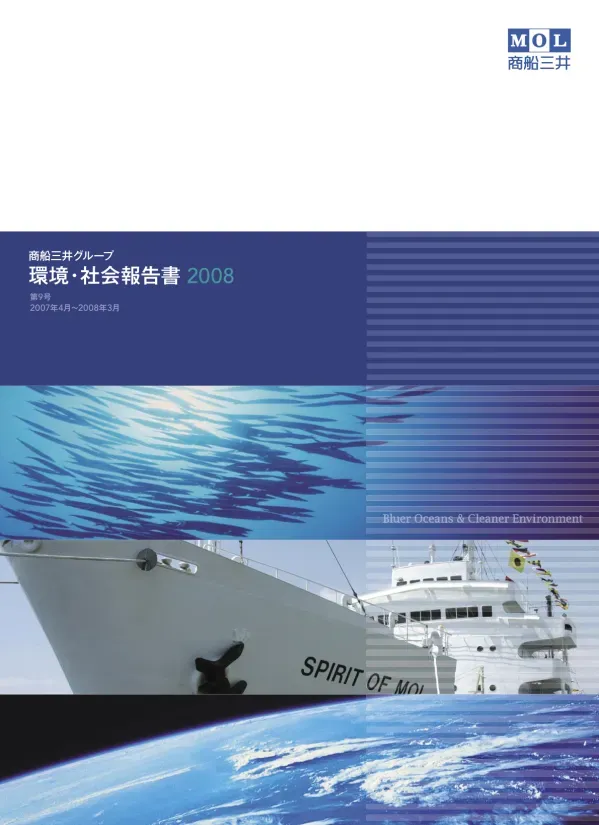
商船三井グループ環境報告書:安全運航と環境保全
文書情報
| 著者 | 商船三井グループ |
| 会社 | 商船三井株式会社 |
| 文書タイプ | 企業報告書 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 4.63 MB |
概要
I.世界最大級の鉄鉱石専用船 ブラジル丸 による環境負荷削減
商船三井は、世界最大級の鉄鉱石専用船である「ブラジル丸」の建造を通じて、CO2排出削減と環境負荷低減に大きく貢献しています。高い推進性能と32万トンの超大型化により、単位輸送当たりの環境負荷を従来型より約20%削減。省エネプロペラ装置の採用など、環境保全に配慮した設計が評価されています。これは、同社の企業理念である「安全運航と海洋・地球環境保全」を具現化した取り組みです。
1. ブラジル丸 の環境性能と設計
大阪商船(株)の伝統を受け継ぐ世界最大級の鉄鉱石専用船「ブラジル丸」は、その高い推進性能と32万トンの超大型化により、単位輸送当たりの環境負荷を大幅に削減することに成功しました。これは、燃料の効率的な使用による温室効果ガス排出量の抑制に直結するものであり、商船三井の企業理念である「安全運航と海洋・地球環境保全」を体現する優れた事例と言えます。 省エネプロペラ装置の採用など、環境保全に十分配慮した設計は関係者から高く評価されており、 単位輸送あたりの環境負荷低減という点で、業界における模範的な取り組みとして注目されています。 この船の建造は、顧客ニーズを的確に捉えた結果であり、顧客が使用する港湾の利点を生かした効率輸送を実現する点が大きな特徴です。 このように、環境配慮と効率性の両立を目指した「ブラジル丸」は、持続可能な海運を目指していく上で重要な一歩となっています。
2. 環境負荷削減効果と受賞歴
ブラジルと日本間の鉄鉱石輸送において、「ブラジル丸」は従来型に比べ、1トンあたりのCO2排出量を約20%削減することに成功しました。これは、優れた推進性能を持つ超大型船型と、高い推進効率のプロペラなどの省エネ設計による成果です。 このCO2排出量の削減効果は、環境保全に配慮した造船技術の革新性を示すものであり、環境負荷低減に対する商船三井の強い意志と技術力を証明しています。 その技術革新性と環境への配慮は高く評価され、「ブラジル丸」は(社)日本船舶海洋工学会が選考する「シップ・オブ・ザ・イヤー2007」を受賞しました。この受賞は、同社の環境保護への取り組みが、業界全体からも認められたことを意味しています。 環境負荷削減と輸送効率の向上を両立させた「ブラジル丸」は、未来の海運業界における環境配慮型船舶のモデルケースとして、その意義をさらに深めていくでしょう。
3. 顧客ニーズへの対応と高い顧客満足度
商船三井は、顧客満足度の高いサービス提供を企業責任として位置付けており、「ブラジル丸」の建造もその一環として捉えることができます。 同社は、世界中のお客様に対し、国や地域ごとに異なる文化・習慣を理解した上で、顧客ニーズに対応したサービスを提供することに力を入れています。 「ブラジル丸」の建造に至った背景には、顧客が使用する港湾の利点を生かした効率輸送というニーズを的確に捉えたことがあり、顧客の期待を上回るサービスを提供することにより、高い顧客満足度を実現しています。 この顧客第一主義の姿勢は、商船三井の事業を支える重要な柱であり、今後とも顧客ニーズの多様化に対応しながら、より高い顧客満足度を目指していくことが期待されます。
II.地球温暖化防止に向けた取り組み
商船三井グループは、国土交通省が推進するモーダルシフト政策にも積極的に対応。海上輸送への切り替えによるCO2排出抑制、エネルギー消費効率向上、道路混雑解消に貢献しています。 具体的には、わが国最大規模のフェリー・内航サービスを提供し、グリーン物流の実現を目指しています。また、京都議定書に基づいた温室効果ガス排出削減目標達成に向け、継続的な取り組みを行っています。
1. 京都議定書と地球温暖化防止への取り組み
2008年4月、京都議定書の第一約束期間が開始され、先進国は温室効果ガス(GHG)排出削減目標に向けて取り組みを進めています。商船三井グループも外航海運会社として、地球温暖化防止に積極的に貢献しています。2012年以降のポスト京都議定書の枠組みについても、発展途上国を含む国際的な議論が展開されており、その動向を注視しながら、持続可能な社会の実現に貢献する取り組みを継続していく必要があります。 具体的な取り組みとしては、国土交通省が掲げる『環境負荷の少ない交通体系の構築』に沿って、モーダルシフトの促進が挙げられます。 自動車輸送から海上輸送への転換を進めることで、CO2排出抑制、エネルギー消費効率の向上、道路混雑の解消を目指しています。 商船三井グループは、国内最大規模のフェリー・内航サービスを提供することで、モーダルシフトに積極的に対応し、グリーン物流(環境負荷の少ない物流)の一翼を担っています。
2. モーダルシフトとグリーン物流への貢献
国土交通省および関係省庁は、鉄道や船舶など環境負荷の小さい輸送機関の利用を促進するモーダルシフトを重要な政策として推進しています。 商船三井グループは、このモーダルシフト政策に積極的に取り組んでおり、陸送から海運への貨物輸送の転換を促進することで、CO2排出量の削減に貢献しています。 具体的には、国内最大規模のフェリー・内航サービス網を活用し、効率的で環境に優しい物流システムの構築を目指しています。 多くの関係者が関わる物流において、全員がパートナー意識を持って取り組むグリーン物流の理念を共有し、環境負荷の少ない輸送システムの構築に貢献していく姿勢を示しています。 この取り組みは、単なる輸送事業にとどまらず、社会全体への貢献という広い視点から行われています。
3. 輸送効率化と環境技術の革新
商船三井グループは、ブラジル・日本間の鉄鉱石輸送において、従来型と比べてCO2排出量を約20%削減できる三代目「ブラジル丸」を投入しました。 これは、推進性能に優れた超大型船型と、高い推進効率のプロペラなどの省エネ設計による成果です。 この成功は、輸送モードの効率化と環境保全に配慮した造船技術の革新性を示しており、環境負荷削減に大きく貢献しています。 「ブラジル丸」は、これらの取り組みが評価され、(社)日本船舶海洋工学会が選考する「シップ・オブ・ザ・イヤー2007」を受賞しました。 この受賞は、商船三井グループの環境への取り組みが、業界全体からも高く評価されていることを示しています。 今後も、環境技術の開発と導入、輸送効率の向上に継続的に取り組むことで、更なるCO2排出量削減を目指していく姿勢を示しています。
III.安全運航体制の強化と安全基準の向上
商船三井は、安全運航を最優先課題としています。2007年2月には本社ビルに「安全運航支援センター(SOSC)」を開設し、365日24時間体制で安全管理を行っています。独自の安全基準「MOL Safety Standard」を大幅に見直し、フェールセーフの観点から安全設備を拡充。さらに、「便乗支援制度」により、航海中の安全管理を強化しています。2007年度からの3ヵ年中期経営計画「MOL ADVANCE」では、安全運航体制強化が最優先課題とされ、大きな成果を上げています。
1. 安全運航支援センター SOSC の設立と24時間体制
地球温暖化による異常気象やテロの脅威など、船舶の安全運航を阻害する要因が増加していることを受け、商船三井は2007年2月1日、本社ビル内に安全運航支援センター(SOSC)を設立しました。 このセンターでは、船長職経験者を含む職員2名が365日24時間体制で常駐し、運航船舶の安全管理を徹底しています。 これは、迅速かつ的確な対応を可能にする体制強化の一環であり、安全運航確保に対する同社の強い意志を示しています。 SOSCの設置は、単なる事故対応だけでなく、予防的な安全管理体制の構築にも寄与し、潜在的なリスクの早期発見と対処を可能にします。 これにより、重大な海難事故の発生を未然に防ぎ、安全運航の維持・向上に貢献しています。
2. MOL Safety Standardの見直しとフェールセーフの導入
商船三井は、国際ルールに準拠した安全仕様を遵守するだけでなく、独自の安全基準「MOL Safety Standard」を設定し、安全対策に取り組んできました。 しかし、人為ミスや機器故障の可能性を常に考慮し、より高い安全性を確保するため、この安全基準を大幅に見直しました。 見直しにおいては、ある部分でトラブルが発生しても他の部分でカバーできる、いわばフェールセーフ(二重安全)の考え方を導入しました。 これは、万が一の事態にも対応できる冗長性を確保することで、重大な事故への発展を防止するための重要な取り組みです。 この安全基準の見直しは、安全対策における抜本的な改革であり、同社の安全に対する強い責任感と、安全文化の醸成への取り組みを明確に示しています。
3. 便乗支援制度による安全運航の徹底
商船三井は、2006年9月から、安全基準に習熟した海技員が本船の港間の航海に便乗し、安全運航の観点から船舶設備、運用、乗組員の作業内容などを細かくチェックする「便乗支援制度」を本格的に導入しました。 この制度は、従来の停泊中の検船に加え、航海中の乗組員の作業内容などもチェックできるため、事故の潜在的要因をより早期に発見し、是正することを可能にします。 事故の芽を早期に発見し、指導・教育により迅速に是正することで、安全運航を維持・向上させるための効果的な仕組みです。 これは、単なる点検ではなく、乗組員への指導・教育を組み合わせることで、安全意識の向上と安全文化の醸成にも貢献する制度となっています。 全ての運航船舶を対象とすることで、より徹底した安全管理体制を構築しています。
4. 中期経営計画 MOL ADVANCE における安全運航体制強化
2007年度から開始された3ヵ年中期経営計画「MOL ADVANCE」では、「質的成長」をメインテーマとして、安全運航体制の強化が最優先課題と位置付けられました。 商船三井グループ全体で安全運航体制強化に取り組んだ結果、当期はほぼ満足できる結果となりました。 これは、安全運航確保に必要となる対策に一切妥協することなく取り組んだ成果です。 今後も安全運航確保に必要となる対策を継続的に実施し、安全に対する姿勢を維持していくことを明確に示しています。 安全運航体制の強化は、企業の持続的な成長と社会への信頼の維持に不可欠であるという強い認識が、この計画に反映されています。
IV.環境配慮型船舶の開発と導入
商船三井グループは、環境に優しい船舶の開発・導入にも力を入れています。「ブラジル丸」以外にも、風圧・水圧抵抗軽減船型など環境技術を備えた船舶を継続的に投入。その結果、2005年度と比較して、単位輸送当たりのCO2及びNOx排出量を7%、SOx排出量を14%削減しています。 さらに、間伐材を活用したディーゼルエンジン排気ガス浄化システムを開発し、「Euphony Ace」などに搭載しています。
1. エネルギー効率の高い大型船舶の導入と環境負荷削減効果
商船三井は、環境負荷削減のため、エネルギー効率の高い大型船舶の導入に力を入れています。 特に、「ブラジル丸」は、その代表的な例として挙げられます。32万トンの超大型化により、単位輸送当たりの燃料消費量を削減し、CO2排出量の低減に大きく貢献しています。 さらに、省エネプロペラ装置の採用など、環境保全に配慮した設計がなされており、関係者から高い評価を得ています。 大型化による輸送効率の向上は、環境負荷低減に直結する重要な要素であり、商船三井は、この点を重視した船舶の開発・導入を進めています。 これらの取り組みは、単なるコスト削減だけでなく、地球環境保全への積極的な貢献という観点からも重要な意味を持っています。
2. 環境技術の開発と搭載例 Euphony Ace
商船三井グループは、船舶の環境性能向上のため、積極的に環境技術の開発・導入を進めています。 その一例として、エム・オー・エル・シップマネージメント(株)が(株)ジュオンと共同開発した、間伐材からの搾取液を利用した発電機排気ガス浄化システムがあります。 このシステムは、ディーゼルエンジン排気管内部に浄化システムを設置し、樹木油を触媒として煤塵(PM)の排出を大幅に削減するものです。 2005年11月に竣工した自動車専用船「Euphony Ace」など、既に複数の船舶に搭載されており、実用化段階に入っています。 この技術は、環境負荷を低減するための革新的な取り組みであり、商船三井グループの環境保全への強いコミットメントを示しています。 今後も、環境に配慮した新しい技術の開発と導入を継続することで、より持続可能な海運を目指していきます。
3. 単位輸送当たりの排出量削減と環境配慮への取り組み
商船三井は、海上荷動きが旺盛な状況下においても、環境保全への取り組みを継続しています。 その結果、2005年度(目標基準年)と比較して、単位輸送当たりのCO2とNOx排出量を7%、SOx排出量を14%削減することに成功しました。 これは、「ブラジル丸」のようなエネルギー効率の良い大型船の継続的な投入と、風圧・水圧抵抗軽減船型などの環境技術を備えた船舶の活用、そして効率的な運航管理の成果です。 これらの数値は、環境負荷低減に向けた同社の具体的な取り組みが、一定の成果を上げていることを示しています。 今後も、環境技術の向上と効率的な運航管理を推進することで、単位輸送当たりの排出量をさらに削減し、環境保全に貢献していくことを目指しています。
V.CSR活動と持続可能な成長
商船三井グループは、CSR活動にも積極的に取り組んでいます。2005年3月には、わが国海運業として初めて国連グローバル・コンパクトに参加。人権、労働、環境、腐敗防止の10原則を支持・実践し、持続可能な成長を目指しています。具体的な活動として、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)への支援、環境関連商品の販売、オフィスにおける環境負荷削減、ISO14001認証取得などがあります。
1. 国連グローバル コンパクトへの参加と持続可能な成長への貢献
商船三井グループは、2005年3月、わが国海運業界で初めて国連グローバル・コンパクトに参加しました。これは、人権、労働、環境、腐敗防止に関する10原則を支持・実践し、持続可能な成長を追求する国際的な枠組みへの参加表明です。 グローバル・コンパクトは、現代社会が直面する様々な問題解決に向けて、企業市民としての向上を促すものです。 商船三井グループは、この10原則に基づき、事業活動における環境負荷の削減、人権尊重、労働条件の改善、透明性のあるガバナンスの確立などに積極的に取り組んでいます。 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)への緊急物資の資金援助と無償輸送の継続実施など、具体的な社会貢献活動も積極的に行っています。 グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワーク(GCJN)との連携も図り、更なるCSR活動の充実を目指しています。
2. 企業理念の具現化と社会からの信頼の獲得
商船三井グループは、企業理念として総合輸送グループとして社会に貢献することを宣言しています。この理念を実現するための基盤として、社会規範と企業倫理の遵守、つまりコンプライアンスの徹底と、透明性のあるコーポレートガバナンスの構築に努めています。 安全運航は、企業活動の基盤であり、環境保全の基本であると認識し、一切の妥協なく取り組んでいます。 これらの活動を通じて、社会からの信頼を獲得し、グループとしての企業価値向上を目指しています。 環境保全、安全運航、コンプライアンス、そして社会貢献活動といった多様な取り組みを通じて、ステークホルダーからの信頼を構築し、持続的な発展を図ろうとしています。 社会貢献活動は、企業の社会的責任を果たす上で不可欠であり、商船三井グループは、その責任を自覚し、積極的に取り組んでいます。
3. 環境会計による情報開示とステークホルダーとのコミュニケーション
商船三井グループは、事業活動における環境保全のための投資・費用と、それによって得られる環境保全効果を定量的に把握し、効率的な環境保全への取り組みを進めています。 この取り組みの一環として、環境会計を報告し、ステークホルダーに対して環境情報を積極的に開示しています。 透明性のある情報開示は、ステークホルダーとの良好な関係を構築し、持続可能な成長を推進するために不可欠です。 環境会計による情報開示は、同社の環境への取り組みを客観的に示し、ステークホルダーからの理解と信頼を深めることを目的としています。 これにより、企業の社会的責任を果たすだけでなく、将来に向けた持続可能な発展のための基盤を築き上げています。
VI.コーポレートガバナンスと情報開示
商船三井は、透明性のある経営とコーポレートガバナンスの強化に努めています。社外取締役の参画を得た取締役会による監督体制を構築し、株主への情報開示を徹底。「適時」「適確」「公平」の原則に基づき、四半期ごとの決算説明会やホームページでの情報公開など、株主・投資家とのコミュニケーションを重視しています。また、**配当性向20%**を目安に、株主への利益還元にも取り組んでいます。
1. コーポレートガバナンスの基本的な考え方と経営改革
商船三井は、社外取締役の参画を得た取締役会による監督と、社長による業務執行という、最適なガバナンス形態を確立するために経営改革を進めてきました。 コーポレートガバナンスへの取り組みは、株主の視点に立ち、企業経営の透明性を高め、経営資源の最適配分を通じてステークホルダーの利益を最大化するための体制作りだと認識しています。 企業理念として「社会規範と企業理念に則った、透明性の高い経営を行い、知的創造と効率性を徹底的に追求し企業価値を高めることを目指します」と謳っており、その実現に向けて継続的に努力しています。 2000年には社外取締役の招聘を含む取締役会改革と執行役員制度を導入し、経営のスピードアップを図っています。 取締役会は、社内取締役8名と社外取締役3名で構成されており(2008年7月現在)、社外取締役は株主の立場から経営のチェックを行い、取締役会の活性化に貢献しています。
2. 取締役会と社外取締役の役割
商船三井の取締役会は、社内取締役8名と社外取締役3名(2008年7月現在)で構成され、社外取締役は経営判断の妥当性と業務執行状況について、株主の立場からチェックを行う重要な役割を担っています。 彼らは経営全般にわたって有益な意見を表明することで、取締役会の活性化に大きく貢献しています。 経営企画部は、取締役会付議案件を社外取締役に対して事前に説明するなど、社外取締役の監督機能が有効に働く体制を整えています。 重要な業務執行については、都度報告を行うことで、透明性を高め、適切なガバナンスを確保しています。 この体制は、企業経営の透明性を高め、ステークホルダーの利益を最大化するための重要な要素となっています。
3. 情報開示と株主 投資家とのコミュニケーション
商船三井は、株主・投資家からの理解を得るため、「適時」「適確」「公平」の原則に則った情報開示を重視し、説明責任を果たすことに努めています。 経営トップ自らがIR(Investor Relations)に率先して当たることで、透明性の高い経営を目指しています。 四半期ごとの決算説明会やスモールミーティングを通して、機関投資家とのコミュニケーションを積極的に図っています。 また、東京証券取引所のTD-Netで和文の四半期決算短信を開示すると同時に、英訳版や和・英両方の決算説明資料をホームページで公開し、国際的な公平開示にも配慮しています。 さらに、個人投資家向け説明会への参加や、ホームページ・携帯電話サービスの充実など、個人投資家への情報提供機会の向上にも努めています。 配当を通じた株主への利益還元も重視しており、連結配当性向20%を目安に、業績に連動した配当を行っています。
VII.人材育成と組織強化
商船三井は、従業員を最も重要な経営資源と捉え、人材育成に力を入れています。陸上総合職はジョブローテーション、階層別集合研修、海外研修など多様な研修制度を実施。国際人育成のための英語力強化プログラムや海外実務研修も充実させています。また、フェアで透明性のある評価制度を構築し、従業員のモチベーション向上に努めています。
1. 人材育成プログラム ジョブローテーションと多様な研修制度
商船三井は、従業員を最も重要な経営資源と捉え、人材育成に力を入れています。陸上総合職については、入社10年目までを育成期間とし、3ヶ所程度の職場・業務を経験するジョブローテーションを実施しています。 OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)に加え、階層別集合研修、海外研修、語学研修、そして海運会社ならではの乗船研修、さらにコーチング研修といった外部研修など、多様な研修制度を提供しています。 自己啓発のための通信教育制度も用意されており、従業員のスキルアップを多角的に支援しています。 これらの研修制度は、従業員の能力開発とモチベーション向上に大きく貢献し、企業全体の競争力強化に繋がっています。 グローバルな視点を持つ人材育成にも注力しており、早期からの海外実務研修や短期留学の機会も提供しています。
2. 人事制度と評価制度 フェアで透明性の高い評価システム
商船三井は、従業員から高いモチベーションとチャレンジ精神を引き出すため、フェアで透明性のある評価制度の確立に力を入れています。 2008年度からは、アシスタントマネージャー級/シニアアシスタント級に、より裁量的な働き方を促す賃金制度の改定を実施しました。 ビジネス・アシスタント級(一般職)にも前年導入された新しい給与制度は、職責と成果を適切に反映する仕組みとなっています。 年1回の人事考課に向けて、期初に上司と部下で年度目標を確認し、年4回の面接を通してきめ細かく、納得できる評価付けを行うことで、従業員の成長を促しています。 管理職に対しては、評価者研修やコーチング研修を実施し、評価能力やコミュニケーションスキルの向上を図ることで、より公正で効果的な人事評価システムの構築を目指しています。
3. 国際人育成 英語力強化とグローバルな視点の涵養
外航海運事業において不可欠な語学力と国際適応力の向上のため、入社半年目から英語力強化プログラムを実施し、外国人とのコミュニケーション能力向上を図っています。 英語以外の語学学習を希望する従業員には、通信教育の受講費用補助などの支援を行っています。 グローバルな視点を早期に養うことを目的として、北米、欧州、アジアなどでの実務研修、短期留学、語学研修など、様々な機会を提供しています。 これらのプログラムは、国際的な舞台で活躍できる人材育成を目指しており、企業のグローバル化戦略を支える重要な取り組みです。 多様な文化に触れる機会を提供することで、国際的な感覚とコミュニケーション能力を備えた人材を育成し、国際競争力の強化に貢献しています。
