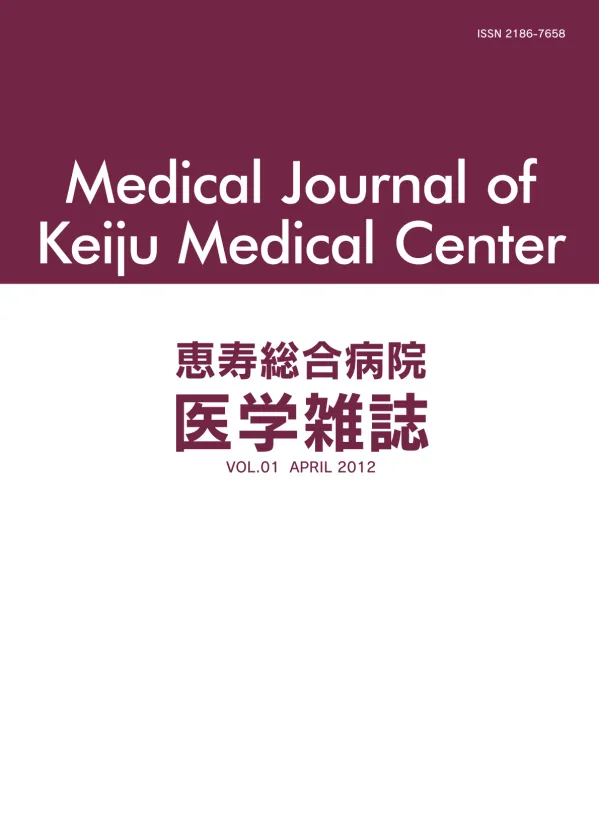
回復期リハビリテーションの現状と課題
文書情報
| 著者 | 川北慎一郎 |
| instructor/editor | 山本達 (病院長) |
| school/university | 恵寿総合病院 |
| subject/major | 医学 |
| 文書タイプ | 医学雑誌 |
| 言語 | Japanese |
| フォーマット | |
| サイズ | 30.29 MB |
概要
I.恵寿総合病院医学雑誌 創刊の目的と期待
恵寿総合病院医学雑誌は、職員の要望を受け、院内の【リハビリテーション医療】を含む臨床研究成果や学習成果を全国に発信する場として創刊されました。【医療の質向上】と患者さんの安心・安全への還元を目指し、職員のモチベーション向上と病院全体の活性化に貢献することが期待されています。論文スコアの高い英字誌への投稿実績もある当法人は、日常診療における経験や技術の中に眠る【研究成果】を更に磨くべく、本誌の創刊に踏み切りました。
1. 職員の要望と医学雑誌創刊
多くの職員からの要望を背景に、恵寿総合病院医学雑誌が創刊されました。これは、当院で行われている臨床研究の業績や様々な学習活動の成果を広く公開し、共有するための場を提供することを目的としています。近年の医療分野における知識と技術の進歩は目覚ましく、それらの成果を日常診療へ迅速に取り入れ、医療の質を向上させ、ひいては患者さんの安心・安全をより一層高めることが、第一線の医療従事者としての責務です。この責務を果たすためには、医療従事者は生涯にわたる学習を継続していく必要があり、本誌はそのための重要なツールとなります。これまで学会発表や院内勉強会で終わっていた研究成果も、本誌を通じて全国に発信できるようになり、情報共有の促進が期待されます。
2. 情報発信による病院活性化への期待
恵寿総合病院医学雑誌の発刊により、これまで発表の機会が限られていた研究成果を全国に向けて容易に発信できる体制が整いました。 これは、職員の職種を問わず、研究発表への積極的な参加を促し、個々の業務に対するモチベーションを高める効果が期待されます。発表を通じて得られる経験やフィードバックは、職員のスキル向上に繋がり、ひいては病院全体の活性化に貢献するでしょう。 医療従事者としての誇りと自信を育み、より質の高い医療を提供できる環境の構築を目指しています。本誌は、単なる情報発信の場だけでなく、職員の成長と病院の発展に大きく寄与するプラットフォームとなることが期待されています。
3. 潜在的成果の発掘と医療の質向上への貢献
当法人はこれまで、論文スコアの高い英字誌を含む多くの学術雑誌に論文を投稿・掲載し、国際、全国、地域レベルの学術集会や研究会で積極的に研究成果を発表してきました。しかし、日常診療の中で培われた経験や技術の中には、まだ十分に活用されていない貴重な知見が数多く存在すると考えています。これらの潜在的な成果を掘り起こし、磨き上げることで、医療の質を更に高め、患者さんへの貢献度を向上させることが本誌の重要な役割です。 地域連携においても、脳卒中などの疾患を中心に地域ごとの取り組みが進められており、本誌を通じてこれらの情報を共有することで、地域医療の更なる発展に繋がることを期待しています。
II.リハビリテーション医療の現状と課題
本誌では【リハビリテーション医療】の現状と課題を詳述。急性期、回復期、維持期のリハビリテーションの役割を解説し、特に【維持期リハビリテーション】の変革の必要性を強調。在宅・通院・通所リハビリテーションの連携強化、回復期リハ病棟の有効活用、そして医療と介護の連携による【ADL】向上を今後の課題としています。回復期リハ病棟は全国で1000病院を超え6万床となり、人口10万人あたり50床の初期目標に到達しつつあります。
III.抗菌剤使用制限と病院感染対策
病院感染対策として【抗菌剤】制限と接触感染予防策が重要です。特にESBL産生菌(Extended-spectrum β-lactamase producing bacteria)による院内感染拡大防止のため、尿路感染症への対策が喫緊の課題です。データによると、ESBL産生大腸菌は尿路感染症で特に顕著であり、尿を汚染源として重視する必要があると結論づけられています。
1. 抗菌剤制限と接触感染予防策の重要性
病院感染対策において、抗菌剤の制限と接触感染予防策の2つのアプローチが重要であることが述べられています。抗菌剤の制限に関しては、ESBL(Extended-spectrum β-lactamase)に効果のないオキシミノセファロスポリン系の抗菌剤の使用制限が有効であるという報告例も存在しますが、この原則を厳格に適用すると、軽症例を除いてゾシンとカルバペネムしか使用できない状況になりかねないため、慎重な検討が必要です。一方で、接触感染予防策のみで感染流行を抑制できたという報告例もあり、対策の効果は多面的です。当院のデータからも、尿路感染症を中心にESBL産生菌による交差感染予防の必要性が示唆されています。特に尿路感染症においては、抗菌剤の濃度が肺などよりも高いため、カルバペネム以上の強力な抗菌剤の使用が必要となるケースもあります。細菌の薬剤耐性化の現状を踏まえ、適切な抗菌薬選択と使用制限、そして感染予防対策の両輪で取り組む必要性を示しています。
2. ESBL産生大腸菌の院内感染拡大防止策
ESBL産生大腸菌による院内感染拡大防止策として、尿路感染症への対策が特に重要視されています。院内感染調査の結果、521株のESBL産生菌のうち、ESBL産生大腸菌は58株(11.1%)を占め、その内訳は尿41株(カテーテル尿18株、導尿8株)、膣分泌物7株、気道7株などです。血液由来株ではESBL産生大腸菌は認められませんでした。入院患者において、尿からESBL産生大腸菌が分離される傾向が特に顕著であることから、尿を汚染源として捉え、適切な感染対策を実施する必要性が強調されています。他の患者や環境からの侵入と、患者自身の消化管からの尿路への定着の区別は困難ですが、いずれにしても尿路感染症の予防対策を徹底することで、ESBL産生大腸菌の拡大を抑制することが重要だと結論付けられています。このデータに基づき、より効果的な院内感染対策の策定と実施が求められています。
IV.看護師業務負担軽減に向けた看護補助者導入の効果
【看護師】の業務負担軽減のため、看護補助者を導入し、記録、ナースコール対応、電話応対、患者案内、入退院準備といった業務の一部移管を行いました。その結果、特に患者案内と入退院準備において業務負担軽減効果が確認されました。本研究は【看護業務量】の現状把握と【業務改善】の有効性を示しています。キーワード:看護補助者、看護業務量、業務改善
V.外来健診における待ち時間短縮の取り組み
外来健診の待ち時間短縮に向けた取り組みが紹介されています。婦人科検診専用の受付設置や受付前の更衣による効率化、部署間の連携強化により、待ち時間を【30分以上(女性)】、【50分以上(男性)】短縮することに成功しました。キーワード:待ち時間短縮、健康診断、連携
1. 健診待ち時間の長時間化問題と患者ニーズ
当院では、健診利用者の増加や健診内容の複雑化・多様化に伴い、健診にかかる時間、特に各検査の待ち時間が長くなる問題が発生していました。 患者からは「婦人科で待たされた後に、他の検査でも待たされるのか?」、「私より後に来た人が既に胃カメラ検査を受けている」といった不満の声が寄せられており、待ち時間の長期化が患者の満足度を低下させていることが明らかでした。婦人科からは、子宮がん検診の患者を朝一番に優先的に受け入れられるよう改善を求める声も上がっていました。これらの声は、患者ニーズに応えるための健診効率化、特に待ち時間短縮の必要性を強く示唆しています。現状のシステムでは、患者満足度を維持・向上させるために抜本的な改善策が求められている状況です。
2. 待ち時間短縮のための効率化施策と効果
待ち時間短縮のため、いくつかの効率化施策が実施されました。その一つとして、受付前の更衣を導入することで、受付後の検査開始までの時間を短縮することに成功しました。これにより、受付での待ち時間を有効に活用し、患者のストレス軽減にも繋がっています。更衣の呼びかけは、患者とのコミュニケーションの機会にもなると考えられています。また、婦人科検診専用の受付を設置したことで、男性一般健診と婦人科検診の検査開始時間に差が生じ、特定の時間帯に集中していた胃カメラ検査などの混雑が緩和されました。その結果、女性では30分以上、男性では50分以上の待ち時間短縮を実現しました。この成功は、婦人科検診と一般健診の受付を分けることで、検査開始時間の分散化に成功したことが要因と考えられます。 これらの施策は、患者満足度の向上に大きく貢献したと言えるでしょう。
3. 部署間連携強化と今後の課題
待ち時間短縮と患者満足度向上には、健診に関わる全スタッフの連携強化が不可欠です。部署間の連携強化、情報の共有により、利用者の全体的な流れを把握し、スムーズな検査進行を実現することが重要です。健診時間の短縮は、病気の早期発見だけでなく、当日中の他科受診や院外への紹介を円滑に進め、早期治療開始の可能性を高めるというメリットもあります。今後の課題としては、健診コース毎に受付時間を設定し、予約システムの更なる改善による待ち時間の完全予測と、それに基づいた最適な人員配置などが挙げられます。より効率的で患者満足度の高い健診システム構築のため、継続的な改善努力が求められます。
VI.手根管症候群におけるMRI診断の最適化
【手根管症候群】のMRI診断における最適な撮像条件(TR、TE、FA)の検討結果が報告されています。3D-FFE法を用いた画像解析により、正中神経を描出する最適なパラメータが特定され、高分解能な【MRI】画像による診断支援への貢献が期待されます。キーワード:手根管、MRI、正中神経
VII.下肢動脈造影CTと血圧 脈波測定値の関連性
下肢動脈造影CT検査前に、血圧・脈波測定値による病変予測の可能性を検討した結果、足関節上腕血圧比(ABI)と脈波伝播速度(PWV)が【閉塞性動脈硬化症】の病変の有無や狭窄率と関連性を持つことが示唆されました。一方、カルシウムスコアは予測指標としては不十分でした。
1. 研究の背景と目的 下肢動脈造影CT検査前の病変予測
当院では、血圧・脈波測定で閉塞性動脈硬化症が疑われる症例に下肢動脈造影CT検査が施行されています。本研究では、このCT検査前に血圧・脈波測定値から病変の存在を予測できる可能性を検証することを目的としています。具体的には、血圧・脈波測定値と下肢動脈造影CT画像所見との関連性、そして下肢単純CTから算出されるカルシウムスコアと脈波伝播速度の相関性を分析しました。 CT画像所見から、病変の有無、部位、狭窄率が足関節上腕血圧比(ABI)や脈波伝播速度(PWV)にどのように影響するかを調べ、検査前の非侵襲的検査による病変予測の可能性を探ります。これにより、CT検査の適応をより的確に判断し、患者への負担軽減や医療資源の効率的な活用に繋がることを期待しています。
2. ABI測定値と病変の関連性 病変予測の可能性
下肢動脈造影CT画像所見を基に、病変がない群、狭窄病変がある群、閉塞病変がある群に分け、それぞれのABI測定値との相関性を分析しました。 結果、下肢動脈に病変が存在する群ではABI測定値が有意に低下することが確認されました。正常な状態では下肢の収縮期血圧は上肢よりも高いですが、末梢動脈に狭窄病変があると下肢血圧が低下し、ABIも低下します。しかし、透析患者や重症糖尿病患者では動脈壁の高度石灰化により、ABIが高値を示す場合もあるため、注意が必要です。一般的にABIが0.9未満または1.3以上は異常とされていますが、今回の検討では、ABI測定値から病変の有無をある程度予測できる可能性が示唆されました。この結果は、CT検査前にABI測定を行うことで、検査の必要性や、より詳細な検査への橋渡しとして役立つ可能性を示唆しています。
3. 脈波伝播速度 PWV とカルシウムスコアとの関連性 病変指標としての限界
病変の狭窄率と脈波伝播速度(PWV)の関連性についても検討しました。その結果、病変の狭窄率が高くなるにつれてPWVは上昇する傾向が見られましたが、閉塞に至るとPWVは低値となることが分かりました。一方、カルシウムスコアはPWVと相関がなく、病変の有無を判断する指標としては不十分であることが判明しました。動脈硬化の石灰化は最終段階の姿であり、動脈の伸展性を反映するPWVは、CTで認識される石灰化が生じる前から低下していると考えられます。また、カルシウムスコアは絶対値ではなく、被験者の身長、体重、性別、年齢、血管容積、全身血管の石灰化割合などを考慮した補正が必要となるため、現状では病変予測指標としては不向きだと結論付けられました。この研究結果から、CT検査前のスクリーニングとして、血圧・脈波測定値が有効である一方で、カルシウムスコアは限定的な有効性しか持たないことが示されました。
VIII.入院時医学管理加算の算定と治癒患者の増加
入院時医学管理加算の算定に向けて、逆紹介(Uターン)の推進と【治癒患者】増加のための取り組みが成功し、年間約5,000万円の増収を実現しました。治癒の定義の見直しと医師への積極的な働きかけが重要でした。
1. 入院時医学管理加算算定に向けた取り組み 逆紹介 Uターン の推進
診療報酬のマイナス改定が続く中、当院では入院時医学管理加算の算定を目指し、積極的な取り組みを行いました。まず、診療録情報から、紹介患者の多くが逆紹介(Uターン)されていない現状を把握しました。そこで、医師に対してUターンを推進するよう働きかけを行いました。この取り組みは、患者紹介元の医療機関との連携強化を目的としており、地域医療連携の向上にも貢献するものです。 具体的な施策としては、医師への個別指導や、逆紹介のメリットを説明する研修会の開催などが考えられます。 この働きかけの結果、紹介患者の逆紹介率が向上し、目標である4割基準を達成しました。この成功は、医師と医療機関との良好な関係構築、そして患者にとって最適な医療提供体制の構築に繋がったと言えるでしょう。
2. 治癒患者増加戦略 医師へのアプローチと定義の見直し
入院時医学管理加算の算定には、治癒患者の増加も必要不可欠です。そこで、医師に対して治癒患者を増やすためのアプローチを行いました。当初は、白内障手術後などの外来通院患者も治癒として算出していましたが、治癒の定義が明確化されたことにより、この算出方法を見直す必要性が生じました。 新たな治癒の定義に基づき、急性アルコール中毒やめまいなど、経過観察目的で入院する患者、大腸ポリープ切除など退院後に結果説明のみを行う患者などを対象としました。 医師へのアプローチとしては、治癒の定義に関する研修や、治癒に該当する患者の増加を目指すための具体的な戦略の共有などが含まれます。 この取り組みによって、治癒患者の数を増加させることが可能となり、入院時医学管理加算の算定要件を満たすことに貢献しました。
3. 入院時医学管理加算算定の成功と増収効果
上記の取り組みの結果、2008年12月より入院時医学管理加算の届出が可能となり、年間約5,000万円の増収を実現しました。これは、医療機関の経営安定化に大きく貢献する成果です。 この成功要因は、逆紹介の推進と治癒患者の増加という2つの戦略を効果的に組み合わせ、目標達成に邁進したことにあります。 しかしながら、この成功は、医師や医療スタッフの努力と連携によるものであり、今後も継続的な取り組みが必要不可欠です。 さらに、2002年以降、2010年を除き診療報酬のマイナス改定が続いており、「届出医療」の重要性がますます高まっています。医事課は、施設基準を満たしているにも関わらず届出をしていない項目や、工夫次第で取得可能な項目がないか、常に問題意識を持って取り組む必要があります。
IX.前立腺全摘除術におけるソフト凝固の有効性
前立腺全摘除術における【ソフト凝固】を用いた止血方法の有効性を検討。ソフト凝固群は対照群と比較して出血量が有意に減少し、自己血輸血量の減量にも繋がりました。ソフト凝固は出血量減少と確実な前立腺尖部の処理に有効であると結論づけられています。
X.若年性脳梗塞 前大脳動脈解離の1症例報告
45歳女性における若年性脳梗塞の症例報告。頭部MRIで左前頭葉に高輝度域を認め脳梗塞と診断されました。経時的頭部MRAにて【前大脳動脈解離】が確定診断され、若年性脳梗塞の原因検索において脳動脈解離の考慮が重要であることが示唆されました。キーワード:脳梗塞、脳動脈解離
XI.頚椎後縦靭帯骨化症 OPLL の1症例報告
頭痛、発熱、後頚部痛を呈した症例において、頚部CTで第2頚椎歯突起周囲の石灰化像が確認され、【頚椎後縦靭帯骨化症(OPLL)】と診断されました。NSAIDsによる治療で症状が改善しました。キーワード:OPLL、頚椎後縦靭帯骨化症
1. 症例概要 45歳女性における頸椎後縦靭帯骨化症 OPLL の診断
本症例は45歳女性。来院前日より右側頭部に強い頭痛と38℃の発熱が出現。近医を受診したものの明確な感染源は発見されず、胸部単純X線や尿沈渣検査でも異常は見られませんでした。血液検査ではWBC10000/μl、CRP10.3mg/dlと炎症反応の高値が認められ、髄膜炎や椎体炎なども疑われ、当院に紹介されました。髄液検査、頭部CT、頭頸部MRI、血液培養、FDG-PET検査などを行い原因究明を試みましたが、診断に至らず症状の改善も見られませんでした。その後、日本内科学会雑誌で頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)の存在を知り、改めて頸部を診察したところ、強い回旋制限が確認されました。頚部CT検査で、OPLLに特徴的な第2頚椎歯突起周囲の石灰化像が認められ、診断に至りました。NSAIDsを投与開始したところ、症状はすみやかに改善しました。
2. 頸椎後縦靭帯骨化症 OPLL の症状と検査所見
頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)は、男女比が3:5と報告されており、後頸部痛、頸部回旋制限、肩痛、発熱などの症状を呈することが知られています。本症例も、強い後頸部痛と発熱、頸部回旋制限を主訴として来院しました。血液検査ではCRP上昇と血沈亢進が認められました。さらに、頚部CT検査において、本症例に特徴的な第2頚椎歯突起周囲の石灰化像が確認されました。この画像所見は王冠のように見えることから、この病名が付けられたとされています。OPLLの病態は、第2頚椎歯突起周囲の靭帯にピロリン酸カルシウムやハイドロキシアパタイトなどの結晶が沈着し、炎症を誘発することにより引き起こされます。この炎症がC1-2関節に発生することで、大後頭神経領域の後頸部や側頭部に痛みを生じると考えられています。
3. 診断と治療 NSAIDs投与による症状の迅速な改善
様々な検査を行った結果、頚部CTで確認された第2頚椎歯突起周囲の石灰化像と臨床症状から、本症例は頸椎後縦靭帯骨化症(OPLL)と診断されました。OPLLは、偽痛風などに見られる結晶誘発性関節炎の一種と考えられています。 初期症状は、後頸部痛、頸部回旋制限、肩の痛み、発熱など多岐に渡ります。診断には、血液検査(CRP上昇、血沈亢進)と頚部CT(第2頚椎歯突起周囲の石灰化像)が重要となります。 本症例では、第12病日にNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の投与を開始したところ、症状はすみやかに改善しました。このことは、OPLLに対するNSAIDsの有効性を示すものであり、早期診断と適切な治療の重要性を改めて示しています。本症例は、OPLLの診断にいたるまでの経緯と、NSAIDsによる治療効果を明確に示しており、臨床上の貴重な知見となります。
XII.くも膜下出血後左視床梗塞による言語性記憶障害の1症例
くも膜下出血後に左視床梗塞を発症し、【言語性記憶障害】を呈した1症例が報告されています。発症初期は超皮質性感覚失語状態でしたが、その後失語症状は消失し、カテゴリー分類課題にのみ困難を示す【意味性記憶障害】が主症状となりました。
